- シニア向け食事提供・栄養管理
- 福祉用具販売 ・レンタル
- 建物修繕・管理・清掃
- 調剤薬局
- コスト適正化・コンサルティング
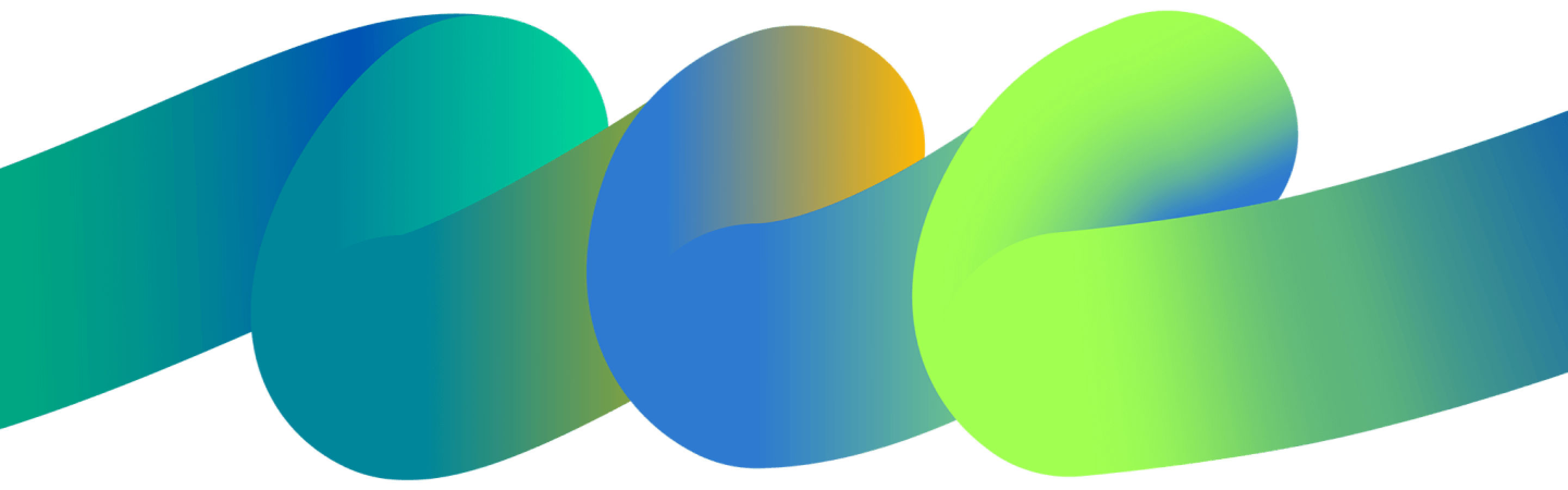
当社は、7月1日(火)、RaiBoC Hall レイボックホール(市民会館おおみや)にて、三井住友銀行 埼玉法人営業部の法人顧客45社・67名を対象に、「認知症に関する講座」を実施しました。

三井住友フィナンシャルグループでは、中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」の基本方針の一つに「社会的価値の創造」を掲げており、企業の持続的成長に取り組まれています。その施策の第一弾として、5月19日(月)に、三井住友銀行 大宮支店にて埼玉法人営業部を中心とした行員の皆さまとともに、認知症の未来を両社で考える講座を実施。今回はより広く地域社会の皆さんとともに認知症を考えていくため、第二弾として埼玉法人営業部の法人顧客を対象に行いました。
<講座の概要>
講義主催:三井住友銀行 埼玉法人営業部
講師:杉本浩司(メディカル・ケア・サービス株式会社)
「認知症の未来を自分ごととして考える」ことをテーマとし、「物忘れ」と「認知症の違い」や、誤解されがちな認知症の中核症状とそれによる行動・心理症状についてお伝えしました。また、普段私たちが何気なく行っている「状況の認知」は、認知症になると苦手になり、どのような状態になるのかを説明することで、認知症の症状をより深く理解していただきました。
そして昨今、企業やその社員にも認知症への理解が求められていることから、部下・チームメンバーがビジネスケアラーや介護が必要になった場合、どうしたら良いのかをお伝えしました。
厚生労働省によると2022年時点で高齢者の3.6人に1人が認知症か軽度認知障害(MCI)と推計 ※1 されており、今後も、自身や家族・大事な人が認知症になる可能性が十分にあります。しかし、まだまだ認知症に対する偏見や誤解があり、認知症を特別なものとして孤立や孤独を招いているのが実態です。そこで、「認知症を取り巻く、あらゆる社会環境を変革する」ことを企業ミッションとして掲げる当社は、2022年12月より主に小・中・高校生を対象に無償で「認知症教育の出前授業」を開始し、これまで、40校(団体)、4,000名以上に実施してきました。
また、2024年1月に「認知症基本法」が施行、同年3月には経済産業省から「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表され、企業や地域社会の認知症に対する理解と行動が一層求められています。そのため、企業や地域の方向けの「出前講座」も実施しています。
※1:厚生労働省「認知症施策推進基本計画」(令和6年12月)
・従業員への案内・アドバイスの幅を広げるきっかけになった
・認知症の行動がどんな心境、状況から起こるのか理解することができた
・親族に認知症のある方がいるので大変参考になった
・介護と言ってもお世話ではなくケアすることで症状が緩和することがわかった
・認知症というと自身と関係ないと思っていたが、とても身近な話だと実感した。今後、家族の参考にしたい
・介護職は認知症のある方に希望を与えられる、頼れる存在。家族にとっても貴重な存在だと感じた
・認知症が身近になったとき、抱え込まなくて良いと知れたので良かった
・認知症だから○○したら良いのではなく、その人が「どうしたいのか」という視点が重要だと知った
■講師
杉本浩司
メディカル・ケア・サービス(株)
品質向上推進部長/コーポレートコミュニケーション部長
“日本一かっこいい介護福祉士”として、講演回数延べ1,300回、聴講者数延べ7万人超の実績がある杉本浩司。国家資格介護福祉士の上級資格である認定介護福祉士策定の際は、180万人の介護福祉士から「唯一の人物モデル」として幹事委員に選ばれる。
当社の認知症教育の出前授業について
https://www.mcsg.co.jp/features/initiatives/dementia_education/