- シニア向け食事提供・栄養管理
- 福祉用具販売 ・レンタル
- 建物修繕・管理・清掃
- 調剤薬局
- コスト適正化・コンサルティング
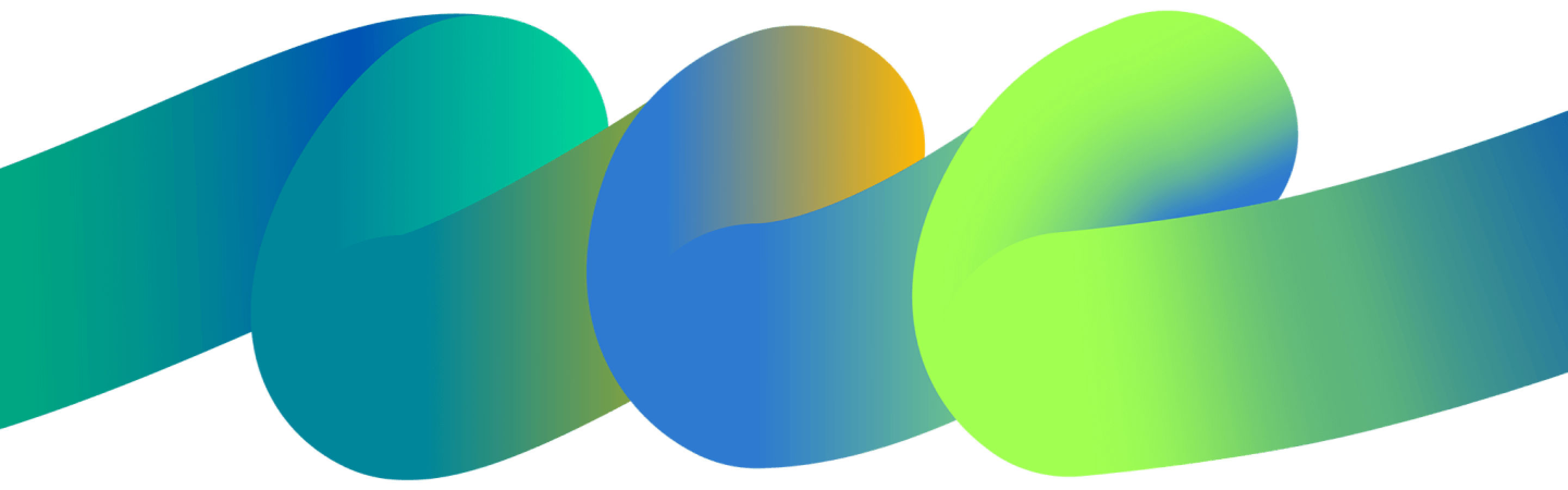
当社は、6月16日(月)に東芝エレベータ株式会社の社員向けの研修として「認知症に関する講座」を行いました。

東芝エレベータでは、全国安全週間として年に1回、各拠点にて安全大会を実施しています。このたび、東芝エレベータ本社安全大会の特別講演として、すでに認知症が身近な存在である方や、将来、認知症が身近な存在になる可能性がある方たちに向け、手助けとなる知識を提供できないかとご依頼いただきました。当日は約300名が参加し、両者で認知症の未来を考える機会となりました。
厚生労働省によると2022年時点で高齢者の3.6人に1人が認知症か軽度認知障害(MCI)と推計 ※1 されるなど、今後、自身や家族・大事な人が認知症になる可能性も十分にあります。しかし、まだまだ認知症に対する偏見や誤解があり、認知症を特別なものとして孤立や孤独を招いているのが実態です。そこで、「認知症を取り巻く、あらゆる社会環境を変革する」ことを企業ミッションとして掲げる当社は、2022年12月より主に小・中・高校生を対象に無料で「認知症教育の出前授業」を開始し、これまで、40校(団体)、4,000名以上に実施してきました。
また、2024年1月に「認知症基本法」が施行、同年3月には経済産業省から「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表され、企業や地域社会の認知症に対する理解と行動が一層求められています。そのため、企業や地域の方向けの「出前講座」も実施しています。
※1:厚生労働省「認知症施策推進基本計画」(令和6年12月)
講座の中では、「物忘れ」と「認知症の違い」や、誤解されがちな認知症の中核症状とそれによる行動・心理症状についてお伝えしました。また、普段私たちが何気なく行っている「状況の認知」は、認知症になると苦手になり、どのような状態になるのかを説明することで、認知症の症状をより深く理解していただきました。講師からは、「『認知』の機会を増やすと、症状の改善が見られやすいため、介護施設を検討する際には、その施設が“どれくらい外に行く機会をつくっているのか”を確認することが重要です」とお伝えしました。
認知症のある方は記憶力の低下から、“目の前の人は誰なのか”“今の季節は何なのか”など、毎秒「不確かさ」で「不安」だらけです。まだまだ認知症のある方が生活しづらい地域社会のなかで、「不確かさ」を「確か」にし「不安」を「安心」に変えるために、必要な声かけや対応方法なども一緒に考えていただきました。
昨今、企業や社会も認知症への理解が求められていることから、部下や同僚から介護に関する相談を受けた際の対応方法もお伝えしました。
認知症は早期に発見するほど、症状の進行を遅らせることも家族関係の悪化の防止も可能です。講座では、「部下に対し、家族や身近な方に介護が必要になった際には発信しようと伝えてください」と説明したうえで、部下や同僚が介護休暇や介護休業を必要としている場合、働きやすい職場環境の整備に努めていただくようお伝えしました。
「出席者の約半数が認知症になります」という衝撃的な言葉から始まった講演でしたが、参加者のほとんどが管理者であり、現在または今後経験するであろう家族の認知症対応について、みんなが非常に興味を持っていたと思います。私自身も認知症に対してネガティブな印象を持っており、「認知症=もうダメ」と思っていました。
メディカル・ケア・サービスの事業所のご利用者が回復する様子を動画で拝見しましたが、あそこまで回復することがあるとは最初は信じられませんでした。今回の研修で、専門家に早期に相談することの重要性を学ばせていただきました。
■講師
杉本浩司
メディカル・ケア・サービス(株)
品質向上推進部長/コーポレートコミュニケーション部長
“日本一かっこいい介護福祉士”として、講演回数延べ1,300回、聴講者数延べ7万人超の実績がある杉本浩司。国家資格介護福祉士の上級資格である認定介護福祉士策定の際は、180万人の介護福祉士から「唯一の人物モデル」として幹事委員に選ばれる。
当社の認知症教育の出前授業について
https://www.mcsg.co.jp/features/initiatives/dementia_education/