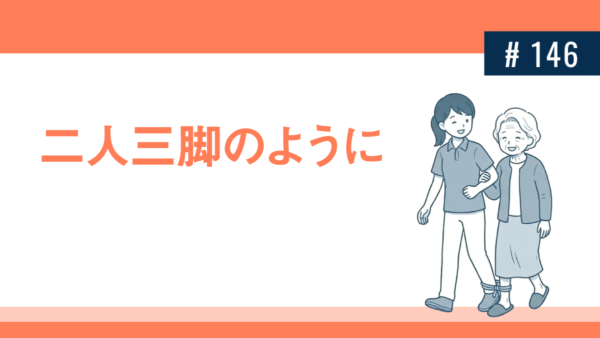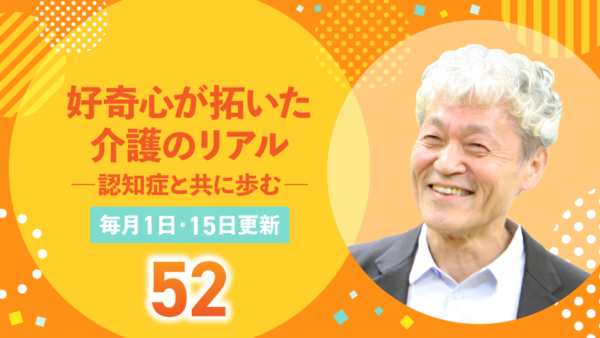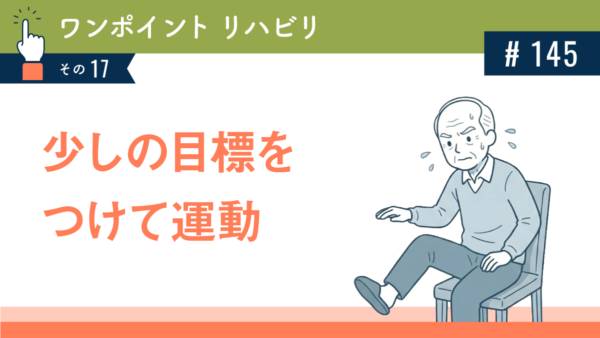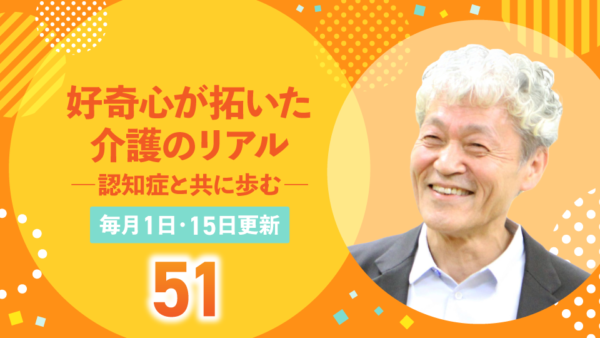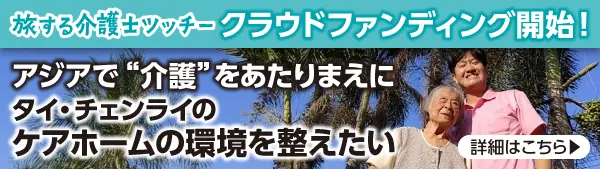
2025年2月末、僕はタイ北部のチェンライで、介護施設「ひだまりホーム」を引き継ぎました。
日本、イギリス、ベトナムでの経験をひっさげて、今度はタイで経営者としてのチャレンジです。
「まあ、これまでの経験もあるし、どうにかなるだろう」
正直、そんな甘い気持ちでスタートを切りました。
ところが、最初の1か月、次から次へと襲いかかってきたのは、僕の想像をはるかに超える“カオス”でした。
今振り返れば笑える話も多いんですけど、その時は本気で「もうダメかもしれない…」と眠れない夜を過ごしたこともあったんです。
試練その1:スタッフとの「当たり前」が通じない!
タイで働くには、まずワークパーミット(就労許可証)の取得が必要です。
これがまた大変で…。事務所が実在するか役所の人が見に来たり、ちょうど国境での事件がニュースになっていた時期で審査が厳しくなったりと、ヒヤヒヤの連続でした。
それでも、担当の人は丁寧で「ごめんね、今こういうご時世だから」と申し訳なさそうに対応してくれる。さすが「微笑みの国」だなと実感しつつ、なんとか無事に取得。
「よし、これでスタートラインに立てた!」と胸をなで下ろしたのも束の間でした。
次に直面したのは、スタッフとの働く意識の違い。
時間を守らない、連絡なしに休む、しまいには夜勤を勝手に友達と交代してしまう…。しかもその“友達”は、介護経験もほとんどないと言うじゃないですか。
「いやいや、無理でしょ!?」と。
入居者さんの命を預かる場所で、なぜこんなことが…?(これってタイでは普通なの???)と、僕は目の前の光景に唖然としました。
次の日、勝手に交代したスタッフに問い詰めると、返ってきたのは「何が悪いんですか?」という一言。
怒りを通り越して、もう理解不能でした。悪気がないのは分かる。でも、日本の「常識」が、ここでは全く通用しないんだと思い知らされました。
試練その2:多民族国家とワークパーミットの危機
結局、そのスタッフは自然と辞めていきました。そして新しく入ってくれたのは、真面目で時間もしっかり守る素晴らしいスタッフ。「やっといい人が来てくれた!」と本当にホッとしました。
…が、後から分かったのは、その人がタイ国籍を持たない少数民族だったという事実。
タイには「外国人1人を雇うには、4人のタイ人雇用が必要」というルールがあり、国籍上、彼女たちは“タイ人”としてカウントできない。つまり、僕のワークパーミットが取り消される大ピンチに陥ってしまったんです。
「え?タイに住んでるのにタイ人じゃない?どういうこと?」
「アカ族」「ラフ族」「カレン族」。
初めてその言葉を聞いたとき、僕の頭の中に「?」が並びました。
“族”ってなんだ? 国籍は? IDカードは?
日本で暮らしてきた感覚では到底理解できないことでした。
そこで初めて、この国では教育や医療、就労から切り離された「無戸籍」という人たちがたくさんいることを知ったんです。
この出来事は、後に僕の「KAIGO×コーヒー」プロジェクトにつながっていくんですけどね。
でもこの時はただ、「ワークパーミットが取り消されるかもしれない、やばい!」という恐怖と混乱に押しつぶされそうでした。
試練その3:井戸とおばけと銀行と…
日々の暮らしもトラブルの連続でした。
「施設を増床するなら水が足りない。井戸を掘らないと」と言われ、「井戸!?」ってなりましたよ。この時代に井戸って!
お金もないし、本気で自分で掘ろうかと考えたくらいです。(結局、大きな貯水タンクを買うだけで解決したんですけどね)
さらにスタッフからは「夜勤は“おばけ”が出るから、一人じゃ無理です」という真剣な訴えが。
思わず「は!?」と声が出ました。冗談かと思いきや、本気も本気。タイの人にとって“霊”がどれだけリアルな存在か分からず、笑い飛ばすこともできない。
かといって、おばけ対策なんてできるわけもなく、この問題はしばらく“未解決の宿題”として残りました。
銀行口座の開設も本当に大変で、支店ごとに言うことが違うし、たらい回しにされるし…。
最終的に150枚近い書類を準備して、なんとか開設できたときには、心底ぐったりでした。
そんなトラブル続きで凹んでいたところに、車を電柱にぶつけて修理代10万円…。
まさに、泣きっ面に蜂状態でした。
介護を始めるずっと手前で、次々と壁が立ちはだかる。
そして、これら全てを上回る最大の試練が、この後すぐにやってくるのです。
(後編につづく)