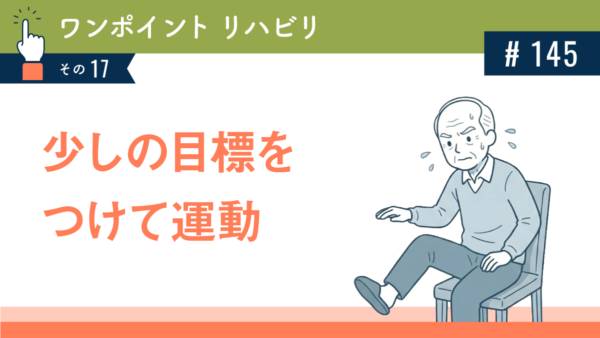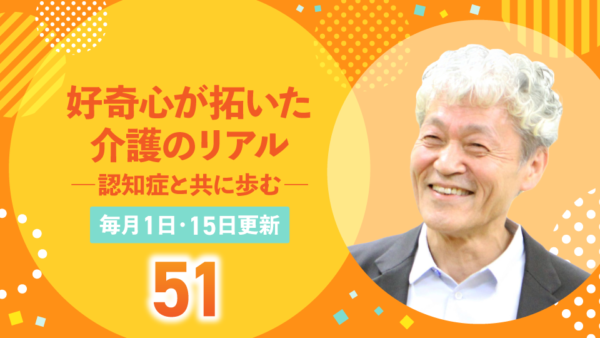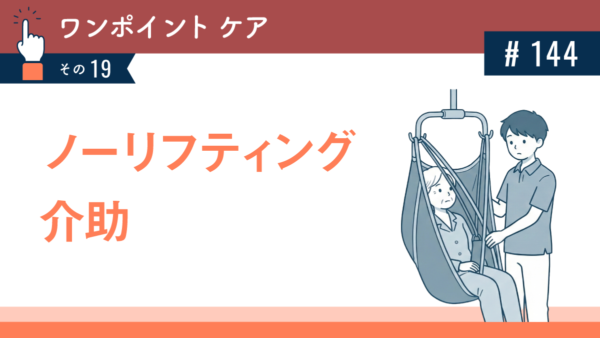介護に携わる専門職がたびたび使用する言葉に“協力動作”があります。例えば、「○○さん全介助なのだけど協力動作はあります」といったような使われかたをします。
つまり、介助を受ける本人が、職員の介助に対して協力してくれているという意味です。全て介助に身を任すのではなく、本人にも少しは動きがあるのですから、その動きを前向きに捉えているわけです。
しかし、本人の動作(動き)に対して、他者が協力するのが介助だったはずです。まさに本人のための本人主体の介助です。
そんなのわかりきったことと、多くの専門職の方からお叱りを受けそうですが、一方で、“協力動作”などという言葉を何気なくとはいえ使ってしまうのは、介助者による介助手技が主体になっていて、その介助手技に対して本人を従わせようとしてしまっている現実があるのではないかと考えてしまいます。
人の動作は百人百様です、しかも、個人の動作であっても動作環境しだいでは動き方も変わってきます。
したがって、介助者が主体となって自分のイメージで介助をしようとすると、介助を受ける本人の動きとの衝突が起こってしまいます。
多くの場合は介助者の方が筋力も体力も強いので、お互い動きの衝突を感じて介助者にとっては介助のしにくさ、本人にとっては動きにくさを感じつつも目的の動作は介助者の主導で成し遂げられます。
できればお互い動きの衝突を避けたいのですが、介助者の手技が優先される以上は、介助を受ける本人はその介助に身を任せるという手段を選択しなければならないのです。
介助者は本人に“協力動作がある”などといって好意的に捉えている状況も、実は本人にとっては介助者にやむなく合わせてくれているだけなのかもしれないのです。
本人の動きに対して介助者が協力する、この原点に立ち帰って介助をしてみると、こちらのほうがどんなにスムースにことが運ぶことかと気づかされると思います。
本人の動きを少しだけ優先する、言葉にすると簡単ですが、現実は意外にも難しいのです。
それは介護における“待つ”がいかに難しいかを、多くの専門職や介護経験者が感じていることからも明らかです。
本人の動きを優先する、そのためには本人の“動き出し”だけでも優先してみる介助が必要です。
介助を受ける本人が協力動作と感じられる介助をしたいものです。