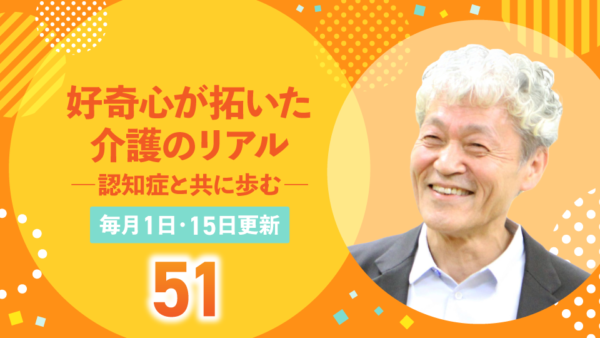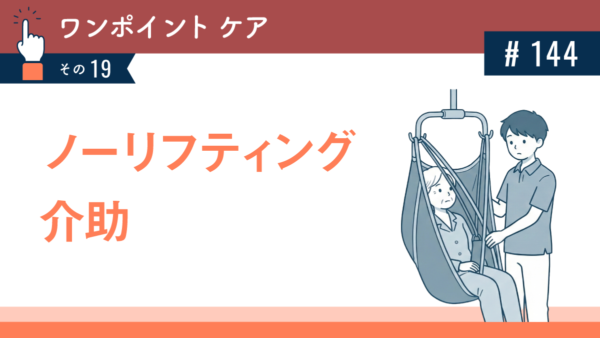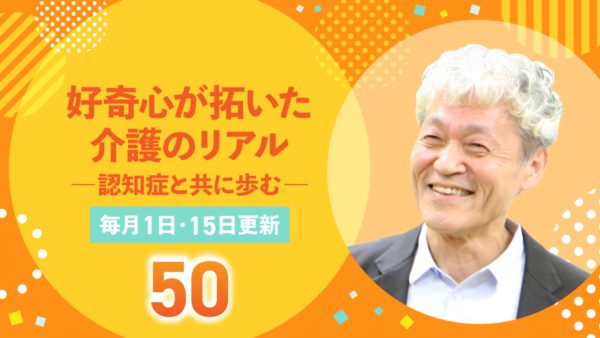気がそぞろでは応えられない
大好きなサッカーの試合をテレビ観戦している夫に妻が「今度の日曜日、どこどこに連れて行って」と声をかけたとき夫は「わかったよ」と答えたのですが、夫は日曜日になったのに出かけようとしません。
「日曜日に連れて行ってくれると言ったじゃない」と怒る妻ですが夫は「??」でした。
相手に何かを伝えるときに大事なことは「相手が聞く気になってくれているかどうか」で、声をかけられた時に大好きなサッカーに夢中になっている夫は気もそぞろに反射的に返事をしただけでしょうから、それでは「インプットされた情報を定着できない=アウトプットできない」のではないでしょうか。
同じようなことが介護現場でも見られます。
伝わらない・伝わりにくい「そぞろ状態」
ガメさん(仮名)の住まいは、介護保険事業所で認知症の状態にある方が入居できる通称グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と呼ばれているもので、メゾネット式建屋(2階建)の2階にお部屋があります。
職員Aがガメさんに丁寧に「お部屋へ戻りましょうか」と階段口で誘い言葉をかけるのですが全く階段を上がろうとされません。
そこへその様子を見ていた職員Bが来て「ガメさん、お部屋に戻りましょうか」と声をかけると「そうか」と言わんばかりにスタスタと階段を上がっていきました。
僕が、それをたまたま見かけたのですが、この違いは何か?
無資格と介護福祉士の違い?
経験年数の違い?
ガメさんとの接触時間数の違い?
言葉のかけ方の違い?
はたまた
たまたまか
こうした話はよくあることで、僕は「介護職は魔法使い」と言って遊ばせていただいていますが、エビデンスあればこその医療と違って介護の仕事の中では、こうしたことを「エビデンス化する」のが難しく、だから「魔法使い」と表現して遊ばせてもらっています。
この様子を見ていた僕に言えることは、職員Aは職員Bよりも言葉も態度も丁寧できちんとガメさんの顔を見て話しをしていました。
逆に職員Bは職員Aよりも言動は雑でした。
でも職員Bは、職員Aと違って、まずは「ガメさん!」と名前を呼んでガメさんが確実に自分の方を向いてから・相手を引きつけてから(相手に認識させてから)行動を伝えていました(お部屋に戻りましょうか)ので、その違いだと感じました。
別のシーンでは、洗面台の前に誘導して薬を飲んでいただくため職員が声掛けしていましたが、声をかけられたトメさん(仮名:認知症という状態にある)は一向に薬を飲もうとされません。
薬を手のひらに渡すことまではスムーズにコトを進められていたのですが、飲もうとされないんです。
それを見ていて「飲もうとされない理由はここだな」と思った僕は職員に「まずは、目と目を合わせることからはじめよう」とアドバイスしました。
その理由は、薬を手のひらにのせたあとトメさんは「あるモノ(観葉植物)」に目をやっていたからです。
つまり、本人からすれば気もそぞろに「飲みましょう」という声掛けを聞いている感じですね。
きっと、そのままにしていたら介護記録に「薬を飲むことを勧めたが拒否された」と、本人の側に問題があるかのように書かれていたかもしれません。
目指すは手品師
でも、こうしたことも本当のことは「?」で確かめようもなく「だろう」としか言いようがありません。
自分が常にいる事業所なら、それを検証して確実なものにして、だから「Aさんには、これが大事」と伝えることができますが、それとて「エビデンス」とまでは言えないだろうし「たまたま」の要素を排除できません。
だから「魔法」という表現でとどめているのですが、このように考え・このように実践した結果が、うまくいったら「なぜうまくいったか」、うまくいかなかったら「なぜうまくいかなかったか」を検証することが必要で、
特に見落としがちなうまくコトが運べた時にこそ「なぜ、うまくいったのか」を検証することを僕は大事にしてきましたが、それは「たまたま」を排除していきたいからです。
合わせて、それを同僚と語り合う・擦り合わせることまでできて初めて「魔法使い」になれると僕は思っていますし、
もっと突っ込んで言えば魔法使いで留まっていてはダメで、言葉の響きが好きだから「魔法」という言葉を使ってはいますが、単にチチンプイプイと唱える魔法使いではなく、
目指すは、周りの人たちに魔法のように思わせてしまう脳と身体の鍛錬を積んで「姿」をつくる「手品師」なんですよね。
手品師を目指す和田を育んだ環境
1987年に日本国有鉄道(現JR)の車両整備士から高齢者福祉の世界・特別養護老人ホームの世界に飛び込みましたが、
その当時の2年先輩・1年先輩・同期・1年後輩が、ある講義後に会いに来てくれて食事を共にしました。みんな10歳以上年下の連中です。
そのときに思い出したのですが、この当時の僕らは、とにかく利用者・入居者のこと、仕事の中で大事にしなきゃいけないことを真面目に面白おかしく時間を忘れて語り合っていたことで、きっとその環境が僕を育んでくれたに違いないことに確信をもちました。
というのも、超久々の顔合わせなのに、いまだに当時の利用者・入居者のことを細かく憶えていて大笑いしながら語り合えましたからね、間違いないです。
その時に「今の介護現場では」という話になったのですが、正しい・間違い、良い・悪いという評価軸での話ではなく「そこが違う」ということで一致できたことがあります。
環境で育まれる手品師
つまり「そこ」とは、特養・グループホームといった事業の違いや法人の違いではなく、僕らと今の違いは「利用者・入居者のことを語り合う時間が少ない=利用者・入居者支援で情報交換する脳の数と量が違う」ということであり同時に、
単に「数や量」の違いだけではなく「突き詰めていこうとする連中・おもしろおかしく展開できる連中=その環境」があればこそ熟すということで、
その環境の中でこそ「手品師(僕は、熟練・熟達・習熟の師と思っています)」は育くまれると僕は思っています。
そんなことを思い返している最中、僕が所属する法人の21歳の職員から「21歳の和田さんなら、〇〇についてどう考えますか、どう伝えますか」というメールが飛び込んできてメチャクチャ嬉しくなりました。
なかなか、こういう質問をしてくる方って出会えないですからね。ゆっくり時間をとって会うことにしていますが、21歳の僕を思い返しながら、とってもたのしみにしています。
追伸
10月10日で「ロック歳」が終わってしまいました。
このブログをアップする今日15日は「コキッ」っと「折れ曲がった歳」を迎えた和田さんで、このブログを仕上げた11日の誕生日は友人のお店、東京都文京区の「ケアギルド」でなにをやるのか・やらされるのかわかりませんがお話をすることになり「出たとこ勝負」が大好きな僕は、どんな夜になるのかとっても楽しみにしています。
ワクワクドキドキ!

グループホーム入居者と公園にお散歩に行ったとき「ブランコに乗ってみますか」と問う前に、ブランコを見つけたおひとりが自ら乗られ、それを見たもうひとりが「私ものってみようかしら」と乗られました。こういう響き合いが共同生活の良さですね。
ブランコはただ乗っただけでは動かず「漕ぐ」という動作が必要ですが、写真のように漕ぐことは何ら問題なくできていましたので、ブランコの漕ぎ方を憶えていた・ブランコを漕ぐ身体能力はあったってことですね。
当時は、みなさんの日常の様子を家族に見ていただく・知っていただく、ここに書いたような「捉え方を共有していただく」ためにカメラを持って外出していましたネ。
ブランコに乗るって「事故リスクでしかないのに、乗ろうとしたことをなぜ止めないか」を共有するということです。
地面を照らす光の具合も良く、僕の好きなステキなショットです。








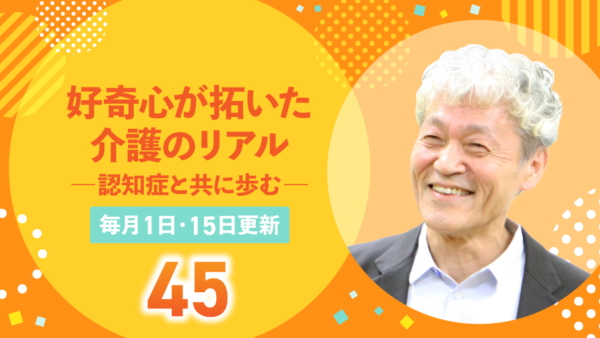




.webp)