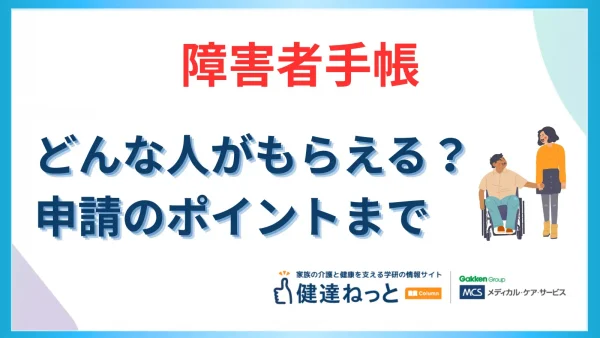- 「自分のこの症状は、障害者手帳の対象になるのだろうか…」
- 「どんな病気や障害の人がもらえるのか、具体的な基準が知りたい」
- 「申請は難しそうだし、メリットやデメリットもよく分からない」
このようなお悩みや疑問を抱え、将来の生活や経済的な見通しに、漠然とした不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
そのお気持ち、よく分かります。
複雑に見える制度を前に、どこから手をつけてよいか分からなくなってしまうのは当然のことです。
しかし、ご安心ください。
この記事を読めば、その不安が「ご自身が何をすべきか」という具体的な道筋に変わります。
障害者手帳は、病名だけで決まるものではありません。
大切なのは「生活にどれだけの影響があるか」という視点です。
この記事では、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- あなたが対象か分かる3つのセルフチェック
- 3種類の手帳の対象者と等級の考え方
- スムーズな申請を実現する5つのステップ
- あなたに近い状況が見つかる具体的なケーススタディ
読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に判断し、次の一歩を踏み出すための知識と勇気が得られているはずです。
スポンサーリンク
障害者手帳はどんな人がもらえる?すぐ分かるセルフチェック3問
障害者手帳の対象になるか、まずご自身の状況を整理してみましょう。
ここでは、判断の基本となる3つの質問をご用意しました。
「はい」「いいえ」で答えてみることで、ご自身の立ち位置が見えてきます。
その「生活のしづらさ」が6か月以上続いているか
障害者手帳の対象となるのは、一時的なケガや病気ではなく、永続的な障害です。
特に精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神障害による初診日から6か月以上経過していることが申請の条件として明確に定められています。
これは、症状が一時的なものではないことを示すための、客観的な指標といえるでしょう。
身体障害者手帳については、障害の固定が条件となりますが、具体的な経過期間の規定はありません。
療育手帳は原則として18歳になるまでに知的機能の障害が現れることが対象となります。
原因は「身体の機能」「精神の不調」「知的な発達」どれに近いか
障害者手帳は、原因となる障害の種類によって大きく3つに分けられます。
ご自身の「生活のしづらさ」の主な原因が、以下のどれに当てはまるかを考えてみましょう。
- 身体の機能:目が見えにくい、耳が聞こえにくい、手足が動きにくい、内臓の機能に問題があるなど。
- 精神の不調:気分が落ち込む、やる気が出ない、幻覚や幻聴がある、人との関わりがうまくいかないなど。
- 知的な発達:物事を理解したり判断したりするのが難しい、年齢相応の社会生活が困難であるなど。
この分類によって、どの手帳の対象となるかが決まります。
複数の原因が考えられる場合もありますが、まずは最も影響の大きいものはどれかを考えてみることが、次のステップに進むための手掛かりとなります。
医師の診察を受けており、状態を客観的に説明できるか
障害者手帳の申請には、医師による専門的な診断書や意見書が不可欠です。
ご自身の判断だけでなく、専門家である医師が診察し、その症状や生活への影響度を客観的に証明する必要があります。
そのため、現在、定期的に医療機関へ通院しているか、また、ご自身の状態を医師に相談できているかが重要なポイントになります。
もし、まだ受診していない場合は、まず専門の医療機関に相談することから始めましょう。
医師との対話を通じて、ご自身の状態を正確に把握することが、適切な支援への第一歩となります。
スポンサーリンク
障害者手帳は3種類のサポーター!それぞれどんな人が対象?
障害者手帳は、単なる証明書ではなく、あなたの生活を支える頼もしい「サポーター」です。
障害の種類に応じて3人のサポーターがいます。
それぞれどのような方が対象となるのか、具体的に見ていきましょう。
身体のサポーター「身体障害者手帳」
「身体障害者手帳」は、身体の機能に一定以上の永続的な障害がある方を支えるサポーターです。
視覚や聴覚、手足の動きだけでなく、心臓やじん臓といった内部の障害も対象となります。
障害者手帳は、身体障害、知的障害、精神障害のある方がさまざまな支援制度やサービスを受けるために必要な重要な証明書です。
対象となる障害は、身体障害者福祉法で具体的に定められています。
主な対象は以下の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹など)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
- 肝臓の機能の障害
これらの障害の程度によって、1級から6級までの等級に分けられます。
ただし、7級の障害は単独では手帳の交付対象とならず、2つ以上重複する場合に6級として認定されます。
例えば、嚥下機能の低下なども対象となり得るため、食事にむせやすくなったなどのお悩みがある方も、一度専門医に相談してみるとよいでしょう。
心のサポーター「精神障害者保健福祉手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患や発達障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方のためのサポーターです。
この手帳のポイントは、対象となる疾患の範囲が広いことです。
対象となるのはすべての精神障害で、以下のような疾患が含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、双極性障害などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
- その他の精神疾患(認知症、ストレス関連障害など)
障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されています。
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要条件となります。
健達ねっとが運営する介護施設では、認知症の方でも感情記憶を元に安定した生活を送る事例や、脳出血後遺症の方が地域で見守られながら自立した生活を取り戻す事例が多数あります。
このような回復の可能性も視野に入れながら、現在の生活の困難さについて、専門家へ相談することが大切です。
成長と生活のサポーター「療育手帳(愛の手帳)」
「療育手帳」は、知的障害のある方が、一貫した指導・相談やさまざまな支援を受けやすくするためのサポーターです。
他の手帳と異なり、法律ではなく各自治体の要綱に基づいて交付されるため、「愛の手帳」など地域によって名称が異なります。
対象となるのは、おおむね18歳になるまでに知的機能の障害が現れ、その障害によって日常生活に支障が生じている方です。
児童相談所や知的障害者更生相談所といった専門機関で、知的障害があると判定される必要があります。
判定の主な基準は以下の通りです。
- 知能指数(IQ):おおむね70~75以下が目安
- 食事、着替え、金銭管理、コミュニケーションといった日常生活能力
これらの要素を総合的に評価し、障害の程度が重度「A」や中度・軽度「B」などに区分されます。
お子様の発達に関する支援だけでなく、大人になってからも就労支援など、生涯にわたるサポートを受けるための大切な手帳です。
「病名」だけでは決まらない「生活への影響度」で見る等級のリアル
障害者手帳の等級は、病名や障害名だけで機械的に決まるわけではありません。
最も重視されるのは、その障害が「日常生活や社会生活に、どの程度の影響を及ぼしているか」という点です。
ここでは、その影響度を3つのレベルに分けて考えてみましょう。
Level3:日常生活や仕事に、時々または一部、支障がある状態
これは、障害者手帳の中では比較的軽い等級に該当するレベルです。
例えば、精神障害者保健福祉手帳の3級がこのイメージに近いでしょう。
具体的な状態としては、「精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」が該当します。
- 日常的な家事や身の回りのことは、工夫や支援があればおおむね一人でできる。
- 対人関係において、多少の困難さを感じることがある。
- 決められた手順の仕事であれば、援助を受けながらこなせる。
基本的な生活は自立して行えるものの、特定の場面で困難さを感じたり、ストレスがかかる状況では支援が必要になったりする状態です。
一見すると障害がないように見えることもありますが、安定した社会生活を送るためには、さまざまな配慮やサポートが有効となります。
Level2:日常生活や仕事に、かなりの支障がある状態
日常生活を送る上で、多くの場面で支援や援助が必要となるレベルです。
精神障害者保健福祉手帳の2級や、身体障害者手帳の中程度の等級がこれに当たります。
精神障害者保健福祉手帳2級の場合、「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
このレベルの状態は、以下のようなイメージです。
- 食事や入浴、金銭管理など、日常生活の多くの場面で助言や手助けが必要。
- 一人で外出することが難しく、誰かの付き添いが求められる。
- 継続して仕事をすることが難しく、ごく簡単な作業に限られる。
常に誰かのサポートが必要なわけではないものの、自立して生活するには多くの壁がある状態です。
福祉サービスなどを活用することで、生活の質を大きく向上させることが可能です。
Level1:他者の補助なしでは、日常生活を送るのがほぼ不可能な状態
生活全般にわたって、常時、他者からの援助や介護が必要となる、最も重い等級のレベルです。
精神障害者保健福祉手帳の1級や、身体障害者手帳の最重度の等級が該当します。
精神障害者保健福祉手帳1級は「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定義されています。
具体的な状態として考えられるのは、以下のものです。
- 食事、排泄、入浴、着替えなど、身の回りのことのほとんどに介助を必要とする。
- 常にベッドの上で過ごしていることが多い。
- 他者との意思疎通が著しく困難である。
当サイトを運営するメディカル・ケア・サービスでは、このような状態の方でも、科学的介護に基づく「MCS版自立支援ケア」により、身体機能が改善する事例が実証されています。
適切なケアによって「生活への影響度」は変化しうるという視点を持つことも大切です。
障害者手帳がもたらす3つの安心
障害者手帳を取得することは、単にサービスを受けるためだけではありません。
それは、将来への不安を具体的な「安心」に変えるための、力強い一歩です。
手帳がもたらす安心には、大きく3つの側面があります。
経済的な安心
障害や病気は、医療費や生活費の負担増につながることが少なくありません。
障害者手帳は、その経済的な不安を和らげるためのさまざまな制度につながっています。
障害者手帳所持者は税金の控除や各種減免制度の適用を受けることが可能です。
主な経済的支援は以下の通りです。
- 税金の控除・減免:所得税の障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。また、住民税、相続税などの控除が受けられます。自動車税なども減免の対象となる場合があります。
- 医療費の助成:自治体によって、心身障害者医療費助成制度などがあり、医療費の自己負担額が軽減されます。
- 各種手当の支給:特別障害者手当や障害児福祉手当など、障害の程度に応じた手当が支給される場合があります。
- 公共料金の割引:NHK受信料の減免や携帯電話料金、上下水道料金などの割引制度が利用可能です。
これらの制度を活用することで、経済的な基盤が安定し、安心して治療や生活に専念できるようになります。
また、手帳とは別に、経済的な支えとなる障害年金という制度もあります。
社会参加への安心
「働きたいけれど、障害のことで不安がある」
「社会とのつながりを持ち続けたい」
障害者手帳は、そのような思いに応え、社会参加への扉を開く鍵となります。
特に大きいのが、就労に関する支援です。
障害者手帳により就労支援や職場での合理的配慮を受けられ、企業への助成金制度も充実しています。
- 障害者雇用枠での就職:企業は法律で定められた割合の障害者を雇用する義務があり、「障害者雇用枠」での就職活動が可能になります。また、手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウントとして認められ、障害への配慮を得ながら、安定して働く機会が広がります。
- 就労支援サービスの利用:就労移行支援事業所などを利用し、仕事に必要なスキルを身につけたり、職場探しや定着のサポートを受けたりすることが可能です。障害者職場適応訓練の実施も受けられます。
障害があることをオープンにして働くことで、無理のないペースで能力を発揮し、社会の一員としての役割を担うことが可能です。
これは、経済的な自立だけでなく、自己肯定感の回復にもつながる大きな安心といえるでしょう。
暮らしの安心
日々の暮らしの中での「ちょっとした不便」が、積み重なると大きなストレスになります。
障害者手帳は、そのような暮らしの中の障壁を取り除き、快適な生活をサポートするサービスにつながっています。
暮らしを支えるサービスの例は以下の通りです。
- 交通機関の運賃割引:JRや私鉄、バス、タクシーなどの運賃が割引になり、通院や外出の負担が軽くなります。
- 公共施設の利用料減免:美術館や博物館、動物園などの公共施設や、映画館などの入場料が割引または無料になることがあります。
- 福祉用具の給付・貸与:車いすや補装具などの購入・レンタル費用について、補助を受けることが可能です。
- 住宅に関する支援:住宅改修や公営住宅の優先入居、家賃の助成などが受けられる場合があります。
これらのサービスは、行動範囲を広げ、生活の質を高めることに直結します。
さまざまな場面で社会的なサポートがあるという事実は、日々の暮らしに大きな安心感をもたらしてくれるでしょう。
障害者手帳をもらうための5つのステップ
「自分も対象かもしれない」と思ったら、次に行動に移してみましょう。
申請手続きは難しく感じるかもしれませんが、ステップをひとつずつ進めれば大丈夫です。
ここでは、申請から交付までの流れを5つのステップで解説します。
ステップ1.市区町村の福祉担当窓口に相談する
すべての始まりは、お住まいの市区町村の役所にある障害福祉担当窓口への相談です。
申請は、市区町村の担当窓口で行ってください。
「障害者手帳の申請を検討している」と伝えれば、専門の職員が対応してくれます。
この段階で、以下のことを確認しましょう。
- どの手帳の対象になりそうか
- 申請に必要な書類一式
- 申請書の書き方
- 今後の大まかな流れ
ここで申請に必要な書類をもらえます。
分からないことや不安なことは、遠慮なく質問することが大切です。
ここでの相談が、スムーズな申請への第一歩となります。
ステップ2.主治医に相談し「診断書・意見書」を依頼する
次に、かかりつけの主治医に相談し、申請に必要な診断書や意見書の作成を依頼します。
この書類は、審査において最も重要なものとなるため、ご自身の日常生活の状況や困っていることを、できるだけ具体的に伝えましょう。
依頼する際のポイントは以下の通りです。
- 身体障害者手帳の場合:診断書を作成できるのは、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師の診断書・意見書のみです。主治医が指定医でない場合は、紹介してもらう必要があります。
- 精神障害者保健福祉手帳の場合:診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(または精神障害の診断または治療に従事する医師)が記載したものが必要です。
- 診断書作成には費用がかかる:医療機関によって異なりますが、数千円程度の文書作成料が必要です。
普段の診察時から、生活上の変化や困難について医師に伝えておくことが、的確な診断書の作成につながります。
ステップ3.申請書・写真・本人確認書類を揃える
診断書が出来上がるのを待つ間に、他の必要書類を準備しましょう。
一般的に必要となるのは以下の書類です。
- 申請書:ステップ1で窓口からもらった書類です。必要事項を記入します。
- 顔写真:本人の写真縦4cm×横3cmの証明写真が基本です。脱帽して上半身を撮影した、1年以内に撮影したものを用意しましょう。
- 本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証などです。
- 印鑑:認印でかまいません。
自治体によっては、この他にも書類が必要な場合があります。
ステップ1で受け取った案内に従って、漏れのないように準備を進めましょう。
ステップ4.準備した書類一式を窓口へ提出する
必要な書類がすべて揃ったら、再び市区町村の担当窓口へ行き、提出します。
提出は本人でなくても、家族や医療機関関係者等が代理で行うことも可能です。
提出時に、職員が書類に不備がないかを確認してくれます。
もし、記入漏れや不足書類があった場合は、その場で指示に従いましょう。
すべての書類が受理されれば、申請手続きは完了です。
この後、専門機関による審査が始まります。
ステップ5.審査を経て、交付の通知を待つ
申請後は、審査結果が出るのを待ちます。
精神障害者保健福祉手帳の場合は、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われます。
審査期間は手帳の種類や自治体によって異なりますが、おおむね1か月半から3か月程度かかるのが一般的です。
審査の結果、交付が決定すると、自宅に交付通知書が郵送されてきます。
その通知書と印鑑、本人確認書類などを持って、指定された期間内に窓口へ手帳を受け取りに行きましょう。
残念ながら却下(非該当)となった場合も、その旨が通知されます。
こんな人はどうなる?障害者手帳はどんな人がもらえるかのケーススタディ
制度の説明だけでは、自分の状況と重ね合わせるのが難しいかもしれません。
ここでは、3つの具体的なケースを通して、どのような方が対象となり得るのかを見ていきましょう。
あなたの状況に近いケースがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
ケース1.40代・うつ病で休職中の方(精神障害者保健福祉手帳)
Aさんは45歳。
仕事のプレッシャーからうつ病を発症し、1年前から心療内科に通院しながら休職しています。
主治医の指示通り服薬を続けていますが、気分の落ち込みや意欲の低下が改善せず、復職の目処が立たない状況です。
日常生活では、外出が億劫で、家事もままならない日が多くあります。
【ポイント】
- 初診日から6か月以上経過:通院歴が1年あるため、条件を満たしています。
- 生活への影響度:意欲低下により家事が困難、就労もできない状態は、社会生活への著しい制限があると判断される可能性があります。
- 対象となる手帳:うつ病などの気分障害は精神障害者保健福祉手帳の対象疾患です。
このケースでは、主治医に相談の上で診断書を作成してもらい、精神障害者保健福祉手帳の2級または3級に該当する可能性が考えられます。
手帳を取得することで、経済的支援を受けながら、安心して療養に専念したり、就労移行支援などを利用して社会復帰の準備を進めたりする道筋が見えてきます。
ケース2.70代・膝の痛みで歩行が困難な親を持つ方(身体障害者手帳)
Bさんの母親は78歳。
長年の変形性膝関節症が悪化し、最近では杖を使っても短い距離を歩くのがようやくの状態です。
買い物や通院には、Bさんの付き添いが欠かせません。
家の中でも、立ち座りや階段の上り下りに大きな苦痛を伴います。
【ポイント】
- 障害の永続性:変形性膝関節症は加齢に伴う進行性の疾患であり、症状の永続性が認められます。
- 生活への影響度:自力での歩行が著しく困難で、日常生活の多くの場面で介助を必要とする状態です。
- 対象となる手帳:下肢の機能障害として、身体障害者手帳の対象となります。
この場合、整形外科の指定医による診察を受け、関節の可動域や筋力などを評価してもらう必要があります。
障害の程度によっては、4級や3級などに該当する可能性があります。
当サイトを運営するメディカル・ケア・サービスでも、適切な運動プログラムにより身体機能が改善した多くの事例があります。
手帳取得後は、適切なリハビリテーションや介護サービスを利用し、生活の質の維持・向上を目指すことが重要です。
ケース3.小学生・発達障害の診断を受けたお子さんを持つ方(療育手帳・精神手帳)
Cさんの息子は小学3年生。
先日、専門機関でASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠陥多動性障害)の診断を受けました。
学校では、授業に集中できなかったり、友達とのコミュニケーションがうまくいかなかったりして、集団生活に困難を抱えています。
また、知的発達にも少し遅れが見られます。
【ポイント】
- 手帳の選択肢:知的な遅れを伴う場合は「療育手帳」、伴わないか軽度の場合は「精神障害者保健福祉手帳」が主な選択肢となります。発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けられます。
- 相談機関:療育手帳は児童相談所、精神障害者保健福祉手帳は市区町村の窓口が起点となります。
- 目的の明確化:放課後等デイサービスなどの福祉サービス利用や、将来の就労支援など、手帳を取得する目的を明確にすることが大切です。
このケースでは、まず児童相談所や主治医に相談し、どちらの手帳が現状の支援ニーズに合っているかを検討することから始めます。
手帳を取得することで、学校での合理的配慮や、専門的な療育を受けやすくなるなど、お子さんの健やかな成長を社会全体でサポートする体制を整えられます。
障害者手帳はどんな人がもらえるかの疑問を解消するQ&A
ここでは、障害者手帳に関してよく寄せられる質問にお答えします。
申請を検討する上で、多くの方が疑問に思うポイントです。
障害年金との違いは?両方もらえる?
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度です。
手帳は「福祉サービスの利用」、年金は「所得の保障」が主な目的です。
審査機関も基準も異なるため、片方を持っていても、もう片方が必ずもらえるわけではありません。
逆に、両方の要件を満たせば、手帳と年金の両方を受給することも可能です。
手帳を2種類以上持てる?
はい、持てます。
例えば、知的障害と精神障害の両方がある方が、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持つケースなどがあります。
ただし、受けられるサービスによっては、どちらかひとつの手帳でしか利用できない場合もあるため、利用時に確認が必要です。
3級だとあまり意味ないのは本当?
いいえ、そんなことはありません。
確かに1級や2級に比べると、受けられるサービスの範囲は狭くなる場合があります。
しかし、3級であっても、税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠への応募など、多くの重要なメリットを受けられます。
生活の負担を軽減し、社会参加を後押しする上で、3級の手帳も非常に大きな意味を持ちます。
引っ越したら手帳はどうなる?
引っ越しをした場合は、転居先の市区町村の担当窓口で、住所変更の手続きが必要です。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は、等級が変わることなく引き継がれます。
ただし、療育手帳は自治体ごとに基準が異なるため、転居先の自治体で再判定が必要になる場合があります。
申請が却下された場合、もう一度申請できる?
はい、再申請は可能です。
却下された理由が、書類の不備などであれば、それを修正してすぐに再申請できます。
症状の程度が基準に満たないという理由で却下された場合は、症状に変化があった時点で、再度、診断書を取得して申請することになります。
諦めずに、主治医や窓口の担当者とよく相談することが大切です。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、障害者手帳はどんな人がもらえるのか、セルフチェックや3種類の手帳の対象者、申請のステップなどを解説してきました。
障害者手帳を取得できるかどうかは、病名や障害名だけで決まるわけではありません。
最も重要なのは、その障害が日常生活や社会生活にどの程度の影響を及ぼしているか、という視点です。
ご自身の状況を客観的に見つめ、セルフチェックやケーススタディを参考に、対象となる可能性を考えてみてください。
もし「自分も対象かもしれない」と感じたら、一人で悩み続ける必要はありません。
この記事でご紹介したように、まずは市区町村の福祉担当窓口や、かかりつけの主治医といった専門家に相談することから始めましょう。
それが、経済的な安心や暮らしの安心を手に入れ、自分らしい生活を送るための、最も確実で大切な第一歩となります。