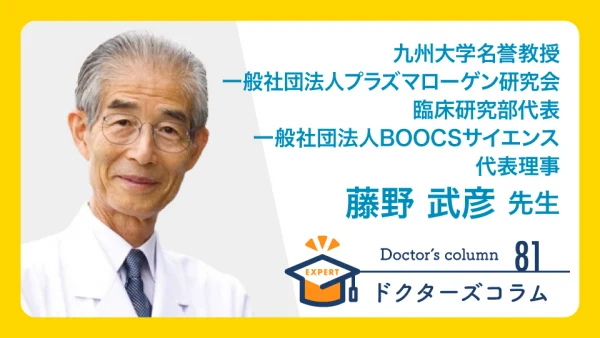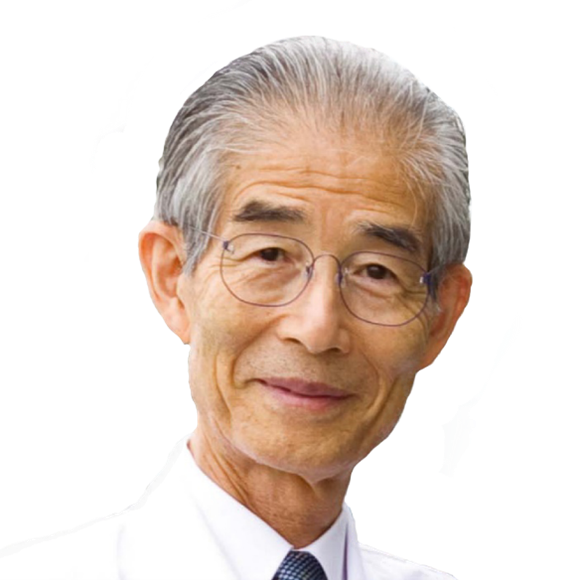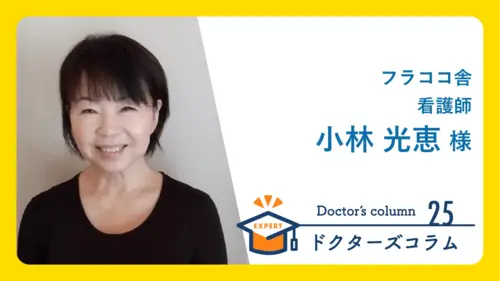スポンサーリンク
はじめに:私たちの時代に蔓延する、見過ごされた「病」―「脳疲労」
原因不明の倦怠感、集中力の低下、わけもなくイライラする、常に何かに追われているような焦燥感。現代社会を生きる多くの人が、こうした心身の不調を抱えています。これらは個人の気力や性格の問題ではなく、私たちの脳が私たちを取り巻く環境によって引き起こされている生理的な反応かもしれません。
この現代特有の不調にいち早く気づき、「脳疲労」と名付けた人物がいます(1991年)。九州大学名誉教授であり、内科医・循環器専門医でもある藤野武彦医学博士です 1。藤野先生は、従来の医学の枠組みを超え、多くの現代病の根源に潜む問題を探求し続けてきました。
本稿では、藤野先生が「脳疲労」という概念を発見し、心と体に優しい健康法「BOOCS理論」を構築するに至った軌跡をたどります。さらに、その研究過程で突き止めた、脳の必須栄養素ともいえる「プラズマローゲン」との劇的な出会い、そして両者を融合させた包括的な健康戦略「プラズマローゲンBOOCS」の科学的根拠と実践法について、専門家の視点から徹底的に解説します。
スポンサーリンク
第1章:ある医師の探求―BOOCS理論の誕生秘話
心臓から脳へ:治療の限界から生まれた逆転の発想
藤野先生のキャリアは、九州大学医学部第一内科における心臓・血管系の専門医として始まりました 4。肥満や高血圧といった生活習慣病が心臓に与える負担を目の当たりにする中で、先生は一つの壁に突き当たります。それは、従来の治療法がしばしば患者に大きなストレスを与え、結果的にリバウンドや挫折を招いてしまうという現実でした 7。厳しい食事制限や運動ノルマは、まさに「我慢」との戦いであり、その戦い自体が新たなストレスを生み出していたのです。
この経験から、藤野先生は根本的なパラダイムシフトを遂げます。食欲や行動、ストレス反応を真にコントロールしているのは胃や心臓ではなく、「脳」であると確信したのです。そして、病気になってから治療するのではなく、病気になる前の「普通の人」の健康をいかに増進させるかという「健康科学」の領域へと研究の舵を切りました。
ここで見出された重要な視点は、健康における「戦い」という比喩の限界です。「脂肪との戦い」「食欲との戦い」といった考え方そのものが、脳に過剰なストレスをかけているという発見でした。従来のダイエット法が「これを食べてはならない」という禁止命令を出すと、理性(大脳新皮質)と本能(大脳辺縁系)の間で深刻な葛藤が生まれます。この葛藤こそが、後に藤野先生が定義する「脳疲労」の正体だったのです。つまり、問題を解決するための従来のアプローチが、より根深い問題である「脳疲労」を生み出していたのです。
BOOCS理論の確立:「北風と太陽」の健康哲学
この「脳疲労」を解消するために生まれたのが、「BOOCS(Brain-Oriented Oneself Care System:脳指向型自己ケアシステム)理論」です。
脳疲労とは、情報過多やストレスにより、理性をつかさどる「父親」役の大脳新皮質と、本能や情動を担う「母親」役の大脳辺縁系の関係性が破綻し、脳内ファミリーの関係性がうまく機能しなくなった状態と定義されます。
BOOCS理論の哲学は、イソップ寓話の「北風と太陽」に例えられます。厳しい禁止や命令という「北風」は、旅人(私たち)にマント(悪い習慣)を固く握りしめさせるだけです。一方、心地よさや快感という「太陽」は、旅人が自らマントを脱ぐのを促します。この考え方に基づき、BOOCSは非常にシンプルで実践的な「2つの原理」と「3つの原則」を提唱しています。
BOOCSの2原理
- 「禁止の禁止」の原理:「~してはダメだ」という自己への禁止命令をやめること。これにより、心が解放されストレスが軽減されます。
- 「快」の原理:自分が本当に心地よいと感じることを、一日一つでもいいから始めてみること。
BOOCSの3原則
- 健康に良いことでも、自分が嫌なら決してしない。
- 健康に悪いことでも、好きでやめられないなら、とりあえず禁止しない。
- 健康に良くて、かつ自分が心地よいと感じることを始める。
この理論の具体的な第一歩として、「一日一快食」が推奨されています。これは、一日一食ということではなく、一日一回は本当に食べたいものを心から味わって食べる。この毎日の小さな「快」の実践が、脳のバランスを整え、脳疲労を解消する入り口となるのです。
BOOCSの効果
実際にBOOCSを実行することによって、肥満や糖尿病、高脂血症、高血圧などのメタボリック症候群の改善につながることが分かっています。その結果として、BOOCSプログラムに参加した人と非参加の人を1993年から2007年までの15年間追跡した研究があります。特に顕著だったのは男性で、肥満の参加者群(男性1,565名)は、肥満コントロール群(男性1,230名)と比較して、全ての原因による死亡リスクが有意に低く、BOOCSプログラムへの参加が死亡率に対して保護効果を持つことが示されたのです。
第2章:脳を守る―プラズマローゲンの発見
藤野先生が脳疲労の研究を深める中で、その生理学的なメカニズムを解明する鍵となる物質に出会います。それが「プラズマローゲン」です。
プラズマローゲンとは、私たちの体を構成する細胞膜の主成分であるリン脂質の一種です 13。特に、心臓や筋肉、そして脳のように、酸素を大量に消費する器官に高濃度で存在しています。
その最も重要な役割は、強力な「抗酸化作用」です。プラズマローゲンは、いわば脳の「ボディガード」のような存在です。その分子構造に含まれる「ビニールエーテル結合」という特殊な部位が、活性酸素などの酸化ストレスに対して非常に反応しやすくなっています。これにより、プラズマローゲンは自らが身代わりとなって酸化されることで、生命活動に不可欠な神経細胞を酸化ダメージから守っているのです。
この「身代わり」という性質は、プラズマローゲンが消耗品であることを意味します。ストレスにさらされるたびに、私たちの脳はプラズマローゲンを大量に失っているのです。ストレスによる消費量が、体内で新たに生産される量を上回ったとき、プラズマローゲンの欠乏が生じます。これは、抽象的な「ストレス」という概念を、血中のプラズマローゲン量を測定する事によって可視化できます。血中のプラズマローゲン濃度の低下は、脳の無防備な状態を意味します。
その他にも、プラズマローゲンは細胞膜の構造を安定させたり、神経の信号伝達をスムーズにしたりと、脳機能の根幹を支える多様な役割を担っています。
第3章:点と線が繋がった瞬間―脳疲労とプラズマローゲン欠乏の悪循環
藤野先生の研究は、ここで大きなブレークスルーを迎えます。「脳疲労」という心理・行動レベルの現象と、「プラズマローゲン欠乏」という生化学レベルの現象が、一致していることを突き止めたのです。
- ストレスと脳疲労:現代社会の慢性的なストレスが「脳疲労」状態を引き起こします。
- 酸化ストレス(神経炎症)の発生:脳疲労はストレスによる酸化ストレス(神経炎症)の発生により脳の神経細胞がダメージを受け、脳の機能が低下した状態です。
- プラズマローゲンの枯渇:発生した酸化ストレスを無害化するため、脳の身代わりになりプラズマローゲンが急速に消費され、枯渇していきます。
- 脳機能の低下:プラズマローゲンが減少すると、神経細胞はダメージを受けやすくなり、情報伝達が滞ります。これが直接的に認知機能、情動制御、記憶力の低下につながります。
- 脳疲労の深刻化:機能が低下した脳はストレスへの対処能力がさらに低下し、疲労感や焦燥感が強まります。これが脳疲労をさらに悪化させ、負のスパイラルに陥るのです。
この仮説を裏付けるように、プラズマローゲンの低下は様々な疾患と関連していることが科学的に証明されています。最も顕著なのがアルツハイマー病で、患者の脳や血液中ではプラズマローゲンが著しく減少していることが数多くの研究で報告されています。さらに、肥満や糖尿病などのメタボリック症候群、うつ病、そして慢性的な疲労感を抱える人々においても、同様にプラズマローゲンの低下が見られることが分かっており、「脳疲労」がこれらの疾患の共通した根源である可能性を強く示唆しています。
第4章:理論から証明へ―科学が示した確かなエビデンス
この脳疲労とプラズマローゲンの関係性を証明するためには、理論だけでなく、客観的な科学的証拠が必要でした。もしこの仮説が正しければ、失われたプラズマローゲンを外部から補給することで、症状が改善するはずです。
藤野先生の研究チームは、医学研究における最も信頼性の高い手法である「ランダム化比較試験(RCT)」を実施しました。これは、被験者を無作為に2つのグループに分け、一方には本物の成分(実薬)、もう一方には有効成分を含まない偽薬(プラセボ)を投与し、その効果を比較する試験です。医師も患者もどちらを投与されているか知らない「二重盲検」という手法を用いることで、あらゆる思い込みや偏見を排除し、純粋な効果を検証することができます。
世界が認めた臨床試験の成果
この大規模な臨床試験の結果は、世界五大医学雑誌の一つである『The Lancet』の姉妹誌『eBioMedicine』に掲載され、国際的にその科学的妥当性が世界で初めて認められました。試験では、軽度のアルツハイマー病(AD)または軽度認知障害(MCI)と診断された328名の患者を対象に、高純度のホタテ由来プラズマローゲン、またはプラセボを24週間にわたって摂取してもらいました。その結果は、これまでの認知症治療の常識を覆す可能性を秘めた、画期的なものでした。
その後、中等症、重症のアルツハイマー病患者の臨床試験も行われ、その結果は『Journal of Alzheimer’s Disease & Parkinsonism』に掲載されました。中等症、重症の場合はプラセボ効果がみられないことから、実薬のみの試験ですが、中等度のアルツハイマー病患者で最も顕著な変化がみられました。
- 軽度アルツハイマー病患者において、記憶機能を評価する検査(WMS-R)で、プラセボ群と比較して統計的に有意な記憶力の改善が認められました。
- 軽度認知障害(MCI)患者において、全般的な認知機能を評価する検査(MMSE-J)で有意な改善が見られ、特に日常生活の自立に不可欠な「場所の見当識(自分がどこにいるかを認識する能力)」が顕著に向上しました。
- 中等度および重度アルツハイマー病患者において、認知機能を評価する検査(MMSE)が向上しました。特に中等度では顕著でした。
- 中等度および重度アルツハイマー病患者において、周辺症状(BPSD)の調査では、幻覚や妄想、抑うつ、不眠などにも改善がみられ、笑顔や気遣いが増えることが分かりました。
- 血液検査では、プラズマローゲン摂取群の血中濃度が維持・上昇したのに対し、プラセボ群では低下が続きました。これは、サプリメントが生化学的に作用している直接的な証拠となります。
表1:ホタテ由来プラズマローゲン臨床試験の主要結果概要
| 対象グループ | 評価項目 | プラズマローゲン摂取群の結果 | プラセボ(偽薬)群の結果 | 示唆される意義 |
| 軽度アルツハイマー病 | 記憶機能 (WMS-R) | 有意に改善 | 有意な変化なし | 記憶機能が維持だけでなく改善する可能性を示唆。 |
| 軽度認知障害 (MCI) | 場所の見当識 | 有意に改善 | 有意な変化なし | 道に迷うなどのリスクを減らす、実生活上の重要な効果。 |
| 中等度・重度アルツハイマー病 | 認知機能 (MMSE) | 有意に改善 | - | 認知機能が維持だけでなく改善する可能性を示唆。 |
| 全グループ | 血中プラズマローゲン濃度 | 上昇または維持 | 低下 | プラズマローゲンが体内に吸収され、効果的に補充されていることを確認。 |
出典:『eBioMedicine』、『Journal of Alzheimer’s Disease & Parkinsonism』などに掲載された臨床試験データに基づく
これらの結果が持つ最も深い意味は、認知機能低下に対する治療パラダイムの転換です。これまで認知症治療の目標は、避けられない進行を「遅らせる」ことでした。しかし、この試験結果は、特に早期段階において、認知機能の「改善」が可能であることを示唆しています。これは、受動的な管理から、細胞レベルの修復と機能回復を目指す積極的な栄養介入へと、治療の選択肢を広げるものであり、多くの患者とその家族に新たな希望をもたらすものです。
第5章:包括的ソリューション―「プラズマローゲンBOOCS」の相乗効果
「プラズマローゲンBOOCS」とは、単なるサプリメントの名称ではありません。それは、藤野先生が提唱するライフスタイルの哲学と、科学的に証明された栄養介入を組み合わせた、脳の健康を守るための包括的な戦略です。
このアプローチは、「穴の空いたバケツの水を満たす」という比喩で説明できます。
- 防御(BOOCS理論の実践):穴を塞ぐ
BOOCSの原理を生活に取り入れることで、ストレスへの対処法を学び、慢性的なストレス反応を鎮めます。これにより、脳内の酸化ダメージの発生が抑えられ、プラズマローゲンの無駄な**消費(漏れ)**を食い止めることができます。 - 攻撃(プラズマローゲンの補給):水を注ぐ
高品質なプラズマローゲンサプリメントを摂取することで、すでに枯渇してしまったプラズマローゲンを直接**補充(水を注ぐ)**します。これにより、細胞の保護、修復、そして最適な機能発揮に必要な材料を供給します。
この2つのアプローチは、どちらか一方だけでは不完全です。BOOCSを実践せずにサプリメントだけを摂取するのは、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるようなもので、絶え間ない消耗との戦いになります。逆に、サプリメントなしでBOOCSだけを実践しても、脳の資源がすでに枯渇しきっている場合には、自己修復能力が追いつかない可能性があります。
両者を組み合わせることで初めて、好循環が生まれます。BOOCSがダメージを減らし、プラズマローゲンがそれを修復する。その結果、脳はより強靭になり、ストレスへの対処能力が高まる。そして、それがさらにBOOCS的な生き方を容易にするのです。
第6章:健やかな脳を手に入れるための実践ガイド
パート1:BOOCSな生き方を始めるための小さな一歩
BOOCSは完璧を目指すものではなく、自分に優しくあることから始まります。
- 実践のヒント1:「一日一快食」から始める。一日に一回、罪悪感なく、本当に好きなものを心から味わって食べる時間を作りましょう。
- 実践のヒント2:小さな「快」をスケジュールに入れる。音楽を聴く、散歩する、趣味に没頭するなど、自分が心地よいと感じる時間を意識的に確保しましょう。
- 実践のヒント3:「禁止の禁止」を意識する。「~すべき」「~してはならない」という思考が浮かんだら、それに気づき、そっと手放す練習を一日一回してみましょう。
パート2:プラズマローゲンサプリメントの賢い選び方
ホタテ、鶏肉、ホヤといった食品にもプラズマローゲンは含まれていますが、治療効果が期待できる量を食事だけで摂取するのはほぼ不可能です。プラズマローゲンは熱に弱く、また食品から効率的に抽出する仕組みが体内にはないため、サプリメントによる補給が現実的です。
- ホタテ:主要な臨床試験で使用され、最も豊富なエビデンスを持つ原料です。脳にはエタノールアミン型のプラズマローゲンが多く含まれており、特に脳に不可欠な脂肪酸であるDHAを含んだエタノールアミン型のプラズマローゲンはホタテが37.1%で、鶏肉(23.8%)やホヤ(19.4%)よりも多く含まれており有用性が期待されています。
- 鶏肉:コリン型のプラズマローゲンが多く含まれています。
- ホヤ:ホヤの素材にはDHAやEPAを豊富に含みますが、DHAを含んだエタノールアミン型のプラズマローゲンの含有率は低いことが分かっています。
- 臨床研究のある原料か:最も科学的根拠が豊富な「ホタテ由来」の製品を選びましょう。
- 含有量が明確か:臨床試験で効果が確認された「1日あたり1mg (1000μg)」という量が明記されているか確認しましょう。
- GMP認定工場で製造されているか:医薬品レベルの品質管理基準である「GMP認定」工場で製造された製品は、安全性と品質の信頼性が高いと言えます。
- 安全性:プラズマローゲンは元々体内に存在する成分であり、「ホタテ由来」の臨床試験でも重篤な副作用は報告されておらず、安全性の高い成分です。
健達ねっとでは、認知機能改善などのサプリメントを販売しておりますので、上記の選ぶポイントを参考にぜひ一度ご覧ください。
スポンサーリンク
結論:自らの手で、脳の未来をデザインする
九州大学名誉教授・藤野武彦先生の探求の旅は、ストレスに満ちた現代医療の限界の観察から始まり、「脳疲労」という核心的な問題の発見、そして「BOOCS」という心に寄り添う哲学の創出へと続きました。その道のりは、科学的探求心によって「プラズマローゲン」という脳の守護神の役割を解明し、その有効性を世界最高水準の臨床試験で証明するという偉業によって、一つの完成形を迎えました。
藤野先生の研究が私たちに伝える最も力強いメッセージは、「脳の健康は自らデザインできるものである」という事実です。脳疲労は、現代生活や加齢の避けられない副産物ではなく、対処可能な状態です。
BOOCSという生き方の指針と、プラズマローゲンという科学的裏付けのあるツール。私たちは今、自らの脳の健康を守り、育むための頼もしい道具箱を手にしています。自身の脳疲労に気づき、この包括的で、科学に基づいたアプローチを検討することは、輝きに満ちた未来への第一歩となるでしょう。
- 藤野武彦 | 人名事典 | お楽しみ – PHP研究所 https://www.php.co.jp/fun/people/person.php?name=%E8%97%A4%E9%87%8E%E6%AD%A6%E5%BD%A6
- 藤野武彦について|脳疲労概念【BOOCS公式サイト】https://boocs.jp/history/
- 脳疲労について知る|脳疲労概念【BOOCS公式サイト】https://boocs.jp/
- 「軽度アルツハイマーの症状が改善」プラズマローゲンとは~藤野武彦医師に聞いた | 認知症ねっと https://info.ninchisho.net/archives/22212
- BOOCSとは| 脳疲労概念【BOOCS公式サイト】 https://boocs.jp/about/boocs
- 『BOOCS―至福のダイエット革命』(藤野 武彦) – 講談社 https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000178991
- プラズマローゲン|脳疲労との関係、認知症との関係 – 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア https://www.amcare.co.jp/amc_labo/plasmalogen/
- BOOCSプログラム参加者の死亡率改善:日本の某職域集団における 15 年間の追跡調査https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4351997/
- (BOOCS)プログラムによる糖尿病患者または肥満患者の赤血球変形能を改善するhttps://jps.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12576-012-0221-z
- プラズマローゲン – Wikipedia, 、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3
- プラズマローゲンとは – プラズマローゲン研究室LABO, https://bandscorp.jp/learn/plslabo/plasmalogen_3/
- 脳組織における役割 | プラズマローゲンとは – レオロジー機能食品研究所, 、 https://www.reoken.com/plasmalogen/about/role.html
- 脳疲労とプラズマローゲン| 脳疲労概念【BOOCS公式サイト】, 、 https://boocs.jp/about/plasmalogen
- 世界が認めたアルツハイマー型認知症症状の改善効果, 、 https://bandscorp.jp/learn/plslabo/study_1/
- 認知症との関係 – プラズマローゲン – 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア, 、 https://www.amcare.co.jp/amc_labo/plasmalogen/seibun/seibun_002/
- 【中編】プラズマローゲンとは?第4のホルモンが認知症治療を変える可能性, 、 https://www.nou-kenkou.jp/dementia_prevention/711/
- プラズマローゲンとは – 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア, 、 https://www.amcare.co.jp/amc_labo/plasmalogen/seibun/seibun_001/
- 「認知症」要因の真髄に迫る! – 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア, 、 https://www.amcare.co.jp/amc_labo/plasmalogen/expert/expert_001/
- BOOCSクリニック福岡/ブックスクリニック福岡~福岡市博多区、糖尿病内科、循環器科、肥満外来、BOOCS, 、 https://www.boocsclinic.com/fukuoka/
- プラズマローゲン物語 (46) (47)を掲載しました。| 脳疲労概念【BOOCS公式サイト】, https://boocs.jp/dblog/archives/53
- 「ホタテ由来プラズマローゲン」の継続摂取で 睡眠改善や疲労回復に効果を示し、集中力を高めるhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=156963
- 第30回日本病態生理学会大会 教育シンポジウム|プラズマローゲンはアルツハイマー病及びその他の精神神経疾患を改善する2022年1月8, 9日(福岡)http://30th-pathophysiology.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=37048
- 第1回日本脳サプリメント学会学術集会|ホタテプラズマローゲンの認知症に対する効果 2019年10月19日(名古屋)https://6b95d072-44e5-4cb6-b67e-26198abec2ca.filesusr.com/ugd/bb2283_bc964325b934432399501f537c102467.pdf
- 認知症を予防できる未来へ。ホタテ由来のプラズマローゲン最新研究成果https://info.ninchisho.net/archives/19156
- 認知症はもう不治の病ではない! 脳内プラズマローゲンが神経細胞を新生する 単行本https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%86%E4%B8%8D%E6%B2%BB%E3%81%AE%E7%97%85%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84-%E8%84%B3%E5%86%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%81%8C%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B4%B0%E8%83%9E%E3%82%92%E6%96%B0%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B-%E8%97%A4%E9%87%8E-%E6%AD%A6%E5%BD%A6/dp/4893088505/ref=pd_bxgy_thbs_d_sccl_1/357-3057478-8123158?pd_rd_w=0vvQM&content-id=amzn1.sym.dee070b1-16ee-44ca-b1c2-031bd9c55b61&pf_rd_p=dee070b1-16ee-44ca-b1c2-031bd9c55b61&pf_rd_r=58J08FPNK6B0S7G1GP8K&pd_rd_wg=mJ8CN&pd_rd_r=841fd8b0-eb27-47f0-89e2-4c54005d1b37&pd_rd_i=4893088505&psc=1
- 認知症も、がんも、「不治の病」ではない! 単行本https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%82%E3%80%81%E3%81%8C%E3%82%93%E3%82%82%E3%80%81%E3%80%8C%E4%B8%8D%E6%B2%BB%E3%81%AE%E7%97%85%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84-%E8%97%A4%E9%87%8E-%E6%AD%A6%E5%BD%A6/dp/4893089021
- 新しいプラズマローゲンの効果が徐々に明らかに!https://www.amcare.co.jp/amc_labo/plasmalogen/expert/expert_004/
- 脳疲労解消、そして脳活性化へ. 保健の科学 2020年 第62巻第3号https://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=ac1hkkgj&ye=2020&vo=62&issue=3
- 脳疲労解消とダイエット. 食と医療 2019 Vol.11 https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000327667
- ホタテ由来プラズマローゲンのアルツハイマー病、軽度認知機能障害に対する治療効果. アルツハイマー病-発症メカニズムと新規診断法・創薬・治療開発- 第2編6章4節 エヌ・ティー・エス, 2018
http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/bio/20180800_202.html - 脳疲労理論とプラズマローゲンーメタボリック症候群とアルツハイマー病の医療を変える― 日本アンチエイジング歯科学会誌 華齢11, 99-103, 2018 https://jd-aa.net/wp-content/uploads/2022/05/jdaa11.pdf
- プラズマローゲン. 認知症と機能性食品-最新動向とその可能性p162-166, 2018 https://www.fuji-medical.jp/book/1320.html
- プラズマローゲンと認知機能障害(認知症)そして「脳疲労」. 機能性食品と薬理栄養https://jsmuff.com/u1hQThdU/aDwt_63d
- プラズマローゲンの経口投与はネガティブ気分を改善し、精神集中力を高めるhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=156963
- プラズマローゲンはGタンパク質共役型受容体(GPCR)21を活性化することによりNK細胞の標的細胞に対する溶解活性を高めるJ Immunol 2022, 209:310-325
- ホタテ由来プラズマローゲンの中等症・重症アルツハイマー病における行動・心理症状への効果(ホタテ由来Plsの経口投与により中等症および重症AD患者のBPSDを改善する)第18回日本機能性食品医用学会総会https://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=157670
- Plsが海馬における脳由来神経栄養因子(Bdnf)の内因性発現を増強し、マウスの学習・記憶の改善に関連する神経新生を促進するhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=157669
- ホタテ由来精製Plsの経口投与で、軽度ADの記憶機能が改善することを示唆しているhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=167333
- Plsには抗神経炎症作用とアミロイド生成予防効果があると考えられ、アルツハイマー病の予防または治療へのPlsの応用が示唆されるhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=167328
- 軽度認知障害に対するプラズマローゲンの効果:日本における無作為化プラセボ対照試験https://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=167314
- ホタテ由来Plsの経口投与により中等度から重度 AD患者の認知機能を改善するhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=157679
- ホタテ由来プラズマローゲンの投与で、パーキンソン病の症状が改善するhttps://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=157676
- ホタテ由来プラズマローゲンの中等症・重症アルツハイマー病における行動・心理症状への効果https://www.pls.jp/entry_ronbun.php?eid=157670