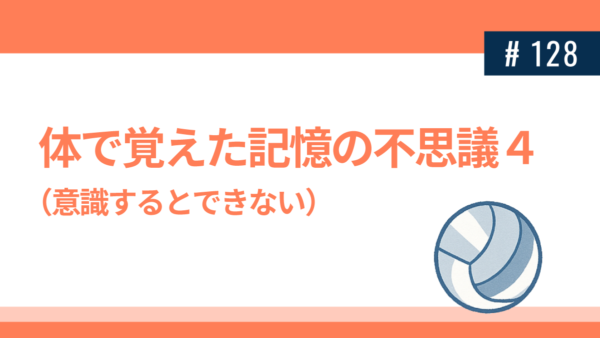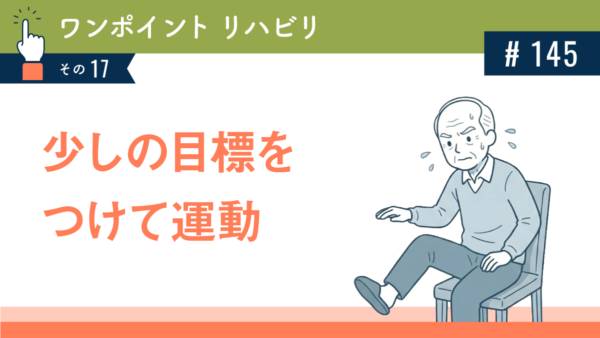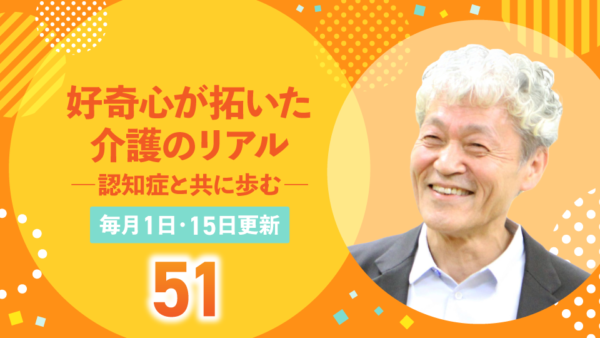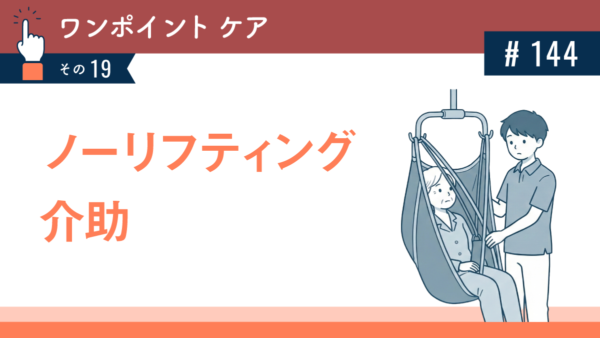意識するとできない
体で覚えることの究極は、その場面がくると無意識に体が動く(反応する)ようになることです。
スポーツがわかりやすいと思いますが、例えばバレーボールを始めたばかりの頃はルールやサーブの打ち方、レシーブやトスの構え、アタックを打つときのジャンプのタイミングなど、いろいろなことを意識して行います。動きもギクシャクとしたぎこちないものです。
しかし、2年、3年と競技を続けるうちに意識せずとも体の動きは滑らかになり、試合に参加するほどのプレイヤーに誰もが育っていきます。
しかし、イップス(動作障害)という言葉を耳にすることもありますが、無意識にやっていたことを、急に意識し始めるとかえって緊張してうまく動けなくなってしまうものです。
生活動作もスポーツと同じように、生活リズムの中で無意識に滑らかに行われているものです。その生活動作を介助する際に、急に動作の手順のようなものを意識させ過ぎてしまうと、動作をする本人は逆に動けなくなってしまうようなことも起こり得るということです。
有名な寓話の一つに、たくさんの足を上手に操っているムカデに対して、「そんなにたくさんの足でどうやって歩いているの?」とアリに聞かれた途端に、これまで動かしていたように足を動かせなくなってしまったというお話があります。
高齢者の生活動作のように一度しっかりとできるようになったことを、本人に対していちいち意識させるような声かけは控えた方が良いのかもしれません。むしろ、意識させないような声かけが重要で、ベッドから起き上がるのであれば、「起きませんか?」、立ち上がるのであれば、「立ってみませんか?」と単純なお誘いが有効だったりします。
つい、「ベッドの柵を掴んで、それを引っ張って」とか、「足に力入れて、お尻あげて」とか、ある動きに意識を集中させるような声かけをしてしまいがちです。病院や施設などで、介助が必要な高齢者は、動作を細かく指示され過ぎてイップスのような状態になってしまっていると考えてみたらいかがでしょう。そうすると介助する者の関わり方、声のかけ方、つまりその方への態度そのものが変わってくるはずです。
体で覚えた記憶はそう簡単に失いません。「さあ、どうぞ」と相手を信用する、安心させる態度がとても重要なのです。
ところで、イップスの治療にも安心感が有効なようです。