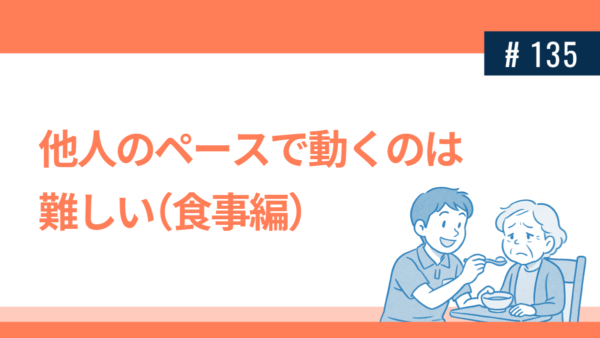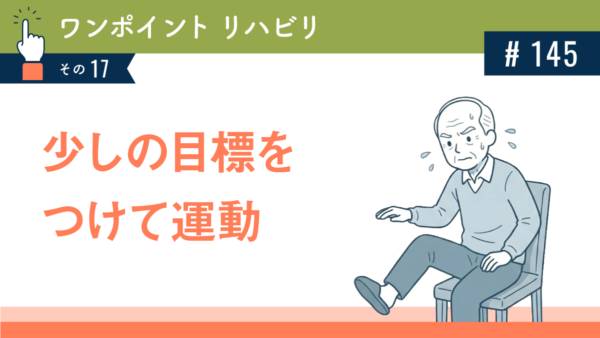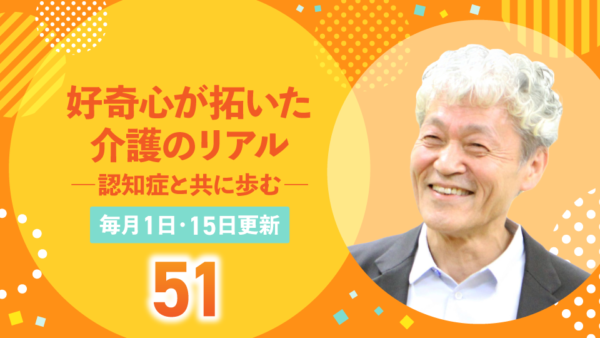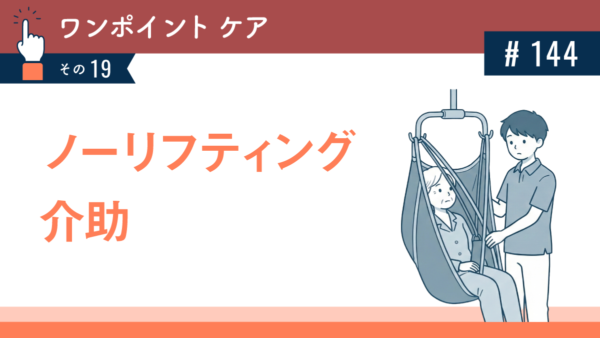突然ですが、大人になってから誰かの介助によって食事を食べさせてもらった経験はあるでしょうか?昭和の時代、結婚披露宴の定番であったウェディングケーキ入刀後に、新郎新婦が一口大にカットされたケーキをお互い食べさせ合うという微笑ましい光景が浮かぶ方もいるかもしれません。
そのような楽しい場面とは裏腹に、一回の食事を全て他者に介助される経験をしてみると、非常に食べにくいことが分かります。
食事は、食べ物を口に運ぶ一回量や咀嚼、飲み込みのタイミング、汁物やお茶など途中で水分を摂りながらといった、かなり複雑で、個別性の強い動作です。食事にかかる時間も、その時の食欲や食事環境(いつ、どこで、誰と、何を)によっても毎回異なります。
それを他者に委ねるという事態は、近づいてきた箸やスプーンから口に食べ物を取り込むだけでも労力を使いますし、咀嚼や飲み込みもそこそこに、次の一回量が、しかも自分の口に入れたい量ではなく運ばれてくると、一気に食欲さえも低下してしまいます。
食事に介助を必要とする高齢者などが、食欲の低下を訴えたり食事量が減ってしまうという事態も多くお見かけします。つい、体調など本人の変化に目を向けがちなところがあります。
しかし、目の前にどんなに豪勢で美味な食事が並んでいたとしても、他者に食べさせてもらわなければならないという状況下では、どうにも食欲は維持しにくいということも知っておく必要があると思います。
施設などで“あるある”のエピソードとして、普段は介助で食事も進まない高齢者が、行事食のお寿司にサッと手が伸び、パクッと口に入れ見事に飲み込みまでされていたというようなことがあります。
つまり、食事とは個人の食欲に導かれた一連の動作であり、咀嚼や飲み込みのタイミングも、あくまでその流れ中で自然発生しているものなのでしょう。スプーンを使い始めた子どもが、母親から食べさせられるのを嫌がり、とにかく自分で食べたがるようになるのも頷けます。
多くの高齢者施設では、たとえ食事に介助が必要になったとしても、本人の食欲を大切にし、嚥下のために刻んだ食事を見栄え良く再整形する、お膳全体が見えるよう椅子やテーブルを工夫するなど配慮がなされています。
本人のタイミングは本人にしか分からないからこそ、“食べたい”を大切にする努力が続けられています。