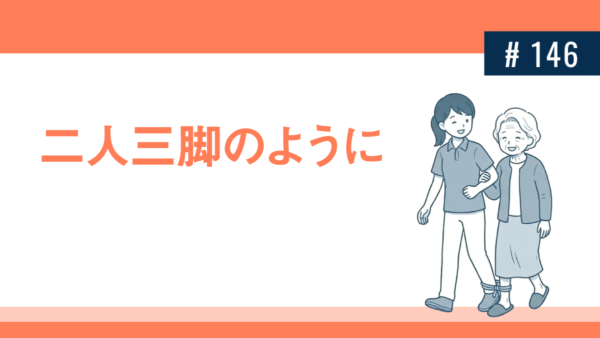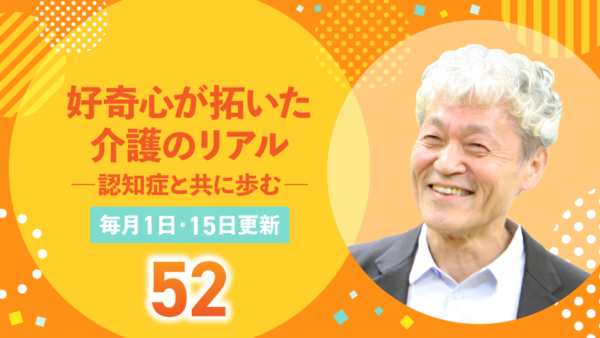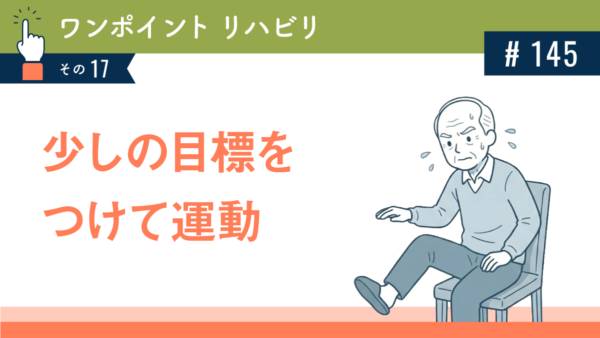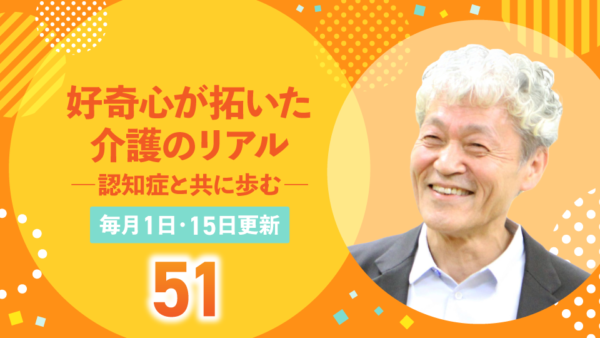2025年「注文をまちがえる料理店」始動
先に「番外編」にてご紹介いただきましたように、2017年に初めて開催した「注文をまちがえる料理店」から8年経った今年、9月20・21日に東京渋谷にある東急プラザ「ハラカドビル」5階にあるレストラン「FAMiRES(ファミレス)」で開催させていただくことになりました。
いま、クラウドファンディングで資金支援を呼びかけさせていただいていますので、ぜひ、ご覧いただき、お力添えをお願いしたいのと、皆様の仲間の方々に広めていただければ幸いです。
▼注文をまちがえる料理店が実現したい、全国みんなで「ま、いっかの日」(READYFOR)
https://readyfor.jp/projects/ORDERMISTAKES_2025
注文をまちがえる料理店につながった「ぎゃくたい」
介護保険制度施行直前の1999年に、東京都初の老人福祉法に基づく「痴呆対応型共同生活援助事業:通称 痴呆性高齢者グループホーム(以下 グループホーム)」が誕生し、僕が施設長を務めることになりました。
グループホームを開設するにあたりグループホームに関する書き物で読んだのは「法文」だけで、すでにグループホームに関することを書いた本は出ていたようですが全く関心をもつことなく自分のイメージで開設準備を進めましたが、
「グループホーム」はそれまでの入居型福祉施設である特別養護老人ホームでは成せなかったことができる仕組みであり、誰もがその仕組みを活かしてグループホームが誕生する前には行えなかった生活支援を展開することを目指していると思い込んでいました。
最もわかりやすいのは「食事」で、特別養護老人ホームでは「食事の提供」が運営基準上謳われているのに対してグループホームでは、そもそも謳っていません。
つまり、グループホームでの「食事」は「提供されるもの」ではなく、一般家庭と同じように「食ごと(食事)」を、食べる当事者自身が携われる仕組み(自炊ができる)になっています。
特別養護老人ホームでは、献立を決めることから盛り付けまで「食ごと」の一切について施設側が動く仕組みになっていますので、
そもそも日常的に食べるものに本人の意思を反映できませんし、意思を反映することは「出されたものを食べるか食べないか」でしかありません。
僕の実践例で言えば「パンとご飯がありますがどちらにしますか」「卵がありますが、卵焼きか目玉焼きかスクランブルのどれがいいですか」「おかずは、肉料理がいいですか、魚料理がいいですか、野菜ものがいいですか、どんぶりにしますか」と個々の意思を確認したうえで、
買物から調理・盛り付けまで入居者自身が行えるように、特別なことではなく日常のこととして支援していました。
又、「お昼ご飯は何にしますか、今日は食べに行きましょうか。何を食べに行きますか」「夕食は出前をとりましょうか。何をとりますか」と選択肢を示して入居者個々人が決められるように支援していましたので、寿司の人もいれば、麺の人もいれば、中華の人もいるわけです。
もちろん、皆さんが同じものを食べることもありましたが、それも入居者の意思表示の結果でした。
こうしたことを可能にしたのがグループホームという生活支援の仕組みであり、入居者自身の意思や能力を活かせる仕組みになっているので「脳と身体」をたっぷり使っていただけるのですから、誰もがそれを活かした生活支援を行っているものだと思い込んでいたわけです。
これは「食事」に限った話ではなく、生きていくために必要なことの全てにおいて「入居者自身が行えるように支援する」ことができる画期的な仕組みであり、
「自分のことが自分でできるように支援する」「入居者同士が互いに助け合えるように支援する」「地域社会生活ができるように支援する」のは誰もが目指しているものだと思い込んでいましたが、
グループホームに携わる人たちと出会うたびに「そうじゃない」ことがわかり、僕の考えていることや実践していることが世間とズレていることに気づかされます。
特に印象的だったのは、僕らの実践をメディアの皆さんが取り上げてくださり、テレビでも紹介されたのですが、
当時は「痴呆症の人に何を食べたいかを聞く、買物をさせる、調理をさせる、掃除をさせる、洗濯をさせる、玄関に鍵をかけない。和田のやっていることは虐待だ」と同業者がバッシングしていることを耳にしたことでした。
巷では「虐待のカリスマ」なんて言われていたようですが、
それでも僕の言っていること、やっていることを応援してくれる学者・研究者など有識者といわれる方々やメディアの方々、そして2003年に出版させていただいた「大逆転の痴呆ケア(中央法規出版 廃刊)」を読んでくださり僕の話を直接聞いてくださる方々に恵まれ、
2012年NHK「プロフェッショナル~仕事の流儀~」という番組で実践が取り上げられることになりました。
その番組を担当したディレクターと一緒に「注文をまちがえる料理店」を開催することになったわけですから、注文をまちがえる料理店誕生の引き金は「ぎゃくたい」だということです。
注文をまちがえるお好み焼き屋
僕が住まうところからクルマで5分くらいのところに、昔ながらの民家でやっているお好み焼き屋がありました。
僕はもともと旧い物が好きなので古民家は大好物。
しかも関西育ちの僕にとってお好み焼きも大好物。
大好物の二乗ですから気になって仕方がないお店でした。
すでにブログで紹介しているかもしれませんね。
なかなか行けなかったのですが、ついに念願かなって連れ合いと二人で食べに行きました。
ガラガラ戸を開けて中に入ると土間(家の内部なのに土を叩いているだけの床)で、ひと間に鉄板焼きの台がありお店の方が焼いているところが丸見えのつくりで、古びたテーブルが3つか4つ置かれていました。
おひとりお客様が来て食べていらっしゃいました。
老夫婦二人(以下 ママとマスター)でやっているお店で、ママが鉄板の前に立っていて、僕らが着席するとマスターがお水をもって注文をとりにきてくれ、お好み焼きを2枚注文しました。
注文を受けたマスターがママに「豚玉1枚とイカ玉1枚(記憶が曖昧で正確ではない)」と告げました。
通常なら、あとは焼きあがったお好み焼きを待つのみなのですが、焼き始めた直後に何と!「お客さん、なんだっけ」とママが僕らに聞いてきたんです。
すでに焼き始めていたのですが、ここでピンときた僕は「豚玉とイカ玉です」とお答えすると「ハイよ」と答えてくれ、焼き進められましたが、この先どんなことが起こるのか気になって仕方がありません。
しばらくすると再びママが「お客さん、なんだっけ」と聞かれたので「豚玉とイカ玉です」と答えましたが、またしばらくして「お客さん、なんだっけ」と聞かれ、これまた普通に「豚玉とイカ玉です」と、この道を歩いている者としてきちんと答えさせていただきました。
先に入っていたお客様は食べながら下を向いて笑っていましたが、イヤな感じではなく「受け止め笑い」って感じでしたネ。
すると更に「お客さん、なんだっけ」と聞かれたのですが、今度はすかさずマスターが「豚玉とイカ玉って言ってるだろ。何度聞くんだ」とお怒りの言葉を発せられました。
僕はここで不覚にも笑ってしまいました。
マスターの一喝が効いたかのように、その後は聞かれませんでしたが、次のステージが待っていました。
食べ終わり、「マスターご馳走様、おいくらですか?」って聞くと「〇〇〇円です」と告げられました。
告げられた金額は「一桁不足している」ことがすぐさまわかりましたので、さすがにそれを受け止めるわけにはいかず「マスター、それでは大損こいてお店つぶれるよ。僕の計算では〇〇〇〇円ですが」とやり返しました。
マスターはバツ悪そうに「すいませんねェ」と苦笑いされたので「食い逃げになる所でしたよ」と言って皆でひと笑いして僕らはお店を出ました。
とても愉しいひとときを過ごさせていただけたと今でも思っていますが、その後、すぐに「お休み」の札がかけられ、一度再営業されましたが、すぐに「閉店」の札に変わってしまいました。
きっと「注文したお好み焼きとは違うものを出されたお客さんがいるんだろうな」と思えるお好み焼き屋でしたが、
下を向いて笑っていた常連さんだろうなと思えたお客さんを思い浮かべると、それでトラブルになることはなく、「だからギリギリまで営業することができたんだろうな」と思い、とっても豊かな気持ちになれましたし「又来たい」って素直に思えましたし、
常連さんや一見でも僕のように思えるお客さんが多数であれば、このお店も閉店にならなかったかもしれないと「閉店」の立て看板を見て思いました。
選択できる社会
2017年に開催した注文をまちがえる料理店の後にテレビ番組で認知症という状態にある方々とご一緒することがあり、司会の方が注文をまちがえる料理店に触れ、その方々に「こういうお店、どうでしょうか」と質問されるシーンになりました。
Aさんは「嫌だね、行きたくない」、Bさんもどちらかというと否定的、Cさんはどちらかというと否定的ではない意見を述べられ、
司会の方が僕に「皆さんの声を聞いて、どう思われますか」と投げてきたので、
「このネーミングのお店で働きたいか働きたくないかは個々の判断で、それって世間一般に普通のことですが、かつてはその選択肢さえなかったんですよね」といったようなことを言いました(記憶が曖昧で正確ではない)。
僕が認知症という状態にある方と初めてお会いした30年前(当時)は、あらゆることに選択肢がなく「選択権」がかなり侵害されていましたが、
今や「意思が反映された暮らしへの支援」は珍しいことではなく、入居系介護保険事業所に入居している方々が、自身の選択に基づいて雇用契約に基づく労働者として就労することが可能な時代へと様変わりしてきました。
一般社団法人注文をまちがえる料理店を法人化する前の「2017年開催の注文をまちがえる料理店」では接客係を担っていただいた認知症という状態にある方々に「謝礼金」でしか働いていただいたことへの対価を支払えなかったのが、
法人格をもつことで「2019年開催の注文をまちがえる料理店at厚労省」では雇用契約に基づく「労働の対価としての賃金」を支給できるようになり、それを実感しました。
今、この国のベクトルは「認知症とともに生きる社会づくり」に向いていると言っても過言ではないと思いますし、
今後一気に高齢社会を迎える諸国にエールを送り続ける国であるために「注文をまちがえる料理店なんて謳わなくても良い社会」のあり様を目指して、僕自身は今「2025年注文をまちがえる料理店」に取り組んでいます。
まだ、お席は空いているようですから、ご支援をよろしくお願いいたします。
追伸
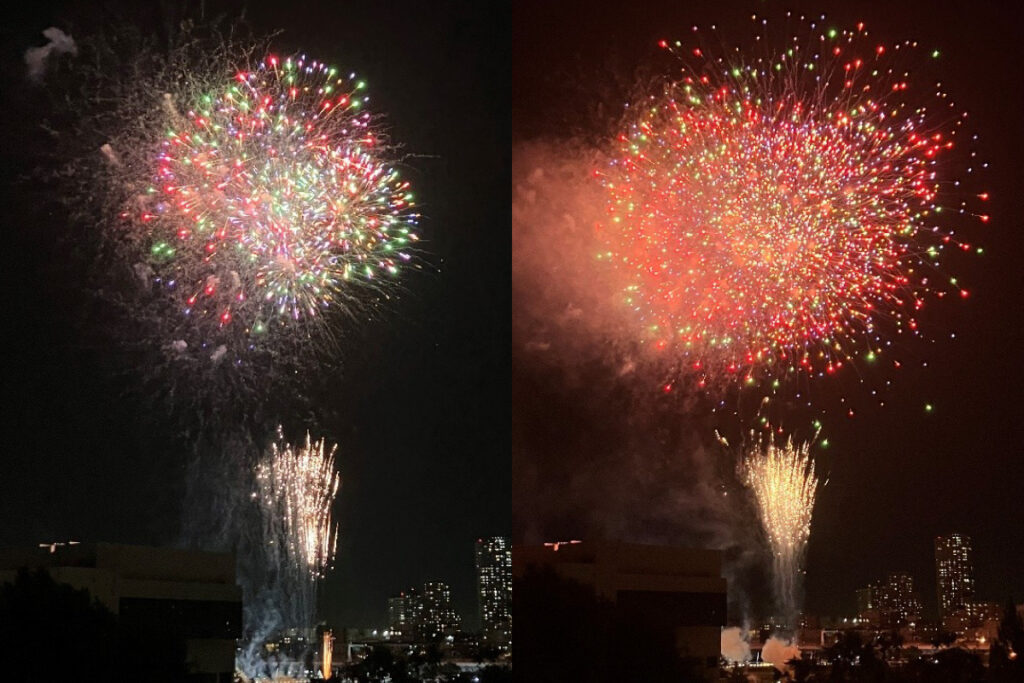
先日、隅田川の花火大会が開催されました。
普段は空いている浅草界隈の喫茶店も昼間から大忙しの賑わいでした。
僕が所属する法人が運営する複合施設は、花火の打ち上げ場の真ん前に位置しているので、花火大会の日の屋上は入居者やその家族、グループ法人の関係者、ボランティア、スタッフであふれかえります。
僕は久しぶりに参加させていただきましたが、前日ギックリ腰になってしまい準備に全くお役に立てない「目障りなヤツ状態」で情けない限りでしたが、ありがたいことに皆さんと一緒にステキな花火たちを見させていただきました。
この日は、グループホーム入居者2名の方とご家族に9月に開催する注文をまちがえる料理店で接客係として働いていただけないかリクルート活動を行いましたが、
おひとりの方が「メイドの土産にお引き受けするわ」と言われたことと、もうひとりの方が「やったことないから不安だわ」と言われていたこと、つまり自身の気持ちを率直に伝えてくださったことや、
いつも一緒にいる職員が「私もいるから」と言った時に「だったら」と答えられたことがとても印象に残りましたし、
ご家族が「僕も手伝わせてよ」と言ってくださったことに「共に人として生きることを支援する仲間感」をもてて嬉しく思いました。








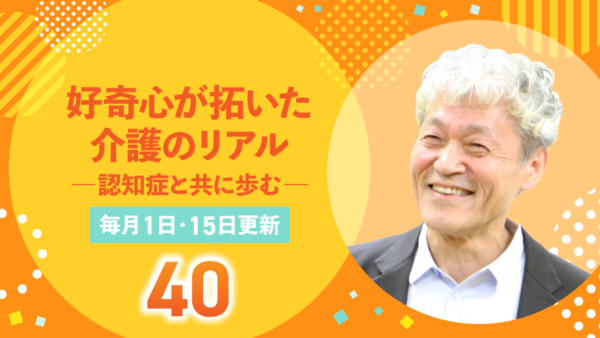




.webp)