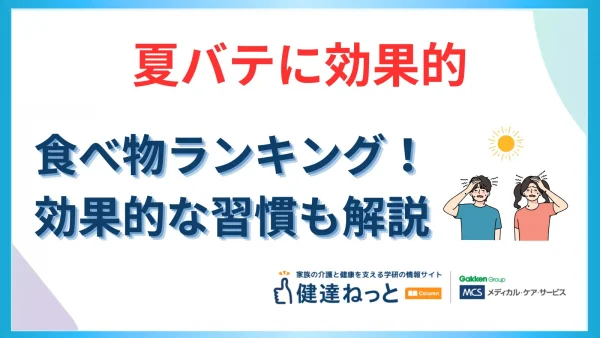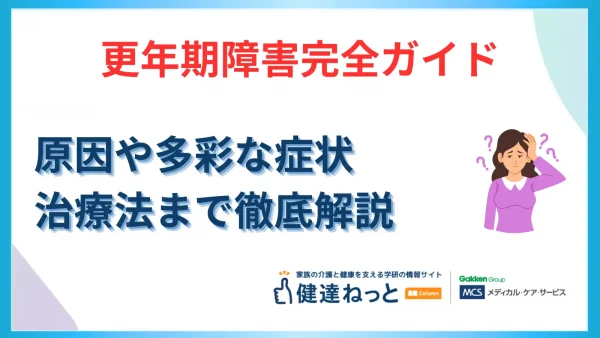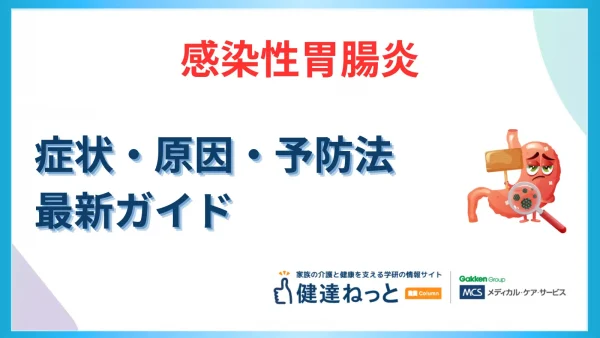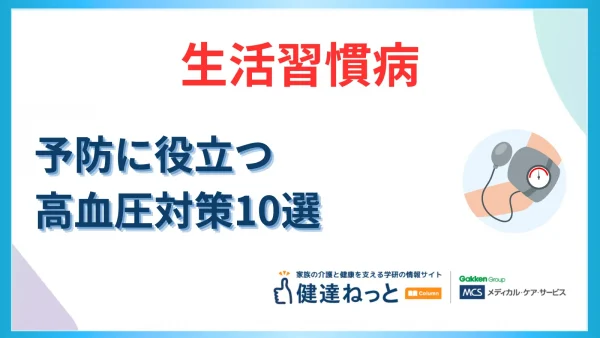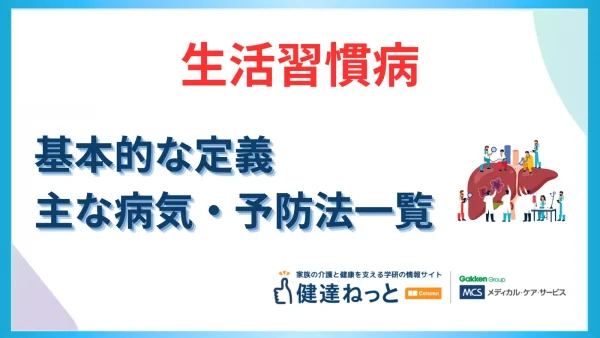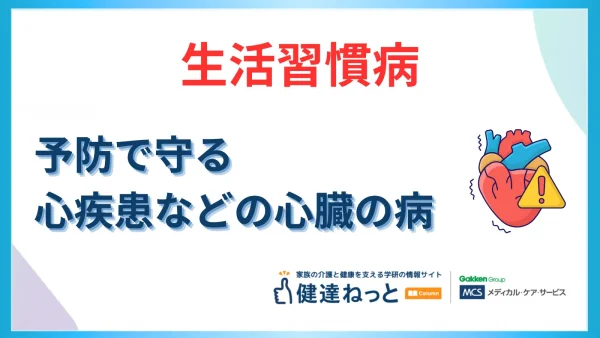夏の厳しい暑さで、下記のようなお悩みはありませんか。
- なんとなく体がだるくて、何もやる気が起きない
- 食欲がなくて、そうめんばかり食べてしまう
- 夜しっかり寝たつもりでも、朝から疲れがとれない
- このまま体調不良が続いたらどうしようと不安になる
その辛い症状、もしかしたら夏バテかもしれません。
夏バテは、高温多湿な環境によって自律神経が乱れ、体内の水分や栄養素が不足することで起こる体の不調です。
放置すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、熱中症などの深刻な事態につながる可能性もあります。
この記事では、介護・医療の現場知見を持つ「健達ねっと」が、科学的根拠に基づいた夏バテ対策を徹底解説します。
- 夏バテに本当に効く食べ物をランキング形式で紹介
- ランキングの根拠となる栄養素の働きを分かりやすく解説
- 食欲がない時でも作れる、火を使わない簡単レシピ
- 食べ物以外で夏バテを予防・改善する生活習慣
この記事を読めば、あなたの症状や状況に合わせた最適な対処法が具体的に分かります。
バランスのよい食事と正しい生活習慣で、辛い夏の不調を乗り切り、毎日を元気に過ごしましょう。
スポンサーリンク
【結論】夏バテに効く食べ物ランキングTOP20
夏バテ対策で何を食べればよいか、結論からお伝えします。
介護・医療の現場での栄養管理の視点と、科学的根拠を元に評価した「夏バテに効く食べ物ランキング」です。
毎日の食事に上手に取り入れて、夏を元気に乗り切りましょう。
1位.豚肉(もも・ヒレ)
夏バテ対策の王様ともいえるのが豚肉です。
豚肉には、糖質をエネルギーに変える働きを持つ「ビタミンB1」が食品の中でもトップクラスに含まれています。
夏はそうめんなど糖質中心の食事になりがちですが、ビタミンB1が不足するとエネルギーがうまく作れず、疲れやすくなってしまいます。
また、たんぱく質も豊富で、低下しがちな体力の維持に役立つのです。
ただし、「夏バテに豚肉・ビタミンB1が効く」ことについて、明確な科学的根拠はまだ十分に確立されていないのが現状です。
とはいえ、脂身の少ないもも肉やヒレ肉を選び、冷しゃぶなどでさっぱりといただくことをオススメします。
ビタミンB1は健康を意識する方にとっては、欠かせない栄養素の1つです。では、ビタミンB1はどんな食べ物に多く含まれているのでしょうか。本記事では、ビタミンB1について、以下の点を中心にご紹介します。 ビタミンB1とは[…]
2位.うなぎ
古くから滋養強壮の食材として知られるうなぎも、夏バテ対策には欠かせません。
ビタミンB1はもちろんのこと、皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA、抗酸化作用のあるビタミンEなど、夏を乗り切るための栄養素がバランスよく含まれています。
特に、食欲がない時でも少量で効率よく栄養を補給できるのがうなぎの魅力です。
介護の現場でも、少量で高栄養の食事を提供することは、食が細くなった方の低栄養を防ぐために非常に重要です。
ご飯と一緒に食べることで、エネルギー源となる糖質も同時に補給できます。
うなぎは滋養強壮によいといわれてきました。疲労回復に効果があるといわれ、夏バテ予防によく食べられています。うなぎにはどのような栄養が含まれるのでしょうか?また、うなぎにはどのような効果・効能が期待できるのでしょうか?本記事では、[…]
3位.梅干し
梅干しに含まれる「クエン酸」は、夏バテで疲れた体に嬉しい成分です。
クエン酸については疲労回復に関する研究がありますが、現時点では十分な科学的根拠が確立されているとは言い切れません。
しかし、体内でエネルギーを生み出すサイクルに関与することが知られています。
さらに、その酸味は唾液や胃液の分泌を促し、低下しがちな食欲を増進させる効果も期待できます。
ご飯に一粒添えるだけでなく、和え物やドレッシングに活用するのもよいでしょう。
ただし、塩分が多いため、食べ過ぎには注意が必要です。
1日1〜2粒を目安に食事に取り入れましょう。
梅干しは日本の家庭料理に欠かせない存在です。その酸っぱさが苦手な人もいれば、炎暑の夏には格別な美味しさを感じる人もいます。しかし、梅干しはただの食べ物ではなく、その効果・効能が注目を集めています。では、梅干しの効果とは具体的[…]
4位.鶏むね肉
鶏むね肉には、「イミダゾールペプチド」という成分が豊富に含まれています。
この成分は、渡り鳥が数千キロも飛び続けられる力の源ともいわれ、優れた抗酸化作用と疲労回復効果があることで注目されています。
高たんぱく質でありながら脂質が少なく、消化にもやさしいのが特徴です。
コンビニエンスストアで手軽に手に入るサラダチキンを活用すれば、調理の手間なく食事に取り入れられます。
介護現場の食事でも、食べやすく消化のよいたんぱく源として、鶏肉は頻繁に活用されています。
5位.枝豆
夏が旬の枝豆は、「畑の肉」といわれる大豆の未熟な豆で、栄養価が非常に高い食材です。
夏バテ対策に重要なビタミンB1、汗で失われやすいカリウム、そして体を作る基礎となるたんぱく質を同時に補給できます。
冷凍のものを常備しておけば、流水解凍や電子レンジで加熱するだけで手軽に食べられるのも嬉しいポイントです。
おつまみとしてだけでなく、ご飯に混ぜ込んだり、サラダのトッピングにしたりと、幅広く活用できます。
弁当のおかずからお酒のつまみまで枝豆は様々な場面で摂取されています。昔から大豆や枝豆は畑の肉といわれタンパク質が豊富なことで有名です。しかし、タンパク質以外にどのような栄養素が含まれているかあまり知られていません。枝豆に含まれる栄養[…]
6位.トマト
トマトの鮮やかな赤色は「リコピン」という色素成分によるもので、強力な抗酸化作用を持ち、紫外線など夏のダメージから体を守ってくれます。
また、汗と共に失われやすいカリウムや水分も豊富に含んでおり、体の熱を冷ます効果も期待できるのです。
介護施設では、夏場のメニューにトマトなどの夏野菜を積極的に取り入れ、食事から自然に水分やミネラルを補給できるよう工夫しています。
生でそのまま食べられる手軽さに加え、加熱するとリコピンの吸収率がアップするため、スープや煮込み料理にするのもオススメです。
7位.卵
卵は、ビタミンCと食物繊維以外のほぼ全ての栄養素を含む「完全栄養食品」です。
良質なたんぱく質源であることはもちろん、ビタミンB群も豊富で、エネルギー代謝を助けてくれます。
どのような調理法でも栄養価が損なわれにくく、安価で手に入りやすいのも大きなメリットです。
食欲がない時は、温泉卵や茶碗蒸しなど、喉ごしのよい調理法を選ぶと食べやすくなります。
たんぱく質摂取を目指す上で、卵は毎日でも取り入れたい優れた食材のひとつといえます。
8位.納豆
納豆もまた、夏バテ対策に非常に優れた日本の伝統的な発酵食品です。
ビタミンB群が豊富でエネルギー代謝をサポートするほか、良質なたんぱく質、ミネラル、食物繊維もバランスよく含んでいます。
発酵食品であるため消化吸収がよく、夏バテで弱った胃腸にやさしいのも特徴です。
ネバネバ成分は食欲をそそり、喉を通りやすいので、食欲がない時でも比較的食べやすいでしょう。
薬味をたっぷり加えたり、卵やオクラと混ぜたりすることで、さらに栄養価を高められます。
9位.豆腐
豆腐は、食欲が全くない時の救世主ともいえる食材です。
消化吸収が非常によく、胃腸に負担をかけずに良質なたんぱく質を補給できます。
体を構成するたんぱく質が不足すると、体力だけでなく免疫力も低下してしまうため、夏バテ時には特に意識して摂りたい栄養素です。
冷奴として手軽に食べられるのはもちろん、温かい味噌汁の具にしたり、あんかけにしたりすれば、冷たいものの摂りすぎで冷えた内臓を温めることもできます。
介護食としても、その食べやすさと栄養価の高さから、豆腐は頻繁に活用されています。
10位.かつお・まぐろ(赤身)
かつおやまぐろの赤身には、貧血予防に役立つ「鉄分」が豊富に含まれています。
夏は汗をかくことで鉄分も失われやすく、不足すると酸素が全身に行き渡りにくくなり、だるさやめまいの原因となるのです。
また、良質なたんぱく質も豊富で、体力の維持・回復を助けます。
刺身やたたき、ヅケ丼など、火を使わずに調理できるメニューが多いのも夏場には嬉しいポイントです。
食欲がない時でも、香味野菜と一緒にさっぱりといただけます。
11位.しじみ・あさり
しじみやあさりなどの貝類には、「タウリン」という栄養素が豊富に含まれています。
タウリンは、肝臓の働きを助け、疲労回復をサポートする効果が期待できる成分です。
また、鉄や亜鉛などのミネラルも豊富に含んでいます。
これらの貝類を味噌汁やスープにすることで、溶け出した栄養素を余すことなく摂取できるだけでなく、水分と塩分(電解質)も同時に補給できます。
まさに「飲む点滴」ともいえる、夏バテに最適な一品です。
12位.バナナ
バナナは、汗で失われやすいカリウムを手軽に補給できる優れた果物です。
カリウムは体内の水分バランスを調整する重要なミネラルで、不足すると夏バテの症状であるだるさやむくみを引き起こしやすくなります。
また、エネルギーに変換されやすい糖質も含まれているため、朝食や運動前のエネルギー補給に最適です。
皮をむくだけで食べられる手軽さは、食欲がなく調理する気力もない時に非常に助かります。
13位.オクラ
オクラのネバネバ成分は「ペクチン」や「ムチン」といった水溶性食物繊維で、弱った胃の粘膜を保護し、消化を助ける働きがあります。
また、たんぱく質の吸収を助ける効果も期待できます。
カリウムやβ-カロテンなどの栄養素も含まれており、夏バテ対策にぴったりの夏野菜です。
さっと茹でて和え物にするほか、刻んで豆腐や納豆と混ぜることで、喉ごしがよくなり、食欲がない時でもつるりと食べられます。
14位.きゅうり
きゅうりはその約95%が水分で構成されており、食べるだけで水分補給ができる野菜です。
体内にこもった熱を冷ます効果があり、火照った体を内側からクールダウンしてくれます。
また、カリウムも豊富に含んでいるため、利尿作用によって体内の余分な塩分や水分を排出し、むくみの解消にも役立ちます。
味噌や塩を少しつけて食べることで、汗で失われた塩分も同時に補給することが可能です。
15位.味噌汁
味噌汁は、日本の伝統的なスープであり、夏バテ対策に非常に有効です。
水分と、汗で失われるナトリウムなどの電解質(塩分)を同時に補給できます。
特に、温かい味噌汁は冷房や冷たい飲み物で冷えた内臓を温め、胃腸の働きを活発にしてくれます。
具材に豆腐やわかめ、夏野菜などを加えることで、たんぱく質やミネラル、ビタミンも一緒に摂ることが可能です。
インスタントのものを活用すれば、手軽に毎日の食事に取り入れられます。
16位.レバー
レバーは「栄養の宝庫」といわれるほど栄養価が高く、特に貧血予防に効果的な鉄分や、エネルギー代謝を助けるビタミンB群が豊富です。
夏バテによるだるさや倦怠感が、鉄分不足による隠れ貧血であるケースも少なくありません。
ただし、独特の風味があり、調理に少し手間がかかる点がデメリットといえます。
ニラやにんにくと一緒に炒める「レバニラ炒め」は、ビタミンB1の吸収を高めるアリシンも一緒に摂れるため、夏バテ対策には最適な組み合わせです。
17位.ヨーグルト
ヨーグルトなどの発酵食品は、腸内環境を整える働きがあります。
夏の暑さや冷たいものの摂りすぎで腸の働きが弱まると、栄養の吸収が悪くなったり、免疫力が低下したりして夏バテを悪化させることがあります。
ヨーグルトは、弱った胃腸にやさしく、良質なたんぱく質やカルシウムも補給することが可能です。
食欲がない時のデザートや朝食に、フルーツやはちみつを加えて食べるのがオススメです。
18位.にんにく・ショウガ
にんにくやショウガなどの香味野菜は、夏バテ対策の強力なサポーターです。
にんにくに含まれる「アリシン」は、豚肉などに豊富なビタミンB1の吸収を高め、その効果を持続させる働きがあります。
また、ショウガには血行を促進し、冷えた内臓を温めたり、食欲を増進させたりする効果が期待できます。
料理のアクセントとして少量加えるだけで、夏バテ撃退の効果を高めてくれるのです。
19位.スイカ
スイカは、きゅうりと同様にそのほとんどが水分で構成されており、カリウムも豊富なため、水分とミネラルの補給に最適な夏の果物です。
赤い果肉には、トマトと同じく抗酸化作用の強いリコピンも含まれています。
体を冷やす効果があるため、暑い日のデザートにぴったりです。
塩を少し振って食べることで、汗で失われた塩分も補給でき、甘みが引き立つのでオススメです。
ただし、体を冷やす作用が強いので、一度に食べすぎないようにしましょう。
20位.そば
夏に食べたくなる麺類の中でも、そばは夏バテ対策にオススメです。
そうめんやうどんと比べて、ビタミンB1やB2、たんぱく質、食物繊維などが豊富に含まれています。
特に、そばに含まれる「ルチン」という成分には、毛細血管を強くする働きがあるとされています。
豚肉やネギ、大根おろしなどをトッピングすることで、さらに栄養バランスがアップするでしょう。
スポンサーリンク
ランキングの秘密!夏バテ撃退に必須の「5大栄養素」
ランキング上位の食品には、夏バテ撃退に効果的な栄養素が共通して含まれています。
これらの栄養素の働きを理解することで、日々の食事をより効果的に組み立てられます。
特に「食べ合わせ」による相乗効果を意識するのがポイントです。
【エネルギーチャージの鍵】ビタミンB1
ビタミンB1は、食事で摂った糖質をエネルギーに変える際に不可欠な栄養素です。
これが不足すると、ご飯やパンを食べてもエネルギーがうまく作れず、体がだるい、疲れやすいといった夏バテ特有の症状が現れます。
以下の食品に豊富に含まれています。
- 豚肉
- うなぎ
- 枝豆
- 納豆
ビタミンB1は水に溶けやすく、熱に弱い性質があるため、調理法にも工夫が必要です。
茹でるよりも蒸したり、炒めたりする方が効率よく摂取できます。
【疲労回復の促進剤】クエン酸
クエン酸は、レモンや梅干しなどに含まれる酸味成分です。
疲労回復に関する研究はありますが、現時点では十分な科学的根拠が確立されているとは言い切れません。
ただし、体内でエネルギーを生み出すサイクルに関与することが知られています。
クエン酸を多く含む食品は以下の通りです。
- 梅干し
- レモン
- お酢
- 柑橘類
また、クエン酸の酸味は唾液や胃液の分泌を促すため、夏バテによる食欲不振の改善にも役立ちます。
【体内の水分調整役】カリウム
カリウムは、私たちの体にとって必須のミネラルです。
汗をかくと水分と一緒に失われやすく、不足すると脱力感や食欲不振、筋肉のけいれんなどを引き起こすことがあります。
カリウムは、体内のナトリウムとバランスを取りながら、細胞の水分量や血圧を正常に保つ重要な役割を担っています。
- トマト
- きゅうり
- スイカ
- バナナ
- 枝豆
これらの夏野菜や果物から、こまめに補給することを心がけましょう。
体の中には様々な栄養分があり、カリウムもその1つです。カリウムは普段の食事から十分に摂取が可能なため、不足や過剰摂取になることは少ないとされています。では、カリウムが不足したり過剰摂取になるとどのような症状が見られるのでしょうか?本[…]
【体づくりの基礎】たんぱく質
たんぱく質は、筋肉や血液、免疫細胞など、私たちの体を作るための最も基本的な材料です。
夏バテで体力が消耗している時こそ、その修復と維持のために十分なたんぱく質が必要になります。
たんぱく質が不足すると、体力が落ちるだけでなく、免疫力も低下して夏風邪などをひきやすくなります。
- 豚肉、鶏むね肉、うなぎ
- 卵
- 豆腐、納豆
厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)では、高齢者(65歳以上)のたんぱく質推奨量は男性60g/日、女性50g/日とされています。
一方、介護現場では、フレイル予防や筋量維持の観点から、MCSケアモデルなど一部の取り組みで1日約80gのたんぱく質摂取を目標とする場合があります。
【効果を倍増させる名脇役】アリシンなど
栄養は、ただ摂るだけでなく、その吸収率や働きを高める「組み合わせ」が重要です。
特に注目したいのが、にんにくや玉ねぎなどに含まれる「アリシン」という成分です。
アリシンは、エネルギーチャージの鍵であるビタミンB1と結びつくことで、その吸収を高め、効果を長く持続させる働きがあります。
これが、「豚肉の生姜焼き」や「レバニラ炒め」が夏バテによいといわれる理由です。
- にんにく
- 玉ねぎ
- ニラ
- ショウガ、ミョウガなどの香味野菜
これらの食材を上手に組み合わせることで、食事による夏バテ対策の効果をさらに高めることが可能です。
年々猛暑日が増える日本の夏は、体調を崩しやすい季節といえます。身体がだるく食欲が出ないなどの症状は、誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。では、夏バテ症状とは上記のほかにどのようなものがあるのでしょうか?夏バテを予防するための方法[…]
【症状別】あなたの夏バテに効く「即決ご飯」はコレ!
夏バテの症状は人それぞれです。
今のあなたの辛い症状に合わせて、最適な食事を選ぶことが回復への近道です。
ここでは、具体的な症状別に「これを食べればOK」という即決ご飯を提案します。
食欲が全くない時
- 提案: きゅうりとトマトの酢の物、喉ごしのよいネバネバ食材(オクラ、長芋)と豆腐の和え物
- 理由: 酢の物に含まれるクエン酸が食欲を刺激し、さっぱりとした味わいで食べやすいです。また、ネバネバ食材は胃の粘膜を保護し、喉を通りやすいため、固形物を食べるのが辛い時にオススメです。
体が重く、だるさが抜けない時
- 提案: 豚しゃぶと玉ねぎのサラダ(お酢のソースで)、鶏むね肉のレンジ蒸し
- 理由: ビタミンB1が豊富な豚肉と、その吸収を助けるアリシンを含む玉ねぎの組み合わせは、エネルギー産生を強力にサポートします。疲労回復効果のある鶏むね肉も効果的です。
動く気力が出ないほどの倦怠感
- 提案: 温かいトマトスープ、サバ缶を使った味噌汁
- 理由: 冷たいものの摂りすぎで疲れた胃腸を温め、内側から機能を高めます。トマトのリコピンやサバ缶の良質なたんぱく質と脂質が、消耗した体力を補ってくれます。
夏バテの食欲不振について夏バテで体がだるくなったり、食欲不振になったりする方もいるのではないでしょうか。食欲不振になってしまうと体力が回復するのに時間がかかってしまいます。では、夏バテの食欲不振になる原因にはどのようなこ[…]
食欲がなくても食べやすい!夏バテに効く簡単レシピ
暑い中でキッチンに立って料理をするのは大変です。
ここでは、火を使わなかったり、電子レンジで完結したりする、本当に簡単でおいしい夏バテ回復レシピを5つご紹介します。
(参考:手軽で簡単な夏バテレシピ)
豚しゃぶネギ塩だれ
ビタミンB1豊富な豚肉を、食欲そそるネギ塩だれでいただく一品です。
電子レンジで加熱するので、火を使わず手軽に作れます。
材料(1人分)
- 豚肉(しゃぶしゃぶ用):100g
- 長ネギ:1/4本
- A ごま油:大さじ1
- A 鶏がらスープの素:小さじ1/2
- A レモン汁:小さじ1
- A 塩、こしょう:少々
作り方
- 長ネギはみじん切りにし、Aの調味料と混ぜ合わせる。
- 耐熱皿に豚肉を広げ、ふんわりとラップをして電子レンジ(600W)で2分ほど加熱する。
- 豚肉の火が通ったら、1のタレをかけて完成。
ネバネバ豆腐丼
喉ごしがよく、食欲がない時でもつるりと食べられます。
オクラや納豆のネバネバ成分が胃腸をやさしく保護します。
材料(1人分)
- 豆腐:1/4丁
- 納豆:1パック
- オクラ:2本
- 卵黄:1個
- めんつゆ:適量
- ご飯:1杯分
作り方
- オクラは塩で板ずりし、さっと茹でて小口切りにする。
- 納豆は付属のたれと混ぜておく。
- ご飯の上に豆腐を乗せ、納豆、オクラ、卵黄をトッピングし、めんつゆをかける。
サラダチキンの梅わさび和え
コンビニのサラダチキンを使った、和えるだけの超簡単レシピです。
梅干しのクエン酸とわさびの香りが食欲を刺激します。
材料(1人分)
- サラダチキン:1/2個
- 梅干し:1個
- きゅうり:1/4本
- A わさび(チューブ):少々
- A 醤油:少々
- A 大葉:2枚(あれば)
作り方
- サラダチキンは手でほぐし、きゅうりは千切り、大葉も千切りにする。
- 梅干しは種を取って包丁でたたく。
- 全ての材料とAの調味料をボウルで和える。
豚バラとナスのさっぱりポン酢蒸し
電子レンジだけで作れる、温かくてさっぱりした一品です。
油を使わないのでヘルシーで、弱った胃腸にもやさしいです。
材料(1人分)
- 豚バラ肉:80g
- ナス:1/2本
- A ポン酢:大さじ2
- A ごま油:小さじ1
- A 大葉やミョウガなど(お好みで)
作り方
- ナスは薄切りにし、水にさらしてアクを抜く。
- 耐熱皿に水気を切ったナスと豚バラ肉を交互に並べる。
- ふんわりとラップをして電子レンジ(600W)で4〜5分加熱する。
- Aを混ぜ合わせたタレをかけ、お好みで薬味を添える。
サバ缶とトマトの夏野菜カレー
スパイスが食欲を増進させるカレーも、夏バテにはオススメです。
サバ缶とトマト缶を使えば、煮込む手間なく手軽に作れます。
材料(1〜2人分)
- サバ水煮缶:1缶
- カットトマト缶:1/2缶
- 玉ねぎ:1/4個
- カレールー:1〜2片
- 水:100ml
- オリーブオイル:少々
作り方
- 玉ねぎは薄切りにする。
- 鍋にオリーブオイルを熱し、玉ねぎを炒める。
- 玉ねぎがしんなりしたら、サバ缶(汁ごと)、トマト缶、水を加えて煮立たせる。
- 火を止めてカレールーを溶かし、再び弱火でとろみがつくまで煮る。
簡単に作れるレシピは、学研グループのMCSが出版している、以下の書籍もぜひチェックしてみてください。
夏バテに悪影響を及ぼすNGな食べ物と習慣
夏バテを早く改善するためには、体によいものを取り入れるだけでなく、悪影響を及ぼすものを避けることも同じくらい重要です。
知らず知らずのうちに夏バテを悪化させていないか、チェックしてみましょう。
冷たいものの摂りすぎ
暑いとつい、アイスやかき氷、冷たいジュースなどを摂りすぎてしまいがちです。
しかし、これらは一時的に体を冷やしてくれますが、摂りすぎると胃腸の働きを直接的に低下させてしまいます。
消化機能が弱まると、栄養の吸収が悪くなるだけでなく、食欲不振をさらに助長する悪循環に陥ります。
脂っこい・辛すぎるものの大量摂取
スタミナをつけようと、焼肉や揚げ物など脂っこいものを食べるのは逆効果になることがあります。
脂質の多い食事は消化に時間がかかり、弱った胃腸に大きな負担をかけます。
また、唐辛子などの辛すぎるスパイスも、大量に摂取すると胃の粘膜を荒らしてしまう可能性があるのです。
適度な香辛料は食欲を増進させますが、何事も「ほどほど」が大切です。
夜更かしや朝食の欠食
不規則な生活は、体温調節などを司る自律神経の乱れに直結します。
特に、熱帯夜で寝苦しいからと夜更かしをしたり、食欲がないからと朝食を抜いたりする習慣は、体内時計を狂わせ、夏バテを深刻化させる大きな原因です。
朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴び、朝食をしっかり食べることで、生活リズムを整えることが夏バテ予防の第一歩です。
夏バテの治し方は夏バテの予防にもなります。夏バテの治し方にはいくつかの方法があります。そもそも夏バテとはなんでしょうか。夏バテの治し方とはどのような方法なのでしょうか。本記事では夏バテの治し方について以下の点を中心に[…]
水分補給も重要!夏バテに効果的な飲み物とNGな飲み物
夏バテ対策において、食事と同じくらい重要なのが「水分補給」です。
汗で失われるのは水分だけでなく、ナトリウムなどの電解質も含まれます。
ただ水を飲むだけでなく、何をいつ、どのように飲むかが重要になります。
オススメの飲み物
日常的な水分補給には、ミネラルを含む麦茶が最適です。
大量に汗をかいた後やスポーツ時には、水分と電解質、糖分を効率よく補給できるスポーツドリンクが有効です。
また、めまいや強い倦怠感など、脱水症状が疑われる場合には、吸収効率が最も高い経口補水液が推奨されます。
- 日常的に飲むなら: 水、麦茶
- 汗をたくさんかいたら: スポーツドリンク
- 脱水症状が見られたら: 経口補水液
注意が必要な飲み物
カフェインを含むコーヒーや緑茶、紅茶には利尿作用があるため、水分補給のつもりで飲むと、かえって体内の水分を排出してしまう可能性があります。
飲む場合は、同量程度の水を一緒に摂るように心がけましょう。
また、糖分の多いジュースや清涼飲料水は、血糖値の急激な変動を招き、だるさの原因になることがあります。
そのため、飲み過ぎには注意が必要です。
避けるべき飲み物
アルコールは、カフェイン以上に強い利尿作用があり、分解するために体内の水分を大量に消費します。
暑い日のビールはおいしいですが、水分補給にはならず、むしろ脱水症状を悪化させるリスクが非常に高いので注意しましょう。
寝る前のお酒も、睡眠の質を低下させ、疲労回復を妨げる原因となります。
夏場になると、脱水症状が気になります。脱水症状は、発見が遅れると命に関わる病気の引き金になる場合があります。飲み物での脱水症状対策には、どのようなものがあるでしょうか?また、正しい水分補給のやり方はどのようなものでしょうか?本記事[…]
食べ物以外に夏バテを予防・改善できる5つの生活習慣
夏バテは、食事だけで解決できるものではありません。
日々の生活習慣を見直すことで、暑さに負けない体を作ることが可能です。
今日から始められる5つの習慣をご紹介します。
質の高い睡眠をとる
睡眠は、日中に消耗した心と体を回復させるための最も重要な時間です。
寝苦しい夜は、エアコンや扇風機を適切に使い、快適な室温(28℃以下が目安)を保ちましょう。
タイマー機能を活用し、体を冷やしすぎないように注意が必要です。
また、就寝前にスマートフォンなどを見るのは避け、リラックスできる環境を整えることが質の高い睡眠につながります。
なかなか寝つけなかったり、夜中に目が覚めてしまったりなど睡眠で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。睡眠は、睡眠時間だけでなく質も大事とされています。では、睡眠の質を上げる方法には、どのようなことがあるのでしょうか。本記事[…]
ぬるめのお風呂に浸かる
暑いとシャワーだけで済ませてしまいがちですが、ぜひ湯船に浸かる習慣をつけましょう。
38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。
また、血行が促進されることで疲労物質が排出されやすくなり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
お風呂に浸かると一日の疲れが取れます。入浴には、さまざまな効果が期待できます。最近、忙しいからとシャワーだけで済ませていませんか?本記事では入浴の効果について以下の点を中心にご紹介します。 入浴するとどんな作用が働くか 入[…]
適度な運動を心がける
軽い運動で汗をかく習慣をつけることは、体温調節機能を正常に保つために重要です。
暑い日中を避け、早朝や夕方の涼しい時間帯にウォーキングやストレッチなどを行いましょう。
運動することで血行がよくなり、胃腸の働きも活発になります。
ただし、無理は禁物です。
体調に合わせて、心地よいと感じる程度の運動を継続することが大切です。
こまめな水分補給
水分補給の基本は、「喉が渇いた」と感じる前に、こまめに飲むことです。
喉の渇きを感じた時には、すでに体内の水分が不足しているサインです。
起床時、食事中、入浴前後、就寝前など、タイミングを決めて飲む習慣をつけるとよいでしょう。
厚生労働省では、一般的に食事以外に1日当たり1.2Lの水分の摂取が目安とされています。
一度にがぶ飲みせず、コップ1杯程度を数回に分けて飲むのが効果的です。
服装や室温を工夫する
吸湿性や速乾性に優れた素材の衣服を選び、汗をかいても快適に過ごせるように工夫しましょう。
屋外から冷房の効いた室内に入る際は、カーディガンなど羽織るものを一枚用意しておくと、急激な温度変化から体を守れます。
エアコンの設定温度は28℃を目安にし、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させると、効率よく快適な環境を作れます。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、夏バテに効く食べ物ランキングTOP20を中心に、その根拠となる栄養素や簡単レシピ、さらには効果的な生活習慣までを網羅的に解説しました。
- 夏バテ対策には「ビタミンB1」「クエン酸」「カリウム」「たんぱく質」が重要
- ランキング上位の豚肉や梅干し、夏野菜などをバランスよく食事に取り入れる
- 食欲がない時は、火を使わない簡単レシピやコンビニ商品を上手に活用する
- 食事だけでなく、適切な水分補給、質の高い睡眠、適度な運動も不可欠
夏の厳しい暑さは、私たちの体に大きな負担をかけます。
しかし、正しい知識を持って食事や生活習慣を少し工夫するだけで、夏バテは十分に予防・改善できます。
この記事で紹介した方法をひとつでも実践していただき、今年の夏を元気に、そして快適に乗り切っていただければ幸いです。
毎日の食事や栄養バランスの管理が難しいと感じる場合は、科学的根拠に基づいた栄養機能食品などを活用するのもひとつの方法です。
ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる対策を見つけていきましょう。
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります