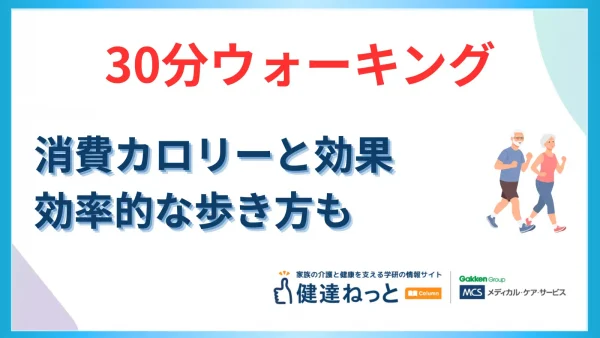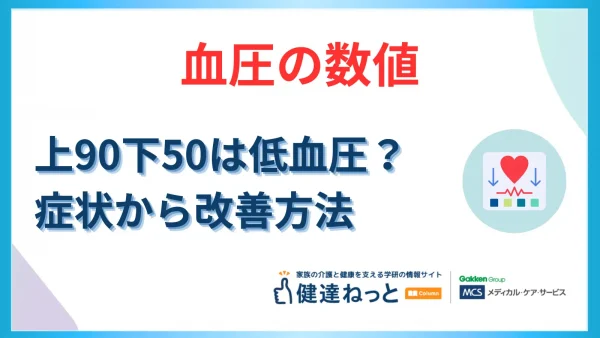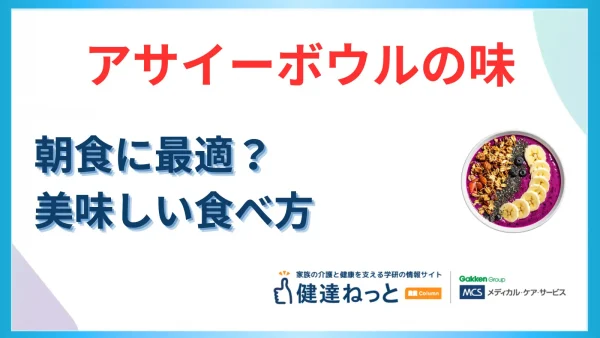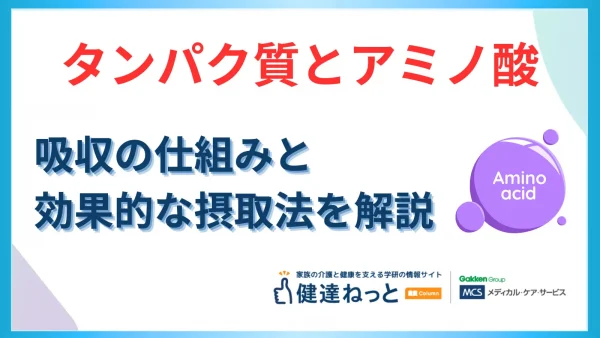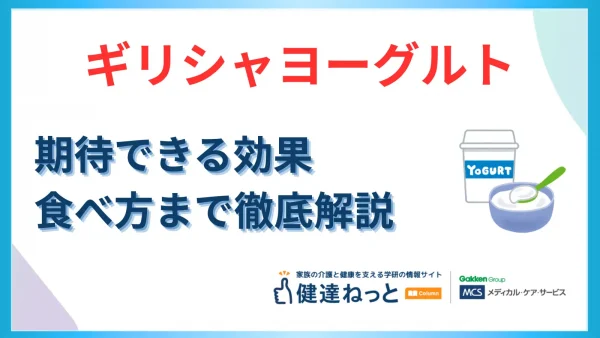「o157の感染経路は?」
「o157に感染しないためにできることは?」
o157の感染経路について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、o157の感染経路について以下の点を中心に詳しく解説します。
- o157の主な感染経路
- o157の感染経路ごとの気をつけるべきポイント
- o157に感染した場合の対処法
o157の感染経路について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
o157の感染経路は主に2種類

まず、o157の2つの感染経路について解説します。
- 経口感染
- 接触感染
①経口感染
o157の感染経路の1つ目は「経口感染」です。
o157の感染経路としてもっとも多いのが、経口感染です。
経口感染では、o157に汚染された水や食品を摂取したり、感染者の糞便に含まれる細菌が直接または間接的に口に入ったりすることで感染します。
o157は微量でも感染する強力な細菌ですが、感染者のせきやくしゃみなどでは感染しません。
o157に汚染された飲食物を口にしないことと、感染者から細菌をもらわないための心がけが大切です。
②接触感染
2つ目は「接触感染」です。
接触感染は、細菌に触れた手を介して飲食物を口にし感染するもので、感染者本人に触っただけで感染することはありません。
接触感染の原因には、感染者の糞便に含まれる細菌がなんらかの形で、ドアノブや手すりなどの共有物に付着することが考えられます。
細菌が付着したものに触れた手で飲食物を摂取すると感染する恐れがあるため、手洗いや消毒を意識しましょう。
スポンサーリンク
o157とは?

次に、o157について知っておきたいその他の情報を以下の4つの項目に分けて解説します。
- 潜伏期間
- 主な症状
- 原因食品
- 対処法
①潜伏期間
1つ目は「潜伏期間」です。
o157の潜伏期間は3〜8日が一般的ですが、最短で1日、最長で10日程のケースもあり、人によりさまざまです。
潜伏期間中は症状が出ないため、感染に気づかず、無意識のうちにo157を拡散させるリスクがあります。
o157は感染力が強く、保育園や高齢者施設での集団感染の事例もあり、一人でも感染者が出た場合は、適切な対応が必要です。
身近にo157の感染者が出た場合は、症状が出ていなくても細菌を保有している可能性があると考えましょう。
②主な症状
2つ目は「主な症状」です。
o157の主な症状は以下のとおりです。
- 腹痛
- 水様性下痢
- 血便
- 嘔吐
- 発熱
o157に感染した場合、多くのケースで激しい腹痛や水様性下痢の症状があります。
場合によっては、血便や発熱、嘔吐などの症状も見られるでしょう。
また、免疫力の低い子どもや高齢者などは重症化しやすく、溶血性尿毒症症候群や脳症などの重症な合併症を起こす恐れもあります
一方、健康な成人がo157に感染した場合、無症状や軽い下痢で治ることもあり、人により症状は異なります。
③原因食品
3つ目は「原因食品」です。
o157の原因となる食品の具体例は以下のとおりです。
- 肉
- 乳製品
- 野菜
- 果物
肉や乳製品は、加熱が不十分であったり、不衛生な環境で加工したりすると、o157に汚染されるリスクがあります。
生野菜や果物のほか、漬物でもo157の集団感染が起きているため、加工されていれば安心というわけではありません。
また、食品以外では、周辺環境の影響を受けやすい井戸水や湧水にも注意が必要です。
④対処法
4つ目は「対処法」です。
o157への感染が疑われる場合は、すぐに病院に行きましょう。
o157の重症化や合併症を防いだり、感染を拡大させたりしないためにも、医師による診察を受け、適切な治療を受けることが重要です。
o157は無症状や軽症で治る人もおり、無自覚のまま細菌を保有している可能性があります。
自分の命を守り、周囲の人への感染を防ぐためにも、o157が疑われる症状がある場合は、まずは病院に行きましょう。
食中毒が治るまでの期間について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
[sitecard subtitle=関連記事 url= target=][sitecard subtitle=関連記事 url= target=]食中毒とは、細菌やウイルスなどの感染が原因で嘔吐や下痢などが起きる病気です。食中毒は、細[…]
食中毒の症状と分類について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
o157の経口感染を防ぐためにできること

次に、o157の経口感染を防ぐためにできることを5つ解説します。
- 手を洗う
- 食品を洗う
- 食品を十分に加熱する
- 食品を適切に管理する
- 調理器具を清潔にする
①手を洗う
o157の経口感染を防ぐためにできることの1つ目は「手を洗うこと」です。
o157をはじめとする感染症対策において、手洗いは基本的かつ効果的とされる方法です。
食事前や調理前、トイレ後は必ず石鹸と流水でしっかりと手を洗いましょう。
また、生肉を調理した手でほかの食品に触れないように、調理中も意識して手を洗うことが大切です。
調理している食品がo157に汚染されている可能性があるため、手洗いを徹底し、細菌を広げないように心がけましょう。
②食品を洗う
2つ目は「食品を洗うこと」です。
野菜や果物を調理したり食べたりする際は、細菌や汚れをしっかりと洗い流しましょう。
トマトやナスなどのつるつるした食品は洗いやすいですが、きゅうりのような凸凹したものは汚れが落ちづらいため、注意深く洗う必要があります。
また、レタスやキャベツなどの葉物野菜は、葉と葉の間に汚れや細菌がいる可能性があるため、一枚ずつ洗うと良いでしょう。
生で食べない食品でも、事前に丁寧に洗っておくことで、より衛生的に調理できます。
③食品を十分に加熱する
3つ目は「食品を十分に加熱すること」です。
o157は加熱に弱いため、食品を十分に加熱すれば、感染を防ぐことが期待できます。
目安は、75℃で1分間以上の加熱です。
とくにo157の感染リスクが高いハンバーグやステーキなどの肉料理は、表面だけでなく内部までしっかりと火を通しましょう。
また、電子レンジで調理する際は、加熱ムラが起きやすいため、専用の容器を使ったり調理時間を意識したりする必要があります。
食品全体にしっかりと火が通るように、混ぜたり位置を変えたりするなどの工夫も大切です。
④食品を適切に管理する
4つ目は「食品を適切に管理すること」です。
肉や生鮮食品を冷蔵庫や冷凍庫などに入れず、常温で放置すると、o157をはじめとする細菌が増殖する恐れがあります。
そのため、食品は温度管理が徹底された環境で保存しましょう。
また、食べ残しも放置せず、清潔な容器に移して冷蔵庫で保存する必要があります。
食べ残しは、75℃以上を目安に再加熱してから食べましょう。
とくに夏場は、常温で放置すると細菌が繁殖しやすいため、食品の管理をより徹底することが重要です。
⑤調理器具を清潔にする
5つ目は「調理器具を清潔にすること」です。
包丁やまな板などの調理器具は、使用後すぐに洗い、熱湯やアルコールで消毒しましょう。
消毒には、次亜塩素酸ナトリウム製剤(台所用漂白剤)や亜塩素酸水が使えます。
とくに肉を調理した後の包丁やまな板を使って、野菜や調理済みの食品を扱うことは避けましょう。
可能であれば、肉用と野菜用で調理器具を使い分けるのがおすすめです。
また、ふきんやたわし、スポンジなども洗浄後、熱湯をかけたり煮沸したりして、清潔な状態で使いましょう。
o157の接触感染を防ぐためにできること

次に、o157の接触感染を防ぐためにできることを3つ解説します。
- 感染者と接触しない
- 消毒をする
- 感染者とタオルや食器などを共有しない
①感染者と接触しない
o157の接触感染を防ぐためにできることの1つ目は「感染者と接触しないこと」です。
感染者がo157を保有している恐れがあるため、できるだけ接触しない環境を作ることが大切です。
家族の感染時など、接触を回避することが難しい場合は、マスクや手袋などを活用すると良いでしょう。
また、感染者の便や体液が付着している衣類などを介して感染が拡大する恐れがあるため、取り扱いには注意しましょう。
②消毒をする
2つ目は「消毒をすること」です。
手洗い後は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどを使って消毒をしましょう。
また、感染者が直接触れる可能性があるトイレやドアノブなどの消毒も効果的とされます。
ほかにも、調理器具や食品を扱う場所の定期的な消毒で、o157への感染を防ぐことが期待できます。
とくに、キッチンやカウンターなど、細菌が繁殖しやすい場所は念入りに消毒することが大切です。
③感染者とタオルや食器などを共有しない
3つ目は「感染者とタオルや食器などを共有しないこと」です。
前述の通り、o157が付着したものに触れた手で飲食物を摂取することで感染するリスクがあります。
o157に触れない環境を作るためには、タオルや食器などを感染者と共有しないことが重要です。
家族それぞれ別のタオルや食器を用意しましょう。
感染者が使ったタオルや衣類は、使用後すぐに洗濯する必要がありますが、家族のものと分けて洗うことで、衛生的に管理できます。
o157の感染時にできること

次に、o157の感染時にできることを3つ解説します。
- 病院に行く
- 入浴を避ける
- 安静にする
①病院に行く
o157の感染時にできることの1つ目は「病院に行くこと」です。
o157に感染した場合は、医師の診断に基づく治療が不可欠のため、すぐに病院に行きましょう。
場合によっては薬を処方されるため、医師や薬剤師の指示に従って、適切に服用します。
とくに免疫力の低い人がo157に感染すると、重症化したり合併症を起こしたりするリスクがあり、早期に適切な治療を受けることが大切です。
②入浴を避ける
2つ目は「入浴を避けること」です。
感染者が入浴すると、浴槽やバスルーム全体にo157が拡散され、家庭内感染する恐れがあります。
とくに、感染者に下痢の症状が見られる場合、排泄物にo157が含まれている可能性があるため、入浴は避けたほうが良いです。
感染者がバスルームを使う場合は、湯船に浸からず、シャワーのみで済ませましょう。
また、重症化のリスクがある子どもや高齢者などへの感染を防ぐためにも、感染者は最後に入浴することが大切です。
感染者のバスルーム使用後の消毒も忘れないようにしましょう。
③安静にする
3つ目は「安静にすること」です。
o157に感染した場合は、体を休めて体力を回復させましょう。
o157に限らず、一般的に下痢の症状が見られる場合は、安静にしながら、以下のことを心がけます。
- 水分を補給する
- 消化しやすい食事を摂取する
下痢のときは脱水症状になりやすいため、経口補水液やスポーツドリンクなどで水分を補給しましょう。
ただし、下痢の症状が悪化する恐れがあるため、冷たい飲み物は避けたほうが良いです。
高齢者が注意したい感染症についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。
o157の感染者が出た場合にしたいこと

最後に、身内や身の回りの人がo157に感染した場合に取りたい行動について、以下の2つをご紹介します。
- 必要に応じて検査を受ける
- 体調を観察する
①必要に応じて検査を受ける
o157の感染者が出た場合にすべきことの1つ目は「必要に応じて検査を受けること」です。
家族がo157に感染した場合などは、症状が出ていなくても、便の検査を求められることがあります。
健康な成人の場合、無症状なケースもありますが、o157に感染しているリスクを否定できないため、医療機関や保健所の指示に従って適切に対応しましょう。
便の検査を受けて感染に気づくケースもあり、無意識のうちにo157を拡散しないためにも、必要に応じて検査を受けることが重要です。
②体調を観察する
2つ目は「体調を観察すること」です。
前述した通り、健康な成人が感染した場合、無症状で治るケースがあり、o157に感染している自覚がないこともあります。
しかし、重症化したり合併症を起こしたりするリスクがあるため、感染時は医師による診察が欠かせません。
そのため、身近に感染者がいる場合は、以下のような症状が見られないか、しっかりと体調を観察することが大切です。
- お腹に違和感がある
- 軽い腹痛や下痢がある
少しでも異変や違和感がある場合は、すぐに病院に行きましょう。
o157の感染経路についてのまとめ

ここまでo157の感染経路についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- o157の感染経路には、経口感染と接触感染がある
- o157を防ぐには、食品の加熱や調理器具の衛生管理などを徹底する必要がある
- o157への感染が疑われる場合は、すぐに病院に行き、医師による診察を受ける
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。