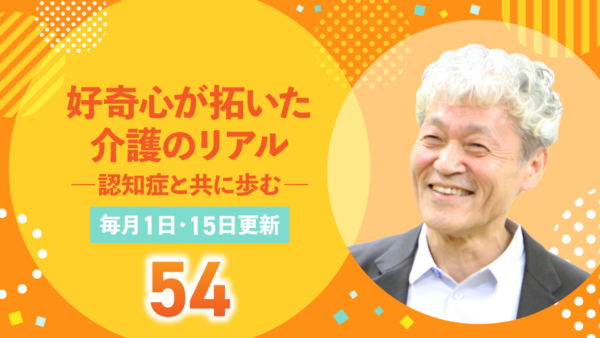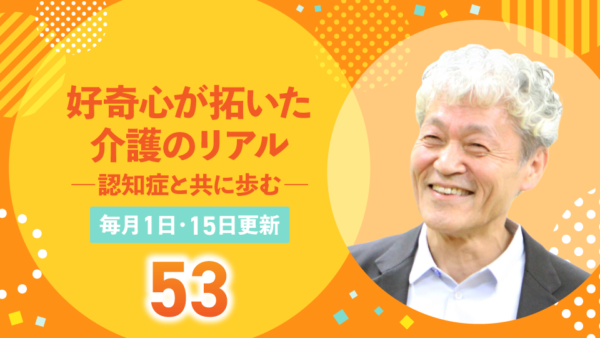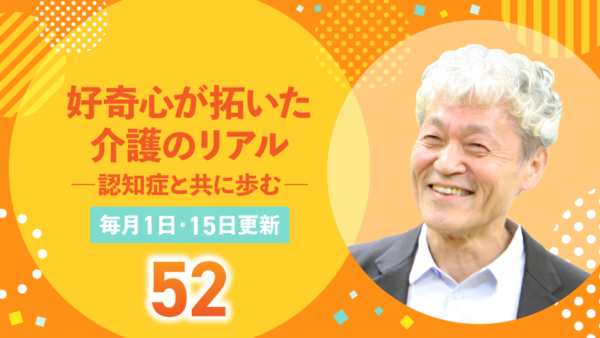別れたい・死にたい
「私、死にたいのよ」
「死ぬのは勝手やけど、僕の前では、やめてくださいね」
保健師から「和田さん、お願いがあるの」と頼まれて向かったお宅には、パーキンソン病を患う若い女性がいました。
「あなた、だれ」
「〇〇保健師さんからご紹介を受けた和田って言います」
「あー、あなたね。入りなさい」
彼女の名前はユリさん(仮名)、年齢は四十歳代前半。パーキンソン病を患い旦那さんとの二人暮らし。
「なにしに来たの」から始まったユリさんとの関係。
「僕は〇〇クリニックで難病リハビリというのをやっていて、そこの相談員をやっている和田って言います。〇〇保健師さんからユリさんに難病リハビリのことを紹介してあげて欲しいと言われたんで、うかがった次第です」
パーキンソン病を患ったことで心を閉じてしまったユリさんは、僕が話をするうちに断続的な語り方でゆっくりでしたが、自分のことをガンガン語り出しました。
「旦那は私の病気の事なんてちっともわかっていない」「やって欲しいことをやってくれない」といった愚痴に始まって「あの旦那と別れたいのよ」とまで口にしました。
僕は、「旦那さんの話を聞いてみないとね」と「一方的に旦那さんに対して言う言葉は信じないよ」的風を吹かせながら「そんなに嫌なら、別れたいって言えばいいじゃないですか」と突っ込んでいった先に出た言葉が「死にたい」でした。
それまで僕の事業の話はしても、誘いの言葉はかけませんでしたが、ユリさんがそこまで語ってくれたので
「うちは、老人デイサービスというのも一緒にやっていてお年寄りが多いけど、一度来てみますか」
と言葉をかけさせてもらいました。
「あなたが居るときに行きたい」
「僕が迎えに来ますから。また、連絡しますね」
“互いに助け合って”を生めるように
僕が勤めていたクリニックでは「難病リハビリ」と「老人デイサービス」という医療と介護の「通ってくる事業ふたつ」を同時にやっていましたが、僕の仕事としてどちらも同じようなものです。老人デイサービスにだって慢性関節リウマチの高齢者が通ってきていましたしね。制度がどうあれ変わりなしです。
あるとき、利用者懇談会を開催しました。
僕以外のスタッフは参加させないで「皆さん、ここはどうですか。嫌な職員さんはいませんか?」といったように利用者の生の声を聴くための会です。
ユリさんもしっかりお馴染みの利用者になっていましたが、ユリさんがこう切り出しました。
「私は、この病気になって、何もしてくれないと旦那さんを責め、死んでしまいたいとさえ思うほど悲観して生きてきましたが、皆さんを見ていて心から励まされました。私よりもずっと年輩の皆さんが一生懸命、訓練に取り組んでいるのを見ていて、自分のダメさを思い知りました。ありがとうございます」
僕は、この言葉がホントに嬉しかったし、こういうことが「人が集まる事業にとってとても大事なこと」だということを再認識しました。
また、重ねて嬉しい言葉が、車いす状態になっている八十歳代半ばんのトメさん(仮名)から飛び出しました。
「何言ってるの。私の方こそ、あなたみたいな若い人が、不自由な身体にめげず、明るく来て訓練している姿を見て感動しているのよ。頑張ってね。ありがとう」
と、65歳以上の方しか利用できない老人デイサービスと年齢に関係がない難病リハビリのコラボレーション効果にハッとしました。
パーキンソン病に出会えて良かった
そのクリニックを退職してグループホームに従事することになってからもユリさんとは交流がありました。
「和田さん、主治医の先生もビックリするくらいお薬がへってきているの。学会で発表しても良いかって言われたよ」
「昔好きだったちぎり絵の教室に行くようになり、こんな作品作ったよ」と持参してきたのは、僕の顔のちぎり絵でした。
「ところでこの額。手作りしているけど、だれが作ったの?」
「フフ、旦那さんです」
奥様であるユリさんが明るく元気になっていくことを喜ばれたのは、本人だけじゃなく旦那さんも同じで、二人で闘病生活に挑むようになっていたのには驚きましたし、一緒に来ていた旦那様さんには「ほんまに、(この人で)いいの」って確認しちゃいました。
自転車に乗れるようになり、あこがれていた東京ドームプロ野球観戦にも行き、ちぎり絵で評価を受けるようになり「死にたい」から激変生活を送っていたユリさんに、初めて一緒に壇上に上がったパーキンソン病友の会の舞台上でこう投げてみました。
「あんなユリさん、パーキンソン病に出会えて良かったやろな。おかげで、今あるあなたにとってのいいことに出会えたんやし、俺にも出会えたしな」
「うん。和田さんに初めて会った頃は、なんで私がとか、生きててもしょうがない、死にたいって毎日思い、旦那のことだけでなく他人を責め恨んでいたけど、今は、パーキンソン病になって良かったって思えてるよ。ちぎり絵にも出会えたし」
死にたいを応援したいと思えたが・・・
ある日、車で都内を走っていると旦那さんから電話が入りました。
「和田さん、ユリが救急車で病院搬送されたのですが、ある検査をしないと数時間後に死んでしまう状態になっているんです。しかも、どうしてもその検査を受けないと言うんです。自分の言葉には耳を貸そうとしません。来てください。お願いします。お願いします」
すっ飛んで病院に行き、まずはドクターの話を聞くと、そのような状態だと説明を受けました。だから旦那さんに「旦那さん、昼夜問わずの介護が辛いって言ってたやん。ほんまにユリさんに生きてて欲しいと思っているんか」って最後になるかもしれない確認をしました。
「和田さん、そりゃ介護は大変やけど、彼女には生きてて欲しいです。お願いします」
僕にできるかどうかわかりませんでしたが、その言葉を受けてユリさんのところに行き「どうや」って声をかけたところ悲痛顔のユリさんから「和田さん、わたし頑張ってきたでしょ、もういいでしょ、もうこの痛みから解放されたいの」と涙声。
その言葉を聞き、思わず「そうかぁ、よぉ、頑張ったよなぁ。これ以上頑張らなくていいと思うよ」って答え、旦那さんのところに行き「もう、解放してやろ」って言いいました。
「和田さん、命をつなぐことは難しいかもしれないけど、この段階で見込みがある以上、先に進めるために何としても検査を受けさせたいんです」
その言葉に「そうかぁ、わかった。もう一回話してみるわ」と言って再びユリさんの病室に入りました。
ユリさんと出会った頃からの思い出話に花を咲かせているうちに「やっぱり、ユリさんの願い(死にたい)に応えることが大事なんじゃないか」と思いはじめ、ここに旦那さんも呼んで三人で話そうかなと思い始めたその時でした。
「和田さん、私の人生、ひとつもいいことなんてなかったわ」
はき捨てるように言ったユリさんのその言葉に、カチンときました。
「あんなユリさん、ひとつもいいことなんてなかった? いい加減なことを言うな。あんた、パーキンソン病に出会えて良かった。そのおかげで和田さんに出会えて良かったって言ってくれてたやないか。
死んでいくのに、この世でひとつもいいことなんてなかったって思われたままあの世に行かれたら僕も旦那も迷惑や。なァ、ユリさん。最期にひとつだけいいことあったって言えるようになってから死んでくれへんか。なァ、ユリさん。検査受けてくれ。なァ」って握手を求めるように手を差し出しました。
ユリさんは、僕の怒り声に号泣し、しばらく身動きひとつしませんでしたが、やがて差し出した僕の手を握り返してくれました。
「ありがとう。それでいいと思うで。旦那さんも僕も嬉しいわ」」
間一髪、ギリギリ間に合いました。
応援できているかどうか自問は続く
こうなると、どこまでが仕事でどこからが単なる人間関係かの線引きは難しいですが、僕らの仕事は「他人の人生」にかかわる仕事であることは間違いなく、それは入居施設の介護職員だって同じことで、いくら仕事でも他人の人生に責任はもてませんが、人生の応援はできるはず。
だから、応援できているかどうか、自問が続く仕事なんですよね。








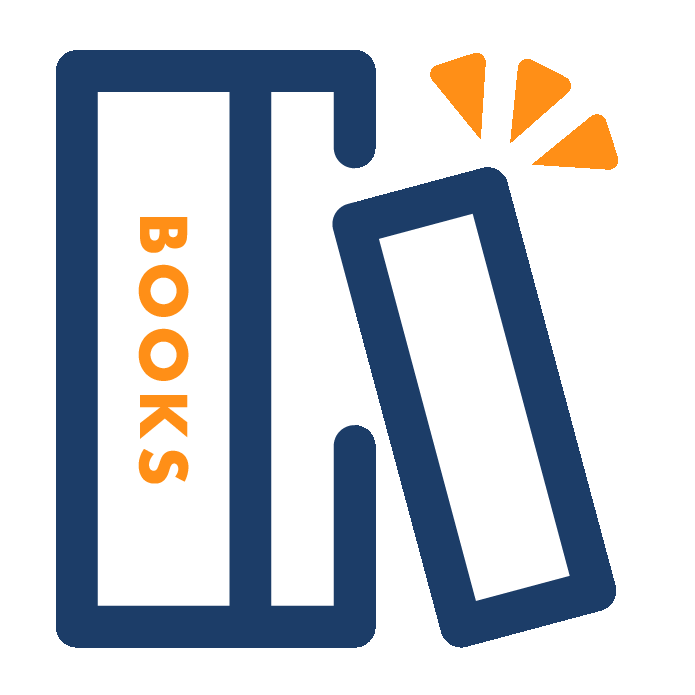

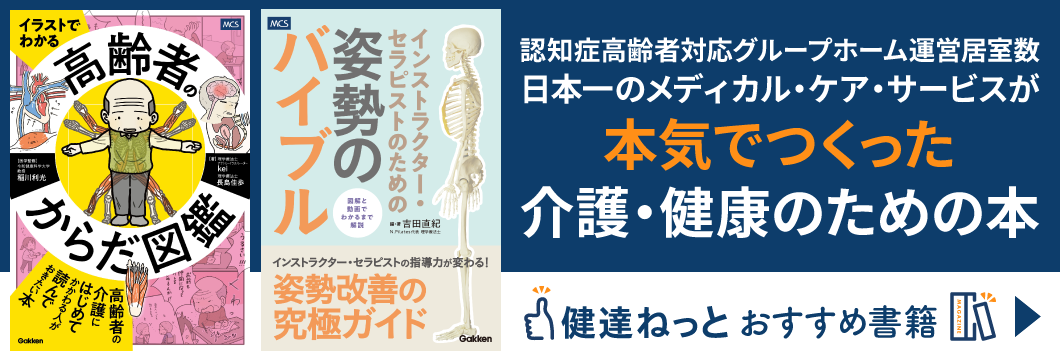
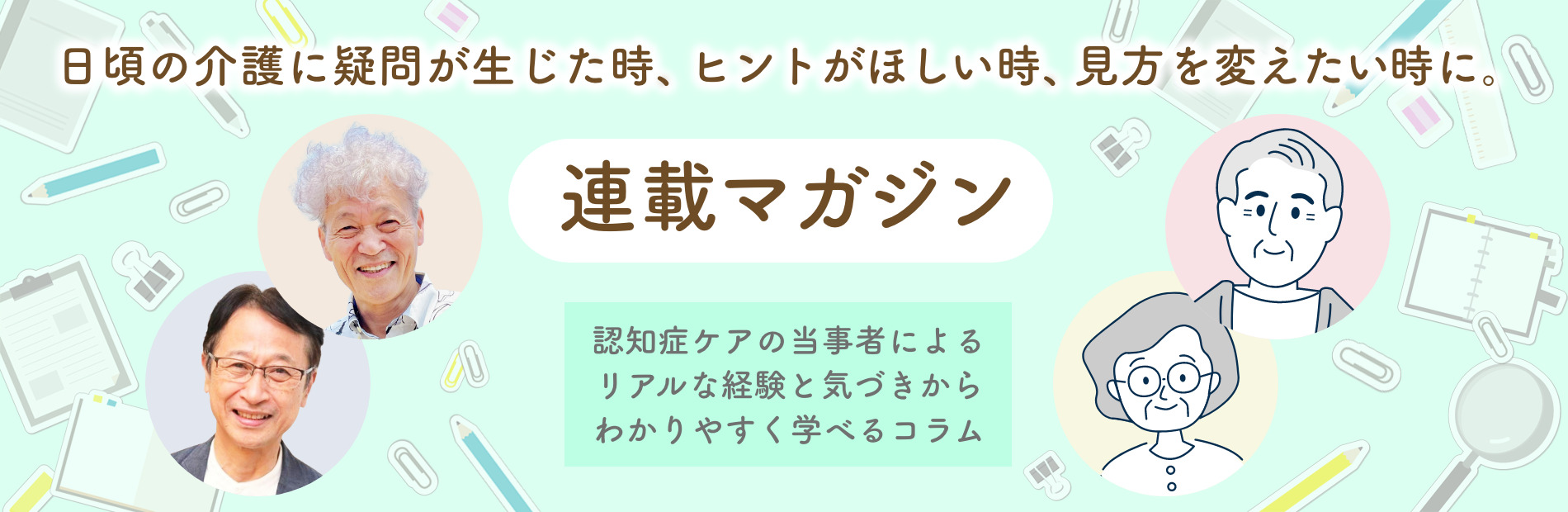


.webp)