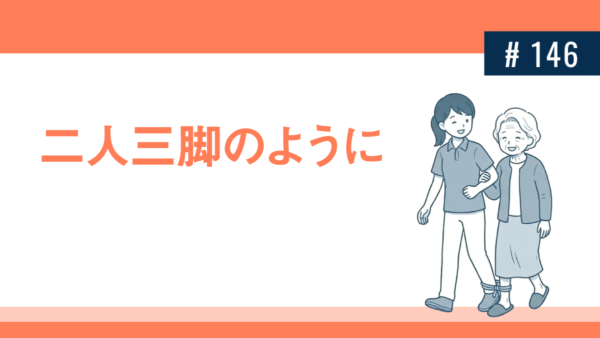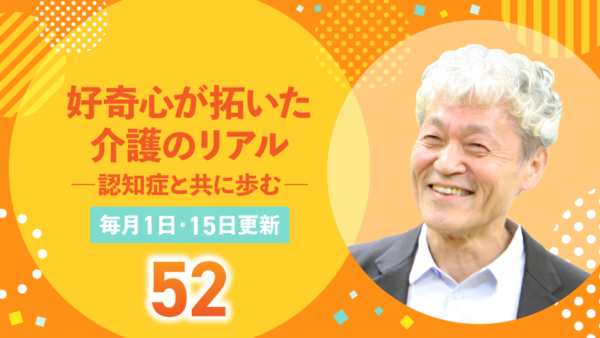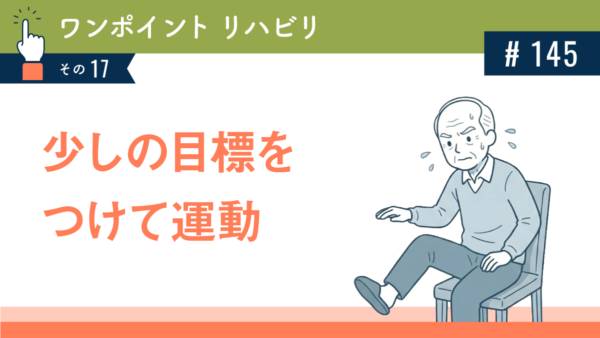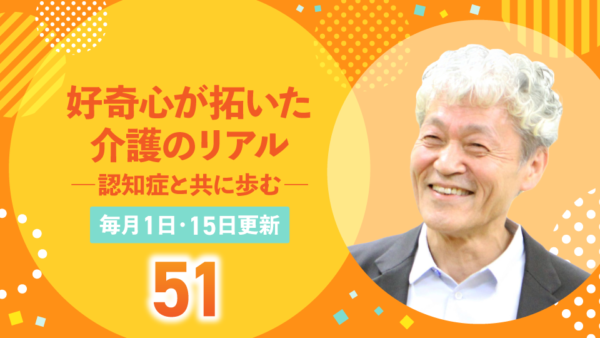しでかしたことで見えたこと
38年前、この仕事に就いて程よい時間が経った頃、気の緩みなのか「しでかしたこと」があり「しでかしたことで見えたこと」がありました。
夜間勤務の休憩時間は2時間でした。
休憩時間は「肉体と精神の解放時間」ですから、休憩時間をどのように過ごすかということに使用者側が大きくは制約を設けてはならないもので、僕が勤め出したばかりの介護事業所では休憩室に寝具が準備されていて「寝具に寝そべること」ができました。
多くの職員は短い時間ですが睡眠(よく仮眠と言われてる)していたように思います。
昔で言う「痴呆専用棟(痴呆症は、現在認知症に呼称変更されています)」で夜間勤務に就いていた時のことです。
休憩時間は3時~5時の2時間で、5時から入所者の「起床介助、洗面介助、排せつ介助、排せつ後のオムツ類の洗濯の下準備まで」をして、早出職員が出勤してくる7時には「入所者がテーブルの周りに座って朝食が来るのを待つ状況」にしておくことが暗黙の了解になっていました。
当時は、自宅での生活が困難になった痴呆症という状態にある人たちの多くは精神病院に入院させられていましたが、措置型の福祉施設(介護事業所)での入所がままならなかった背景もありました。
だから僕が勤めていた介護事業所のように痴呆専用棟を備えているところに痴呆症という状態にある人たちが集まってきていましたから多彩な方が入所されていました。
今思えば、今なら精神疾患の状態と診断される方も含めて入所されていたように思います。
その方々の「起床から食事前」までの支援に要する時間は、「5時~7時の二時間で少し余裕がある」といった感じでした。
ヤバい!寝過ごした
ある日、休憩時間を使ってひと眠りをした僕が目覚めた時間は6時!
「エーッ!!!!!!!!」
5時に休憩時間は終了しますから、寝過ごしてしまったんです。
小心者の僕の頭の中にすばやく出てきたのは「早出の職員がきたら寝坊したことがバレる、ヤバい」でした。
先述のように入所者への支援に要する時間は通常2時間弱かかるわけですから、どう考えてもバレるわけです。
でも、そうは思っても先に進めるしかないわけで、いつも通り〇号室の入所者から起床の声掛けをスタートさせました。
「よねさん(仮名)、起きましょうか」・・・「服を着替えましょうか」・・・
いつもなら、パジャマの上衣を脱いで昼間着の上衣を着ていただき、パジャマの下衣を脱いでいただいて昼間着の下衣を穿いていただくと、下衣をおへその辺りへ持ち上げた勢いで、さっき着たばかりの昼間着の上衣を脱ぎだし、その上衣を着ていただくと、今度はその勢いで昼間着の下衣を脱いでしまわれることを繰り返される方が、一発で着替え完了!
「ガンさん(仮名)、起きましょうか」・・・「オーッ」・・・
いつもなら、ベッドから起き上がってベッドサイドに立ち上がっていただくまでにかなりの時間を要する方ですが、これまた一発で立ち上がってくださり、着替えも実にスムーズに完了となりました。
極めつけは、言葉がうまく出せないトメさん(仮名)が、僕は何も言っていないにもかかわらずテーブルの周りに椅子を勝手に準備しようとしているのを目にして涙がポロリ。
ここは思い切ってトメさんに任せるとして他のことを行っていると、椅子がすべてセットされて、すでに何人かの利用者が座っているじゃありませんか。
いつものあの手間暇かかる状態はどこへいったんやろ
きっと、僕の顔が悲壮な懇願顔だったんやろな
お願いだから・・・って感じの顔が、通じたんかな
見得た瞬間
この出来事は、退職するまでほんの一握りの人にしか言えませんでしたが、僕にとっては衝撃的な出会いで、僕が認知症という状態にある方々の生活支援を考えていくうえで大切にすべき軸が見えた瞬間でもありました。
つまり、「認知症=わからない状態」ではなく「認知症=わかろうとしない僕ら=わからない状態」だということで、逆に言えば「僕のことがわかる・察することができたってこと」で、
その時から「人は脳が病変に侵されてもお見通し能力があり、それが病変を補完するのではないか」と僕流に捉えられるようになれましたし、それがいいように活きていると言えますからね。
上手くいかなかったことも上手くいったことも通過点でしかない
よく「失敗から学ぶ」って言いますけど、ということは、その角度からみれば「失敗はない」ってことで、すべてのことが「通過点」とも言えます。
よって「上手くいかなかったこと=失敗ではなく」、上手くいかなかっただけの事と捉えれば、上手くいったことも上手くいかなかったことも同じであり、「なぜ、上手くいかなかったのか」を考えるのと同じように「なぜ、うまくいったのか」も考えることが大事なこととなるわけですが、
実は上手くいったことの方が上手くいった理由を見出すのが難しかったりするんです。
追伸
名古屋-秋田クルマ往復(約1,800キロ)、名古屋-東京クルマ3往復(約2,300キロ)、名古屋-広島クルマ往復(約1,000キロ)、東京-ハノイ飛行機往復(約7,500キロ)
このひと月の間に移動した距離はクルマで5,000キロ超、飛行機で7,500キロ、合計12,500キロ以上でした。
地球一周赤道で40,000キロのようですからその三分の一弱を移動したことになり、僕が乗ったことのあるシベリア横断鉄道が極東の町ナホトカから首都ロシアまで9,300キロぐらいでしたから、それ以上の移動距離。
20歳代の頃は新車を購入して3か月で21,000キロ、ひとつき平均7,000キロ超と走り回っていたことはありますが、今になってもなお5,000キロ以上走るとは「すごいね、和田さん」って感じですね。とにかく移動・移動・移動だった気はします。
いつも書かせてもらっていますが、僕にとって「移動」って至福の時間で、特にクルマでの移動は「一人っきりの時間」ですからたまらないひとときですね。
他の人と一緒にいる時間が多くを占める僕にとって誰にも邪魔されずに音楽を聞け、見たい景色を見て、走りたい道を走り、寄りたいところにより、もの思いにふけって・・・のはずなのですが、コロナ感染症で爆発的に広まった「オンライン」とやらが至福の時間に割り込んできました。
飛行機が発達する前、出張での移動は「汽車」で、新幹線が開通する前(昭和39年)でさえ東京-大阪間は約7時間の電車旅でしたから日帰りは描けず「泊まり込み」で、そのころの出張は至福の時間だったと年輩の方によく聞きますが、何となくわかる気がしますね。
便利になったこと=豊かになったかどうかは別で、それも人によって随分と評価が違ってきているでしょうね。
僕のようにあちこちに出かけては何かにつけ触れることが大好きで一人っきりになる時間を欲していると、交通機関の進展で日帰りとなり、オンラインでいつでもどこでも打合せできるようになった現代社会は「便利やけどなぁ・・・」と「・・・」の数が増え、良くないストレスで疲労度が増すばかりですが、そうでない人にとっては真逆でしょうからね。

写真の「ランブータン」という果物もそのひとつで、ベトナムでは「チョムチョム」と呼ばれていて今が旬です。ライチに似た甘酸っぱい果肉をもつフルーツで赤い毛に覆われた外見が特徴で、僕は思わず「美味しい!」と声が出ました。













.webp)