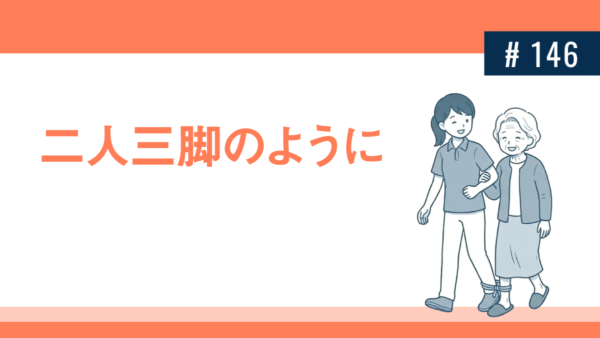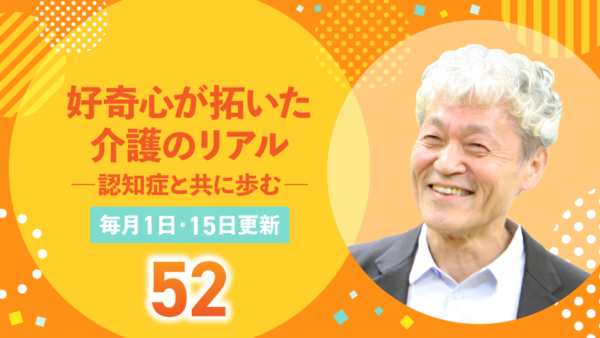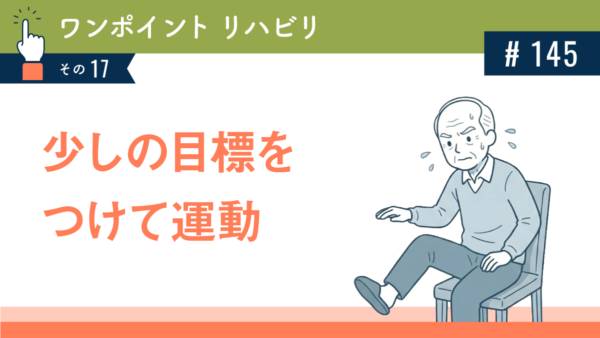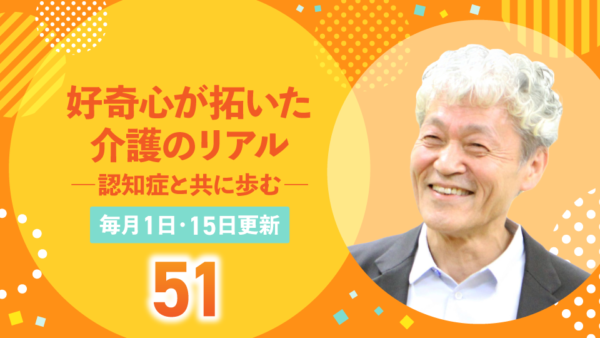ブログのコメント欄からご質問(文章に手を加えています)をいただきましたので、お応えさせていただきます。
<質問>
介護事業所で働いている私は男性入居者Aさんから、ある時を境に「花子(仮名)」と呼ばれるようになりました。花子は入居者A(以下 Aさん)さんの娘さんの名前です。
Aさんは、入居後しばらくは「家に帰る」と言って何度も介護事業所(以下 入居施設)から出て行かれ、職員は後ろからついて見守ったり車でご自宅まで送り自宅で短時間過ごして頂いたりしていました。
なぜ、ある時から花子と呼ぶようになったのか、その真相はわかりませんが、私の事を「その入居施設の施設長である自分の娘(花子)」と思ったようで「花子」と呼ぶようになったのです。
(Aさんが入居されている入居施設の施設長がAさんの娘さん(花子)なのかどうかは確認できず)
またAさんは、時を同じくして主体的な行動が増えました。
自らリンゴを剥いて来客者にお出しするような姿もみられるようになり、それらの行動を見て「Aさんがここに居る理由ができた」と判断した私は、Aさんの頭の中の設定(私のことを花子という娘さんだと思っている)に合わせる事が必要と判断し、その後、私は何度かAさんの事を「おとうさん」と呼ばせていただきました。
支援チームのスタッフと申し合わせをして互いに理解していましたが、明確なルールは存在しなかったので、この時の「おとうさん」という呼び方は、私自身のなかで「ジャッジすると×」で「ルールをつくり完全な管理下にあれば○」だと(私自身は)思っています。
似たようなケースを別の介護事業所でも経験しました。
同じ理由で私なりにジャッジすると同じ結論です。
なので、私は状況により、且つ管理下(コントロール下)にある場合に限り、呼ばれ名を変更する事、支援者が個別に1人だけ違う呼び方をするなどは「あり」だと思っています。
間違っていますでしょうか?
まずは整理
まずお伝えしなければならないことは、僕が個別の案件について「正しいか否か」を評価できませんのでご承知おきください。
僕が思うことをお伝えさせていただきます。
質問者の質問には「いくつかのこと」が混在していますので整理させていただきながら進めていきますね。
Aさんが職員のことを花子と呼ぶことをどう考えるか
僕が、認知症という状態にある方が入居できるグループホームで施設長をしていたときのことです。
あるテレビ番組の取材を受けたとき、グループホーム入居者が僕のことを「せんせい」と呼ばれ、それが放送され、その放送を見た方から「和田さんは、入居者に自分のことをせんせいと呼ばせている。許しがたい」とご批判をいただいたことがあります。
僕が入居者にどう呼ばれたいか、その「呼ばれ名」を僕が決めることはありませんので「呼ばせている」というご指摘は正しくありません。
入居者は僕を呼ぶ際に「せんせい」「あんちゃん」「おにいさん」「そこのひと」「あなた」など、その時々でいろいろな「呼び名」を使われますが、どんな「呼び名」であっても、それは全て「僕」のことであることはわかっていますので、僕がどう呼ばれようが僕のことである以上、僕はそれを受け止めるだけのことです。
だから「せんせい」と呼ばれても、いちいち「せんせいじゃありませんよ」と否定したり修正したりすることはなく、入居者にとって今の僕は「せんせいなんだなァ」と受け止めるだけで、逆にそれを「入居者支援」に生かすこともあります。
例えば「せんせい」と呼ばれたのなら「せんせい(医師か教師かはどうでもよい)」を活かさせもらい「動かないと動けなくなり身体が弱って病気やケガのもとだからできるだけ動いてくださいね」と、医師や教師の意見できる立ち位置を使って伝えるなどです。
つまりAさんが「職員である質問者のことをどう思ってどう呼ぼう」が、それを受け止めるだけで、受け止めた上で「なぜ、そういうふうに思っているのだろうか」を思考(この場合で言えば何で私を娘さんだと思っているのかな)します。
Aさんから娘と思われている職員がAさんのことを「おとうさん」と呼ぶことについてどう考えるか
もう一度質問者の話に戻しますが、
「Aさんは時を同じくして主体的な行動が増えました。自らリンゴを剥いて来客者にお出しするような姿もみられるようになり、Aさんがここに居る理由ができたと判断した私は、Aさんの頭の中の設定(花子という娘)に合わせる事が必要と判断し、その後、私は何度かAさんの事をおとうさんと呼ばせていただきました。」
とあります。
ここで気になったのは、質問者は「なぜ、おとうさんと呼ぶことにしたのか」です。
というのは、職員である質問者のことを娘の花子と思い込んだAさんについて、理由はどうあれ結果として「主体的な行動が増えた」と判断していますし、職員側から見て「ここに居る理由ができた」と判断していますので、Aさんを「おとうさん」と呼ぶ必要性が見いだせないからです。
つまり、娘さんだと思い込んでいるAさんのことを「おとうさん」と呼ぶことによって「更に生きる意欲を引き出せるんじゃないかと」いったように「支援策」として「おとうさんと呼ぶこと」を活かそうとしたのなら理解できるのですが、文面からは、そのようにも思えないからです。
また、「Aさんがここに居る理由ができた」と判断したのが「私」で「職員集団(チーム)で判断したのではない」ことも気になりました。
呼ばれ名を変えることは支援策を変えること
また、後半の質問にある「呼ばれ名を変更する」「支援者が個別に1人だけ違う呼び方をする」ことについてですが、これは「同じ質問内容」と捉えました。
こんなことがありました。
行政の運営指導(旧実地指導)がグループホームに入った時のことです。
職員は、入居者・家族が決めた「呼ばれ名」に基づいて「入居者キクさん(仮名)さんをキクちゃん」とチャンづけで呼んでいましたが行政官から「入居者をチャンづけで呼ぶのはおかしいのではないか」との指摘を受けました。
そこで、入居後の「呼ばれ名」について当方の考え方を説明したところ「ご本人やご家族が決めた呼び名なんですね。わかりました。では、それを介護計画に計画化・記録してください。また、変更する際は改めて計画化・記録してください」とのことでした。
僕は面倒だなとは思いましたが筋は通っているとも思いました。
世間一般が、公的事業である介護保険事業において利用者・入居者を呼ぶのは「氏名にさんづけ」が当たり前になっていると思われる今の社会において、そこから外れたことをするのなら外れるなりの理由と手続きを求められることは公的事業者として当然のことだと思いましたし、外れる僕らが余分に手間暇を求められるのはしょうがないと思ったからです。
画一的に「氏名をさんづけで呼びなさい」と取り決めている事業者は「世間とずれないことをやっている」ため違和感を持たれにくく、いちいち介護計画に「呼び名」を落とし込まなくても、誰も何も言わないでしょう。
でも僕の場合は、ご本人やご家族が呼んでもらいたい「呼ばれ名」を決めますから、それが結果として「氏名にさんづけ」でも「呼ばれ名」は支援策ですから介護計画で位置付けているということです。
変化するのは当然のこと
そこから質問者の質問内容を俯瞰すると、「呼ばれ名を変更することは支援策を変更するということ」であり、「支援策は必要に応じて変更するのは当然のこと」で、また、「支援者側が個別に1人だけ違う呼び方をする」というのも支援策の一環ですから「あり」だと僕は考えています。
認知症という状態においては「氏名にサンづけ(わださん)で呼んでください」と言っていた方が「わださん」では通じなくなることがあります。
実際に、お呼びしても応じてくれなくなった方がいて、その先「どう呼ばせていただけば応じていただけるか」を探し出すために家族から聞き取りました。
この方の場合は、「配偶者が呼ぶときに使用していたゆきおさん」と「仕事仲間たちが使用していた社長」で試みたところ、「しゃちょう!」に「オーッ」と応えてくれましたので、それからは職員一同「しゃちょう」と呼ぶことに変更した経験談もあります。
参考になりますでしょうか。
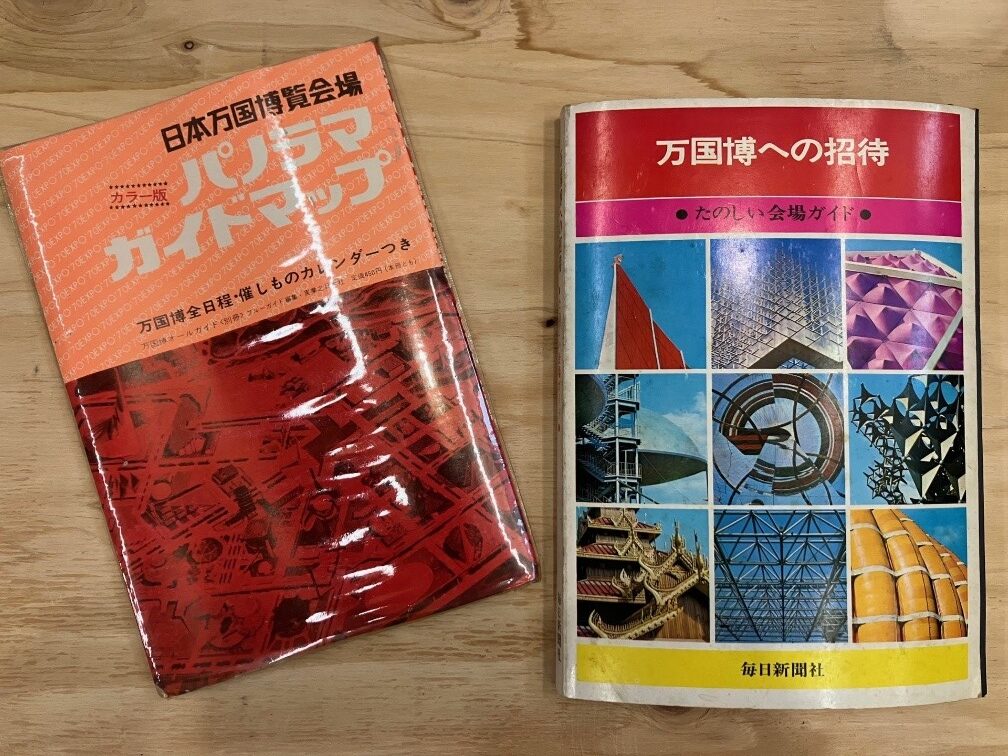
僕が中学三年生15歳の時ですから「何年持ってるの?」って感じで自分でも驚きました。
左の「カラー版」って表記しているところが時代を感じさせてくれます。








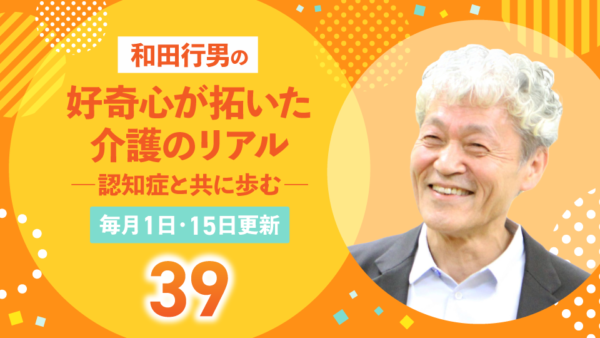




.webp)