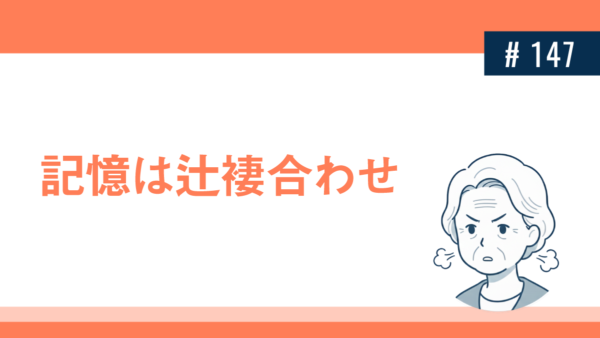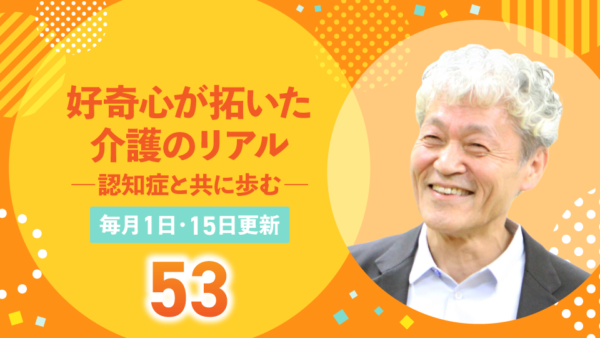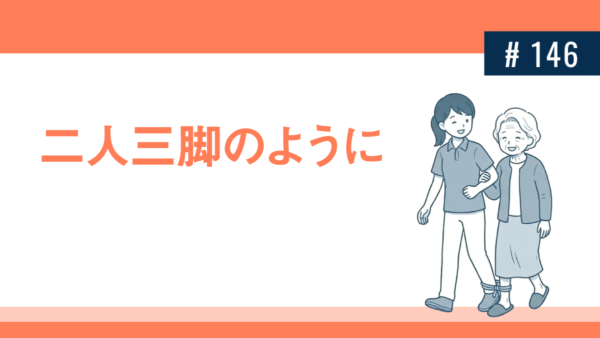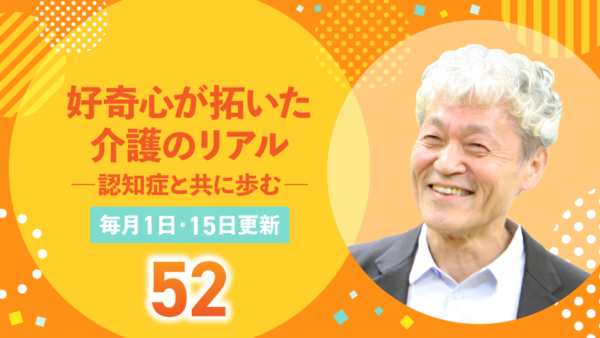前回(46話)、他法人の研修会にお招きいただいた折に「入居者の中に存在するボス婆さんに困っている。職員の言うことも聞き入れてもらえない」というご相談を受け、認知症対応型共同生活介護事業所(以下 グループホーム)の中に入って見かけた光景や少し試みてみたことについて書かせていただきました。
今回はその続きです。
グループホームを訪ねた日は「良い天気」でしたが、入居者のおひとりトメさん(仮名)が窓の外を見て「雨が降っている」と言われたことに、入居者Aさん(ボス婆さんと言われている入居者)は「雨なんか降ってないわよ」とトメさんのことを叱責されました。
この「両者の言い分の違い=トメさんとAさんとの間のズレ」に対してその場に居た職員さんは、トメさんに対して「トメさん、良いお天気ですよ」という言葉をかけられましたが「皆さんならどんな言葉をかけますか?」と、前号で投げかけさせていただいていますので、その続きについて述べさせていただきます。
事実を伝えただけで「仕事」ができていない
トメさんに「トメさん、良いお天気ですよ」と言った職員さんは、ウソ・でたらめなことは言っておらず、良い天気であることをトメさんに「事実」として伝えただけのことですから人間として間違ったことはしていません。
きっと、中学生でもボランティアの方でも別の専門職である学校の教師でも、この光景で言葉をかけるとしたらこの職員さんと同じように「事実をトメさんに伝える」ことでしょうし、言わずともこの言葉に違和感をもつことはないのではないでしょうか。
でも「認知症対応型共同生活介護事業に従事する専門職」としてはどうでしょうか。
前号で述べた「グループホームというコミュニティ(共同生活住居)において、そこに住まう者同士のズレに対して仕事をする」という観点から考えると、
その結果がどうであれ「事実だけを伝えた言葉」に意味や目的は感じず、そこに「専門性(仕事)」を感じられません。
しかもその結果は、事実を述べたAさんにすれば、事実に基づいてトメさんを諭(さと)した職員を味方につけたことになります。
つまり、「良い天気にもかかわらず雨が降っていると言うトメさんはおかしい」と言っているAさんの味方が増えたわけですから、
両者の「ズレ」を明瞭にしたばかりか、さらに大きくしてしまい、Aさんの「ボス力」を強固・強大・無敵なものにする手助けをしてしまったということで、僕はこの言葉は「Aさんのボス力をさらに引き上げてしまった」と捉えるべきだと考えました。
これでは、このグループホームで課題化している「入居者の中に存在するボスに困っている」を解決していくことにならないでしょうし、トメさんにとって暮らしにくい環境が続きますし、こうした光景を目にした他の入居者もAさんに従っていかざるを得なくなることでしょう。
ズレを埋めるための言葉
逆に、職員さんが「Aさん、トメさんにそんなきつい言い方をしなくても良いのでは」といったようにトメさんをかばう様な言葉をAさんにかけたり、「トメさん、あちらに行きましょうか」とトメさんをかばうようにAさんと引き離すかのような態度をとったりするとどうでしょうか。
ここからは推測でしかないのですが、その時のAさんの心模様を推測すると「あっちのことばっかりかばうんだから」とか「言われるのは、わたしばっかり」となってもおかしくありませんからAさんの心を痛めたり歪めたりさせてしまいかねませんし、
何より「ズレを埋める手立て」にはなりませんから、Aさんにとって職員さんが自分を上回る存在にはならず「ボス位置」は安泰ではないでしょうか。
ここで大事なことは、入居者Aさんに対して手立てをとるのではなく、「Aさんにくっついているボスのチカラを弱めること=他者とのズレを埋める」ことです。
前号で紹介したように、Aさんは僕と初めてのやりとりの中で「ボス・チカラ」を垣間見せられましたが、
僕の試みの中で他の入居者と一緒にとても楽しそうに歌われた方でもあり、僕からみればグループホームでの共同生活や個別の生活支援においてチカラになってもらえる状態の方と思いましたので、
ここの管理者たちが抱えている「Aさんに問題がある」という捉え方はしておらず、Aさんにくっついた「ボス」を課題視したということです。
つまり課題はAさんではなくAさんにとりついている「ボス」ですから、とりついた「ボス」に向けて、職員さんにはどういう言動が必要かということで、極端にわかりやすく表現すればAさんとトメさんとの関係性を断ち切れば済む話ではないということです。
では、どんな言葉がAさんの「ボス力」を弱めることに効果的でしょうか。
この日の夜に開催された職員研修会で、グループホームで見たことや少し試みたこと(前号参照)やその意図、そしてこの話を題材にしました。
他者への「?」から自分への「?」に
人は自分に「確か」があることは他者にひるむことなく表現できるように思います。
Aさんは「今、良い天気だから良い天気だと言う自分に確かがある」ため「今、良い天気なのに雨が降っている(現在進行形)」というトメさんの「間違い」に強く言えているのでしょう。
そう考えると、そもそもAさんが言う「間違ってはいない確かな今」に何か手立てをとるよりは「不確かな過去」を見出して手立てをとる方が又、それもAさん自身が自分に向けて「?」が生じるような言葉かけ(働きかけ)が、Aさん自身への「確か」に「揺らぎ」を生じやすくできるし、トメさんに向いていた「?」を弱められるのではないかと僕は考えました。
降っていた???
トメさんが「雨が降っている」と言った直後に
「降っていた雨がやんで、良いお天気になりましたね」
Aさん・トメさんに向けて職員さんが、よく聞こえるように、わかりよい言葉で、このように語りかけたとしたら、まずトメさんは自分に対して責めを受けている言葉だとは思わないでしょうし、
ひょっとしたら「ホントねェ」というように肯定され、さきほど「雨が降っている」と言ったことがなかったかのように言われるかもしれません。
いづれにしてもトメさんがどう思おうが、どういう言葉を出されようが、ここでは関係ありません。この言葉の矛先は、あくまでもAさんにくっついた「ボス」に対してです。
では、この言葉を受けたAさんにくっついた「ボス」の心模様を推測してみましょう。
人は過去(記憶)には脆いものです。
学問や生理的なことは専門家に任せるとしても、脳は過去に入ってきた情報を全て記憶化し想起できるようにしているわけではなく、情報の中からストックすること・受け流すことを仕分けしているのではないでしょうか。
だから「誰かに会ったこと、何かを話したこと」は想い起せても「誰に会ったか、何を話したか」まで正確に想い起せないもので、それを誰も異常だとは思っておらず「そういうものだ」と何となく共有し合えていますから「共通となりうる不確か」は受け止められやすいものです。
「降っていた雨が」は過去で
「良いお天気になりましたね」は今ですね
この言葉の中の「良い天気は」は、「今の良い天気=事実」に対してAさんと共有できる「今に向けた言葉」なので、言葉をかけた職員とAさんの間に「ズレ」は生じませんが、「降っていた雨が」は、Aさんとトメさんとの間ではなくAさんと職員さんとの間でズレが生じるはずです。
きっとAさんにくっついたボスは強い口調で「雨なんか降ってないわよ」とトメさんに言ったものの、職員さんの言葉に一旦は「エッ、雨、降っていたかしら」と自分の記憶に気が向くことでしょう。
しかも「過去」のことで「不確か」なことですから、「雨、降っていた?」と自分の記憶を確かめにかかる言動をとってもおかしくなく、その時点でトメさんを責めている場合じゃなくなるはずです。
また、自分よりも若い、若く見え・若く思える職員さんからの「過去に向けた言葉」との闘いですから、Aさんが「引き下がらざるを得ない(自分に疑いを持つため強く出られない)」と思う確率はゼロではないはずですし、
Aさんの「ボス力」が闘う相手はトメさんではなく職員さんですから、そこはどうなろうが職員さんが受けて立てば済む話でもあります。
しかも、次の瞬間に職員さんから「良いお天気になりましたからお買い物に行きましょうか」と角度を変えたお誘い等の言葉をかけることで、そこからは別の方向へ流れを変えていける可能性をも秘めます。
又、その状況を見ながらAさんの「モヤモヤ」を解消していけるような支援策(職員さんから投げかける言葉や行動)をかぶせ、更に「かぶせる支援策」がAさんにとって「快」を感じるようなことであればあるほど、そのモヤモヤは過去となって薄まっていくことでしょうし、
そもそも「不確か」なことですからAさんが酷くダメージを被るとは考えにくいですし逆に、トメさんに事実をもって強く出た「ボス力」にとってはダメージとなることでしょう。
もうひとつ想定できるのが「雨なんか降ってないわよ」とAさんが反論してくることですが、この場合でもAさんの矛先はトメさんではなく職員さんなので、これも受けて立てば済む話で、この場合は「どう受けるか」です。
Aさんに「降ってましたよ」と仕掛けていく、「さあ、出かけましょう(買物に行きましょう)」とそらす、「降ってたんですけどねェ・・・」とボソボソつぶやく、「そうだ、Aさんにお願い事があったんですよ」とかわすなど、様々な「受け手」があるかと思いますが、
ここで大事なことはAさんにとってとても興味関心がもてる言葉が効果的だということです。
例えば、とてもコーヒーが好きな方なら「Aさん、コーヒー淹れましょうか」ですし、血圧を気にしている方なら「血圧図りましょうか」もありますし、息子さんのことが気になっている方なら「そういや、息子さんから電話するように言われていました」も良いでしょう。
何がAさんにとって興味関心をもてるかは日常的にかかわっている職員さんたちが一番知っていることでしょうからネ。
人は「意味や目的の重たい方に行動する生き物」で、「雨が降っていたかどうかを確かめること」よりも意味や目的を感じられることがあれば、必ずそちらに脳も身体も向きますから。
後手から先手へ
和田さん的表現をすれば、晴れているのに雨が降っていると言うトメさんに対してAさんは「事実を言う」ことでトメさんを責めて「先手」をとっていて、
Aさんが事実を言っているため、それにどう対処するかを考える職員さんは、その時点で「後手」になってしまっているということです。
このままでは相談事である「職員の言うことも聞いてもらえないんです」をひっくり返せるわけもなく、ずっと後手に回ったままになってしまうでしょうし、現に、その相談を持ち掛けてきていることが、その状況を表しています。
この場合で言えば、「職員さんが考え込む状況が後手」で「Aさんが考え込む状況にもちこむことが先手を取り直すということ」なのですが、
それが「不確かな過去を持ち出す手を打つ(言葉を出す)」ことで「職員さんが考える」から「Aさんが考える」に場面を転換できればAさんがトメさんを責めたボスとしての先手感は薄れるでしょうし、薄まったところへ次々と手をかぶせていくことで、どんどんボス力を弱め、職員さん側が先手を取り返せるということです。
こんなことを介護保険事業利用者・入居者との間でやっている和田さんは不適切と思われますよネ。
自分でも、そう思うところが無くはないですが、僕の仕事を僕が突き詰めていくと、思考と実践がそうなってしまうんです。
きっと僕の中でこうしたことは世間一般「人間社会にある普通のこと」だと思っていて、その「普通のことが必要だ」と考えているからなんでしょう。
いかがでしょうか。

ちなみに北海道の皆さんから「和田さんが雪をもってきた」とやっぱり言われてしまいました。というのも北海道を出る日は晴れ予報だったし現に晴れましたからね。









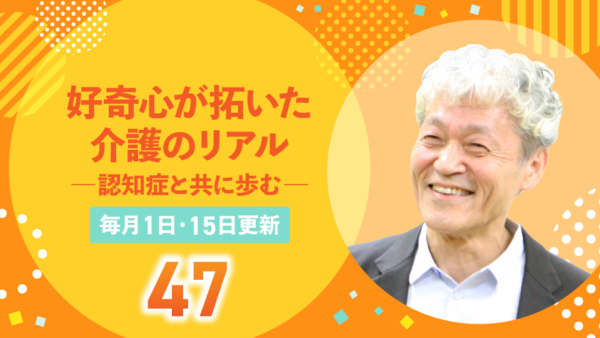




.webp)