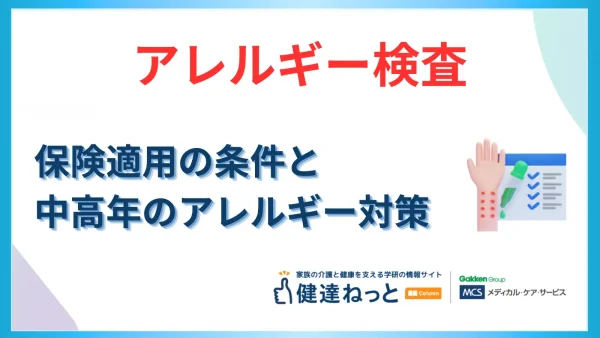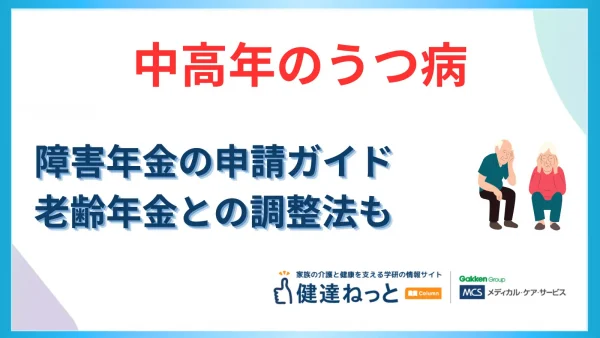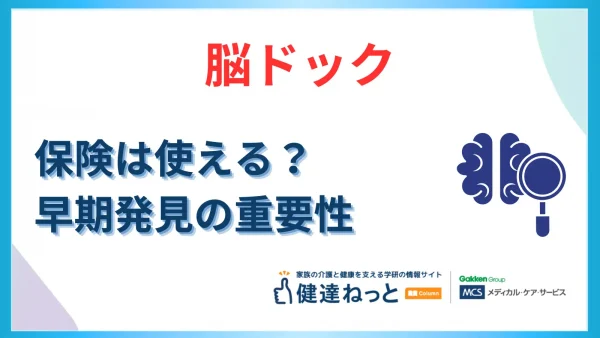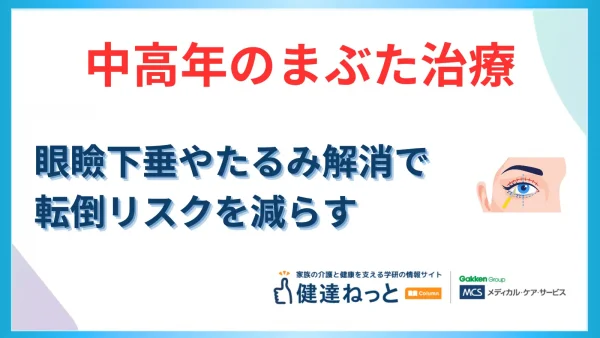配信サービスで観る
あらすじ
立花茂造は84歳。妻の突然の死をきっかけに認知症となってしまった。
息子の信利と嫁の昭子、孫の敏と同居する茂造だが、近所を徘徊したり、鍋の煮物を手づかみで食べたりと奇行が目立つ。
働く女性である昭子は、仕事と介護の両立に疲れ果てていく。
ある雨の日、道端で泰山木の花を見つめる茂造の姿を見て、昭子は気づく。茂造には美しいものを感じる心が残っている、と。
介護の困難さと家族の絆を描いた、日本の認知症映画の先駆的作品。
特徴・見どころ
日本映画史において、「介護」と「認知症」というテーマを社会に広く問いかけた金字塔、それが『恍惚の人』です。
有吉佐和子のベストセラー小説を巨匠・豊田四郎監督が映画化しました。
1973年の公開から半世紀以上が経過した現在、改めて本作が持つ力強さと、私たちに問いかけるメッセージの重さをご紹介します。
森繁久彌の熱演と「認知症」を社会問題化した衝撃
本作の最大の見どころは、主演・森繁久彌の鬼気迫る演技にあります。
当時60歳だった森繁が、84歳の認知症の老人・立花茂造を見事に演じきりました。
単なる「もの忘れ」といった表面的な描写にとどまりません。
徐々に記憶が薄れ、幼少期に戻ったかのような言動を見せる茂造の姿は、観る者の胸を締め付けます。
その鬼気迫る役作りとリアリティは、圧巻の一言です。
彼の演技によって、「恍惚の人」という言葉は爆発的な流行語となりました。
それまでタブー視されがちだった「老い」や「認知症」の問題が、一気に社会の共通認識として広がるきっかけを作ったのです。
家族が直面する混乱、愛情、そして葛藤。
この作品がなければ、現代の私たちが認知症について語る言葉も、また違ったものになっていたかもしれません。
50年の時を超え、現代に問いかける介護の本質
『恍惚の人』が名作として語り継がれる理由は、そのテーマの普遍性にあります。
公開当時は「老人問題」として捉えられていましたが、描かれているのは現代の私たちが直面する「介護」そのものです。
茂造が見せる特有の行動や言動。
例えば、日々の習慣や特定の物事への強い執着は、現代でいう認知症のこだわりと深く通じるものがあります。
家族は、そんな茂造にどう向き合えばよいのか悩み続けます。
特に、嫁である昭子が介護に直面する現実は壮絶です。
その姿は、「介護」と「生活の介助」の境界線が曖昧になっていく過程を生々しく映し出します。
精神的なサポートとしての「介護」と、日常の動作を手助けする「介助」。
この二つのバランスの難しさは、介護と介助の違いがどこにあるのかを、私たちに改めて考えさせます。
50年以上前の作品でありながら、介護者の孤独や社会的サポートの必要性など、現代の介護問題の核心を突いているのです。
『恍惚の人』は、単なる過去の名作映画ではありません。
家族のあり方、老いとの向き合い方、そして「尊厳とは何か」を問い続ける、現代の私たちへのメッセージです。
介護に直面している方、これから向き合う可能性のある方、そして専門職として関わっている方。
すべての人にとって、この作品は多くの気づきと深い共感を与えてくれるはずです。
日本が初めて「認知症」と真正面から向き合った、この歴史的傑作の重みをぜひ体感してください。