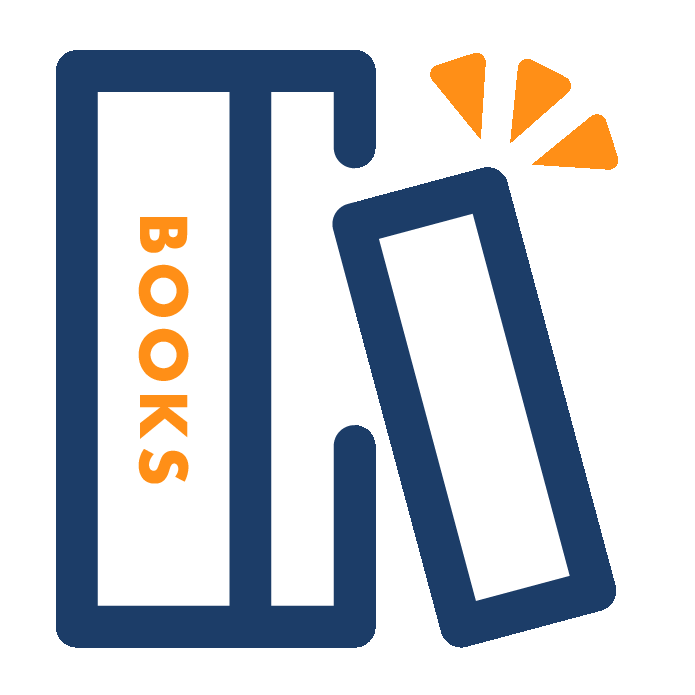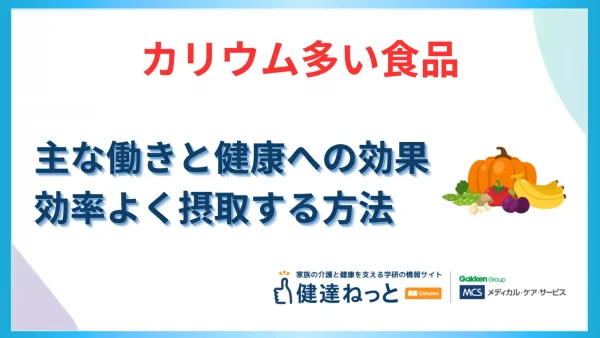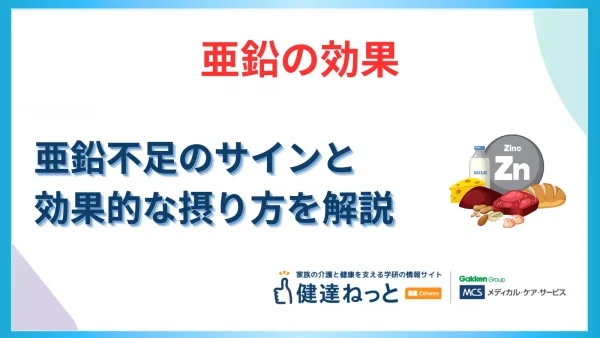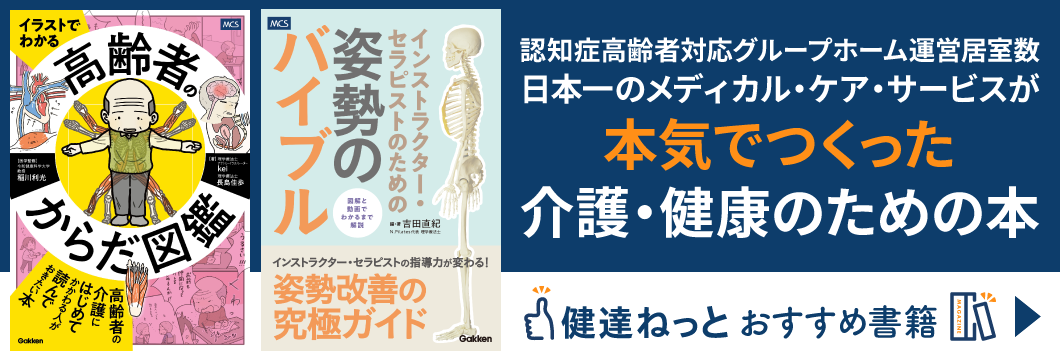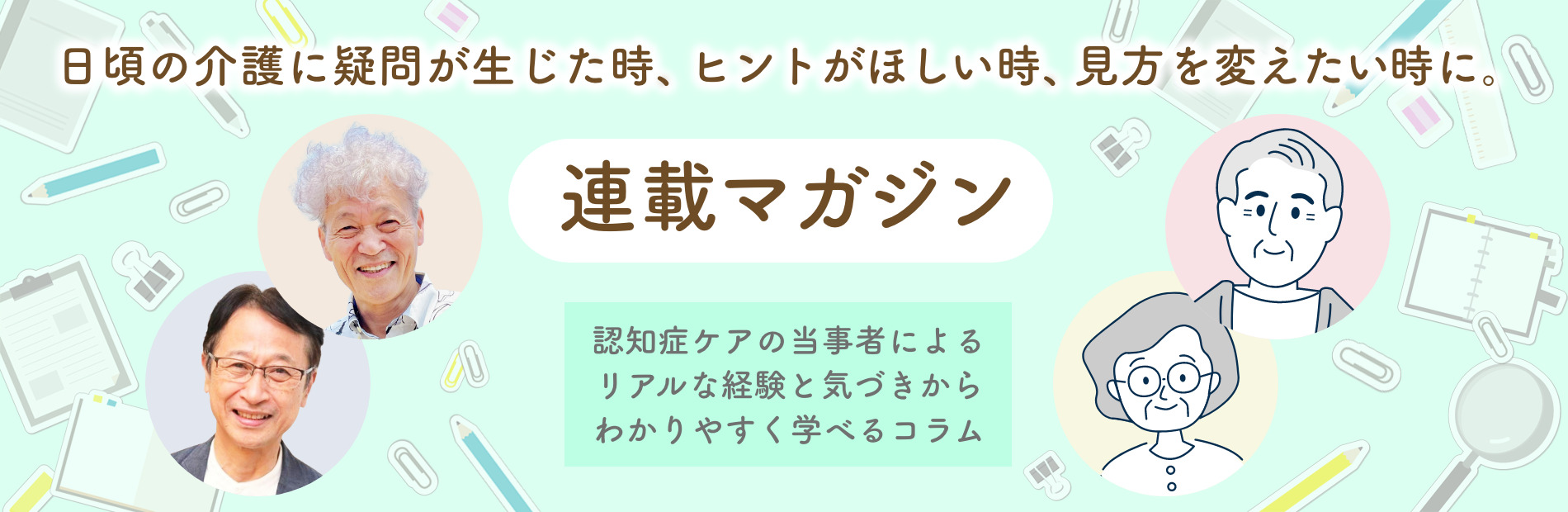配信サービスで観る
あらすじ
昭和39年、小説家の伊上洪作は父が亡くなり、母・八重の面倒を見ることになる。
幼少期に母と離れて暮らしていたため距離を置いていた洪作だったが、妻や3人の娘、妹たちに支えられ、自身の幼いころの記憶と八重の思いに向き合うことになる。
八重は徐々に認知症の症状が進み、薄れゆく記憶の中で息子への愛を確かめ、洪作はそんな母を理解し、次第に受け入れられるようになっていく。
特徴・見どころ
昭和を代表する文豪・井上靖の自伝的小説を、役所広司さん、樹木希林さん、宮崎あおいさんといった日本映画界を代表する実力派キャストで映画化した、深く心に響く家族の物語です。
本作が単なる「お涙頂戴」の物語と一線を画すのは、認知症で記憶を失っていく母と、息子との間に横たわる「確執」の歴史に真正面から向き合っている点にあります。
主人公の小説家・伊上洪作(役所広司)は、幼少期に「母に捨てられた」という心の傷を抱えたまま、大人になりました。
その記憶は、彼の人生に重い影を落とし、母・八重(樹木希林)との間には、ずっと埋められない溝がありました。
しかし、その母が認知症を発症し、記憶が徐々に失われていきます。
失われる記憶と、蘇る「真実」
物語の軸となるのは、母の介護を通して、洪作が自らの「記憶」と向き合うプロセスです。
母が失っていく記憶と反比例するように、洪作はこれまで封印してきた、あるいは目をそらしてきた過去の「真実」の断片を拾い集め始めます。
母がなぜ、自分を「捨てた」のか。
それは、果たして本当に「捨てられた」という事実だったのか。
認知症の母が時折見せる言動や、ふと口にする言葉が、洪作の揺るがないと思っていた記憶を揺さぶっていきます。
この構成は、ミステリーのようでもあり、観る者も洪作と共に「記憶の旅」に引き込まれていきます。
幼少期の記憶と現在が巧みに行き来し、母と子の複雑な愛情が、丁寧に、そして切なく紡がれていくのです。
圧巻の演技が問いかける、家族の絆
本作を語る上で欠かせないのが、母親・八重を演じた樹木希林さんの圧巻の演技です。
この演技で第36回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞したことも、その凄まじさを物語っています。
ただ記憶を失っていく姿を演じるのではなく、混乱の中にいながらも、その言動の奥底に「息子への愛」を確かに感じさせる、深遠な演技は必見です。
「母に捨てられた」と信じる息子と、「息子を愛し続けた」母。
認知症というフィルターを通して、二人のすれ違った時間が、ゆっくりと溶け合っていくラストは、涙なしには見られません。
認知症と家族の絆とは何か、そして「記憶」と「愛」の関係とは何かを、深く問いかけてくれる不朽の名作です。