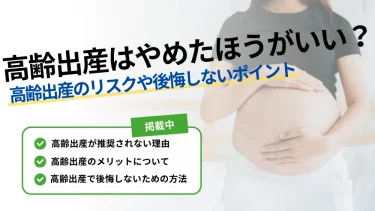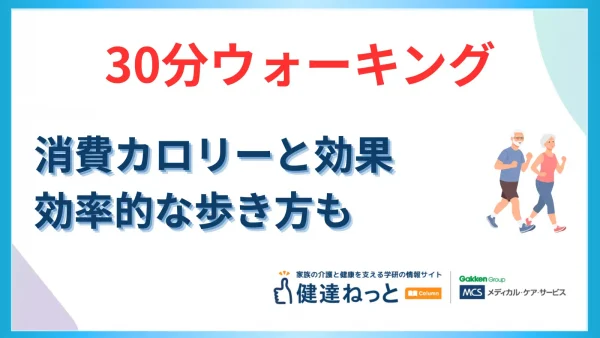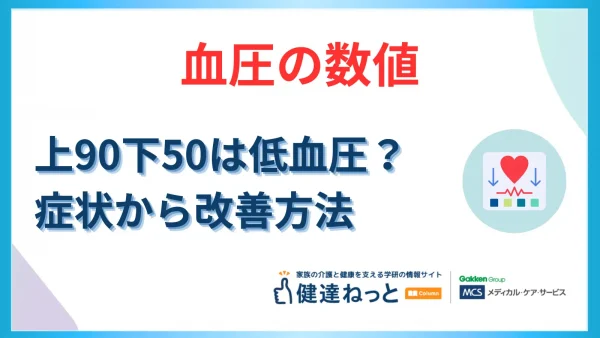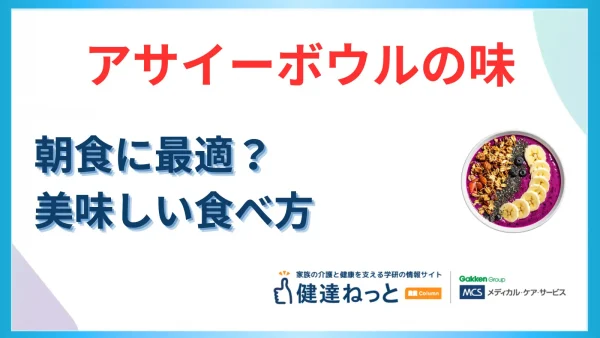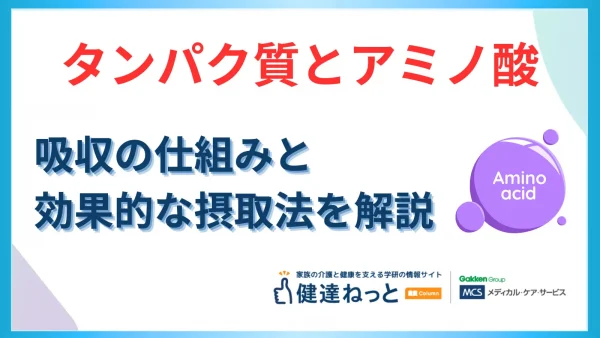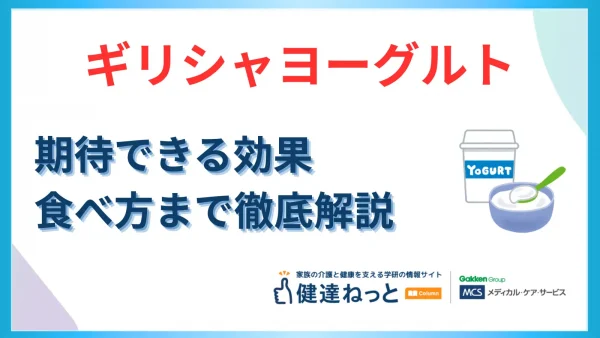「高齢出産によるダウン症について知りたい」
「ダウン症を抱える子どもを産んでしまったことを後悔しているかもしれない」
高齢出産によって子どもを出産した方、あるいは高齢出産を予定している方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
出産による母親の体や子どもへの影響は、母体の健康状態やパートナーの健康状態によって大きく変化するものです。
中には、高齢出産によって合併症に感染したり、子どもが病気を抱えてしまったりといったケースもあります。
そこで本記事では、高齢出産によるダウン症について以下の点を中心に詳しく解説します。
- 高齢出産によるダウン症の確率について
- 高齢出産によってダウン症の子どもが生まれる理由について
- 高齢出産によるダウン症を事前に確認できるのかについて
高齢出産によるダウン症にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
高齢出産とは?

まずはじめに、高齢出産についてご紹介します。
高齢出産とは、一般的に35歳以上での出産を指し、2人目以降を35歳以上の年齢で出産した場合も高齢出産に該当します。
近年は、女性の社会進出や経済的な問題などから、高齢出産を経験する女性の割合も増加している傾向にあります。
経済的に安定してから出産したい、医療技術なども発展しているから安心感がある、といった声も多い一方で、それに伴って高齢出産によるリスクなども注目されています。
高齢出産でも健康な子どもを産み、母子ともに健康な状態で生活されている方も多いですが、高齢出産によるリスクは多岐に渡るため、リスクや体への影響についてしっかりと把握しておくことが重要です。
スポンサーリンク
高齢出産によるダウン症の確率

次に、高齢出産によるダウン症の確率についてご紹介します。
結論から述べると、高齢出産によるダウン症の確率は、母親の年齢によって異なります。
また、高齢出産によるダウン症の確率は高齢になればなるほど上昇するとされており、20歳で出産した場合は約0.05%、30歳は約0.01%、40歳となると約3-4%程度にまで昇るといわれています。
若い年齢で出産したからといって子どもがダウン症を抱える確率がゼロではないということは、頭に入れておくと良いでしょう。
次の記事では、高齢出産のリスクや発達障害について詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
「高齢出産はダウン症のリスクが高まるって本当?」「具体的な確率やリスクを軽減する方法を知りたい」高齢出産を検討されている方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。本記事では、高齢出産におけるダウン症の確[…]
高齢出産によってダウン症の子どもが生まれる理由

次に、高齢出産によってダウン症の子どもが生まれる理由についてご紹介します。
高齢出産によってダウン症の確率が上昇する主な理由は、歳を取るごとに卵子の質が低下するためであるといわれています。
女性の卵子には、子どもの染色体を正確に分配する機能が備わっていますが、高齢になるとこの機能がだんだんと弱まってしまいます。
染色体は、卵子と精子にそれぞれ23本存在しており、これらが合わさって胎児が形成されていきます。
しかし、染色体異常が起こると、21番目の染色体の不分離が起こり、結果としてダウン症という症状が赤ちゃんに現れてしまうのです。
また、卵子の健康状態は、母親の年齢によって左右されますが、その他にも食事や運動などによる健康への影響も関わっています。
ダウン症などの症状は、出産前に分かる?

では、子どもが抱えるダウン症などの症状は、出産前に分かるものなのでしょうか?
結論から述べると、出産以前の段階で、子どもが抱えるダウン症を検査することは可能です。
出産以前の段階で行われる検査にはいくつかの種類があり、最も受検者が多いのがNIPT(新型出生前診断)であるといわれています。
NIPT(新型出生前診断)は、母体の血液を採取するだけで、胎児の染色体異常の可能性を高い精度で調べられる検査方法であり、妊娠10週目以降から検査が可能となります。
しかし、NIPT(新型出生前診断)はあくまで精度の高いスクリーニング検査であり、確定的な診断にはなりません。
確定的な診断を受けたいという場合は、絨毛検査(妊娠10週目〜15週目)や羊水検査(妊娠15週目〜18週目)を受検する必要があります。
また、NIPT(新型出生前診断)や絨毛検査、羊水検査にかかる費用は15万円〜20万円程度となっています。
高齢出産による子どもや母親への影響

ここでは、高齢出産による子どもや母親への影響について、以下の7つの点をご紹介します。
- ダウン症などの先天性異常を抱えるリスクがある
- 子どもの知的能力が低くなるリスクがある
- 早産や難産、流産のリスクがある
- 帝王切開率が向上する
- 母親が合併症に感染するリスクがある
- 子育てが負担になる可能性がある
- 親子間の世代のギャップ
ダウン症などの先天性異常を抱えるリスクがある
高齢出産による子どもや母親への影響の1つ目は「ダウン症などの先天性異常を抱えるリスクがあること」です。
本記事でもご紹介した通り、母親が持つ卵子の質は、年齢に応じて低下します。
卵子の質は、子どもの発達や健康状態に直接影響するため、高齢出産になればなるほど、子どもが抱えるダウン症やその他の先天性異常のリスクは高くなってしまいます。
また、高齢出産によって子どもが抱える病気には、ダウン症の他にもエドワーズ症候群やパトー症候群などがあります。
子どもの知的能力が低くなるリスクがある
2つ目は「子どもの知的能力が低くなるリスクがあること」です。
高齢出産では、ダウン症などの病気を発症せずとも、卵子の質の低下によって子どもの知能が低下するというケースもあります。
これは、早産や低出生体重児によって脳の発達が妨げられることが原因であるといわれていますが、教育環境や両親の関わり方などによっても影響を受けるため、一概に高齢出産が原因であるとはいい切れません。
早産や難産、流産のリスクがある
3つ目は「早産や難産、流産のリスクがあること」です。
高齢出産では、母体の健康状態が若い時期と比較して良好ではないケースが多く、子宮や卵巣の機能が低下し、妊娠の維持が難しくなることがあります。
このような場合では、本来の定められた時期に出産することが難しくなったり、場合によっては流産となったりしてしまうケースもあります。
帝王切開率が向上する
4つ目は「帝王切開率が向上すること」です。
高齢出産となると、母体の合併症のリスクが高まり、これらの管理のために帝王切開が選択されることが多くなります。
また、高血圧や糖尿病などの基礎疾患を持つ可能性が高く、これらの疾患も帝王切開の適応となることがあります。
母親が合併症に感染するリスクがある
5つ目は「母親が合併症に感染するリスクがあること」です。
私たちの体は、男性や女性に限らず常に病気や感染症を発症するリスクを抱えています。
無論、それは妊娠/出産する女性でも同様です。
そんな中、出産は生理的変化や健康状態の不安定さをもたらすため、正常で健康な状態の時と比較して合併症に感染してしまうリスクが向上してしまうのです。
代表的な合併症には、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などが挙げられます。
子育てが負担になる可能性がある
6つ目「子育てが負担になる可能性があること」です。
高齢出産後の子育ては、若い親に比べて体力的かつメンタル的な負担が大きくなる可能性があります。
子育てでは、夜間の授乳や日中の世話など、体力を要する作業が続くため、疲労が蓄積しやすく、それに応じて育児ストレスも高まりやすい傾向があります。
また、高齢となると、親の介護の時期と重なる可能性があり、時間的かつ精神的な余裕がなくなってしまうケースもあります。
経済面や経験値などの側面から見ると、高齢出産によるメリットが大きいと感じることもありますが、それに応じて子育てにおける体力的かつメンタル的な負担が大きくなることは、覚えておく必要があるでしょう。
親子間の世代のギャップ
7つ目は「親子間の世代のギャップが生まれること」です。
私たちも経験している通り、子どもと親とでは生きている時代が大きく異なり、社会的な状況や文化、価値観なども変化します。
特に現代はテクノロジーなどの発展も著しいため、世代が一回りも二回りも異なると親子間の価値観が合わず、考え方に大きな相違が生まれてしまうこともあるでしょう。
高齢出産についてお悩みの方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
「高齢出産はやめたほうがいいの?」「高齢出産をやめたほうがいい理由を知りたい」現在妊娠している方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、高齢出産をやめたほうがいいといわれる理由について、以下の[…]
後悔しない!ダウン症を抱える子どもとの向き合い方

次に、ダウン症を抱える子どもとの向き合い方について、以下の5つに分けてご紹介します。
- 子どもの状態や環境を理解する
- 常に子どもの味方であることを意識する
- ,能力に合わせた学習環境を用意する
- 適切な療育や支援を受けさせる
- 積極的にコミュニケーションを取る
子どもの状態や環境を理解する
ダウン症を抱える子どもと向き合う際に意識すべきことの1つ目は「子どもの状態や環境を理解すること」です。
ダウン症は染色体異常によって引き起こされる先天性障害ですが、その症状や程度は個人によって大きく異なります。
そのため、保護者がしっかりと子どもと向き合い、個人としての能力や強み、不得意なことなどを把握してあげることが、非常に重要です。
常に子どもの味方であることを意識する
2つ目は「常に子どもの味方であることを意識すること」です。
ダウン症を抱える子どもは、日常生活や学校生活、あるいは対人関係などにおいて、困難を抱えることが多いといえます。
そんな中、本人が抱えるストレスや心理的な不安を最小限に抑えるためには、保護者が子どもに寄り添い、味方であることをしっかりと伝えることが大切になります。
また、それと同時に、子どもの個性や意思を尊重し、過度の干渉や保護にならないよう注意を払うことも重要です。
能力に合わせた学習環境を用意する
3つ目は「能力に合わせた学習環境を用意すること」です。
ダウン症を抱える子どもの学習において、適切な環境を用意することは必要不可欠です。
認知能力には長けているが言語能力が低い傾向にある、視覚的な情報処理が得意だが情報整理は不得意など、ダウン症を抱える子どもの個性や傾向は様々です。
まずは個人の能力をしっかりと把握した上で、子どもが極端に大きな負担を抱えることなく楽しみながら学習を進められるような環境を用意することをおすすめします。
適切な療育や支援を受けさせる
4つ目は「適切な療育や支援を受けさせること」です。
症状の程度にも寄りますが、ダウン症を抱える子どもは、専門的なセラピーや特別支援教育が必要なケースが多いといえます。
そのような場合は、地域の支援センターや障害者福祉サービスを積極的に活用し、子どもの成長段階に応じた支援を受けることが重要となります。
また、定期的な健康診断や専門医による診察を通じて、ダウン症に関連する健康上の問題を早い段階で発見し、適切に対処することも大切です。
積極的にコミュニケーションを取る
5つ目は「積極的にコミュニケーションを取ること」です。
ダウン症を抱える子どもとの積極的なコミュニケーションは、子どもの言語発達や社会性の向上に役立つだけでなく、子どもの情緒面や精神的な安定にも大きく貢献します。
また、言語だけでなく、ジェスチャーや表情、絵カードなどの視覚的な道具などを活用し、多様なコミュニケーション手段を用いるのも良いでしょう。
ダウン症の子どもを出産したことを後悔している方へ

ダウン症を抱えたお子さまの誕生に、複雑な思いや不安を抱えている方も多いかと思います。
後悔や不安を感じるのは自然なことです。
しかし、あなたのお子さまは、かけがえのない存在です。
子どもには、ダウン症や一般的な子どもに関係なく、一人ひとりに個性があり、人間として大きく成長する可能性を秘めています。
最初は戸惑いや困難、子どもに対する罪悪感を感じることもあるかもしれませんが、現代ではダウン症を抱える子どもを対象とした多くの支援や療育の選択肢があります。
同じ境遇の家族や専門家のサポートを受けることで、新たな視点や希望が見つかることもあるでしょう。
また、お子さまとの日々の触れ合いの中で、予想もしなかった喜びや発見、感動もあるはずです。
その小さな瞬間を大切にしながら、一緒に成長していく過程を楽しんでいただければと思います。
スポンサーリンク
高齢出産 ダウン症 後悔 まとめ
ここまで高齢出産によるダウン症についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 高齢出産によるダウン症の確率は、母親の年齢によって異なり、20歳で出産した場合は約0.05%、30歳は約0.01%、40歳となると約3-4%程度である
- 高齢出産によってダウン症の子どもが生まれる理由は、母親の卵子の質が低下することが原因である
- 高齢出産によるダウン症は、出産以前に確認することが可能である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。