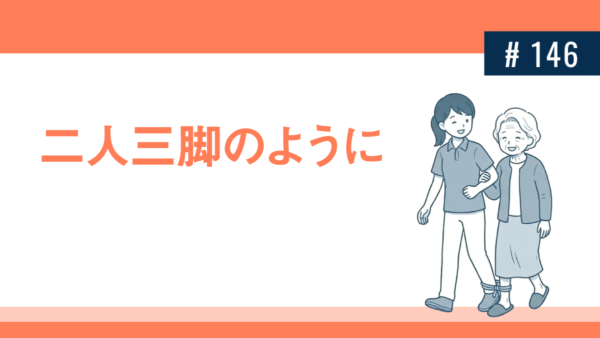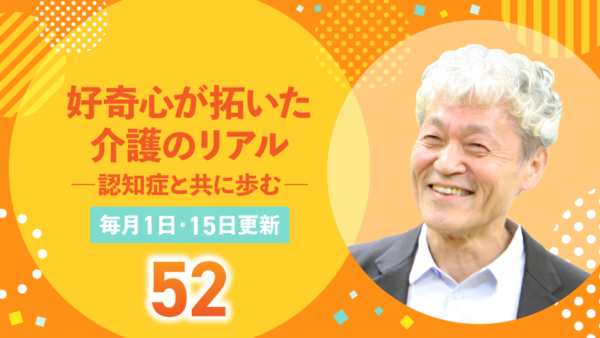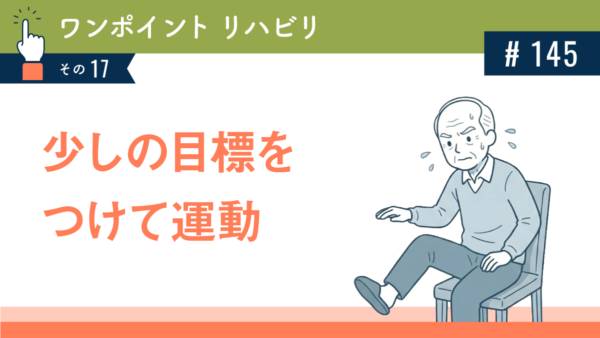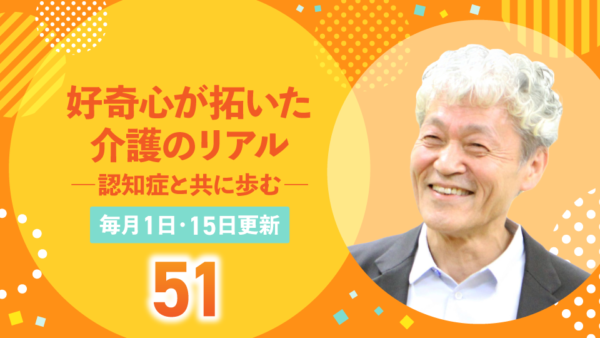前号で「一筋縄ではいかない」と結びましたが、それはお気づきのように「相手があるから」に他ありません。
相手とはもちろん、僕らが支援をさせていただく相手のことですから、介護保険事業を利用される・入居される方々のことです。
お金を払っているのに払った私が動かないといけないっておかしい!
僕がどう思おうが考えようが、利用者や入居者が認知症という状態にあろうがなかろうが、相手には相手なりに「思う」や「考え」があります。
「ここの食事は高いのよ」
小規模多機能型居宅介護事業所(以下 小規模多機能)に登録して通いサービスに来ているトメさん(仮名 認知症という状態にある)が他の利用者(認知症と言う状態にある方々)に話します。
「しかも高いお金とっておきながら、私たちに作らせようとするのよ」
認知症対応型共同生活介護事業所(以下 グループホーム)でも職員の言葉に入居者が言い返します。
「Aさん、一緒にご飯を作りましょうか」
「若いあなた方がいるのだから、あなた方がつくりなさいよ」
グループホームの入居相談に来られた家族からは
「ヘーッ、うちの親が家事をやるんですか。初めて聞きました。かわった介護施設ですね」
あるグループホームでは開設してからずっと職員が入居者の食事を作っていましたが、僕の著書:大逆転の痴呆ケア(2003年中央法規出版社 現廃刊)を読んで考え方を変えることになり入居者に法人代表者が語りかけました。
「今までは私たちが食事を作って提供させていただいてきましたが、明日からは、こうこうこういう理由で皆さん自身がお買い物できるように・お食事を作れるようにサポートさせていただくやり方にかえさせていただきますので、よろしくお願いします」
そう伝えると大ブーイングが起きたと聞きました。
培われてきた国民感情・その国民が介護保険制度従事者になる
介護保険制度が施行される前から「介護」は国民の中では「してくれる」となっていたでしょうし、支援する職業人も「してあげる」が普通のことでしたから無理からぬことです。
合わせて、介護職員、介護福祉士といった職業とは別に家政婦という職業もあり、歴史ある家政婦の仕事は基本「してあげる」で、介護保険制度の「有する能力に応じ自立した日常生活が営めるように」とは別物ですが、国民からすれば「同じ」であり「同じ=してくれる」でしょうからね。
随分前のことですが、いくつかの市民講演会で「介護って何だと思いますか」って参加者の方々に訊ねると「身の回りのお世話をしてくれること」「いろいろなことをしてくれること」って多くの方が言っていたことからも介護を受ける側は「介護=してくれること」であり、介護を提供する側は「介護=してあげること」が根付いていたことは間違いなのではないかと思います。
介護保険法はそれをひっくり返したものと僕は思っていますが、現状はまだまだ「根付き」をひっくり返せてはいませんし、前述の利用者・入居者の言葉は、いまだに出てきますからね。
ちなみに僕は、例えば介護保険制度の指定を受けていない有料老人ホームなど介護保険制度以外の事業で「介護=してあげる」となっていても何ら違和感をもっていないのですが、その違いは「介護保険制度によって運営される介護事業は公金によって運営される公務だと捉えているから」です(これは又の機会に書かせていただきます)
介護保険制度における「できるように支援する」は「サービス」とズレを生みかねない
1990年代半ばに老人デイサービスB型(介護保険法でいう通所介護)・E型(介護保険法でいう認知症対応型通所介護)、機能訓練事業(老人保健法で展開されていた事業で40歳以上が対象で脳血管性疾患後遺症の方が多く利用されていた)の中で
「自分でできることは自分ですることができる環境の整備、自分でできるように支援する支援策、利用者同士が互いに助け合って過ごせるようにする環境の整備、そのための支援策」を打ち出したときも、
まずは職員間ですり合わせ、次に利用者家族とすり合わせ、措置の時代のデイサービス等は行政サービスなので行政職員とのすり合わせなど手順を踏んでから実行しましたが、
その理由は「あそこへ行くとお茶は自分でいれないといけない」「職員は見ているだけなのよ」「サービスがなってない」など、必ずクレームになると思ったからです。
行政サービスを受けている利用者・その家族からすれば「してもらう」は当たり前でしたからね。
今も多くの方が介護保険事業を「介護サービス」と言われますので、いまだに国民に「サービス」だと思わせてしまっていますが、産業分類的にも「介護保険事業はサービス業ではない」ことからすれば、おかしなことになっています(これも又、改めて書かせていただきます)。
「納得を継続できない」のであれば「線でつなぐ」
相手には相手なりの考えがある。
だからこそ「相手とすり合わせながら行う」という当たり前の事であるにもかかわらず一筋縄でいかないのは、その相手に「記憶障害」をきたす病気があるということです。
つまり、説明した時に納得はしてくださるのですが「その納得を病気によって維持しきれない状態にある」わけですから、一度伝えたから大丈夫とはなりません。
つまり「点」ではダメで「線」での対応が必要です。
「みなさんには長生きしてもらいたいというよりも元気で生きていただきたい。そのためには動かないとね。じっとしていたら動けなくなりますから」
この仕事に就いて以降、利用者・入居者と話をしてきて実感しているのは「長く生きる」というメッセージよりも「元気で」の方がまた、「動かないと動けなくなる」という言葉はとてもわかりやすく、利用者・入居者やその家族に届きやすいということで、ことあるごとに皆さんに「元気で生きてもらいたい」「動かないとね」を吐きまくってきました。
僕の言葉で言えば「メッセージの線化」ということですが、単発的な「点」では忘れ去られてしまいますからね。
動けるを探り・動きを止めない支援
介護保険事業を利用する方・入居される方の多くは、全く動けない方ではなく「動き」に「意思表示できる」まで含めて捉えると、まだまだ「動き」を失ってはいないことが見えてきます。
ガンさん(仮名)が退院して戻ってきたとき車いすに座るガンさんに「ガンさん、生きててよかったね」って声をかけると同時にガンさんに見えるように手を差し出したのですが、差し出した僕の手に自分の手を重ねようと必死に手を動かそうとしていました。
「オッ! ガンさん、まだまだ元気じゃないですか」
立っていることさえ維持できなくなり言葉も失い「何にもできない状態」に見えるガンさんでしたが「意思をもって動ける状態・動こうとする状態」であることを確認でき、とても嬉しく思いました。
その光景を見ていた家族も泣いていらっしゃいました。
これも僕が「してあげる」の考えでガンさんの手を握りにいっていたら「ガンさんが自ら手を差し出そうとする行為は不要」となり、結果、僕がガンさんの意思表示の機会を奪ってしまっていたでしょうからね。
動けるを知ったうえで動きを止めるのはあり
つまり「してあげる」では「動けるか否か」は見えてこないし、そもそも「動ける・動こうとする状態かどうかを探ろうともしていない」の現れが「してあげる」だと僕は思っていますし、付け加えるならば、動けるか否かを探った先で「利用者・入居者が動けることはわかった。だけど、これは・今日は、僕がしてあげる(させてもらう)」という行動は「ありだ」と思っていることもお伝えしておきます。

嵐男と呼ばれている僕ですから虹もたくさん目にしてきましたが、恐ろしさを感じたこれほどの虹は目にしたことがありません。僕の周りには「こんな虹初めて見ました」って人が結構いましたね。下記、ダブルの虹の写真は、僕の携帯電話カメラでは全体を写しきれず同僚が撮ってくれたものをいただき掲載しています。
虹は不安定な天候の贈り物で喜んでばかりはいられませんが、不謹慎ながら見とれてしまいます。














.webp)