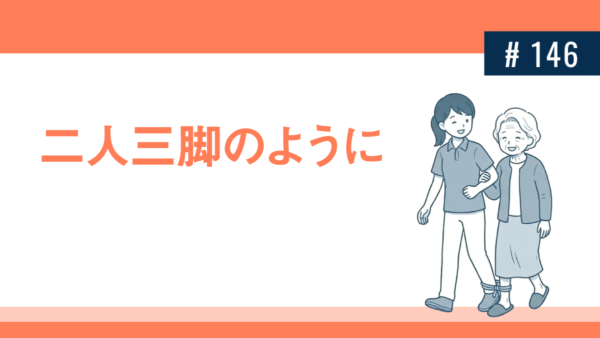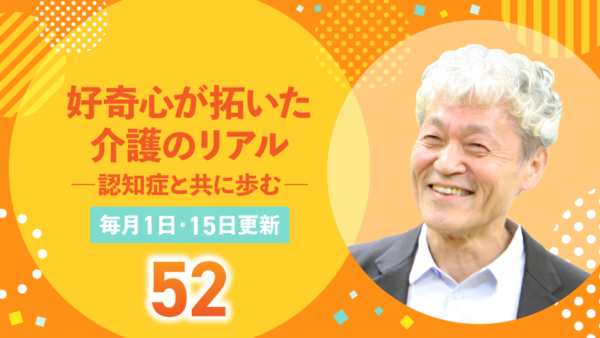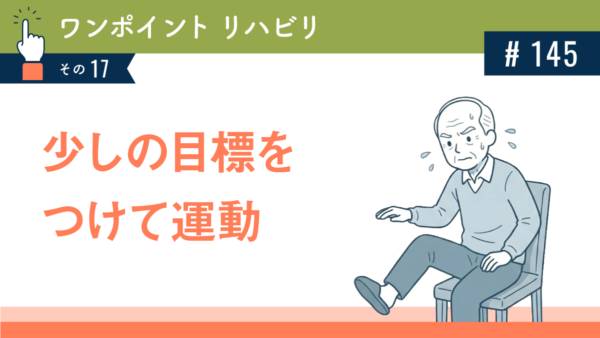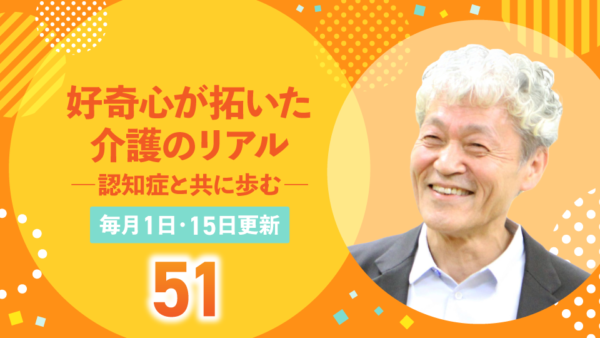先日、あるセミナーに認知症専門医と一緒に出演させていただいたのですが、受講者から「介護側と医師が認知症のことについて意見を言い合えるようになれば良いと思います。そのためにどのような動きをすればよいのか経験も踏まえ教えてください」とのご質問をいただきました。
これまでにも別の研修会等で同様の質問をいただいたことがありますので、この場をお借りして応じさせていただきます。
そもそも医師という職業人について思うこと
人に様々に起こる現象の理由(因子)は大きくは二つと僕は捉えていて、ひとつはその人の中の因子(僕は内因と表現しています)、もうひとつはそれ以外の因子(外因)で、
例えで言えば「いつもの活気がない」と現象は同じでも「大事な人が病気になった」ならば「外因」であり「お腹の調子が悪かったので調べたら病気が見つかった」なら「内因」ということで、この内因を調べ確定させ治療していく専門職・職業人が医師です。
研修会などで「医療・医師が存在しなければ暮らし方は変わりますか?」と受講者に問うと多くが「変わる」と答えられますが、
医療・医師が存在しなければ、もっと高額ならば「病気しないように、ケガしないように」への意識は高まることでしょうから、今よりも少しだけであったとしても気を付けるようになるでしょうから暮らし方は変わることでしょう。
また、医師が「すごいなぁ」と思うのは、医師は事前調査をしないで受診に来られた方を診ることですね。出会ってから自分の専門性で勝負します。
介護のように「事前調査をしてから利用していただく」なんてなく、だから僕も見習って「即日利用」を目指してきました。だって困っておられるんですからね。
僕が鉄道の仕事をしているときで言えば、列車が故障した時に駆けつけるチームがありましたが、停車している場で何らかの解決策を見出すプロフェッショナルチームで「選りすぐられた方々」でした。
特に、頭蓋骨に囲まれている脳、まだわからないことが多いと言われている脳に起因する病気等によって認知症という状態にある方の支援をさせていただくうえでは、現象に惑わされることなく内因を突き詰められる専門職:医師は不可欠で、医師との関係は生命線とも言えます。
ひとまず質問者が問う「医師」を整理すると
質問者は介護事業の従事者なので、質問者が言われている「医師」を僕なりに整理させていただくと次のように整理できるのではないかと思いました。
1 ひとつは質問者が言う医師が「主治医」の場合
2 ひとつは質問者が言う医師が「医師という専門職」の場合
この「2」の中にも2つあって
「一般的な意見を交換できる医師」
「利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師」
となります。
ちなみに僕とセミナーで話をした医師との関係は基本的には「認知症という状態に対して一般的な意見を交換できる医師」で、時々は「利用者・入居者への支援のために意見を聞くこともある医師」でもあります。
意見を交換できる主治医を望むことについて
これは最もハードルが高い望みだと僕は思っています。
というのも「医師を選択する権利(選択権)は国民の側にある」のですが介護事業を利用・入居している方の主治医となると、おのずと制約がかかるでしょうから、出会いは「運」に任せるしかないと言え、出会えれば「幸運」位の確率ではないかと思えるからです。
介護事業所で暮らしている方の場合「訪問診療」を受けている方が多いかと思いますが、
医師側は訪問診療を提供する範囲に定めがあるので、その範囲を超えて「主治医にする」となると介護事業所では通院等に無理が生じるため家族等との連携が不可欠で、そうなると家族等の事情も絡んできて「この医師にかかりたい」を日常化するのは容易いことではありません。
また、主治医の選択肢が乏しい地域もあり「医療環境は住まう場所次第」とも言えます。ただ、これは医療に限った話ではなく、あらゆることに共通していることで「介護」だって同じですからね。
利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師を望むことについて
僕は「最後の砦と思える医師」を探し求めてきました。
最後の砦とはどういうことかというと「主治医として」ではなくても、本当にわからないときに相談にのってもらえる・診てもらえる医師をもつということです。
幸い僕の場合は環境(多くは周りの人)に恵まれていて、ずっと認知症について「横の関係」で一緒に考えてもらえる・話ができる医師が存在してくれていますが、
その理由をカッコよく言わせていただければ僕が真剣に「介護」「認知症」「生活支援」など目の前のことに一生けんめい取り組んできたからであり、同時に僕が医師との横の関係づくりを欲していたからだと勝手に思い込んでいます。
そういう意味では僕みたいな者でも相手にしてもらえたのは、小心者のくせに言いたいことは言う(伝える)生意気な性質が生きているかもしれません。
つまり、質問者がどこまでそういう医師を欲しているかということに尽きるのですが、欲し・行動してこそ「欲は完結」できますから、その本気度にかかっているのではないかと思います。
ただ、自分の「度」がいくら高くても相手のあることですから、容易いことではありませんがね。
自分ができること
いろいろな場に出向くことはできますが出向くだけではダメで、アクションを起こして自分を知っていただくことであり、
知っていただくには「人の暮らし」「脳が病気になるということ」「そもそも家に帰りたいって言うことって症状なの?」などなど、今ある学問に縛られない・とらわれないで自分自身の思考を詰めておくことが大事だと思います。
そうでないと、医師と出会ってもそのことについて意見を交わし合えず、せっかくの機会を得たとしても単なる医師の話の聴講者になってしまい講演を聞きに行ったのと同じことになってしまいますからね。
医師の思考や実践が垣間見えないと次にコマを進める気になりませんでしょうから、懇親会がある取り組みならば「席は医師の近場をとって自ら声をかける積極性」も必要でしょうし「お酒の場」は何かと緩みがちですから「お互いにわかりやすくなるチャンスととらえる貪欲さ」も必要でしょう。
しかも僕みたいに生意気な者でも医師に対してモノを申すのはかなりの「勇気(言う気)」がいりますからね。借りられる力(機会、仲間、お酒など)はなんでも借りないと容易くは近寄れないでしょう。
つまり「利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師」は、僕の場合で言えば「一般的な意見を交換できる医師」が次にコマを進める(関係性を構築する)上での入口の出会いで、
互いの意見を交し合った結果「この医師なら」と思えれば自分がかかわる認知症という状態にある方への支援のために「利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師」に至れるようにアクションを起こすということで、
「利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師」を求めているからこそ「一般的な意見を交換できる医師」との出会いを、まずは大切にするということです。
随分前のことですが、認知症という状態にある方とその家族が集う会に行かせていただきグループワークを傍で聞いていて気になった方がいました。
その方が懇親会にも来ていたので話すと「医師」だということがわかり「だからなんだぁ」と思ったのですが、そこからはより突っ込んだ話をさせていただき、その後は「利用者・入居者への支援のために意見を交換できる医師」としての関係づくりへ進展させることが叶い、僕の言う「最後の砦」としてお力添えを得ることができた経験があります。
ちなみに、僕の経験は参考にならないと思えるほど僕は恵まれていると自覚していますので、あくまでもエピソード程度の助言しかできないことを承知おきください。
医師と意見交換しやすい環境づくり
質問者が望まれるように「医師と意見交換しやすいように環境を整える」のは僕の法人内での仕事なので、所属する法人では他法人と「医療職と緊密な医療連携チーム」を組んで、法人間の関係をバックに医師(入居系介護事業所に住まう入居者の主治医にあたる)と介護事業所側が意見交換しやすい関係づくりを数年前から取り組んでいます。
ここにきて国が医療機関(医師)と介護事業所の連携について加算までつけて体制づくりを整えてきているのも、背景には「医師と介護職が意見交換しやすいようにする」ということがあるのではないかと勝手に思っています。
そう考えると、前述した「運任せ」にならないための体制づくりが進んできていると捉えることもできるわけで上手く活用するべきでしょう。
さらに、こうしたことを実効性のあるものにしていくには僕ら介護側も医師と意見交換し合えるように力をつけていかないといけないってことでしょうが、なかなか「このハードルは高し」です。














.webp)