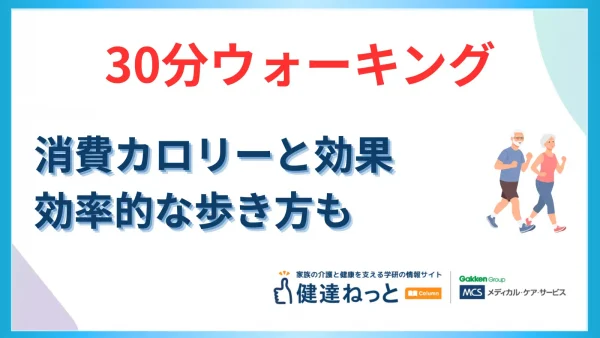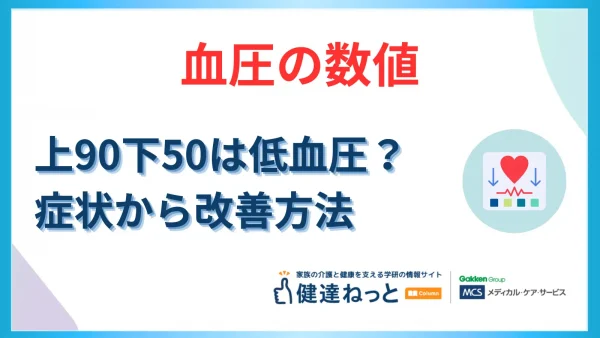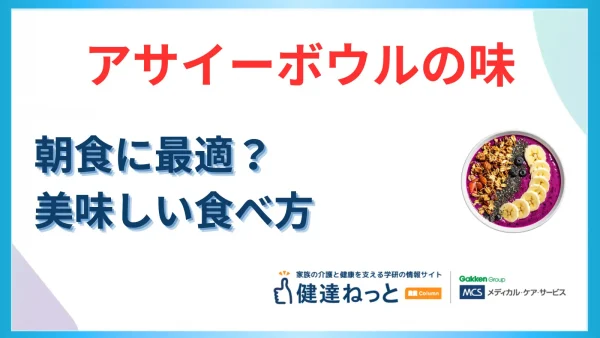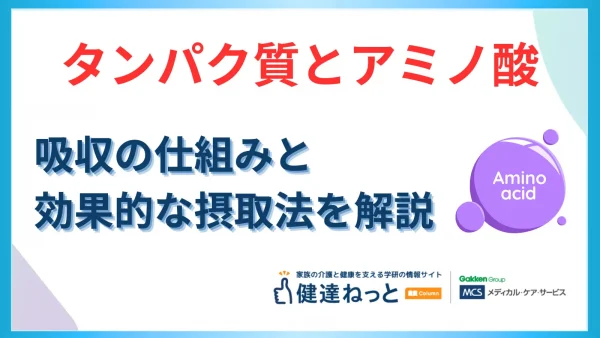配信サービスで観る
あらすじ
大阪北浜に住む87歳の母・ママリン(酒井アサヨ)は認知症を患い、昼夜を問わず街を徘徊する。
娘の章子さん(愛称アッコ)は、母を家に閉じ込めるのをやめ、徘徊に付き合うという決断をする。
過去4年間でママリンが徘徊した記録は、家出回数1338回、徘徊時間1730時間、最長徘徊時間15時間/日、最長徘徊距離12㎞/日。
まるで漫才のような母娘のやり取りから、認知症と共に生きることの意味を問いかける。
特徴・見どころ
認知症の介護と聞くと、ご本人やご家族が抱える困難や閉鎖的なイメージを思い浮かべる方も少なくないかもしれません。
しかし、本作はそんな従来の介護観を根底から覆す、驚きと感動に満ちたドキュメンタリー作品です。
認知症の母親との日常を、悲劇ではなく、愛情あふれる喜劇として描き出す娘の斬新なアプローチが、私たちの心に新しい光を灯してくれます。
「隠す」のではなく「お披露目する」という逆転の発想
本作の最大の特徴は、認知症の母親を「隠すべき存在」としてではなく、「お披露目する」というポジティブな視点で捉えている点です。
娘である監督は、徘徊する母親を「ママリン」と呼び、その行動をSNSでユーモラスに発信し始めます。
一見、無謀にも思えるこの行動が、次第に周囲の人々の心を動かし、温かい支援の輪を広げていく様子は必見です。
認知症という重いテーマを扱いながらも、そこには閉塞感は一切なく、むしろ開放的で笑いに満ちた日常が映し出されています。
この作品が示すのは、介護される側もする側も、自分らしさを失わずに共に生きていくための新しいヒントです。
地域社会全体で支える、これからの介護の在り方
この物語は、決して親子だけの閉じた関係で完結しません。
「お披露目」をきっかけに、ご近所さんや地域の人々が、ごく自然にママリンを見守り、手を差し伸べるようになります。
例えば、以下のような心温まるサポートの輪が広がっていきます。
- 散歩中のママリンに「こんにちは」と声をかける学生
- お店の人が顔を覚えてくれて、休憩場所を提供してくれる
- 警察官もママリンの「パトロール」を優しく見守る
このような地域ぐるみのサポートは、認知症の方やそのご家族が孤立せず、安心して暮らせる社会の重要性を改めて教えてくれます。
健達ねっとの認知症の人はなぜ徘徊するの?危険性や対策グッズについて解説しますでは、徘徊の原因や地域で見守る際のポイントについても詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
本作は、私たち一人ひとりが地域でできること、そして「支え合い」の本当の意味を考えるきっかけを与えてくれるでしょう。
親子の絆の強さ、そして周囲の優しさが織りなす感動の物語は、認知症介護に携わる方はもちろん、すべての人々の心に深く響く感動作です。