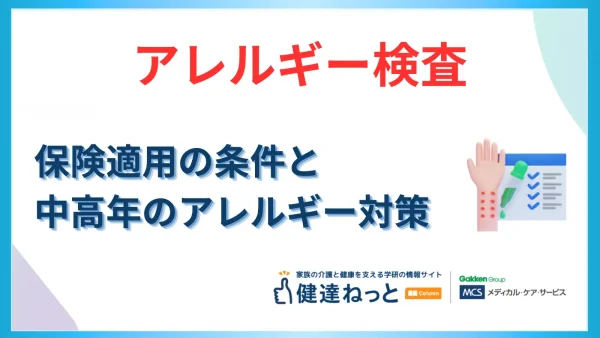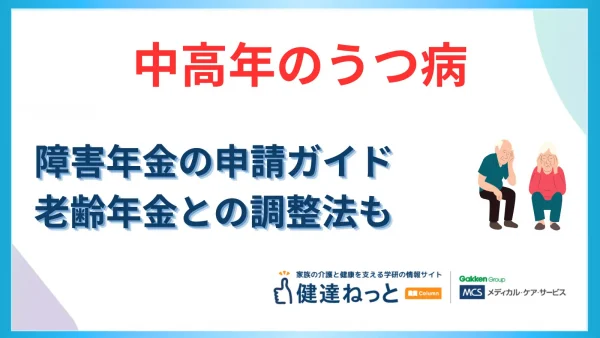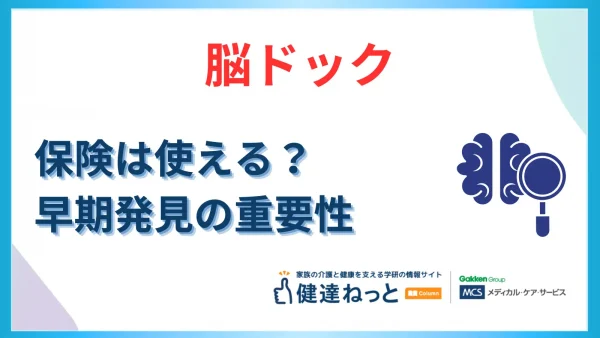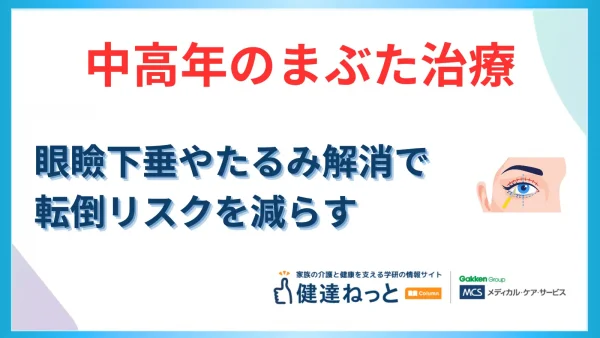あらすじ
クラスでいじめられ公園に1人で座っている小学生の大輝に、散歩途中の認知症を患う拓三が話しかける。
二人は意気投合し次第に心を通わせていく。
認知症の症状や家族の気持ちの変化、介護者の交流の大切さなどを、ドラマを通じて学んでいく。
特徴・見どころ
本作『認知症と向き合う』は、私たちが普段目にする劇場映画とは異なり、東映が教育・啓発の目的で制作した特別なドラマ作品です。
認知症について、「なんとなく知っている」から「正しく理解する」へとステップアップするために、非常に優れた内容となっています。
「もし自分の家族がなったら?」「地域で出会ったらどう接すればいい?」といった、多くの人が抱える疑問や不安に、真正面から応えてくれる作品です。
なぜ「小学生」が主人公なのか
本作の最大の特徴であり、分かりやすさの秘訣は、小学生と認知症の高齢者との「交流」を物語の軸に据えている点です。
大人が持つ「認知症=大変だ」「何も分からなくなってしまう」といった先入観やフィルターを通さず、子どもの純粋で真っ直ぐな視点を通して、認知症の人の姿を描写しています。
例えば、認知症の人がなぜ不思議な行動をとるのか、なぜ急に怒ったり、不安になったりするのか。
大人の理屈ではなく、子どもが素朴な疑問を持ち、相手の世界を理解しようと努める過程を通じて、認知症の人の内面や見ている世界が、非常に分かりやすく、自然に伝わってきます。
症状・本人・家族の「気持ち」を丁寧に描写
このドラマは、単に認知症の症状を解説するだけではありません。
症状の裏にある「本人の気持ち」、そしてそれを支える「家族の気持ち」の変化を、丁寧に描いている点が大きな見どころです。
認知症によくみられる症状として、以下のようなものが挙げられます。
- 何度も同じことを言ったり、尋ねたりする
- 日付や場所が分からなくなる
- 突然、怒りっぽくなったり、不安になったりする
- 「家に帰る」と外に出ようとする(徘徊)
本作では、こうした行動がなぜ起こるのかを、本人の不安や戸惑いといった「心の内側」から描き出します。
同時に、それによって戸惑い、疲れ、悩む家族の葛藤や、介護者同士の交流の大切さにも触れています。
認知症は本人だけの問題ではなく、家族や周囲の人間関係全体に関わる問題であることを、深く理解させてくれます。
子どもから大人まで「学ぶ」ための実用性
本作が教育用ドラマとして優れているのは、その高い実用性です。
実際に、全国の学校教育の現場や、地域の「認知症サポーター養成講座」の教材としても広く活用されています。
これは、内容が正確であると同時に、専門家でなくても理解しやすい普遍性を持っていることの証です。
症状への適切な対応方法のヒントや、声をかける際の心構えなども具体的に学べるため、子どもにとっては「おじいちゃん、おばあちゃん」への理解を深めるきっかけになります。
大人にとっては、地域社会でどのように認知症の人と共生していくべきかを学ぶ、貴重な教材となります。
認知症への理解を深めるための「最初の一歩」として、また、改めて基礎から学び直したい方にも最適な作品です。