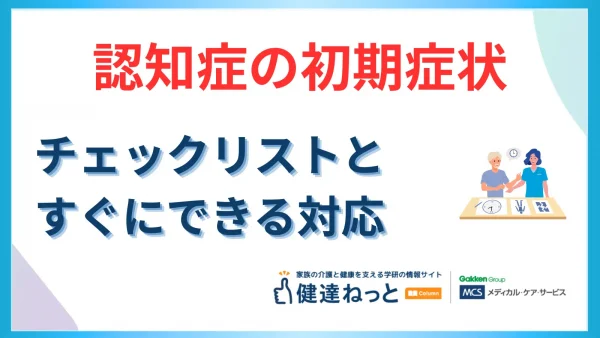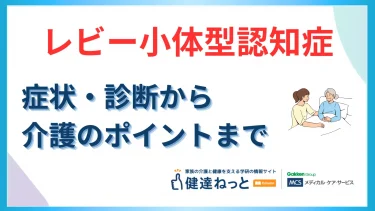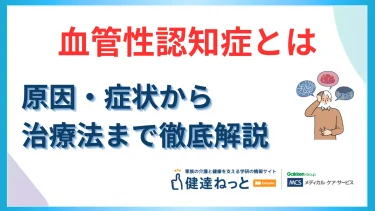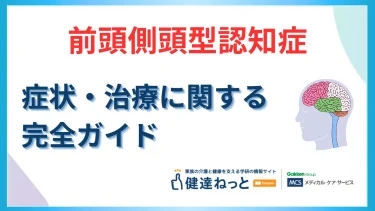- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「さっき言ったことを何度も聞いてくるのは、年のせい?」
- 「もしかして、認知症の始まり…?」
ご家族のささいな変化に、このような不安を抱えていませんか。
その不安の裏には、「この先どうなってしまうのだろう」「大切な家族との関係が変わってしまったらどうしよう」という、誰にもいえない深いお悩みがあるかもしれません。
そのお気持ち、決してひとりで抱え込む必要はありません。
認知症は誰にでも起こりうる身近な病気であり、正しい知識を持つことが、ご本人とご家族の未来を守るための第一歩となるためです。
この記事では、認知症の初期症状について、以下のポイントを網羅的に解説します。
- 具体的な症状が分かるチェックリスト
- 「ただのもの忘れ」との決定的な違い
- 初期症状に気づいた時に家族が取るべき3つのステップ
- 認知症の進行を遅らせるためにできること
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が「何をすべきか」という具体的な行動へと変わり、落ち着いて次の一歩を踏み出せるようになっているはずです。
あなたと大切なご家族が、これからも穏やかな日々を送るためのヒントがここにあります。
スポンサーリンク
認知症の初期症状とは?まずおさえるべき基礎知識
認知症への不安を感じた時、まず大切なのは病気を正しく理解することです。
ここでは、初期症状を見極める上で欠かせない基礎知識として、「もの忘れ」との違いや医学的な定義、そして重要な中間段階であるMCIについて解説します。
「認知症」と老化による「もの忘れ」の決定的な違い
「また同じことを聞いている」と感じた時、それが加齢による自然なもの忘れなのか、認知症のサインなのかを見分けることは非常に重要です。
両者は似ているようで、その性質には決定的な違いがあります。
老化によるもの忘れは、体験したことの一部を忘れるのが特徴です。
例えば、「昨日の夕食に何を食べたか」は思い出せなくても、「夕食を食べたこと」自体は覚えています。
ヒントがあれば思い出すことも多く、忘れている自覚があるため、日常生活に大きな支障はきたしません。
一方で、認知症によるもの忘れは、体験したことのすべてをすっぽりと忘れてしまうのが特徴です。
夕食を食べたこと自体を忘れ、そのことを指摘されても「食べていない」と主張することがあります。
忘れている自覚がなく、症状が徐々に進行していくため、日常生活に支障が出始めます。
| 観点 | 認知症によるもの忘れ | 老化によるもの忘れ |
|---|---|---|
| 忘れる範囲 | 体験したこと自体を忘れる | 体験の一部を忘れる |
| 自覚の有無 | 忘れたことの自覚がない | 忘れた自覚がある |
| 進行 | 症状が徐々に進行する | 年齢相応で大きくは進行しない |
| 日常生活 | 支障が出てくる | 大きな支障はない |
このように、両者の違いを理解することが、ご家族の変化に冷静に対応するための第一歩といえるでしょう。
認知症の医学的定義と診断基準
認知症は、医学的にICD-10(世界保健機関による国際疾病分類第10版)において「通常、慢性あるいは進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断等多数の高次脳機能の障害からなる症候群」と定義されています。
これは、意識障害がない時に見られる症状であることが前提です。
国際的な診断基準では、主に以下の項目が重視されます。
- 記憶障害:新しいことを覚えたり、過去の出来事を思い出したりすることが困難
- 他の認知機能障害:言葉がうまく出てこない(失語)、動作がぎこちない(失行)、物事を認識できない(失認)、計画を立てて実行できない(実行機能障害)のうち、ひとつ以上が見られる
- 生活への支障:上記の症状により、仕事や社会生活、日常生活に明確な支障が出ている
認知症の方の世界を理解する上で重要な特徴として、「感情残像の法則」があります。
これは、公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事の杉山孝博医師が提唱した概念です。
出来事そのものは忘れても、その時に感じた「嬉しい」「悲しい」「楽しかった」という感情は心に残りやすいという特徴を表現したものです。
健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービス(MCS)の現場でも、職員との外出体験を5年後も感情的に鮮明に記憶している方がいました。
このことから、認知症の方への対応では、安心できる感情的な関わりがいかに大切かが分かります。
軽度認知障害(MCI)という重要な中間段階
軽度認知障害(MCI)とは、もの忘れなどの症状はあるものの、日常生活への支障はない、健常な状態と認知症の中間段階(グレーゾーン)を指します。
本人や家族からもの忘れの訴えがあり、客観的な認知機能検査で低下が認められるものの、全般的な認知機能や日常生活動作は保たれている状態です。
MCIは、認知症の前段階として非常に重要視されています。
なぜなら、MCIの段階で適切な対応をとることで、認知症への進行を防いだり、遅らせたりできる可能性があるためです。
研究によると、MCIの方のうち年間10~15%が認知症に移行するとされている一方、健常な状態に回復する人もいると報告されています。
MCIの段階で変化に気づき、生活習慣の見直しや予防に取り組むことが、その後の生活の質を大きく左右します。
MCIについてより詳しく知りたい方は、MCI(軽度認知障害)とは?認知症との違いとすぐできるセルフチェックをご覧ください。
スポンサーリンク
【チェックリスト付き】認知症の初期症状を症状別に完全解説
認知症のサインは、もの忘れだけでなく、さまざまな形で現れます。
ここでは、具体的な症状別にチェックリストを用意しました。
ご本人やご家族に当てはまる項目がないか、確認してみましょう。
MCSの実践データでは、初期症状として特に不安からくる行動が見られやすいことが分かっています。
もの忘れ・記憶障害の初期サイン
記憶障害は、認知症の最も代表的な初期症状のひとつです。
特に、新しいことを記憶する力が低下するため、直前の出来事を忘れやすくなります。
具体的なサインとして、以下のようなものがあります。
- □ 食事の内容や、電話で話した相手の名前をすぐに忘れる
- □ 同じことを何度も言ったり、質問したりする
- □ しまい忘れや置き忘れが増え、常に探し物をしている
- □ 財布や通帳などを「盗まれた」と、家族を疑うことがある
- □ 約束そのものを忘れてしまう
このような体験全体を忘れてしまうのが、単なるもの忘れとの大きな違いです。
ご本人は忘れた自覚がないため、周囲との認識のズレが生じやすくなります。
理解力・判断力低下の見極めポイント
情報を処理し、状況に応じて適切に判断する能力が低下するのも、認知症の初期症状です。
これまで当たり前にできていたことが、うまくできなくなります。
見極めのポイントは以下の通りです。
- □ 料理や片付けの手順が悪くなり、時間がかかるようになった
- □ 買い物の際に、計算を間違えることが増えた
- □ テレビや新聞の内容が、以前ほど理解できなくなった
- □ 車の運転で、信号や標識の見落としなどが増えた
- □ 状況に合わない服装を選ぶことがある
これらの症状は、ご本人が「何かおかしい」と感じて自信を失い、ふさぎ込んでしまう原因にもなります。
見当識障害(時間・場所・人物の認識困難)
見当識(けんとうしき)とは、現在の時間、自分がいる場所、周囲の人物との関係性などを正しく認識する能力のことです。
この能力が低下すると、日常生活で混乱が生じやすくなります。
以下のようなサインに注意しましょう。
- □ 今日の日付、曜日、季節が分からなくなる
- □ 約束の日時や場所を間違える
- □ 慣れているはずの道で迷子になる
- □ 親しい人の顔や名前が、すぐに出てこないことがある
見当識障害は、ご本人に大きな不安感をもたらします。
MCSでは、コミュニケーションを通じて時間や場所を「確か」なものにし、安心できる環境を作ること(これを「不確かさ」から「確かさ」への転換といいます)を重視しています。
実行機能障害(計画・実行の困難)
実行機能障害とは、目標を立て、計画し、段取りよく実行することが難しくなる症状です。
複数の作業を同時に行うことや、予期せぬ変化に対応することが苦手になります。
具体的な症状の例は以下の通りです。
- □ 料理の品数を一度に作れなくなった
- □ 家電製品やリモコンの操作に戸惑うようになった
- □ 計画的に買い物や用事を済ませられない
- □ 指示通りに作業を進めることが困難
これまでテキパキとこなしていた家事などが、以前のようにできなくなることで、ご本人が混乱したり、意欲を失ったりすることがあります。
性格・人格変化の特徴的パターン
認知症は、脳の感情をコントロールする部分にも影響を及ぼすため、以前と性格が変わったように見えることがあります。
これは病気による症状であり、本人の意思ではないことを理解するのが重要です。
認知症の周辺症状(BPSD)について詳しくは、認知症周辺症状とは?具体的な症状と原因を説明をご参照ください。
特徴的なパターンには、以下のようなものがあります。
- □ ささいなことで怒りっぽくなった
- □ 周囲への気遣いがなくなり、自己中心的になった
- □ 自分の失敗を人のせいにする
- □ 頑固になり、人の意見を聞き入れなくなった
- □ 疑い深くなった
環境の変化は、このような症状を悪化させる大きな要因です(リロケーションダメージ)。
MCSの事例では、「家に帰りたい」という訴えに寄り添い、一緒に散歩することで落ち着きを取り戻したケースがあります。
ご本人の不安な気持ちを否定せず、受け止める姿勢が大切です。
言語機能の変化と表現力低下
言葉を理解したり、話したりする能力にも変化が現れることがあります。
スムーズな会話が難しくなり、コミュニケーションに支障が出始めるのです。
以下のような変化に気づくことがあります。
- □ 「あれ」「それ」といった代名詞が多くなり、話が分かりにくい
- □ 知っているはずの物の名前が、すぐに出てこない
- □ 言葉の聞き間違いや、言い間違いが増える
- □ 口数が減り、あまり話さなくなる
ご本人は、言葉がうまく出てこないことにもどかしさを感じているかもしれません。
会話の際は、急かさずにゆっくりと話を聞き、ご本人の伝えたいことを汲み取ろうとする姿勢が求められます。
意欲低下・うつ症状との見分け方
認知症の初期には、何事にも興味を失い、無気力になる「アパシー」と呼ばれる状態が見られることがあります。
これはうつ病の症状と似ていますが、違いもあります。
認知症による性格変化については、認知症になったら性格が変わる?原因や対策を解説で詳しく解説しています。
見分けるためのポイントを整理しました。
- □ 好きだった趣味やテレビ番組に関心を示さなくなった
- □ 身だしなみを気にしなくなり、入浴などを面倒くさがる
- □ 一日中、ぼーっとしていることが増えた
- □ 人付き合いを避けるようになり、家にこもりがちになる
うつ病の場合は、悲しみや気分の落ち込みを強く訴えることが多いのに対し、認知症による意欲低下では、感情の起伏自体が乏しくなる傾向があります。
ただし、判断は難しいため、専門医への相談が不可欠です。
認知症の種類別の初期症状
認知症はひとつの病気ではなく、原因となる病気によっていくつかの種類に分けられます。
種類によって現れやすい初期症状も異なります。
MCSでは、約250項目の詳細なアセスメントによって個々の状態を正確に把握し、最適なケアを提供しています。
ここでは、代表的な認知症の初期症状の特徴を見ていきましょう。
アルツハイマー型認知症の初期症状
アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多いタイプで、全体の約68%を占めています。
脳にアミロイドβという特殊なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症します。
- 主な初期症状:新しいことを記憶できない「もの忘れ(記憶障害)」から始まることが多いのが特徴です。
- 進行:年単位でゆっくりと進行
- その他:初期には、麻痺などの身体的な症状はほとんど見られない
アルツハイマー型認知症について詳しく知りたい方は、アルツハイマー病について|認知症との違いや症状・原因を解説をご参照ください。
レビー小体型認知症の初期症状
レビー小体という特殊なたんぱく質が脳にたまることで発症します。
アルツハイマー型、血管性に次いで多い認知症です。
- 主な初期症状:実際にはないものが見える「幻視」や、パーキンソン病に似た症状(動作が遅い、小刻みな歩行など)が特徴的
- 症状の変動:日や時間帯によって、頭がはっきりしている時と、ぼーっとしている時の差が激しい
- 睡眠時の異常:大声で寝言を言ったり、暴れたりする「レム睡眠行動異常症」が見られることもある
しっかりしている時と、ぼーっとしている時の差が激しい誰もいないのに「人がいる」といい、不安そうにしている歩き方がおぼつかなくなり、よくつまずくようになった夜中に突然、大声を出したり手足をばたつかせたりする[…]
血管性認知症の初期症状
脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって、脳の神経細胞がダメージを受けることで発症します。
男性にやや多く見られます。
- 主な初期症状:脳の障害を受けた部分によって症状が異なり、「まだら認知症」ともいわれる。記憶障害は比較的軽い場合もある
- 身体症状:手足の麻痺や言語障害、嚥下障害などを伴うことがある
- 感情の変動:ちょっとしたことで泣いたり笑ったりする「感情失禁」が見られることがある
認知症の種類による症状の違いについては、三大認知症ってなに?それぞれの認知症の特徴と原因を徹底解説で詳しく比較しています。
「最近、親の物忘れが気になる…」 「さっきまで穏やかだったのに、急に怒り出すことがあるのはなぜ?」 「血管性認知症という言葉を聞いたけど、どのような病気なんだろう?」ご家族のこのような変化に戸惑いや不安を感じてい[…]
前頭側頭型認知症の初期症状
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症する認知症です。
比較的若い年代での発症も多く、ピック病とも呼ばれます。
- 主な初期症状:もの忘れよりも、性格変化や行動異常が先に目立つ
- 行動異常:社会のルールを守れなくなったり、同じ行動を繰り返す「常同行動」が見られる
- 感情の変化:他人の気持ちに共感できなくなり、思いやりのない言動をとることがある
「最近、家族の性格がまるで別人のように変わってしまった…」「理解できない行動が増え、どう接すればよいか分からない」「もしかしたら認知症かもしれないけど、誰に相談すれば…」「この先どうなるのか、経済的なことも含めて不安で仕方が[…]
若年性認知症の初期症状
65歳未満で発症する認知症を総称して、若年性認知症といいます。
原因となる病気は血管性認知症が最も多く(約40%)、次いでアルツハイマー型(約25%)となっています。
- 気づきの遅れ:働き盛りであるため、症状が仕事のミスや疲れとして見過ごされ、診断が遅れる傾向
- 主な症状:もの忘れに加え、段取りよく仕事を進められない実行機能障害などが目立ちやすい
- 影響:経済的な問題や、配偶者・子どもの生活への影響が大きいという特徴
若年性認知症の詳細については、【2025年最新】若年性認知症とは?症状や特徴・予防方法を解説をご覧ください。
認知症の初期症状に気づいた時に家族が取るべき3ステップ
ご家族の「いつもと違う」というサインに気づいた時、冷静に行動することが大切です。
ひとりで抱え込まず、適切な手順を踏むことで、ご本人とご家族の負担を軽減できます。
ここでは、家族が取るべき具体的な3つのステップを紹介します。
ステップ1.まずは記録した上で家族や親しい人に状況を共有する
まず初めに行うべきは、客観的な事実の記録と、信頼できる人との情報共有です。
感情的に「認知症ではないか」と決めつけるのではなく、冷静に状況を整理しましょう。
具体的な行動は以下の通りです。
- 記録する:いつ、どこで、どのような言動があったのかを具体的にメモに残す。この記録は、後に専門医に相談する際の非常に重要な情報となる
- 共有する:ひとりで悩まず、他の家族や親しい友人に状況を伝える。複数の視点で見ることで、変化に気づきやすくなったり、対応策を一緒に考えたりできる
MCSが実施した認知症教育の授業では、授業をきっかけに「認知症の祖父を避けていたけれど、これからは祖父の家を多く訪れたい」と考えるようになった小学生もいました。
家族が病気について正しく知り、向き合うことが、関係性を良好に保つ鍵となります。
ステップ2.相談窓口に連絡する
次に、専門的な知識を持つ機関に相談しましょう。
公的な相談窓口は無料で利用でき、今後の道筋を示してくれます。
主な相談先には、以下のような場所があります。
- かかりつけ医:まずは最も身近な医療の専門家。ご本人の普段の健康状態をよく知っているため、変化に気づきやすい立場にある。専門医への紹介状を書いてもらうことも可能
- 地域包括支援センター:高齢者の医療・介護・福祉に関する総合相談窓口。保健師や社会福祉士などの専門家が、無料で相談に応じてくれる
- 認知症疾患医療センター:認知症の専門的な診断や治療、相談を行う医療機関。都道府県や指定都市によって指定されている
認知症の相談先について詳しくは、認知症についてはどこに相談すべき?徹底解説をご参考ください。
また、地域包括支援センターでの相談については、認知症相談には地域包括支援センターがいい?業務内容や相談内容を解説で詳しく説明しています。
ステップ3.本人と受診について話す
ご本人に受診を促すことは、最も難しいステップかもしれません。
「認知症扱いするのか」と、プライドを傷つけてしまう可能性があります。
ご本人の気持ちに寄り添い、上手に受診へとつなげることが重要です。
以下のような伝え方を試してみましょう。
- 「認知症の検査」とは言わず、「体の健康診断と一緒に、脳の健康診断も受けてみない?」と誘う
- 「最近忘れっぽくなったのが心配で。自分も一緒に受けたいから、付き合ってほしい」と、家族も一緒の立場であることを示す
- かかりつけ医から、「念のために一度、専門の先生に診てもらいましょう」と勧めてもらう
受診を強制するのではなく、あくまでご本人の健康を心配している気持ちを伝えることが大切です。
認知症の検査や診断について詳しくは、認知症の検査とは?気になる内容や検査との向き合い方を解説をご覧ください。
認知症の初期症状が出た時に家族・周囲ができる対応
認知症の症状が見られ始めた時、家族や周囲の人の対応は、ご本人の心の安定や症状の進行に大きく影響します。
病気を正しく理解し、適切な関わり方を学ぶことが、穏やかな生活を続けるための鍵となります。
本人の尊厳を保つコミュニケーション方法
認知症の方と接する上で最も大切なのは、ひとりの人間として尊厳を保ち、尊重する姿勢です。
できないことに目を向けるのではなく、できることやその人らしさを大切にしましょう。
コミュニケーションのポイントは以下の通りです。
- 否定しない、叱らない:間違いを指摘したり、叱ったりすることは、ご本人を混乱させ、傷つけるだけ。まずは話を受け止める
- 急かさない、待つ:言葉がすぐに出てこなくても、ゆっくりと待つ。ご本人のペースに合わせることが安心感につながる
- 目線を合わせて話す:上から見下ろすのではなく、同じ高さの目線で、穏やかな表情で話しかけることを心がける
- 感謝の気持ちを伝える:「ありがとう」「助かるよ」といった言葉は、ご本人の自己肯定感を高める
認知症の方との効果的なコミュニケーション方法は、認知症患者の会話の特徴と注意点|コミュニケーションのポイントを解説で具体例とともに解説しています。
また、言ってはいけない言葉について詳しくは、認知症の方へ言ってはいけない言葉とは?接し方について解説をご参照ください。
日常生活でのサポートのポイント
日常生活では、ご本人が混乱せず、できるだけ自立した生活を続けられるようなサポートが重要です。
過剰に手伝うのではなく、さりげなく見守り、必要な部分だけを支援する姿勢が求められます。
具体的なサポートのポイントは以下の通りです。
- 役割を持ってもらう:簡単な洗濯たたみや食器洗いなど、ご本人にできる役割をお願いすることで、自信や生きがいにつながる。MCSの現場でも、「人の役に立ちたい」という思いを支援することで、症状が改善した事例がある
- 安全な環境を整える:火の元や戸締りの確認、転倒しやすい場所の整理など、事故を防ぐための環境整備を行う
- 習慣を大切にする:毎日同じ時間に起きる、散歩するなど、長年の生活リズムをできるだけ維持することが、心の安定につながる
症状悪化を防ぐ環境づくり
認知症の方は環境の変化に敏感なため、安心して過ごせる環境を整えることが、症状の悪化を防ぐ上で非常に効果的です。
ご本人が混乱しない、シンプルで分かりやすい環境を目指しましょう。
環境づくりの工夫には、以下のようなものがあります。
- 物を減らし、整理整頓する:探し物が見つからないストレスを減らすため、身の回りをシンプルに保つ
- ラベリングを活用する:引き出しや扉に「下着」「タオル」など、中身が分かるように写真や大きな文字でラベルを貼る
- カレンダーや時計を置く:時間や日付が分かりやすいように、目につく場所に大きな文字のカレンダーや時計を設置
- 馴染みの家具や物を置く:ご本人が長年使ってきた愛着のある物をそばに置くことで、安心感を得られる
このような小さな工夫の積み重ねが、ご本人の混乱を減らし、穏やかな生活を支えます。
介護負担を軽減する社会資源の活用
ご家族だけで介護を抱え込むと、心身ともに疲弊してしまいます。
介護保険サービスなどの社会資源を積極的に活用し、負担を分かち合うことが、長く介護を続けるためには不可欠です。
活用できる主な社会資源は以下の通りです。
- 介護保険サービス:デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)、訪問介護など、さまざまなサービスがある。ご本人の社会参加や、ご家族の休息(レスパイトケア)につながる
- 家族会:同じ悩みを持つ家族と情報交換をしたり、悩みを分かち合ったりする場。精神的な支えとなる
- 成年後見制度:判断能力が不十分になった方の財産管理や契約などを、後見人が法的に支援する制度
これらのサービスを利用するには、要介護認定の申請などが必要です。
まずは地域包括支援センターに相談してみましょう。
初期症状が出てから認知症の進行を遅らせるためにできること
認知症と診断された後も、「もう何もできない」と諦める必要はありません。
日常生活の中で意識的に取り組むことで、病気の進行を穏やかにしたり、心身の状態を良好に保ったりすることが可能です。
生活習慣を改善する
健康的な生活習慣は、脳の健康を保つための基本です。
特に食事と運動は、認知機能の維持に大きく関わっていることが分かっています。
- バランスのよい食事:野菜や果物、青魚などを積極的に摂り、栄養バランスを整える。MCSのケアでは、十分な水分(約1,800ml)とたんぱく質(約80g)の摂取を基本とし、脳の覚醒を促す
- 適度な運動の習慣:ウォーキングなどの有酸素運動は、脳の血流を改善し、認知機能によい影響を与えるといわれている。無理のない範囲で、毎日続けることが大切
認知症予防に効果的な運動については、認知症予防に運動は効果的?効果や運動方法を解説で詳しく解説しています。
食事による認知症予防については、認知症予防できていますか?効果的な食べ物やトレーニング方法を解説をご覧ください。
また、認知機能を改善するサプリメントを導入することも効果的です。
健達ねっとでもさまざまなサプリメントを販売しているので、食事の補助として検討してみてください。
社会とのつながりを保つ
孤立は認知症の進行を早める要因のひとつです。
人と交流し、社会的な役割を持つことは、脳へのよい刺激となり、生きがいにもつながります。
- 積極的に会話する:家族や友人と、日々の出来事について話す機会を増やす
- 趣味や活動に参加する:デイサービスや地域のサークル活動などに参加し、他者と関わる場を持つことが大切
- 役割を持つ:「お茶を入れる係」「新聞を取りに行く係」など、家庭内で簡単な役割を担ってもらうことも、社会参加のひとつ
MCSのケアモデルでも、「人」との「つながり」や「コミュニケーション」を重視し、認知症の方の生活の質を高めることを目指しています。
脳を活性化する習慣を持つ
脳にとって、新しい刺激や「考える」機会は非常によいトレーニングになります。
楽しみながら続けられることを見つけるのが、長続きのコツです。
脳を活性化させる習慣の例は以下の通りです。
- 計算ドリルや漢字の書き取り
- パズルや囲碁、将棋
- 楽器の演奏や合唱
- 日記や手紙を書くこと
- 料理の献立を考え、手順通りに作ること
これらの活動は、脳のさまざまな部分を使い、認知機能の維持を助けます。
ご本人の興味や関心に合わせて、いくつか組み合わせてみるとよいでしょう。
認知症の初期症状に関するよくある質問
ここでは、認知症の初期症状に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
正しい知識を持つことが、不安の解消につながります。
認知症を早期発見するにはどうすればよい?
認知症の早期発見には、ご家族や周囲の人が「いつもと違う」というささいな変化に気づくことが最も重要です。
この記事で紹介したチェックリストを参考に、日頃からご本人の様子を気にかけてみてください。
そして、「おかしいな」と感じたら、ひとりで判断せずに、かかりつけ医や地域包括支援センターなどの専門機関に相談することが大切です。
定期的な健康診断や脳ドックを受けることも、早期発見のきっかけになります。
認知症の早期発見方法については、認知症の早期発見は大事?認知症の兆候や予防方法を徹底解説で詳細に説明しています。
認知症の始まりに特徴的な口癖はある?
特定の「この口癖があれば認知症」というものはありませんが、初期症状のサインとして現れやすい言葉の傾向はあります。
例えば、物の名前が出てこずに「あれ」「それ」といった代名詞が多くなったり、会話の中で同じことを何度も繰り返したりするような場合は注意が必要です。
これは、新しいことを記憶する力や、言葉を思い出す力が低下しているサインである可能性があります。
口癖そのものよりも、会話の全体的な内容や、コミュニケーションのスムーズさに変化がないかを見るのがポイントです。
認知症が一気に進む原因はある?
認知症の症状は、通常ゆっくりと進行しますが、ある出来事をきっかけに急に悪化したように見えることがあります。
主な原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 環境の変化:引っ越しや入院、介護施設の入所など、住む環境が大きく変わると、混乱して症状が悪化することがある(リロケーションダメージ)
- 体調の悪化:風邪や脱水、便秘、怪我など、身体的な不調が脳の働きに影響し、一時的に症状が強く出ることがある
- 薬の影響:服用している薬の種類や量が変わったことで、副作用としてせん妄(意識の混乱)などが現れる場合がある
これらの原因を取り除くことで、症状が落ち着くことも多いため、急な変化があった場合は、まずかかりつけ医に相談することが重要です。
認知症の進行について詳しくは、認知症の行動心理症状ってなに?認知症の症状について解説をご覧ください。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、認知症の初期症状に関するチェックリストから、種類別の特徴、ご家族が取るべき対応、そして進行を遅らせるための方法まで、幅広く解説しました。
認知症の始まりは、ご本人にとってもご家族にとっても、大きな不安を伴うものです。
しかし、最も大切なのは、そのささいなサインを見逃さず、早期に正しい対応を始めることです。
「年のせい」と見過ごすのではなく、まずは客観的に状況を把握し、ひとりで抱え込まずに専門の窓口へ相談するようにしましょう。
認知症は、正しい知識と適切なサポートがあれば、進行を穏やかにし、その人らしい穏やかな生活を長く続けることが可能です。
この記事が、あなたの抱える不安を具体的な一歩に変えるための、信頼できる道しるべとなれば幸いです。