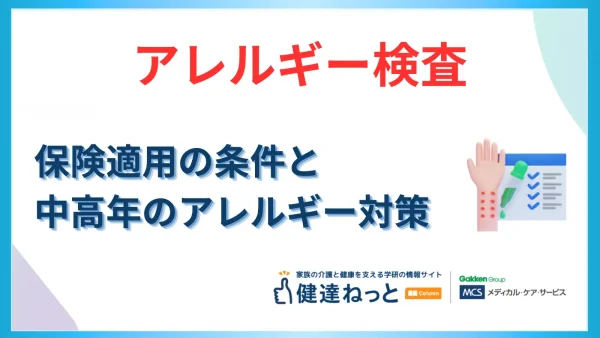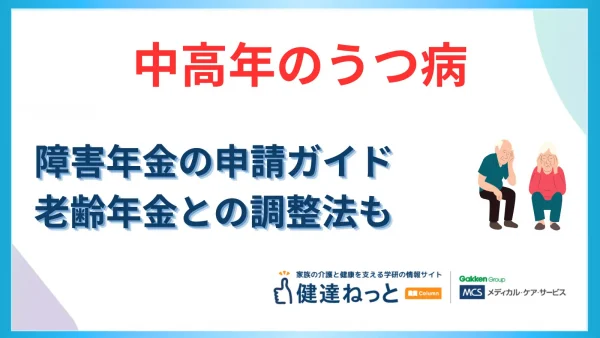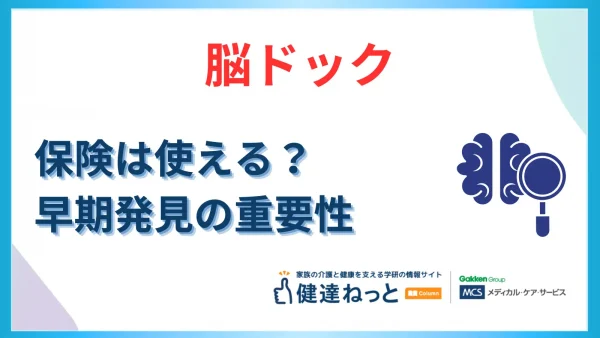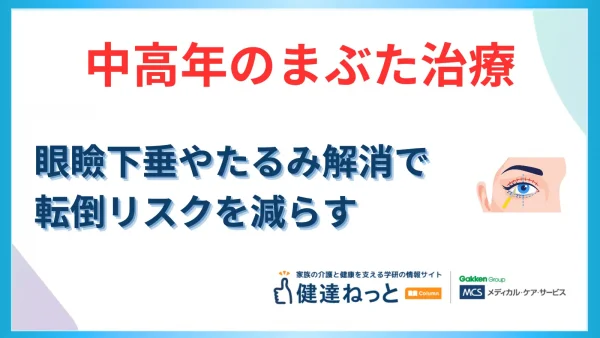あらすじ
いじめられている小学生の大輝と、散歩中の認知症を患う拓三が公園で出会う。
最初は戸惑う大輝だったが、拓三の優しさに触れ次第に心を開いていく。
二人の交流を通じて、認知症の症状や認知症の人の気持ち、周囲の接し方について学んでいく。
特徴・見どころ
本作『永遠の記憶〜認知症を知る』は、これから社会を担っていく、小学校高学年から中学生という多感な時期の子どもたちに向けて制作された、認知症理解のための教材ドラマです。
大人が一方的に「教える」のではなく、主人公である子ども自身の視点から認知症の人との関わりを描いているのが、大きな特徴です。
「どうして、あの人はあんな行動をするんだろう?」。
そうした子どもの純粋な疑問や戸惑いを出発点に、認知症への偏見や誤解を解きほぐし、温かく見守る心を育てることを目的としています。
「いじめ」と「認知症」を結ぶ、思いやりの心
本作の構成で非常にユニークな点は、「いじめ」と「認知症」という、一見すると異なる二つの重いテーマを同時に扱っている点です。
しかし、この二つの問題には、「相手を理解できない」「自分と違う」というところから生まれる恐怖心や拒絶、偏見という共通点があります。
ドラマは、いじめの問題に直面する子どもが、地域で暮らす認知症の高齢者と出会い、最初は戸惑いながらも、次第にその人の内面や背景を知ろうと努める過程を描きます。
相手を思いやることの大切さ。
その心は、いじめをなくすためにも、認知症の人と共生していくためにも、等しく不可欠なものであるという、深く大切なメッセージが込められています。
症状の「なぜ」を、子どもの目線で学ぶ
この物語は、認知症の症状についても、子どもにも分かりやすい具体的なエピソードを交えて伝えています。
例えば、
- なぜ、何度も同じことを言ったり、尋ねたりするのか
- なぜ、急に怒ったように見えたり、不安になったりするのか
- なぜ、今いる場所が分からなくなってしまうのか
こうした症状を「問題行動」として表面的に捉えるのではありません。
その行動の裏にある本人の不安や戸惑い、心の動きを描くことで、「困った人」ではなく「困っている人」なのだという、最も重要な視点を教えてくれます。
この作品は、その分かりやすさとテーマ性から、全国の学校教育の現場や、地域の啓発活動、認知症サポーター養成講座などで広く活用されています。
認知症を「自分ごと」として考えるきっかけが少ない若い世代にとって、当事者の視点に触れる貴重な機会となります。
子どもから大人まで、認知症と共に生きる社会をどう作るべきか。
そのヒントと、人を思いやる心の尊さを学ぶことができる、教育的価値の非常に高い作品です。