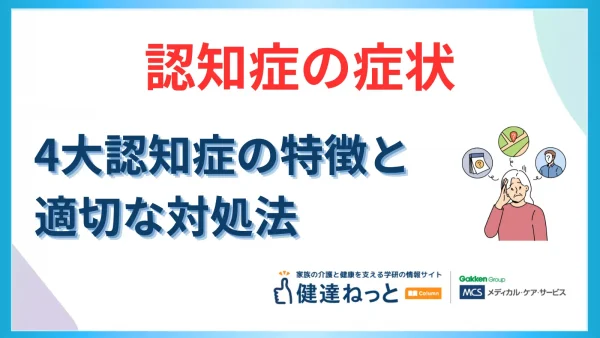- 「最近、親の物忘れがひどくて心配…」
- 「同じことを何度も聞かれるけど、これって認知症の始まり?」
- 「もし家族が認知症になったら、どう接すればよいのだろう?」
- 「自分自身の将来を考えて、認知症の症状について知っておきたい」
このような不安や疑問を抱えていませんか。
身近な人の変化に戸惑い、先の見えない不安を感じるのは当然のことです。
しかし、認知症の症状を正しく理解し、適切な対処法を知ることで、その不安は大きく和らぎます。
この記事では、認知症の様々な症状から、いざという時のための具体的な向き合い方まで、専門的な情報と介護現場のリアルな事例を交えて網羅的に解説します。
この記事で分かることは以下の通りです。
- 加齢による物忘れと認知症の決定的な違い
- 見逃したくない認知症の代表的な初期症状
- 「中核症状」と「行動・心理症状(BPSD)」の全一覧
- 4大認知症それぞれの特徴的な症状と経過
- 症状を和らげ、穏やかに過ごすための具体的なケア方法
最後までお読みいただくことで、認知症への漠然とした不安が「備え」に変わり、あなたとあなたの大切な人が、よりよい関係を築きながら安心して毎日を送るためのヒントがきっと見つかります。
スポンサーリンク
そもそも認知症とは?加齢による物忘れとの違い
「認知症」という言葉はよく耳にしますが、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
ここでは、認知症の基本的な定義と、多くの人が気になる「加齢による物忘れ」との違いを明確に解説します。
正しい知識は、不要な心配を減らし、適切な第一歩を踏み出すための土台となります。
認知症は「生活に支障が出る」脳の病気
認知症とは、脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能(記憶、判断力など)が低下し、日常生活全般に支障が出ている状態(およそ6ヵ月以上継続)をいいます。
単なる物忘れとは異なり、病的に認知機能が低下することで、これまで普通にできていたことができなくなってしまうのです。
認知症の症状は、脳の機能低下によって直接起こる「中核症状」と、本人の性格や環境、人間関係などが影響して起こる「行動・心理症状(BPSD)」に分けて捉えられます。
特に後者のBPSDは、適切なケアによって改善する可能性があるという点が非常に重要です。
実際に、MCSの自立支援ケアを6か月間継続した結果、対象者のうち85.12%の方で認知症の周辺症状や身体機能の改善が確認されています。
この事実は、認知症になっても諦めるのではなく、適切な関わり方次第で穏やかな生活を取り戻せる可能性を示しています。
(引用元:MCSケアモデル)
【比較表】「認知症の物忘れ」と「加齢による物忘れ」の決定的違い
「物忘れ」は誰にでも起こりますが、それが自然な老化によるものか、病的なものかを見分けることが重要です。
両者の違いを以下の表にまとめました。
大きな違いは、体験したことの一部を忘れるのが加齢による物忘れ、体験したこと自体をすっぽり忘れてしまうのが認知症による記憶障害という点です。
| 観点 | 加齢による物忘れ | 認知症による記憶障害 |
|---|---|---|
| 忘れる範囲 | 体験したことの一部(例:夕食のメニュー) | 体験したことの全て(例:夕食を食べたこと自体) |
| 自覚 | 物忘れの自覚がある | 物忘れの自覚がないことが多い |
| 探し物 | 自分で探そうとする、ヒントで思い出せる | 探そうとしない、盗まれたと思い込むことがある |
| 日常生活への影響 | ほとんどない | 支障が出る(約束を忘れる、物の管理ができない) |
| 進行 | 年齢相応で、あまり進行しない | 症状が徐々に進行していく |
正しい知識を持つことは、世代を超えてよい影響を与えます。
当社が全国の小・中・高校生を対象に実施した「認知症教育の出前授業」では、授業後に92%の子どもたちが「認知症が良いイメージに変わった」と回答しました。
「祖父と話すことで元気に過ごせると分かったので、これからはもっと家を訪れたい」という声もあり、正しい理解が家族の絆を強めるきっかけにもなっています。
より詳しい物忘れと認知症の違いについては、こちらの記事もご覧ください。
(引用元:認知症教育調査結果)
スポンサーリンク
【チェックリスト】認知症の始まりを示す代表的な初期症状
認知症は、早期に発見し対応を始めることで、その後の進行を緩やかにできる可能性があります。
「いつもと違うな」と感じる些細な変化が、実は認知症の始まりのサインかもしれません。
ここでは、特に注意したい代表的な初期症状を4つ紹介します。
ご自身やご家族に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
初期症状について更に詳しく知りたい方は初期症状の詳細ガイドをご覧ください。
物忘れ(記憶障害)
認知症の初期症状として最もよく知られているのが物忘れです。
しかし、これは単なる物忘れではありません。
数分前や数時間前といったごく最近の記憶が抜け落ちてしまうのが特徴です。
具体的なサインとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 同じことを何度も話したり、聞いたりする
- 物の置き場所を忘れ、いつも探し物をしている
- 約束の日時や場所を忘れてしまう
これらの物忘れは、日常生活に少しずつ影響を与え始めます。
本人は忘れている自覚がないため、「そんなことあったかしら?」と不思議そうな顔をすることもあります。
このような変化に気づくことが、早期対応への第一歩となります。
理解力・判断力の低下
これまでスムーズにできていたことの段取りが悪くなったり、時間がかかるようになったりするのも注意すべきサインです。
これは、情報を整理し、理解し、適切に判断する能力が低下しているために起こります。
例えば、以下のような変化が見られることがあります。
- 料理の手順が分からなくなり、味付けを間違える
- テレビドラマの内容が理解できなくなる
- ATMや電化製品の操作に戸惑う
- 些細なことで怒ったり、混乱したりする
物事の判断が難しくなるため、詐欺の被害に遭いやすくなるなど、具体的なトラブルにつながる危険性も潜んでいます。
本人は「できなくなった」という事実にもどかしさや不安を感じていることが多いです。
時間や場所が分からなくなる(見当識障害)
見当識(けんとうしき)とは、現在の年月や日時、自分がどこにいるかなど基本的な状況を把握する能力のことです。
この能力が衰えると、時間や場所の感覚が不確かになります。
初期の段階では、まず時間の感覚から薄れることが多く、次第に場所、人物の認識へと障害が広がっていきます。
時間感覚のずれや見当識障害の詳細についても併せてご覧ください。
具体的なサインは以下の通りです。
- 今日が何月何日か、何曜日かが分からなくなる
- 約束の時間を間違える、すっぽかしてしまう
- 慣れているはずの場所で道に迷う
- 季節感のない服装をしてしまう(例:夏にセーターを着る)
見当識障害は、社会生活を送る上で大きな支障となります。
待ち合わせ場所にたどり着けなくなったり、自宅に帰れなくなったりと、深刻な事態につながる可能性もあるため、注意が必要です。
人柄の変化・気分の落ち込み
認知症は、脳の機能低下によって感情のコントロールが難しくなるため、人柄が変わったように見えることがあります。
また、自分の能力が低下していることに無意識に気づき、不安や焦りから精神的に不安定になることも少なくありません。
家族が気づきやすい変化には、以下のようなものがあります。
- 些細なことで怒りっぽくなった
- 頑固になり、人の意見を聞かなくなった
- 以前より疑い深くなった
- 好きだった趣味や外出に関心を示さなくなった
- 身だしなみを気にしなくなり、だらしなくなった
このような変化の背景には、本人も言葉にできない不安や混乱があります。
実際に「愛の家グループホーム伊東南町」の事例では、新しい環境に慣れず「帰りたい」と訴えていた方が、職員の丁寧な関わりによってわずか1か月で落ち着きを取り戻し、「ここは過ごしやすい」と笑顔で話せるようになりました。
この事例は、周囲の理解と適切なサポートが、本人の精神的な安定にいかに重要であるかを示しています。
(引用元:施設体験談)
認知症の2大症状の一覧
認知症の症状は、大きく「中核症状」と「行動・心理症状(BPSD)」の2つに分けられます。
中核症状は脳の神経細胞が壊れることで直接起こる症状で、BPSDは中核症状に本人の性格や環境などが影響して現れる二次的な症状です。
この2つの違いを理解することが、適切な対応の第一歩となります。
脳の機能低下による「中核症状」
中核症状は、脳の機能が低下することによって誰にでも現れる可能性がある、認知症の基本的な症状です。
これらの症状は、残念ながら現在の医療では完治が難しいとされていますが、薬によって進行を緩やかにすることは可能です。
ここでは、代表的な中核症状を解説します。
記憶障害
記憶障害は、新しい出来事を覚えたり、過去の出来事を思い出したりすることが困難になる症状です。
特に、数分前や数時間前といったごく最近の記憶が抜け落ちてしまうのが大きな特徴といえます。
これは、脳の記憶を司る「海馬」という部分が萎縮することで、新しい情報を一時的に保管する機能が損なわれるためです。
これにより、以下のような具体的な状況が起こります。
- 食事をしたこと自体を忘れ、何度も食事を要求する
- 同じことを何度も質問したり、話したりする
- 約束の日時や内容を完全に忘れてしまう
このように、体験そのものが記憶から消えてしまうため、本人は忘れたという自覚を持ちにくく、周囲との認識のずれが生じやすくなります。
見当識障害
見当識障害とは、時間、場所、人物といった自分を取り巻く状況を正しく認識できなくなる症状です。
多くの場合、「時間」の感覚から曖昧になり、次第に「場所」、そして「人物」の認識へと障害が広がっていきます。
脳が外部からの情報を整理し、現在の状況と結びつける機能が低下することが原因です。
この障害によって、生活の中で様々な混乱が生じます。
- 時間の障害:今日が何月何日か、季節がいつかが分からなくなる。
- 場所の障害:慣れた道で迷う、自宅のトイレの場所が分からなくなる。
- 人物の障害:毎日会っている家族の顔が分からなくなる。
約束を守れなくなったり、危険な状況に陥ったりする可能性があるため、周囲のサポートが不可欠な症状のひとつです。
理解・判断力の障害
この障害は、物事を筋道立てて考えたり、複数の情報を同時に処理したりすることが難しくなる症状です。
思考のスピードが低下し、抽象的な話やいつもと違う出来事への対応が困難になります。
例えば、2つ以上の指示を同時に出されると混乱してしまうのは、この障害が影響しています。
日常生活では、以下のような形で現れます。
- 会話のペースについていけず、話が噛み合わなくなる。
- 自動販売機で切符を買うなど、手順の多い作業ができない。
- 冗談が通じず、真に受けて怒ってしまうことがある。
本人が混乱しないよう、情報をひとつずつ、分かりやすく伝える配慮が求められます。
実行機能障害
実行機能障害は、目標を立てて計画し、段取りよく物事を実行することができなくなる症状です。
日常生活における多くの行動は、無意識のうちに計画と実行を繰り返していますが、この機能が損なわれると、当たり前のことができなくなってしまいます。
例えば、以下のような状況が代表的です。
- 料理:味付けや手順を考えられず、調理を途中でやめてしまう。
- 買い物:必要な物をリストアップし、店で探して買うという一連の行動ができない。
- 片付け:何をどこにしまうべきか判断できず、部屋が散らかったままになる。
できなくなったことを責めるのではなく、作業を細かく分けたり、手順を紙に書いたりするなど、具体的な手助けが有効です。
失語(言葉が出てこない)
失語は、話す、聞く、読む、書くといった言葉を操る能力に障害が起こる症状です。
認知症における失語では、特に「物の名前が出てこない(喚語困難)」が多くみられます。
頭の中では分かっているのに、それを表す適切な言葉が見つからない状態です。
失語の主な特徴は以下の通りです。
- 「あれ」「それ」といった代名詞が会話の中に増える。
- 言いたいことと違う言葉が出てしまうことがある。
- 回りくどい説明で、何とか伝えようとすることがある。
相手の話している内容は理解できている場合が多いため、言いたいことを急かさずに待ったり、選択肢を示して答えやすくしてあげたりするコミュニケーションの工夫が大切になります。
失行(動作の障害)
失行とは、手足に麻痺などの身体的な問題はないにも関わらず、目的を持った一連の動作や、これまで習慣的に行ってきた行動ができなくなる症状です。
脳が体に正しい指令を送れなくなるために起こります。
失行には様々な種類がありますが、代表的な例は以下の通りです。
- 着衣失行:パジャマや下着など、服の上下や表裏が分からず、うまく着られない。
- 観念運動失行:「ハサミで紙を切る真似をして」など、口頭での指示された動作ができない。
- 構成失行:図形を模写したり、積み木を組み立てられない。
一見すると不器用になったように見えますが、これも脳機能の低下による症状のひとつなのです。
失認(物や人を認識できない)
失認は、目や耳などの感覚器官に異常はないのに、対象物が何であるかを正しく認識できなくなる症状です。
視覚や聴覚から入ってきた情報を、脳が過去の記憶と照合して「これは〇〇だ」と判断するプロセスがうまくいかなくなるために生じます。
具体的な症状の例としては、以下のようなものがあります。
- 物体失認:毎日使っているはずの歯ブラシや茶碗が何かわからなくなる。
- 相貌失認:親しい家族や友人の顔を見ても誰だかわからなくなる。
- 身体部位失認:自分の手や足が自分のものであると認識できなくなる。
本人の見ている世界が、私たちとは違って見えている可能性があることを理解し、寄り添うことが重要です。
本人の性格や環境が影響する「行動・心理症状(BPSD)」
BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、中核症状が土台となり、そこに本人の性格、身体的な苦痛、不安な環境、不適切なケアなどが加わって現れる症状です。
そのため、現れる症状やその程度は人によって様々であり、周囲の関わり方次第で改善する可能性があります。
BPSD(周辺症状)の詳細と対応方法も併せてご確認ください。
妄想
妄想とは、明らかに事実とは異なることを、訂正不可能なほど固く信じ込んでしまう症状です。
特に、記憶障害によって置き忘れた物を「誰かに盗まれた」と思い込む「物盗られ妄想」は代表的です。
これは、本人の不安感や孤立感、そして「忘れたのは自分のせいではない」と考えたい心理が背景にあるといわれています。
主な妄想の種類は以下の通りです。
- 物盗られ妄想:「財布を盗まれた」「通帳を隠された」など。
- 見捨てられ妄想:「家族が自分を邪魔者扱いしている」「施設に捨てられる」など。
- 嫉妬妄想:配偶者が浮気をしていると激しく思い込む。
頭ごなしに否定すると、かえって不信感を強めてしまいます。
まずは本人の訴えを受け止め、不安な気持ちに寄り添うことが大切です。
幻覚・幻視
幻覚・幻視は、実際にはそこにないものを、あたかも実在するかのように鮮明に感じてしまう症状です。
特にレビー小体型認知症では、「部屋の隅に子どもがいる」「壁に虫がたくさん這っている」といった、具体的でリアルな幻視が繰り返し現れるのが特徴です。
認知症による幻覚の詳しい原因と対処法について、更に詳しく解説しています。
幻覚・幻視がある方への対応のポイントは以下の通りです。
- 本人が見えているものを否定しない。
- 「怖いですね」「不安ですね」と本人の感情に共感する。
- 部屋を明るくしたり、幻視の原因になりそうな物(壁のシミやハンガーの影など)を取り除いたりする。
本人にとっては紛れもない現実であるため、その世界観を尊重し、安心させてあげることが重要です。
抑うつ・不安
抑うつは、気分が落ち込み、何事にもやる気や興味が持てなくなる症状で、認知症の初期段階によく見られます。
「うつ病」と症状が似ていますが、認知症の抑うつは、自分の認知機能が低下していることへの不安や焦り、将来への悲観などが引き金になることが多いと考えられています。
周囲が気づきやすいサインには、以下のようなものです。
- 口数が減り、表情が乏しくなる。
- 「もう死にたい」「生きていても仕方がない」といった悲観的な言動が増える。
- 食欲がなくなったり、眠れなくなったりする。
励ますつもりの「がんばって」という言葉が、かえって本人を追い詰めてしまうこともあります。
まずはゆっくりと話を聞き、何もせずにそばにいるだけでも、本人の安心につながります。
無気力(アパシー)
無気力(アパシー)は、抑うつとは異なり、特に悲しんでいるわけではないのに、何事に対しても自発的な意欲や関心が著しく低下してしまう状態です。
周りからは「怠けている」「やる気がない」と誤解されがちですが、これも脳の前頭葉の機能低下によって起こる症状のひとつです。
アパシーは具体的に以下のような特徴があります。
- 一日中、何もせずにぼんやりと過ごしている。
- 呼びかけへの反応が乏しくなる。
- 好きだった趣味やテレビ番組などにも関心を示さなくなる。
- 身だしなみに構わなくなり、入浴や着替えを面倒くさがる。
無理に行動を促すのではなく、本人が少しでも興味を示したものがあれば、それをきっかけに関わりを広げていくようなアプローチが有効です。
徘徊・行方不明
徘徊は、一見すると目的もなく歩き回っているように見える行動ですが、本人にとっては切実な理由がある場合がほとんどです。
見当識障害によって自分のいる場所が分からなくなり、「家に帰らなければ」という思いに駆られたり、過去の習慣から「会社に行かなければ」「子どもを迎えに行かなければ」と考えたりすることが原因となります。
徘徊への対応で重要なことは以下の通りです。
- 無理に行動を止めようとしない。
- 「どこかへお出かけですか?」と目的を尋ねてみる。
- 「少し疲れたので、お茶でも飲みませんか」と休憩を促し、関心をそらす。
行方不明のリスクに備え、GPS機能付きの機器を持ってもらったり、地域の見守りネットワークに登録したりすることも大切です。
攻撃的な言動
些細なことをきっかけに、大声で怒鳴ったり、物を投げたり、時には手を出してしまったりする行動です。
これは、自分の思い通りにならないことへの苛立ちや、相手の言動を誤解してしまうこと、自分の気持ちをうまく言葉で伝えられないもどかしさなどが複雑に絡み合って起こります。
攻撃的な言動の背景には、以下のような本人の「困りごと」が隠れている場合があります。
- 身体的な不快感(痛み、かゆみ、便秘など)
- プライドを傷つけられたと感じた時
- 周囲の環境がうるさかったり、急かされたりした時
まずは介護者自身の安全を確保し、本人が落ち着くのを待ちましょう。
そして、何が引き金になったのかを冷静に振り返ることが、再発防止につながります。
介護への抵抗
介護への抵抗は、入浴、着替え、食事、排泄といったケアを頑なに拒否する行動で、介護者を最も悩ませる症状のひとつです。
本人が「なぜそれが必要なのか」を理解できなくなっている場合や、他人に体を触られることへの羞恥心や不快感、あるいはケアのやり方そのものに問題がある場合も考えられます。
介護拒否が見られた時の対応のポイントは以下の通りです。
- 無理強いは決してしない。
- 一度時間を置いて、本人の気分が変わるのを待つ。
- ケアの方法や担当者を変えてみる。
- 本人が納得できるような理由を、分かりやすく説明してみる。
「なぜ拒否するのか」という理由を探り、本人の気持ちに寄り添う姿勢が、信頼関係を築く鍵となります。
不潔行為
不潔行為とは、失禁した下着を隠したり、便を手で触ったり、壁に塗りつけたりする行動を指します。
この行動は、本人に悪意があるわけではなく、様々な理由から起こります。
例えば、失禁という失敗を隠したい一心であったり、便を便と認識できなくなっていたり、あるいは身体の不快感を訴えるためのサインであったりします。
この症状に対応する上で最も大切なことは、本人の尊厳を傷つけないことです。
- 驚いたり、叱ったりせず、冷静に対応する。
- 黙って片付け、清潔な状態に戻す。
- トイレの場所を分かりやすく表示したり、排泄の時間を記録して誘導したりする。
このような行動の背景には、本人の混乱やSOSが隠されていることを忘れないようにしましょう。
睡眠障害
睡眠障害は、夜眠れずに活動してしまう、昼夜のリズムが逆転する、夜中に何度も起きるといった症状の総称です。
加齢によって睡眠が浅くなることに加え、認知症による体内時計の乱れや、日中の活動量不足、精神的な不安などが原因で起こります。
夜間の不眠は、本人の心身の状態を悪化させるだけでなく、介護者の大きな負担にもなります。
睡眠の質を改善するための工夫は以下の通りです。
- 日中はできるだけ太陽の光を浴び、散歩などで体を動かす。
- 昼寝の時間を短くする(15〜30分程度)。
- 就寝前はテレビやスマートフォンの光を避け、リラックスできる環境を作る。
- 夜中に起きてしまった場合は、温かい飲み物を提供するなどして安心させる。
生活リズムを整えることが、最も基本的な対策となります。
興奮・叫び声
興奮や叫び声は、突然、理由が分からず不穏になったり、大きな声を出し続けたりする症状です。
多くの場合、本人が言葉でうまく伝えられない身体的・精神的な苦痛のサインと考えられます。
例えば、体の痛み、便秘、空腹といった不快感や、寂しさ、不安、退屈といった感情が、叫び声という形で表現されることがあります。
このような症状が見られた時のアプローチは以下の通りです。
- まずは本人のそばに行き、優しく体に触れながら「どうしましたか?」と声をかける。
- 身体的な不調がないか確認する(熱はないか、お腹は張っていないかなど)。
- 環境を変えてみる(静かな場所に移動する、好きな音楽をかけるなど)。
MCSケアモデルでは、このようなBPSDを「不確かさ」による不安の表れと捉え、塗り絵などの本人が集中できる活動を提供することで、「確かさ」による安心感を取り戻し、症状を改善させた事例があります。(引用元:施設体験談)
【種類別】4大認知症の症状と特徴
認知症は、原因となる病気によっていくつかの種類に分けられます。
症状の現れ方や進行の仕方が異なるため、種類に応じた適切な対応を知ることが大切です。
ここでは、一般的には、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症の頻度が高く、4大認知症と呼ばれています。
まずは三大認知症の基礎知識から理解を深めるのもよいでしょう。
アルツハイマー型認知症
認知症の中で最も多く、全体の半数以上を占めるタイプです。
脳にアミロイドβやタウといった特殊なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症します。
女性に多く見られる傾向があります。
アルツハイマー病と認知症の違いについても理解しておくと、より知識が深まるでしょう。
主な症状と特徴は以下の通りです。
- 症状:初期は「物忘れ(記憶障害)」から始まることが多い。ゆっくりと進行し、次第に見当識障害や実行機能障害などが現れる。
- 進行:緩やかに進行する。
- 人柄:取り繕うような言動が見られることがある。
- その他:物盗られ妄想などのBPSDが出やすい。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血など、脳の血管の病気(脳血管障害)によって神経細胞が壊れ、発症する認知症です。
脳血管障害が起こるたびに症状が段階的に悪化するのが特徴です。
男性に多く、高血圧や糖尿病などの生活習慣病があるとかかりやすいといわれています。
主な症状と特徴は以下の通りです。
- 症状:障害された脳の部位によって症状が異なるため「まだら認知症」ともいわれる。記憶障害は比較的軽いが、手足の麻痺や言語障害などを伴うことがある。
- 進行:脳血管障害が再発するたびに、階段を降りるように悪化する。
- 人柄:感情の起伏が激しくなり、急に泣いたり笑ったりする「感情失禁」が見られることがある。
- その他:日や時間によって症状に波があることが多い。
レビー小体型認知症
脳の神経細胞に「レビー小体」という特殊なたんぱく質の塊が現れることで発症します。
アルツハイマー型、血管性に次いで3番目に多い認知症で、認知症の原因のうち10~15%を占めます。
レビー小体型認知症の症状詳細はこちらで詳しく解説しています。
主な症状と特徴は以下の通りです。
- 症状:リアルな「幻視(人や虫などが見える)」、手足の震えや筋肉のこわばりといった「パーキンソン症状」が特徴的。
- 進行:症状が良い時と悪い時を繰り返しながら、全体的に進行していく。
- 人柄:真面目で几帳面な性格の人に多いといわれる。
- その他:睡眠中に大声で寝言をいったり暴れたりする「レム睡眠行動異常症」が初期から見られることがある。
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症する認知症です。
他の認知症と比べて、比較的若い65歳未満で発症する「若年性認知症」の原因としても多いタイプです。
性格変化や行動異常が目立つため、周囲が気づきにくいこともあります。
詳細は前頭側頭型認知症とピック病の詳細でご確認ください。
主な症状と特徴は以下の通りです。
- 症状:記憶障害よりも先に、社会のルールを無視した行動(万引きなど)や、同じ行動を繰り返す「常同行動」がみられる。感情の鈍麻や共感性の欠如も特徴。
- 進行:ゆっくりと進行する。
- 人柄:他人への配慮がなくなり、自己中心的な振る舞いが目立つ。
- その他:ピック病とも呼ばれることがある。
認知症の症状の進み方
認知症の症状は、多くの場合、時間をかけてゆっくりと進行していきます。
進行のスピードは人それぞれですが、一般的には「初期」「中期」「後期」の3つの段階に分けられます。
それぞれの段階で現れやすい症状や必要なケアを知っておくことで、将来に備えることが可能です。
より詳しくは認知症の進行過程の詳細で解説しています。
【初期】日常生活は自立、物忘れが目立つ段階
この段階では、日常生活のほとんどを自立して送れます。
しかし、物忘れ(記憶障害)や判断力の低下といった中核症状が現れ始めます。
主な状態と必要なケアは以下の通りです。
- 症状:同じことを何度も聞く、物の置き場所を忘れる、料理の段取りが悪くなるなど。
- 本人の気持ち:自分の変化に戸惑い、不安や抑うつ状態になることがある。
- ケアのポイント:本人のプライドを傷つけないよう、さりげなくサポートする。失敗を責めずに、安心できる言葉かけを心がける。
【中期】一部介護が必要、BPSDが現れやすい段階
中核症状が更に進行し、日常生活を送る上で部分的な介護が必要になってきます。
この時期は、徘徊や妄想、興奮といった行動・心理症状(BPSD)が最も現れやすい時期でもあります。
主な状態と必要なケアは以下の通りです。
- 症状:時間や場所が分からなくなる、着替えや入浴に介助が必要になる、失禁が増えるなど。
- 本人の気持ち:混乱や不安が強まり、コミュニケーションが難しくなることもある。
- ケアのポイント:生活リズムを整え、本人が安心できる環境作りを徹底する。BPSDの背景にある本人の気持ちを汲み取り、原因を取り除く工夫をする。
【後期】常時介護が必要、身体的な合併症も増える段階
症状が更に重度になり、日常生活の全般にわたって常時介護が必要となります。
コミュニケーションは困難になり、多くの場合は寝たきりの状態になります。
重度認知症の詳細な症状についてはこちらをご覧ください。
主な状態と必要なケアは以下の通りです。
- 症状:家族の顔が分からなくなる、言葉を発しなくなる、歩行が困難になる、食事の飲み込み(嚥下)が難しくなるなど。
- 本人の気持ち:意思の疎通は難しいが、感情は残っているといわれる。
- ケアのポイント:身体的な苦痛を和らげるケアが中心となる。肺炎などの合併症を予防するための口腔ケアや、床ずれ防止の体位交換が重要。
家族や自分に認知症の症状が見られた時の相談・受診ガイド
「もしかして認知症かも?」と感じた時、どこに相談し、何科を受診すればよいのか、不安に思う方も多いでしょう。
しかし、認知症は早期の対応が非常に重要です。
ここでは、相談できる窓口や、病院で行われる検査について具体的に解説します。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
まず相談できる相談先
認知症に関する悩みは、様々な場所で相談できます。
本人だけでなく、家族だけでも相談可能です。
受診をためらう場合でも、まずは話を聞いてもらうことから始めましょう。
主な相談先リストは以下のようなものがあります。
- かかりつけ医:まずは最も身近な医師に相談してみましょう。必要に応じて専門医を紹介してくれます。
- 地域包括支援センター:高齢者の暮らしを支える総合相談窓口です。保健師や社会福祉士などの専門家がおり、無料で相談できます。詳しくは地域包括支援センターでの相談方法をご覧ください。
- 専門の医療機関:
- 物忘れ外来:認知症を専門的に診断・治療する外来です。
- 精神科・心療内科:妄想や抑うつなどの精神症状が強い場合に適しています。
- 神経内科:脳の病気を専門とし、パーキンソン症状などがある場合に適しています。
病院で行われる主な検査内容
病院では、認知症かどうか、またその原因や種類を調べるために、いくつかの検査を組み合わせて診断します。
診断を受けることで、適切な治療やケアの方針が決まり、介護保険サービスなども利用できるようになります。
要介護認定の申請と利用できるサービスについても知っておくと安心です。
主な検査内容は以下の通りです。
- 問診:医師が本人や家族から、いつからどのような症状があるか、生活の様子などを詳しく聞き取ります。
- 神経心理学検査:長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)など、質問形式で記憶力や判断力を評価するテストです。
- 画像検査:CTやMRIで脳の萎縮の程度や脳血管障害の有無などを調べます。
- 血液検査:認知症と似た症状を引き起こす他の病気(甲状腺機能低下症など)がないかを確認します。
認知症の症状を和らげて穏やかに過ごすための方法
認知症と診断されても、あるいはその疑いがあっても、悲観する必要はありません。
症状の進行を緩やかにしたり、行動・心理症状(BPSD)を和らげたりするために、できることは色々あります。
ここでは、家族ができるケアの基本から、日常生活の工夫、専門的な治療まで、穏やかな毎日を送るための具体的な方法を紹介します。
家族や介護者ができるケアと接し方の基本(非薬物療法)
薬を使わない「非薬物療法」は、認知症ケアの基本であり、最も重要なアプローチです。
日々の接し方ひとつで、本人の不安を和らげ、BPSDを軽減できることが多くあります。
効果的なコミュニケーション方法を学ぶことも非常に役立ちます。
ケアと接し方の5つの基本は以下の通りです。
- 驚かせない、急かさない、自尊心を傷つけない:認知症ケアの「3ない」原則です。本人のペースに合わせ、一人の人間として尊重する姿勢が大切です。
- 否定せずに、まずは共感し受け止める:本人の言葉や行動を頭ごなしに否定せず、「そうなんですね」と一度受け止めましょう。安心感が信頼関係につながります。
- 短く、分かりやすい言葉で話す:一度に多くの情報を伝えず、具体的で簡潔な言葉を選んで、ゆっくりと話しかけることがポイントです。
- 本人に役割を持ってもらう:簡単な家事など、本人ができることを見つけて役割をお願いすると、自信や意欲の向上につながります。秋田県の施設では、元清掃員の経験を活かして掃除をお願いしたところ、笑顔が戻り「ここが私の居場所」と話すようになった事例もあります。(引用元:施設体験談)
- 安心できる環境を整える:生活環境をなるべく変えず、使い慣れた物をそばに置くなど、本人が混乱しないように配慮します。
【症状別】具体的な対応事例と声かけ
BPSDには、その背景に必ず本人の何らかの理由や感情があります。
症状そのものではなく、その原因に目を向けることが大切です。
ここでは、よくある症状への具体的な対応例を紹介します。
ただし、言ってはいけない言葉と適切な接し方もあるため注意が必要です。
| 症状 | 対応のポイント | 声かけの例 |
|---|---|---|
| 物盗られ妄想 | 否定せずに一緒に探す。本人の不安な気持ちに寄り添う。 | 「大変!それは心配ですね。一緒に探しましょう」 |
| 徘徊・帰宅願望 | 行動を制止せず、理由を聞く。散歩に誘うなどして気分転換を図る。 | 「お家に帰りたいのですね。お茶を一杯飲んだら、一緒に行きましょうか」 |
| 介護拒否 | 無理強いはしない。時間や方法、担当者を変えてみる。 | 「今は気が進まないのですね。また後で伺いますね」 |
| 暴力・暴言 | まずは安全を確保し距離を置く。興奮が収まったら、原因を探る。 | (落ち着いてから)「何か嫌なことがありましたか?」 |
| 幻視 | 見えているものを否定せず、まずは本人の恐怖や不安な気持ちを受け止める。 | 「私には見えませんが、怖いですね。大丈夫ですよ、私がそばにいますから」 |
「愛の家グループホーム弥富」では、「自由に外出したい」という本人の思いを実現するため、地域住民の協力も得て一人で散歩できる環境を整えました。
その結果、興奮状態が落ち着き、笑顔が多く見られるようになりました。
このように、本人の思いを尊重する個別支援が、心理的な安定につながります。(引用元:施設体験談)
症状の進行を遅らせるために日常生活でできること
認知症の進行を緩やかにし、心身の機能を維持するためには、日々の生活習慣が非常に重要です。
本人も楽しみながら続けられることを、生活の中に少しずつ取り入れていきましょう。
これまでの多くの研究で、中年期・老年期の運動習慣や定期的な身体活動が、アルツハイマー型認知症を含む認知症の発症率を低下させることが報告されています。
認知症予防に効果的な生活習慣を意識することが、結果的に症状の緩和につながります。
バランスの取れた食事
低栄養は認知機能の低下を招きます。
日々の食事では、脳のエネルギー源となる炭水化物、神経細胞を作るたんぱく質、体の調子を整えるビタミン・ミネラルをバランスよく摂取することが基本です。
特に、以下の栄養素を意識するとよいでしょう。
- DHA・EPA:脳の血流をよくするといわれる。サバやイワシなどの青魚に豊富。
- ビタミンC・E:抗酸化作用があり、神経細胞を守る働きが期待される。野菜や果物、ナッツ類など。
- たんぱく質:筋肉や血液の元となり、活動的な体を維持するために不可欠。肉、魚、卵、大豆製品など。
健達ねっとでは、高齢者の食事への関心を高めるマンガ形式のレシピ本「ハルと思い出めぐりごはん」も出版しています。
回想法を取り入れた懐かしいレシピは、食欲だけでなく、楽しい記憶を呼び覚ますきっかけにもなります。
また、健達ねっとでは認知機能が改善するサプリメントの販売も行っています。
上記の栄養素を含むサプリメントもあるので、日々の食事と併せてご活用ください。
定期的な運動
適度な運動は、脳の血流を促進し、神経細胞を活性化させる効果が期待できます。
また、体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、質のよい睡眠にもつながります。
大切なのは、無理なく楽しみながら続けられることです。
認知症予防に効果的な運動方法も参考に、以下の運動を取り入れてみましょう。
- 有酸素運動:ウォーキング、軽いジョギング、水泳など。週に3回以上、1回30分程度が目安。
- 筋力トレーニング:スクワットや椅子からの立ち座りなど、下半身の筋肉を鍛える運動。
- デュアルタスク運動:計算しながら歩くなど、2つのことを同時に行う運動。脳の活性化に効果的。
また、食事をおいしく食べ続けるためには、飲み込む力(嚥下機能)の維持も重要です。
「健達ねっと」では、新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が開発した、1回5秒でできる「ノドトレ」も紹介しています。(引用元:ノドトレ詳細)
質のよい睡眠
睡眠は、脳と体を休息させ、日中に得た情報を整理するために不可欠です。
睡眠不足や昼夜逆転は、BPSDを悪化させる大きな要因となります。
質のよい睡眠を確保するためには、生活リズムを整えることが基本です。
以下のポイントを意識して、快適な睡眠環境を作りましょう。
- 毎日、同じ時間に起きて、同じ時間に寝ることを心がける。
- 日中は太陽の光を十分に浴びて、体内時計をリセットする。
- 昼寝をする場合は、15時までに30分以内にとどめる。
- 就寝前は、スマートフォンやテレビの強い光を避ける。
規則正しい生活が、夜の穏やかな眠りへとつながります。
知的活動・趣味
脳に適度な刺激を与え、活発に使い続けることは、認知機能の維持に役立ちます。
計算ドリルやパズルなどのいわゆる「脳トレ」も有効ですが、何よりも本人が「楽しい」と感じられる活動を続けることが長続きの秘訣です。
本人のこれまでの経験や興味関心に寄り添い、活動のきっかけを作ってみましょう。
具体的には、以下のような活動が挙げられます。
- 趣味:編み物、園芸、将棋、カラオケ、絵画など、昔からの趣味を続ける。
- 学習:新しい楽器に挑戦する、英会話を学ぶなど。
- 家事:料理や掃除など、できる範囲で役割を担ってもらう。
「やらされている」と感じるとストレスになるため、本人の自発性を尊重する姿勢が大切です。
社会とのつながり
孤立は、認知症の進行を早める最も大きな危険因子のひとつです。
社会的孤立を避けることなどにより、認知症の一部は予防できる可能性があるとする研究もあります。
他者とのコミュニケーションは、脳にとって最高の刺激であり、精神的な安定にもつながります。
意識的に社会との接点を持つ機会を作り、本人の世界が狭まらないようにサポートしましょう。
社会とのつながりを保つための方法は様々です。
- 家族や友人、近所の人と積極的に会話する。
- デイサービスや地域のサロン、老人会などに参加する。
- 趣味のサークル活動に参加する。
「愛の家グループホーム帯広東12条」の事例では、ご主人を亡くされた後も、職員との日々の関わりで生まれたよい感情の記憶が、ご本人の「ここが私の居場所」という安心感につながっています。
信頼できる人との温かい関係性が、心の支えになるのです。(引用元:施設体験談)
専門医による薬での治療(薬物療法)
認知症の症状を和らげるためには、薬による治療も選択肢のひとつです。
薬物療法には、中核症状の進行を緩やかにすることを目的とした薬と、BPSDを緩和することを目的とした薬があります。
詳しくは認知症の治療法全般をご覧ください。
主な認知症治療薬は以下の通りです。
- 抗認知症薬:アルツハイマー型認知症の中核症状に対しては、コリンエステラーゼ阻害薬(塩酸ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)とNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)に改善効果があることが認められています。レビー小体型認知症では、塩酸ドネペジルのみ保険適応が認められています。しかし、これらの薬剤の効果は一時的で、認知症の進行を完全に抑えるものではありません。
- 向精神薬:幻覚、妄想、興奮、抑うつなどのBPSDを緩和するために用いられる。BPSDに対しては、適切なケアや環境調整、リハビリテーション等の非薬物療法が優先されます。抗精神病薬などを使用する際には、高齢者では副作用が生じやすいこと、転倒や骨折のリスクが高くなること、死亡リスクが上昇することを考慮し、慎重に行う必要があります。
薬には効果だけでなく副作用のリスクもあるため、認知症治療薬の効果と副作用を正しく理解することが重要です。
メディカル・ケア・サービスでは、ケアによって症状が改善した場合に、医師と連携して不要な薬を減らしていく「薬の適正化」にも取り組んでいます。
薬はあくまで補助的なものであり、ケアと組み合わせることで最大の効果を発揮するといえるでしょう。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、認知症の様々な症状について、その種類や特徴、進行の仕方、そして具体的な対処法までを詳しく解説しました。
この記事のポイントは以下の通りです。
- 認知症は、加齢による物忘れとは異なり、日常生活に支障が出る脳の病気である。
- 症状は、脳機能の低下で起こる「中核症状」と、環境やケアで改善可能な「行動・心理症状(BPSD)」に大別される。
- アルツハイマー型やレビー小体型など、原因となる病気によって症状の現れ方が異なる。
- 症状は「初期・中期・後期」と段階的に進行するが、早期からの適切な対応が重要となる。
- 薬だけに頼らず、本人の尊厳を守るケアや生活習慣の工夫で、症状を和らげ穏やかに過ごすことは可能である。
認知症は、誰にでも起こりうる非常に身近な病気です。
しかし、正しい知識を持ち、適切なケアを実践することで、ご本人もご家族も、その人らしい生活を続けることが可能です。
もし、あなたやあなたの大切な人に気になる症状が見られたら、一人で抱え込まず、かかりつけ医や地域包括支援センターなどの専門機関に相談するようにしましょう。
その一歩が、穏やかな未来へとつながっていきます。