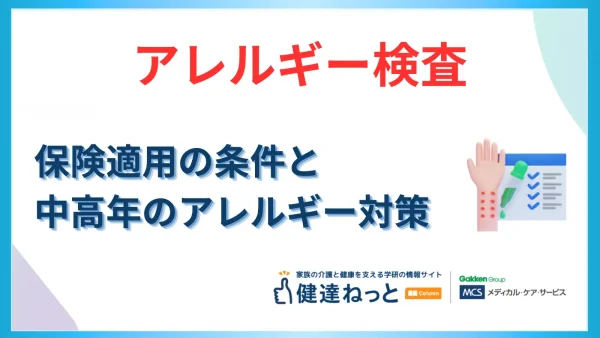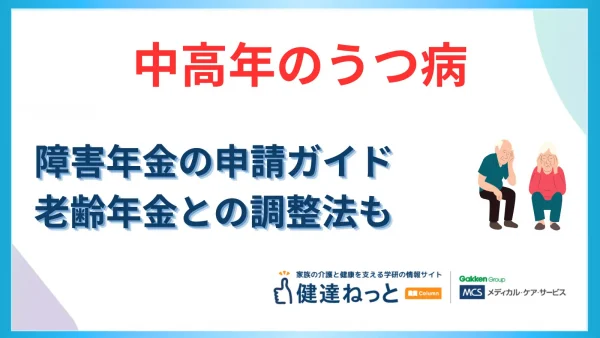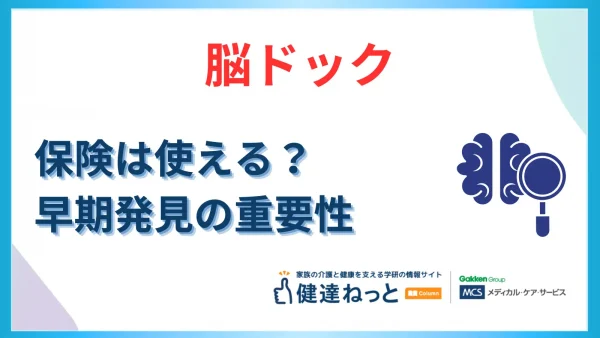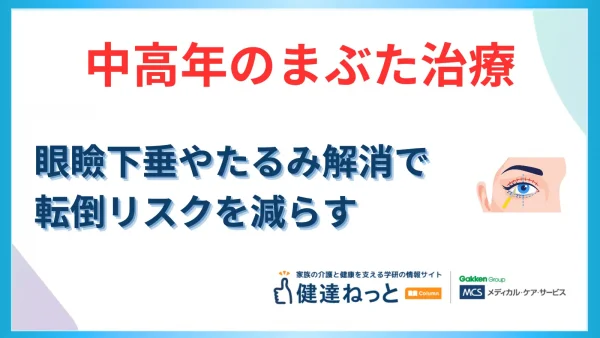配信サービスで観る
あらすじ
62歳の漫画家・ゆういち(愛称ペコロス)の89歳の母・みつえは、認知症の症状が進行し、グループホームに入居する。
面会に訪れた息子のことが分からず、そのはげ頭を見てようやく「ペコロス」と思い出す母。
夫が亡くなったことを忘れ、見えない夫と話をする姿や、原爆で失った幼い妹の幻を見る母を、ゆういちは優しく見守る。
少しずつ少女に戻っていく母との日々の中で、ゆういちは過ぎ去った思い出に心を馳せる。
長崎の歴史と家族の記憶が交錯する、笑いと涙の物語。
特徴・見どころ
「介護」や「認知症」と聞くと、私たちはどうしても「大変だ」「つらい」「悲壮なもの」といったイメージを抱きがちです。
しかし、本作『ペコロスの母に会いに行く』は、そうした介護映画の固定観念を、温かく、そして優しく覆してくれる、類まれな作品です。
原作は、著者である岡野雄一さんが、ご自身の認知症の母親との実体験を描いた同名の漫画。
実話だからこそ感じられるリアリティと、著者ならではのユーモラスな視点が、観る者の心をじんわりと温めます。
物語の舞台は、長崎。
主人公は、バツイチで還暦間近のマンガ家・ゆういち(岩松了)。
彼の母・みつえ(赤木春恵)は、夫を亡くしてから少しずつ認知症が進み、グループホームでお世話になっています。
ゆういちは、そんな母の元へ、まるで小さな玉ねぎ(=ペコロス)のようなハゲ頭を揺らしながら、足しげく通うのです。
ギネス世界記録・赤木春恵の「映画初主演」
本作を語る上で絶対に欠かせないのが、母・みつえを演じた故・赤木春恵さんの存在です。
当時88歳であった赤木さんは、この作品で驚くべきことに「映画初主演」を果たしました。
この功績により、彼女は「世界最高齢での映画初主演女優」としてギネス世界記録に認定されています。
しかし、本作の見どころは、そうした記録的な側面だけではありません。
赤木さんが演じるみつえは、ただ「認知症の人」として存在するのではなく、一人の人間としての「愛らしさ」や「チャーミングさ」に満ちあふれています。
息子のことは忘れてしまっても、施設で出会う人々や、ふとした瞬間に見せる笑顔は、彼女が歩んできた人生の豊かさを感じさせます。
名優・赤木春恵が、その長いキャリアの集大成として辿り着いた、深遠でありながらも自然体な演技は必見です。
「頑張らない介護」という、息子の温かな視点
本作のもう一人の主人公は、息子・ゆういちです。
彼は、認知症の初期症状を見せる母に対し、必死に「介護を頑張る」わけではありません。
また、認知症の進行を「食い止めよう」と奮闘するのでもありません。
彼はただ、母の変化をありのままに受け入れ、まるで観察日記をつけるかのように、その日常をユーモラスに見つめます。
この「頑張らない」「受け入れる」という息子のスタンスこそが、本作全体を包む温かな空気感の源です。
メガホンを取ったのは、喜劇映画の名手である森崎東監督。
監督の温かな演出は、介護の現実を描きながらも、決して重苦しくなることなく、母と子の間に流れる愛情の機微を丁寧にすくい取っていきます。
母が徘徊して騒動が起きても、どこかクスッと笑ってしまう。
そんな「深刻になりすぎない」視点が、介護に疲れた家族の心をそっと軽くしてくれるのです。
「ボケるのも、悪か事ばかりじゃなか」
本作のテーマを象徴するのが、「死んだ父ちゃんに会えるなら、ボケるのも悪か事ばかりじゃなかかもしれん」という、母・みつえの言葉です。
認知症によって、彼女の記憶は現在から過去へと遡っていきます。
目の前にいる息子のことは忘れてしまっても、彼女の心の中では、若き日に愛した夫(=父ちゃん)との幸せな日々が、鮮やかに蘇っているのです。
認知症は、確かに多くの記憶を奪っていきます。
しかし本作は、認知症を「喪失」としてだけ描くのではなく、彼女が「自分自身の幸せな記憶の世界に帰っていく」プロセスとして、優しく肯定します。
息子のゆういちは、母が自分を忘れても、母が「父ちゃん」に会えて幸せそうなら「それも良か」と、その世界を丸ごと受け入れます。
介護の現実を描きながらも、そこには絶望ではなく、家族の絆と確かな希望が描かれています。
認知症という出来事を、家族がどう受け止め、どう乗り越えていくか。
その一つの「答え」として、観る者に深い感動と、「これでいいんだ」という安堵感を与えてくれる、珠玉の作品です。