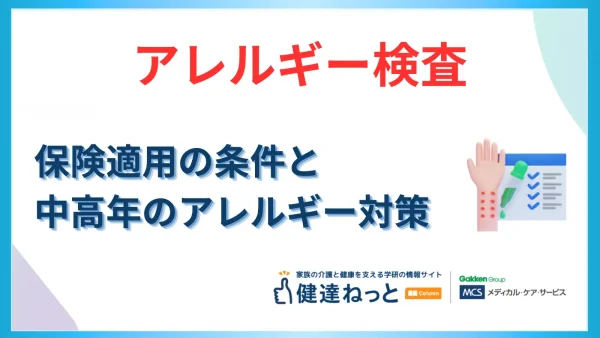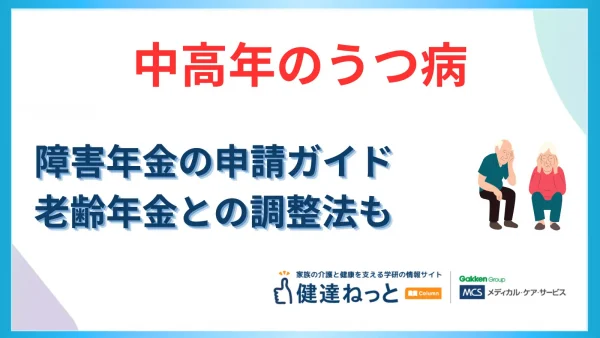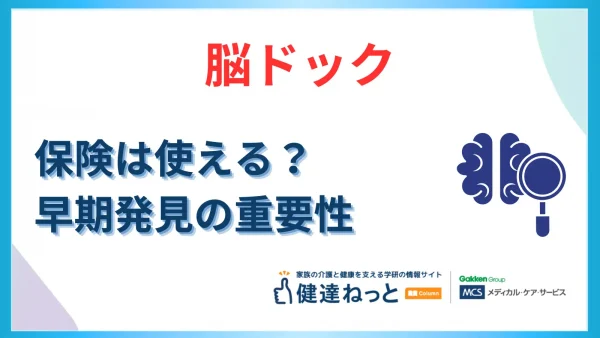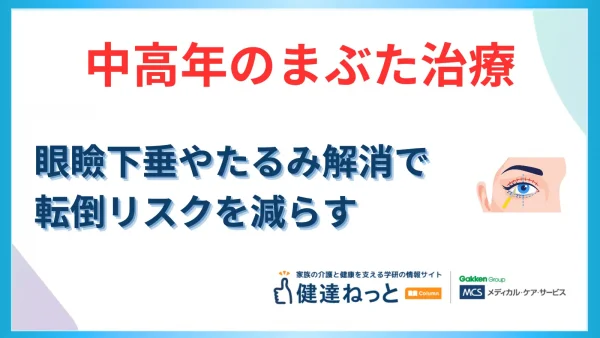あらすじ
家族と暮らす高齢の父は、最近物忘れがひどく会話も成り立たなくなってきた。
家族は父が認知症になったのではないかと心配する。
ふらっと外出しては警察のお世話になることも増え、家族の不安は募るばかり。
しかし、実は父は認知症ではなく、耳が聞こえにくくなっていただけだった。
難聴により周囲とのコミュニケーションが取れず、認知症と誤解されていたのだ。
家族が父の聴力の問題に気づき、適切な対応をすることで、父の表情が明るくなり、家族の絆も深まっていく。
特徴・見どころ
「最近、家族との会話が噛み合わない」。
「呼びかけても、反応が鈍くなった」。
そうした高齢者の変化を、私たちは安易に「認知症が始まったのかもしれない」と思い込んでいないでしょうか。
本作『気づかなくてごめんね』は、まさにその「思い込み」に鋭く警鐘を鳴らす、短編啓発映画です。
制作したのは、会話支援機器メーカー。
彼らがこの映画を通して伝えたかったのは、「認知症と誤認されていた行動が、実は『難聴』が原因だった」という、非常に見過ごされがちでありながら、深刻な問題です。
本作は、高齢者の「聞こえ」の問題が、いかに本人の尊厳や家族関係に影響を及ぼすかを、静かに、しかし力強く描き出しています。
石倉三郎が「話さない」演技で伝える、孤立の痛み
本作の大きな見どころは、主演の石倉三郎さんが見せる、圧巻の演技です。
彼が演じるのは、耳が聞こえにくくなった高齢の男性。
驚くべきことに、石倉さんはこの役を「一言も話さない」ことで表現しています。
家族が楽しそうに会話をしていても、自分だけがその輪に入れない。
何を言っているのか分からず、聞き返すのも億劫になり、やがて諦めたように笑ってごまかす。
そして、次第に自信を失い、自らコミュニケーションを遮断し、社会的に孤立していく。
この「話さない」演技は、セリフ以上に雄弁に、聴力の衰えによって心が傷つき、他者から隔絶されていく高齢者の悲しみ、疎外感、そして諦めを、観る者の胸に突き刺します。
家族は、そんな彼の姿を「無気力になった」「ぼんやりしている」と捉え、認知症の初期症状ではないかと疑い始めます。
本人は「聞こえない」だけなのに、その苦しみに誰も「気づかない」。
このすれ違いの描写こそが、本作の核心です。
「ヒアリングフレイル」が認知症と誤認される理由
本作が光を当てるのは、「ヒアリングフレイル」という重要な概念です。
これは、加齢などにより聴覚機能が低下した状態を指します。
なぜ、このヒアリングフレイルが、認知症の初期症状と誤認されやすいのでしょうか。
それは、聴力の低下が引き起こす行動が、認知症の症状と非常によく似ているからです。
- 会話についていけず、反応が遅れる、あるいは無反応になる。
- 聞き間違いが増え、的外れな答えをしてしまう。
- 何度も聞き返すことを恐れ、会話そのものを避けるようになる。
- 結果として、他者との交流が減り、家に閉じこもりがちになる。
こうした「社会的な孤立」や「コミュニケーションの意欲低下」は、認知機能の低下とも密接に関連していると言われています。
本作は、この実態をドラマとしてリアルに描くことで、本人の状態を正しく理解し、早期に適切な対応(補聴器の利用や会話支援機器の導入など)をとることの重要性を、強く訴えかけています。
「気づく」ことから始まる、孤立の防止
本作は、犬童一心監督による第1作が大きな反響を呼び、その後、武田知大監督による「デイサービス編」も制作されました。
それは、この「難聴による認知症誤認」という問題が、家庭内だけでなく、介護の現場(デイサービスなど)でも深刻であることを示しています。
デイサービスで、他の利用者と馴染めず、一人ポツンと過ごしている高齢者。
その原因は、協調性がないからでも、認知症が進んでいるからでもなく、単純に「周りの声が聞こえていない」からかもしれません。
認知症のチェックを行う際には、まず聴力検査をしっかりと行い、「聞こえ」の問題がないかを確認する必要がある。
本作は、その啓発的な役割も担っています。
『気づかなくてごめんね』というタイトルは、家族や介護者から、聞こえずに苦しんでいた本人への「謝罪」であると同時に、今まさに同じ状況にいるかもしれない人々へ向けた、社会全体へのメッセージです。
高齢者の孤立を防ぐ第一歩は、私たちが「もしかして、聞こえていないのでは?」と、その可能性に「気づく」ことから始まるのです。