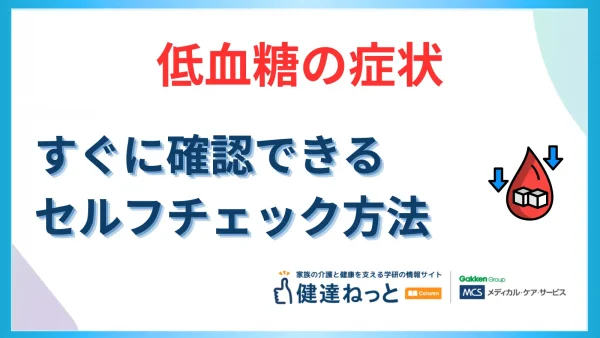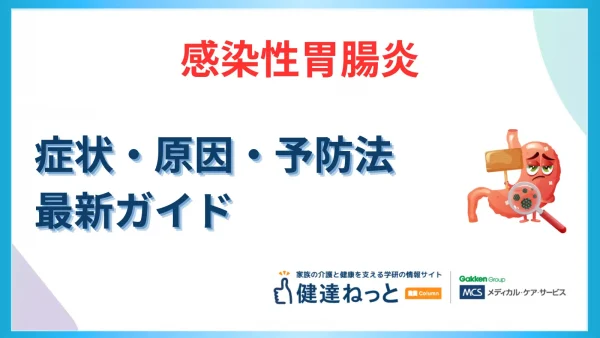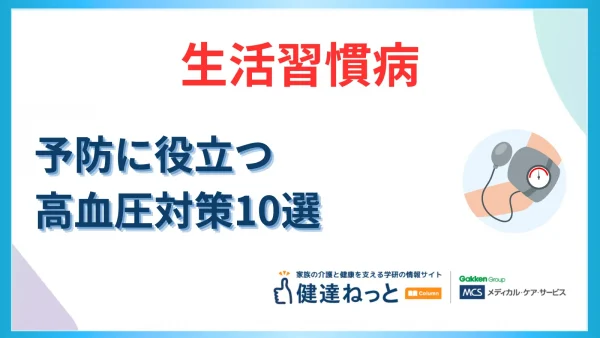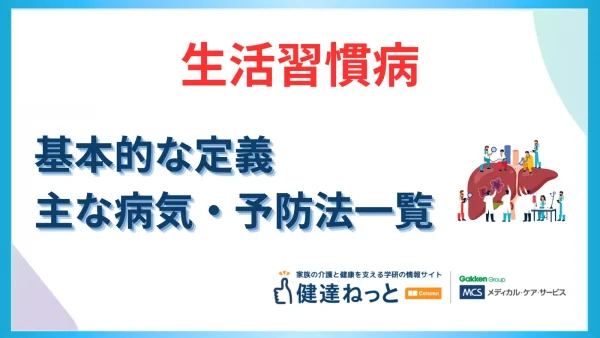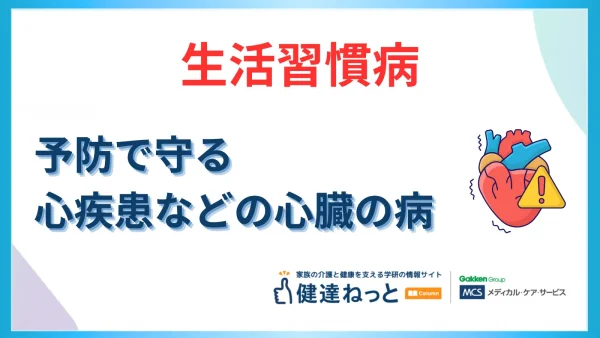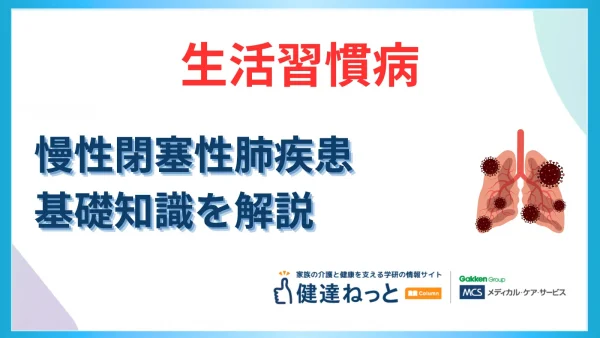- 「急な冷や汗や動悸がして、理由が分からず不安…」
- 「食事を抜くと、頭がぼーっとして集中できないことがある」
- 「このまま放置して、仕事中や運転中に意識を失ったらどうしよう…」
このような身体のサインに、心当たりはありませんか。
その不調は、もしかしたら「低血糖」が原因かもしれません。
低血糖は誰にでも起こりうる身近な症状ですが、放置すると重大な事態につながる可能性もあり、身体だけでなく心にも大きな不安をもたらします。
この記事では、ご自身の症状が低血糖に当てはまるかを確認できるセルフチェックリストから、いざという時の正しい対処法、そして繰り返さないための予防策までを網羅的に解説します。
- 今の症状が低血糖かどうかが明確になる
- 症状のレベルに応じた適切な対処法が分かる
- 低血糖を予防し、安心して毎日を送るための知識が身につく
この記事を読めば、低血糖への漠然とした不安が解消され、ご自身の健康を主体的に管理するための具体的な一歩を踏み出せるでしょう。
スポンサーリンク
【まずはセルフチェック】低血糖に当てはまる症状かの確認ポイント
ご自身の体調不良が低血糖によるものかを見極めることは、適切な対処への第一歩です。
血糖値の低下レベルによって現れる症状は異なります。
まずはご自身の症状がどの段階に当てはまるか、冷静に確認してみましょう。
初期症状(自律神経症状):血糖値60-70mg/dL未満で現れやすいサイン
血糖値が下がり始めると、体は血糖値を上げようとして警告サインを出します。
これを自律神経症状といい、比較的早い段階で自覚できることが多いです。
放置すると次の段階に進んでしまうため、このサインに気づくことが非常に重要です。
具体的には、以下のような症状が現れます。
- 異常な空腹感
- 冷や汗
- 動悸(心臓がドキドキする)
- 手足の震え
- 不安な気持ちになる
- 顔面が蒼白になる
- 吐き気
- 目がチカチカする
これらの症状は、体がエネルギー不足を訴えている証拠です。
「少し疲れているだけかな?」と見過ごさず、体の声に耳を傾けましょう。
中程度の症状(中枢神経症状):血糖値50mg/dL未満で危険度が増すサイン
初期症状に気づかず血糖値がさらに低下すると、脳のエネルギー不足が深刻になります。
その結果、脳の働きが低下して起こるのが中枢神経症状です。
この段階では、自分自身で異常に気づきにくくなることもあり、周囲のサポートが重要になるケースも少なくありません。
危険度が増しているサインとして、以下の症状に注意しましょう。
| 症状の種類 | 具体的な状態 |
|---|---|
| 意識・思考力の低下 | 強い眠気、めまい、ふらつき、集中力の低下 |
| 身体機能の異常 | 頭痛、ろれつが回らない、目のかすみ |
| 感情・行動の変化 | いつもと違う奇妙な行動をとる |
これらの症状は、脳が正常に機能していない危険な状態を示しています。
放置すれば、さらに重篤な状態へと進行する可能性が高いです。
重度の症状:命に係わる緊急性の高いサイン
血糖値が極度に低下すると、大脳の機能が著しく低下し、命に係わる非常に危険な状態に陥ります。
このレベルになると、自力での回復は困難であり、一刻も早い医療介入が必要です。
ご自身だけでなく、周りの人にこのような症状が見られた場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
命の危険がある緊急性の高いサインは以下の通りです。
- 意識が朦朧とする、呼びかけに反応しない
- 異常な行動(興奮、暴れるなど)
- けいれんを起こす
- 意識を完全に失う(昏睡)
このような重篤な症状は、脳に深刻なダメージを与える可能性があります。
最悪の事態を避けるためにも、迅速かつ適切な対応が求められます。
特に注意すべき「無自覚性低血糖」
低血糖を繰り返している方や、一部の糖尿病患者の方では、初期症状である自律神経症状が現れないことがあります。
これを「無自覚性低血糖」といい、警告サインなしに、突然意識障害といった重い中枢神経症状が起こるため非常に危険です。
特に高齢者の場合、認知症の症状と間違われることも少なくありません。
低血糖による意識障害は、脳の機能に影響を及ぼす可能性があります。
記憶や判断力の変化には日頃から注意を払うことが大切です。
詳しくは物忘れと認知症の違いは?物忘れから考えられる病気についても解説で解説していますので、あわせてご覧ください。
スポンサーリンク
【緊急度別】低血糖の症状が出た時の正しい対処法
低血糖の症状が現れたら、パニックにならず冷静に対処することが重要です。
意識の状態によって対処法は大きく異なります。
いざという時のために、正しい知識を身につけておきましょう。
【基本の応急処置】意識がある場合にすぐ行うこと
意識がはっきりしていて、自分で飲食ができる場合は、速やかに糖分を補給することが基本です。
吸収の早いブドウ糖が最も効果的です。
車の運転中や危険な作業中は、ただちに中断し、安全な場所で対処するようにしましょう。
応急処置のポイントは以下の通りです。
- ブドウ糖を10g摂取する
- ブドウ糖がない場合は、砂糖約20gやブドウ糖を含む清涼飲料水・ジュースを150~200ml飲む
- 15分経っても症状が改善しない場合は、もう一度同じ量を摂取する
薬局やコンビニで手軽に購入できるブドウ糖を、普段からカバンなどに入れて携帯しておくと安心です。
【緊急】意識がない・朦朧としている場合
意識がない、または朦朧としていて自分で飲食ができない場合は、家庭での対処は困難であり、極めて危険な状態です。
無理に食べ物や飲み物を口に入れると、窒息の危険があるため決して行わないでください。
このような場合は、一刻も早く専門的な医療が必要です。
周りの人が行うべき緊急対応は以下の通りです。
- ためらわずに救急車を要請する
- 体のベルトを緩めるなど、楽な姿勢にする
- 糖尿病で処方されているグルカゴン注射があれば、家族が使用する
ご家族や職場の人など、身近な人にもしもの時の対応を共有しておくことが、ご自身の命を守ることにつながります。
低血糖の対処でやってはいけないこと
慌てていると、よかれと思ってとった行動が逆効果になることがあります。
特に、糖分の種類と服用中の薬には注意が必要です。
間違った対処法は回復を遅らせるだけでなく、症状を悪化させる可能性もあります。
対処時の注意点を以下にまとめました。
- チョコレートや飴、スナック菓子に頼らない:
脂肪分やたんぱく質が多く、糖の吸収が遅いため、緊急時の対応には不向き - α-グルコシダーゼ阻害薬(糖の吸収を遅らせる薬)を服用中の場合:
砂糖では分解・吸収できないため、必ず「ブドウ糖」を摂取する必要がある - 運転や危険な機械の操作を続けない:
意識レベルが低下し、重大な事故につながる危険がある
正しい知識を持つことが、迅速で安全な回復への鍵となります。
生活習慣病になっているかもしれないと気になる方も多いのではないでしょうか。生活習慣病になってしまう原因がわかれば、予防ができます。本記事では生活習慣病の原因について以下の点を中心にご紹介します。 生活習慣病の原因とは 生活習[…]
低血糖の原因として考えられる7つの要素
低血糖は、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。
原因を理解することは、再発防止の第一歩です。
ご自身の生活習慣や健康状態と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。
糖尿病の治療薬
低血糖の最も多い原因は、糖尿病の治療に用いる一部の薬(インスリン注射やSU薬など)によるものです。
薬の効果が食事の量や運動量と合わない時に、血糖値が下がりすぎてしまうことがあります。
薬の量や種類、食事の時間を自己判断で変更するのは非常に危険です。
糖尿病患者の方で低血糖を頻繁に起こす場合は、血糖値が高いとどうなる?原因や症状を徹底解説!で解説している高血糖の管理方法もあわせて確認し、血糖値の適切なコントロールを心がけましょう。
また、インスリンは血糖値を下げるホルモン|働きと抵抗性を詳しく解説!では、インスリンの詳しい働きについて専門的に解説しています。
食生活の乱れ
私たちの体は、食事から得る糖分をエネルギー源としています。
そのため、食生活の乱れは血糖値の不安定に直結します。
特に、食事を抜いたり、極端な糖質制限ダイエットを行ったりすると、エネルギー源が枯渇し低血糖を引き起こしやすくなるのです。
逆に、糖質を一気に過剰摂取すると、血糖値が急上昇し、その反動で急降下することもあります。
血糖値を安定させるためには、血糖値を下げる方法は?食事からサプリメントまで一挙ご紹介!で紹介している食事療法が効果的です。
特にGI値とは?人体に与える影響から低GI値食品を紹介!で解説されているGI値を意識した食事選択が重要です。
空腹時の激しい運動
運動は血糖値を下げる効果がありますが、特に空腹時に長時間激しい運動をすると、蓄えられていたエネルギー(グリコーゲン)を使い果たし、低血糖に陥ることがあります。
運動前には軽く糖分を補給するなど、エネルギー不足にならないような工夫が必要です。
運動の強度や時間と、食事のバランスを考えることが大切です。
アルコールの摂取
アルコール、特に空腹時の飲酒は低血糖の大きな原因となります。
アルコールが肝臓で分解される際に、肝臓での糖の生成が抑制されてしまうためです。
さらに、アルコールの影響で低血糖の初期症状に気づきにくくなったり、判断力が低下して対処が遅れたりする危険性もあります。
お酒を飲む際は、必ず食事と一緒にとるようにしましょう。
胃の切除後など
胃の手術を受けた方は、食べた物が急速に腸に流れ込む「ダンピング症候群」によって、食後に反応性の低血糖を起こすことがあります。
食べ物が急激に吸収されることで血糖値が急上昇し、それを下げようとインスリンが過剰に分泌され、結果として低血糖状態に陥ってしまうのです。
食事を少量ずつ頻回に分けるなどの工夫が求められます。
インスリノーマや副腎、下垂体の病気
非常に稀ですが、インスリンを過剰に作り出す膵臓の腫瘍「インスリノーマ」や、血糖値を調整するホルモンの異常(副腎皮質機能低下症など)といった病気が原因で低血糖が起こることもあります。
食事や生活習慣に関係なく、特に空腹時に低血糖を繰り返す場合は、これらの病気の可能性も考え、専門医に相談することが重要です。
ストレスやホルモンバランスの乱れ
強いストレスは、血糖値をコントロールする自律神経やホルモンのバランスを乱す原因となります。
ストレスに対抗するために分泌されるホルモンは血糖値を上げる働きがありますが、慢性的なストレス状態が続くと、このシステムがうまく機能しなくなり、血糖値が不安定になることがあります。
心身のサインを見逃さず、適切な休養をとることも大切です。
機能性低血糖症(反応性低血糖症)とは
糖尿病ではないのに、食後に低血糖の症状が現れることがあります。
これを「機能性低血糖症(反応性低血糖症)」といいます。
近年の食生活の変化などを背景に、この症状に悩む人が増えているといわれています。
機能性低血糖症の予防には、生活習慣病における一次予防の重要性。一次予防の具体的な方法は?で解説されている予防アプローチが効果的です。
また、食事による生活習慣病予防とは?予防内容やおすすめレシピを紹介では、具体的な食事療法について詳しく説明されています。
機能性低血糖のメカニズム
機能性低血糖症は、主に糖質の多い食事を摂取した後に起こります。
そのメカニズムは以下の通りです。
- 血糖値の急上昇:
清涼飲料水や菓子類、精製された炭水化物などを摂取すると、糖質が急速に吸収され、血糖値が急激に上昇します。 - インスリンの過剰分泌:
急上昇した血糖値を下げようと、膵臓からインスリンというホルモンが必要以上に分泌されてしまいます。 - 血糖値の急降下:
過剰に分泌されたインスリンの働きで、血糖値が正常範囲を下回るまで急激に低下し、低血糖症状を引き起こします。
このように、血糖値の乱高下が症状の根本的な原因です。
機能性低血糖症になりやすい人の特徴
ご自身の食生活や生活習慣が、機能性低血糖症のリスクを高めていないかチェックしてみましょう。
特に、無意識のうちに血糖値を急上昇させる習慣が身についている方は注意が必要です。
以下のような特徴に当てはまる方は、リスクが高いといえます。
- 甘いジュースやお菓子を日常的に摂取する
- パンや麺類など、精製された炭水化物が中心の食事が多い
- 食事を早食いする習慣がある
- ストレスを強く感じやすい
- 朝食を抜くことが多い
これらの習慣は、血糖値のコントロールを難しくします。
心当たりのある方は、生活習慣の見直しを検討しましょう。
低血糖症を繰り返さないための予防策
低血糖は、一度経験すると「また起こるのではないか」という不安につながります。
しかし、日々の生活習慣を見直すことで、そのリスクを大幅に減らすことが可能です。
食事・運動・生活習慣の3つの側面から、具体的な予防策を見ていきましょう。
食事のポイント
血糖値の安定には、食事が最も重要な役割を果たします。
何を、いつ、どのように食べるかを意識するだけで、体は大きく変わります。
日々の積み重ねが、低血糖の不安から解放される鍵となるのです。
低血糖予防のための食事のポイントは以下の通りです。
| ポイント | 具体的な実践方法 |
|---|---|
| 規則正しい食事 | 1日3食、なるべく決まった時間に食べる。食事を抜かない。 |
| 食べる順番の工夫 | 食事の最初に野菜やきのこ類(食物繊維)から食べる。 |
| 糖質の選び方 | 白米より玄米、食パンより全粒粉パンなど、精製度の低い炭水化物を選ぶ。 |
| ゆっくりよく噛む | 早食いを避け、時間をかけて食べることで血糖値の急上昇を防ぐ。 |
| 適切な補食 | 食事と食事の間が長く空く場合は、ナッツやヨーグルトなどの補食を上手に活用する。 |
低血糖予防には、栄養バランスのいい食事とは?日本人に不足しがちな栄養素も紹介!で解説されている基本的な栄養バランスの理解が不可欠です。
また、食物繊維の効果や働きは?多く含まれる食品や効率的な摂取の仕方を解説!で紹介されている食物繊維の摂取により、血糖値の急激な変動を防ぐことが期待できます。
運動のポイント
適度な運動は、血糖コントロールを良好に保つために有効ですが、やり方を間違えると低血糖の引き金にもなります。
運動の種類やタイミングを工夫することで、安全かつ効果的に体力づくりができます。
ご自身の体と相談しながら、無理のない範囲で継続することが大切です。
運動時の注意点は以下の通りです。
- 空腹時の運動は避ける:
食後1~2時間後など、血糖値が安定している時間帯に行うのがオススメ - 運動前後の血糖測定:
糖尿病治療中の方は、安全のために血糖値を測定し、必要に応じて補食をとること - 補食の準備:
長時間の運動を行う際は、ブドウ糖や軽食を携帯し、いつでも補給できるようにしておくこと
適度な運動は血糖値の安定に重要な役割を果たします。
ウォーキングの5つの効果|質を高めるコツと時間帯・注意点を説明で紹介されているように、定期的なウォーキングは生活習慣病予防に効果的です。
生活習慣のポイント
食事や運動だけでなく、日々の生活リズム全体が血糖値の安定に関わっています。
ストレス管理や睡眠も、ホルモンバランスを整える上で非常に重要です。
心と体の両方から健康を考えることで、低血糖を根本から予防することにつながります。
生活習慣で意識したいポイントを以下に示します。
- 質のよい睡眠を確保する:
睡眠不足はホルモンバランスを乱し、血糖コントロールを悪化させる - ストレスを上手に発散する:
趣味の時間やリラックスできる時間を作り、心身を休ませること - 血糖値や症状の記録をつける:
どのような時に症状が出やすいかを把握することで、対策が立てやすくなる
血糖値の管理とあわせて、認知機能の維持にも配慮することが大切です。
詳しくは認知機能改善サプリをご覧ください。
※商品の効果には個人差があります。健康食品は医薬品ではありません。
低血糖の症状をチェック後の病院受診の目安と診療科
セルフチェックで低血糖が疑われる場合や、症状を繰り返す場合は、自己判断で放置せずに医療機関を受診することが大切です。
背後に思わぬ病気が隠れている可能性もあります。
適切なタイミングで専門医に相談しましょう。
病院を受診するべき症状・状況
一度でも低血糖の症状を経験すると不安になるものですが、特に以下のような場合は、早めに医師の診察を受けることを強くオススメします。
症状を正確にメモしておくと、診察がスムーズに進みます。
受診を検討すべき目安は以下の通りです。
- 低血糖の症状を月に数回以上、頻繁に繰り返す
- 応急処置をしても、症状の改善に時間がかかる、または改善しない
- 意識を失ったり、けいれんを起こしたりしたことがある
- 糖尿病ではないのに、空腹時に強い低血糖症状が出る
- 無自覚性低血糖が疑われる(周りの人から指摘されたなど)
何科を受診すればよい?
どの診療科に行けばよいか迷う方も多いでしょう。
まずはかかりつけの医師に相談するのが第一選択です。
かかりつけ医がいない場合や、より専門的な検査が必要な場合は、以下の診療科が適しています。
| 診療科 | 主な対象となる方 |
|---|---|
| 内科 | まずどこに相談すればよいか分からない場合 |
| 糖尿病内科・内分泌内科 | 糖尿病の治療中の方、ホルモンの病気が疑われる方 |
症状やこれまでの経緯を具体的に伝えることで、適切な診断につながります。
病院で行われる主な検査
病院では、低血糖の原因を特定するために、問診に加えていくつかの検査が行われます。
原因を正確に突き止めることが、適切な治療と再発防止の鍵となります。
不安な点があれば、事前に医師に質問しておきましょう。
一般的に行われる検査は以下の通りです。
- 問診:
症状が起こる時間帯、食事内容、運動習慣、服用中の薬などについて詳しく聞かれる - 血液検査:
血糖値やインスリン、その他関連するホルモンの値を測定する - 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):
ブドウ糖の入った甘い液体を飲み、時間経過による血糖値とインスリン値の変動を調べることで、インスリンの分泌パターンなどを評価する
これらの検査を通して、低血糖の根本的な原因を探ります。
低血糖の症状チェックに関するよくある質問
ここでは、低血糖の症状チェックに関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
正しい知識を持つことで、不要な不安を解消し、適切な行動をとれます。
低血糖の前触れはどのような症状?
低血糖の前触れとして最もよく見られるのは、「異常な空腹感」「冷や汗」「動悸」「手足の震え」といった初期症状(自律神経症状)です。
体がエネルギー不足を知らせる最初のサインであり、この段階でブドウ糖などを補給すれば、重い症状に進むのを防げます。
これらのサインを見逃さないことが非常に重要です。
低血糖になりやすい体質や特徴は?
以下のような体質や特徴を持つ方は、低血糖になりやすいといわれています。
- 糖尿病の治療(特にインスリンやSU薬)を受けている方
- 食生活が不規則で、食事を抜きがちな方
- 糖質中心の食事や甘いものを好む方
- 胃の手術を受けたことがある方
- ストレスを感じやすく、自律神経が乱れがちな方
これらに当てはまる方は、日頃から血糖値の安定を意識した生活を送ることが大切です。
低血糖で死ぬことはある?
重度の低血糖を治療せずに放置した場合、昏睡状態が長く続くと脳に深刻なダメージが残り、最悪の場合、命に関わることがあります。
特に、車を運転中や高所での作業中に重度の低血糖が起これば、重大な事故につながり、結果的に命を落とす危険性も否定できません。
低血糖は決して軽視できない症状であり、迅速で正しい対処が不可欠です。
子どもや高齢者の低血糖で気をつけることは?
子どもや高齢者は、低血糖の症状をうまく伝えられないことがあるため、周りの人が気づいてあげることが特に重要です。
| 対象 | 注意すべきポイント |
|---|---|
| 子ども | 不機嫌になる、ぐったりしている、集中力がない、夜中にうなされるなどのサインに注意。 |
| 高齢者 | 認知症の症状(ぼんやりする、異常な行動)と間違われやすい。食事量が減っていないか、薬の管理はできているかなどを確認する。 |
高齢者の低血糖対策については、高齢者の病気について|生活習慣の改善方法まで徹底解説!で詳しく解説されています。
また、新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が監修する嚥下機能向上プログラム「ノドトレ」は、高齢者が緊急時に糖分を安全に摂取する上でも役立ちます。
スポンサーリンク
まとめ
今回は、低血糖の症状セルフチェックから、緊急時の対処法、原因、そして繰り返さないための予防策までを詳しく解説しました。
低血糖は、誰にでも起こりうる症状ですが、そのサインを見逃さず、正しく対処することで重症化を防ぐことが可能です。
この記事の重要なポイントを改めて確認しましょう。
- まずはセルフチェックで症状のレベルを把握する
- 意識がある場合は、すぐにブドウ糖を補給する
- 意識がない場合は、ためらわず救急車を呼ぶ
- 低血糖を繰り返さないためには、食事・運動・生活習慣の見直しが不可欠
- 不安な症状が続く場合は、必ず医療機関を受診する
私たちメディカル・ケア・サービスでは、全国約300の介護施設で得られた約6,000名分の健康データを元に、科学的根拠に基づいた血糖値管理や低血糖予防を実践しています。
この記事が、あなたの低血糖への不安を解消し、健やかな毎日を送るための一助となれば幸いです。
低血糖の予防と認知機能の維持には、日々の栄養管理が重要です。
バランスの取れた食事に加えて、健達ねっとECサイトでは、中高年の方の認知機能維持をサポートする機能性表示食品をご紹介しています。
※これらの商品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
気になる症状がある場合は、必ず医師にご相談ください。