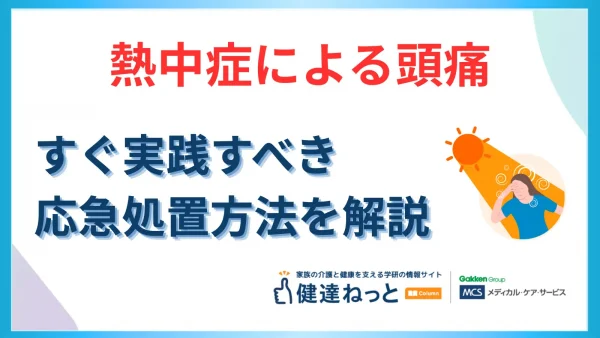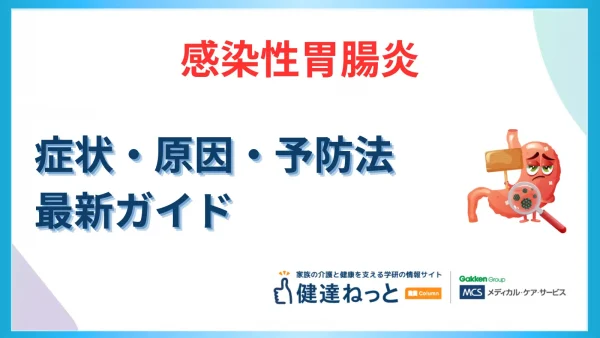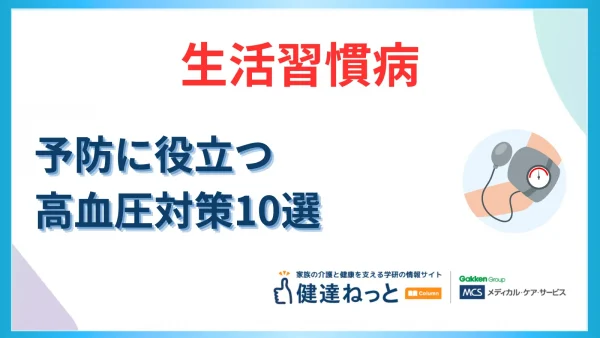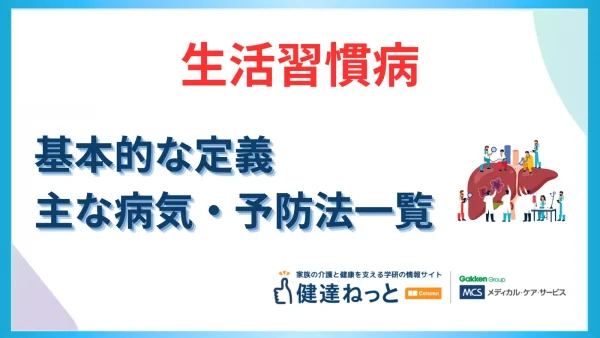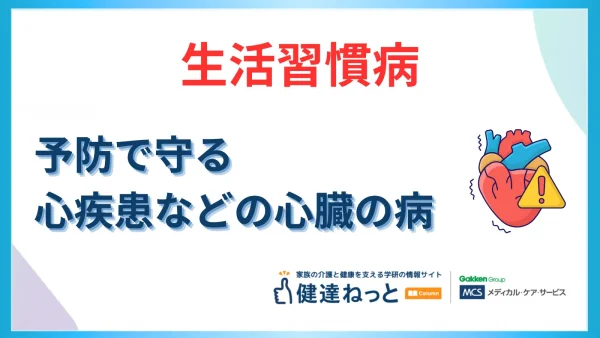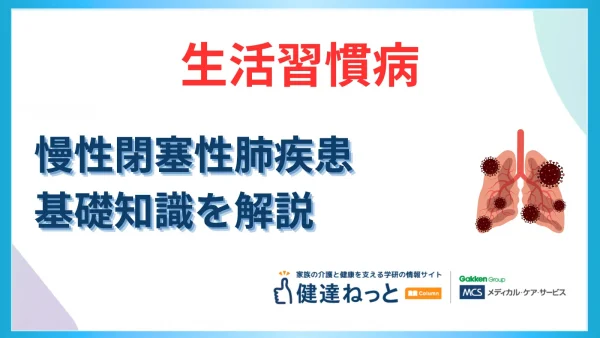- 「ガンガンするこの頭痛、もしかして熱中症…?」
- 「暑い中で作業をしていたら、頭が痛くなってきた…」
- 「子どもや親が頭痛を訴えているけど、どうすればいいの?」
夏の厳しい暑さの中で、突然の頭痛に襲われると、どのように対処すればよいか分からず、大きな不安を感じますよね。
特に、その頭痛が熱中症のサインかもしれないと思うと、「このまま様子を見ていて大丈夫なのだろうか」「薬を飲んでもよいのだろうか」と、次々に疑問が湧いてくることでしょう。
その不安な気持ち、この記事が解消します。
この記事では、熱中症による頭痛が起きた際に、あなたやあなたの大切な人の健康を守るための具体的な行動を分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、得られる情報は以下の通りです。
- すぐに病院へ行くべきか、救急車を呼ぶべきかの明確な判断基準
- その場で即効性を期待できる、正しい応急処置の方法
- 症状を悪化させかねない、決してやってはいけないNG行動
この記事の情報を元に、いざという時に迷わず、そして安全に行動できるようになります。
まずはご自身の、またはご家族の症状がどの段階にあるのかから確認していきましょう。
スポンサーリンク
【重要】熱中症に頭痛は病院に行くべきかの判断基準
熱中症による頭痛は、体の危険を知らせる重要なサインです。
症状の重症度によって対処法が大きく異なるため、まずは冷静に状態を見極めることが何よりも大切です。
ご自身や周りの方の症状がどのレベルに当てはまるか、確認してみましょう。
参考情報として、厚生労働省では熱中症を重症度に応じてI度(軽症)、II度(中等症)、III度(重症)に分類しており、頭痛はII度の中等症に該当する症状として位置づけられています。
ためらず救急車を呼ぶべき危険なサイン
熱中症が疑われ、これから挙げるような重篤な症状が見られる場合は、命に関わるサイン(Ⅲ度:重症)の可能性があるため、ためらわずに救急車を呼んでください。
一刻も早い専門的な医療介入が、その後の回復を大きく左右します。
特に、認知症のある高齢者では症状の変化が見落とされやすい傾向にあります。
当社グループの認知症介護現場で培った実践経験から、以下の症状が見られた場合は直ちに救急車を要請するようにしましょう。
熱中症における意識障害は、認知症のある高齢者では特に見落とされやすく、「普段と違う」という微細な変化を捉える専門的な視点が必要です。
愛の家グループホーム熊谷石原では、全スタッフがご利用者との挨拶時に許可を得て肌に触れるなど、言葉にならない「いつもと違う」サイン(肌の熱っぽさ、元気のなさ等)を多角的に捉える見守り体制を確立しています。
具体的には、以下のポイントを確認してみてください。
- 呼びかけに反応しない、または返答がおかしい
- 体がガクガクとけいれんしている
- まっすぐに歩けない、または立てない
- 体が非常に熱い(体温40度以上が目安)
これらのサインは、体が極めて危険な状態にあるという明確な証拠です。
意識障害などがある場合に救急車を呼ぶタイミングを逃さないよう、迅速な判断で救急要請を行うようにしましょう。
すぐに医療機関を受診すべき症状
意識ははっきりしているものの、頭痛や吐き気などのつらい症状がある場合は、中等症(Ⅱ度)の熱中症が考えられます。
応急処置で改善しない場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
厚生労働省の分類によると、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感はII度(中等症)の症状とされており、病院への搬送が必要とされています。
ご自身で水分補給ができない、または応急処置をしても症状がよくならない場合は、無理をせず専門家の診断を仰ぎましょう。
受診の目安となる症状は以下の通りです。
| 症状の例 | 対応 |
|---|---|
| ズキズキとした強い頭痛が続く | 医療機関を受診 |
| 吐き気が治まらない、嘔吐してしまう | 医療機関を受診 |
| 体が重く、ぐったりしている(強い倦怠感) | 医療機関を受診 |
| 集中できない、ぼーっとする | 医療機関を受診 |
これらの症状が見られる場合は、お近くの内科や救急科を受診するようにしましょう。
頭痛が出たら早めに病院を受診することが、重症化を防ぐ鍵となります。
現場で対処できる症状
軽症の熱中症(Ⅰ度)であれば、現場での適切な応急処置で症状の改善が期待できます。
I度は、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、大量の発汗が主な症状で、この段階では頭痛は通常含まれていません。
熱中症は段階的に症状が悪化する疾患です。
初期症状の見極めが重要で、この段階で正しく対処できれば、重症化を防ぐことが可能です。
現場で対処できる症状の例を以下に示します。
- 一時的なめまい、立ちくらみ
- 手足の筋肉がピクピクとけいれんする
- 汗が止まらない
ただし、これらの症状でも応急処置を行っても改善しない、または頭痛など他の症状が現れてきた場合は、軽症と判断せずに速やかに医療機関へ相談するようにしましょう。
スポンサーリンク
速攻でやりたい熱中症での頭痛の応急処置方法
熱中症による頭痛を感じたら、一刻も早く応急処置を開始することが重要です。
これから紹介する方法は、症状の悪化を防ぎ、体を回復させるための基本となります。
速攻で実践できる3つのステップを確認していきましょう。
まずは涼しい場所に行く(連れていく)
熱中症の応急処置で、何よりもまず優先すべきは、体をこれ以上温めない環境へ移動することです。
直射日光が当たる場所や、高温多湿の環境から、速やかに離れてください。
クーラーが効いた室内や、風通しのよい日陰などが最適です。
もし、そのような場所がすぐに見つからない場合は、日傘や上着などで日差しを遮るだけでも効果があります。
愛の家グループホーム熊谷広瀬では、認知症のある方に対して快適な室内から短時間だけ外に出て、あえて暑さを肌で感じていただくことで、その後の「冷たいものを飲みませんか」という声かけがスムーズに受け入れられるという独自のアプローチを実践しています。
涼しい場所へ移動したら、まずは安静にできる体勢をとりましょう。
衣服をゆるめ、ベルトやネクタイなどを外して、体から熱が逃げやすい状態を作ってあげることが大切です。
体を冷やす
涼しい場所へ移動したら、次は積極的に体の中から熱を奪う「冷却」のステップに移ります。
体を冷やす際は、正しい冷却方法を実践することが重要です。
日本救急医学会の熱中症診療ガイドライン2024では、効果的な冷却のために太い血管が体の表面近くを通っている場所を冷却することが推奨されています。
効果的に体を冷やすためのポイントは以下の通りです。
- 首の付け根(左右)
- 脇の下
- 足の付け根
これらの場所に、濡らしたタオルやハンカチ、保冷剤、冷たいペットボトルなどを当ててください。
体の中を循環する血液を直接冷やすことで、効率よく体全体の熱を下げることが可能です。
また、手のひらや足の裏には体温を下げるための特殊な血管があるため、ここを冷やすのも効果的といえます。
霧吹きなどで体に水をかけ、うちわや扇風機で風を送ることも、気化熱を利用した有効な冷却方法のひとつです。
電解質を飲む
体を冷やすのと同時に、失われた水分と塩分(電解質)を補給することが不可欠です。
この時、ただの水を飲むだけでは不十分な点に注意が必要です。
MCSケアモデルでは、水分摂取約1,800mlという具体的指標を設けており、この科学的根拠に基づいた水分管理が認知症ケア現場で85%以上の改善実績を上げています。
水分補給には、塩分やミネラルを含む経口補水液やスポーツドリンクを選ぶようにしましょう。
経口補水液は、軽度から中等度の脱水症の際に適した飲料として医学的に推奨されており、熱中症による脱水状態の回復に最適です。
| 飲み物の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 経口補水液 | 水分と電解質の吸収が速く、脱水時の補給に最適 |
| スポーツドリンク | 電解質や糖分を含み、予防や軽度の症状によい |
ただし、吐き気がある場合は無理に飲ませず、少量ずつ、こまめに摂取することを心がけてください。
熱中症で頭痛が発生する時に決してやってはいけないNG行動
よかれと思って取った行動が、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。
熱中症による頭痛が起きた際に、決してやってはいけないNG行動を3つ紹介します。
ご自身や家族の安全を守るために、必ず覚えておきましょう。
自己判断で頭痛薬(ロキソニンなど)を飲む
頭が痛いからといって、自己判断でロキソニンなどの頭痛薬を飲むのは絶対にやめてください。
ロキソニンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は、腎臓に入る血液量を減少させる副作用があり、熱中症で脱水状態にある体では急性腎障害を引き起こすリスクが非常に高まります。
どうしても解熱鎮痛薬が必要な場合は、アセトアミノフェン系の薬が比較的安全とされていますが、これも医師の指示なく使用することは推奨されません。
市販薬を使用する際は、薬の副作用や注意点を理解することが大切です。
熱中症の頭痛は、まず体を冷やし、水分と電解質を補給するという応急処置で対処するのが大原則です。
水分補給で水やお茶だけを大量に飲む
「水分補給が大事」と聞くと、水やお茶をたくさん飲もうと考えがちですが、これも危険な行動です。
熱中症で大量の汗をかいた体は、水分だけでなく塩分(ナトリウム)も一緒に失っています。
そこに水分だけを大量に補給すると、体内の塩分濃度がさらに薄まってしまいます。
この状態は「低ナトリウム血症(水中毒)」と呼ばれ、血清ナトリウム濃度が135mEq/L未満に低下することで、頭痛の悪化や吐き気、けいれんなどを引き起こす可能性があり、非常に危険です。
水分補給の際は、必ず塩分も一緒に摂ることを忘れないでください。
脱水症状にオススメの飲み物として、経口補水液やスポーツドリンクが最適です。
意識がもうろうとしている人に無理に水を飲ませる
呼びかけにうまく反応できない、意識がはっきりしない人に、無理やり水分を飲ませることは絶対に避けてください。
意識レベルが低下している状態では、うまく飲み込めず、水分が気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」を起こす危険性があります。
誤嚥は、窒息や重篤な肺炎(誤嚥性肺炎)の原因となり、命に関わる事態になりかねません。
自力で水分を摂れない場合は、すでに重症の状態です。
この場合は、水分補給よりも救急車を呼び、専門的な医療機関での点滴治療に切り替える必要があります。
落ち着いてから読みたい熱中症と頭痛の関連性
応急処置で少し落ち着いたら、なぜ熱中症で頭痛が起きるのか、その仕組みについても理解を深めておきましょう。
原因を知ることで、今後の予防にもつながります。
ここでは、熱中症と頭痛の関連性について、専門的な視点から解説します。
熱中症で頭痛が起きる3つの原因
熱中症による頭痛は、ひとつの原因ではなく、体の中で起きている複数の異常が複雑に絡み合って発生します。
医学的には、主な原因は以下の3つです。
- 高体温による脳血管拡張:体温上昇により血管が拡張し、脳組織への血液供給が増えることで頭痛が生じる。
- 脱水による血流低下:体内の水分・塩分不足により血液の流れが悪くなり、脳への血液供給が不足することで頭痛を引き起こす。
- 電解質バランスの崩れ:大量の発汗により体内の電解質バランスが崩れ、神経の興奮や筋肉の機能異常により頭痛が発生する。
つまり、体温の上昇、水分不足、塩分不足という3つの要素が、脳の血管や血流に影響を与え、頭痛という症状を引き起こしているのです。
熱中症による頭痛は、通常の頭痛の治し方とは異なるアプローチが必要な理由がここにあります。
頭痛薬を飲んではいけない理由
先ほどNG行動でも触れましたが、熱中症の頭痛に自己判断で頭痛薬を飲むべきではない理由は、主に2つあります。
ひとつは「効果が期待できない」こと、もうひとつは「体に害を及ぼす危険性がある」ことです。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 効果が期待できない | 熱中症の体温上昇は、風邪などの「発熱」とはメカニズムが異なるため、解熱鎮痛薬は効きません。 |
| 体に害を及ぼす危険性 | 脱水状態でNSAIDs系の鎮痛薬を飲むと、腎臓の血流が低下し、急性腎障害を引き起こすリスクがあります。 |
熱中症による頭痛の原因は、あくまで体温の上昇と脱水です。
したがって、対処法は原因を取り除くこと、つまり「体を冷やして、水分・塩分を補給する」こと以外にないのです。
水だけではいけない理由
私たちの体は、水分と電解質(特にナトリウム)が一定のバランスを保つことで正常に機能しています。
汗をかく時、体は水分と同時に電解質も排出します。
この状態で水分だけを補給すると、血液中の電解質濃度が薄まってしまうのです。
体は濃度を一定に保とうとするため、余分な水分を尿として排出しようとし、結果的に脱水状態から抜け出せなくなってしまうのです。
MCS版自立支援ケアでは、水分1,800mlとたんぱく質80gという具体的指標に加え、適切な電解質バランスの維持を重視しています。
このような理由から、熱中症の際には水分と電解質を同時に補給することが、科学的に見ても非常に重要といえます。
【シーン別】熱中症で頭痛が発生した際の適切な対処法
熱中症は、炎天下の屋外だけでなく、さまざまなシーンで発生する可能性があります。
ここでは、状況に応じた適切な対処法を知っておきましょう。
いざという時に、慌てずに行動するための知識です。
夜、寝てから頭痛で目覚めたら
「夜間熱中症」という言葉があるように、夜寝ている間に発症するケースも少なくありません。
睡眠中は知らず知らずのうちに汗をかき、水分が失われがちです。
もし、夜中に頭痛で目覚めた場合は、まず室温を確認し、暑いようであればためらわずにエアコンを使いましょう。
タイマーを設定せず、朝まで快適な温度を保つことが大切です。
そして、枕元に経口補水液やスポーツドリンクを常備しておき、目が覚めた際に少量ずつ飲むようにするとよいでしょう。
症状が改善しない場合は、夜間であっても救急相談窓口や医療機関に連絡することを検討するようにしましょう。
野外・スポーツ中に起きたら
屋外での活動中やスポーツ中に頭痛を感じた場合は、熱中症のサインである可能性が非常に高いです。
「まだ大丈夫」と活動を続けることは絶対にやめてください。
直ちに活動を中止し、涼しい日陰や建物の中に移動しましょう。
その後は、これまで解説してきた応急処置(衣服をゆるめる、体を冷やす、水分・電解質を補給する)を速やかに行ってください。
特に注意すべき点は、一度症状が治まったように感じても、その日のうちに活動を再開しないことです。
体はまだ回復しきっていないため、無理をすると再び症状が悪化する危険性があります。
家族(子どもや高齢者)が頭痛を訴えたら
子どもや高齢者は、熱中症のリスクが特に高い「ハイリスク群」です。
子どもは体温調節機能が未熟で、高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいという特徴があります。
そのため、本人が頭痛を訴えた際には、すでに症状が進行している可能性があります。
愛の家グループホームでの経験から、認知症のある高齢者では「喉が渇いた」と言えない方の”サイン”を捉える専門的観察が重要です。
普段との違いを注意深く観察し、少しでも異常を感じたら早めの対処を心がけてください。
特に高齢者では喉の渇きを感じにくく、体内の水分量も成人より少ないため、より慎重な管理が必要です。
特に高齢者の場合、水分摂取量の管理が重要となります。
「いつもより元気がない」「受け答えがぼんやりしている」など、普段との些細な違いに気づくことが大切です。
症状が軽く見えても、早めに医療機関へ相談することを強くオススメします。
熱中症の頭痛に関するよくある疑問
ここでは、熱中症の頭痛に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
正しい知識を身につけて、いざという時の不安を解消しておきましょう。
熱中症の頭痛は何日で治る?
適切な応急処置や治療を行えば、軽症から中等症の場合、多くは24時間以内に改善します。
しかし、回復までの時間は、発症時の重症度やその人の体力、年齢などによって大きく異なります。
注意が必要なのは、熱中症の後遺症として頭痛や倦怠感などが数週間から数か月続くケースもあることです。
これは、脳などがダメージを受けた場合に起こりうるといわれています。
もし、応急処置から一日以上経っても頭痛が改善しない場合や、一度よくなった後に再び症状が出てきた場合は、自己判断で様子を見ずに、必ず医療機関を受診するようにしましょう。
吐き気があって何も飲めない時は?
吐き気がひどく、水分を摂ろうとしても吐いてしまう場合は、すでに中等症以上の危険な状態です。
この状態では、口からの水分補給は困難であり、かえって嘔吐を誘発して脱水を悪化させる可能性があります。
無理に飲ませようとせず、体を冷やす応急処置を続けながら、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
病院では、点滴によって直接血管に水分と電解質を補給する治療が行われます。
これは、家庭ではできない専門的な治療です。
「飲めない」という状態は、医療機関を受診する明確なサインだと覚えておきましょう。
受診するなら何科?
どの診療科を受診すればよいか迷うこともあるでしょう。
症状によって適切な診療科は異なります。
| 症状の状態 | 受診すべき診療科 |
|---|---|
| 意識ははっきりしているが、頭痛や吐き気がある | 内科 |
| 意識障害(呼びかけに反応しない等)やけいれんがある | 救急科(ためらわず救急車を) |
| 子どもが発症した場合 | 小児科 |
基本的には、意識がしっかりしていれば内科、意識障害があれば救急科と考えると分かりやすいです。
判断に迷う場合や、夜間・休日でかかりつけ医がいない場合は、救急外来を受診するか、救急相談センター(#7119)に電話して指示を仰ぐのがよいでしょう。
まとめ
この記事では、熱中症による頭痛が起きた際の判断基準から、即効性が期待できる応急処置、そしてシーン別の対処法までを詳しく解説しました。
熱中症による頭痛は、体が発する危険なサインであり、軽視は禁物です。
しかし、正しい知識を持って迅速に行動することで、重症化を防ぎ、あなた自身や大切な人の健康を守ることが可能です。
最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。
- まずは冷静に症状を見極める: 意識障害など危険なサインがあれば、ためらわず救急車を呼びましょう。
- 応急処置は3ステップ: 「涼しい場所へ移動」「体を冷やす」「電解質を飲む」を速やかに行いましょう。
- NG行動を避ける: 自己判断での頭痛薬の使用や、水だけの大量補給は絶対にやめてください。
夏の暑さは避けられませんが、熱中症は予防できる疾患です。
環境省や厚生労働省では熱中症予防のための情報サイトを提供しており、暑さ指数(WBGT)の確認や予防対策について詳しい情報を得られます。
日常的な熱中症予防対策を心がけると共に、万が一の際にはこの記事の内容を思い出して、冷静に対処するようにしましょう。
あなたの的確な判断と行動が、何よりも有効な「治し方」となります。