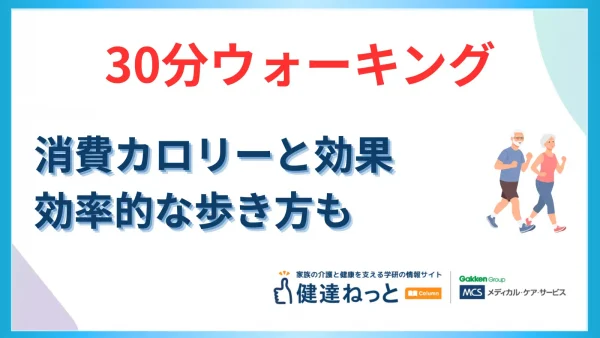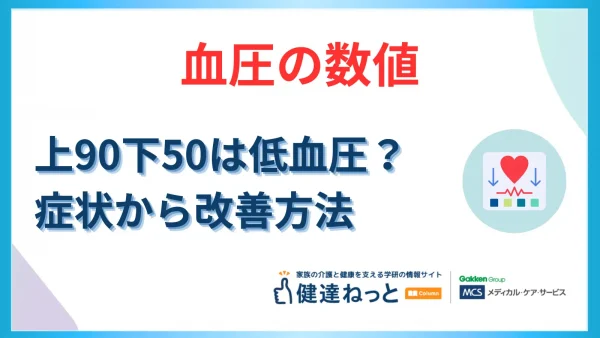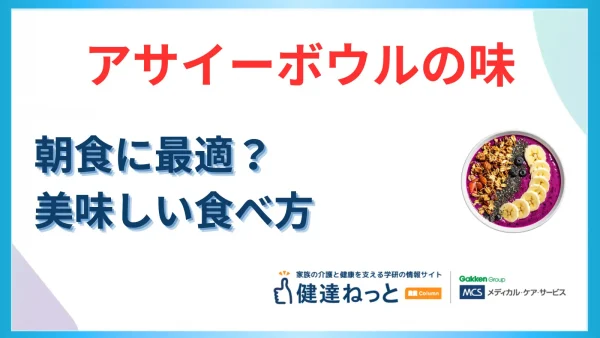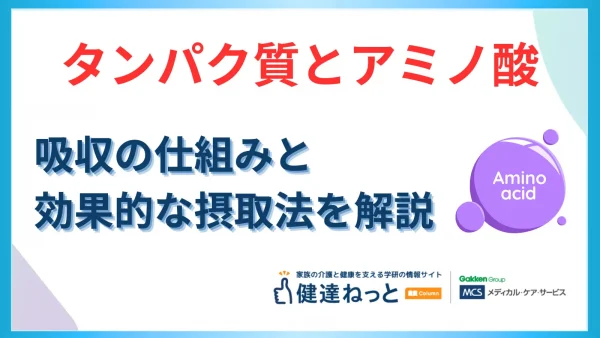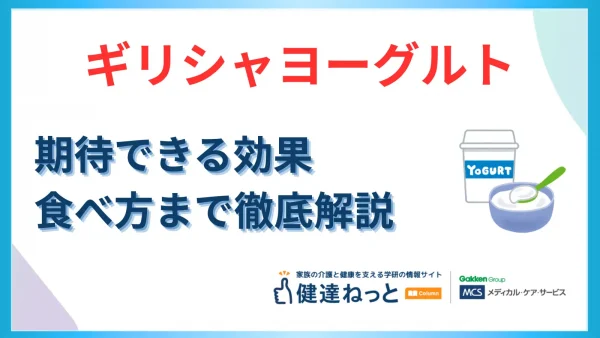腸管出血性大腸菌の症状は?」
「腸管出血性大腸菌にならないために予防策はあるの?」
腸管出血性大腸菌などの話題を目にする方や感染対策をしたい方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、腸管出血性大腸菌について以下の点を中心に詳しく解説します。
- 腸管出血性大腸菌の種類や特徴、感染後の主な症状
- 腸管出血性大腸菌の感染経路、感染対策
- 腸管出血性大腸菌の発生事例
腸管出血性大腸菌にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
腸管出血性大腸菌とは?

初めに、腸管出血性大腸菌について解説していきます。
腸管出血性大腸菌とは、ベロ毒素という毒素によって腸管にダメージを与え、血便などの感染症を引き起こす菌のことで、汚染された食べ物や水を口にすることで感染します。
また、ベロ毒素は、腸や腎臓など内臓の細胞にダメージを与え、血便や腎不全を起こす(溶血性尿毒症症候群)場合もあります。
特に、子どもや高齢者が腸管出血性大腸菌に感染すると、命に関わる深刻な事態になる可能性があります。
スポンサーリンク
腸管出血性大腸菌の種類と特徴

次に、腸管出血性大腸菌の中でも、代表的な5つの種類や特徴について解説します。
- o157
- o111
- o26
- o103
- o121
①o157
腸管出血性大腸菌の種類の1つ目は「o157」です。
o157は、最も有名な種類で少量の菌でもo157などを引き起こしやすく、重症化すると命に関わることもあります。
主な症状は、激しい腹痛や血便を伴う下痢、嘔吐や発熱がみられます。
子供や高齢者が感染すると、溶血性尿毒症症候群を引き起こすリスクも高くなるでしょう。
②o111
2つ目は「o111」です。
o111は、o157の次に知られている種類で、主な症状には、o157と同様に血便や腹痛などが挙げられます。
o157ほど感染者が少ないですが、感染すると重篤な合併症を引き起こす可能性が高いため、注意が必要です。
③o26
3つ目は「o26」です。
o26は、症状や感染経路はo157と似ています。
日本のo26の感染者は、2023年は1件、2022年は11件でした。
o26は日本だけでなく、北米やヨーロッパでも感染が確認されています。
④o103
4つ目は「o103」です。
o103は、症状や感染経路など他の種類と同様に引き起こされますが、一般的に感染者はo157ほど多くありません。
しかし、少量の細菌でも感染するため、注意が必要です。
⑤o121
5つ目は「o121」です。
o121は、他と比べて比較的稀な種類ですが、米国などで食中毒の事例が報告されています。
近年では、o121による集団感染が報告されており、特に生の生地や未加熱の食品を食べたことにより感染します。
o157については、次の記事で詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
腸管出血性大腸菌の主な症状

次に、腸管出血性大腸菌によって引き起こされる感染症の症状について、以下の4つをご紹介します。
- 腹痛/下痢
- 発熱
- 吐き気や嘔吐
- 溶血性尿毒症症候群
①腹痛/下痢
腸管出血性大腸菌によって引き起こされる感染症の症状の1つ目は「腹痛/下痢」です。
初期症状として、腹痛や下痢は最も多くみられ、一般的な食あたりとは異なり、腸内での炎症や腸粘膜の損傷によって、激しい腹痛や下痢(血便)の症状がでます。
腹痛や血便が見られる場合は早めに医療機関を受診し、適切な処置を受けましょう。
②発熱
2つ目は「発熱」です。
腸管出血性大腸菌に感染すると、37〜38°C程度の軽度の発熱が見られることがあります。
しかし、腸管出血性大腸菌が悪化し合併症を発症した場合は、全身の炎症や臓器への影響によって発熱が続く場合もあります。
発熱が続く場合や、子どもや高齢者、免疫力の低下した人に症状がある際は、重症化する可能性が高いため、速やかに医師の診察を受けましょう。
③吐き気や嘔吐
3つ目は「吐き気や嘔吐」です。
腸管出血性大腸菌に感染すると、吐き気や嘔吐の症状が現れることがあります。
消化器全体が感染によって強く刺激されるため、激しい腹痛から吐き気を感じて嘔吐する方が多い傾向にあります。
これらの症状は、脱水や体力低下に繋がるため、少量ずつの水分補給を心がけ、症状が悪化する場合は医師の診察を受けることが大切です。
④溶血性尿毒症症候群
4つ目は「溶血性尿毒症症候群」です。
溶血性尿毒症症候群とは、腸管出血性大腸菌の感染後に発症する、腎臓に重篤な影響を及ぼす症状のことです。
溶血性尿毒症症候群を発症すると、赤血球の破壊や急性腎不全など重篤な合併症になる可能性があります。
そのため、早期発見や治療が重要のため、早めに医療機関を受診し、溶血性尿毒症症候群など合併症の重症化を防ぎましょう。
食中毒の症状については、次の記事でも詳しく解説しています。
合わせて参考にしてください。
食中毒は高温多湿な夏季に起こるものというイメージがあります。ですが食中毒には細菌性とウイルス性があり、ウイルス性の食中毒は季節を問いません。食中毒にはどのような症状があるでしょうか?食中毒になったときはどうすればよいでしょうか?本記事で[…]
腸管出血性大腸菌の感染経路

続いて、腸管出血性大腸菌の感染経路について以下の2つをご紹介します。
- 経口感染
- 接触感染
①経口感染
腸管出血性大腸菌の感染経路の1つ目は「経口感染」です。
腸管出血性大腸菌の経口感染は、主に汚染された食品や水を摂取することで感染します。
例えば、未加熱の肉や洗浄不足の野菜などが感染源です。
また、感染者との接触や感染者の排泄物に触れた手を通じて口に入ることで感染することもあり、幼児や高齢者の施設で集団感染が発生した事例もあります。
経口感染を防ぐためには、食品の取り扱いや衛生管理が大切になるでしょう。
②接触感染
2つ目は「接触感染」です。
腸管出血性大腸菌による接触感染は、主に感染者の体液や排泄物に触れることで、他の人に感染します。
例えば、腸管出血性大腸菌に感染した人が、便を処理した後に手を洗わずに他の人や物に触ることによって感染する可能性があります。
特に、保育園や学校、介護施設など、集団生活の場では感染が広がりやすくなります。
そのため、手洗いや定期的な消毒など日常的な衛生管理が必要です。
幼児や高齢者がいる環境では、感染予防策を徹底し、感染拡大を防ぐことが求められるでしょう。
腸管出血性大腸菌の潜伏期間

次に、腸管出血性大腸菌の潜伏期間について解説します。
腸管出血性大腸菌の潜伏期間は、通常3〜8日間ですが、多くは3〜5日間で発症します。
ただし、個人差があり、潜伏期間が1日程度の短い場合もあれば、最長で10日程度かかることもあります。
食中毒の潜伏期間について詳しく知りたい場合は、次の記事もご覧ください。
食後すぐに体調に異変をきたすと、「食中毒かも…?」と心配になることでしょう。食中毒とはなにが原因で起こるのでしょうか。また、症状は食後どれくらいで現れるものなのでしょうか。本記事では、食後すぐ発症する食中毒について以下の点を[…]
腸管出血性大腸菌の発生状況

ここでは、最近の腸管出血性大腸菌の発生状況はどのような傾向があるのかをご紹介します。
腸管出血性大腸菌の発生状況については、国や地域ごとに定期的に報告されています。
日本では、厚生労働省や地方自治体が毎年腸管出血性大腸菌の発生状況を配信しています。
厚生労働省のホームページの報告では、日本国内で2023年の腸管出血性大腸菌の発生件数は19件、患者数は265名とあります。
過去3年間と比べると増加傾向にあります。
また、過去には腸管出血性大腸菌に感染者の中で、死亡例もあります。
腸管出血性大腸菌の発生の多い時期

続いて、腸管出血性大腸菌の発生が多い時期はいつなのかをご紹介します。
腸管出血性大腸菌の発生が多発する時期は、6月〜9月(夏場)です。
夏場は、気温や湿度が高く、細菌が繁殖しやすい環境が整っているため、感染リスクが高くなります。
また、夏場はバーベキューや生野菜を多く食べる機会が増えるため、未加熱の肉類や洗浄不足の野菜を通じた感染もみられます。
他にも、水遊びなどを通じて感染が広がる可能性もあるため、夏場が一番感染する可能性が高いです。
スポンサーリンク
腸管出血性大腸菌の発生事例

次に、腸管出血性大腸菌の発生事例についてご紹介します。
国内と海外での事例の違いを考えてみましょう。
①国内での発生事例
国内での腸管出血性大腸菌の事例は、主に保育施設や高齢者施設での感染事例や夏場の感染予防策が十分にされておらず感染してしまう事例が多いです。
例えば、2024年に東京都では腸管出血性大腸菌の感染の報告数が増加傾向にあり、特にo157の感染が多く報告されています。
感染経路としては、主に汚染された食品を摂取したことが考えられていますが、人から人への感染も疑われる事例も確認されています。
特に保育施設での集団感染が多い傾向にあります。
また、夏季には未加熱の牛肉やサラダなどをそのまま食べることが多く、感染が増加します。
感染予防には、食品の十分な加熱や手洗い、調理器具の衛生管理が求められます。
②海外での発生事例
海外での腸管出血性大腸菌の発生事例は、特に欧米諸国や中南米で注目されています。
例えば、ドイツでは2011年o104による大規模な集団感染が発生した事例があります。
この感染は、汚染された野菜が原因とされ、約4,000件の感染が報告され、50人以上の死亡が確認されています。
感染者の多くが溶血性尿毒症症候群を発症し、重度の合併症を引き起こしました。
また、アメリカでは、o157による感染が年間約97,000件発生しており、主に未加熱の牛肉や未殺菌の牛乳が原因とされています。
過去には、ハンバーガー、サラダ、未殺菌のリンゴジュースなどが感染源として特定されており、野菜や果物の汚染による集団感染も増加傾向にあります。
スポンサーリンク
腸管出血性大腸菌の予防策

最後に、腸管出血性大腸菌の予防策について、以下の7つをご紹介します。
- 食品は1分以上加熱する
- ,野菜はよく洗う
- 生肉の取り扱いに注意する
- 食材ごとにまな板を分ける
- こまめに手洗いをする
- 調理器具は清潔に保つ
- 食品は低温で保存する
①食品は1分以上加熱する
腸管出血性大腸菌の予防策の1つ目は「食品は1分以上加熱すること」です。
腸管出血性大腸菌などの食中毒を防ぐためには、食品を1分以上加熱すると良いでしょう。
具体的には、食材の内部温度が70°C以上に達するまで十分に加熱することが必要です。
1分以上加熱することで、腸管出血性大腸菌の病原菌が死滅し、食べられる状態になります。
②野菜はよく洗う
2つ目は「野菜をよく洗うこと」です。
野菜は腸管出血性大腸菌や他の食中毒菌が付着している可能性があるため、食べる前によく洗うことが重要です。
特に、土や動物の排せつ物が原因で汚染されることがあり、洗うことで感染症のリスクを低下させられるでしょう。
③生肉の取り扱いに注意する
3つ目は「生肉の取り扱いに注意すること」です。
生肉の取り扱いには特に注意が必要です。
腸管出血性大腸菌などの細菌が存在する可能性があり、適切な処理を行わないと食中毒のリスクが高まります。
牛肉の料理方法には十分に気をつけましょう。
④食材ごとにまな板を分ける
4つ目は「食材ごとにまな板を分けること」です。
生肉や魚、卵などの生鮮食品は、細菌やウイルスの感染源となる可能性があります。
生肉などの食品を扱ったまな板と、野菜や果物、調理済みの食品を扱うまな板を分けることで、感染を防げます。
⑤こまめに手洗いをする
5つ目は「こまめに手洗いをすること」です。
手には、細菌やウイルスが気づかない間に付着しています。
特に、食材を扱う前や後やトイレの使用後、咳やくしゃみをした後には、必ず手を洗うと良いでしょう。
これにより、食中毒だけでなく、風邪やインフルエンザなどの感染症のリスクを大幅に減らせます。
⑥調理器具は清潔に保つ
6つ目は「調理器具は清潔に保つこと」です。
調理器具が汚れていると、細菌やウイルスが食材に移る可能性があります。
特に、生肉や魚、卵などの生鮮食品を扱った器具は、他の食材と分けて使用し、使用後はすぐに洗浄することが良いでしょう。
⑦食品は低温で保存する
7つ目は「食品は低温で保存すること」です。
食品を低温で保存することは、食品の鮮度を保ち、病原菌の増殖を抑えるために非常に重要です。
多くの細菌は、温度が高いと繁殖しやすくなり、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌は、摂氏4度以上で急速に増えるため、冷蔵保存すると良いでしょう。
スポンサーリンク
腸管出血性大腸菌に関するまとめ
ここまで腸管出血性大腸菌についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 腸管出血性大腸菌は、激しい腹痛や血便などの通常の食あたりとは違う症状が現れる
- 感染症対策として、「つけない」「増やさない」「やっつける」ことが重要
- 腸管出血性大腸菌は、主に未加熱の牛肉や野菜から感染する事例が多い
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。