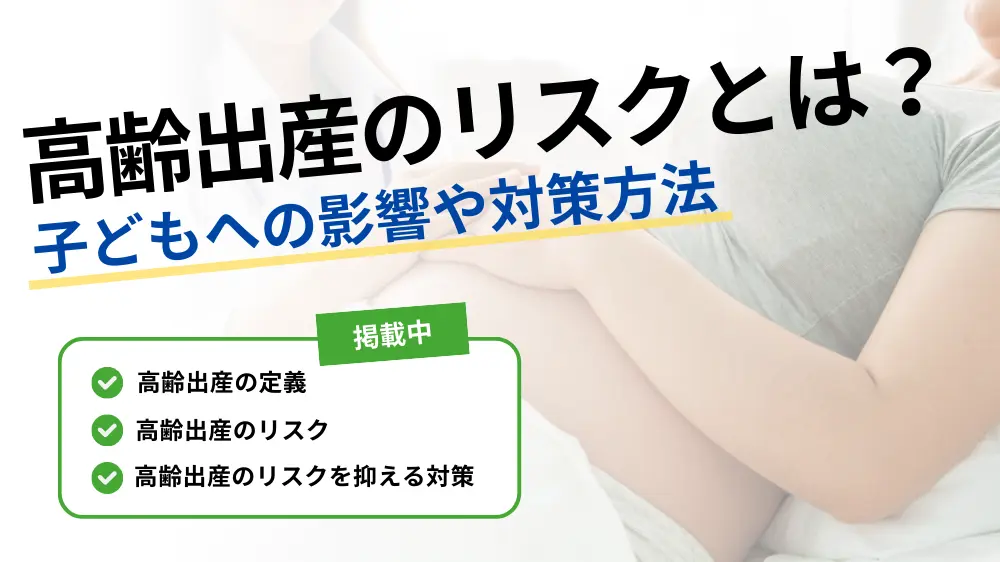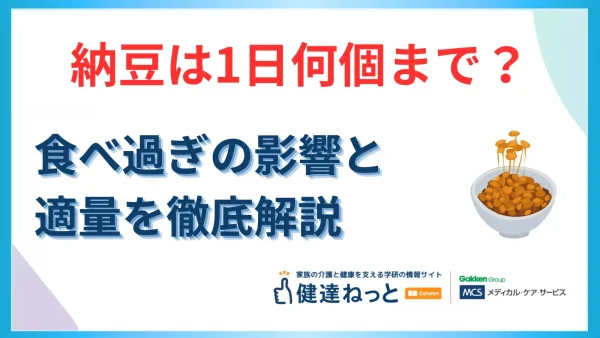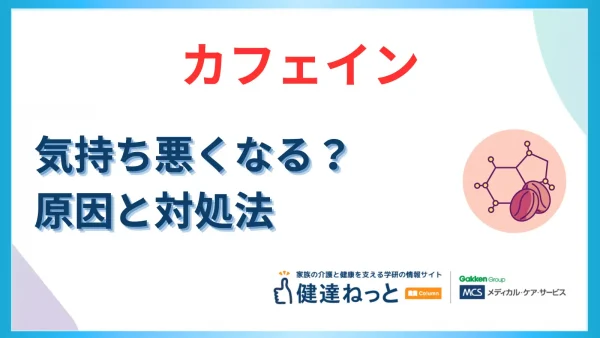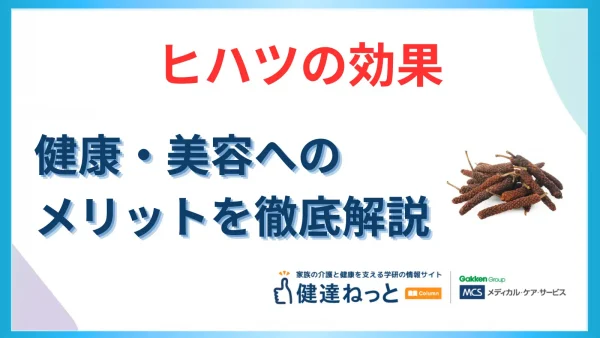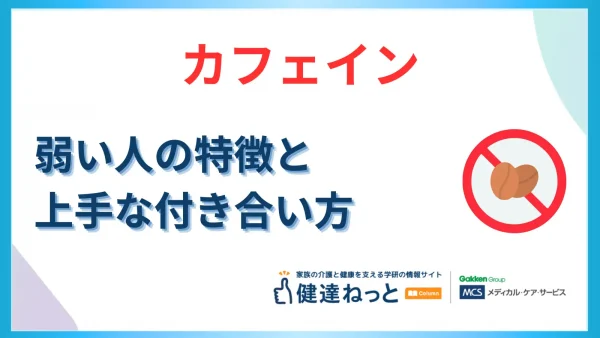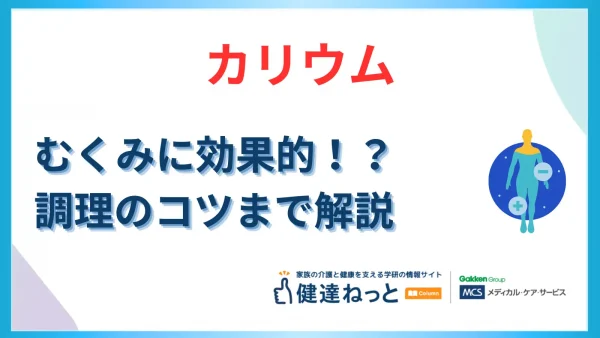「40代の出産は危ないの?」
「40代での出産は子どもにリスクがあるのかな」
出産を考えている方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。
40代での出産は高齢出産といわれ、母子の身体に影響が出やすいです。
本記事では、40代の出産について以下の点を中心に解説します。
- 40代で出産する人の割合
- 40代での出産に伴う母子への影響
- 高齢出産の成功率を上げるための対策
40代での出産や出産の成功率を上げる対策についてご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
高齢出産の定義

まず初めに、高齢出産についてご紹介します。
実は高齢出産という医学用語はないため、明確な定義づけはされていません。
そのため、一般的には35歳以上の女性が初めて出産することを指します。
しかし、35歳以前に出産を経験している方の場合では、二度目以降の出産が40歳以上のときに高齢出産ということもあります。
初産婦と経産婦いずれにしても、40歳以降の出産は、高齢出産といわれるのが一般的です。
以下の記事は、高齢出産の傾向やリスクについて詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
「高齢出産って何歳から?」「高齢出産による子どもの体への影響が心配」30代で子どもを産もうと考えている、あるいは出産を控えている30代〜40代の方の中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。国内[…]
スポンサーリンク
40代で出産する人の割合

ここでは、40代で出産する人の割合についてご紹介します。
厚生労働省の調査によると、令和5年における全国の出生数は727,277人でした。そのうち、母親が40代以上の出生数は47,764人なので、40代以上で出産した人の割合は全体の約6.5%となります。
平成25年の調査結果では、40代以上で出産した人の割合は全体の4.6%だったので、高齢出産は増加傾向といえます。
また、女性の社会進出や晩婚化、核家族化によって身近に頼れる親族がいないなどの理由から高齢出産は今後も増えることが予想できます。
40代での出産に伴う母子への影響

次に40代での出産に伴う母子への影響を7つご紹介します。
- 子どもが障害を持つ確率が高まる
- 流産/難産となる可能性が高まる
- 母親が合併症に感染する可能性が高まる
- 子宮機能の低下によって分娩のリスクが高まる
- 子宮復古不全の可能性が高まる
- 出産後の回復が遅くなる
- 妊娠確率が低くなる
子どもが障害を持つ確率が高まる
40代での出産に伴う母子への影響の1つ目は「子どもが障害を持つ確率が高まること」です。
卵子の老化に伴い、子どもに染色体異常を持つ可能性が高まることがわかっています。
染色体異常があると先天的に障害や疾患を持つ子どもが生まれる確率が高くなるため、子どもがダウン症候群などを発症する恐れがあります。
ダウン症候群は知的障害や精神障害などの症状が見られ、その発症率は母親が20歳のときの出産では1/1667、40歳のときの出産では1/106の確率です。
母親の年齢が上がるにつれ、子どもに障害や疾患があらわれる可能性も上がります。
流産/難産となる可能性が高まる
2つ目は「流産/難産となる可能性が高まること」です。
流産は妊娠22週より前に赤ちゃんが亡くなることを指し、難産は分娩時間が長くてなかなか生まれないことを指します。
母親の高齢化によって、子どもに染色体異常が起こりやすくなることや子宮機能の低下が影響していると考えられています。
特に母親の年齢が35歳を超えると、流産のリスクが高まり、22歳では流産率が8.7%であるのに対して、48歳での流産率は84.1%と高リスクです。
母親が合併症に感染する可能性が高まる
3つ目は「母親が合併症に感染する可能性が高まること」です。
加齢に伴う身体機能の低下などの要因によって、合併症を患う可能性が高くなります。
妊娠中に見られる合併症としては、妊娠高血圧症候群と妊娠糖尿病が多いです。
また、これらの症状が重症化すると、母体だけではなく赤ちゃんにも影響が及びます。
赤ちゃんに出る影響としては、発育不全や形態異常などがあり、最悪の場合、死に至るケースもあります。
子宮機能の低下によって分娩のリスクが高まる
4つ目は「子宮機能の低下によって分娩のリスクが高まること」です。
高齢出産では前期破水や切迫流産などのトラブルが起きやすくなります。
また、初めて高齢で出産する場合だと、産道や子宮口が硬くなり難産になりやすいです。
加齢による子宮機能低下が原因で、トラブルや難産の可能性が上がり、分娩時のリスクも高まります。
そのため、高齢出産では自然分娩ではなく、帝王切開するケースが多く見られ、麻酔が切れた後に切開部分の痛みや後陣痛など、母体に負担がかかりやすいです。
子宮復古不全の可能性が高まる
5つ目は「子宮復古不全の可能性が高まること」です。
子宮復古不全とは、妊娠や出産で広がった子宮が様々な原因によって元に戻らない状態のことをいいます。
高齢出産で子宮復古不全になりやすい理由としては、加齢によって身体の回復能力が落ちるためです。
子宮復古不全になると、子宮から出血が止まりにくくなるなどの影響が出てしまい、母親の疲労にも繋がってしまいます。
出産後の回復が遅くなる
6つ目は「出産後の回復が遅くなること」です。
産後の回復力は若い人の方が高いとされており、加齢によって回復力が下がるのは事実です。
回復力が下がれば、先ほどお伝えした子宮復古不全になったり、体力の回復にも時間がかかったりします。
また、母体に疲労が溜まると、乳汁分泌症で母乳が出づらくなったり、産後うつになりやすかったりといった問題も起こってしまいます。
妊娠確率が低くなる
7つ目は「妊娠確率が低くなること」です。
日本生殖医学会によると、30代前半までは妊娠できる確率が25~30%あるのに対して、35歳~39歳では18%、40歳になると約5%まで妊娠確率が下がってしまいます。
妊娠確率が下がる主な理由としては、加齢とともに卵子の質が低下することが挙げられます。
卵子の質の低下を止めることは難しいため、出産を望むのであれば早めに妊活に取り組むべきです。
また、妊娠を希望してもなかなか赤ちゃんができない場合は、不妊治療の検討も視野にいれましょう。
不妊治療では検査をもとに、タイミング療法や人工授精など年齢や希望などに応じた治療を進めます。
高齢出産と発達障害の関わりについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
「高齢出産による発達障害のリスクが気になる」「高齢出産による発達障害のリスクを軽減するために、どのような対策を取ればいいのか知りたい」高齢出産を検討されている方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。本記事[…]
高齢出産の成功率を上げるための対策

ここでは高齢出産の成功率を上げるための対策を8つご紹介します。
- 葉酸を積極的に摂取する
- 食事改善を行う
- ストレス管理を行う
- 十分な休息をとる
- 適度な運動で体力をつける
- 肥満にならないよう体重管理を行う
- 妊婦検査で母子の健康状態をチェックする
- 出生前検査で子どもの病気の可能性を知る
葉酸を積極的に摂取する
高齢出産の成功率を上げるための対策の1つ目は「葉酸を積極的に摂取すること」です。
葉酸は赤ちゃんの発育に欠かせない栄養素のため、妊娠前から授乳期まで積極的に摂取するよう心掛けましょう。
特に、赤ちゃんの脳や神経などが形成されていく段階では多くの葉酸が必要なため、妊娠初期は葉酸が不足しがちです。
不足する葉酸を補うためには、以下の食材や食品を食事に取り入れると良いでしょう。
- ブロッコリー
- アボカド
- さつまいも
- いちご
- 納豆
また、食事だけでは不足するのでサプリメントを服用して補うこともおすすめです。
食事改善を行う
2つ目は「食事改善を行うこと」です。
母親が肥満や痩せすぎの場合には、母子に以下の悪影響が出る恐れがあります。
- 妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などのリスクが高まる(肥満)
- 流産や死産、成長障害などのリスクが高まる(肥満)
- 神経管閉鎖障害、発育不全、貧血のリスクが高まる(痩せすぎ)
このような事態を避けるためにも、栄養バランスの整った3度の食事を心掛け、食塩は控えましょう。
また、インスタント食品やコンビニの惣菜などは塩分が多く含まれるので、出来るだけ手作りの料理を用意することをおすすめします。
ストレス管理を行う
3つ目は「ストレス管理を行うこと」です。
母親がストレスを感じると、赤ちゃんに必要な栄養素や酸素が上手く届けられないなどの悪影響があります。
また、ストレスホルモンのコルチゾールは通常、健康な胎盤であれば通過しないため、赤ちゃんに影響が出ることはありません。
しかし、胎盤機能に問題があると、コルチゾールが赤ちゃんに伝わり、神経機能の障害を引き起こす可能性があります。
子どもの成長を妨げないためにも、日光に当たりセロトニンを分泌させたり、泣ける映画を観て涙を流したりするなど、ストレス発散を心掛けましょう。
十分な休息をとる
4つ目は「十分な休息」です。
妊娠中は免疫力が低下し、普段症状が出ないような弱い感染症にもかかりやすくなります。
そのため、疲れているにもかかわらず、無理に動いたり、働いたりすると体調を崩しやすくなるので注意が必要です。
疲労を溜めないためにも、適宜休憩をとり、十分な睡眠をとりましょう。
睡眠は8時間程度が理想ですが、つわりなどで夜に寝付けない場合は、日中に睡眠をとると良いです。
家事や仕事については、出来るだけ周りに協力を仰ぎ、心身への負担を減らすようにしてください。
適度な運動で体力をつける
5つ目は「適度な運動で体力をつけること」です。
体力がないと、出産時にいきむ力が弱くなるので、分娩時間が長引く恐れがあります。
また、産後の育児では想像以上に体力が必要になるので、運動をして体力づくりを心掛けましょう。
妊娠初期は母子ともにとても不安定な時期のため、妊娠中期(安定期)に入ってから運動を始めるのが良いです。
ウォーキングは1日30分を目安とし、週5回行うのがベストですが、運動習慣がない人は、週3回から始めてみましょう。
また、気分転換にマタニティ専用のスイミングやヨガなどに通うのもおすすめです。
肥満にならないよう体重管理を行う
6つ目は「肥満にならないよう体重管理を行うこと」です。
先ほどもお伝えした通り、肥満は母子へ悪影響を及ぼす可能性が高くなります。そのため、食事や運動に気を配りながら、体重管理もしっかり行っていきましょう。
また、体重が急激に増加したからといって、過度な食事制限をすることは避けましょう。
過度な食事制限によって赤ちゃんの発育に影響が出る可能性があるためです。
体重の急激な増加がある場合は、かかりつけ医に相談し、適切な食事管理や適度な運動について指導を仰ぎましょう。
妊婦健診で母子の健康状態をチェックする
7つ目「妊婦健診で母子の健康状態をチェックすること」です。
妊婦健診ではお腹の中の赤ちゃんの状態と母親の健康状態をチェックします。
健診に行くことで病気の早期発見に繋がるため、必ず検査に行くべきといえます。
また、妊婦検診を受けていないことで、出産時に病院から受け入れを拒否されるリスクもあります。
落ちついて出産に臨むためにも、妊婦検診は必ず受けるようにしてください。
出生前検査で子どもの病気の可能性を知る
8つ目は「出生前検査で子どもの病気の可能性を知ること」です。
出生前検査は任意の検査で、染色体異常や発育、形態異常などを調べられます。
検査ではダウン症候群などの特定の疾患については調べられますが、全ての障害を特定できるわけではありません。
しかし、事前に検査を受けることで次のようなメリットがあります。
- 余裕を持って子どもを受け入れる準備ができる
- 出生後の療養計画を立てられる
- 子どもに必要な支援などの情報を事前に把握できる
検査を受けるかは、パートナーと十分に話し合って決める必要があります。
次の記事では、妊娠中におすすめのサプリをご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
妊娠は女性の体に大きな変化をもたらし、その期間中に適切な栄養素を摂取することが非常に重要です。サプリメントは、必要な栄養素を効率的に摂取する手段として、多くの妊婦にとって欠かせない存在となっています。しかし、どのサプリメントを選[…]
40歳 出産 まとめ
ここまで40代の出産についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 40代以降の出産は年々増加傾向だが、加齢に伴い母子へのリスクは高まるので、早めの出産が望ましい
- 高齢出産を成功させるためには、健康管理を習慣化し、健康や出産に不安がある人は専門機関に相談する
- 検査を受けて赤ちゃんの健康状態を知ることも出産に向けて必要な準備の一つ
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。