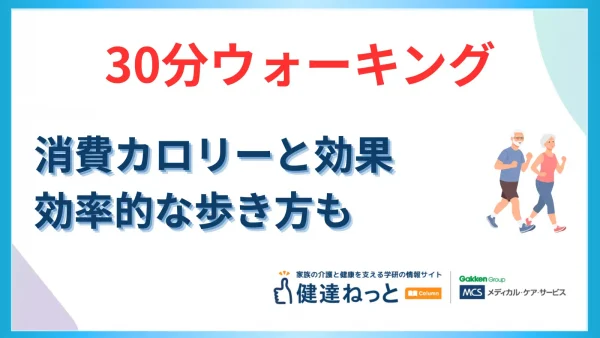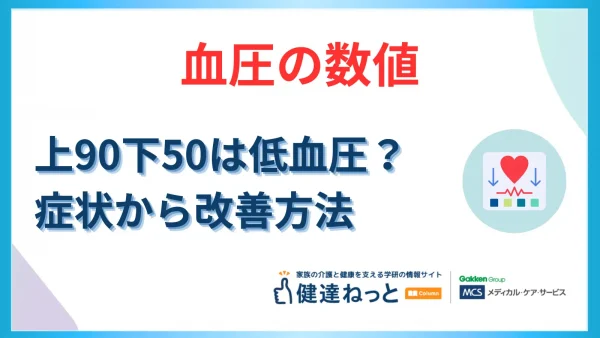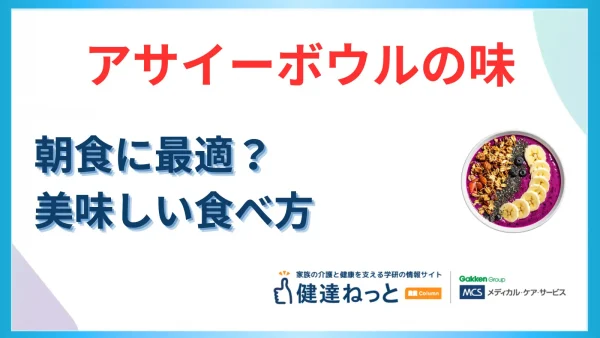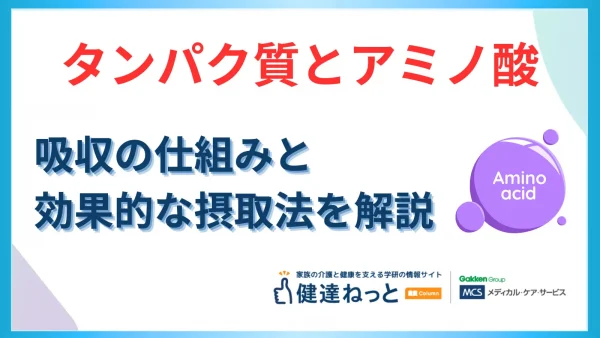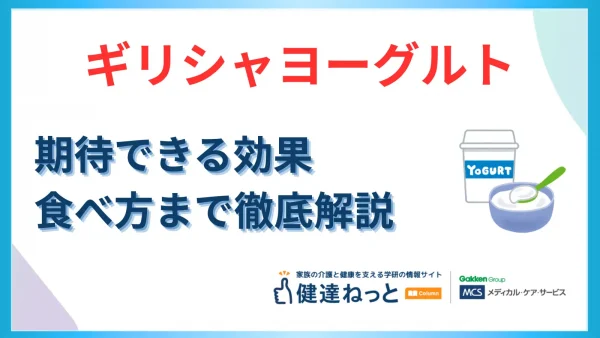「o157の原因となる食品は?」
「調理する際に気をつけるべきポイントは?」
o157の原因となる食品について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、o157の原因となる食品について以下の点を中心に詳しく解説します。
- 原因となる具体的な食品
- 原因となる食品を調理する際の注意点
- o157を防ぐためにできること
o157の原因となる食品について知りたい方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
o157とは?

はじめに、o157について解説します。
o157とは、別名腸管出血性大腸菌と呼ばれており、主に食品を媒介して感染する菌の一種です。
また、o157は食中毒の原因として知られており、微量でも感染するほど強力なため、注意が必要です。
o157は初夏から秋にかけて流行しやすいため、食品の管理や調理をする際は、衛生面を意識しましょう。
o157に感染すると下痢や腹痛の症状が多く見られます。
健康な成人であれば軽い症状で治るケースが多いですが、免疫力の低い子どもや高齢者がo157に感染すると、重症化したり合併症を起こしたりするリスクがあり危険です。
場合によっては命に関わることもあるため、感染者が身近にいる場合はしっかりと予防策を講じる必要があります。
スポンサーリンク
o157の原因となる食品

次に、o157の原因となる代表的な4つの食品について解説します。
- 肉
- 生野菜
- 漬物
- 井戸水
①肉
o157の原因となる食品の1つ目は「肉」です。
肉は、o157のもっとも代表的な感染源のひとつで、生肉や十分に加熱できていない肉の加工品などに注意する必要があります。
具体例は以下のとおりです。
- レアステーキ
- ローストビーフ
- 牛レバー刺し
- ハンバーグ
- 牛角切りステーキ
- 牛タタキ
- シカ肉
肉を調理する際は中心部までしっかりと火を通したり、焼くときと食べるときで箸を使い分けたりするなどの心がけが大切です。
また、バーベキューなど屋外で肉を調理する場合は、風の影響で火力の調整が難しいこともありますが、生焼けで食べないようにしましょう。
②生野菜
2つ目は「生野菜」です。
野菜を育てる畑や農場には、さまざまな微生物が存在しており、なんらかの細菌がついていると考えられます。
過去には、きゅうりの和え物が原因でo157が発生し、死亡者が出る事故もありました。
生野菜を食べる際は、十分に洗い、目に見えない汚れや細菌を流しましょう。
たとえば、トマトのヘタやきゅうりのトゲの周りは汚れが溜まりやすく、レタスやキャベツなどは葉と葉の間にも細菌がいる可能性があります。
また、生野菜を調理する際は、清潔な器具を使うことが大切です。
③漬物
3つ目は「漬物」です。
最近は、健康のために減塩を意識している漬物もありますが、塩分濃度が低い場合、o157をはじめとする食中毒菌が増える恐れがあります。
過去には、白菜漬けが原因のo157による食中毒も起きています。
また、不衛生な環境での調理により感染が拡大する危険性があるため、肉や魚を調理した包丁やまな板はそのまま使わず、こまめに洗うことが重要です。
④井戸水
4つ目は「井戸水」です。
井戸水は食品ではありませんが、o157の感染の原因になるため注意が必要です。
1990年には、幼稚園で使用していた井戸水が原因でo157が発生し、園児が死亡した事例もあります。
井戸水は、動物や人の糞便、o157をはじめとする細菌などに汚染されやすく、摂取すると健康被害が起きる恐れがあります。
井戸水などの生水を飲む際は沸騰させ、定期的に衛生検査を受けることが重要です。
o157について解説

次に、o157について以下の4つの項目に分けて解説します。
- 症状
- 感染経路
- 感染時の対処法
- 治療方法
①症状
1つ目は「症状」です。
o157に感染すると以下のような症状が出ます。
- 腹痛
- 水様性下痢
- 血便
- 嘔吐
- 発熱
o157の症状は、激しい腹痛ではじまり、数時間後に水様性下痢を起こす場合が多く、血便が見られることもあります。
また、o157に感染すると溶血性尿毒症症候群や脳症などの重症な合併症を起こす恐れがあるため、免疫力の低い子どもや高齢者などはとくに注意が必要です。
なお、o157の潜伏期間は一般的に3〜8日とされていますが、最短で1日、最長で10日程のケースもあります。
②感染経路
2つ目は「感染経路」です。
o157の感染経路は主に以下の2つです。
- 経口感染
- 接触感染
経口感染では、汚染された食品や水の摂取、接触感染では、感染者や汚染された物体への接触で感染します。
経口感染を防ぐには、食品をしっかりと管理したり加熱したりして、汚染されたものを口に入れることを防ぎましょう。
接触感染の場合は、経口感染の対策に加えて、消毒などを心がけることが大切です。
また、家庭内や保育園、高齢者施設での集団感染の事例もあるため、o157の感染者が出た場合は適切に対応する必要があります。
③感染時の対処法
3つ目は「感染時の対処法」です。
o157への感染が疑われる場合は、自己判断で市販の下痢止めを服用せず、すぐに医療機関を受診しましょう。
家族が感染した場合などは、症状が出ていなくても便の検査を求められることがあります。
はっきりと症状は出ていなくても感染している恐れがあるため、身近に感染者がいる場合は、手洗いやうがいなどを徹底しながら体調を観察しましょう。
お腹に違和感があったり、軽い腹痛や下痢が見られたりする場合は、注意が必要です。
④治療方法
4つ目は「治療方法」です。
o157に感染した場合、医師の診断に基づく治療を受けることが欠かせません。
o157には下痢の症状が見られますが、別の病気の可能性も考えられるため、必ず医師の診察を受けましょう。
薬を処方された場合は適切に服用し、医師の指示に従い安静に過ごすことが重要です。
なお、下痢の症状が見られる場合の基本的な対処法は以下のとおりです。
- 安静にする
- 水分を補給する
- 消化しやすい食事を摂取する
o157の治療薬については、現在さまざまな方面から研究開発が進められています。
食中毒が治るまでの期間について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
[sitecard subtitle=関連記事 url= target=][sitecard subtitle=関連記事 url= target=]食中毒とは、細菌やウイルスなどの感染が原因で嘔吐や下痢などが起きる病気です。食中毒は、細[…]
o157の原因となる食品を調理する際に気をつけたいこと

次に、o157の原因となる食品を調理する際に気をつけたいことを6つ解説します。
- 食品を洗う
- 加熱する
- 調理器具を使い分ける
- 食品は冷蔵庫や冷凍庫で管理する
- 調理後はすぐに食べる
- 調理器具の洗浄と消毒をする
①食品を洗う
o157の原因となる食品を調理する際に気をつけたいことの1つ目は「食品を洗うこと」です。
とくに生で食べる野菜や果物はしっかりと洗い、汚れや細菌を取り除きましょう。
トマトなどの表面がつるつるした食材は洗いやすいですが、きゅうりなど凸凹したものは洗いづらいため、より注意深く扱う必要があります。
また、調理時にほかの食品に肉や魚の汁がつかないように分けて管理することも重要です。
②加熱する
2つ目は「加熱すること」です。
加熱が必要な食品は「中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱」を目安に、しっかりと火を通しましょう。
とくにo157の原因になりやすいハンバーグやステーキなどの肉料理は、十分な加熱が欠かせません。
電子レンジでの調理は、加熱ムラが起きやすいため、専用の容器やフタを使ったり、調理時間に気をつけたりしましょう。
熱の伝わりにくいものは、途中でかき混ぜたり、位置を変えたりするなどの工夫も重要です。
③調理器具を使い分ける
3つ目は「調理器具を使い分けること」です。
肉を切った後に、同じ調理器具を使って、生で食べる野菜や調理済みの食品を扱うのは避けましょう。
肉を調理した包丁やまな板は、洗ってから熱湯をかけて使うと、調理器具を介した感染予防には効果的とされています。
包丁やまな板は、肉と野菜を切るもので使い分けるとより安全でしょう。
また、調理器具だけでなく、たわしやスポンジなどの道具も、使用後に洗剤と水で洗い流す必要があります。
たわしやスポンジなどは、可能であれば、煮沸するのがおすすめです。
④食品は冷蔵庫や冷凍庫で管理する
4つ目は「食品は冷蔵庫や冷凍庫で管理すること」です。
肉や生鮮食品は、購入後すぐに冷蔵庫や冷凍庫で保存し、常温での放置は避けましょう。
o157をはじめとする細菌の多くは、温かい環境で急速に増殖するため、温度管理の徹底が感染予防につながります。
また、肉や魚などはビニール袋や容器に入れ、ほかの食品に汁がかからないように注意しましょう。
なお、冷蔵庫や冷凍庫は詰めすぎると機能が低下するため、7割程度に抑えるのがおすすめです。
⑤調理後はすぐに食べる
5つ目は「調理後はすぐに食べること」です。
調理した食品はできるだけ早く食べましょう。
食べ残しがある場合は、きれいな容器に移し保存する必要があります。
とくに夏場は、常温で放置すると細菌が繁殖しやすいため、食べ残しがある場合は冷蔵庫で保存し、再加熱してから食べることが重要です。
食べ残しを食べる際は、75℃以上を目安に再加熱し、味噌汁やスープなどは沸騰するまでしっかりと火を通します。
ただし時間が経ちすぎたり、少しでも違和感があったりする場合は、食べずに捨てましょう。
⑥調理器具の洗浄と消毒をする
6つ目は「調理器具の洗浄と消毒をすること」です。
調理に使った器具は、使用後すぐに洗い、熱湯消毒やアルコール消毒をしましょう。
とくに肉を扱った後の器具は、しっかりと洗浄することが重要です。
洗浄後は、調理器具を次亜塩素酸ナトリウム製剤(台所用漂白剤)や亜塩素酸水に一晩つけ込むと良いでしょう。
正しく管理された清潔な調理器具を使用すれば、o157の原因となる食品でも適切に調理できます。
o157は加熱で防ぐ!についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。
o157を防ぐためにできる4つのこと

最後に、o157を防ぐためにできる4つのことを解説します。
- 手洗いを徹底する
- 消毒をする
- 感染者と接触しない
- 感染者が使用したものを使わない
①手洗いを徹底する
o157を防ぐためにできることの1つ目は「手洗いを徹底すること」です。
手洗いは、もっとも基本的かつ効果とされる感染症の予防対策です。
とくに調理前や食事前、トイレ後には必ず石鹸を使ってしっかりと手を洗いましょう。
また、肉や魚などの調理後にも手を洗い、清潔な手でほかの食品を取り扱うことも感染対策に必要です。
調理の途中でペットなどの動物に触ったり、おむつを交換したりした場合も同様に手を洗いましょう。
②消毒をする
2つ目は「消毒をすること」です。
手洗い後は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどを使って手の消毒をしましょう。
また、調理器具や食品を扱う場所も定期的に消毒をすることが重要です。
とくにキッチンやカウンターは菌が繁殖しやすい場所のため、念入りに消毒をして清潔に保ちましょう。
万が一感染者が出た場合は、以下のような場所の消毒も欠かせません。
- トイレ
- ドアノブ
- 食卓
- 洗面台
③感染者と接触しない
3つ目は「感染者と接触しないこと」です。
感染者と接触しないことが感染対策に重要ですが、家族が感染した場合、接触を完全に断つことは難しいでしょう。
感染者と接触する場合は、マスクやビニール手袋を着用したり、すぐに手洗いや消毒を徹底したりして、感染しないように心がけることが大切です。
また、感染者に下痢の症状がある場合、排泄物に細菌が含まれているリスクがあるため、家族が一緒に入浴することは意識して避けましょう。
④感染者が使用したものを使わない
4つ目は「感染者が使用したものを使わないこと」です。
感染者が使用したタオルや食器などを共有すると、簡単に感染が拡大するため、分けて使いましょう。
加えて、感染者の便や体液の付着のリスクがある衣類や下着などの管理方法も重要です。
おむつ交換や着替えのサポートをする際は手袋を着用し、使用後はすぐに処分し、手を洗う必要があります。
感染者が使用したものを洗濯をする際は、ほかのものと分けるようにしましょう。
感染者が使用したものを使わないことはもちろん、取り扱いにも注意しましょう。
o157の原因となる食品に関するまとめ

ここまでo157の原因となる食品についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- o157の原因となる食品には、肉や生野菜、漬物などがある
- o157の原因となる食品の調理時は、十分な加熱や調理器具の使い分けなどを意識する
- o157の感染を防ぐためには、手洗いや消毒などの基本的な感染症対策を徹底する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。