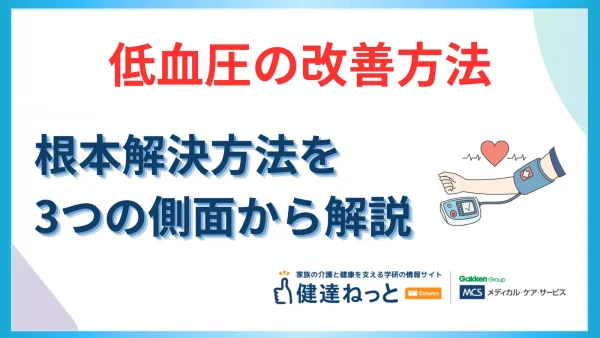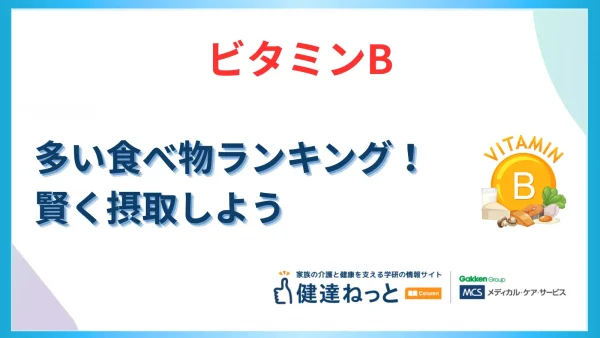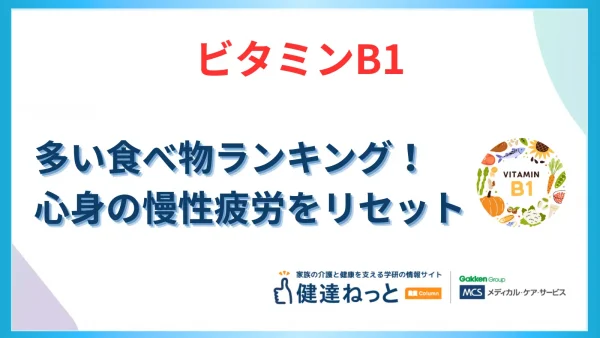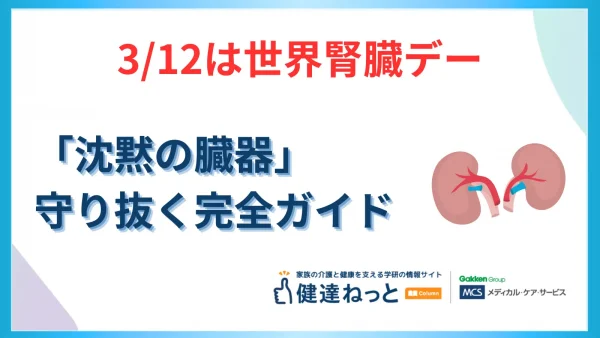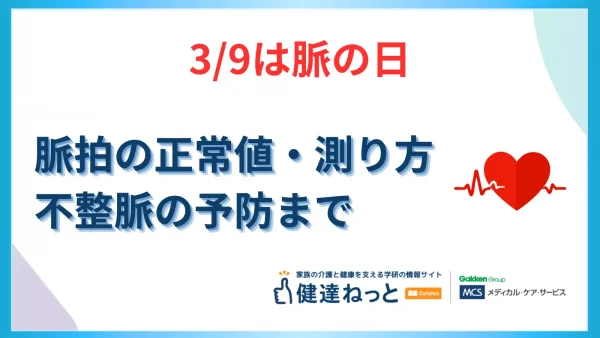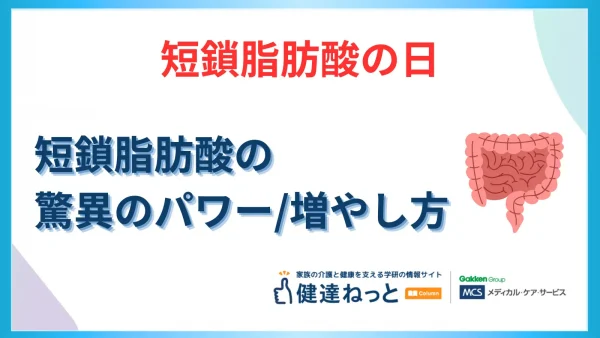- 朝、ベッドから起き上がるのがとにかくつらい
- 立ち上がった瞬間に、目の前がクラっとする
- 午前中は頭が働かず、周りから「やる気がない」と思われていないか不安
- 常に身体がだるくて、疲れがまったく取れない
このようなつらい症状、単なる「体質」だと諦めていませんか。
その不調は、低血圧が原因かもしれません。
低血圧は、日々の生活の質を大きく下げてしまう深刻な問題です。
しかし、正しい知識を元に生活習慣を見直すことで、その症状は改善できる可能性があります。
この記事では、低血圧の基本的な知識から、今日からすぐに実践できる具体的な改善策までを網羅的に解説します。
- 結論:低血圧は、食事・運動・生活習慣の見直しで改善が期待できる
- 食事:何を、どう食べるべきかが分かる
- 運動:無理なく続けられる簡単なエクササイズが分かる
- 生活習慣:日常のちょっとした工夫で症状を予防する方法が分かる
この記事を最後まで読めば、つらい低血圧の症状から解放され、毎日を元気に、そして前向きに過ごすための具体的なヒントがきっと見つかります。
スポンサーリンク
あなたの不調の原因は低血圧かも?まずは症状と基準をセルフチェック
「もしかして自分も低血圧?」と感じたら、まずは客観的な基準とご自身の症状を照らしあわせてみましょう。
正しい知識を持つことが、改善への第一歩です。
WHOにおける低血圧の基準と一般的な目安
一般的に、低血圧とは血圧が正常範囲よりも低い状態を指します。
WHO(世界保健機関)の基準では、収縮期血圧(最高血圧)が100mmHg以下、拡張期血圧(最低血圧)が60mmHg以下の状態が低血圧のひとつの目安とされています(愛知県薬剤師会)。
ただし、大切なのは数値そのものよりも、血圧の低さによって何らかの自覚症状が出ているかどうかです。
たとえ基準値以下でも、元気に過ごせている場合は体質的なものと考えられ、必ずしも治療の対象とはなりません。
一方で、高血圧とは異なり、低血圧には明確な病気の診断基準がないのが現状です。
(高血圧は日本高血圧学会ガイドライン2019により、診察室血圧140/90mmHg以上と明確に診断基準が定められています)
ご自身の血圧の状態を把握するためにも、日頃から正しい血圧測定方法で数値を記録しておくことがオススメです。
| 血圧の種類 | WHOの基準 |
| 収縮期血圧(最高血圧) | 100mmHg 以下 |
| 拡張期血圧(最低血圧) | 60mmHg 以下 |
この基準はあくまで目安です。
重要なのは、これらの数値とともに、次に挙げるようなつらい症状があるかどうかです。
低血圧の代表的な症状チェックリスト
低血圧によって引き起こされる症状は実にさまざまです。
全身の血流が悪くなることで、脳や身体の隅々に十分な酸素や栄養が届きにくくなることが原因といわれています。
ご自身の体調と比べながら、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。
- 朝、すっきりと起きられない、起き上がるのが非常につらい
- 立ち上がった時や、お風呂から出た時にめまいや立ちくらみがする
- 常に身体がだるい、疲れやすく、回復しにくい
- 頭痛や肩こりが慢性的にある
- 集中力が続かず、午前中は特に頭がボーッとする
- 食後に強い眠気やだるさを感じる
- 少し動いただけでも動悸や息切れがする
これらの症状に複数当てはまる場合、あなたの不調は低血圧が原因かもしれません。
原因を知ることで、より効果的な対策が見つかります。
スポンサーリンク
血圧が低くなる4つの主な原因とタイプ
低血圧とひとことでいっても、その原因はひとつではありません。
ご自身の症状がどのタイプに近いかを知ることで、より的確なセルフケアにつなげられます。
体質や遺伝が関係する「本態性低血圧」
低血圧の中で最も多いのが、この「本態性低血圧」です。
特定の病気や原因が見当たらず、体質や遺伝的な要因が大きいと考えられています。
特に症状がなく、日常生活に支障がなければ問題視されることは少ないタイプです。
しかし、だるさや疲れやすさなどの症状を伴う場合は、生活習慣の見直しによる改善が望まれます。
やせ型で筋肉量が少ない若い女性によくみられる傾向があります。
立ち上がった瞬間にクラっとする「起立性低血圧」
急に立ち上がった時や、長時間立ったままでいる時に、血圧が急激に下がり、めまいや立ちくらみを起こすのが「起立性低血圧」です。
これは、血圧をコントロールする自律神経がうまく機能しないことで起こります。
通常、立ち上がると重力で血液が下半身に集まりますが、自律神経が即座に血管を収縮させ、心臓のポンプ機能を高めて血圧を維持します。
しかし、この調整がうまくいかないと、脳への血流が一時的に不足してしまうのです(MSDマニュアル)。
起立性低血圧の年代別症状はさまざまですが、ひどい場合は失神することもあり、転倒によるケガのリスクも伴うため注意が必要です。
具体的なめまい・立ちくらみの対策法を身につけておくことも大切です。
食後にだるくなる「食事性低血圧」
食事をした後、特に炭水化物を多く摂った後に、強い眠気やだるさ、めまいを感じるのが「食事性低血圧」です。
これは、消化のために血液が胃や腸などの消化器官に集中し、その結果、脳への血流が相対的に減少するために起こります。
高齢者の3人に1人にみられるといわれており、血圧の調整機能が低下している方や、自律神経に乱れがある方で起こりやすい症状です(MSDマニュアル、愛知県薬剤師会)。
食後の活動に支障が出ることもあるため、食事の摂り方を工夫する必要があります。
ほかの病気が隠れている「症候性(二次性)低血圧」
心臓病・内分泌系の疾患(甲状腺機能低下症など)・重度の貧血、または服用している薬の副作用など、何らかの病気や原因がはっきりしている低血圧を「症候性(二次性)低血圧」と呼びます。
この場合は、原因となっている病気の治療が最優先されます。
セルフケアで改善しない、あるいは急に低血圧の症状が現れた場合は、安易に自己判断せず、必ず医療機関を受診するようにしましょう。
【食事編】低血圧を改善する食べ物・飲み物と食事のコツ
低血圧の改善は、毎日の食生活を見直すことから始まります。
身体の内側から血圧を安定させるために、何を、どのように食べるかが非常に重要です。
積極的に摂りたい血圧を安定させる食べ物・栄養素
血圧を適切に保ち、血流をよくするためには、バランスのよい食事が基本です。
特に、以下の栄養素を意識的に摂取することが、症状の改善につながります。
筋肉や血液の材料となるたんぱく質は、特に重要です。
メディカル・ケア・サービスが実践するケアモデルでは、身体機能改善のためにたんぱく質約80g(食事で約60g+補食で20g)の摂取を推奨しており、これは低血圧改善にも大いに役立ちます。
また、チーズに含まれる「チラミン」には血管を収縮させ血圧を上げる作用があることが知られており(利根中央病院)、ほうれん草などに豊富な「鉄分」は血液の質を高める効果が期待できます。
| 栄養素 | 役割 | 多く含まれる食品の例 |
| たんぱく質 | 筋肉や血液の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 適度な塩分 | 血液量を増やし血圧を維持 | 味噌汁、梅干し、漬物 |
| 鉄分 | 血液の酸素運搬能力を高める | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
| チラミン | 血管を収縮させ血圧を上げる | チーズ、赤ワイン、アボカド |
過度な塩分摂取は禁物ですが、低血圧の方は適切な塩分摂取量を心がけることで、血液の量を保ちやすくなります。
飲み物で改善!水分補給とカフェインの上手な摂り方
体内の水分量が不足すると、血液の量も減少し、血圧が下がる直接的な原因となります。
そのため、意識的でこまめな水分補給は、低血圧改善の基本中の基本といえます。
健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービスでは、1日あたり約1,800mlの水分摂取を推奨しています。
この科学的根拠に基づいた水分管理は、血液量を増やして血圧の安定化に寄与し、実際に多くの方の症状改善実績があります。
特に、昼食までにより多くの水分を摂ることは、脳の覚醒レベルを上げ、立ちくらみやめまいの軽減につながります。
また、コーヒーや緑茶、紅茶に含まれるカフェインには、交感神経を刺激して一時的に血圧を上げる作用があります。
朝が特につらい方や、食後にだるさを感じる方は、タイミングよくカフェインを摂るのもひとつの方法です。
効果的な水分補給方法とあわせて、日常に取り入れてみましょう。
食後の不調を防ぐ「食事の摂り方」4つのルール
食事性低血圧に悩む方は、何を食べるかと同時に「どう食べるか」が非常に重要です。
高齢者の3人に1人が経験するといわれるこの症状には、介護現場でも実践されている食事の工夫が効果的です。
ポイントは、消化器官への血液集中を緩やかにし、急激な血圧低下を防ぐことにあります。
- ゆっくりよく噛んで食べる:消化の負担を軽くする
- 一度に食べ過ぎない:1回の食事量を減らし、回数を増やす(1日3食→5食など)
- 温かい食べ物を優先する:身体を冷やさず、血流を穏やかに保つ
- 食事と一緒にコーヒーなどを飲む:カフェインの効果で血圧低下を予防する
これらのルールを意識するだけで、食後のつらいだるさや眠気を大きく軽減できる可能性があります。
【生活習慣編】今日から始める低血圧を改善する5つのアクション
食事の改善とあわせて取り組みたいのが、日々の生活習慣の見直しです。
血流を促進し、血圧をコントロールする自律神経を整えることで、低血圧の根本的な改善を目指します。
血流がアップする無理なく続ける簡単エクササイズ
低血圧の方は、筋肉量が少なく、血液を心臓に送り返す「筋ポンプ作用」が弱い傾向にあります。
特に「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの筋肉を鍛えることは、全身の血流改善に直結するのです。
メディカル・ケア・サービスのケアモデルでも、正しい姿勢の保持と自分の意思で自由に移動できる運動能力の向上が、血流改善と低血圧の根本改善につながる重要な要素とされています。
| 運動の種類 | 効果とポイント |
| ウォーキング | 全身の血流を促進する最も手軽な有酸素運動 |
| かかと上げ下げ運動 | ふくらはぎの筋ポンプ作用をダイレクトに刺激 |
| スクワット | 下半身全体の筋肉を効率よく鍛える |
激しい運動は必要ありません。
ウォーキングが血流に与える効果は科学的にも証明されています。
日常生活に軽い血流改善のための運動法を取り入れるだけでも、身体は変わっていきます。
自律神経を整える朝の習慣と夜の習慣
血圧のコントロールは、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスによって成り立っています。
このバランスを整えるためには、規則正しい生活リズムが何よりも大切です。
特にオススメしたいのが、健達ねっとが共同開発した「ノドトレ」です。
これは1回5秒でできる簡単なプログラムですが、深呼吸と同様のリラックス効果が期待でき、副交感神経に働きかけ、自律神経のバランスを整える効果が期待できます(健達ねっと「ノドトレについて」)。
- 朝の習慣:起きたらまず太陽の光を浴びる。体内時計がリセットされ、活動モードの交感神経が優位になる
- 夜の習慣:就寝1〜2時間前にぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり浸かる。リラックスモードの副交感神経が優位になり、質のよい睡眠につながる
自律神経を整える方法を参考に、ご自身に合った習慣を見つけてみてください。
質のよい睡眠で体をリセットする
睡眠不足は自律神経の乱れに直結し、低血圧の症状を悪化させる大きな原因となります。
毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きることを心がけ、身体のリズムを整えましょう。
睡眠の質を高めるためには、就寝前の過ごし方が重要です。
スマートフォンやパソコンのブルーライトは脳を覚醒させてしまうため、就寝1時間前には見るのをやめるのが理想です。
また、リラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするのも効果があります。
睡眠の質を向上させる方法はさまざまありますが、まずは起きる時間を一定にすることから始めてみるのがオススメです。
休日でも平日と同じ時間に起きることで、生活リズムが整いやすくなります。
急な立ちくらみを防ぐ「ゆっくり動作」のススメ
起立性低血圧による立ちくらみは、日常の動作を少し意識するだけで、かなりの頻度で予防できます。
ポイントは、頭の位置が急激に変わる動作を避け、ワンクッション置くことです。
これは実際の介護現場でも、転倒予防のために徹底されている重要な習慣です。
- 朝起きる時:目が覚めてもすぐに起き上がらず、布団の中で手足を動かす → ゆっくりと身体を横向きにする → 腕の力を使って上半身を起こし、ベッドに数秒座る → ゆっくりと立ち上がる
- 椅子から立つ時:いきなり立たずに、まず浅く腰掛け直す → 足をしっかりと床につける → ゆっくりと腰を上げる
- 床の物を拾う時:腰を曲げるのではなく、膝を曲げて腰を落とす
これらの「ゆっくり動作」を習慣にすることで、急激な血圧変動のリスクを減らし、安全な毎日を送れます。
【特に夏場】こまめな水分と塩分補給の徹底
夏場は、汗をかくことで体内の水分と塩分(ミネラル)が失われやすくなります。
これは血液量の減少に直結するため、低血圧の症状が悪化しやすい季節です。
のどが渇いたと感じる前に、意識的に水分を摂ることが重要です。
外出時や運動時はもちろん、室内で過ごしている時でも、こまめな水分補給を忘れないようにしましょう。
また、汗とともに失われる塩分の補給も大切です。
スポーツドリンクや経口補水液、麦茶にひとつまみの塩を入れるなどの工夫がオススメです。
特に高齢者はのどの渇きを感じにくくなるため、周囲の方のサポートも重要になります。
やってはいけない低血圧を悪化させるNGな習慣
よかれと思ってやっている習慣が、実は低血圧の症状を悪化させているかもしれません。
改善のためのアクションとあわせて、避けるべきNG習慣も知っておきましょう。
急に起き上がる・立ち上がる
これまでも触れてきましたが、急激な頭の位置の変化は、起立性低血圧を誘発する最大の原因です。
脳への血流が追いつかず、めまいや立ちくらみを引き起こします。
朝の寝起きや、長時間座った後などは特に注意し、「ゆっくり動作」を徹底しましょう。
長時間の立ちっぱなし
長時間じっと立ったままでいると、重力によって血液が下半身に溜まり、心臓に戻る血液量が減ってしまいます。
これにより血圧が低下し、気分が悪くなったり、ひどい時には失神したりすることもあります。
仕事などでどうしても長時間立つ必要がある場合は、足踏みをしたり、つま先立ち運動をしたりして、ふくらはぎの筋肉を動かすように心がけてください。
熱いお風呂やサウナの長湯
熱いお湯に長く浸かると、血管が拡張して血圧が下がりやすくなります。
また、大量の汗をかくことで脱水状態になり、さらに血圧が低下するリスクも高まります。
お風呂から上がる際に立ちくらみを起こし、転倒する事故は非常に多いため、特に注意が必要です。
入浴はぬるめのお湯で、時間は短めにし、出る時もゆっくりと行動しましょう。
過度なアルコール摂取と寝不足
アルコールには血管を拡張させる作用があるため、飲み過ぎは血圧低下の原因となります。
また、アルコールを分解するために体内の水分が使われるため、脱水状態にもなりやすくなります。
寝不足が自律神経の乱れを引き起こすことはいうまでもありません。
お酒はほどほどにし、質のよい睡眠を十分に摂ることが、血圧の安定につながります。
セルフケアで低血圧が改善しない時の病院受診の目安
さまざまなセルフケアを試しても症状が改善しない場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。
背後に病気が隠れている可能性も考えられます。
このような症状の時は受診のサイン
低血圧は体質的なものも多いですが、以下のような症状が見られる場合は、専門家による診断が必要です。
我慢せずに、早めに医師に相談するようにしましょう。
健達ねっとでは、特に次のような症状がある場合の早期受診を推奨しています。
- 気を失ったことがある(失神発作)
- 朝起きるのが非常につらく、学校や仕事に行けない日がある
- めまいや立ちくらみが頻繁に起こり、転倒の不安がある
- 安静にしていても動悸・息切れ・不整脈を感じる
- これまでになかった、強い頭痛や吐き気を伴う
これらのサインは、身体が助けを求めている証拠かもしれません。
自己判断で放置しないことが重要です。
まずは内科への相談がオススメ
「どの科を受診すればいいか分からない」という場合は、まずはかかりつけ医や一般内科に相談するのがよいでしょう。
全身の状態を総合的に診察し、必要に応じて循環器内科や神経内科など、専門の診療科を紹介してくれます。
メディカル・ケア・サービスでは、収縮期血圧100mmHg以下、拡張期血圧60mmHg以下の状態で、めまいやだるさなどの症状がある場合は、内科への相談を第一選択として推奨しています(健達ねっと「低血圧の症状と改善方法」)。
受診の際は、いつから、どのような時に、どのような症状が出るのかを具体的に伝えられるよう、メモを準備しておくと診察がスムーズです。
低血圧の改善に関するよくある疑問
ここでは、低血圧の改善に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
正しい知識を持つことで、不要な不安を取り除き、前向きに改善に取り組めます。
低血圧をすぐ治す方法はある?
残念ながら、低血圧の体質そのものを「すぐに治す」という特効薬のような方法はありません。
カフェインの摂取などで一時的に血圧を上げることは可能ですが、それは対症療法に過ぎません。
低血圧の根本的な改善には、これまで解説してきたように、食事や運動、睡眠といった生活習慣を地道に見直し、時間をかけて体質を整えていくことが最も確実で効果的な方法といえます。
焦らず、できることからひとつずつ継続していくことが大切です。
血圧が90以下だとやはり危険?
血圧の数値だけを見て「危険だ」と判断することはできません。
収縮期血圧が90mmHg以下であっても、特に自覚症状がなく元気に過ごせているのであれば、それはその人の体質であり、過度に心配する必要はないといわれています。
問題となるのは、血圧の数値が低く、かつ、めまいや立ちくらみ、強い倦怠感など、日常生活に支障をきたす症状が出ている場合です。
数値に一喜一憂するのではなく、ご自身の体調をよく観察することが重要です。
低血圧の人にオススメのサプリはある?
低血圧の改善は、まずバランスのよい食事から栄養を摂ることが基本です。
その上で、食事だけでは補いきれない栄養素をサプリメントで補助的に活用するのはひとつの方法といえるでしょう。
健達ねっとショップでは、血液循環や脳の働きをサポートする可能性のある製品を取り扱っています。
例えば、栄養機能食品である「骨育注意報」には、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素である海水由来のマグネシウムが配合されています。
また、機能性表示食品「プラズマローゲンBOOCSスペシャル60」は、脳の働きを活性化させる効果が報告されており、脳血流の低下が気になる方をサポートします(健達ねっとショップ)。
サプリメントを利用する際は、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談の上、ご自身の判断で適切に活用するようにしましょう。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、つらい低血圧の症状を改善するための、食事・運動・生活習慣における8つの具体的な方法を中心に解説しました。
低血圧は単なる「体質」だと諦めてしまいがちですが、その原因とタイプを正しく理解し、ご自身に合った対策を継続することで、症状は着実に改善していく可能性があります。
低血圧改善のポイント
- 食事:たんぱく質と適度な塩分、そして十分な水分(1日1.8L目安)を摂る
- 運動:ウォーキングやふくらはぎを鍛える運動で、血流を促進する
- 生活習慣:規則正しい生活と「ゆっくり動作」で自律神経を整え、急な血圧変動を防ぐ
何よりも大切なのは、焦らず、今日からできることをひとつずつ生活に取り入れていくことです。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひあなたに合った改善策を見つけて、実践してみてください。
もしセルフケアを続けても症状が改善しない場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、決して一人で抱え込まず、早めに医療機関に相談しましょう。