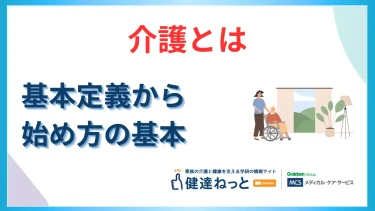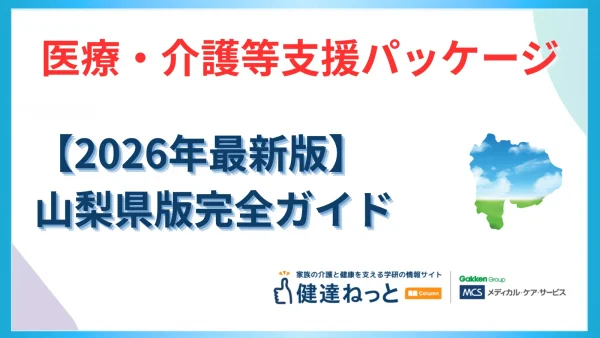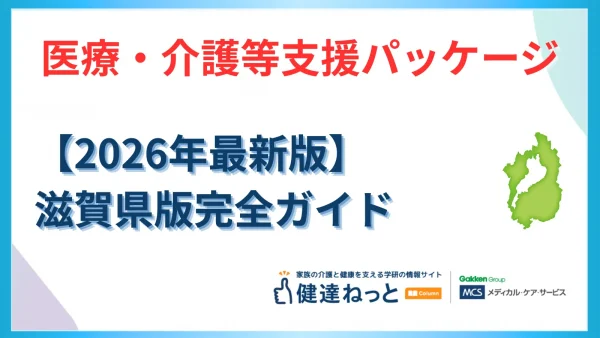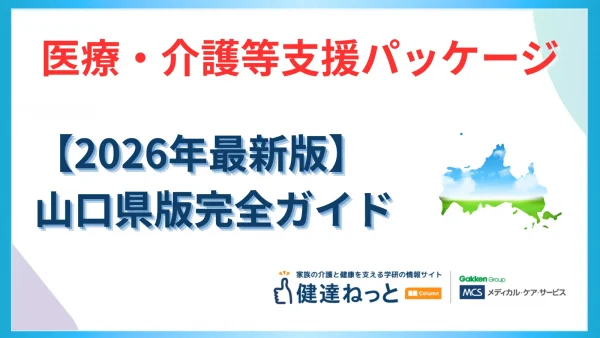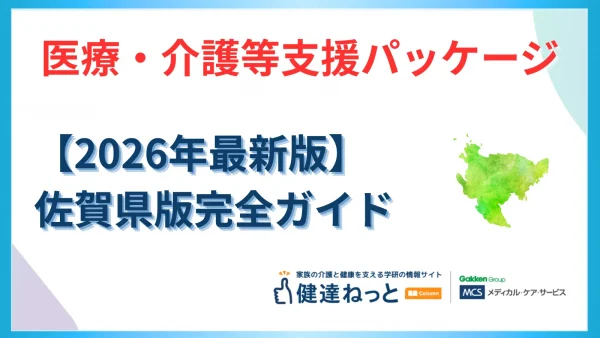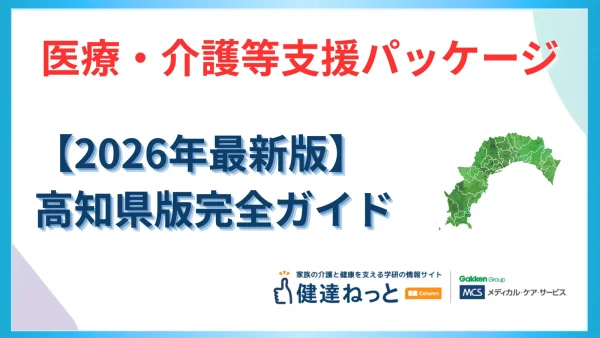「運転が心配だ」「事故を起こさないか心配」と繰り返し言われるたびに、親は「信用されていない」と感じることがあります。
心配する側としては「大切だからこそ伝えたい」という思いがありますが、言葉を受け取る側にとっては、「自分の判断力を疑われている」という印象が強く残ります。
「気にかけてくれるのはありがたい。でも、そればかり言われると疲れる」
親の心の中には、「自分はまだ大丈夫なのに」「そこまで心配されるほど衰えていない」という思いがあり、それが苛立ちや反発につながるのです。
些細な言葉でも、「心配だ」という言葉が繰り返されることで、相手には「無力感」や「疎外感」を感じさせることがあります。
スポンサーリンク
高齢者とのコミュニケーションで看護に役立つ視点とは?
高齢者とのコミュニケーションにおいて、看護の視点で重視されるのは、相手の立場に寄り添う姿勢です。
特に「心配だ」と繰り返し伝えることは、一見すると親切心の表現ですが、相手には「信用されていない」「自分の判断力を疑われている」と感じさせる要因にもなり得ます。
看護の視点では、相手の行動や表情を観察し、小さな変化にも敏感になることが求められます。
例えば、「最近、車の運転を避けている」「以前よりも外出が減った」といった些細な変化も、
言葉では表現されない心身の変調のサインかもしれません。
また、高齢者はこれまで自立してきた自負があります。
「心配だ」と繰り返すことで、自尊心を傷つけたり、無力感を感じさせることがあるため、
看護の場面では「心配」を強調せずに相手の意思や状況に寄り添う姿勢が求められます。
看護の視点でのコミュニケーションは、相手の言葉を受け止め、否定せずに共感を示すことが重要です。
言葉だけでなく、相手のペースに合わせた聞き方や表情の使い方も大切なポイントです。
スポンサーリンク
「ナッジ」を活用した高齢者とのコミュニケーション術
高齢者とのコミュニケーションで「心配だ」と繰り返すことは、相手に「信用されていない」と感じさせ、反発を招くことがあります。
そんなときに役立つのが「ナッジ」のアプローチです。
ナッジとは、相手の承認欲求を満たしながら、自発的な行動を促す方法です。
強制せず、「そうかもしれない」と相手が自然に気づく形を作るのがポイントです。
例えば、「大切に思っているからこそ、心配したくなる気持ち、わかるよね?」と伝えることで、
「心配している」という感情を直接的にぶつけるのではなく、相手の経験や感情に寄り添う形に変えることができます。
また、「自分も誰かを心配した経験があるから、その気持ちがよくわかる」と共有することで、
相手も「確かに、自分も同じだった」と受け入れやすくなります。
ナッジのポイントは、「気づき」を促すこと。
相手が自ら考え、行動を見直すきっかけを作ることで、「心配」という言葉を押しつけずに伝えることができます。
介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか? 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない… 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう? 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいい[…]
親の運転に寄り添うための心がけ
高齢者の運転に不安を感じると、「事故を起こさないか心配」「もう運転を控えた方がいい」と伝えたくなります。
しかし、繰り返し伝えることで、「自分は信用されていない」「判断力が疑われている」と感じさせてしまうことがあります。
長年運転してきた親ほど、「まだ大丈夫」「昔と同じようにできる」と思い込みやすく、
その結果、心配の言葉が反発や疎外感につながることも少なくありません。
親の運転に寄り添うためには、次の3つのポイントを意識することが大切です。
- 状況を尋ねる:「最近、運転してて困ったことはない?」と具体的な質問をすることで、相手自身が現状を振り返るきっかけを作る
- 共感を示す:「長年運転してきたから、まだまだ慣れてるよね」と経験を尊重する言葉を伝える
- ナッジを活用する:「大切に思っているからこそ、心配したくなる気持ち、わかるよね?」と共感の形で伝える
直接「心配だ」と伝えるのではなく、相手の経験や気持ちに寄り添うことで、お互いの立場を尊重した穏やかなコミュニケーションが生まれます。
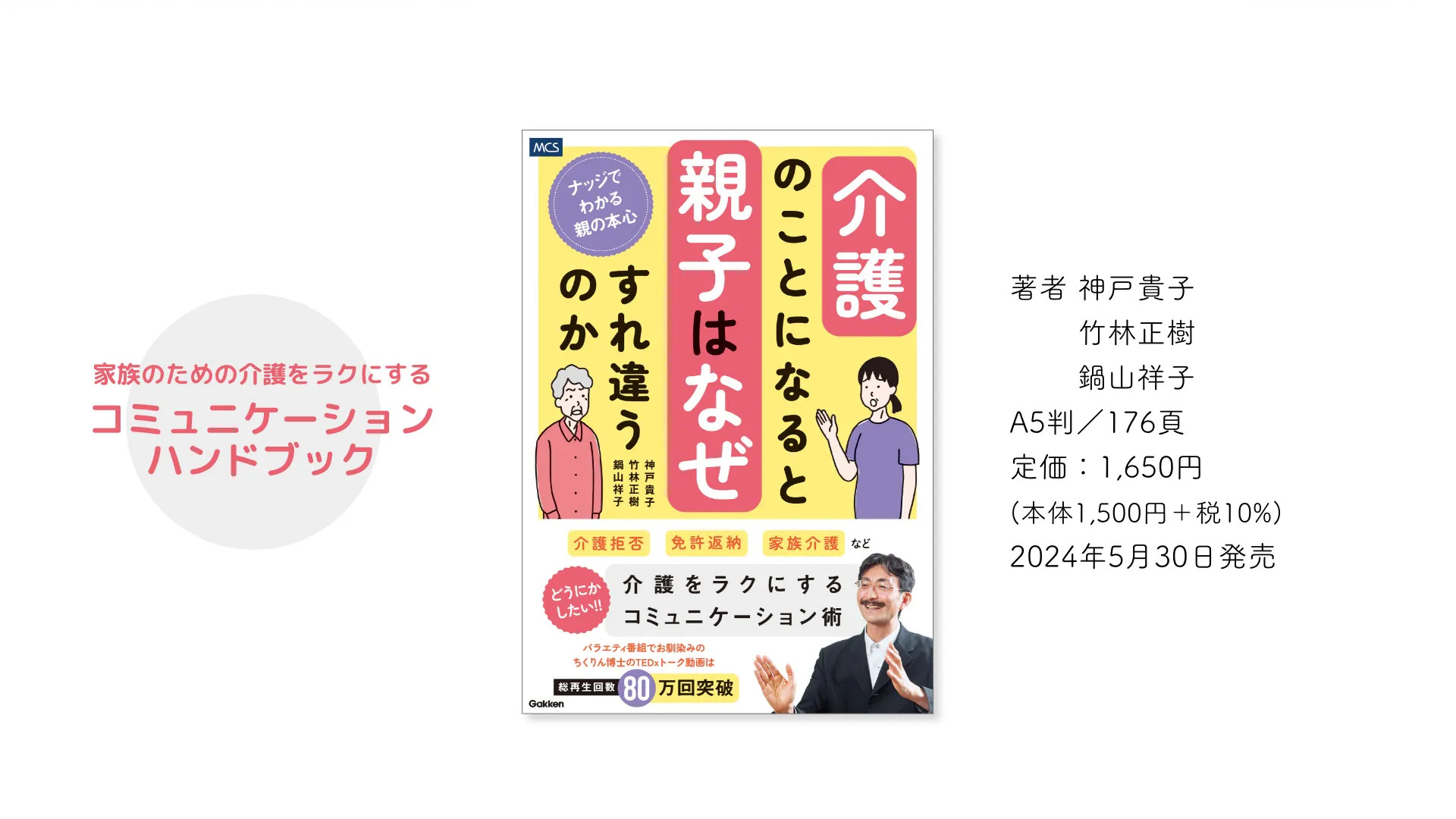
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります