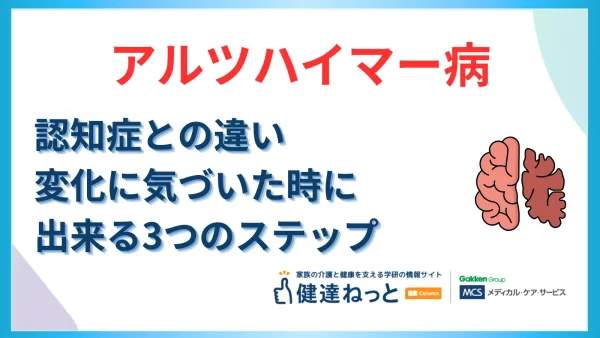- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「もしかして、認知症の始まりなのだろうか?」
- 「アルツハイマー病と認知症って、結局何が違うの?」
親の些細な変化に、このような不安を感じていませんか。
大切な家族だからこそ、心配になるのは当然のことです。
しかし、不確かな情報に振り回され、ひとりで悩みを抱え込む必要はありません。
この記事では、認知症とアルツハイマー病の決定的な違いから、ご家族が今すぐ取るべき具体的な行動まで、専門的な知見を元に分かりやすく解説します。
この記事を読めば、次の点が明確になります。
- 認知症とアルツハイマー病の根本的な違い
- 単なる「もの忘れ」と病気を見分けるチェックリスト
- アルツハイマー病以外の主な認知症の種類と特徴
- いざという時に頼れる相談先と受診までのステップ
漠然とした不安が解消され、親御さんのために「次に何をすべきか」が具体的に見えてくるはずです。
正しい知識を身につけ、冷静な第一歩を踏み出しましょう。
アルツハイマー型認知症の詳細を解説した記事も参考にしてみてください。
スポンサーリンク
【3分で分かる】認知症とアルツハイマー病の決定的な違い
「認知症」と「アルツハイマー病」。
このふたつの言葉の違いを、あなたは明確に説明できるでしょうか。
多くの方が混同しがちですが、実は両者の関係は全く異なります。
ここでは、その決定的な違いを誰にでも分かるように解説します。
違いが一目瞭然!「認知症」と「アルツハイマー病」の関係性
結論からいうと、「認知症」は病名ではなく、記憶や判断力などの認知機能が低下して日常生活に支障が出ている「状態」を指す言葉です。
一方で、「アルツハイマー病」は、その認知症を引き起こす原因となる「病気の名前」のひとつです。
つまり、アルツハイマー病を発症した結果として、認知症という状態になる、という関係性なのです。
メディカル・ケア・サービスでは、全国29校3,423名の小中高校生に認知症教育を行ってきました。メディカル・ケア・サービス発表
その経験から、この関係を最も分かりやすく説明する方法をご紹介します。
『認知症という大きな傘の下に、アルツハイマー病というひとつの病気がある』と考えてください。
雨(認知症)にはいろいろな種類がありますが、その中で最も多いのがザーザー降りの雨(アルツハイマー型認知症)だというイメージです。
この説明方法により、子どもたちの92%が認知症に対してよいイメージを持つようになったという調査結果も出ています。
(引用元:認知症とともに生きるまちづくりへの貢献に向けた実証研究を開始)
家族内でも、このような分かりやすい例えを使って説明することで、認知症への理解と向き合い方が変わっていくでしょう。
「病気」と「加齢」を見分けるもの忘れとの違い7つのチェックリスト
「最近、親のもの忘れが気になるけれど、年のせいかもしれない…」と悩む方は少なくありません。
もの忘れと認知症の見分け方の基本についてはこちらの記事でも解説していますが、加齢による自然なもの忘れと、病気のサインである認知症のもの忘れには、明確な違いがあります。
認知症によるもの忘れは、体験したこと自体をすっぽりと忘れてしまうのが特徴です。
例えば、「昨日の夕食に何を食べたか思い出せない」のは加齢によるもの忘れですが、「夕食を食べたこと自体を忘れてしまう」のは認知症の可能性があります。
ご家族の言動に当てはまるものがないか、以下のリストで確認してみましょう。
| 加齢によるもの忘れ | 認知症のサインとなりうるもの忘れ |
|---|---|
| 体験の一部を忘れる | 体験のすべてを忘れる |
| 探し物を見つけ出せる | 探し物をしたこと自体を忘れる |
| もの忘れの自覚がある | もの忘れの自覚がないことが多い |
| 日常生活に支障はない | 日常生活に支障が出ている |
| 症状はあまり進行しない | 症状が徐々に進行していく |
| 判断力は保たれている | 判断力が低下している |
| 時や場所は理解できる | 今いる時間や場所が分からなくなる |
このチェックリストはあくまで目安ですが、複数当てはまる場合は注意が必要です。
認知症は早期発見・早期対応が非常に重要になるため、少しでも気になったら専門家へ相談することを検討しましょう。
スポンサーリンク
アルツハイマー病だけではない!知っておくべき4大認知症の特徴と違い
認知症の原因となる病気は、アルツハイマー病だけではありません。
原因によって症状の現れ方や対処法も異なります。
ここでは代表的な4つの認知症について、それぞれの特徴と違いを解説します。
三大認知症の詳細な特徴と原因についてはこちらの記事もご参照ください。
【国内最多】アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も患者数が多く、全体の約67.6%を占めています。朝日生命調査データ
脳に「アミロイドβ」や「タウ」といった特殊なたんぱく質が蓄積し、神経細胞がダメージを受けることで脳が萎縮していく病気です。
特に記憶を司る「海馬」から萎縮が始まるため、初期症状としてもの忘れが目立つのが大きな特徴といえます。
症状は年単位でゆっくりと進行していきます。
アルツハイマー型認知症の主な症状の経過は以下の通りです。
- 初期症状:新しいことを覚えられない、同じことを何度も尋ねる
- 中期症状:時間や場所が分からなくなる(見当識障害)、段取りが立てられない
- 後期症状:人の顔が認識できない、失禁、歩行障害など身体機能の低下
もの忘れから始まり、徐々に日常生活全般に支障が及ぶようになります。
しかし、早期に治療を開始することで、症状の進行を緩やかにすることが可能です。
脳梗塞や脳出血が原因となる「血管性認知症」
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血といった脳の血管障害によって引き起こされる認知症です。
脳の血管が詰まったり破れたりして、神経細胞の一部が死んでしまうことで認知機能が低下します。
アルツハイマー型認知症が脳全体でゆっくりと進行するのに対し、血管性認知症は脳卒中の発作をきっかけに段階的に症状が悪化することがあります。
ダメージを受けた脳の部位によって症状が異なるため、「できること」と「できないこと」が比較的はっきりしているのが特徴です。
そのため「まだら認知症」とも呼ばれます。
認知症全体の約19.5%を占める二番目に多い認知症です。(参考:統計データ)
血管性認知症の主な特徴は以下の通りです。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 主な症状 | 意欲低下、感情のコントロールが難しい、手足の麻痺、言語障害 |
| 症状の進行 | 脳卒中などをきっかけに段階的に悪化する傾向 |
| 記憶障害 | 比較的保たれることが多いが、思い出すのに時間がかかる |
| 判断力 | 正常に保たれている部分も多い |
高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主なリスク因子となるため、これらの管理が予防につながります。
幻視やパーキンソン症状が特徴の「レビー小体型認知症」
レビー小体型認知症は、脳の神経細胞に「レビー小体」という特殊なたんぱく質のかたまりが現れることで発症します。
アルツハイマー型認知症、血管性認知症に次いで3番目に多い認知症です。
認知症全体の約4.3%を占めています。朝日生命調査データ
特徴的な症状として、「実際にはないものが見える」というリアルな幻視や、手足の震え・筋肉のこわばりといったパーキンソン症状が現れます。
また、日によって認知機能がよい時と悪い時の波が激しいのも特徴のひとつです。
レビー小体型認知症の詳しい症状についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
レビー小体型認知症の代表的な症状は以下の通りです。
- 幻視:「部屋の隅に子どもがいる」「虫が這っている」など、具体的な内容を訴える
- パーキンソン症状:小股で歩く、動作が遅くなる、手が震える、転びやすくなる
- 認知機能の変動:会話がしっかりできる時と、ぼーっとしている時の差が激しい
- レム睡眠行動異常症:睡眠中に大声で寝言をいったり、手足を激しく動かしたりする
これらの症状は、ご家族が気づきやすいサインでもあります。
早期発見のためにも、これらの特徴を知っておくことが大切です。
性格変化や万引きなど社会性が失われる「前頭側頭型認知症」
前頭側頭型認知症は、脳の中でも理性や感情、社会性をコントロールする「前頭葉」と「側頭葉」が萎縮することで起こる認知症です。
認知症全体の約1.0%を占める比較的稀な認知症です。統計データ
他の認知症と大きく異なるのは、記憶障害よりも先に性格の変化や行動の異常が目立つ点です。
感情の抑制が効かなくなり、自己中心的になったり、社会のルールを守れなくなったりします。
例えば、万引きをしてしまったり、信号無視を平気でしたりするなど、以前のその人からは考えられないような行動をとることがあります。
前頭側頭型認知症についてより詳しく知りたい方は、こちらの徹底ガイドをご覧ください。
厚生労働省の最新統計によると、認知症の種類別割合は以下の通りです。
- アルツハイマー型認知症:67.6%
- 血管性認知症:19.5%
- レビー小体型認知症:4.3%
- 前頭側頭型認知症:1.0%
前頭側頭型認知症の主な初期症状は以下の通りです。
- 性格の変化:周囲に無関心になる、共感性がなくなる、頑固になる
- 社会性の欠如:人の話を聞かずに一方的に話す、思ったことをすぐに口に出す
- 同じ行動の繰り返し:同じ道を何度も歩き回る、毎日同じものを食べる
- 食行動の異常:甘いものばかりを大量に食べる、食べ物の好みが極端に変わる
これらの行動は病気による症状であると理解し、頭ごなしに叱るのではなく、冷静に対応することが重要になります。
進化するアルツハイマー病の治療と予防法
「認知症は治らない」というイメージは、もはや過去のものです。
近年の目覚ましい医学の進歩により、進行を抑える新しい治療薬が登場しています。
また、日々の生活習慣が予防につながることも科学的に明らかになってきました。
ここでは、最新の治療と予防法について解説します。
進行を抑える新薬「レカネマブ」とは?最新の薬物療法
2023年9月25日に承認された「レカネマブ」は、アルツハイマー病の原因物質である「アミロイドβ」を脳内から除去することで、病気の進行そのものを緩やかにする画期的な新薬です。(参考:国立長寿医療研究センター)
これまでの薬が症状を一時的に改善する対症療法だったのに対し、レカネマブは病気の原因に直接アプローチする根本治療薬として期待されています。
ただし、この薬は病気の初期段階で高い効果を発揮するため、早期診断がこれまで以上に重要になりました。
レカネマブを含む認知症治療薬の詳細についてはこちらの記事もご覧ください。
レカネマブ治療の主なポイントは以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象 | アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症患者 |
| 効果 | 脳内のアミロイドβを除去し、認知機能の低下を約27%抑制(症状の進行をおよそ7.5か月遅らせる効果に相当)国立長寿医療研究センター |
| 投与方法 | 2週間に1回の点滴投与 |
| 注意点 | 脳のむくみや出血などの副作用が報告されており、定期的なMRI検査が必要 |
レカネマブの登場は、アルツハイマー病治療の新たな扉を開きました。
今後も新しい治療薬の開発が進んでおり、早期発見・早期治療の流れはさらに加速していくでしょう。
今日からできる!認知症リスクを下げる5つの生活習慣
アルツハイマー病の発症は、遺伝的要因だけでなく、長年の生活習慣も大きく関わっています。
つまり、日々の生活を見直すことで、発症リスクを下げることが可能です。
厚生労働省の研究によると、運動習慣がない方は運動習慣がある方(週2〜3回以上)と比べて認知症になるリスクが1.82倍であることが報告されています。
科学的根拠に基づく具体的な予防方法は様々ですが、まずは以下の5つの習慣を意識することから始めましょう。
具体的な食事内容や運動方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
認知症予防に効果的な5つの習慣は以下の通りです。
- 1. 適度な運動:週に3回、30分程度のウォーキングなど、少し汗ばむくらいの有酸素運動が脳の血流を促進します
- 2. バランスのよい食事:青魚、緑黄色野菜、ナッツ類など、抗酸化作用のある食品を積極的に摂りましょう
- 3. 知的な活動:読書、パズル、囲碁・将棋など、脳に刺激を与える趣味を持つことが大切です
- 4. 社会的な交流:友人との会話や地域の集まりへの参加は、脳の活性化につながります
- 5.質のよい睡眠:睡眠中に脳の老廃物が除去されるため、7時間程度の睡眠時間を確保しましょう
実際の介護現場では、どのような具体的な数値を目標にすればよいのでしょうか。
メディカル・ケア・サービスが全国287ホーム3,821名のデータから開発した「MCSケアモデル」では、水分摂取量1,800ml、たんぱく質摂取量80gといった具体的な数値目標を設定し、85%以上の機能改善実績をあげています。
これらの数値は、認知症予防においても重要な指標となります。
特に水分不足は認知機能の低下に直結するため、1日1,800mlの水分摂取を意識することから始めてみましょう。
生活習慣の改善とあわせて、科学的根拠に基づいた栄養補助も認知機能の維持に役立ちます。
メディカル・ケア・サービス監修の機能性表示食品「記憶の鉄人」は、PQQ(ピロロキノリンキノン)を配合し、記憶力・注意力・判断力の認知機能をサポートします。
また、「プラズマローゲンBOOCSスペシャル60」は、国産・高純度のホタテ由来プラズマローゲンを使用し、記憶力の維持に働きかけます。
これらの商品は、認知症専門医の監修の元、多数の論文に基づいて開発されており、日常の予防対策の一環として活用いただけるでしょう。
ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割であり、バランスの取れた食事と適度な運動が基本となることを忘れずに。
親がアルツハイマー病かも?と思ったら家族が今すぐすべき3つのステップ
親御さんの変化に気づいた時、ご家族は冷静に行動することが求められます。
しかし、何から手をつければよいのか分からず、不安ばかりが募るかもしれません。
ここでは、ご家族が「今すぐ」取り組むべきことを3つの具体的なステップに分けて解説します。
ステップ1.親の「気になる言動」をメモに残す
専門家に相談したり、医療機関を受診したりする際に最も重要なのが、客観的な情報です。
「最近、もの忘れがひどくて…」という曖昧な伝え方では、医師も正確な判断ができません。
いつ、どこで、どのような言動があったのかを具体的に記録しておくことで、的確な診断につながります。
初期症状のチェックポイントについてはこちらの記事も参考にしてみてください。
記録しておきたいポイントの例は以下の通りです。
| 記録する項目 | 具体例 |
|---|---|
| 日付と時間 | 9月29日の午前10時頃 |
| 場所 | 自宅のリビングで |
| 具体的な言動 | 「朝ごはん、まだ?」と3回聞かれた(実際には30分前に食べ終えている) |
| その時の様子 | 不安そうな表情をしていた |
| ご家族の対応 | 「さっき食べたよ」と伝えると、少し考えてから「ああ、そうだった」と納得した |
このようなメモは、ご家族にとっても状況を客観的に把握する助けになります。
スマートフォンやノートなど、記録しやすい方法で今日から始めてみましょう。
ステップ2.頼れる専門家と相談窓口に相談する
ひとりで抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
認知症に関する相談は、様々な場所で受け付けています。
いきなり専門の医療機関に行くのはハードルが高いと感じる場合は、まずは身近な相談窓口を利用してみましょう。
介護や認知症に関する相談窓口の詳細は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
主な相談先とその特徴は以下の通りです。
- かかりつけ医:まずは一番身近な医療の専門家。必要に応じて専門医を紹介してくれます
- 地域包括支援センター:市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師や社会福祉士が無料で相談に応じてくれます
- 認知症疾患医療センター:認知症の専門的な診断や治療を行う病院。かかりつけ医からの紹介状があるとスムーズです
どのような専門家に、どのような相談をすればよいのか迷う方も多いでしょう。
健達ねっとの専門家インタビューシリーズでは、認知症専門医や臨床心理士など、実際に認知症ケアに携わる専門家が「家族からよく受ける質問」に詳しく答えています。
『親のもの忘れが気になった時、最初に誰に相談すべきか』『医療機関を受診する前に準備しておくべきこと』など、多くの家族が抱える疑問への具体的なアドバイスをご覧いただけます。
専門家の生の声を聞くことで、より適切な相談先を見つけられるでしょう。
ステップ3.医療機関を受診して、検査・診断してもらう
専門家への相談と並行して、医療機関での検査・診断を進めましょう。
認知症の診断は、問診、神経心理検査、脳画像検査などを総合的に行って判断されます。
受診する診療科の選び方についてはこちらの記事で、医療機関で実施される長谷川式認知症スケールなどの検査についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
本人が受診を嫌がることも少なくありませんが、その場合は「健康診断の一環だよ」「脳の検査で健康状態をチェックしよう」など、本人の気持ちに配慮した伝え方を工夫しましょう。
一般的な検査・診断の流れは以下の通りです。
| 検査の種類 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 医師が本人や家族から、いつからどのような症状があるかなどを詳しく聞き取ります |
| 神経心理検査 | 長谷川式認知症スケールなどを用いて、記憶力や判断力といった認知機能の状態を評価します |
| 脳画像検査 | CTやMRIを撮影し、脳の萎縮の程度や脳血管障害の有無などを確認します |
| 血液検査 | 認知症と似た症状を引き起こす他の病気(甲状腺機能低下症など)がないかを調べます |
これらの検査結果を総合的に評価し、認知症の有無や種類、進行度を診断します。
確定診断を受けることは、適切な治療や介護サービスを利用するための重要な第一歩となります。
認知症ケアの最前線の経験から学研グループ「メディカル・ケア・サービス」としての取り組み
私たちメディカル・ケア・サービスは、学研グループの一員として、全国で認知症高齢者グループホーム「愛の家」などを運営しています。
グループホームの運営居室数は日本一を誇り、日々多くの認知症の方々とそのご家族に寄り添っています。
私たちは、単に介護サービスを提供するだけでなく、「認知症を取り巻く、あらゆる社会環境を変革する」ことが使命です。
認知症に関する正しい知識の普及や、科学的介護(MCSケアモデル)の実践、地域社会との連携など、多岐にわたる活動を行っています。
認知症と診断されても、適切なケアにより生活の質を向上させることは可能です。
実際に、当社グループホームにご入居された90歳のAさんは、毎日泣いて過ごされていましたが、得意だった調理の役割を担っていただくことで、1か月後には笑顔で他の入居者様と会話を楽しまれるようになりました。
また、3年間引きこもりがちだったBさんは、四つんばいでの移動から始まり、現在では押し車を使って歩行されるまでに機能が改善されています。
(参考事例:愛の家グループホーム 津一身田、愛の家グループホーム 津垂水)
これらの事例は、本人の世界観を否定せず、得意分野や興味のあることを見つけて役割を提供することの重要性を示しています。
認知症になっても、その人らしい生活を続けることは十分に可能なのです。
まとめ
この記事では、認知症とアルツハイマー病の決定的な違いから、主な認知症の種類、最新の治療法、そしてご家族が取るべき具体的なステップまでを解説しました。
重要なポイントを改めて振り返りましょう。
- 認知症は「状態」、アルツハイマー病は原因となる「病名」のひとつ
- もの忘れには「加齢」と「病気」の違いがあり、チェックリストで確認できる
- 認知症にはアルツハイマー病以外にも種類があり、原因によって症状や対処法が異なる
- 親の変化に気づいたら、「記録」「相談」「受診」の3ステップで行動することが大切
厚生労働省の2024年最新統計によると、2022年時点で65歳以上の高齢者における認知症の有病率は12.3%、軽度認知障害(MCI)の有病率は15.5%となっており、認知症とMCIの合計で約28%の高齢者が何らかの認知機能の問題を抱えています。
親御さんの変化に直面した時の不安は計りしれないものだと思います。
しかし、ひとりで抱え込む必要はありません。
正しい知識を身につけ、専門家や相談機関と連携することで、必ず道は開けます。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。