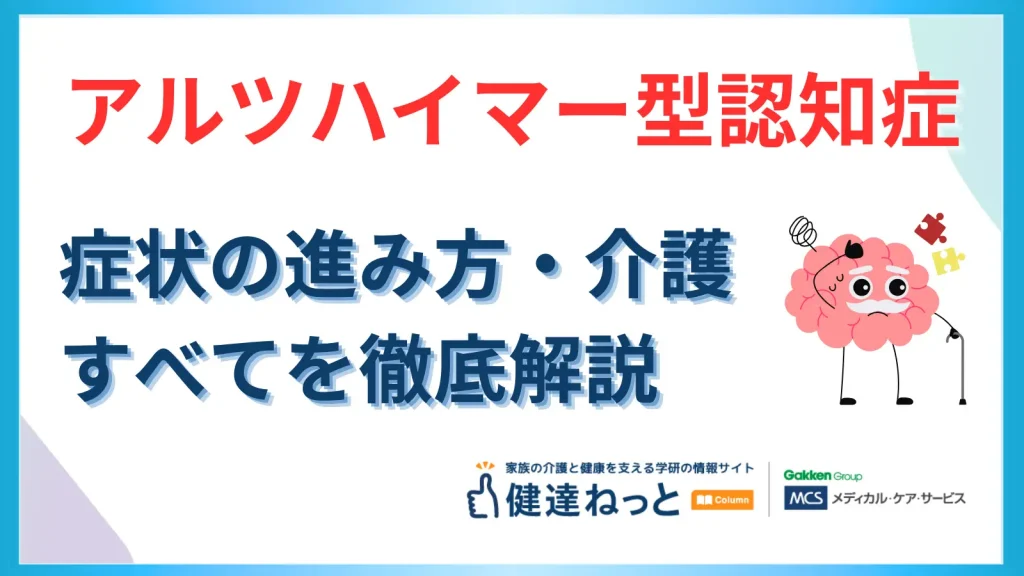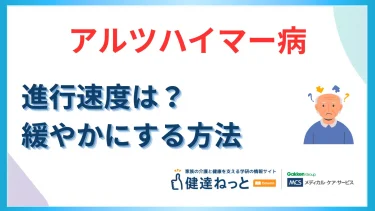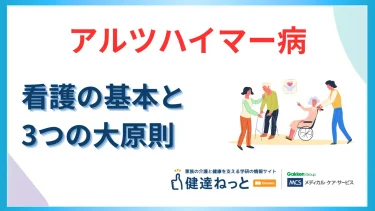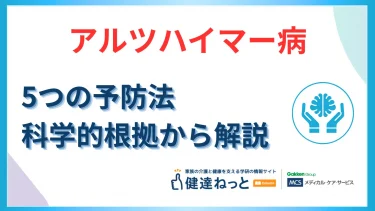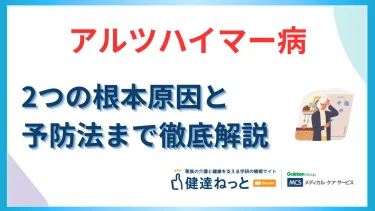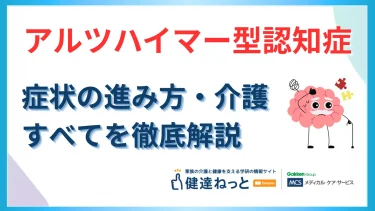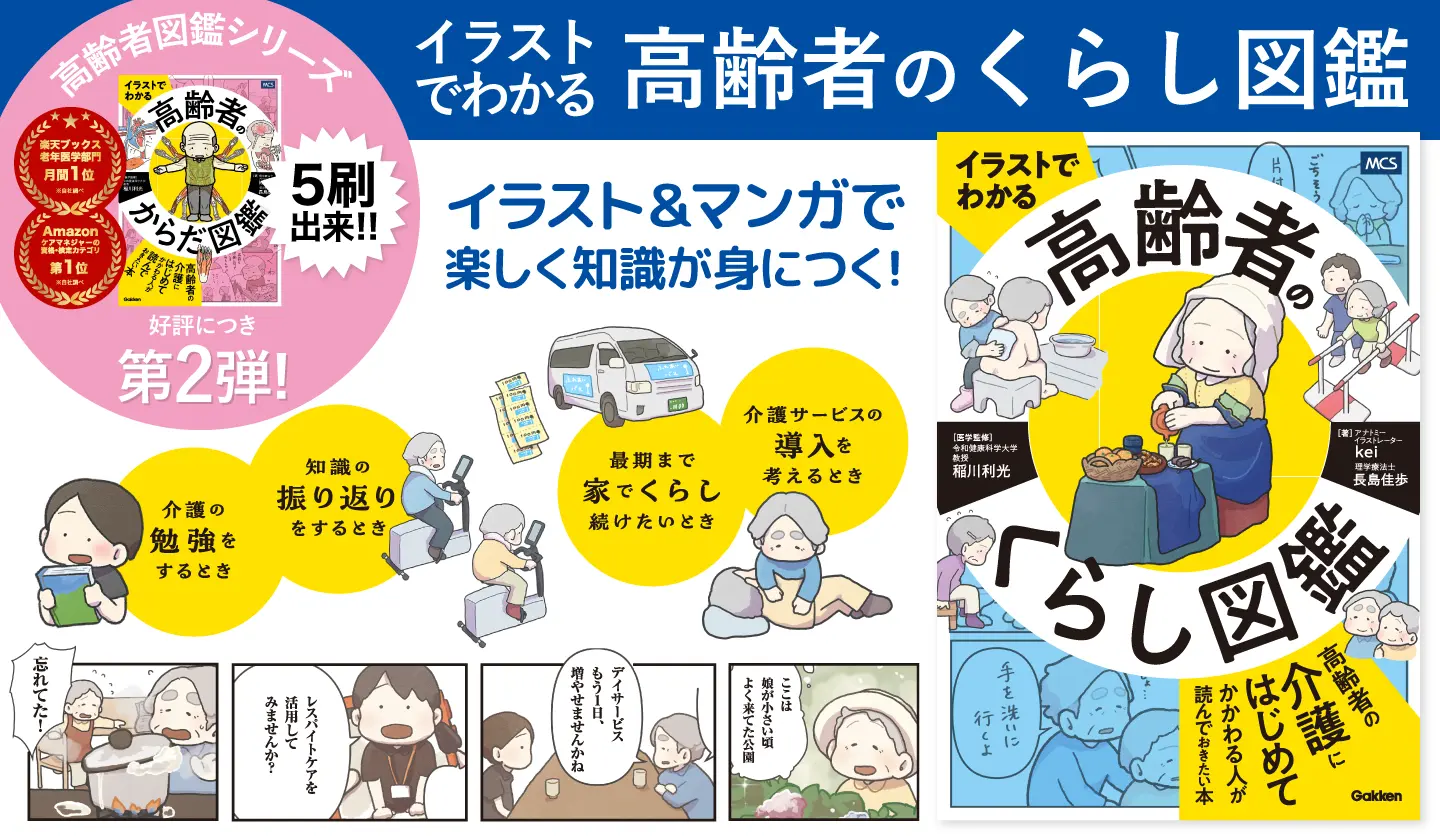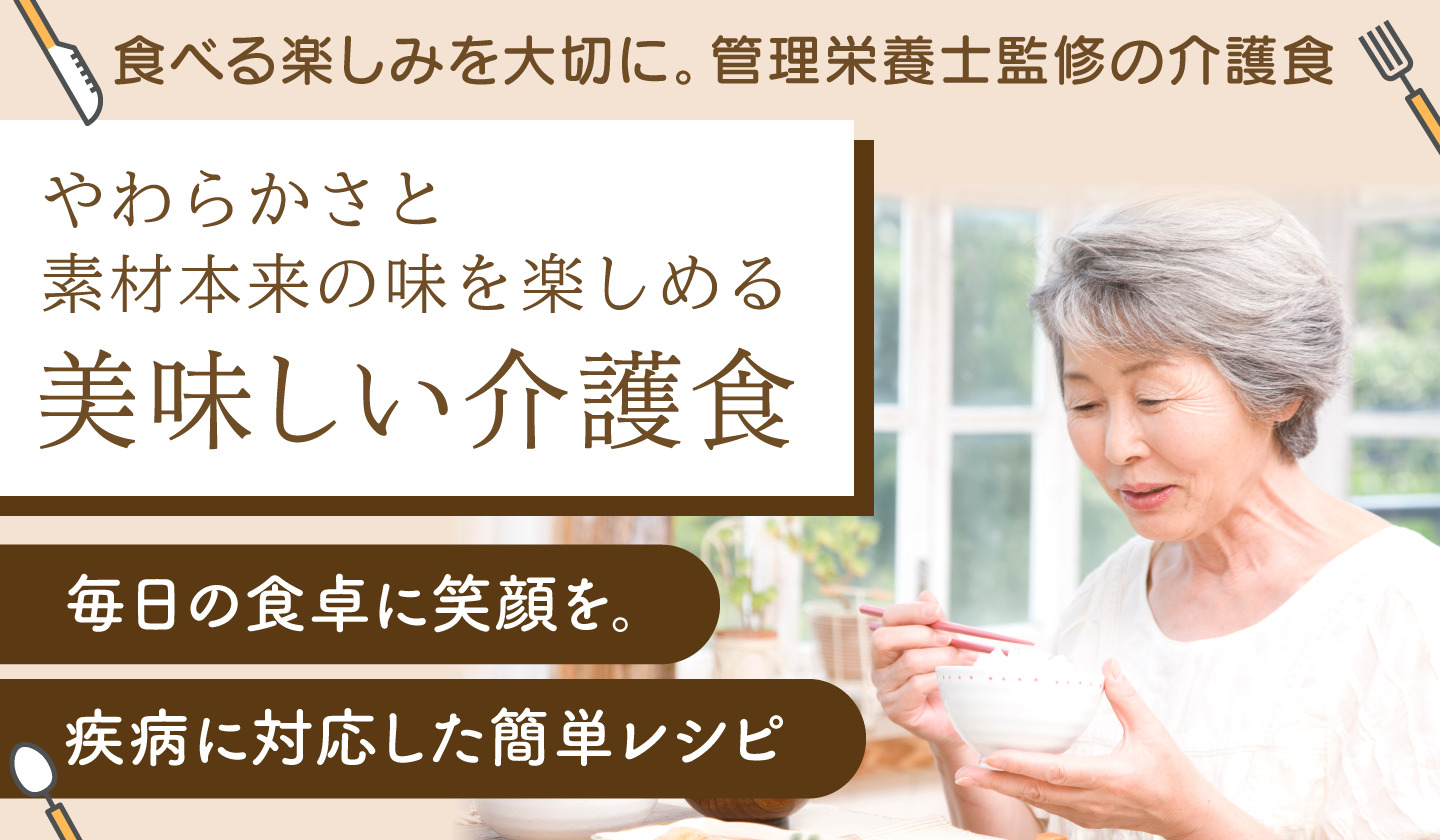- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「自分や家族の未来がどうなってしまうのか、不安で仕方ない」
- 「大切な人との関係が、病気のせいで壊れてしまったらどうしよう」
このような、言葉にしづらい不安を抱えてはいませんか。
アルツハイマー型認知症は、誰にとっても他人事ではない病気です。
しかし、その不安の多くは「知らないこと」から生まれます。
そこでこの記事では、アルツハイマー型認知症に関するあらゆる疑問にお答えします。
この記事を最後まで読めば、以下のポイントが明確に理解できるでしょう。
- アルツハイマー型認知症の正しい知識と症状の進行
- 原因と、今日からできる予防法
- 最新の治療法と、その選択肢
- 家族としてできることと、利用できる社会の支え
この記事は、あなたの不安を解消し、希望を持って未来への一歩を踏み出すための「羅針盤」です。
ぜひ、ご自身や大切な家族のために、正しい知識を身につけていきましょう。
スポンサーリンク
そもそもアルツハイマー型認知症とは
アルツハイマー型認知症とはどのような病気なのか、まずはその全体像を正しく理解することが、不安を解消する第一歩です。
ここでは、基本的な定義から他の認知症との違いまで、分かりやすく解説します。
「認知症」という状態と「アルツハイマー病」という原因疾患
「認知症」と「アルツハイマー病」は、しばしば混同されがちですが、その意味は異なります。
認知症とは、記憶力や判断力といった認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている「状態」を指す言葉です。
一方、アルツハイマー病は、その認知症を引き起こす原因となる病気のひとつです。
アルツハイマー病は、認知症の中で最も多く、全体の約60〜70%を占めるといわれています(若年性認知症の場合は52.6%)。
つまり、「認知症」という大きな枠組みの中に、原因のひとつとして「アルツハイマー病」が存在する、と理解するとよいでしょう。
厚生労働省の統計によると、若年性認知症(65歳未満)における基礎疾患の内訳は以下の通りです
- アルツハイマー型認知症:52.6%
- 血管性認知症:17.1%
- 前頭側頭型認知症:9.4%
- その他:26%程度
アルツハイマー病は、脳の神経細胞が徐々に壊れていくことで脳が萎縮し、認知機能が低下していく進行性の病気です。
この根本的な違いを理解することが、適切な対応を考える上で非常に重要になります。
より詳しい違いについては、アルツハイマー病と認知症の違いを徹底解説の記事もご参照ください。
【比較表】アルツハイマー型・レビー小体型・血管性認知症の主な違い
認知症の原因となる病気は、アルツハイマー病だけではありません。
代表的なものに「レビー小体型認知症」と「血管性認知症」があり、それぞれ症状や進行の仕方に特徴があります。
以下に、3大認知症の主な違いをまとめました。
| 種類 | 主な初期症状 | 進行の仕方 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|---|
| アルツハイマー型 | 新しいことを覚えられない記憶障害 | ゆるやかに進行する | 物盗られ妄想、取り繕い |
| レビー小体型 | リアルな幻視、パーキンソン症状 | よい時と悪い時の波が大きい | 薬剤への過敏性、レム睡眠行動異常症 |
| 血管性 | 障害された脳の部位による(まだら認知症) | 脳卒中などをきっかけに段階的に悪化 | 感情失禁(急に泣く・怒る)、意欲低下 |
このように、原因となる病気によって対応方法も異なります。
正確な診断を受けることが、その後の適切なケアにつながるのです。
それぞれの認知症の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
- レビー小体型認知症:症状・診断から介護までの徹底ガイド
- 血管性認知症:原因・症状から治療法まで
日本の患者数の現状と最新データ
日本では高齢化に伴い、認知症の患者数が増加の一途をたどっています。
厚生労働省の推計では、認知症高齢者数は2012年で462万人、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)に達すると予測されています。
また、2040年には約800〜950万人(65歳以上の高齢者の約4〜5人に1人)に達する見込みです。
若年性認知症(65歳未満)については、2020年度の実態調査では全国で約3.6万人と推計されています。
年齢と認知症発症の関係は深く、誰にとっても身近な問題といえます。
しかし、適切なケアによって症状の進行を穏やかにすることは可能です。
メディカル・ケア・サービス(MCS)が全国287の介護施設で蓄積したデータ分析では、独自のケアモデルを適用した結果、アルツハイマー型認知症の方々の85%以上に周辺症状(BPSD)や身体機能の改善が見られました。
この事実は、たとえ診断を受けても、その後のケア次第で穏やかな生活を維持できる可能性を示しています。
スポンサーリンク
アルツハイマー型認知症の症状の進み方
アルツハイマー型認知症は、時間をかけてゆっくりと進行します。
症状がどのように変化していくのか、その時間軸を理解しておくことで、心の準備ができ、各段階で適切な対応をとることが可能になります。
始まりのサイン(MCI)と加齢によるもの忘れの境界線
「最近、もの忘れが増えたな」と感じた時、それが単なる加齢によるものなのか、病気のサインなのかを見分けることは非常に重要です。
健常な状態と認知症の中間には、MCI(軽度認知障害)という段階が存在します。
MCIは「認知症予備軍」とも呼ばれ、記憶力の低下などの症状はあるものの、日常生活に大きな支障はない状態を指します。
この段階で早期に気づき、適切な対策を始めることで、認知症への進行を防いだり、遅らせたりできる可能性があるのです。
MCIの主な特徴は以下の通りです。
- 本人や家族からもの忘れの訴えがある。
- 以前と比べて記憶力が落ちている。
- 日常生活や社会生活は自立して送れている。
MCIについて詳しく知りたい方は軽度認知障害(MCI)の症状と対策をご参照ください。
また、MCI段階での簡単セルフチェック方法もあわせてご確認いただけます。
初期:記憶障害・段取り力の低下など
アルツハイマー型認知症の初期段階では、日常生活に大きな支障は出ないものの、本人や家族が「あれ?」と感じる変化が現れ始めます。
特に目立つのが、新しい出来事を記憶する力の低下です。
初期症状の具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 数分前、数時間前の出来事を忘れる(食事したこと自体を忘れるなど)。
- 同じことを何度も話したり、尋ねたりする。
- 料理や買い物など、段取りが必要な作業が苦手になる(遂行機能障害)。
- 物の名前がすぐに出てこない(喚語困難)。
- 好きだったことへの興味や関心が薄れる(アパシー)。
これらのサインは、単なる「うっかり」とは質が異なります。
初期症状のチェックリストと早期発見のポイントで、ご自身やご家族の状況を客観的に確認してみることをオススメします。
中期:日常生活への支障やBPSD(物盗られ妄想・徘徊など)の顕在化
中期に進行すると、記憶障害はさらに進み、日常生活におけるさまざまな場面で支障が目立つようになります。
また、この時期はBPSD(行動・心理症状)と呼ばれる、介護の負担を大きくする症状が現れやすいのが特徴です。
BPSDは、脳の機能低下に、本人の性格や環境、身体状態などが複雑に絡み合って起こります。
主な症状には、以下のようなものがあります。
- 物盗られ妄想:「財布を盗られた」など、事実ではないことを固く信じ込む。
- 徘徊:目的もなく歩き回り、帰り道が分からなくなる。
- 興奮・暴力:些細なことで怒りっぽくなったり、暴言や暴力が出たりする。
- 幻覚・幻視:いないはずの人が見える、声が聞こえるなど。
- 介護への抵抗:入浴や着替えなどを頑なに拒否する。
これらの行動は、本人のわがままではなく、病気による不安や混乱の表れです。
この段階での家族の対応方法と介護のコツを学ぶことが、ご本人とご家族双方の負担を軽減する鍵となります。
終期・終末期:意思疎通の困難化と身体的ケアへの移行
終期(高度)になると、認知機能の低下はさらに進み、意思疎通が非常に困難になります。
言葉を発することが少なくなり、家族の顔を認識できなくなることもあります。
この段階では、精神的な症状よりも身体的な問題が中心となり、全面的な介護が必要となります。
終末期に見られる主な状態は以下の通りです。
- ほとんど寝たきりの状態になる。
- 食事を飲み込む力が低下する(嚥下障害)。
- 失禁が増える。
- 身体が硬直し、手足が動かしにくくなる(拘縮)。
精神的な活動は低下しますが、感情が完全になくなるわけではありません。
穏やかな声かけや、肌に触れるなどのコミュニケーションを通じて、安心感を与えるケアが重要になります。
認知症の最期に向けた準備と家族のケアでは、この時期の心構えや具体的なケアについて詳しく説明していますので、あわせて参考にしてみてください。
アルツハイマー認知症の平均余命
「診断された後、あとどのくらい生きられるのか」というのは、ご本人やご家族にとって非常に切実な問題です。
複数の研究によると、平均余命は5年〜12年の幅があり、「8年〜10年」の表記は一部の研究に基づくものです。
また、日本のある研究では、認知症と診断された患者の10年生存率がアルツハイマー病で18.9%とされています。
余命に影響を与える要因はさまざまです。
- 診断時の年齢:若くして発症した方が進行は早い傾向にあります。
- 性別:男性よりも女性の方が余命は長い傾向があります。
- 健康状態:高血圧や糖尿病などの合併症の有無や、栄養状態が影響します。
- ケアの質:適切な医療や介護を受けられる環境も重要です。
大切なのは、数字に一喜一憂するのではなく、残された時間をいかに豊かに、穏やかに過ごすかを考えることです。
認知症の進行速度と生存期間に関する詳細なデータも参考にしながら、今後の生活設計について家族で話し合うきっかけにしてください。
アルツハイマー型認知症が発症する原因
「なぜ、アルツハイマー型認知症になるのだろうか」という疑問は、多くの方が抱くものです。
原因を正しく理解することは、病気への向き合い方や予防法を考える上で欠かせません。
アミロイドβとタウの蓄積といった脳内の変化
アルツハイマー型認知症の根本的な原因は、脳の中に「アミロイドβ(ベータ)」と「タウ」という2種類の異常なたんぱく質が蓄積することにあると考えられています。
この2つのたんぱく質が、脳に次のような変化を引き起こします。
- アミロイドβの蓄積:脳のゴミといわれるアミロイドβが排出されずに溜まり、「老人斑」というシミのようなものを作ります。これが神経細胞にダメージを与え始めます。
- タウの蓄積:神経細胞内で、栄養などを運ぶレールを支える役割のタウが異常をきたし、もつれて固まってしまいます(神経原線維変化)。これにより、神経細胞そのものが死んでしまいます。
この一連の変化が、記憶を司る「海馬」という部分から始まり、徐々に脳全体に広がっていくことで、脳が萎縮し、さまざまな認知機能の障害を引き起こすのです。
脳への影響メカニズムについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
年齢と遺伝子(APOE4)などの避けられない要因
アルツハイマー型認知症の発症には、自分ではコントロールが難しい、避けられない要因も関係しています。
その代表的なものが「年齢」と「遺伝子」です。
- 年齢:アルツハイマー型認知症の最大のリスク因子は加齢です。65歳を過ぎると有病率は年齢とともに上昇し、85歳以上では約4人に1人が認知症になるといわれています。
- 遺伝子:特定の遺伝子が発症リスクと関連することが分かっています。特に「APOE4(アポリポタンパクE4)」という遺伝子を持っていると、APOE4を1コピー受け継ぐとリスクは約3〜4倍、2コピーだと約10〜12倍に高まるとされています。ただし、これはあくまで「なりやすい」というだけで、必ず発症するわけではありません。
APOE4遺伝子に関する最新の研究情報によると、APOE4を2つ持つ人は人口の約2〜3%で、アルツハイマー病患者の約15%を占めることが分かっています。
また、性別とアルツハイマー病の関係も指摘されており、女性の方が男性よりも発症しやすいことが知られています。
これらの要因があるからといって悲観する必要はありません。
次のセクションで解説する、自分で変えられるリスク因子への対策が重要になります。
生活習慣で見直せる12のリスク因子
アルツハイマー型認知症の発症には、日々の生活習慣が大きく関わっています。
国際的な医学雑誌『ランセット』の委員会報告によると、認知症の約40%は、12の修正可能なリスク因子を改善することで予防できる可能性があるとされています。
その12のリスク因子は以下の通りです。
- 高血圧
- 肥満(中年期)
- 難聴
- 喫煙
- うつ病
- 運動不足
- 社会的孤立
- 低学歴
- 糖尿病
- 過度の飲酒
- 頭部外傷
- 大気汚染
これらのリスクをひとつずつ減らしていくことが、アルツハイマー型認知症の予防につながります。
特に生活習慣病と認知症の深い関係は深く、日頃の健康管理がいかに大切かが分かります。
詳しい予防アプローチについては、生活習慣からの認知症予防アプローチの記事もぜひ参考にしてみてください。
もしかしてアルツハイマー型認知症かも?と思った時の診断までのステップ
「もしかして…」と感じた時、不安な気持ちのまま過ごすのではなく、勇気を出して専門機関に相談することが大切です。
ここでは、受診を決めてから診断が下されるまでの具体的なステップを解説します。
何科に行けばよいか
もの忘れが気になった時、どの病院の何科を受診すればよいか迷う方は少なくありません。
アルツハイマー型認知症の診断を専門としているのは、主に以下の診療科です。
- もの忘れ外来・メモリークリニック:認知症を専門に診る外来で、最も相談しやすい窓口です。
- 神経内科(脳神経内科):脳や神経の病気を専門とする科で、的確な診断が期待できます。
- 精神科・心療内科:うつ病など他の精神疾患との鑑別が必要な場合に適しています。
まずはかかりつけ医に相談し、専門医を紹介してもらうのもよい方法です。
また、どこに相談すればよいか分からない場合は、お住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」が最初の相談窓口として非常に頼りになります。
受診先に迷った際は、認知症の相談先と受診の流れを参考にしてみてください。
検査内容のすべて
アルツハイマー型認知症の診断は、ひとつの検査だけで行われるわけではありません。
問診、神経心理学検査、画像検査などを組み合わせて、総合的に判断されます。
診断プロセスで行われる主な検査は以下の通りです。
| 検査の種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 問診 | 本人や家族から症状の経過などを詳しく聞く | 症状の具体的な内容や生活への影響を把握する |
| 神経心理学検査 | 長谷川式スケール、MMSEなどを用いて記憶力や判断力を評価する | 認知機能の低下の程度を客観的に測定する |
| 画像検査 | MRI、CTなどで脳の萎縮の程度や他の病気の有無を調べる | 脳の状態を視覚的に確認し、他の病気との鑑別を行う |
| 血液検査 | 甲状腺機能や栄養状態などを調べる | 認知症に似た症状を引き起こす他の身体疾患を除外する |
| バイオマーカー検査 | アミロイドPET検査や脳脊髄液検査で原因物質を調べる | より確実な診断や、新薬の適応判断のために行われる |
これらの認知症検査の全体像と検査との向き合い方を事前に知っておくことで、安心して検査に臨めるでしょう。
最近では血液検査による診断の最新情報も進歩しており、診断技術は日々進化しています。
診断で重視されるポイント
医師がアルツハイマー型認知症の診断を下す際には、いくつかの重要なポイントを総合的に評価します。
検査の数値だけでなく、日常生活の様子が診断の大きな手がかりとなります。
診断において特に重視されるのは、以下の3点です。
- 認知機能の低下:記憶、見当識、判断力などの機能が、以前と比べて明らかに低下しているか。
- 日常生活への支障:認知機能の低下によって、仕事や家事、社会生活に支障が出ているか。
- 他の原因の除外:症状が、うつ病や甲状腺機能低下症、薬の副作用など、治療可能な他の病気によるものではないか。
このため、受診の際には、いつから、どのような症状で、どのように困っているのかを具体的に伝えることが非常に重要です。
事前にメモを準備していくとよいでしょう。
正確な診断のためには、診断の流れと必要な情報の準備について理解しておくことが大切です。
今受けられるアルツハイマー型認知症の治療法のすべて
「アルツハイマー型認知症は治らない」と聞いて、希望を失ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、現在の医療では、病気の進行を穏やかにし、生活の質を維持するためのさまざまな治療法が存在します。
【薬物療法】2つのアプローチ
アルツハイマー型認知症の薬物療法には、大きく分けて2つのアプローチがあります。
ひとつは症状の進行を穏やかにする「症状緩和薬」、もうひとつは病気の根本原因に働きかける新しいタイプの「疾患修飾薬」です。
症状の進行を穏やかにする薬
現在、アルツハイマー型認知症の治療で中心的に使われているのが、症状の進行を一定期間ゆるやかにすることを目的とした薬です。
これらの薬は、脳内の神経伝達物質の働きを調整することで、認知機能をサポートします。
現在、日本で承認されている主な治療薬は以下の4種類です。
- ドネペジル(アリセプト®など):軽度から高度まで、すべての病期で使用できる。
- ガランタミン(レミニール®など):軽度から中等度の段階で使用される。
- リバスチグミン(イクセロン®パッチなど):貼り薬タイプで、軽度から中等度で使用される。
- メマンチン(メマリー®など):中等度から高度の段階で使用される。
これらの認知症薬の基本薬一覧と効果・副作用を正しく理解し、医師と相談しながら治療を進めることが重要です。
詳しくはアルツハイマー型認知症の薬の種類と副作用の詳細もご覧ください。
【最新治療】原因物質に働きかける新薬
近年、アルツハイマー型認知症の治療は大きな転換期を迎えています。
病気の根本原因である脳内のアミロイドβに直接働きかけ、取り除くことで病気の進行そのものを抑制する「疾患修飾薬」が登場したのです。
その代表的な薬が「レカネマブ(レケンビ®)」です。
この薬は、これまでの薬とは全く異なる作用を持ち、アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が臨床試験で証明されました。
レカネマブの詳細な効果と承認状況は以下の通りです。
- 2023年9月25日に日本で承認取得
- 臨床試験では認知機能低下を27%抑制
- 症状の進行を約5.3〜7.5か月遅らせる効果
ただし、この新しい治療にはいくつかの注意点があります。
- 対象者:治療を受けられるのは、アミロイドβの蓄積が確認された、ごく早期の患者さん(MCIまたは軽度認知症)に限られます。
- 副作用:ARIA(アミロイド関連画像異常)と呼ばれる、脳のむくみや出血などの特有の副作用があり、定期的なMRI検査による厳重な管理が必要です。
- 費用:治療費は非常に高額であり、医療保険制度の適用や高額療養費制度の活用が不可欠です。
この最新治療は大きな希望ですが、誰もが受けられるわけではありません。
主治医とよく相談し、メリットとデメリットを十分に理解した上で検討することが大切です。
【非薬物療法】生活の質を高めるリハビリテーション
薬による治療と並行して、あるいはそれ以上に重要なのが、薬を使わない「非薬物療法」です。
これは、リハビリテーションを通じて残っている機能を最大限に活かし、生活の質(QOL)を高めることを目的とします。
さまざまな種類がありますが、科学的にも効果が示されている代表的なリハビリテーションは以下の通りです。
- 運動療法:ウォーキングなどの有酸素運動や軽い筋力トレーニングは、認知機能の維持だけでなく、気分の安定や転倒予防にもつながります。
- 認知刺激療法:ゲームやクイズ、計算など、楽しみながら脳を活性化させる活動です。
- 回想法:昔の写真や音楽をきっかけに、過去の楽しい思い出を語り合うことで、精神的な安定を図ります。
- 音楽療法:歌を歌ったり楽器を演奏したりすることで、不安や興奮を和らげ、コミュニケーションを促します。
これらの認知症リハビリの内容と効果は多岐にわたります。
特に運動療法の効果と種類は多くの研究で証明されており、日々の生活に積極的に取り入れることが推奨されます。
また、薬物療法やリハビリと併用し、記憶力の維持をサポートする科学的根拠に基づいた機能性表示食品を生活習慣の一環として取り入れる方法も選択肢のひとつです。
アルツハイマー型認知症の発症と進行を遅らせる方法
アルツハイマー型認知症は、現在の医療では完治が難しい病気です。
しかし、発症を遅らせたり、進行を穏やかにしたりするために、自分自身でできることは数多くあります。
ここでは、科学的根拠に基づいた予防法をご紹介します。
脳を守る食事法と運動習慣
「食事」と「運動」は、認知症予防の二大要素です。
日々の生活習慣を見直すことが、脳の健康を守ることに直結します。
特に効果的とされる食事法と運動習慣は以下の通りです。
- 食事法:野菜、果物、魚、全粒穀物を中心とした「地中海式食事法」が、認知機能の低下を抑制することが多くの研究で示されています。青魚に含まれるDHAやEPA、緑黄色野菜に含まれる抗酸化物質などを積極的に摂りましょう。
- 運動習慣:週に3回以上、30分程度のウォーキングなどの有酸素運動が推奨されます。運動は、脳の血流を改善し、神経細胞を保護する物質を増やす効果が期待できます。
効果的な食べ物とトレーニング内容や、予防に適した食事と栄養素について詳しく知り、今日から実践してみましょう。
DHAやEPAなどの栄養素を効率的に摂取したい場合は、DHAやEPAを配合した機能性表示食品の活用も選択肢のひとつです。
知的活動と人とのつながりによる「認知予備脳」の向上
脳も身体と同じで、使わなければ衰えていきます。
日頃から頭を使い、知的好奇心を持ち続けることが、脳の予備能力である「認知予備能(コグニティブ・リザーブ)」を高め、認知症の発症を遅らせることにつながります。
認知予備能を高める活動の例は以下の通りです。
- 新聞や本を読む
- 日記をつける
- パズルやボードゲームをする
- 新しい趣味を始める(楽器、絵画、語学など)
- 旅行の計画を立てる
また、人とのコミュニケーションは、脳にとって最高の刺激です。
家族や友人との会話を楽しんだり、地域のサークルやボランティア活動に参加したりと、社会的なつながりを保つことが非常に重要です。
認知症予防に効果的な趣味と続けるコツを参考に、楽しみながら続けられる活動を見つけてみてください。
生活習慣病と難聴の管理
アルツハイマー型認知症の予防は、脳だけを考えるのではなく、全身の健康管理と密接に関わっています。
特に、「生活習慣病」と「難聴」の管理は、認知症リスクを低減させる上で非常に重要です。
- 生活習慣病の管理:高血圧、糖尿病、脂質異常症などは、動脈硬化を進め、脳の血流を悪化させることで認知症のリスクを高めます。定期的な健康診断を受け、医師の指導のもとで血圧や血糖値を適切にコントロールしましょう。
- 難聴の管理:耳が聞こえにくくなると、人との会話が減り、脳への刺激が少なくなってしまいます。これが認知機能の低下につながることが分かっています。聞こえに問題を感じたら、早めに耳鼻科を受診し、必要であれば補聴器を適切に使用することが大切です。
生活習慣病と認知症予防の深い関係を理解し、日々の健康管理に努めましょう。
アルツハイマー型認知症の患者の家族ができること
ご家族がアルツハイマー型認知症と診断された時、どのように接すればよいのか、戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。
しかし、ご家族の対応ひとつで、ご本人の心の安定や症状の進行は大きく変わります。
3つの基本的な姿勢
アルツハイマー型認知症の方と接する上で、最も大切にしたいのが以下の3つの基本的な姿勢です。
これは「スリー・ドント(3つのDON’T)」とも呼ばれ、介護の現場で広く知られています。
- 驚かせない(Don’t surprise):急に話しかけたり、後ろから肩を叩いたりせず、相手の視野に入ってから、穏やかに話しかけましょう。
- 急がせない(Don’t hurry):ご本人のペースを尊重し、ゆっくりと待つ姿勢が大切です。焦らせることは、混乱や不安を招くだけです。
- 自尊心を傷つけない(Don’t hurt his/her pride):失敗を責めたり、子ども扱いしたりする言動は避けましょう。一人の人間として尊重し、敬意を持って接することが信頼関係の基本です。
これらの姿勢を心掛けることが、穏やかな関係を築く第一歩となります。
家族の向き合い方から対応方法までをまとめた完全ガイドも、ぜひご一読ください。
BPSD症状別の困った時の対応方法
介護において家族を悩ませるのが、物盗られ妄想や徘徊といったBPSD(行動・心理症状)です。
これらの症状は、ご本人の不安や混乱の表れであることを理解し、頭ごなしに否定せず、その気持ちに寄り添うことが対応の鍵となります。
| 症状 | やってはいけない対応(NG例) | オススメの対応(OK例) |
|---|---|---|
| 物盗られ妄想 | 「盗るわけないでしょ!」と強く否定する | 「それは大変。一緒に探しましょう」と共感し、気持ちを逸らす |
| 徘徊 | 「どこへ行くの!」と力ずくで止めようとする | 「何かお探しですか?」と目的を聞き、少し付き添ってから家に誘う |
| 食事の拒否 | 「食べないとダメでしょ!」と無理強いする | 「あら、美味しそうですね」と関心を引いたり、時間を変えたりする |
メディカル・ケア・サービスの介護現場での実例からも、出来事の記憶は失っても、その時の「感情」は心に残り続けることが分かっています。
日々の関わりで安心感や楽しいといったよい感情を積み重ねることが、何よりのBPSD対策となるのです。
より詳しい対応方法は、認知症の方への対応の仕方と家族ケアをご覧ください。
介護者が燃え尽きないために大事なこと
アルツハイマー型認知症の介護は長期戦です。
ご本人のケアと同じくらい、あるいはそれ以上に大切なのが、介護者自身の心と身体の健康を守ることです。
介護者が倒れてしまっては、元も子もありません。
介護者が燃え尽きないために、以下のことをぜひ心掛けてください。
- 完璧を目指さない:「100点満点の介護」は存在しません。60点くらいでよしとしましょう。
- 一人で抱え込まない:家族や親戚、専門家など、頼れる人には積極的に助けを求めましょう。
- 自分の時間を持つ:介護から離れて、趣味や休息の時間を意識的に作ることが大切です(レスパイトケア)。
- 悩みを共有する:同じ境遇の人が集まる家族会などに参加し、気持ちを分かち合うことも有効です。
「介護に疲れた」と感じるのは、あなたが一生懸命だからです。
介護に限界を感じた時のストレス軽減方法を参考に、ご自身のケアも決して忘れないでください。
スポンサーリンク
知っておきたい公的制度と相談先
アルツハイマー型認知症の介護は、家族だけで抱え込むものではありません。
日本には、介護を社会全体で支えるためのさまざまな制度や相談窓口が用意されています。
これらの支援を積極的に活用することが、ご本人とご家族の負担を軽減する鍵となります。
最初の相談窓口である地域包括支援センターの活用法
「どこに相談したらいいか分からない」――そのような時に、まず訪ねてほしいのが「地域包括支援センター」です。
これは、高齢者の保健・医療・福祉に関する「よろず相談窓口」で、各市区町村に設置されています。
地域包括支援センターでは、以下のようなサポートを無料で受けられます。
- 認知症に関する全般的な相談
- 専門の医療機関やサービスの紹介
- 介護保険の申請手続きの支援
- 成年後見制度などの権利擁護に関する相談
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が連携して対応してくれます。
認知症に関する悩みが生じたら、まずはお住まいの地域包括支援センターの業務内容と利用条件を確認し、電話をかけてみましょう。
経済的負担を軽くする制度
認知症の介護には、医療費や介護サービス費など、経済的な負担が伴います。
その負担を軽減するために、国や自治体はさまざまな公的制度を設けています。
主に活用できる制度は以下の通りです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 介護保険制度 | 要介護認定を受けることで、ヘルパーやデイサービスなどを1〜3割の自己負担で利用できる。 |
| 高額療養費制度 | 医療機関や薬局で支払った医療費が、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される。 |
| 高額介護サービス費 | 介護保険サービスの自己負担額が、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される。 |
| 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳) | 取得することで、税金の控除や公共料金の割引など、さまざまな福祉サービスを受けられる場合がある。 |
これらの制度は、自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。
どのような制度が利用できるか、地域包括支援センターや市区町村の窓口で積極的に相談しましょう。
施設費用と助成制度についてもあわせてご確認ください。
仲間とつながる場所
介護における大きなつらさのひとつが「孤立」です。
同じ悩みや経験を持つ仲間とつながり、気持ちを分かち合うことは、何よりの心の支えになります。
そのような仲間と繋がれる場所として、以下のようなものがあります。
- 認知症カフェ(オレンジカフェ):認知症のご本人やご家族、地域住民、専門職などが気軽に集い、お茶を飲みながら交流できる場所です。情報交換の場であると同時に、ほっと一息つける居場所にもなります。
- 家族会:「認知症の人と家族の会」など、当事者やその家族によって運営されている会です。介護の具体的な悩み相談や、最新の情報を得られるだけでなく、社会への働きかけ(アドボカシー活動)も行っています。
メディカル・ケア・サービスでは、認知症患者家族へのサポートと地域連携の重要性を認識し、全国の施設で地域交流を積極的に行っています。
一人で抱え込まず、ぜひこのような社会資源を活用してみてください。
スポンサーリンク
アルツハイマー型認知症のいざという時に備える住まいと終末期ケアの選択
病状が進行し、在宅での生活が難しくなってきた時、あるいは万が一の時に備えて、将来の住まいやケアについて考えておくことは非常に大切です。
早めに家族で話し合い、本人の意思を尊重した選択ができるように準備しておきましょう。
在宅介護と施設入所のメリット・デメリット
「住み慣れた家で最期まで」と願う方は多いですが、介護者の負担や安全面を考えると、施設入所も有力な選択肢となります。
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご家族の状況に合った選択をすることが重要です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 在宅介護 | ・住み慣れた環境で過ごせる ・本人のペースに合わせやすい ・費用を抑えられる場合がある | ・介護者の身体的・精神的負担が大きい ・24時間の見守りが難しい ・専門的なケアが受けにくい |
| 施設入所 | ・24時間体制で専門的なケアが受けられる ・介護者の負担が軽減される ・他の入居者との交流が生まれる | ・費用が高額になる場合がある ・集団生活になじめない可能性がある ・希望の施設にすぐに入れないことがある |
認知症の在宅介護の方法とポイントや、認知症の方の施設選び:種類とメリット・デメリットを参考に、ご家族にとって最善の選択肢は何かを話し合ってみましょう。
施設の種類と選び方のポイント
認知症の方が利用できる施設には、さまざまな種類があり、それぞれ特徴や費用が異なります。
ご本人の状態や必要なケアに合わせて、適切な施設を選ぶことが大切です。
主な施設の種類は以下の通りです。
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護):認知症の方を対象とした少人数の共同住居。家庭的な雰囲気の中で、スタッフの支援を受けながら自立した生活を送ることを目指します。
- 介護付き有料老人ホーム:24時間体制で介護サービスが提供される施設。レクリエーションやイベントが充実しているところも多いです。
- 特別養護老人ホーム(特養):公的な施設で、費用が比較的安いのが特徴。原則として要介護3以上の方が入居対象で、待機者が多い傾向にあります。
施設を選ぶ際は、費用や立地だけでなく、スタッフの雰囲気、医療体制、看取りへの対応などを実際に見学して確認することが不可欠です。
グループホームの特徴と注目される理由や、施設種類別の比較とサービス内容もぜひ参考にしてください。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)のススメ
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とは、将来の意思決定能力の低下に備え、ご本人が望む医療やケアについて、ご家族や医療・ケアチームと事前に話し合い、共有するプロセスのことです。
「人生会議」とも呼ばれるものです。
認知症が進行すると、ご自身の希望を伝えることが難しくなります。
まだ意思疎通ができるうちに、以下のようなことについて話し合っておくことが、本人の尊厳を守り、家族の後悔を減らすことにつながります。
- どのような場所で最期を迎えたいか。
- 延命治療(人工呼吸器、胃ろうなど)を望むか。
- 痛みや苦痛を和らげるケアを優先してほしいか。
これは一度で決めるものではなく、繰り返し話し合うことが大切です。
メディカル・ケア・サービスの介護現場でも、このACPを重視し、ご本人とご家族の意思を尊重したケアを実践しています。
認知症の最期と家族ができることを参考に、ぜひご家族で「人生会議」を始めてみてください。
スポンサーリンク
まとめ
アルツハイマー型認知症は、誰にでも起こりうる身近な病気ですが、決して希望のない病気ではありません。
この記事を通して、症状の進行から最新の治療法、そして家族としてできることまで、網羅的に解説してきました。
大切なポイントを改めて振り返ります。
- 早期発見・早期対応が鍵:MCIの段階で気づき、対策を始めることで、その後の経過は大きく変わります。
- 予防は可能:生活習慣の改善は、アルツハイマー型認知症の最も有効な予防策のひとつです。
- 治療法は進化している:新薬の登場により、病気の進行そのものを遅らせるという新たな希望が生まれています。
- 一人で抱え込まない:ご家族だけで頑張らず、公的な制度や地域のサポート、専門家を積極的に頼ることが重要です。
この記事が、あなたの抱える不安を和らげ、正しい知識を持って次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
さらに詳しく学びたい方へ
- 症状の理解:認知症の進行段階と対応
- 予防方法:生活習慣からの認知症予防
- 家族の対応:家族向け完全ガイド
健康習慣の継続サポートに
日々の健康管理の一環として、科学的根拠に基づいた記憶力維持をサポートする機能性表示食品の活用も検討してみてください。
プラズマローゲンやDHA・EPAなど、さまざまな研究で注目されている成分を配合した製品を取り揃えています。
健達ねっとは、皆様の健康で充実した生活をサポートし続けてまいります。