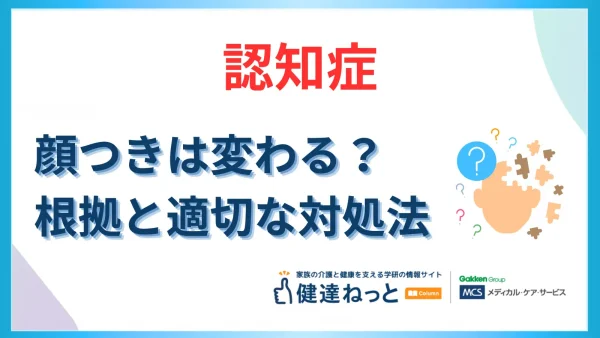- 「最近、親の表情が乏しくなった気がする…」
- 「なんだか不機嫌で、怒りっぽくなったように見える…」
- 「もしかして、これが認知症のサインなのかな…?」
大切なご家族の顔つきの変化に、言葉にできない不安を感じていらっしゃるかもしれません。
その表情が病気のサインかもしれないと思うと、ご本人への心配と、これからどうなってしまうのだろうというお気持ちで、いてもたってもいられないことでしょう。
この記事では、そのような不安を抱えるあなたのために、認知症と顔つきの変化に関する医学的な情報を、介護のプロフェッショナルである「健達ねっと」が分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 顔つきに見られる7つの特徴的なサイン
- 顔つきが変化する5つの医学的根拠
- 変化に気づいた時に家族が取るべき5つのステップ
なぜ顔つきが変わるのか、そしてどう対処すればよいのかを正しく理解することは、冷静に、そして愛情を持ってご家族と向き合うための大切な第一歩です。
早期の気づきと適切な対応が、ご本人とご家族双方の未来をより穏やかなものにする鍵となります。
スポンサーリンク
【結論】認知症になると顔つきは変わる!特徴的な7つのサイン
結論からいうと、認知症の進行に伴って顔つきや表情が変化することは実際にあります。
これはご家族が気づきやすいサインのひとつです。
ここでは、特に特徴的な7つの変化について、ひとつずつ具体的に解説します。
無表情・表情が乏しくなる
認知症のサインとして最もよく見られる変化のひとつが、喜怒哀楽の表情が乏しくなることです。
以前はよく笑っていたのに笑顔が減ったり、テレビ番組や家族との会話に対して反応が薄くなったりします。
このような無表情の状態は、周りからは「無関心になった」と誤解されがちですが、本人の意欲や感情を司る脳の機能が低下しているために起こる症状です。
具体的には、以下のような様子が見られることがあります。
- 以前は好きだったことにも興味を示さなくなった
- 会話をしていても、表情があまり変わらない
- 嬉しいことや楽しいことがあっても、笑顔が見られない
この状態は、単なる気分の問題ではなく、病気の症状である可能性を考えることが重要です。
認知症の他の認知症の初期症状チェックリストとあわせて確認し、総合的に判断しましょう。
目つきが鋭くなる・ぼんやりする
目は感情を表す重要なパーツですが、認知症になると目つきにも変化が現れることがあります。
不安や混乱、あるいは周囲の状況がよく理解できないために、人を睨むような険しい目つきになることがあります。
一方で、注意力が散漫になり、焦点が合わず、一点をぼんやりと見つめるようなうつろな目つきになることも少なくありません。
| 変化の種類 | 見られる状態 | 考えられる心理的背景 |
|---|---|---|
| 鋭い目つき | 人を睨む、疑い深い表情 | 不安感、焦り、混乱、幻視 |
| ぼんやりした目つき | 焦点が合わない、うつろな表情 | 注意力低下、無気力(アパシー) |
これらの目つきの変化は、ご本人の内面で起きている混乱の表れともいえます。
4大認知症それぞれの症状の特徴や適切な対処法を理解し、その背景にある本人の気持ちを汲み取ることが大切です。
口角が下がり、不機嫌に見える
ご本人は特に意識していなくても、口角が下がり、常に不機嫌であるかのような表情に見えることがあります。
これは、表情を作る筋肉(表情筋)の動きが乏しくなったり、気分が落ち込みがちになったりすることが原因で起こります。
周りの人は「怒っているのかな?」と誤解し、話しかけるのをためらってしまうかもしれません。
しかし、ご本人は怒っているわけではなく、病気の症状として表情がそのように見えているだけの場合がほとんどです。
ご家族は、表情だけで判断せず、「何かあったの?」と優しく声をかけるなどの配慮が求められます。
怒っているような険しい表情
認知症、特に血管性認知症では、感情のコントロールが難しくなり、ささいなことで怒り出す「感情失禁」という症状が見られることがあります。
そのため、常に眉間にしわが寄り、怒っているような険しい表情が定着してしまうことがあるのです。
また、自分の思い通りにならないことへのいらだちや、状況が理解できないことへの不安が、怒りの表情として現れることも考えられます。
この表情の変化も、本人の性格が変わったのではなく、脳の機能障害による症状のひとつとして理解することが重要です。
不安そう・悲しそうな表情
記憶力の低下や判断力の衰えにより、ご本人は常に強い不安の中にいることが少なくありません。
「今いる場所が分からない」「次に何をすればよいか分からない」といった混乱が、表情を曇らせ、不安げで悲しそうな顔つきに見せることがあります。
特に、レビー小体型認知症では、気分が落ち込みやすく、暗く悲しそうな表情になる傾向があるといわれています。
ご家族は、その表情の裏にある不安な気持ちに寄り添い、安心できる言葉をかけてあげることが大切です。
感情の起伏がなくなり、反応が薄くなる
以前は感情豊かだった人が、まるで感情の起伏がなくなったかのように、周囲の出来事への反応が薄くなることがあります。
例えば、下記のような変化が見られます。
- お孫さんが遊びに来ても、以前のように喜ばない
- 冗談をいっても笑わない
- 悲しいニュースを見ても、表情が変わらない
これは、感情を生み出す脳の部位の働きが低下することが原因です。
ご家族にとっては寂しい変化かもしれませんが、愛情がなくなったわけではありません。
病気による症状だと理解し、根気強く関わり続けることが、ご本人の心の安定につながります。
年齢以上に老けて見える
認知症になると、表情筋の衰えや全体的な活力の低下から、急に老け込んだような印象を与えることがあります。
無表情でいる時間が長くなると、顔の筋肉が使われなくなり、たるみやしわの原因となります。
また、食事や身だしなみへの関心が薄れることも、見た目の印象に影響するものです。
生き生きとした表情は、その人を若々しく見せる重要な要素です。
ご家族や周りの人が積極的に話しかけ、笑う機会を増やすことが、若々しい表情を保つ手助けとなります。
スポンサーリンク
認知症で顔つきが変化する5つの医学的根拠
ご家族の顔つきが変わってしまうのには、性格の問題ではなく、認知症という病気に起因する医学的な根拠があります。
なぜそのような変化が起こるのか、主な5つの原因を理解することで、より適切な対応が可能になります。
アパシー(自発性・意欲低下)による無関心
アパシーとは、何事に対しても意欲や自発性が低下し、無関心になってしまう状態を指します。
認知症、特に前頭側頭型認知症などでよく見られる症状です。
脳の前頭葉の機能が低下することで、「何かをしたい」という気持ちそのものが湧きにくくなります。
その結果、周囲の出来事や人との交流に興味を失い、表情が乏しくなってしまうのです。
うつ病の「気分が落ち込んで何もできない」状態とは異なり、アパシーは「悲しいわけではないが、何もする気が起きない」という点が特徴です。
アパシーとうつ病の具体的な見分け方のコツを知ることで、より適切なケアにつなげられます。
抑うつ状態による気分の落ち込み
認知症の初期段階では、ご本人が自身の記憶力や能力の低下に気づき、強い不安や喪失感から抑うつ状態に陥ることがあります。
将来への悲観や、できなくなったことへの焦りが、気分の落ち込みを引き起こします。
その結果、表情が暗くなったり、悲しそうな顔つきになったり、笑顔が消えたりするのです。
この抑うつ状態は、認知症の進行を早める要因にもなりうるため、早期の対応が重要です。
周りの人が本人の気持ちに寄り添い、自尊心を傷つけないような関わり方をすることが、気分の安定につながります。
脳の特定部位の萎縮
認知症は、脳の神経細胞が壊れて脳の一部が萎縮していく病気です。
感情や意欲をコントロールする「前頭葉」や、表情の制御に関わる「側坐核」「淡蒼球」といった部位が萎縮すると、表情を豊かに作ることが物理的に難しくなります。
つまり、本人が「笑いたい」「驚きたい」と感じていても、脳からの指令が表情筋までうまく伝わらなくなるのです。
この脳の器質的な変化が、無表情や反応の薄さといった顔つきの変化に直結する根本的な原因といえます。
パーキンソン症状による表情筋の硬直
パーキンソン病やレビー小体型認知症では、体の動きを滑らかにするドーパミンという神経伝達物質が減少します。
これにより、手足の震えや筋肉のこわばりといったパーキンソン症状が現れます。
この症状は顔の筋肉にもおよび、表情筋が硬直して動かしにくくなるのです。
その結果、まばたきが減り、常に同じ表情をしているように見える「仮面様顔貌(かめんようがんぼう)」と呼ばれる特徴的な状態になることがあります。
これは本人の感情とは無関係に現れる身体的な症状です。
コミュニケーション機会の減少による表情筋の衰え
認知症になると、会話についていけなくなったり、言いたい言葉が出てこなかったりすることから、人と話すのが億劫になりがちです。
引きこもりがちになり、社会的な交流が減ると、必然的に表情筋を使う機会も減少します。
筋肉は使わないと衰えるため、表情筋の衰えがさらに無表情を助長するという悪循環に陥ってしまうのです。
| 原因 | 概要 |
|---|---|
| 社会との断絶 | 外出や他者との交流が減る |
| 会話の減少 | コミュニケーションが困難になり、口数が減る |
| 表情筋の不使用 | 笑ったり話したりする機会が減り、筋肉が衰える |
この悪循環を断ち切るには、ご家族や周りの人が意識的にコミュニケーションの機会を作り、ご本人が安心して話せる環境を整えることが非常に重要です。
【認知症の種類別】顔つき・表情の変化の違い
認知症とひとことでいっても、その原因となる病気によっていくつかの種類に分けられます。
種類によって脳の障害される部位が異なるため、顔つきや表情の変化にもそれぞれ特徴が見られます。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、もの忘れから始まる最も一般的なタイプの認知症です。
初期には自身の変化への不安から表情が硬くなることもありますが、進行すると周囲の状況がよく分からなくなり、多幸的で幸せそうな表情を示すことがあるといわれています。
周りから見ると穏やかに見えますが、ご本人は混乱している場合もあるため、表情だけで判断せず、丁寧なコミュニケーションが大切です。
アルツハイマー病の詳しい症状や原因について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、幻視やパーキンソン症状が特徴的な認知症です。
パーキンソン症状の影響で、表情筋がこわばり、まばたきの少ない無表情な「仮面様顔貌」になりやすいという大きな特徴があります。
これは、中脳の黒質という部位が障害され、ドパミンの分泌が阻害されるという神経学的な原因によるものです。
また、気分が落ち込みやすく、暗く悲しそうな表情になる傾向も見られます。
レビー小体型認知症の特徴的な症状について詳しく解説しています。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、人格の変化や社会性の欠如が目立つタイプの認知症です。
感情を司る前頭葉の機能が著しく低下するため、他人の気持ちに共感したり、状況に合わせた表情を作ったりすることが困難になります。
診察室で呼びかけられてもまったく無関心な無表情状態が特徴的といわれ、アパシー(意欲低下)が強く現れます。
前頭側頭型認知症の症状から治療法までの詳細情報はこちらで確認できます。
血管性認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害によって引き起こされる認知症です。
障害された脳の部位によって症状が異なる「まだら認知症」が特徴ですが、感情のコントロールが効かなくなる「感情失禁」が起こりやすいといわれています。
そのため、他の認知症に比べて怒りっぽい表情を示すことが多く、ささいなことで泣き出したり笑い出したりすることもあります。
血管性認知症の原因・症状から治療法まで詳しくはこちらで解説しています。
顔つきの変化は認知症のサイン?他に見られる初期症状
顔つきの変化は、認知症の重要なサインのひとつですが、それだけで判断することはできません。
他の初期症状とあわせて観察することで、より正確に状況を把握することが可能です。
認知症の早期発見のキーポイントについてもあわせてご覧ください。
もの忘れが目立つ
「もの忘れ」は認知症の最も代表的な初期症状です。
単なる加齢によるもの忘れとの違いは、体験したこと自体を丸ごと忘れてしまう点です。
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 加齢によるもの忘れ | 夕食に何を食べたか思い出せない | ヒントがあれば思い出せる |
| 認知症によるもの忘れ | 夕食を食べたこと自体を忘れる | 体験そのものが抜け落ちる |
「さっきも同じことを聞いたでしょ」と指摘すると、ご本人の自尊心を傷つけ、不安を増大させてしまうため注意が必要です。
同じことを何度も話す・尋ねる
もの忘れと関連して、同じことを何度も話したり、尋ねたりするのも特徴的な症状です。
ご本人にとっては、話したり尋ねたりした記憶そのものが抜け落ちているため、毎回初めてのつもりでいます。
ご家族にとっては根気のいる対応になりますが、毎回丁寧に答えてあげることが、ご本人の安心につながります。
会話が嚙み合わない・言葉に詰まる
「あれ」「それ」といった代名詞が多くなったり、物の名前がなかなか出てこなかったりして、会話がスムーズに進まなくなることがあります。
言いたいことが言葉にならず、ご本人ももどかしい思いをしていることが多いです。
話を急かしたりせず、ゆったりとした気持ちで聞いてあげることが大切です。
時間や場所の感覚が不確かになる
今日が何月何日か、今が朝なのか夕方なのかといった、時間に関する感覚(見当識)が不確かになります。
症状が進行すると、今いる場所が自宅なのかどうかが分からなくなったり、季節に合わない服装をしたりすることもあります。
カレンダーや時計を見やすい場所に置くなどの工夫が有効です。
金銭管理や計画的な行動が苦手になる
これまで問題なくできていたお金の計算や、公共料金の支払いなどが難しくなります。
また、買い物で同じものをいくつも買ってきたり、料理の手順が分からなくなったりと、計画を立てて物事を実行する「遂行機能」にも障害が現れます。
家族が認知症かもしれないと感じた時の具体的な向き合い方と対応方法を参考に、さりげなくサポートすることが重要です。
慣れた道で迷う
近所のスーパーへ行く道順が分からなくなったり、いつも利用しているバスの乗り場が分からなくなったりします。
方向感覚が失われることで、外出すること自体に不安を感じ、引きこもりがちになる原因にもなります。
ご家族が一緒に外出するなど、安全を確保しながら行動範囲を狭めない工夫が重要です。
人柄や性格が変わったように見える
穏やかだった人が怒りっぽくなったり、社交的だった人がふさぎ込んだりと、以前とは人柄が変わったように感じられることがあります。
これは、脳の機能低下によって感情のコントロールが難しくなったり、不安から防衛的になったりするために起こる変化です。
決して元々の性格が変わったわけではないことを、ご家族が理解してあげることが何よりも大切です。
家族の顔つきの変化に気づいた時に今日からできる5つのステップ
「もしかして…」と感じても、何から始めればよいのか分からず、戸惑ってしまうのは当然のことです。
しかし、一人で抱え込まず、正しいステップを踏むことで、ご本人とご家族の負担を大きく軽減できます。
ステップ1.まずは本人の変化を否定せず受け止める
ご家族の顔つきの変化やもの忘れに気づいた時、つい「しっかりして!」「前は違ったのに」と否定的な言葉をかけてしまいがちです。
しかし、ご本人が一番の変化に戸惑い、不安を感じています。
まずは、「そうなんだね」と、ご本人が感じていることや置かれている状況を、ありのままに受け止めてあげましょう。
この受容的な姿勢が、ご本人の安心感の土台となります。
ステップ2.不安を煽らず、安心できるコミュニケーションを心がける
認知症のご本人と接する上で最も大切なのは、自尊心を傷つけないことです。
以下のような点を心がけ、安心できる環境を作りましょう。
- 間違いを指摘したり、試すような質問をしたりしない
- ゆっくり、はっきり、穏やかな口調で話す
- 驚かせないように、相手の視界に入ってから話しかける
- スキンシップを交えながら、愛情を伝える
ご家族の笑顔と優しい言葉が、ご本人にとって何よりの薬となります。
ステップ3.一人で抱え込まず、地域包括支援センターや専門医に相談する
認知症の悩みは、家族だけで抱え込むにはあまりにも重い問題です。
お住まいの地域にある「地域包括支援センター」は、高齢者の総合相談窓口です。
保健師や社会福祉士などの専門家が、無料で相談に乗ってくれます。
地域包括支援センターの具体的な役割や相談方法を理解し、早い段階で専門家のサポートを得ることが、介護の負担軽減につながるのです。
ステップ4.受診を嫌がる場合の自然な促し方
ご本人が「自分は認知症ではない」と受診を拒否することはよくあります。
その場合、無理強いは禁物です。
かえって頑なになり、関係が悪化してしまう可能性があります。
「健康診断の一環だよ」「もの忘れの専門の先生に、健康の相談をしに行こう」など、本人のプライドを傷つけない誘い方を工夫しましょう。
地域包括支援センターに相談すれば、かかりつけ医などを通じて自然に受診を促す方法を一緒に考えてくれます。
受診を嫌がる家族への具体的な対応法と介護のポイントも参考にしてみてください。
ステップ5.もの忘れ外来・神経内科・精神科など適切な診療科を選ぶ
認知症の診断は、専門的な知識と検査が必要です。
かかりつけの内科でも相談は可能ですが、できれば認知症専門医がいる医療機関を受診するのが理想です。
| 診療科 | 特徴 |
|---|---|
| もの忘れ外来 | 認知症の早期発見・診断に特化した専門外来 |
| 神経内科 | 脳や神経の病気を専門とし、画像検査などが充実 |
| 精神科・老年科 | 抑うつや妄想などの精神症状への対応に強い |
「もの忘れ外来」は、精神科・脳神経内科などの専門医が設置しているケースが多く、認知症の種類を特定し、適切な治療方針を立てる上で重要な役割を果たします。
失われた表情を取り戻すために!認知症の進行を穏やかにする4つのアプローチ
認知症と診断されても、決して終わりではありません。
適切なケアやアプローチによって、症状の進行を穏やかにし、ご本人らしい表情や笑顔を取り戻すことは可能です。
メディカル・ケア・サービスが実践する「MCSケアモデル」でも、ご本人の望みや想いを表出できる状態を重視し、多くの改善実績を上げています。
コミュニケーションを増やす
最も基本的で重要なアプローチは、ご家族や周りの人々との豊かなコミュニケーションです。
ご本人が安心して自分の気持ちを話せる環境は、心の安定に直結します。
昔の写真を見ながら思い出話をしたり、ご本人が得意だったことについて教えてもらったりするのもよいでしょう。
埼玉県「愛の家グループホーム飯能川寺」では、職員が本人の「役に立ちたい」という気持ちを汲み取り役割を提供したことで、表情が明るくなった事例もあります。
想いを言葉で表出することが、表情の豊かさを取り戻す第一歩です。
表情筋を動かすトレーニングやレクリエーション
使わない筋肉が衰えるのは、表情筋も同じです。
意識的に顔の筋肉を動かすトレーニングや、歌を歌うなどのレクリエーションを取り入れることで、表情を豊かにすることが期待できます。
口周りの筋肉を刺激して表情筋を鍛える効果的な体操方法も有効です。
専門家が考案した、以下のような科学的根拠のあるトレーニングもオススメです。
- 脳活顔ヨガ: 指先を使いながら表情を動かすことで、脳を効果的に活性化させる手法。「くちゃぱーグーパー運動」など、簡単な動きで実践できます。
- ノドトレ: 1回5秒の簡単なトレーニングで嚥下機能を向上させるプログラム。口腔機能が改善されることで、表情筋の動きもよくなります。
趣味や散歩など本人が楽しめる活動を促す
ご本人が「楽しい」「嬉しい」と感じる時間を持つことは、自然な笑顔を引き出す最高の薬です。
昔の趣味を再開したり、天気のよい日に一緒に散歩に出かけたり、ご本人が好きな音楽を聴いたりする時間を作りましょう。
認知症予防に効果的な趣味活動は、表情を豊かにするだけでなく、QOL(生活の質)の向上にもつながります。
三重県「愛の家グループホーム五ヶ所」では、引きこもり状態だった方が、他の利用者との交流や歌を歌うことで自然な笑顔を取り戻した事例が報告されています。
薬物療法・非薬物療法について医師と相談する
認知症の進行を穏やかにしたり、抑うつや不安などの周辺症状を和らげたりするための薬物療法があります。
また、回想法や音楽療法、運動療法といった非薬物療法も、表情の改善に効果的であることが分かっています。
非薬物療法として効果的な脳トレ方法など、さまざまな選択肢があります。
どのような治療法がご本人に合っているのか、必ず専門医とよく相談し、納得した上で進めることが大切です。
また、規則正しい食生活を心がけることも大事です。
栄養を補完する方法としてサプリメントで認知効果を高めることも可能なので、健達ねっとで独自開発している認知機能改善サプリ一覧も取り入れていただければと思います。
まとめ
今回は、認知症による顔つきの変化について、その特徴や医学的な原因、ご家族が取るべきステップを詳しく解説しました。
大切なポイントを振り返りましょう。
- 認知症になると、無表情になったり、目つきが変わったりと、顔つきに変化が現れることがある。
- その原因は、アパシーや脳の萎縮、パーキンソン症状など、医学的な根拠に基づくもの。
- 顔つきの変化は認知症の重要なサインであり、他の初期症状とあわせて観察することが大切。
- 変化に気づいたら、一人で抱え込まず、地域包括支援センターや専門医に相談することが第一歩。
ご家族の顔つきの変化は、あなたへの大切なサインです。
そのサインを見逃さず、早期に適切な対応を始めることが、ご本人らしい穏やかな生活を守り、ご家族の未来を支えることにつながります。
この記事が、不安を抱えるあなたの、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
認知症予防のための具体的な食事療法と運動方法についても、ぜひあわせてご覧ください。