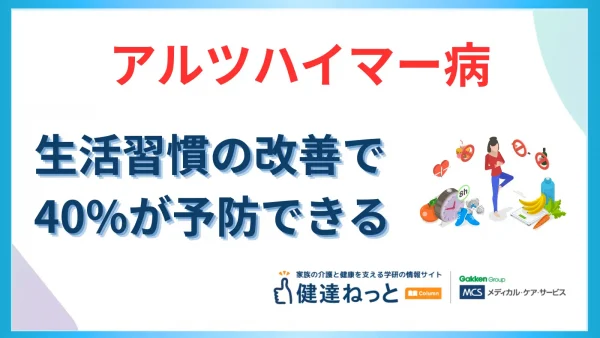- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「もしかして、アルツハイマー型認知症の始まり…?」
- 「もしそうなら、もう治らないの…?」
親の些細な変化に、このような不安を感じていませんか。
大切な家族だからこそ、心配は尽きず、もしものことを考えると夜も眠れないかもしれません。
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
この記事は、そのような不安を抱えるあなたが、絶望の淵で希望の光を見つけるためのものです。
全国300以上の介護施設を運営し、日々認知症ケアの最前線にいる私たちだからこそお伝えできる、最新の治療法とご家族にできることがあります。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
- アルツハイマー型認知症が「完治しない」本当の理由
- 治療の最前線で使われる新薬「レカネマブ」の可能性
- 絶望する前にご家族が今すぐ実践すべき3つのステップ
- 「治らなくても、症状は改善できる」という介護現場の事実
この記事を読み終える頃には、「治らない」という言葉に打ちのめされるのではなく、「これから何ができるか」という前向きな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
スポンサーリンク
アルツハイマー型認知症は治る?【結論】完治しないが共生はできる
アルツハイマー型認知症は治るのか、という問いに対する現在の医学的な結論は、「完治は難しいが、進行を遅らせ、症状とうまく付き合いながら共に生きていく『共生』は可能」です。
絶望的な情報に聞こえるかもしれませんが、治療法やケアは日々進化しており、希望は決して失われていません。
現在のアルツハイマー型認知症治療の限界と可能性
アルツハイマー型認知症は、アミロイドβという異常なたんぱく質が脳に蓄積し、神経細胞が少しずつ壊れていくことで発症する病気です。
アルツハイマー病の新しい治療薬(前編)レカネマブについてによると、このアミロイドβが脳に蓄積すると脳神経細胞が死滅し、脳が萎縮してアルツハイマー型認知症を発症します。
一度壊れてしまった神経細胞は、現在の医学では元に戻せないため、「完治」は難しいとされています。
しかし、治療の目的は「病気の進行を穏やかにし、ご本人らしい生活を一日でも長く続けること」です。
アルツハイマー型認知症は、認知症全体の約67.6%を占める最も多い認知症(認知症のおもな4つの種類・特徴・割合について解説 – 朝日生命)ですが、早期に治療を開始すれば、その進行を遅らせる効果が期待できます。
| 治療の目的 | 具体的なアプローチ |
|---|---|
| 中核症状の進行抑制 | 薬物療法(新薬レカネマブなど)を用いて、記憶障害などの進行を遅らせる。 |
| 行動・心理症状の緩和 | 周囲の環境調整や適切なコミュニケーション(非薬物療法)で、不安や興奮を和らげる。 |
| 生活の質の維持・向上 | 運動やリハビリテーションを取り入れ、身体機能と生活能力を維持する。 |
治療法がないわけでは決してなく、さまざまなアプローチを組み合わせることで、穏やかな生活を維持することは十分に可能です。
認知機能の低下を遅らせることは可能であると理解することが、希望の第一歩となります。
「治る認知症」との違い
「認知症」と診断されても、原因によっては治療で改善するケースもあります。
これを「治る認知症」といい、アルツハイマー型認知症とは原因も治療法も全く異なります。
安易な自己判断はせず、専門医による正確な診断が不可欠です。
代表的な「治る認知症」には、以下のようなものがあります。
| 疾患名 | 原因 | 特徴 | 治療法 |
|---|---|---|---|
| 正常圧水頭症 | 脳脊髄液が脳室に過剰に溜まることで脳を圧迫する | 歩行障害、認知機能障害、尿失禁がみられる | シャント手術で脳脊髄液を排出することで、症状の劇的な改善が期待できる |
| 慢性硬膜下血腫 | 頭部打撲などにより、脳の表面にゆっくりと血液が溜まる | – | 手術で血腫を取り除くことで、認知機能が回復する可能性がある |
| 甲状腺機能低下症 | 甲状腺ホルモンの不足により、心身の活動が低下する | – | ホルモン剤の服用で症状が改善する |
一部の認知症は原因疾患の治療により改善する可能性があるため、「認知症だから」と諦める前に、まずは専門医に相談し、原因を特定することが非常に重要です。
スポンサーリンク
アルツハイマー型認知症治療の最前線!希望の新薬と研究動向
アルツハイマー型認知症の治療は、「治らない」と諦める時代から、進行をコントロールする時代へと大きく変化しています。
特に新薬の登場は、多くの患者さんとご家族にとって大きな希望の光となっています。
ここでは、治療の最前線についてみていきましょう。
進行を27%抑制する新薬「レカネマブ」とは
2023年9月に日本で承認された新薬「レカネマブ(製品名:レケンビ®)」は、アルツハイマー型認知症の進行そのものを抑制する効果が期待される画期的な治療薬です。
この薬は、病気の原因物質であるアミロイドβを脳内から直接取り除くことで、認知機能の低下を緩やかにします。
国立長寿医療研究センターの報告によると、臨床試験(クラリティAD試験)では、プラセボ(偽薬)と比較して全般臨床症状(CDR-SB)の悪化を27%抑制する結果が報告されています。
これは症状の進行をおよそ7.5か月遅らせる効果に相当することが明らかになっているのです。
ただし、この薬は誰でも使用できるわけではなく、いくつかの条件があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象者 | アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症の方 |
| 投与方法 | 2週間に1回、約1時間の点滴投与 |
| 主な副作用 | 脳浮腫や脳出血などのアミロイド関連画像異常(ARIA)。定期的なMRI検査が必要。 |
従来の認知症治療薬とは作用機序が異なり、根本原因に働きかける薬として期待されていますが、効果とリスクを専門医とよく相談することが重要です。
詳しくは、専門医による詳細解説もご参照ください。
治療だけではない!MCIなら回復も目指せる非薬物療法
薬物療法と並行して非常に重要なのが、日常生活における非薬物療法です。
特に、アルツハイマー型認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の段階であれば、生活習慣の改善によって健常な状態に回復する可能性があることも分かっています。
日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」によると、MCIから正常な状態に回復する人の割合は1年で16~41%とされており、早期に適切な対策を講じることで健常な状態に戻る可能性が十分にあることが示されています。
特に効果的とされるのが以下の3つのアプローチです。
- 運動療法:ウォーキングなどの有酸素運動は、脳の血流を促進し、神経細胞を活性化
- 食事療法:野菜や魚、オリーブオイルなどを中心とした地中海式の食事は、認知機能低下のリスクを下げることが報告
- 知的活動・社会参加:趣味や人との交流は、脳によい刺激を与え、認知機能の維持に貢献
非薬物療法の一環として注目されているのが、認知機能に関わる成分の研究です。
特に「プラズマローゲン」は、脳に多く存在するリン脂質の一種で、アルツハイマー型認知症の方では健康な方と比べて著しく減少していることが、複数の研究で報告されています。
健達ねっとでは、この研究成果を元に機能性表示食品として「記憶の王道」(鶏由来プラズマローゲン)や「プラズマローゲンBOOCSスペシャル」(ホタテ由来)などを提供しています。
これらの成分は「言葉を記憶し思い出す」「視覚情報の処理」といった認知機能の維持に関する研究報告があり、40代以降の「最近もの忘れが気になる」という方々からご利用いただいています。
ただし、サプリメントはあくまで日常生活の補助であり、医師の診断や治療の代替になるものではありません。
気になる症状がある場合は、まず専門医療機関での相談を優先することが重要です。
親の異変に気づいたら…アルツハイマー型認知症に絶望する前の3つのステップ
親の「いつもと違う」様子に気づいたとき、不安で頭が真っ白になるかもしれません。
しかし、ここで冷静に行動することが、その後の未来を大きく左右します。
絶望する前に、ご家族が今すぐできることを3つのステップで具体的に解説します。
ステップ1.「いつもの親と違う」変化を見逃さず記録する
医師に相談する際、最も重要な情報となるのが「日常生活での具体的な変化」です。
「もの忘れがひどい」という漠然とした情報だけでは、医師も正確な判断ができません。
認知症の初期症状チェックリストなどを参考に、客観的な事実を記録することが第一歩です。
「健達ねっと」を運営するメディカル・ケア・サービス(MCS)では、287ホーム、3,821名のアルツハイマー型認知症の方への支援データから「MCSケアモデル」を構築してきました。
この中で最も重要なのが「本人を知る」というプロセスです。
MCS式「いつもと違う」を見つける6つの観察ポイントは以下の通りです。
- 食事への関心の変化:好きだった食べ物への反応、食べる量やスピード
- 日常活動の変化:掃除や洗濯などの家事への取り組み方
- 社会との関わりの変化:近所の人とのあいさつ、電話での会話
- 身だしなみの変化:お化粧や服装選びへの関心
- 感情表現の変化:笑顔の頻度、怒りやすさの変化
- 睡眠・生活リズムの変化:夜中の行動、朝の目覚めの様子
私たちは2,000件以上の改善事例を通じて、これらの変化を早期に発見し記録することで、適切な支援方法を見つけられることを実証しています。
記録する際は「いつ・どのような場面で・どのような変化があったか」を具体的にメモし、1週間程度継続して観察することをオススメします。
ステップ2.ひとりで抱え込まず専門家に相談する
「家族だけで何とかしなければ」と抱え込むことは、最も避けるべきです。
認知症は、家族だけで対応するには限界があり、専門家のサポートが不可欠です。
不安や疑問を相談できる場所は、あなたが思うよりも身近に多くあります。
主な相談窓口は以下の通りです。
| 相談窓口 | 特徴 |
|---|---|
| かかりつけ医 | 最も身近な相談相手。必要に応じて専門医を紹介してくれる。 |
| 地域包括支援センター | 市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師や社会福祉士などが無料で相談に応じてくれる。 |
| 認知症疾患医療センター | 認知症の専門的な診断や治療、相談を行う専門医療機関。 |
| もの忘れ外来 | 認知症を専門とする外来。精神科や脳神経内科、老年科などに設置されていることが多い。 |
家族が認知症かもしれないと感じたときは、まずこれらの窓口に電話してみることから始めましょう。
認知症の方への適切な対応方法を知るだけでも、ご家族の心の負担は大きく軽減されます。
医療機関を受診する前に、多くのご家族が「認知症についてよく分からない」「どう接したらいいか分からない」という不安を抱えています。
MCSでは、この不安解決のために全国で認知症教育の出前授業を実施し、これまで29校、3,423名の方々に認知症への理解を深めていただいてきました。
正しい知識は、ご家族の心理的負担を軽減し、よりよい関係性を築く土台となります。
ひとりで悩まず、まずは認知症という病気について理解を深めることから始めてみてください。
ステップ3.受診と診断で正しく理解する
記録と相談で準備が整ったら、次のステップは医療機関の受診です。
しかし、ご本人が受診を嫌がるケースも少なくありません。
その際は「認知症の検査」と直接的に伝えるのではなく、「健康診断の一環」「脳の元気度をチェックしよう」など、本人のプライドを傷つけない言葉を選ぶ工夫が必要です。
医療機関では、以下のような検査を組み合わせて総合的に診断します。
- 問診:本人や家族から、日常生活の変化や症状について詳しく聞き取り
- 神経心理学検査:記憶力や判断力などを評価する質問形式の検査(長谷川式認知症スケールなど)
- 画像検査:MRIやCTで脳の萎縮の程度や脳梗塞の有無などを調査
- 血液検査:他の病気の可能性を除外するために実施
診断を受けることは、終わりではなく「適切なケアの始まり」です。
病名を正しく理解することで、軽度認知障害(MCI)の可能性も含め、その後の最適な治療やサポートにつなげられます。
アルツハイマー型認知症が治ることはないけど、介護のプロのMCSが伝えたいこと
「アルツハイマー型認知症は治らない」。これは医学的な事実です。
しかし、私たちMCSが全国300以上の施設で支援してきた経験から、ひとつ確実にお伝えできることがあります。
それは「症状は改善できる」ということです。
実際の改善事例は以下の通りです。
- 3年間引きこもりから歩行・発語回復した83歳女性:四つんばい移動から押し車歩行まで改善
- 毎日泣いていた方が調理役割で笑顔を取り戻した事例:得意分野発見による生活リズム改善
- 「物がない」不安から信頼関係を築けた事例:不安の本質を理解した支援
これらの改善は、病気の「完治」ではありません。
しかし、本人の持つ力を引き出し、環境を整えることで「その人らしい生活」を取り戻すことは十分できます。
認知症の症状は進行しますが、非薬物療法による改善や家族の支援により、その人らしい生活を長く続けることは可能です。
「治らない」という言葉に絶望するのではなく、「今できること」に焦点を当てることが、ご本人にとってもご家族にとっても、よりよい未来への第一歩なのです。
まとめ
この記事では、アルツハイマー型認知症が「治る」のかという疑問に対し、現在の医学的限界と、新薬やケアの進化がもたらす希望の両面から解説しました。
- 結論:アルツハイマー型認知症の「完治」は現時点では難しいが、進行を遅らせ、症状と「共生」することは可能
- 最新治療:新薬「レカネマブ」は進行を27%抑制する効果が期待されるが、対象者は限定的
- 家族ができること:「いつもと違う変化の記録」「専門家への相談」「早期受診」の3ステップが重要
- 希望:「治らなくても、症状は改善できる」。適切なケアで、その人らしい穏やかな生活を取り戻せる可能性
親の変化に気づいたあなたの不安は、決して無駄ではありません。
それは、大切な家族を守るための第一歩です。
「治らない」という事実に立ち止まるのではなく、この記事で得た知識を元に、「今できること」から始めてみてください。
ひとりで抱え込まず、専門家を頼り、そして何よりも、ご自身の心の健康も大切にするようにしましょう。
その一歩が、必ずや希望の光へとつながっていくはずです。