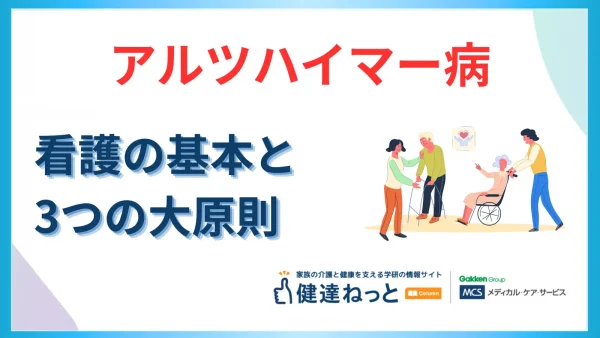- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「さっき言ったことを忘れて、何度も同じ話をするようになった…」
- 「もしかして、アルツハイマー型認知症…?これからどう接していけばいいの?」
親御さんの変化に戸惑い、このような不安や悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
どう対応すればよいのか分からず、ご自身を責めてしまうこともあるかもしれません。
しかし、そのお悩みは決してあなた一人だけのものではありません。
この記事では、認知症ケアの専門家として数多くの現場を支えてきた知見を元に、アルツハイマー型認知症の方への看護の基本を分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下のポイントが分かります。
- 看護の前に知っておくべきアルツハイマー型認知症の基本的な症状
- すぐに実践できる、看護で最も重要な「3つの大原則」
- 具体的な症状別にどう対応すればよいかが分かる看護ケア
- ご家族の心身の負担を軽くするための公的サービスや制度
この記事を最後まで読めば、親御さんとの関わり方についての不安が解消され、穏やかな時間を取り戻すための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
まずは、アルツハイマー型認知症の基礎知識をまとめた記事もご覧いただくと、より理解が深まります。
スポンサーリンク
看護の前に知るべきアルツハイマー型認知症の基本
アルツハイマー型認知症の方への適切な看護を行うためには、まず病気の症状を正しく理解することが不可欠です。
症状は、脳の機能低下によって直接起こる「中核症状」と、本人の性格や環境が影響して現れる「BPSD(行動・心理症状)」の2つに大別されます。
これらは病気の症状であり、本人の性格が変わったわけではないと知ることが、看護の第一歩となります。
記憶や判断力が低下する「中核症状」
中核症状とは、脳の神経細胞が壊れることで直接的に起こる認知機能の障害です。
代表的な症状には、新しいことを覚えられなくなる「記憶障害」や、今日の日付や自分のいる場所が分からなくなる「見当識障害」などがあります。厚生労働省
具体的には、以下のような症状が現れます。
- 記憶障害:少し前にあった出来事(食事の内容など)を忘れる
- 見当識障害:季節に合わない服装をしたり、慣れた道で迷ったりする
- 理解・判断力の低下:考えるのに時間がかかり、一度に複数のことが処理できなくなる
- 実行機能障害:計画を立てて物事を実行することが難しくなる(例:料理の手順が分からなくなる)
これらの症状は脳の機能低下が原因であり、本人を責めても改善しません。
アルツハイマー型認知症の詳しい症状や進行については、こちらで詳しく解説しています。
行動や心理面に現れる「BPSD(行動・心理症状)」
BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、中核症状に本人の性格、環境、人間関係、心理状態などが複雑に絡み合って現れる症状です。
BPSDは、本人が感じている不安や混乱、苦痛などを表現するサインでもあります。(参考:厚生労働省)
| 症状の例 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 不安・焦燥 | 落ち着きがなくなり、イライラしやすくなる |
| うつ状態 | 元気がなくなり、好きだったことにも興味を示さなくなる |
| 妄想 | 「財布を盗られた」と思い込む(物盗られ妄想)など |
| ひとり歩き(徘徊) | 理由もなく家の中を歩き回ったり、外に出て行こうとしたりする |
| 介護抵抗 | 入浴や着替えなどを頑なに拒否する |
【用語について】
近年、「徘徊」という言葉は差別的な意味合いがあるとして、「ひとり歩き」という表現に言い換える動きが広がっています。
厚生労働省も近年、文書や口頭で「ひとり歩き」を使用しており、この記事でも「ひとり歩き」という表現を用います。
これらの症状は、関わり方や環境を整えることで改善する可能性があります。
認知症の行動・心理症状(BPSD)の詳細について、さらに詳しく学ぶことが大切です。
スポンサーリンク
アルツハイマー型認知症の看護で最も重要な3つの原則
アルツハイマー型認知症の方と接する上で、すべての看護ケアの土台となる非常に重要な3つの原則があります。
この原則を心に留めておくだけで、ご本人との関係性が大きく改善し、介護するご家族の精神的な負担も軽減されるでしょう。
本人の自尊心を傷つけない
認知症になっても、感情やプライドは保たれています。
できないことを指摘したり、子ども扱いしたりするような言動は、ご本人の自尊心を深く傷つけ、かえって混乱や反発を招く原因となります。
| NGな対応 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 「さっきも言ったでしょ!」と間違いを指摘する | 「そうでしたね、もう一度確認しましょう」と寄り添う |
| 「それはダメ!」と行動を否定・禁止する | 「こちらはいかがですか?」と代替案を提案する |
| 子どもに話しかけるような言葉遣いをする | 一人の大人として、敬意をもった丁寧な言葉で話す |
常に一人の人間として尊重する姿勢が、信頼関係の基礎となります。
言葉選びは特に大切です。
認知症の方に言ってはいけない言葉と適切な接し方も参考に、日頃のコミュニケーションを見直してみましょう。
本人のペースに合わせて、急かさない
アルツハイマー型認知症の方は、考えたり、行動したりするのに時間がかかるようになります。
介護する側が焦って急かしてしまうと、ご本人はさらに混乱し、不安になってしまいます。
ご本人のペースを尊重し、ゆっくりと見守る姿勢が大切です。
食事や着替えの際に時間がかかっても、「早くして」とは言わずに、静かに待つ余裕を持ちましょう。
ひとつの動作が終わるまで見守り、必要であれば「次はこちらですね」と、さりげなく手助けをするのがよいでしょう。
驚かせず、安心できる環境を作る
認知症の方は、予期せぬ出来事や環境の変化に対して非常に敏感で、不安を感じやすい状態にあります。
そのため、ご本人が安心できる環境を整えることが、穏やかな生活を送る上で非常に重要です。
ポイントは以下の通りです。
- 穏やかなコミュニケーション:後ろから急に声をかけず、視線を合わせて笑顔で話しかける
- 分かりやすい言葉:一度に多くの情報を伝えず、短く具体的な言葉で話す
- 慣れ親しんだ環境:家具の配置をあまり変えず、使い慣れたものをそばに置く
安心感を与えるコミュニケーションが重要です。
認知症の方との効果的なコミュニケーション方法で、具体的な話し方のコツを学びましょう。
【症状別】家族ができるアルツハイマー型認知症の看護ケア
ここでは、ご家族が直面しやすい具体的な症状別に、明日から実践できる看護のポイントを解説します。
3つの基本原則を思い出しながら、それぞれの状況に合わせて対応してみましょう。
もの忘れ(記憶障害)への対応
もの忘れは、アルツハイマー型認知症の最も代表的な症状です。
忘れていること自体を指摘したり、問い詰めたりするのは逆効果です。
ご本人は忘れている自覚がない場合が多く、指摘されることで混乱し、プライドが傷ついてしまいます。
| NGな対応 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 「忘れたの?」と問い詰める | 事実をさりげなく伝える(例:「お昼は先ほどいただきましたよ」) |
| 「しっかりして!」と叱咤激励する | 一緒にスケジュールを確認したり、メモを見たりする |
| 探し物をしている時に「また無くしたの?」と言う | 「何を探していますか?一緒に探しましょう」と声をかける |
忘れたことへの不安な気持ちに寄り添い、一緒に解決しようという姿勢が、ご本人の安心につながります。
記憶障害により同じことを何度も話すのは典型的な症状です。
同じ話を繰り返される時の対処法で、ストレスを溜めない対応方法を学びましょう。
物盗られ妄想への対応
「財布を盗られた」「通帳がない」といった物盗られ妄想は、BPSDのひとつです。
これは、自分でしまった場所を忘れてしまった不安から、「誰かに盗られた」という考えに結びついてしまうために起こります。(参考:日本神経学会)
| NGな対応 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 「誰も盗ってないよ」「勘違いだよ」と真っ向から否定する | まずは「大切なものがなくなって、心配ですね」と本人の不安な気持ちに共感する |
| 犯人探しに同調してしまう | そして、「一緒に探しましょう」と寄り添い、本人の気持ちが落ち着くのを待つ |
物盗られ妄想は認知症でよく見られる症状です。
認知症の被害妄想への種類別対応法で、より詳しい対応方法を確認できます。
ひとり歩きへの対応
ひとり歩きには、ご本人なりの理由や目的があることがほとんどです。
例えば、「家に帰る」「会社に行く」「子どもを迎えに行く」など、過去の習慣や役割に基づいた行動であることが多いといえます。
| NGな対応 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 「どこへ行くの!」と強く制止する | 「どちらへお出かけですか?」と目的を尋ね、話を聞く |
| 部屋に閉じ込める | 一緒に少し歩いて気分転換を促し、落ち着いたら家に戻るよう誘導する |
| 目的を否定する | 本人の話に耳を傾け、「そうでしたね」と気持ちを受け止める |
無理に引き留めようとすると、不安や混乱が強まることがあります。
まずは目的を聞き、気持ちを受け止めることが大切です。
安全確保のために、GPSを持ってもらったり、近所の人に事情を話しておいたりするなどの対策も有効です。
ひとり歩き以外にもさまざまな症状への対応が必要となります。
認知症の症状一覧と適切な対処法で包括的な対応方法を学びましょう。
看護拒否への対応
入浴や着替え、服薬などを頑なに拒否することも、BPSDのひとつです。
その背景には、「入浴が面倒」「なぜ薬を飲まないといけないのか分からない」「裸になるのが恥ずかしい」など、さまざまな理由が隠されています。
| NGな対応 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 「わがまま言わないで!」と無理強いする | 一旦時間をおいて、気分が変わった頃に再度誘ってみる |
| 理由も説明せずに行おうとする | 「お風呂に入ってさっぱりすると気持ちがいいですよ」とメリットを伝える |
| ひとつの方法に固執する | 「今日は足湯だけにしませんか?」など、代替案を提案する |
なぜ拒否するのか、その理由を探ろうとすることが大切です。
ご本人の気持ちを尊重し、納得できるような声かけや工夫を試みましょう。
看護拒否が激しい場合の対応も必要です。
認知症による攻撃的言動への対応法で、困難なケースへの対処法を確認しましょう。
看護の負担を減らすために利用できるサービス・制度
アルツハイマー型認知症の看護は、ご家族だけで抱え込む必要はありません。
むしろ、専門家や公的なサービスを積極的に活用することが、ご本人にとってもご家族にとっても、よりよい生活につながります。
ここでは、代表的なサービス・制度をご紹介します。
専門的なケアを受けられる「訪問看護」
訪問看護とは、看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
健康状態のチェックや服薬管理、BPSDへの対応、ご家族からの介護相談など、幅広いサポートを受けることが可能です。
訪問看護を利用するメリット
- 専門家による客観的な健康管理
ご家族では「年のせいかな?」と見過ごしがちな体調の変化も、看護師が定期的なバイタルチェックや問診を行うことで、病気の早期発見や重症化予防につながります。 - BPSD(行動・心理症状)への適切な対応
ご家族だけでは対応が難しい妄想や興奮状態に対しても、専門的な知識に基づいてご本人の気持ちを落ち着かせたり、原因を探ったりする支援が受けられます。 - 家族の介護負担(精神的・身体的)の軽減
「この対応で合っているのだろうか」という日々の不安や悩みを専門家に相談できるだけで、心の負担は大きく軽減されます。
また、入浴介助などの身体的なケアを一部任せることも可能です。 - 医療機関とのスムーズな連携
主治医と密に連携を取り、ご本人の状態を正確に報告してくれるため、診察時にも適切な治療方針を立てやすくなります。
訪問看護を利用するデメリット
- 費用負担の発生
介護保険や医療保険が適用されますが、一定の自己負担が必要です。
利用頻度やサービス内容によって月々の費用は変動するため、事前にケアマネジャーとよく相談することが重要です。
費用の自己負担割合は、介護保険では1割〜3割(所得に応じて)、医療保険では1割〜3割となります。(参考:厚生労働省) - 看護師との相性問題
人と人との関わりなので、どうしても担当の看護師とご本人やご家族との相性が合わないケースもあります。
違和感があれば、事業所に相談して担当者の変更を依頼することも可能です。 - 24時間対応の限界
24時間対応の事業所もありますが、緊急時に電話をしても、すぐに駆けつけられるわけではありません。
24時間対応体制加算がある場合でも、あくまで電話相談や必要時の緊急訪問が基本となることを理解しておく必要があります。
24時間対応体制加算の費用は月額約6,520円〜6,800円(1割負担の場合約650円〜680円)が発生します。
サービス選択に迷う場合は、認知症の方に対する訪問介護と訪問看護の違いを参考に、最適なサービスを選びましょう。
気軽に相談できる「地域包括支援センター」
「どこに相談すればいいか分からない」という場合に、最初の窓口となるのが「地域包括支援センター」です。
高齢者のための総合相談窓口で、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が配置されています。
主な役割は以下の通りです。
- 総合相談:介護に関する悩みや相談に幅広く対応
- 情報提供:必要なサービスや制度についての情報を提供
- 関係機関との連携:病院や介護サービス事業者など、適切な機関へつなぐ
- 要介護認定の申請支援:介護保険サービスを利用するための申請手続きをサポート
相談は無料ですので、まずはお住まいの地域のセンターに電話してみることをオススメします。
また、厚生労働省の情報も参考にするとよいでしょう。
経済的負担を軽減する「介護保険制度」
介護保険制度は、介護が必要になった方を社会全体で支える仕組みです。
市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行い、認定を受けることで、費用の1割〜3割の自己負担でさまざまな介護サービスを利用できます。
利用できるサービスの例は以下の通りです。
| サービスの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 在宅サービス | 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、デイサービス、ショートステイなど |
| 施設サービス | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど |
| その他 | 福祉用具のレンタル・購入、住宅改修費の助成など |
介護保険を活用した訪問看護について、介護保険の訪問看護サービスの詳細で利用条件や料金を確認できます。
※参考:介護保険制度の概要|厚生労働省
まとめ
この記事では、アルツハイマー型認知症の看護について、基本的な知識から具体的な対応法、そしてご家族の負担を軽減するためのサービスまで幅広く解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 看護の基本は症状の理解から:もの忘れやBPSDは病気の症状であり、本人のせいではないと理解することが大切
- 3つの原則を忘れずに:「自尊心を傷つけない」「ペースを合わせる」「安心できる環境を作る」ことが、信頼関係の土台となる
- 症状別に対応法を変える:もの忘れや妄想など、それぞれのBPSDの背景にある本人の気持ちを汲み取ることが、適切なケアにつながる
- 一人で抱え込まない:訪問看護や地域包括支援センターなど、利用できるサービスは多数ある。積極的に専門家や社会の力を借りる
アルツハイマー型認知症の看護は、時に大変なこともありますが、正しい知識を持つことで、ご本人との穏やかな時間を取り戻すことは可能です。
決して一人で悩まず、まずは地域包括支援センターなどの身近な窓口に相談することから始めてみてください。