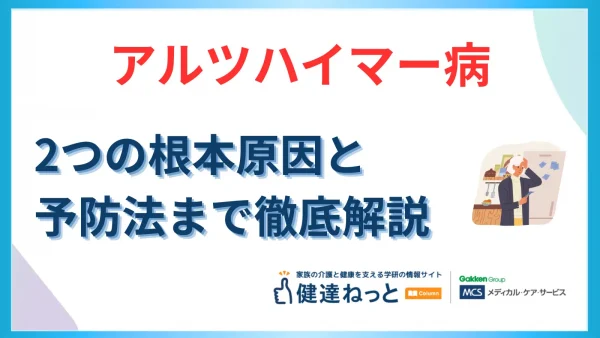- 「最近、自分や家族のもの忘れが増えてきた気がする…」
- 「親の様子が少しおかしいけど、年のせいなのかな?」
- 「アルツハイマー病の確実な原因や予防法が知りたい」
このような、漠然とした不安を感じていませんか?
アルツハイマー病は、誰にとっても無関係ではない病気です。
だからこそ、将来への不安や、大切な家族との関係が変わってしまうかもしれないという恐怖を感じるのは、ごく自然なことです。
この記事では、そのような不安を解消し、未来への具体的な一歩を踏み出すために、アルツハイマー病の根本原因から最新の治療法まで、科学的根拠に基づいて分かりやすく解説します。
この記事を読めば、以下のポイントが明確になります。
- アルツハイマー病を引き起こす脳内の2大原因物質
- 発症リスクを高める可能性のある14の危険因子
- 原因から分かる、今日から実践できる具体的な予防法
- 病気の進行を抑える最新の治療薬
正しい知識は、不安を希望に変える力になります。
この記事を通して、あなたと大切なご家族の健康な未来を守るための、確かな情報を手に入れてください。
スポンサーリンク
アルツハイマー病の原因は2つの物質
アルツハイマー病の根本的な原因は、脳の中に特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が破壊されてしまうことにあると考えられています。
ここでは、その原因となる2つの代表的な物質について詳しく解説します。
アミロイドβ(Aβ)の蓄積と「老人斑」
アルツハイマー病の最初の引き金となるのが、「アミロイドβ(ベータ)」というたんぱく質の蓄積です。
アミロイドβは、本来、神経の成長や修復を助けるたんぱく質から作られる断片で、健康な人の脳にも存在します。
通常は脳内のゴミとしてすぐに分解・排出されますが、加齢などが原因で分解・排出のバランスが崩れると、脳内に蓄積し始めます。
この蓄積は、認知症を発症する20年以上も前から始まるといわれています。
国立長寿医療研究センターの研究によると、アミロイドβが塊になった「老人斑」は、神経細胞同士のつながりを傷つけ、最終的に神経細胞を死なせてしまうのです。
その結果、脳が萎縮し、アルツハイマー病が発症するのです。
アルツハイマー病は脳にどんな影響があるの?効果的な脳トレ方法も解説では、より詳しいメカニズムを解説しています。
当社の介護施設で実践する「MCS版自立支援ケア」では、このような脳内変化で生じる症状に対し、科学的根拠に基づくケアで改善を目指しています。
タウたんぱく質の異常と「神経原線維変化」
アミロイドβの蓄積に続いて、神経細胞内で起こるのが「タウたんぱく質」の異常です。
タウたんぱく質は、神経細胞の中で、物質を運ぶレールの役割を果たす「微小管」を安定させる働きを持っています。
しかし、何らかの原因でタウたんぱく質が過剰にリン酸化されると、異常なタウたんぱく質同士が絡まり合い、「神経原線維変化」と呼ばれる線維の塊を形成します。
この神経原線維変化が細胞内に蓄積すると、栄養などが運ばれなくなり、最終的に神経細胞そのものが死んでしまうのです。
アミロイドβが外からじわじわと神経細胞を攻撃するのに対し、タウたんぱく質は細胞の内部から崩壊を引き起こすイメージです。
このように、アミロイドβの蓄積とタウたんぱく質の異常という2つの変化が、ドミノ倒しのように連鎖して脳の機能を損なっていくのが、アルツハイマー病の基本的なメカニズムです。
アルツハイマー病の原因物質について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
スポンサーリンク
アルツハイマー病になりやすい?原因となりうる危険因子
アルツハイマー病は、直接的な原因物質だけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症リスクが高まります。
ここでは、自分で変えることが難しい因子と、生活習慣の見直しで改善できる可能性のある因子に分けて解説します。
修正できない危険因子
アルツハイマー病の発症リスクには、努力では変えることのできない生物学的な要因も関わっています。
これらの因子について正しく理解し、過度に不安になることなく、変えられる部分に目を向けることが大切です。
年齢
アルツハイマー病の最も大きな危険因子は「加齢」です。
年齢を重ねるにつれて発症しやすくなるのは、長年の間に脳内でアミロイドβを分解・排出する能力が低下し、蓄積が進みやすくなるためと考えられています。
実際に、厚生労働省の最新統計によると、65歳以上の高齢者における認知症有病率は12.3%であり、85歳以上では約30%が認知症となっています。
ただし、加齢はあくまでリスクのひとつであり、「高齢=アルツハイマー病」ではありません。
年齢という変えられない事実を受け入れ、他のリスク因子をいかに管理するかが重要になります。
年齢と認知症発症の詳しい関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺伝的要因
アルツハイマー病の発症には、遺伝的な要因が関与することもあります。
特に、65歳未満で発症する「若年性アルツハイマー病」の一部である「家族性アルツハイマー病」は、特定の遺伝子変異が直接的な原因となり、高い確率で子孫に受け継がれます。
また、「APOE4(アポリポたんぱく質E4)」という遺伝子の型を持つ人は、持たない人と比べて発症リスクが数倍高まることが分かっているのです。
しかし、これらの遺伝的要因を持つ人が必ず発症するわけではありません。
遺伝は数ある危険因子のひとつに過ぎず、他の生活習慣などの要因も大きく影響します。
ご家族にアルツハイマー病の方がいて心配な場合は、専門医に相談することも選択肢のひとつです。
修正の可能性がある危険因子
アルツハイマー病のリスクを高める要因の多くは、日々の生活習慣と深く関わっています。
イギリスの医学誌「ランセット」の2024年報告では、14のリスク因子を管理することで認知症の45%は予防できる可能性があると指摘されています。
ひとつずつ見ていきましょう。
高血圧
中年期の高血圧は、アルツハイマー病の重要な危険因子です。
血圧が高い状態が続くと、脳の細い血管が常に張り詰めた状態になり、少しずつダメージが蓄積します。
これにより血管の壁が硬くなる動脈硬化が進み、脳の血流が悪化。
神経細胞へ十分な酸素や栄養が届かなくなり、アミロイドβの排出能力も低下すると考えられています。
当社のケアモデルでも、フィジカルサインとして血圧などのデータを継続的に把握し、医療と連携した適切な管理を重視しています。
定期的な血圧測定と、必要に応じた治療が脳を守ることにつながるのです。
WHO推奨の高血圧管理方法も参考に、早期からの対策を心がけましょう。
糖尿病
国立長寿医療研究センターの研究によると、糖尿病はアルツハイマー型認知症の発症リスクを約2.1倍に高めることが明らかになっています。
高血糖の状態は、脳の血管にダメージを与えるだけでなく、「インスリン抵抗性」という状態を引き起こすのです。
インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、アミロイドβの分解にも関わっています。
インスリンが効きにくくなると、アミロイドβが脳内に溜まりやすくなってしまうのです。
また、高血糖は体内で「糖化」という老化現象を促進し、神経細胞にダメージを与えます。
血糖値のコントロールは、生活習慣病予防だけでなく、認知症予防の観点からも非常に重要です。
脂質異常症(高コレステロール)
血液中の悪玉(LDL)コレステロール値が高い状態も、危険因子のひとつです。
悪玉コレステロールは、血管の壁に蓄積して動脈硬化を引き起こし、脳の血流を悪化させます。
また、近年の研究では、コレステロールの代謝異常が、脳内でのアミロイドβの産生を促進する可能性も指摘されています。
食生活の見直しや適度な運動によってコレステロール値を適正に保つことは、全身の血管の健康を守り、ひいては脳の健康維持にもつながるのです。
健康診断などで数値を指摘された場合は、放置せずに医師に相談することが大切です。
肥満(中年期)
特に40~50代の中年期における肥満は、その後のアルツハイマー病発症リスクを高めることが分かっています。
肥満は、これまで述べてきた高血圧、糖尿病、脂質異常症といったさまざまな生活習慣病の温床となります。
これらの疾患が複合的に脳の血管や神経細胞に悪影響を及ぼし、アルツハイマー病の引き金になると考えられているのです。
また、脂肪細胞から分泌される炎症物質が、脳に慢性的な炎症を引き起こすこともリスクを高める一因とされています。
適正体重を維持することは、将来の認知症リスクを低減するための重要なステップといえます。
喫煙
喫煙習慣は、アルツハイマー病を含む多くの認知症のリスクを大幅に高めます。
タバコに含まれるニコチンや数多くの有害物質は、血管を収縮させて血圧を上げ、動脈硬化を促進するのです。
これにより脳の血流が悪化するだけでなく、体内に「酸化ストレス」というダメージを与え、神経細胞を直接傷つけます。
久山町研究では、喫煙者は非喫煙者に比べてアルツハイマー型認知症のリスクが約1.4~1.8倍高まると報告されています。
禁煙は、何歳から始めても遅すぎることはありません。
ご自身の健康、そして脳の健康のために、禁煙に取り組むことが強く推奨されます。
過度の飲酒
長期間にわたる過度な飲酒は、アルツハイマー病のリスクを高めることが知られています。
アルコールそのものや、その代謝産物であるアセトアルデヒドには、神経細胞に対する毒性があります。
大量の飲酒は脳を萎縮させ、記憶障害などを引き起こす「アルコール性認知症」の原因にもなるのです。
また、過度な飲酒は、ビタミンB1などの脳の働きに必要な栄養素の吸収を妨げます。
適度な飲酒であればリスクは低いとされていますが、「百薬の長」という言葉を過信せず、休肝日を設けるなど、節度ある楽しみ方を心がけることが重要です。
運動不足
体を動かす習慣がないことも、アルツハイマー病の間接的な原因となります。
運動不足は、肥満や生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、脳の血流を低下させます。
脳の血流が悪くなると、神経細胞の活動が鈍り、アミロイドβなどの老廃物も排出されにくくなるのです。
逆に、定期的な運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の成長を促す「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質の分泌を増やすことが分かっています。
研究によると、1日5000歩・7.5分の早歩きで認知症予防効果が期待されるため、日常生活の中に運動習慣を取り入れることが大切です。
社会的孤立・うつ病
人との交流が乏しい「社会的孤立」や、気分の落ち込みが続く「うつ病」も、アルツハイマー病のリスク因子です。
人との会話は、相手の話を理解し、記憶し、自分の意見を組み立てて話すという、脳のさまざまな機能を使う高度な知的活動です。
孤立によってこのような刺激が減ると、脳の機能が低下しやすくなります。
当社の施設でも、人とのつながりがご本人様の表情や活動性をいかに向上させるかを実感しています。
また、うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスを崩したり、ストレスホルモンを増加させたりすることで、記憶を司る海馬にダメージを与える可能性があるのです。
心の健康を保つことも、脳の健康にとって不可欠です。
難聴
聞き取りにくさを放置することも、認知症のリスクを高めることが最新の研究で分かっています。
ランセットの2024年報告では、難聴は修正可能な危険因子の中で最大のリスクとされています。
耳からの音の刺激が減ることで、脳の聴覚に関連する部分の活動が低下し、脳全体の機能低下につながると考えられているのです。
また、会話が聞き取れないことでコミュニケーションを避けるようになり、結果として社会的孤立に陥りやすいことも大きな要因です。
当社の施設でも、補聴器を適切に使用することで、ご本人様の会話が増え、表情が明るくなった事例が数多くあります。
「年のせい」と諦めずに、聞こえに問題を感じたら耳鼻咽喉科に相談することが重要です。
頭部外傷
転倒や事故などで頭に強い衝撃を受けることも、将来のアルツハイマー病リスクを高める可能性があります。
頭部外傷は、脳に直接的なダメージを与えるだけでなく、その修復過程で炎症を引き起こします。
この脳内の慢性的な炎症が、アミロイドβの蓄積やタウたんぱく質の異常を促進するのではないかと考えられているのです。
特に、意識消失を伴うような重度の頭部外傷や、ボクシングなど繰り返し頭部に衝撃を受けるスポーツの経験は、リスクを高めるとされています。
日常生活での転倒予防や、自転車乗車時のヘルメット着用など、頭を守る意識が大切です。
大気汚染
PM2.5などの大気汚染物質に長期間さらされることも、危険因子のひとつとして注目されています。
呼吸によって体内に取り込まれた微小な汚染物質が、血液を通って脳に到達し、神経炎症や酸化ストレスを引き起こす可能性が指摘されています。
これにより、神経細胞がダメージを受けたり、アルツハイマー病の原因物質が蓄積しやすくなったりすると考えられているのです。
個人で対策するのは難しい問題ですが、大気汚染が深刻な日は不要な外出を避ける、空気清浄機を活用するなどの工夫が考えられます。
環境問題が、私たちの脳の健康にも直結しているのです。
教育歴の不足
若い頃に教育を受けた期間が短いことも、統計的にアルツハイマー病のリスクと関連付けられています。
これは、長期間の教育を通じて得られる知的活動の習慣が、脳の神経ネットワークを密にし、「認知予備能(コグニティブ・リザーブ)」と呼ばれる脳の貯蓄を増やすためと考えられています。
認知予備能が高いと、加齢や病気によって脳に多少のダメージが生じても、残った神経ネットワークで機能を補え、症状が現れにくいのです。
重要なのは、大人になってからの学び直しや、知的好奇心を持ち続けることでも認知予備能は高められるということです。
生涯にわたる学習が、脳の健康を支えます。
視力低下
2024年のランセット報告で新たに追加された危険因子が視力低下です。
視力の低下により視覚情報が減少すると、脳の視覚野の活動が低下し、脳全体の認知機能に影響を与える可能性が指摘されています。
また、視力低下により外出や社会参加が減り、身体活動の低下や社会的孤立につながることも、間接的なリスク要因となります。
定期的な眼科受診や適切な視力矯正、白内障などの治療可能な疾患への対処が重要です。
これらの原因因子を下げるアルツハイマー病の予防法
アルツハイマー病の原因や危険因子が分かってきたことで、具体的な予防法も見えてきました。
当社が全国の施設で3,821名以上の改善実績を持つ「MCS版自立支援ケア」の科学的アプローチを元に、今日からできる予防法を紹介します。
【食事】予防につながる食べ物・避けたい食べ物
毎日の食事は、脳の健康を直接左右する重要な要素です。
特定の食品だけを食べるのではなく、バランスのよい食事を心がけることが基本となります。
当社のケアモデルでは、科学的根拠に基づき、以下の栄養管理を実践しています。
- たんぱく質約80g:筋肉や血液の元となり、身体活動を支える
- 水分約1,800ml:脱水は認知機能低下の大きな原因。脳の覚醒レベルを保つ
食事の内容としては、地中海食やDASH食(高血圧予防食)が認知機能の維持に効果的とされています。
具体的には、以下のような食品を積極的に摂ることがオススメです。
認知症予防に効果的な食べ物や、避けるべき食べ物について、さらに詳しく解説した記事も参考にしてみてください。
- 青魚:DHAやEPAが豊富で、血液をサラサラにする
- 野菜・果物:抗酸化作用で、細胞の老化を防ぐ
- 大豆製品:コレステロールを下げる効果が期待できる
健達ショップで扱う「ハルと思い出めぐりごはん」は、管理栄養士が高齢者向けの栄養と食べやすさを考えて監修したレシピ本で、食事による予防を実践する上で大変勉強になるでしょう。
【運動】どのような運動をどれくらい行うべきか
運動は、脳の血流を改善し、神経細胞を活性化させるホルモンの分泌を促すなど、多くのメリットがあります。
アミロイドβを分解する酵素を増やす効果も期待されているのです。
どのような運動がよいかというと、息が少し弾むくらいの有酸素運動が特に推奨されています。
研究によると、1日5000歩・7.5分の早歩きで認知症予防に効果が期待されるというデータもあります。
当社の施設では、独自の身体機能評価「SIDE」スケールに基づき、一人ひとりに合った個別の運動プログラムを提供しています。
無理なく継続できることが最も重要ですので、まずは散歩や軽い体操から始めてみましょう。
認知症予防に効果的な運動方法については、こちらの記事もご覧ください。
【知的活動・社会参加】脳への刺激を保つ
脳は使わなければ衰えていきます。
新しいことに挑戦したり、趣味に没頭したりすることは、脳のさまざまな領域を使い、認知機能を維持する上で非常に重要です。
これを「認知予備能(コグニティブ・リザーブ)」を高めるといいます。
また、人とのコミュニケーションは、相手の話を理解し、自分の考えをまとめて話すという、高度な知的活動です。
社会的な孤立は認知症の大きなリスク因子であり、積極的に人と交流する機会を持つことが大切です。
当社が実施している小中学生向けの「認知症教育の出前授業」では、3,749名の生徒のうち92%が「認知症がよいイメージに変わった」と回答しました。
これは、世代を超えた交流が、社会全体の認知症への理解を深め、当事者が安心して社会参加できる環境作りにつながることを示しています。
アルツハイマー病の最新治療法
アルツハイマー病の治療は、近年大きな転換期を迎えています。
これまでの症状を和らげる治療に加え、病気の進行そのものを抑える新しいタイプの薬が登場し、注目されています。
進行を遅らせる薬(疾患修飾薬)
疾患修飾薬は、アルツハイマー病の根本原因である脳内のアミロイドβに直接働きかけ、除去することで病気の進行を抑制する画期的な薬です。
2023年9月に承認された「レカネマブ(レケンビ®)」と、2024年9月に承認された「ドナネマブ(ケサンラ®)」が代表的です。
これらの薬は、MCI(軽度認知障害)や軽度のアルツハイマー病といった早期の段階でのみ使用できます。
レカネマブの臨床試験では、18か月間の投与で認知機能の低下を27%抑制し、進行を5.3か月遅らせる効果が示されました。
薬価は年間約300万円と高額ですが、公的医療保険が適用されます。
これらの新薬については、最新の治療法情報で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
症状を緩和する薬(症状改善薬)
現在、アルツハイマー病の治療で中心的に使われているのが、症状の進行を一時的に緩やかにする薬です。
これらは神経伝達物質の働きを調整することで、記憶障害や見当識障害などの中核症状を改善する効果が期待できます。
厚生労働省資料によると、代表的な薬には以下の4種類があります。
- ドネペジル(アリセプト®)
- ガランタミン(レミニール®)
- リバスチグミン(イクセロンパッチ®、リバスタッチパッチ®)
- メマンチン(メマリー®)
これらの薬は病気を根本的に治すものではありませんが、ご本人様やご家族の生活の質を維持する上で重要な役割を果たします。
基本薬一覧と効果・副作用を解説した記事もございます。
薬を使わない治療法(非薬物療法)
薬物療法と並行して非常に重要なのが、薬を使わないアプローチである非薬物療法です。
これには運動療法、回想法、音楽療法などがあり、精神的な安定や残存機能の維持を目指します。
当社が実践する「MCSケアモデル」は、この非薬物療法の集大成ともいえるアプローチです。
以下の「12の解決方法」に基づき、ご本人様の状態を総合的に評価し、ケアを提供します。
- 人・つながり
- コミュニケーション
- 生活空間
- 靴道具
- 口腔機能
- 運動
- 姿勢
- フィジカルサイン
- 水分
- 栄養
- 薬
この包括的なケアにより、薬に依存しない生活を目指し、実際に症状が改善して医師への減薬提案に至ったケースも多数あります。
アルツハイマーの原因に関するよくある疑問
ここでは、アルツハイマー病の原因について、多くの方が抱く疑問にお答えします。
日々の不安を解消するため、正しい知識を身につけましょう。
若年性アルツハイマーの原因は?
若年性アルツハイマーは、65歳未満で発症するアルツハイマー病を指します。
基本的な原因メカニズム(アミロイドβとタウの蓄積)は高齢者と同じですが、遺伝的要因が強く関与するケースが多いのが特徴です。
特に、原因遺伝子が特定されている「家族性アルツハイマー病」は、若年で発症するケースが大半を占めます。
詳しくは若年性認知症の症状や特徴・予防方法で解説しています。
アルツハイマーになりやすい人の特徴はある?
「このような性格の人がなりやすい」といった、医学的に証明された特徴はありません。
しかし、これまでの研究から、認知症になりにくい人の生活習慣は見えてきています。
健達ショップで扱う認知症専門医・長田乾医師の著書「認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣」によると、社交的、知的好奇心が旺盛、運動習慣がある、といった特徴を持つ人は、脳の「認知予備能」が高く、認知症になりにくい傾向があると解説されています。
これは、日々の習慣が脳の健康に大きく影響することを示しているのです。
ストレスがアルツハイマーの直接の原因になることはある?
ストレスがアルツハイマー病の直接的な原因になるという、明確な証拠はまだありません。
しかし、慢性的なストレスは、高血圧やうつ病といった危険因子を引き起こす可能性があります。
また、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されると、記憶を司る「海馬」を傷つけることも分かっています。
間接的にリスクを高める可能性はあるため、上手にストレスを管理することが大切です。
ストレスとアルツハイマー病の関係性については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
この記事では、アルツハイマー病の2つの根本原因から、発症リスクを高める危険因子、そして原因から分かる具体的な予防法までを詳しく解説しました。
アルツハイマー病は、アミロイドβとタウたんぱく質という異常なたんぱく質が脳に蓄積することで発症します。
そして、その発症には、高血圧や糖尿病、運動不足、社会的孤立といった、日々の生活習慣が深く関わっています。
しかし、裏を返せば、これらの危険因子を管理し、食事や運動、知的活動といった習慣を見直すことで、発症リスクを大きく下げられる可能性があるということです。
最新の治療薬も登場し、アルツハイマー病は「不治の病」から「進行を遅らせ、共に生きる病気」へと変わりつつあります。
最も大切なのは、不安を一人で抱え込まず、正しい知識を持って今日から行動を起こすことです。
この記事が、あなたと大切な方の未来を守るための、確かな一歩となれば幸いです。