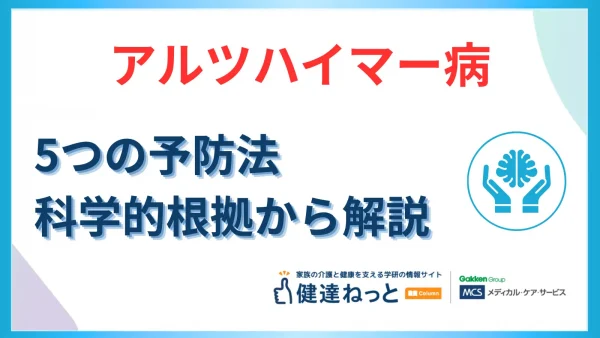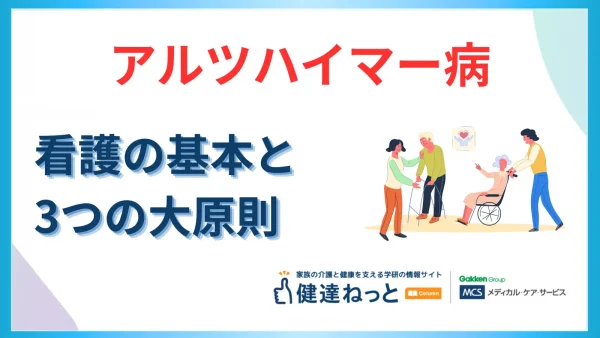- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「もしかして、アルツハイマー病の始まりかもしれない…」
- 「自分も将来なるのではないかと、漠然とした不安を感じる…」
このような、ご両親やご自身の将来に対する不安を感じていませんか。
大切な家族との穏やかで幸せな関係を、これからもずっと守りたいと願うのは自然なことです。
その漠然とした不安、この記事が「未来への希望」に変えるお手伝いをします。
アルツハイマー病は、誰にでも起こりうる身近な病気ですが、決してただ怖がるだけの対象ではありません。
最新の研究により、40代・50代からの生活習慣の改善が、発症リスクを大きく左右することが分かってきました。
この記事では、以下のポイントを専門的な知見から分かりやすく解説します。
- 科学的根拠に基づいた、今日から始められる5つの予防法
- 単なるもの忘れとアルツハイマー病の決定的な違い
- もしもの時に家族ができることや利用できる公的制度
この記事を最後まで読めば、アルツハイマー病に対する正しい知識が身につき、あなたと大切な家族の未来を守るための具体的な一歩を踏み出せるようになります。
スポンサーリンク
予防の前に知っておきたいアルツハイマー病の予備知識
アルツハイマー病の予防を効果的に進めるには、まず相手を正しく知ることが不可欠です。
ここでは、単なる加齢によるもの忘れとの違いや、発症のリスク、注意すべき初期症状について解説します。
正しい知識は、漠然とした不安を解消し、冷静な第一歩を踏み出すための羅針盤となります。
単なるもの忘れとの違い
アルツハイマー病によるもの忘れは、年齢を重ねることで生じる自然なもの忘れとは、その質が根本的に異なります。
加齢によるもの忘れは、体験したことの「一部」を思い出せない状態です。
ヒントがあれば思い出せることが多く、もの忘れに対する自覚もあります。
一方で、アルツハイマー病によるもの忘れは、脳の神経細胞が壊れることによって起こるため、体験した「こと自体」を忘れてしまいます。
そのため、ヒントを与えられても思い出すのが難しく、もの忘れの自覚がないケースも少なくありません。
厚生労働省の資料によると、認知症によるもの忘れの特徴として「出来事の記憶(エピソード記憶)の障害が目立ち、体験したすべてを忘れてしまう」点が挙げられています。
具体的な違いを以下の表にまとめました。
| 加齢によるもの忘れ | アルツハイマー病によるもの忘れ | |
|---|---|---|
| 忘れる範囲 | 体験の一部(例:夕食の献立) | 体験のすべて(例:夕食を食べたこと自体) |
| 自覚 | もの忘れの自覚がある | 自覚がないことが多い |
| 進行 | 年齢相応で、あまり進行しない | 症状が徐々に進行していく |
| 日常生活 | 大きな支障はない | 日常生活に支障が出てくる |
もの忘れが気になり始めた方は、まずMCI(軽度認知障害)についても正しく理解しておくことが重要です。
MCIは認知症の一歩手前の段階で、適切な対策により健常な状態に回復する可能性が16~41%もあることが研究で明らかになっています。
- 日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」
- 国立長寿医療研究センター MCIハンドブック
この違いを正しく理解し、変化に早期に気づくことが、ご自身とご家族を守るための重要な鍵となります。
あなたや家族に潜むリスクと初期症状
アルツハイマー病は、遺伝だけでなく、日々の生活習慣が発症リスクに大きく関わることがわかっています。
特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や、喫煙、過度の飲酒、社会的孤立などは、リスクを高める要因とされています。
リスクを減らすためには、ご自身の生活習慣を見直すとともに、病気のサインとなる初期症状に早く気づくことが大切です。
初期症状に不安を感じた方は、認知症の初期症状チェックリストで客観的に状況を確認してみましょう。
以下に、特に注意すべき初期症状の例を挙げます。
- 同じことを何度も話したり、聞いたりする
- 最近の出来事を思い出せない
- 時間や場所の感覚が不確かになる
- 慣れているはずの道で迷う
- 料理や買い物など、段取りが必要なことが苦手になる
- 趣味や好きだったことへの関心を失う
- ささいなことで怒りっぽくなるなど、人柄が変わったように感じる
これらのサインは、単なる疲れや年齢のせいと見過ごされがちです。
しかし、早期発見のためのポイントを知っておくことで、適切な対応へとつなげられます。
「もしかして?」と感じたら、ひとりで抱え込まず、専門家へ相談する勇気を持ちましょう。
スポンサーリンク
今日から始められるアルツハイマー病予防5つの生活習慣
当サイト「健達ねっと」を運営するメディカル・ケア・サービス株式会社は、25年以上にわたり認知症ケアの最前線に立ち続けてきました。
全国370以上の介護事業所で、これまで延べ2万人以上の認知症の方々にケアを提供し、独自に開発した「MCS版自立支援ケア」により、認知症の周辺症状(BPSD)において85%以上の方で改善を実現しています。
さらに、慶應義塾大学との共同研究をはじめとする科学的エビデンスの蓄積により、認知症の症状改善だけでなく、その予防においても重要な知見を得ています。
今回ご紹介する5つの予防法は、これらの豊富な現場経験と研究成果に基づいた、実践性の高い内容となっています。
しかし、これは認知症になった方に対する症状改善の実績であり、認知症予防の効果を示すものではありません。
【食事】脳を守る地中海式食事法と予防によい食べ物
毎日の食事が、未来のあなたの脳を作ります。
アルツハイマー病の予防には、特定の食品を摂るだけでなく、食事全体のバランスを整えることが重要です。
特に注目されているのが、野菜・果物・魚・オリーブオイルなどを中心とした「地中海式食事法」です。
2023年の研究では、地中海食を摂っている人は、そうでない人に比べて認知症のリスクが最大23%も低くなったことが報告されています。
この食事法は、抗酸化作用や抗炎症作用のある栄養素を豊富に含み、脳の神経細胞を酸化ストレスから守る効果が期待されています。
認知症を予防できる食事の詳細解説も、ぜひ参考にしてみてください。
日々の食事で意識したいポイントは、以下の通りです。
| 分類 | 食品・栄養素 | 効果・理由 |
|---|---|---|
| 積極的に摂りたいもの | 魚(特に青魚) | DHAやEPAが神経細胞の働きをサポート |
| 野菜・果物 | 抗酸化ビタミンが脳の老化を防ぐ | |
| オリーブオイル、ナッツ類 | 良質な脂質が脳の健康を維持 | |
| 控えたいもの | 飽和脂肪酸 | 肉の脂身やバターなど |
| 糖質の過剰摂取 | 菓子パンや清涼飲料水など |
逆に認知症になりやすい食べ物についても知っておくことで、より効果的な予防が可能です。
毎日の食卓に、脳にうれしい一品を加えてみませんか。
忙しい毎日でも手軽に認知機能をサポート
理想的な食事を毎日続けるのは簡単ではありません。
そのような時に役立つのが、科学的根拠に基づいた機能性表示食品です。
健達ねっとショップでは、記憶力や認知機能の維持をサポートする以下の商品を取り扱っています。
- 記憶の鉄人(PQQ配合):中高年の記憶力・注意力・判断力の維持をサポート
- メモリービフィズス菌:森永乳業開発の記憶力・認知機能・空間認識力をサポートするビフィズス菌
- プラズマローゲンBOOCSスペシャル:国産高純度のホタテ由来プラズマローゲンで記憶力維持をサポート
これらの商品は、日々の食事と併用することで、より効率的な認知機能の維持が期待できます。
ただし、サプリメントは食事の代替ではありません。
バランスのよい食事を基本として、補完的にご活用ください。
【運動】無理なく続ける「コグニサイズ」とオススメの運動習慣
運動は、脳の血流を促進し、神経細胞に栄養を届けるための最も効果的な方法のひとつです。
運動をすることで、記憶を司る海馬の神経細胞を増やす「脳由来神経栄養因子(BDNF)」という物質が増えることも分かっています。
有酸素運動により、BDNFと呼ばれる血中脳由来神経栄養因子の濃度が上昇し、このBDNFの上昇が海馬の神経新生を促進することが明らかになっています。
しかし、激しい運動を無理して行う必要はありません。
大切なのは、楽しみながら継続することです。
特にオススメなのが、国立長寿医療研究センターが開発した「コグニサイズ」です。
コグニサイズとは、計算やしりとりなどの認知課題と、ウォーキングやステップ運動などの運動を組み合わせたエクササイズです。
国立長寿医療研究センターの公式資料によると、「運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語」と定義されています。
認知症予防に効果的な運動方法で詳しく解説していますので、ご覧ください。
具体的な運動のポイントは以下の通りです。
- 運動の種類:ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動が基本
- 運動の強度:「ややきつい」と感じる程度
- 運動の頻度:週に3回以上、合計で150分程度が目標
- ポイント:運動中に頭を使う(例:景色を覚えながら歩く、計算する)とさらに効果的
筋トレに興味のある方は筋トレが認知症に与える効果も参考になります。
まずは、通勤時にひと駅分歩いてみる、エレベーターを階段に変えるなど、生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めてみましょう。
【脳トレ】日常を「脳への刺激」に変える習慣
脳の健康を保つためには、体だけでなく頭も使い続けることが大切です。
普段使わない脳の領域を刺激し、神経ネットワークを活性化させることが、認知機能の低下を防ぎます。
これを「認知予備能(Cognitive Reserve)」を高めるといいます。
特別なドリルやゲームだけが脳トレではありません。
日常生活の中に、脳を刺激するチャンスはあふれています。
例えば、いつもと違う道を通って帰る、利き手と反対の手で歯を磨く、料理のレシピを見ずに作ってみるなど、少しの工夫で脳は活性化します。
具体的な方法は、認知症予防の脳トレ・クイズも参考にしてみてください。
認知症ケア現場で実証された「12の解決方法」を予防に活用
当社の認知症ケア現場では、「MCSケアモデル」に基づく12の解決方法で、認知症の方々の症状改善を実現しています。
これらの手法は、予防段階でも効果的に活用できます。
| 手法 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| コミュニケーション強化法 | 家族との会話で「場所・時間・人」を意識的に確認し合う |
| 不確かな情報を「確か」にする声かけを心がける | |
| 生活空間の最適化 | 安心して行動できる環境づくり(整理整頓、適切な照明など) |
| 「自分でできる」を増やす道具の工夫 | |
| つながりの創出 | 地域や人とのつながりで役割を感じられる活動への参加 |
| 過去の経験や趣味を活かした社会貢献 |
これらは単なる脳トレではなく、認知症になっても「当たり前の生活」を送れるよう支援してきた現場ノウハウです。
日常生活に取り入れることで、より包括的な予防効果が期待できます。
【社会参加】人との交流が脳の最大の栄養になる
人とのつながりを持ち、社会的な役割を担うことは、アルツハイマー病予防において極めて重要です。
孤立は、うつや認知機能低下の大きなリスク因子となることが知られています。
友人との会話、趣味のサークル活動、ボランティアなど、どのような形でもかまいません。
他者とコミュニケーションをとることは、相手の話を理解し、自分の考えをまとめ、適切な言葉で表現するという、脳のさまざまな機能を同時に使う高度な知的活動なのです。
また、社会とのつながりは、生活にハリや目的意識をもたらし、精神的な健康を保つ上でも欠かせません。
まずは、地域のイベントに参加してみる、旧友に連絡をとってみるなど、小さな一歩から始めてみませんか。
認知症カフェの活用や認知症予防の趣味活動なども効果的です。
あなたも認知症理解の輪を広げる一員に
社会参加は脳の健康維持に不可欠ですが、同時に認知症への正しい理解を広めることも重要な社会貢献です。
当社では、学校や企業向けに「認知症教育の出前授業」を実施しており、これまで45校・4,800名以上が受講されました。
受講後のアンケートでは、驚くべき結果が出ています。
- 100%の方が「認知症について理解できた」と回答
- 81.7%の方が「認知症に対してよいイメージに変わった」と回答
- 71.4%の方が「介護や介護職に対してよいイメージに変わった」と回答
このように、正しい知識の普及により、認知症への偏見や誤解が大きく改善されています。
あなたも家族や友人との会話で認知症について正しい情報を共有することで、誰もが暮らしやすい社会づくりに貢献できます。
認知症予防は個人の取り組みであると同時に、社会全体で支え合う共生社会の実現にもつながる重要な活動なのです。
【睡眠と休養】脳のゴミを洗い流す質の高い睡眠
睡眠は、単なる休息ではありません。
日中の活動で脳に溜まった老廃物を掃除し、記憶を整理・定着させるための重要なメンテナンス時間です。
アルツハイマー病の原因物質とされる「アミロイドβ」というたんぱく質は、私たちが眠っている間に、脳のリンパシステム(グリンパティックシステム)によって効率的に洗い流されることがわかっています。
特にノンレム睡眠時にグリンパティックシステムが活性化し、アミロイドβの排出が促進されます。
睡眠不足が続くと、この清掃活動が滞り、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなってしまうのです。
詳しくは、睡眠不足が認知症を引き起こすメカニズムで解説しています。
質のよい睡眠を確保するためのポイントは、以下の通りです。
- 毎日同じ時間に起き、朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 日中に適度な運動を行い、心地よい疲労感を得る
- 就寝前のスマートフォンやパソコン操作を控える
- 寝室の環境(温度、湿度、光、音)を整える
- カフェインやアルコールの摂取は、就寝の数時間前までにする
適切な昼寝の取り方については認知症予防に効果的な昼寝も参考になるかと思います。
忙しい毎日の中でも、脳をしっかりと休ませる時間を意識的に確保しましょう。
大切な人がアルツハイマー病になった時に家族ができることや利用できる制度
もしもの時に備えて、認知症についてさらに深く理解したい方には、当サイトで販売している専門書籍「認知症になりにくい人・なりやすい人」をオススメします。
この書籍は、多くの認知症患者を診察してきた認知症専門医の長田乾先生が、数多くの論文から導き出した科学的知見をまとめたものです。
頭の大きさや歩行速度・社交性・多言語能力など、さまざまな要因が認知症リスクにどう影響するかを、認知予備能という概念を軸に詳しく解説しています。
「40歳からの30の習慣で認知症を超える」をテーマに、明日から実践できる具体的な対策が満載です。
ご自身の傾向を知り、個人に最適化された予防戦略を立てるのに役立つ一冊です。
予防に取り組むと同時に、万が一、ご家族がアルツハイマー病と診断された場合の備えをしておくことも、未来の安心につながります。
ひとりで抱え込まず、利用できるサポートを正しく知っておきましょう。
まずは早期発見・早期診断が何より重要
アルツハイマー病の進行を完全に止める治療法はまだありませんが、早期に発見し、適切な治療やケアを開始することで、症状の進行を緩やかにし、ご本人とご家族が穏やかに暮らせる時間を長く保つことが可能です。
なぜなら、薬物療法や非薬物療法(運動療法や認知リハビリテーションなど)は、早期に始めるほど効果が高いとされているためです。
また、早い段階で診断を受けることで、今後の生活設計や介護の準備を、本人や家族が一緒に考え、進める時間的・精神的な余裕が生まれます。
早期診断には、以下のようなメリットがあります。
- 治療の選択肢が広がる
- 症状の進行を遅らせることが期待できる
- 介護保険サービスなどの公的支援を早期に利用できる
- 本人や家族が病気と向き合う準備ができる
「年のせいかな?」と見過ごさず、「もしかして?」と感じたら、ためらわずに専門医に相談することが、ご本人とご家族の未来を守るための最も重要な一歩です。
認知症の早期診断の流れについても、ぜひご確認ください。
利用できる相談窓口
ご家族の認知症について悩んだ時、決してひとりで抱え込まないでください。
専門的な知識を持ち、親身に相談に乗ってくれる窓口が多くあります。
まずは、かかりつけ医に相談するのが第一歩です。
そこから、必要に応じて専門の医療機関を紹介してもらえます。
その他、公的な相談窓口として以下のような場所があります。
- 地域包括支援センター:高齢者の暮らしを支える地域の総合相談窓口
- 認知症疾患医療センター:認知症の専門的な診断や治療、相談を行う病院
- 市区町村の高齢者福祉担当窓口:介護保険や福祉サービスに関する相談窓口
厚生労働省によると、地域包括支援センターは「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援」する機関です。
各窓口の特徴については、認知症についてどこに相談すべきかで詳しく解説しています。
専門家からの客観的なアドバイスは、家族の精神的な負担を大きく和らげてくれます。
公的な支援制度
アルツハイマー病と診断された場合、ご本人とご家族の生活を支えるためのさまざまな公的支援制度を利用できます。
これらの制度をうまく活用することで、経済的・身体的な負担を軽減し、安心して療養生活を送ることが可能になります。
どのような制度があるのかを事前に知っておくことが、いざという時の助けになるでしょう。
代表的な制度を下の表にまとめました。
| 制度の名称 | 内容 |
|---|---|
| 介護保険サービス | ヘルパーの訪問、デイサービス、施設入所など、介護に必要なサービスを1~3割の自己負担で利用できる制度。 |
| 成年後見制度 | 判断能力が不十分になった方の財産管理や契約などを、後見人が法的に支援する制度。 |
| 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳) | 認知症の症状の程度により交付され、税金の控除や公共料金の割引などの支援が受けられる。 |
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度。 |
厚生労働省によると、成年後見制度は「知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをする際にお手伝いする制度」です。
これらの制度の全体像については、認知症になったらどうする?利用できる制度で詳しく解説しています。
手続きが複雑な場合もあるため、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談しながら進めるのがよいでしょう。
まとめ
アルツハイマー病は、決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる病気です。
しかし、この記事で解説したように、発症リスクを抑えるための予防法は確かに存在します。
重要なのは、40代・50代のうちから、未来の自分のために生活習慣を見直すことです。
ご紹介した5つの予防法を、改めて振り返ってみましょう。
- 食事:魚や野菜中心のバランスのよい食事を心がける
- 運動:無理なく続けられる有酸素運動を習慣にする
- 脳トレ:新しいことに挑戦し、脳に刺激を与える
- 社会参加:人との交流を楽しみ、社会とのつながりを保つ
- 睡眠:脳のメンテナンスのために、質のよい睡眠を確保する
すべてを完璧に行う必要はありません。
まずは、この中からひとつでも「これならできそう」と思えることを見つけて、今日から始めてみませんか。
その小さな一歩が、10年後、20年後のあなたと、あなたの大切な家族の笑顔を守ることにつながります。
認知症予防についてより専門的な知識を得たい方は、認知症の権威による40代からの予防法や生活習慣病と認知症予防の関係などの専門家インタビューもぜひご覧ください。
あなたの未来への不安が、この記事をきっかけに、自分で未来を創る希望へと変わることを心から願っています。