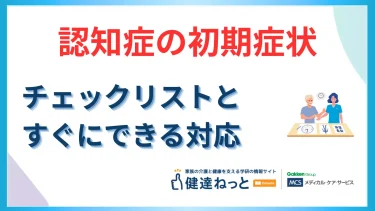- 「最近、もの忘れがひどくなった気がする…」
- 「親の言動に、以前とは違う変化を感じる…」
- 「MCIという言葉を聞くけど、認知症とは違うの?」
このような不安や疑問を感じていませんか。
年齢を重ねるにつれて増える「もの忘れ」に対し、「もしかして認知症の始まりでは?」と心配になるのは自然なことです。
しかし、その症状は認知症ではなく、「MCI(軽度認知障害)」かもしれません。
この記事では、MCIの基本的な定義から、認知症や単なるもの忘れとの違い、ご自身やご家族が当てはまるかを確認できるセルフチェックリストまで、網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、以下のことが分かります。
- MCIが認知症とは異なる「回復可能な段階」であること
- MCIの具体的な症状と原因
- 科学的根拠に基づいた5つの具体的な予防策
- 最新の治療法や家族の適切な対処法
MCIは、決して絶望的な状態ではありません。
正しい知識を身につけ、早期に適切な対策を講じることで、認知症への進行を防ぎ、健やかな毎日を維持することが可能です。
あなたの不安を解消し、未来に向けた具体的な一歩を踏み出すために、ぜひこの記事をお役立てください。
スポンサーリンク
MCI(軽度認知障害)とは?基本的な定義から認知症やもの忘れとの違い
MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)について、正しく理解することが対策の第一歩です。
ここでは、MCIの基本的な定義をはじめ、多くの方が混同しがちな認知症や加齢による「もの忘れ」との明確な違い、そして国内のMCI人口の現状について解説します。
MCIは認知症と健常の間にあたる「グレーゾーン」
MCI(軽度認知障害)とは、記憶力や注意力といった認知機能に問題が生じているものの、日常生活への支障は出ていない状態を指します。
健常な状態と認知症の中間にあたる、いわば「グレーゾーン」といえるでしょう。
本人や家族から「もの忘れが増えた」といった訴えがあり、客観的な認知機能検査でも低下が認められるのが特徴です。
しかし、食事の支度や買い物・公共交通機関の利用など、基本的な日常生活はこれまで通り自立して行える点が、認知症との大きな違いです。
MCIの段階で適切な対策を行うことで、認知機能が改善したり、認知症への進行を遅らせたりできる可能性が多くの研究で示されています。
そのため、MCIを「認知症の入り口」と悲観的に捉えるのではなく、「生活を見直すための重要なサイン」と前向きに捉えることが大切です。
MCIと認知症の決定的な違い
MCIと認知症を分ける最も決定的な違いは、「日常生活に支障が出ているかどうか」です。
MCIの段階では、もの忘れなどの症状があっても、周囲のサポートなしに自立した生活を送ることが可能です。
一方で認知症に進行すると、認知機能の低下が顕著になり、これまで普通にできていた家事や金銭管理、外出などがひとりでは困難になります。
例えば、食事したこと自体を忘れてしまうのは認知症の典型的な症状ですが、MCIでは「何を食べたか思い出せない」といった症状に留まることが多いです。
MCIと認知症の主な違いを以下にまとめました。
| 項目 | MCI(軽度認知障害) | 認知症 |
|---|---|---|
| 日常生活 | 基本的に自立している | 支障があり、介助が必要になる |
| 記憶障害 | 体験の一部を忘れる | 体験の全体を忘れる |
| 判断力 | おおむね保たれている | 低下している |
| 病識 | もの忘れの自覚がある | 自覚がないことが多い |
| 回復可能性 | 健常な状態に回復する可能性がある | 回復は極めて困難 |
MCIの段階で気づき、適切な対策を始めることが、その後の生活の質を大きく左右します。
MCIと加齢による「もの忘れ」の見分け方
「人の名前がすぐに出てこない」「昨日の夕食を思い出せない」といった経験は、誰にでもある自然な「もの忘れ」です。
加齢による生理的なもの忘れは、脳の処理速度が少し遅くなることで起こります。
しかし、MCIによるもの忘れは、脳の機能自体に障害が起きている可能性を示唆しており、質的に異なります。
見分けるポイントは、「体験の一部を忘れているか、全体を忘れているか」です。
加齢によるもの忘れは、出来事の一部を忘れているだけなので、ヒントがあれば思い出すことが可能です。
一方、MCIでは体験したこと自体をすっぽり忘れてしまうため、ヒントを与えられても思い出せないケースが増えてきます。
| 加齢によるもの忘れの例 |
|
| MCIが疑われるもの忘れの例 |
|
MCIから認知症へ進行すると、このような症状がさらに顕著になります。
認知症の初期症状についても知っておくことで、より早期の変化に気づけるでしょう。
「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」「さっき言ったことを何度も聞いてくるのは、年のせい?」「もしかして、認知症の始まり…?」ご家族のささいな変化に、このような不安を抱えていませんか。その不安の裏には、「この先ど[…]
最新データ:国内のMCI・認知症の人口
国内において、MCIは決して珍しい状態ではありません。
厚生労働省の最新調査(2024年)では、2022年時点で65歳以上の高齢者のうち、認知症有病者は約443万人(12.3%)、MCIの有病者は約559万人(15.5%)と推計されました。
これは、65歳以上の約7人に2人(27.8%)が認知症またはMCIである計算になります。(参考:厚生労働省 認知症・MCI有病率調査)
高齢化がさらに進む日本では、この数は増加し続けると予測されています。
2040年には、認知症患者は約584万人、MCI患者は約613万人に達し、合計で約1,200万人に上ると見込まれています。
このデータは、MCIや認知症が誰にとっても身近な問題であることを示しています。
自分や家族がいつ当事者になってもおかしくないという意識を持ち、正しい知識と予防策を身につけておくことが、これからの時代を生きる私たちにとって不可欠といえるでしょう。
スポンサーリンク
MCIで見られる代表的な症状
MCIのサインは、単なる「もの忘れ」以外にも、日常生活のさまざまな場面に現れます。
ここでは、MCIの方によく見られる代表的な6つの症状を解説します。
ご自身やご家族に当てはまるものがないか、チェックしながら読み進めてみてください。
同じことを何度も聞いたり話したりする
MCIの症状として最も分かりやすいのが、記憶障害です。
特に、新しい出来事を記憶する「短期記憶」の機能が低下するため、直前に聞いたことや話したことを忘れ、同じ質問や話を繰り返すようになります。
「今日の予定は何だっけ?」と何度も確認したり、同じエピソードを初めて話すかのように語ったりする行動が目立ちます。
これは本人が忘れたくて忘れているわけではなく、脳の機能低下によるものです。
周囲の人は、そのことを理解し、根気強く付き合う姿勢が求められます。
このような症状は、MCIの初期段階から現れることが多いサインのひとつです。
物の置き忘れや探し物が明らかに増える
鍵や財布、眼鏡など、毎日使うものをどこに置いたか忘れてしまうことは誰にでもあります。
しかし、MCIになるとその頻度が明らかに増え、以前では考えられなかったような場所に物をしまい込んでしまうこともあります。
例えば、冷蔵庫の中にリモコンを入れてしまったり、タンスの中に本をしまったりするなど、不自然な置き忘れが目立つようになるのです。
これは記憶力の低下に加え、注意力が散漫になっていることも影響しています。
「また物を探しているな」と感じる場面が急に増えたら、注意が必要なサインかもしれません。
料理や買い物など段取りが必要なことが苦手になる
料理や買い物、旅行の計画など、複数の手順を考え、効率よく実行する必要がある作業を「段取り」といいます。
この段取り能力は「実行機能」と呼ばれ、MCIになるとこの機能が低下することがあります。
主な症状の例は以下の通りです。
- 料理の品数を同時に作れなくなる
- 買い物で買うべきものを買い忘れる
- 公共料金の支払いや手続きを忘れる
これまでスムーズにできていた家事や作業に時間がかかったり、ミスが増えたりするようになります。
本人は「なぜかうまくできない」と混乱し、自信を失ってしまうことも少なくありません。
このような実行機能の低下は、日常生活における隠れたMCIのサインといえるでしょう。
新しい家電の操作や慣れない場所での運転に戸惑う
MCIになると、新しい情報を取り込んで理解し、応用する能力が低下することがあります。
そのため、新しく購入したスマートフォンや家電の操作方法がなかなか覚えられなかったり、取扱説明書を読んでも理解できなかったりするのです。
また、視空間認知能力の低下も影響し、慣れない場所での車の運転に戸惑うことも増えます。
例えば、スーパーの駐車場で自分の車をどこに停めたか分からなくなったり、標識や信号の見落としが増えたりします。
これらの変化は、本人が最も強く不安を感じる部分でもあり、事故につながる危険性もはらんでいるため、注意深い観察が必要です。
会話中に適切な言葉が出てこないことが増える
会話の最中に、「あれ」「それ」といった指示代名詞が目立つようになり、人や物の名前がすぐに出てこないことが増えます。
これは言語機能の低下によるもので、「言葉のど忘れ」が頻繁に起こる状態です。
単なるど忘れであれば、話の流れやヒントで言葉を思い出せることが多いですが、MCIの場合は言葉自体がなかなか出てこない、あるいは見当違いの言葉を使ってしまうこともあります。
このような言語機能の低下は、コミュニケーションへの自信喪失につながりかねません。
実は、話す、飲み込むといった口腔機能は、脳の幅広い領域と関連しています。
新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が監修する「ノドトレ」は、嚥下機能だけでなく発話機能の向上にも効果が期待できるプログラムです。
口腔機能を維持・向上させることは、MCIの症状緩和や予防にもつながる可能性があります。
以前は楽しめていた趣味や活動への意欲・関心が低下する
以前は大好きだった趣味や、友人との集まり、外出などに対して、急に興味や関心を失い、億劫に感じるようになることがあります。
これは「アパシー(無気力・無関心)」と呼ばれる症状で、MCIのサインのひとつです。
うつ病の症状と似ていますが、うつ病が気分の落ち込みや悲哀感を伴うのに対し、アパシーは感情の起伏自体が乏しくなる特徴があります。
「何もやる気が起きない」「前は楽しかったのに、今はどうでもいい」といった状態が続く場合は注意が必要です。
この意欲の低下は、社会的な孤立につながりやすく、さらなる認知機能の低下を招く悪循環に陥る危険性があります。
周囲の人は、本人の変化に気づき、無理強いはせず、本人が少しでも興味を示せるような働きかけをすることが大切です。
すぐできるMCIセルフチェックリスト13項目
ご自身やご家族にMCIの疑いがあるか、簡単な質問でチェックしてみましょう。
以下の13項目は、認知機能の主要な5つの領域(記憶、注意・実行機能、言語、視空間認知、意欲・人格)に関するものです。
最近の様子を振り返り、「はい」がいくつあるか数えてみてください。
【注意】
このチェックリストは、あくまでMCIの可能性に気づくための「きっかけ」を提供するものであり、医学的な診断に代わるものではありません。
気になる症状がある場合は、必ず専門の医療機関に相談してみてください。
記憶に関する質問
- 最近の出来事(昨日したことなど)を思い出せないことがある
- 同じことを何度も話したり、聞いたりすると指摘される
- 約束や大事な用事を忘れてしまうことがある
注意・実行機能に関する質問
- 料理や買い物など、段取りが必要なことでミスが増えた
- 注意力が散漫になり、うっかりミスが増えた
- 新しい機器(スマートフォンなど)の操作に戸惑う
言語に関する質問
- 会話中に「あれ」「それ」が増え、物の名前がすぐに出てこない
- 言葉に詰まることが増え、会話がスムーズに進まない
視空間認知に関する質問
- 慣れているはずの場所で道に迷うことがある
- 物の置き場所が分からなくなることが増えた
意欲・人格に関する質問
- 以前は楽しめていた趣味や活動に興味がなくなった
- 外出するのが億劫になった
- ささいなことで怒りっぽくなった、または頑固になった
【結果の目安】
「はい」が5つ以上あった場合は、MCIの可能性があります。
一度、かかりつけ医や専門の医療機関に相談してみるのがオススメです。
また、健康状態の把握には、他のセルフチェックも役立ちます。
その他の健康セルフチェックもあわせて実施することをオススメします。
MCIになる主な原因と種類
MCIはなぜ起こるのでしょうか。
その原因はひとつではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
ここでは、MCIの主な原因と、症状によって分けられるMCIの種類について解説します。
最も関連が深いアルツハイマー病とアミロイドβ
MCIの最も大きな原因のひとつが、認知症の中で最も多い「アルツハイマー病」につながる脳の変化です。
アルツハイマー病は、「アミロイドβ」という異常なたんぱく質が脳内に蓄積し、神経細胞を傷つけることで発症します。
この脳の変化は、認知症の症状が現れる20年以上も前から始まっていることが分かっており、MCIの段階ですでにアミロイドβの蓄積が認められるケースが多くあります。
しかし、ここで重要なのが「認知予備能(コグニティブ・リザーブ)」という考え方です。
横浜総合病院の長田乾医師によると、脳にアルツハイマー病の病理変化があっても、認知機能が正常に保たれる人がいることが分かっています。
これは、教育歴の長さや知的な職業・趣味・運動習慣などが、脳のダメージを補う「予備能力」として働くためです。
つまり、脳に原因物質が蓄積しても、生活習慣次第で発症を抑えられる可能性があるのです。
横浜総合病院・横浜市認知症疾患医療センター長田 乾 先生アルツハイマー病になっても、認知症を発症しないケースがあるアルツハイマー病が原因の認知症を、「アルツハイマー型認知症」と呼びます。(*1)で、脳にアルツハイマー病の特徴[…]
糖尿病や高血圧など生活習慣病も大きなリスク要因
アルツハイマー病の変化以外にも、MCIのリスクを高める要因はさまざまです。
特に、糖尿病や高血圧・脂質異常症といった生活習慣病は、脳の血管にダメージを与え、脳梗塞や脳出血のリスクを高めます。
これらの脳血管障害は、血管性認知症の直接的な原因となるだけでなく、脳の血流を悪化させることで、アルツハイマー病の進行を早めることも知られています。
生活習慣病の管理は、脳の健康を守る上で非常に重要です。
健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービス(MCS)では、科学的介護に基づいた自立支援ケアを実践しています。
適切な栄養管理(水分約1,800ml、たんぱく質約80gなど)が認知機能の維持・改善に寄与することを確認しています。
生活習慣病の予防・改善は、MCIの予防にも直結するといえるでしょう。
「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症高齢者対応のグループホーム「 愛の家」を主軸に介護事業所を300か所…
記憶障害が主体の「健忘症」とそれ以外の「非健忘症」
MCIは、現れる症状によって大きく2つのタイプに分類されます。
どのタイプのMCIかによって、将来的に移行しやすい認知症の種類も異なると考えられています。
- 健忘性MCI(amnesic MCI)
- 主な症状は「記憶障害」。新しいことを覚えられない、出来事を忘れるといった症状が中心です。
- アルツハイマー型認知症に進行しやすいタイプとされています。
- 非健忘性MCI(non-amnesic MCI)
- 記憶障害は目立たず、注意・実行機能、言語機能、視空間認知能力など、記憶以外の認知機能に問題が見られます。
- 段取りが悪くなる、言葉が出にくい、道に迷いやすいといった症状が主です。
- 将来的に、レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症など、アルツハイマー病以外の認知症に移行する可能性があります。
この分類は、その後の経過予測や治療方針を立てる上で重要です。
自分の症状がどのタイプに近いかを知ることも、MCIを理解する一助となります。
MCIは回復できる!認知症への進行を防ぐ5つの科学的予防策
MCIは、認知症とは異なり、健常な状態に回復する可能性がある段階です。
研究により、MCIの方のうち年間約5~15%が認知症に進行する一方、16~41%は健常な状態に改善したというデータもあります。
ここでは、認知症への進行を防ぎ、回復を目指すための科学的根拠のある5つの予防策を紹介します。
【運動】週3回以上の有酸素運動+脳トレ
運動は、MCI予防において最も科学的根拠が豊富な方法のひとつです。
特に、ウォーキングやジョギング・水泳などの有酸素運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の栄養となる物質(BDNF:脳由来神経栄養因子)を増やす効果があります。
推奨される運動の目安は、「週3回以上、1回30分程度の有酸素運動」です。
さらに、運動と同時に頭を使う「コグニサイズ」のようなデュアルタスク(二重課題)を取り入れると、より効果的に脳を活性化できます。
横浜総合病院の長田乾医師も、運動習慣が脳の予備能力である「認知予備能」を高める重要な要素であると指摘しています。
今日からできる簡単なウォーキングから始めてみませんか。
- 具体的な脳トレ方法はこちらで詳しく解説
認知症の予防には脳トレが効果的?具体的な内容を解説します! - 運動と認知課題を組み合わせたコグニサイズについて詳しくはこちら
認知症の方にオススメの体操とは?コグニサイズの効果について解説
【食事】地中海式を参考に多種多様な食品をバランスよく摂る
日々の食事も、脳の健康に大きく影響します。
世界保健機関(WHO)も推奨しているのが、野菜、果物、魚、オリーブオイルなどを豊富に使う「地中海式食事」です。
これらの食品に含まれる抗酸化物質や不飽和脂肪酸が、脳の炎症を抑え、神経細胞を保護する働きをします。
ポイントは、特定の食品だけを食べるのではなく、多種多様な食材をバランスよく摂ることです。
メディカル・ケア・サービス(MCS)の実践では、1日約1,800mlの水分と約80gのたんぱく質摂取を目標とした栄養支援が、認知機能の改善につながることが示されています。
また、DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸には、中高年の方の認知機能の一部(記憶力、判断力、注意力)をサポートする機能が報告されています。
- WHO推奨の地中海式食事の詳細はこちら
【WHO推奨】認知症リスク低減のためのポイント|健康的な食事 - DHA・EPAの認知機能への効果について詳しくはこちら
DHAとEPAの効果|摂取量、オススメサプリメントなど解説 - 認知機能をサポートするDHA・EPAの詳細はこちら
健達DHA+EPA
食事から十分な栄養を摂るのが難しい場合は、機能性表示食品などを活用するのもひとつの方法です。
【知的活動】趣味や社会参加などの交流で脳を元気にする
脳は使わなければ衰えてしまいます。
囲碁や将棋・楽器演奏・読書といった趣味に没頭したり、友人とおしゃべりを楽しんだりすることは、脳のさまざまな領域を刺激し、活性化させます。
これが前述の「認知予備能」を高めることにつながるのです。
重要なのは、人との交流を伴う活動です。
慶應義塾大学との共同研究では、良好な職場環境や社会参加がメンタルヘルスによい影響を与えることが示されています。
これはMCI予防にも通じる考え方です。
地域のイベントに参加したり、ボランティア活動を始めたりするなど、社会とのつながりを持ち続けることが、脳を元気に保つ秘訣です。
また、「ハルと思い出めぐりごはん」の実践知見では、懐かしい食事をきっかけに昔の記憶を語り合う「回想法」が、コミュニケーションを活性化させ、知的活動を促す効果的なツールとなることが示されています。
>参考:メディカル・ケア・サービス 慶應義塾大学との共同研究
【生活習慣病の管理】特に中年期はメタボ、高齢期はフレイルに注意する
糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、脳の血管にダメージを与え、MCIや認知症の強力なリスク因子となります。
特に中年期(40~60代)の生活習慣は、その後の認知機能に大きく影響するため、この時期のメタボリックシンドロームの予防・改善は極めて重要です。
メディカル・ケア・サービス(MCS)では、科学的介護情報システム(LIFE)を活用し、個々人の状態に合わせたケアプランを作成することで、生活習慣病の重症化予防や心身機能の改善に取り組んでいます。
高齢期においては、体重減少や筋力低下を特徴とする「フレイル(虚弱)」にも注意が必要です。
適切な栄養管理と運動により、生活習慣病とフレイルの両方を管理し、脳の健康を維持することが大切です。
【質の高い睡眠】脳のメンテナンス時間を確保する
睡眠は、単なる休息ではありません。
眠っている間に、脳内では「グリンパティックシステム」という仕組みが働き、日中の活動でたまったアミロイドβなどの老廃物を洗い流しています。
つまり、睡眠は脳のメンテナンス時間なのです。
睡眠不足が続いたり、睡眠の質が低下したりすると、この浄化作用がうまく働かず、脳内に老廃物が蓄積しやすくなります。
これがMCIやアルツハイマー病のリスクを高める一因と考えられています。
質の高い睡眠を確保するためには、以下のポイントを心がけましょう。
- 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
- 就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控える
- 適度な運動を習慣にする
- 日中に太陽の光を浴びる
適切な昼寝も効果的ですが、長すぎる昼寝は夜の睡眠を妨げるため注意が必要です。
超高齢社会の日本において、年々増加している認知症。認知症予防の重要性も次第に高まっています。認知症予防はハードルが高いと思っている人が多いのではないでしょうか?昼寝といった簡単なことでも、認知症予防の効果が期待できます。[…]
MCIの治療法は?最新治療薬「レケンビ」の効果と限界
MCIと診断された場合、どのような治療が行われるのでしょうか。
ここでは、治療の基本となる非薬物療法から、話題の最新治療薬「レケンビ」の効果と限界まで、詳しく解説します。
治療の基本は運動やリハビリなどの「非薬物療法」
現在のMCI治療の基本は、「非薬物療法」です。
これは、薬に頼らずに、認知機能の維持・改善を目指すアプローチを指します。
具体的には、これまで紹介してきた以下の予防策を、個人の状態に合わせて専門家の指導のもとで実践することです。
- 運動療法: 有酸素運動や筋力トレーニング
- 認知リハビリテーション: 脳トレや回想法など
- 食事指導: バランスの取れた栄養管理
- 生活習慣病の管理: 血圧や血糖値のコントロール
メディカル・ケア・サービスが厚生労働省のLIFE活用事業で実践しているように、科学的根拠に基づいたアセスメントを行い、一人ひとりに最適なケアを提供することが、MCIから認知症への進行を防ぐ鍵となります。
アルツハイマー病によるMCIの治療薬「レケンビ」とは
2023年、アルツハイマー病によるMCIおよび軽度認知症の治療薬として、「レケンビ(一般名:レカネマブ)」が国内で承認されました。
この薬は、アルツハイマー病の原因物質である「アミロイドβ」が脳内に蓄積するのを防ぎ、除去を促進する画期的な新薬です。
臨床試験では、レケンビを投与された患者は、偽薬を投与された患者に比べて、18か月後の認知機能の低下が約27%抑制されたと報告されています。
これにより、病気の進行を緩やかにする効果が期待されています。
ただし、この薬はアミロイドβが原因のMCIや軽度認知症が対象であり、全てのMCI患者に有効なわけではありません。
アミロイドβの蓄積を防ぐ他のアプローチについても、理解を深めておくとよいでしょう。
アミロイドβを減らす方法について高齢化が進む中、年々増加している病気の1つが認知症です。近年、アルツハイマー型認知症の原因となる物質について、明らかになりつつあります。原因となる物質とは、アミロイドβというタンパク質です。[…]
新薬の限界と副作用
レケンビは希望の光である一方、限界と課題も存在します。
まず、この薬は病気の進行を「緩やかにする」ものであり、失われた認知機能を取り戻したり、病気を完治させたりするものではありません。
また、治療を受けるには、PET検査などで脳内のアミロイドβの蓄積が確認されている必要があります。
さらに、副作用にも注意が必要です。
主な副作用として、脳内に微小な出血やむくみが生じる「アミロイド関連画像異常(ARIA)」が報告されています。
そのため、投与中は定期的なMRI検査が欠かせません。
レケンビの主な課題
- 高額な薬価(年間数百万円)
- 定期的な通院(2週間に1回の点滴)が必要
- 副作用(ARIA)のリスク管理
- 投与できる医療機関が専門施設に限られる
これらの限界点を正しく理解し、医師と十分に相談した上で、治療の選択肢を検討することが重要です。
家族や周りの方がMCIになった時の本人と周囲の適切な対処法
ご家族や身近な人がMCIになった時、本人はもちろん、周囲の方も戸惑いや不安を感じるものです。
ここでは、本人の変化に気づいた際の適切な対応や、利用できる公的な相談窓口について解説します。
本人の変化に気づいた時の適切な対応と言葉かけ
家族がMCIのサインに気づいた時、最も大切なのは「本人の尊厳を傷つけない」ことです。
もの忘れを頭ごなしに否定したり、責めたりするような言動は、本人を深く傷つけ、かえって症状を悪化させる可能性があります。
「最近、少し忘れっぽくなったかな?心配だから一度病院で相談してみない?」など、不安な気持ちに寄り添い、一緒に考える姿勢で接することが重要です。
メディカル・ケア・サービス(MCS)の杉本浩司氏が行う認知症教育の出前授業では、92%の受講生が授業後に「認知症がよいイメージに変わった」と回答しています。
これは、正しい知識が偏見をなくし、ポジティブな関わり方を生むことを示しています。
MCIも同様に、病気への正しい理解が、本人と家族の良好な関係を築く第一歩となるのです。
変化に気づいたら、なるべく早い段階で専門医の診断を受けることが、その後の適切な対応につながります。
参考:メディカル・ケア・サービス 認知症教育の出前授業 アンケート調査結果
関連記事:認知症は早期診断が大切!診断の流れや必要な情報を解説
無料で利用できる公的な相談窓口一覧
MCIや認知症に関する悩みや不安は、ひとりで抱え込まずに専門機関に相談しましょう。
国や自治体は、無料で利用できるさまざまな相談窓口を設置しています。
これらの窓口では、専門知識を持ったスタッフが、医療や介護に関する情報提供、サービスの紹介、家族の悩み相談などに応じてくれます。
以下に、主な公的な相談窓口をまとめました。
お住まいの地域の窓口を事前に確認しておくと、いざという時に安心です。
| 相談窓口 | 主な役割 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 高齢者の総合相談窓口。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が在籍し、介護・医療・福祉に関する相談に幅広く対応。 |
| 認知症疾患医療センター | 認知症の専門的な診断、治療方針の決定、合併症への対応などを行う専門医療機関。かかりつけ医からの紹介で受診することが多い。 |
| 認知症コールセンター | 都道府県や指定都市が設置。本人や家族からの電話相談に、専門の相談員が対応。 |
| 若年性認知症コールセンター | 65歳未満で発症する若年性認知症に特化した相談窓口。就労支援や社会参加に関する相談も可能。 |
| 市町村の高齢福祉課など | 自治体の担当部署。介護保険サービスや地域の福祉サービスに関する情報提供や手続きの窓口。 |
これらの専門機関を積極的に活用し、専門家のアドバイスを受けながら、本人にとって最適なサポート体制を整えていくことが大切です。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、MCI(軽度認知障害)について、認知症との違いからセルフチェック、科学的根拠に基づく予防策、治療法、家族の対処法まで幅広く解説しました。
MCIは、認知症と健常な状態の中間にあたる「グレーゾーン」であり、決して認知症とイコールではありません。
最も重要なポイントは、MCIが「回復可能な段階」であることです。
その理由は、運動、食事、知的活動、生活習慣病の管理、質の高い睡眠といった適切な対策を早期に始めることで、認知機能の維持・改善や、認知症への進行予防が科学的に期待できるためです。
まずは、この記事で紹介したセルフチェックリストでご自身やご家族の状態を確認し、MCIのサインに気づくことが第一歩となります。
そして、今日からできる予防策をひとつでも生活に取り入れてみてください。
もし不安や心配なことがあれば、ひとりで抱え込まず、かかりつけ医や専門の相談窓口に相談しましょう。
正しい知識を身につけ、前向きに行動を起こすことが、あなたの未来の健康を守る鍵となります。
健達ねっとでは、MCIや認知症の予防に役立つ機能性表示食品も取り扱っています。日々の生活習慣の見直しとあわせて、ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。