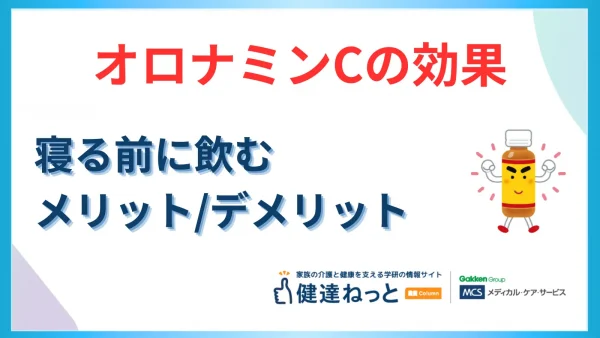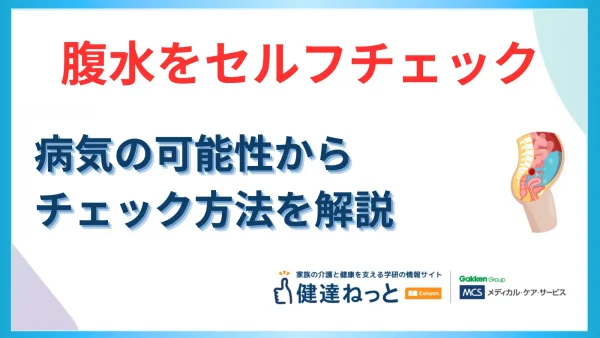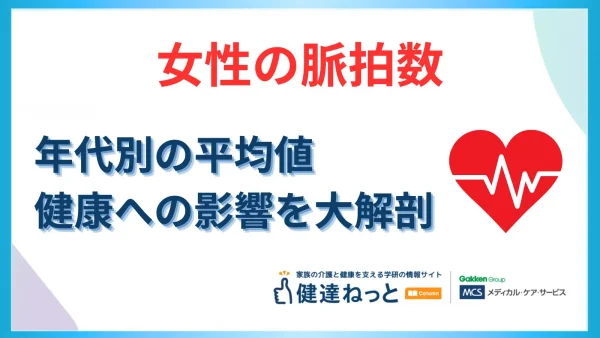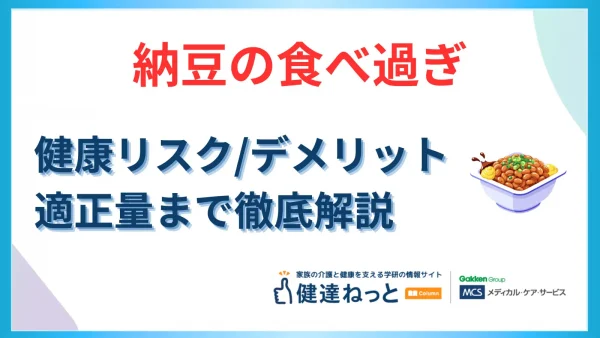睡眠障害には、夜に眠れない症状や、途中で起きてしまう症状があります。
また、原因はストレスや生活習慣にあることが多いです。
そもそも、中学生の睡眠障害の症状はどのようなものでしょうか。
本記事では中学生の睡眠障害のチェックについて以下の点を中心にご紹介します。
- 睡眠障害の症状のチェック
- 睡眠障害の原因のチェック
- 中学生の睡眠障害の治し方
- 仮眠は睡眠障害に関係するのか
中学生の睡眠障害のチェックについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
睡眠の質を上げるブレスレット「フィリップスタイン」とは?

フィリップスタインとは、就寝30分前に腕につけて眠るだけで、翌日のパフォーマンスの集中力の向上などが期待できるブレスレットです。
睡眠状態に近い周波数を発生させて、睡眠の質をサポートしてくれます。
「最近よく眠れないな」という方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
スポンサーリンク
睡眠障害とは

睡眠障害とは、何らかの理由により、十分な睡眠がとれていない状態のことをいいます。
睡眠障害の症状は、寝つきが悪いことや、眠りが浅いことが挙げられます。
症状を治すためには、生活習慣の改善や、治療が必要です。
症状が悪化すると、日常生活に支障をきたすことがあります。
スポンサーリンク
中学生の睡眠障害とは

中学生は体が成長する大事な時期です。
成長ホルモンは、寝ている間に最も多く分泌されるため、質のよい睡眠をとることが大切です。
しかし、生活習慣やストレスにより、睡眠障害の症状が現れることがあります。
睡眠障害になると、睡眠の質が低下して、子供の成長が妨げられてしまいます。
多く見られる症状は、寝つきが悪くなることや、日中に眠気が生じることです。
中学生の睡眠障害のチェック

睡眠障害には、次のような症状があります。
あてはまる症状があるか、チェックしてみましょう。
一口に睡眠障害の症状といっても原因はさまざまで、病気が潜んでいることがあります。
継続的にその症状が見られる場合は要注意です。
医療機関を受診し、医師に相談しましょう。
寝起きが悪い状態が毎日続いている
自律神経失調症やうつ病の可能性があります。
朝食をしっかり食べてエネルギーをしっかり補充する、規則正しい生活をする、ストレスをためないようにするなどの生活習慣上の対策をとりましょう。
それでも改善しない場合は、なるべく早く医療機関を受診しましょう。
午前中ボーっとしている
起立性調節障害である可能性もあります。
子どもの体から大人の体へと変化するこの時期に自律神経のバランスが崩れ易いために中学生時代に起きやすい症状です。
午後から元気になるような場合は可能性が高いです。
症状が継続する場合は医療機関を受診しましょう。
授業に集中できない程の眠気が続く
ナルコレプシーである可能性もあります。
ナルコレプシーは日中突然眠ってしまう睡眠発作が特徴です。
覚醒を維持するホルモンの低下が原因です。
残念ながら自然には治らず、治療が必要です。
ナルコレプシーだと突然の発作で事故や怪我にあってしまう可能性があります。
休日に寝だめする
休日無気力症候群でうつ病の初期症状である可能性もあります。
普段無理をしているために取っている行動かもしれません。
まずは平日にも十分に休めるよう生活を見直しましょう。
十分休んでいるのに症状が続く場合は医療機関を受診しましょう。
乗り物で移動する際に寝てしまう
乗り物の揺れや午後の時間帯などは誰でも眠くなります。
乗り物以外でもしばしば寝てしまうような場合は、上記のナルコレプシーである可能性もあります。
ナルコレプシーは治療が必要です。
継続する場合はなるべく早く医療機関を受診しましょう。
帰宅してすぐ寝てしまう
原因で多いのが睡眠不足です。
睡眠時間を確保できない、寝床へ入ってもすぐに寝付けない(入眠障害)、睡眠中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)など不眠症である場合もあります。
十分に睡眠時間をとっても続く場合は体調不良の原因にもなるので、医療機関の受診をおすすめします。
深夜になっても眠れない
不眠症の1つである入眠障害かもしれません。
入眠障害とは就寝後30分~1時間以上の眠れない状態が続く不眠症の1つです。
継続的に症状がある場合は成長ホルモンの不足にもつながり、成長に障害が出る可能性も出てきます。
継続する場合はなるべく早めに医療機関を受診しましょう。
入眠しても途中で目覚める
不眠症の一つである中途覚醒かもしれません。
中途覚醒とは眠りが浅く、夜中に目が覚める不眠症の1つです。
睡眠の質が悪いため、翌日に眠気、だるさ、集中力が低下するなどの恐れがあります。
原因としては、ストレス、睡眠無呼吸症候群などがあります。
いびきが大きい
睡眠時無呼吸症候群の可能性もあります。
他に無呼吸・睡眠中の陥没呼吸・起床時の不機嫌などの症状が出ることもあります。
アデノイドや扁桃肥大でもいびきは大きいです。
この場合の自然治癒は難しく、切除や摘出が必要です。
放置すると、子どもの成長・発達に障害が出るリスクがあります。
寝言が大きい
過去のストレス体験が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)、不安障害などの神経障害、てんかんの発作や睡眠時無呼吸症候群などの可能性があります。
寝言の状況(痙攣が一緒に起こるなど)によっては早めに睡眠障害専門医に相談すると良いでしょう。
無意識に起き上がる
睡眠時遊行症の可能性もあります。
睡眠中に無意識の状態で歩き回る症状で、睡眠の最も深いノンレム睡眠中に起こります。
睡眠中のことはほとんど覚えていません。
睡眠不足であったり、遅くまで液晶画面を見ていたりすると起こりやすくなります。
まず生活を正しましょう。
それでも継続する場合は医療機関への相談をおすすめします。
おねしょをする
15歳では100人に1人が夜尿症と言われています。
自然治癒の例が非常に多いですが、遺伝や家庭不和が原因の場合もあります。
一般的に小学校3年以上でおねしょの回数が1~2回/週であれば治療開始となります。
頻度によっては専門医の受診が必要ですが、その場合も本人のプライドを最大限に守ってあげましょう。
睡眠の質を上げるブレスレット「フィリップスタイン」とは?

フィリップスタインとは、就寝30分前に腕につけて眠るだけで、翌日のパフォーマンスの集中力の向上などが期待できるブレスレットです。
睡眠状態に近い周波数を発生させて、睡眠の質をサポートしてくれます。
「最近よく眠れないな」という方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
中学生の睡眠障害の原因をチェック

睡眠障害にはさまざまな原因があります。
当てはまる原因があるか、チェックしてみましょう。
睡眠時間が不足している
中学生になると勉強量が増えるので、本人が気づかないうちに寝不足になっている可能性があります。
国の統計(平成25年版 子ども・若者白書 )では、中学生の平均睡眠時間は7時間46分でした。
米国の国立睡眠財団は8~10時間を14歳~17歳の子どもの睡眠時間として推奨しています。
7~11時間の睡眠時間は適切な可能性があるとも述べています。
平均睡眠時間の7時間46分はほぼ適切だといえます。
課外活動が忙しい
中学生になると部活動が始まります。
また放課後、塾にいっている中学生も多いでしょう。
部活や塾も大切ですが、睡眠時間を削る必要があるのは考えものです。
中学生なので自分のことを自分でするのは大切ですが、必要な睡眠時間を確保できるように保護者の方も家庭生活では少し協力してあげましょう。
受験勉強で睡眠時間と精神を削っている
睡眠時間を削っての受験勉強は、成長が遅れたり、精神的ストレスも溜まりやすくなったりと身体的悪影響があるのでおすすめできません。
十分な睡眠時間を取らないと勉強に集中できないという問題も発生します。
十分な睡眠をとれば、情緒が安定し集中力が上がる、記憶が定着しやすくなるなど、勉強にとっては良いことが多いです。
保護者が寝る時間帯を管理するのも、効率的で効果的な勉強法と睡眠時間を作るための1つの方法です。
夜遅くまでスマホやゲームをしている
スマホやゲームの時間が日常生活を侵食し、睡眠時間を削るような生活をしている中学生は多いのかもしれません。
こういった生活は心身の成長に取り返しのつかない影を落とします。
寝る2時間前にはスマホやゲームをするのを止めましょう。
削るべきは睡眠ではなく、スマホやゲームの時間だということを保護者はきちんと子どもに伝えていかなくてはなりませんね。
保護者の帰宅時間が遅い
両親とも働いている家庭も多く、帰宅時間が本来なら中学生の就寝時刻といった方もあるでしょう。
保護者の生活スタイルを子どもの生活時間に支障のないようにしたいものです。
保護者の帰宅時間が遅い場合でも子どもだけ食事を早く取らせるようにしたり、テレビは遅い時間になったら保護者の方も見ないようにしたりすることが必要です。
子どもが睡眠不足にならない環境をつくってあげることが大切ですね。
ホルモンバランスの変化
成長ホルモン、メラトニン、セイロトニンなどの睡眠と特に関わりあいの深いホルモンは、およそ1日のリズムで分泌されています。
睡眠不足や不規則な睡眠リズムが続くとホルモンの分泌に影響し、イライラ・攻撃性が高くなる・無表情など情緒面に影響が出てきます。
睡眠を十分にとって、ホルモンバランスを保ち、安定した精神状態で過ごせるようにしましょう。
中学生の睡眠障害を予防する方法

中学生の睡眠障害を予防するにはどうしたらよいでしょうか。
ここでは、中学生の睡眠障害を予防する具体的な方法を説明します。
朝型の生活リズムにする
朝型の生活リズムにし、休日もそれを崩さないことが大切です。
学校がないと昼すぎまで寝てしまうということもあるかもしれませんが、それを続けるのは止めましょう。
夏休みなどの長期の休み、不登校などで連続して「遅起き」になると体内時計を調整できなくなり、昼夜が逆転してしまう恐れがあります。
朝型の生活リズムを作り、それを守りましょう。
決まった時間に起きるようにする
起きる時間が毎日マチマチでは体内時計のリズムが一定しません。
決まった時刻に起きて、体内時計のリズムを整えましょう。
決まった時間に起きることで、自然と夜になると眠くなり、決まった時刻に眠れるようになります。
自分で決まった時刻に起きれるようになるまでは、家族の声掛けも大切です。
バランスの良い朝食を食べる
朝食をしっかり食べることは体を目覚めさせ、脳を活発に働かせるためにとても大切です。
バランスの良い朝食を食べて、午前中からしっかり活動できるようにしましょう。
起きてすぐにはお腹は空かないので、朝食の30分前には起きるようにしましょう。
しっかりバランスの良い朝食を食べることが、朝決まった時間に起きるきっかけにもなります。
セロトニンを増やすためにバナナを食べる
セロトニンは睡眠を促すホルモンであるメラトニンを生成させます。
バナナにはセロトニンの材料である必須アミノ酸であるトリプトファンが含まれているほか、ビタミンB6、炭水化物のすべてを含んでいるため、効率的にセロトニンを生成します。
バナナだけををたくさん食べれば良いというわけではないので、プラスアルファで摂取という形が望ましいでしょう。
起床後、日光を浴びるようにする
起床後、太陽の光を浴びることで、1日がほぼ24時間周期の体内時計がリセットされます。
起床時の体内時計のリセットは、夜に自然と眠る準備の始まりです。
朝の光が体内時計を整え、寝つき、睡眠の安定につながります。
起床後すぐ、カーテンなどを開けて日光を浴びるようにしましょう。
就寝前にリラックスできる環境を整える
緊張や不安があったり、興奮していたりするとなかなか眠りにつくことができません。
寝る前に体がリラックスした状態になる環境をつくる工夫が必要です。
室内を適温の20℃前後の温度、照明は暖色系の照明、戸外の音が気になる場合は防音カーテンを使うなどして寝室環境を整えましょう。
さらにスマホやゲームは寝る2時間前には使用を止めましょう。
からだや季節に合った枕や寝具を整えることも大切です。
からだや気持ちをリラックスさせ、良質な睡眠を取るために、必ずパジャマなどに着替え、部屋着などのままで寝ないようにしましょう。
信頼できる人と会話して不安を取り除く
家族、信頼できる友人、尊敬している教師など信頼している人と会話して不安を取り除きましょう。
話題は何でもよいです。
悩みをストレートにぶつけてもいいし、話題は今日あったできごとや朝ごはんのおかずでもよいのです。
話す内容ではなく、話すことに意味があるので、信頼できる人と会話しましょう。
不眠で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。睡眠障害はさまざまなことが原因で眠れなくなってしまいます。睡眠障害にはどのような原因があるのでしょうか?本記事では、睡眠障害の原因について以下の点を中心にご紹介します。 睡眠障害・[…]
中学生の睡眠障害の症状をチェック

中学生に多い睡眠障害には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、睡眠障害の具体的な症状をチェックします。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群では、寝ている間にいびきや無呼吸の症状が現れます。
原因は、アデノイドや扁桃腺肥大によることが多いです。
治療方法は、アデノイド切除術や扁桃腺摘出が挙げられます。
また、肥満により発症するケースも多くあります。
その場合は、高血圧や糖尿病などの、生活習慣病が伴っていることもあるので注意しましょう。
不眠症
不眠症は、寝つきが悪い、途中で目覚めるなどの症状が見られます。
十分な睡眠が取れないことにより、疲れが取れないことや、集中力が低下することもあります。
睡眠障害の原因になる、生活リズムの乱れやスマホの使用がないか、チェックしましょう。
また、薬の副作用やうつ病などの、精神疾患が原因になることもあります。
過眠症
過眠症は、夜間に十分な睡眠を取っているにもかかわらず、日中に眠気が生じる症状です。
日中に耐え難い眠気を感じることで、学校生活や勉強に支障をきたします。
過眠症かどうかは、日中の眠気をチェックして判断します。
過眠症の中でも、ナルコレプシーは、日中に突然眠ってしまう睡眠発作が特徴です。
また、笑ったり驚いたりしたときに突然体の力が抜けてしまう、情動脱力発作が起こることもあります。
ナルコレプシーの原因は、覚醒を維持するホルモンが低下していることです。
中学生の睡眠障害のケース別対処法

不眠症や過眠症になった際の、対処法を知っておくとよいでしょう。
ここでは、自分でも行える対処法についてチェックします。
不眠症の場合
不眠症を治すためには、寝る前にスマホやパソコンを見ないことが大切です。
また、毎日の就寝時間と起床時間を一定にすると、体内時計が整えられます。
寝る前は、リラックスした状態で眠ることを心がけましょう。
過眠症の場合
朝に太陽の光を浴びると、体内時計を整えることができます。
また、日中は適度に体を動かしましょう。
生活習慣を整えると、症状が改善されることが多いです。
スポンサーリンク
中学生に必要な睡眠時間

中学生に必要な睡眠時間は、何時間くらいなのでしょうか。
必要な睡眠時間の目安と、睡眠不足により引き起こされる影響を見ていきます。
必要な睡眠時間
14~17歳に必要な睡眠時間は、8~10時間が目安です。
中学生は成長期なため、成人よりも多くの睡眠を必要とします。
睡眠不足による影響
睡眠不足になると、日中の生活にも影響が出るようになります。
どのような影響が出るのか、知っておくとよいでしょう。
学習面
睡眠が十分に取れていないと、集中力の低下に繋がります。
集中力の低下は、勉強の妨げになるでしょう。
そのため、記憶力が低下したり、計算ミスが増えたりすることが考えられます。
身体面
睡眠不足になると、成長ホルモンが正常に分泌されなくなります。
成長ホルモンの働きは、疲れた体を回復し、ストレスを解消することです。
また、発育を促し、体を成長させる働きもあります。
精神面
睡眠不足になると、自律神経が乱れて情緒不安定になります。
自律神経は、交感神経と副交感神経からなるものです。
自律神経のバランスが悪くなると、体や心にも影響が出ます。
睡眠が足りなくなると、交感神経が優位になり、心身が不安定になるでしょう。
スポンサーリンク
仮眠も中学生の睡眠障害をもたらす?

中学生の睡眠障害に、仮眠は関係しているのでしょうか。
子供を対象にした睡眠調査では、午前中に不調がある子供は、前日の帰宅後に仮眠をとっていることがわかりました。
このことから、仮眠が睡眠障害の原因になることがわかります。
スマホの使用時間も、睡眠障害に大きく関わることがわかりました。
スマホを見る時間が長くなるほど就寝時間が遅くなり、朝起きることに苦痛を感じる子供が増えています。
また、深夜0時以降に寝ている中学生は、20%以上を占めることがわかっています。
参考:睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との関係性に関する調査の結果(概要)
スポンサーリンク
中学生の睡眠障害をチェックして当てはまった場合にすること5選

睡眠障害をチェックして当てはまった場合にどういったアプローチをすればよいかについて簡単に解説します。
睡眠障害にはさまざまな病態があり、治療や改善のために必要なのは、症状が出るタイミングや頻度の自覚です。
その上で思春期外来や睡眠外来など専門医の診療を受けられる病院の受診をおすすめします。
睡眠を含めた一日の行動を記録する
自分の睡眠パターンや習慣、生活リズムを把握しましょう。
就床時刻、起床時刻はだいたい一定なのか、変動するのか、睡眠時間は何時間なのか、就床前の行動の特徴は何か、よく眠れないことと関連するものは何か(刺激物やカフェイン類を摂ったか、精神的に興奮する行動はなかったかなど)について、自分の身を振り返ってみるのです。
1週間続けて記録することによって、睡眠や生活のリズムを管理することができるようになります。
記録するだけで、睡眠障害の原因や改善の方法が分かることもあります。
記録をする際は本人の責任だけにせず、家族の協力も必要です。
自分なりの対応策をとっても睡眠障害が改善しない場合は、記録を持参して医療機関を受診しましょう。
どのような状況で眠気を感じるか振り返ってみる
どのような状況の時に眠気を感じるか生活を振り返ってみましょう。
授業中、乗り物の中、帰宅後など決まっているのか、突然、感じるのか、またその程度はどのくらいか、我慢できるのか、できないほどなのかなどを知ることで原因を知る手掛かりにもなります。
中学生くらいだと自分の体調をうまく表現できない場合もあります。
そのような場合は家族が協力してあげましょう。
突然、予兆なく眠気を感じ、眠ってしまうなど症状が日常生活に支障をきたしている場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
1週間だけ頑張って朝型の生活に変えてみる
特に目立って日常生活に支障が生じていない場合は、1週間だけ頑張って朝型の生活に変えてみましょう。
最初は辛いかもしれませんが、頑張って続けているうちに、疲れて夜には眠気が来るようになり、次第にしっかり眠れるようになります。
どうしても眠気が辛い場合は15分程度の昼寝をしましょう。
寝過ぎは禁物です。
およそ1週間試して効果が出なければ医療機関を受診しましょう。
炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく食べる
成長期には体をつくるためにさまざまな食べ物を摂取しますが、大人と違ってバランスを考えて食事を摂取するような環境下にありません。
家庭で作られたものを食べるか、自分で買って食べるかですが、バランスよりも食べたいものを優先的に摂取する傾向にあります。
その結果、栄養素が偏ってしまうということもあり得ます。
普段の食事を治療と考え、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく食べましょう。
睡眠外来を受診する
緊急を要する症状のある場合のほか、日常生活の改善を一定期間試みても改善しなかった場合、医療機関への受診をおすすめします。
思春期外来や睡眠外来など専門医の受診が無理な場合は、15歳までは小児科が窓口なので、小児科を受診します。
寝付けない、朝起きられないなどの症状があり不登校となっている場合は、児童精神科も対応可能です。受診の場合は、睡眠を含めた一日の行動記録があるととても役立ちます。
是非、持参しましょう。
中学生の睡眠障害のチェックのまとめ

ここまで中学生の睡眠障害のチェックについてお伝えしてきました。
中学生の睡眠障害のチェックをまとめると以下の通りです。
- 疲れが取れないことや、寝起きが悪いことがあるかチェックする
- 睡眠時間が足りないことや、スマホを長時間使っているかチェックする
- 中学生の睡眠障害は、スマホの使用を控えたり、朝に太陽の光を浴びることで改善される
- 中学生は仮眠を取ると、次の日の朝に不調が起こることがある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
睡眠の質を上げるブレスレット「フィリップスタイン」とは?

フィリップスタインとは、就寝30分前に腕につけて眠るだけで、翌日のパフォーマンスの集中力の向上などが期待できるブレスレットです。
睡眠状態に近い周波数を発生させて、睡眠の質をサポートしてくれます。
「最近よく眠れないな」という方はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。