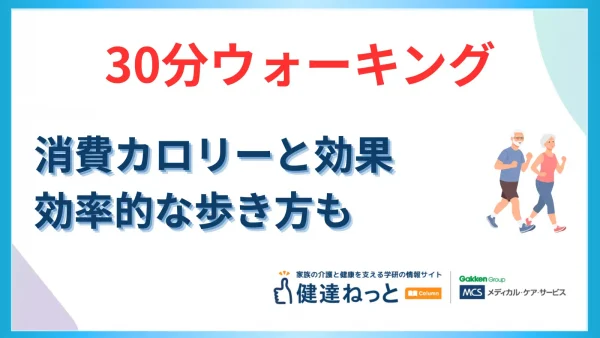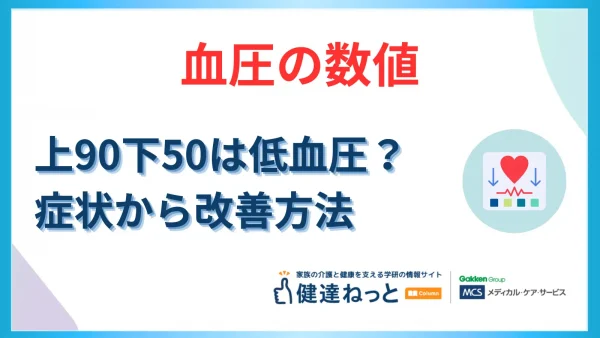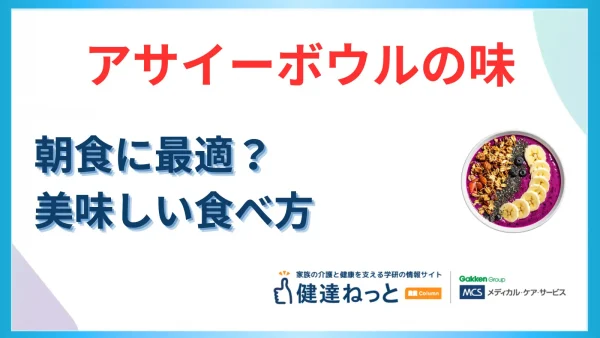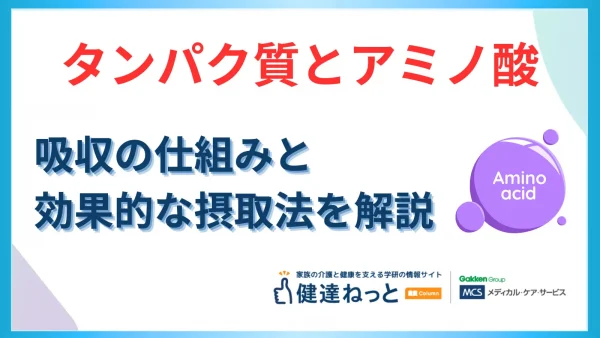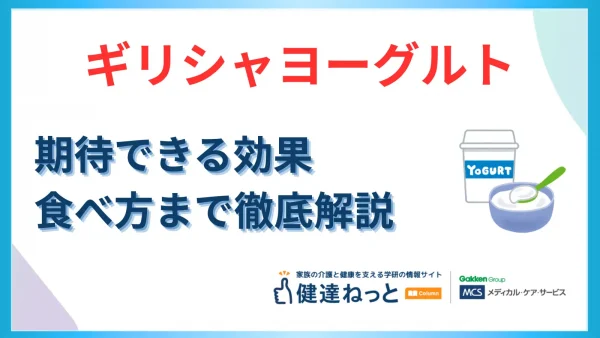「o157ってどのような症状が現れるの?」
「o157が重症化したらどうなる?」
o157に感染した方や身の回りにo157に感染者がいる方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、o157の重症化リスクや感染対策などについて以下の点を中心に詳しく解説します。
- o157の症状や潜伏期間
- o157に感染すると重症化しやすい人
- 家庭でできるo157の感染予防策
o157の症状や感染リスクについてご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
o157(腸管出血性大腸菌)とは?

初めに、o157(腸管出血性大腸菌)について解説します。
o157とは、腸管出血性大腸菌の一種です。
o157は、強いベロ毒素を出し、腸や腎臓にダメージを与え、激しい腹痛や下痢、血便などの症状を引き起こします。
また、症状が重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を発症するリスクがあり、死に至るケースもあります。
o157は感染力が強く、o157の菌が少量でも体内に侵入すると感染します。
o157の感染リスクを少しでも下げるために、感染予防に努めることや食品の衛生管理が非常に重要です。
スポンサーリンク
o157の症状

次に、o157の症状について以下の4つの症状をご紹介します。
- 激しい腹痛
- 下痢/血便
- 発熱
- 吐き気/嘔吐
①激しい腹痛
o157の症状の1つ目は「激しい腹痛」です。
o157感染の代表的な症状で、他の胃腸炎とは異なり鋭い腹痛(刺すような腹痛)を感じます。
腹痛は、腹部全体または下腹部(腸が集中する部分)に集中して起こります。
その要因は、ベロ毒素が腸を刺激し、炎症を起こすことで腸管にダメージを与えるからです。
腹痛を放置すると、吐き気などを引き起こすだけでなく、重篤な合併症などに進展する可能性があるので、早めに医療機関などを受診をしましょう。
②下痢/血便
2つ目は「下痢/血便」です。
感染した直後は、通常の食中毒と似た水様性の下痢ですが、進行すると粘液や血液が混じることがあり、次第に血便に変わります。
1日に数十回の下痢をすることもあり、脱水症状のリスクが高くなります。
また、血便が出た場合、溶血性尿毒症症候群(HUS)の可能性があるため、早急に医療機関に相談しましょう。
③発熱
3つ目は「発熱」です。
o157に感染すると、37.5℃〜38.5℃程度の中等度の発熱の症状が現れます。
一般的な細菌性腸炎ほどの高熱(39℃以上)が出ることは、ほとんどありません。
しかし、o157の感染が進行して合併症を引き起こした場合に、高熱や体調の急激な悪化が見られることもあるため、注意が必要です。
発熱が数日続く場合は、一度医師に相談すると良いでしょう。
④吐き気/嘔吐
4つ目は「吐き気/嘔吐」です。
吐き気や嘔吐の症状は、o157に感染後、数時間から数日以内に現れることが多いです。
空腹時でも嘔吐を繰り返す場合があり、胃に何も残っていない状態で嘔吐することもあります。
下痢や腹痛の症状も同時に現れるため、急速に体力が低下し、免疫力も弱ります。
また、水分を摂ることが難しくなり、脱水症状を引き起こすこともあるでしょう。
o157の初期症状や食中毒の症状に関しては、次の記事でも詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
食中毒は高温多湿な夏季に起こるものというイメージがあります。ですが食中毒には細菌性とウイルス性があり、ウイルス性の食中毒は季節を問いません。食中毒にはどのような症状があるでしょうか?食中毒になったときはどうすればよいでしょうか?本記事で[…]
感染後の潜伏期間

続いて、o157の潜伏期間についてご紹介します。
o157感染後の潜伏期間は、平均1〜5日程度です。
感染後は徐々にo157の菌が徐々に増えて行くため、潜伏期間中は感染者本人が症状を感じないこと(無症状)が多いです。
そのため、潜伏期間に感染が拡大する可能性が高くなります。
中には、初期症状が軽い場合もあり、症状を放置してしまう方もいます。
しかし、進行すると血便や溶血性尿毒症症候群(HUS)などを引き起こし、重篤化するリスクもあるでしょう。
子供や高齢者は重症化しやすい

次に、子供や高齢者が重症化しやすい理由について解説します。
子供や高齢者がo157に感染すると重症化しやすく、場合によっては命に関わることがあります。
子供の場合は、腸管が未発達のため抵抗力が弱く、o157に感染すると合併症を引き起こしやすくなるからです。
また、症状の進行が早く、下痢や嘔吐症状により、短時間で重度の脱水や血便などの症状が現れます。
高齢者の場合は、免疫力や腎機能が低下したり、基礎疾患があったりするため、o157に感染すると重症化しやすくなるからです。
他にも、o157に感染すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)という重篤な合併症を発症する可能性があります。
溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症すると、赤血球の破壊(溶血)や腎不全、血小板減少を引き起こし、場合によっては命に関わるでしょう。
子供や高齢者は、免疫力や臓器の機能が弱いため、感染が進行すると重篤な合併症を起こす可能性が高いため、迅速な対応と予防が重要となるでしょう。
o157に感染する原因となる食品

それでは、o157に感染する原因となる食品について、以下の2つを解説していきます。
- 生肉などの加熱されていない食品
- 二次汚染された食品
①生肉などの加熱されていない食品
o157に感染する原因の食品の1つ目は「生肉などの加熱されていない食品」です。
o157に感染する可能性が高くなるのは、主に加熱が不十分な食品を食べるからです。
例えば、加熱が不十分な肉料理には、ユッケ、タタキなどの生肉やステーキのレアなどが挙げられます。
牛の腸内や表面に存在するo157の菌が存在するため、解体処理の際に肉に付着することがあります。
そのため、なるべく加熱して食べることをおすすめします。
また、未殺菌の牛乳やハム、ソーセージなども感染の可能性があるため、食べる前には十分に加熱されていることや殺菌処理をされていることを確認しましょう。
②二次汚染された食品
2つ目は「二次汚染された食品」です。
o157は、二次汚染された食品からも感染する可能性があります。
二次汚染とは、o157の菌が生肉や汚染された調理器具から他の食品へ移ることです。
例えば、調理中に汚れた手や調理器具で野菜やフルーツに触ったり、生野菜や果物を洗うときに汚染された水を使ったりすることでo157に感染する可能性があります。
二次汚染を防ぐためには、生肉や生野菜などの取り扱いに十分に気をつけ、調理器具や手の衛生を保つことが重要です。
特に、食品を触る前後やトイレ後の手洗いは徹底して行いましょう。
調理後の保存状態や、家庭内での感染予防をして、食品の二次汚染を防ぎましょう。
食中毒の原因に関しては、次の記事でも詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。
家庭でできる予防策

続いて、家庭でできるo157の予防策を6つ紹介します。
- 手洗いうがいの徹底
- 食材は新鮮な内に食べる
- 調理器具の消毒をする
- 調理器具は使い分ける
- 低温保存をする
- 加熱処理をする
①手洗いうがいの徹底
家庭でできる予防策の1つ目は「手洗いうがいを徹底すること」です。
生肉や魚介類を触った後は、石鹸で20秒以上、手を洗いましょう。
特に、指の間や爪は菌が溜まりやすいため、洗い忘れがないように丁寧に洗います。
できれば、調理中は、食材ごとにこまめに手を洗うことをおすすめします。
また、トイレ後や動物などに接触した場合も手洗いを忘れず行いましょう。
②食材は新鮮な内に食べる
2つ目は「食材は新鮮な内に食べること」です。
食材を新鮮な内に食べることは、菌の繁殖を防ぎ、食中毒リスクを減らすために非常に重要です。
購入後は、できるだけ早く使い切りましょう。
特に、生肉や魚は買ったその日に調理することが理想です。
また、野菜や果物も、保存中に鮮度が落ちると傷んで菌が繁殖しやすくなるため、早めに食べるよう心がけましょう。
その日に調理したり食べられなかったりした時は、賞味期限や消費期限を守り、適切な温度で保管するとo157に感染する可能性が低くなります。
③調理器具の消毒をする
3つ目は「調理器具の消毒をすること」です。
o157の感染を防ぐために、調理器具をしっかり消毒することが重要です。
家庭でできる消毒方法には、熱湯消毒や塩素系漂白剤による消毒、アルコール消毒などがあります。
また、定期的な調理器具の消毒を習慣化することで、家庭でのo157感染を予防できます。
他にも、肉や魚を切った後は包丁やまな板を必ず洗浄と消毒をすると、より感染を防げます。
調理器具に適した消毒方法で、o157の感染予防をしましょう。
④調理器具は使い分ける
4つ目は「調理器具は使い分けること」です。
調理器具を使い分けることで、o157や他の食中毒菌の二次感染を防げます。
例えば、包丁やまな板は、生肉用や魚用、野菜/果物用と食材ごとに分けることがおすすめです。
どうしても一枚のまな板を使う場合は、生肉を切った後はすぐに洗浄/消毒をするといいでしょう。
調理器具の使い分けを徹底することで、o157などの二次汚染のリスクを減らせます。
特に、生肉を扱った後は器具の洗浄と消毒をこまめに行うことや食材ごとに専用の道具を用意するようにしましょう。
⑤低温保存をする
5つ目は「低温保存をすること」です。
低温保存は、o157などの食中毒菌の繁殖を抑えるための基本的な対策です。
購入した食材は、帰宅後すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れると良いでしょう。
また、調理後に食べきれなかった料理はラップをして冷蔵庫に入れることをおすすめします。
o157の感染リスクを低くするために、冷蔵庫や冷凍庫を正しく使いましょう。
⑥加熱処理をする
6つ目は「加熱処理をすること」です。
適切な加熱は、o157の感染予防で最も効果的とされる方法の一つです。
o157などの食中毒菌は、75℃以上で1分以上の加熱で消失させられます。
食材を加熱するときは、中心部までしっかり火を通すことが重要です。
特に、肉の内部まで温度が届くように加熱しましょう。
また、温度計の使用やトング/器具の使い分けを徹底すると感染を防げます。
特に、焼き肉をするときは、十分に加熱を行い、生肉用のトングととりわけようのトングなど分けることを徹底しましょう。
食中毒予防3原則を知っておこう

最後に、食中毒予防の3原則について紹介します。
食中毒予防の3原則は、以下の通りです。
- 菌をやっつける
- 菌をつけない
- 菌を増やさない
①菌をやっつける
食中毒予防の3原則の1つ目は「菌をやっつけること」です。
菌をやっつけるために、加熱処理を十分に行うことが大切です。
食材は75℃以上で1分以上加熱し、中心部までしっかり火を通しましょう。
②菌をつけない
2つ目は「菌をつけないこと」です。
手洗いや器具の消毒、食品の取り扱いに注意を払い、清潔な環境を維持することが不可欠です。
調理前や食事前、トイレの後など、手をしっかり洗い、清潔に保ちましょう。
また、調理器具や器具の消毒や購入した食品などの取り扱いには十分に注意することが重要です。
③菌を増やさない
3つ目は「菌を増やさないこと」です。
o157の菌を増やさないために、食品は冷蔵庫で4℃以下、冷凍庫で-18℃以下に保存しましょう。
常温放置を避け、調理後の食品は、2時間以内に冷蔵庫に入れ、長時間常温に置かないようにします。
また、大きな鍋で調理した料理は、冷却が遅くなるため、小分けにして冷やすなどの工夫が必要です。
スポンサーリンク
o157の症状に関するまとめ
ここまでo157の症状などについてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- o157の症状は、激しい腹痛や下痢/血便、嘔吐などがみられる
- 子供や高齢者は、o157に感染すると重症化する可能性がある
- 家庭でできる感染対策は、食中毒予防3原則を実践しよう
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。