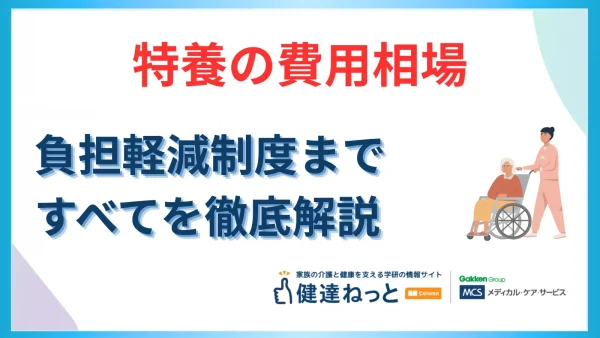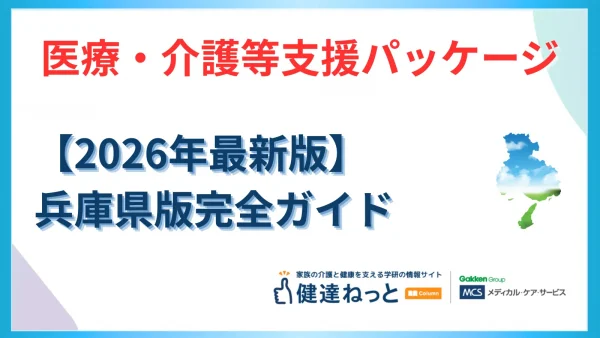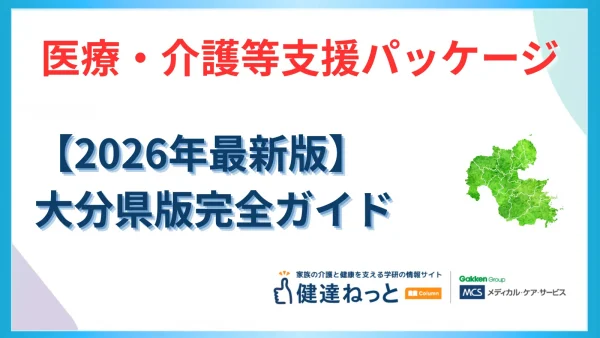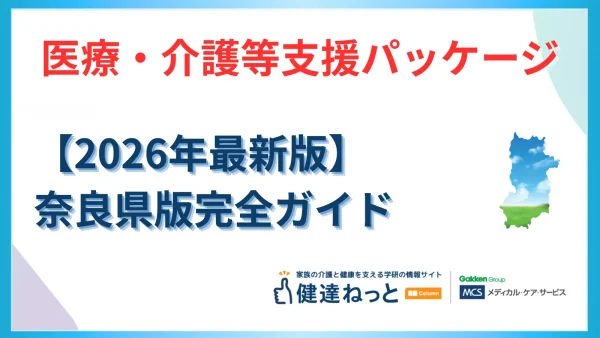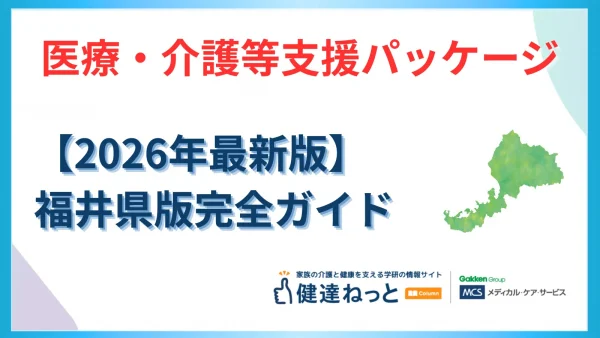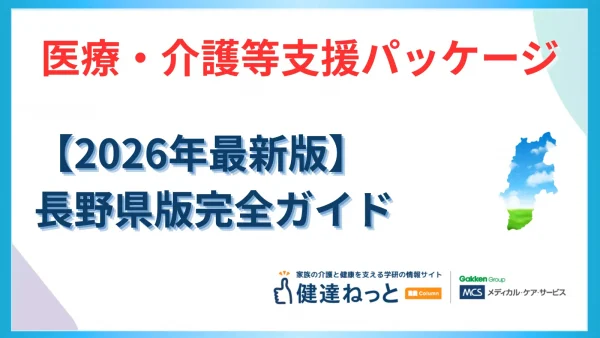特別養護老人ホームへの入居を考え始めた時、多くの方がこのような疑問や不安を抱えるのではないでしょうか。
- 親の年金だけで費用をまかなえるだろうか…?
- 費用が払えなくて、家族に迷惑をかけてしまわないか不安。
- 制度が複雑で、何から調べればよいのか分からない。
- 安さだけで選んで、サービスの質が低かったらどうしよう…。
大切なご家族のことだからこそ、費用への不安は尽きませんよね。
経済的な問題で最適な介護を諦めてしまったり、ご家族の関係がぎくしゃくしてしまったりするのは、あまりにも悲しいことです。
ご安心ください。
この記事では、そのような不安を解消し、ご家族全員が納得できる選択をするためのお手伝いをします。
この記事を読めば、以下のポイントが明確になります。
- あなたのケースでの具体的な自己負担額の目安
- 費用負担を劇的に軽くする5つの公的制度
- 今すぐできる、費用を抑えるための8つのアクション
- 費用だけで決めない、後悔しない施設選びのコツ
この記事を最後まで読めば、特養の費用に関する漠然とした不安が「納得の選択」へと変わるはずです。
専門的な知識を分かりやすく解説しますので、ぜひご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
スポンサーリンク
【結論】特別養護老人ホームの費用は月額8~20万円が目安!料金が分かる早見表
特別養護老人ホームの費用は、複数の信頼できる調査によると月額8~20万円程度が一般的な相場です。
しかし、この金額は後述する「利用者負担段階」や居室タイプ、要介護度によって大きく変動します。
まずは、ご自身の自己負担額がどのくらいになるのか、その仕組みと目安を把握しましょう。
まず知りたい自己負担額を決める「利用者負担段階」とは
特養の費用を理解するうえで最も重要なのが「利用者負担段階」です。
これは、世帯の所得状況に応じて定められた区分で、特に居住費や食費の負担額に大きく影響します。
令和6年8月1日から制度が改正され、利用者負担段階の区分が細分化されました。
| 負担段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階1 | 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超~120万円以下の方 |
| 第3段階2 | 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
| 第4段階 | 上記以外の方(市町村民税課税世帯の方) |
ご自身がどの段階に該当するかで、費用負担を軽減できる「負担限度額認定」の対象になるかが決まります。
この制度については、後ほど詳しく解説します。
特養の費用が決まる「4つの要素」
特養の月額費用は、主に以下の4つの要素を合計して算出されます。
これらの内訳を理解することで、なぜその金額になるのかが明確になります。
- 1.介護サービス費:介護サービスに対して支払う費用。介護保険が適用され、自己負担は原則1割(所得に応じて2~3割)です。
- 2.居住費:施設の家賃にあたる費用。部屋のタイプによって金額が異なります。
- 3.食費:日々の食事にかかる費用。
- 4.日常生活費:理美容代や個人の希望による特別なサービスなど、全額自己負担となる費用です。
これらの基本費用に加えて、施設の人員体制や提供するサービスに応じた「各種加算」が上乗せされる場合があります。
居室タイプ・要介護度別の月額費用シミュレーション早見表
それでは、実際にどのくらいの費用がかかるのか、モデルケースを見ていきましょう。
以下の表は、所得が平均的な「第4段階」の方を想定した、居室タイプ・要介護度別の自己負担額の目安です。
| 多床室(相部屋) | 従来型個室 | ユニット型個室 | |
|---|---|---|---|
| 要介護3 | 約10.2万円 | 約11.0万円 | 約13.9万円 |
| 要介護4 | 約10.8万円 | 約11.6万円 | 約14.6万円 |
| 要介護5 | 約11.4万円 | 約12.2万円 | 約15.2万円 |
※自己負担1割、30日利用の場合の目安
この表はあくまで目安であり、非課税世帯の方(第1~3段階)は、後述の軽減制度を利用することで自己負担額をさらに抑えることが可能です。
スポンサーリンク
特別養護老人ホームの費用の仕組みを分解して詳細を解説
月額費用の目安を把握したところで、次はその内訳をひとつずつ詳しく見ていきましょう。
費用の仕組みを正しく理解することが、ご自身に合った施設選びと賢い費用計画の第一歩です。
それぞれの項目がどのように計算されているのかを解説します。
介護サービス費
介護サービス費は、介護保険サービスの対価として支払う費用のことです。
この費用は、入居者の要介護度と施設の体制によって国が定めた「単位」で計算され、自己負担額は所得に応じて1割から3割となります。
2024年度の自己負担割合判定基準:
- 1割負担:年金収入等280万円未満
- 2割負担:年金収入等280万円以上340万円未満
- 3割負担:年金収入等340万円以上
要介護度が高いほど必要なケアが多くなるため、介護サービス費も高くなるのが一般的です。
具体的な自己負担額の目安は以下の通りです。
| 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 | |
|---|---|---|---|
| 要介護3 | 約21,360円 | 約42,720円 | 約64,080円 |
| 要介護4 | 約23,400円 | 約46,800円 | 約70,200円 |
| 要介護5 | 約25,380円 | 約50,760円 | 約76,140円 |
※従来型個室、30日利用の場合の目安
この費用は、介護保険の限度額制度についての範囲内で利用するサービスに対して支払います。
居住費・食費
居住費は施設の部屋代、食費は1日3食の食事代にあたります。
これらの費用は介護保険の適用外で、原則として全額自己負担となります。
ただし、所得の低い方は後述する「負担限度額認定」を受けることで、負担を大幅に軽減することが可能です。
居住費は、プライバシーの確保度合いによって金額が変動します。
- 多床室:定員2名以上の相部屋。料金が最も安い。
- 従来型個室:居室は個室だが、食堂やリビングは共有。
- ユニット型個室:全室個室で、10人程度の少人数グループ(ユニット)ごとに共有スペースがある。料金が最も高い。
食費は、栄養バランスの取れた食事が提供され、国が定める基準額(1日1,445円程度)を元に各施設が設定しています。
日常生活費
日常生活費は、介護保険の対象外となる個人的な費用で、全額が自己負担です。
具体的にどのような費用が含まれるかは施設によって異なりますが、一般的には以下のような項目が挙げられます。
- 理美容代
- 新聞、雑誌などの購読料
- クリーニング代
- 個人の希望によるレクリエーションの材料費や参加費
- 嗜好品(お菓子やお酒など)の購入費
多くの施設では、おむつ代や基本的なリネン交換費用は施設サービス費に含まれており、別途請求されることはありません。
入居前に、どこまでが基本料金に含まれ、どこからが自己負担になるのかをしっかり確認しておきましょう。
各種加算
各種加算とは、手厚い人員配置や専門的なケアを提供している施設が、基本の介護サービス費に上乗せして請求できる費用のことです。
加算がある施設は、それだけ質の高いサービスを提供している証ともいえます。
どのような加算があるかは施設の人員体制や機能によってさまざまですが、代表的なものには以下のようなものがあります。
- 夜勤職員配置加算:国の基準より多くの夜勤職員を配置している場合に加算されます。
- 看取り介護加算:人生の最期を施設で迎えるための体制を整えている場合に加算されます。
- 個別機能訓練加算:理学療法士などを配置し、個別のリハビリ計画に基づいた訓練を実施している場合に加算されます。
これらの加算は、施設の専門性や手厚さを示す指標にもなります。
費用だけでなく、どのようなケアを受けられるのかという視点で確認することが大切です。
日本では少子高齢化が社会問題となっており、高齢者の割合が年々増加しています。そんな中、認知症の高齢者を専門にケアする施設も増えてきました。その施設の一つが「グループホーム」です。今回の記事では、「家族が認知症になって自宅で介護を続[…]
特別養護老人ホームの費用負担を劇的に軽くする5大制度
特養の費用は公的施設のため比較的安いといわれますが、それでも月々の負担は決して軽くありません。
しかし、ご安心ください。
国や自治体には、費用負担を軽減するためのさまざまな制度が用意されています。
これらの制度を賢く活用することで、経済的な不安を大幅に和らげることが可能です。
負担限度額認定で非課税世帯の居住費・食費が安くなる
「負担限度額認定」は、費用軽減制度の中で最も重要といえる制度です。
これは、所得や資産が一定基準以下の非課税世帯の方(利用者負担段階が第1~3段階の方)を対象に、居住費と食費の自己負担額に上限を設けるものです。
令和6年8月1日からの改正により、居住費の負担限度額が60円(日額)引き上げられました。
ただし、第1段階の多床室利用者については負担額は据え置かれています。
| 負担段階 | 居住費(ユニット型個室) | 食費 | 合計(月額) |
|---|---|---|---|
| 軽減なし(第4段階) | 60,180円 | 43,350円 | 103,530円 |
| 第3段階2 | 40,200円 | 19,500円 | 59,700円 |
| 第3段階1 | 39,600円 | 19,500円 | 59,100円 |
| 第2段階 | 26,400円 | 11,700円 | 38,100円 |
| 第1段階 | 26,400円 | 9,000円 | 35,400円 |
※30日利用の場合の目安(令和6年8月改正後)
資産要件(令和6年8月改正):
- 第1段階:預貯金等1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)
- 第2段階:預貯金等650万円以下(夫婦1,650万円以下)
- 第3段階1:預貯金等550万円以下(夫婦1,550万円以下)
- 第3段階2:預貯金等500万円以下(夫婦1,500万円以下)
この制度を利用するには、市区町村への申請が必要です。
詳しくは「介護保険負担限度額認定証の申請方法」の記事も参考にしてください。
高額介護サービス費で月々の自己負担に上限を設ける
高額介護サービス費は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割の部分)が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
この制度により、介護サービスの利用が増えても、負担が青天井になるのを防げます。
2024年現在の上限額は世帯の所得状況によって区分されています。
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
| 市町村民税課税世帯(上記以外) | 44,400円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 |
| 非課税世帯で所得が低い方等 | 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者など | 15,000円 |
一度申請すれば、該当する月には自動的に払い戻しが行われる自治体が多いです。
高額介護サービス費の詳細と申請方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
医療費・介護費も高い場合には高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、その額が所得に応じた基準額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
この制度は、特に医療機関への受診が多く医療費もかさみがちな方や、同じ世帯に介護サービスを利用している方が複数いる場合に、大きな助けとなります。
基準額は加入している医療保険や所得によって異なります。
申請先はご自身が加入している公的医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険組合など)の窓口となります。
社会福祉法人などによる低所得者向けの独自減免
社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームでは、独自の利用者負担軽減制度を設けている場合があります。
これは、特に生計が困難な方を対象に、介護サービス費の自己負担額や居住費、食費などをさらに軽減する制度です。
対象となる条件は以下の通りです。
- 市町村民税が世帯非課税であること
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
対象となる方は、利用料の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減されます。
すべての施設で実施しているわけではないため、入居を検討している施設に確認が必要です。
確定申告で税金が戻ってくる「医療費控除」
特別養護老人ホームで支払った費用の一部は、確定申告の際に医療費控除の対象となり、所得税や住民税が還付・軽減される可能性があります。
特養の場合、「施設サービスの対価として支払った自己負担額の2分の1」が医療費控除の対象として認められています。
控除を受けるためには、以下の点に注意が必要です。
- 施設が発行する、医療費控除の対象額が記載された領収書が必要。
- 食費や居住費、日常生活費は原則として対象外。
- 生計を同一にする親族が支払った場合も対象となる。
年末調整では手続きできないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
特別養護老人ホーム費用の医療費控除について、対象範囲や注意点を詳しく解説した記事もございます。
自分の場合はどう?特別養護老人ホームの費用に関する制度の申請と節約ロードマップ
さまざまな軽減制度があることは分かりましたが、「実際に自分はどうすればよいのか?」が気になるところですよね。
ここでは、制度を利用するための具体的な手続き方法から、年金で費用をまかなえるのか、さらに費用を抑えるための実践的なアクションプランまで、具体的なロードマップをご紹介します。
負担限度額認定の申請フローと必要書類チェックリスト
費用軽減の効果が最も大きい「負担限度額認定」は、必ず申請しておきたい制度です。
申請から認定証が交付されるまでの流れを把握しておきましょう。
申請フロー
- 申請窓口の確認:お住まいの市区町村の高齢者福祉担当課や介護保険担当課が窓口です。
- 申請書類の入手:窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードします。
- 書類の記入・提出:申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出します。
- 審査:市区町村が所得や資産の状況を審査します。
- 認定証の交付:認定されると「介護保険負担限度額認定証」が郵送で届きます。
- 施設への提出:入居する施設に認定証を提示することで、軽減措置が適用されます。
申請には、本人と配偶者の所得や資産を証明する書類が必要です。
スムーズに手続きを進めるために、事前に準備しておきましょう。
| 必要書類の例 | 確認内容 |
|---|---|
| 申請書 | 自治体指定の様式 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 介護保険被保険者証 | – |
| 所得証明書類 | 課税証明書、年金の源泉徴収票など |
| 資産証明書類 | 預貯金通帳の写し(全ページ)、有価証券の残高が分かるものなど |
※自治体によって必要書類は異なりますので、必ず事前にご確認ください。
「年金だけで足りる?」ケース別の収支シミュレーション
多くの方が不安に感じるのが、「年金だけで特養の費用を支払えるのか」という点でしょう。
ここでは、年金の種類別に収支のシミュレーションを見ていきます。
2024年度の年金受給額データ:
- 老齢基礎年金の満額:年間816,000円(月額68,000円)
- 老齢厚生年金(男性):平均月額約166,600円
- 老齢厚生年金(女性):平均月額約107,200円
国民年金(老齢基礎年金)のみの場合
- 平均月額受給額:約6.8万円
- 特養の費用(軽減後・多床室):約6万円~
- 収支:軽減制度を活用すれば年金だけでまかなえる可能性があります。
厚生年金を受給している場合
- 平均月額受給額:約16.7万円(男性)、約10.7万円(女性)
- 特養の費用(軽減後・多床室):約6万円~
- 収支:年金だけで十分まかなえる可能性が高い。
国民年金のみの場合でも、第1~3段階の軽減制度を活用することで、年金の範囲内で特養を利用できる可能性があります。
まずはご自身の年金受給額を正確に把握することが重要です。
費用をさらに抑える8つのアクションプラン
公的な軽減制度に加えて、ご自身の工夫次第でさらに費用を抑えることも可能です。
今日から始められる8つのアクションプランをご紹介します。
居室タイプを再検討する
最も費用に影響するのが居室タイプです。
ユニット型個室はプライバシーが確保されますが、費用は高くなります。
多床室(相部屋)であれば、月々の費用を3~5万円程度抑えることが可能です。
ご本人の性格や希望、予算を総合的に考慮して、最適な居室タイプを検討しましょう。
自治体独自の助成制度を調べる
国が定める制度のほかに、自治体が独自に費用助成制度を設けている場合があります。
例えば、以下のような事例があります。
- 横浜市:特養や老健のユニット型個室の居住費を月額5,000円程度助成。
- 渋谷区:低所得世帯向けの独自減免制度を実施。
お住まいの市区町村のウェブサイトを確認したり、地域包括支援センターに問い合わせたりして、活用できる制度がないか調べてみましょう。
世帯分離を検討する
世帯分離とは、同じ住所に住みながら、住民票の世帯を分ける手続きのことです。
世帯分離を行うと、入居者本人の世帯が住民税非課税になる場合があり、その結果、利用者負担段階が下がり、特養の費用が大幅に安くなる可能性があります。
詳しくは世帯分離による介護費用の削減効果を解説した記事をご覧ください。
日常生活費を見直す
理美容や嗜好品の購入など、日常生活費は全額自己負担です。
施設によって提供されるサービスや料金は異なるため、入居前に確認し、不要な出費がないか見直してみましょう。
例えば、理美容は施設に頼むのではなく、ご家族が対応することで節約につながる場合もあります。
医療費のかかり方を確認する
特養には配置医師がいますが、専門外の診療や緊急時以外は外部の医療機関を受診することになります。
その際の通院介助費用や交通費が自己負担となる場合があります。
施設の協力医療機関や、医療連携の体制を事前に確認し、医療費がどのくらいかかるか把握しておくことが大切です。
介護保険外サービスを賢く使う
施設によっては、散歩の付き添いや個別の外出支援などを、介護保険適用外のオプションサービスとして提供している場合があります。
これらのサービスは便利ですが、利用すると費用がかさみます。
ご家族が面会時に対応するなど、本当に必要なサービスを見極めて賢く利用しましょう。
生活保護の申請を視野に入れる
年金収入が少なく、預貯金もほとんどないなど、どうしても費用が支払えない場合は、生活保護の申請も選択肢のひとつです。
生活保護を受給すると、介護サービス費の自己負担分やその他の費用が「介護扶助」「生活扶助」として支給されるため、自己負担なく特養に入居できます。
申請には厳しい審査がありますが、最終的なセーフティネットとして覚えておきましょう。
専門家に相談する
ここまでさまざまな方法をご紹介しましたが、ご自身の状況に最適な方法を見つけるのは簡単ではありません。
そのような時は、一人で悩まずに専門家に相談することが重要です。
お住まいの地域の「地域包括支援センター」や、担当のケアマネジャーは、公的な立場で親身に相談に乗ってくれます。
費用だけで選ぶのは危険!特別養護老人ホームの施設選び
費用を抑えることは非常に重要ですが、安さだけで施設を選んでしまうと、後悔につながる可能性があります。
「こんなはずではなかった」とならないために、費用以外の視点からも施設を総合的に判断することが大切です。
ここでは、後悔しない施設選びのための3つのポイントを解説します。
特養は本当に最適?老健や有料老人ホームとの違い
介護施設には、特養以外にもさまざまな種類があります。
それぞれの特徴を理解し、ご本人の心身の状態や目的に合った施設を選ぶことが重要です。
| 施設種類 | 特徴 | 費用の目安(月額) |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 終身利用が可能な「生活の場」。要介護3以上が原則。 | 8~20万円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設。入居は原則3~6か月。 | 10~16万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 介護サービスが充実した民間の施設。さまざまな価格帯がある。 | 15~30万円 |
より詳しい情報は「介護施設の種類と選び方ガイド」でも解説しています。
ご本人の状態やご家族の希望を整理し、最適な施設は何かを検討しましょう。
費用が安くても入れない入居条件と待期期間
特養は費用が比較的安いため人気が高く、すぐに入居できない「待機者」が多いのが現状です。
また、入居には原則として「要介護3以上」という条件があります。
2015年4月から、特養の新規入所は原則として要介護3以上に限定されました。
ただし、要介護1や2の方でも、認知症で日常生活に支障がある、家族による虐待の恐れがあるなど、やむを得ない事情がある場合は「特例入居」として認められることがあります。
特別養護老人ホームの入居条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
入居まで数か月から数年待つケースも珍しくないため、早めに申し込みをしつつ、待機期間中は他の施設や在宅サービスを利用するなどの計画が必要です。
重要事項説明書で絶対確認すべき費用のチェックリスト
入居契約を結ぶ前に、必ず「重要事項説明書」に目を通し、費用の詳細を確認しましょう。
後々のトラブルを避けるため、特に以下の点は重点的にチェックすることをオススメします。
- 追加料金が発生するケース:協力医療機関以外への通院介助費や、特別なレクリエーションの参加費など、どのような場合に追加費用がかかるか。
- 各種加算の詳細:どのような加算があり、月々いくらになるのか。
- 長期入院時の費用:入院した場合、施設の居住費や管理費は発生し続けるのか。
- 退去時の費用:居室の原状回復費用などが請求されることはないか。
- 費用の改定:介護報酬の改定などで、将来的に費用が変更になる可能性はあるか。
分からない点や不明瞭な点があれば、納得できるまで施設の担当者に質問することが大切です。
特別養護老人ホームの費用に関してよくある質問
ここでは、特別養護老人ホームの費用に関して、特に多く寄せられる質問にお答えします。
細かな疑問を解消し、不安なく施設選びを進めましょう。
本当にお金がない時はどうすればよい?
年金収入が少なく、預貯金もないなど、経済的に支払いが困難な場合は、まずお住まいの市区町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターに相談してみてください。
社会福祉法人による減免制度や、最終手段としての生活保護の申請など、利用できる制度についてアドバイスをもらえます。
決して一人で抱え込まず、公的な窓口に相談することが解決への第一歩です。
老健と特養、結局どちらが安い?
月額費用だけを比べると、老健(介護老人保健施設)と特養に大きな差はありません。
しかし、老健はリハビリをして在宅復帰を目指す施設であり、終身の利用はできません。
一方、特養は「生活の場」として最期まで暮らせる施設です。
施設の目的が異なるため、単純な費用の安さだけでなく、ご本人がどのような生活を送りたいのかという視点で選ぶことが重要です。
預貯金がいくら以上あると軽減制度は使えない?
居住費や食費の負担を軽減する「負担限度額認定」には、資産要件があります。
令和6年8月改正後の基準では、預貯金や有価証券などの合計額が、単身で500万~1,000万円以下、夫婦で1,500万~2,000万円以下であることが段階別の基準となります。
この基準額を超えると、たとえ収入が少なくても制度の対象外となるため注意が必要です。
正確な情報は市区町村の窓口でご確認ください。
要介護度が変わると、費用はどれくらい上がる?
要介護度が上がると、介護サービス費の自己負担額が増えます。
例えば、自己負担1割の方の場合、要介護3から要介護4に上がると月額約2,000円、要介護4から要介護5に上がると月額約2,000円、自己負担額が増えるのが一般的です。
ただし、高額介護サービス費制度があるため、負担額が上限を超えれば払い戻しを受けられます。
生活保護を受けていても入れる?
はい、生活保護を受給している方も特別養護老人ホームに入居できます。
その場合、介護サービス費は「介護扶助」から、居住費や日常生活費などは「生活扶助」から支払われるため、自己負担は原則としてありません。
入居を希望する場合は、まず担当のケースワーカーに相談し、市区町村と連携して手続きを進めることになります。
まとめ
この記事では、特別養護老人ホームの費用について、その仕組みから負担を軽減するための具体的な方法まで、網羅的に解説してきました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
特養の費用は月額8~20万円が目安ですが、「利用者負担段階」によって大きく変わります。
費用負担を軽減するためには、「負担限度額認定」や「高額介護サービス費」といった公的な制度を最大限に活用することが何よりも重要です。
さらに、世帯分離の検討や自治体独自の助成制度の活用など、ご自身の工夫次第で負担をさらに抑えられます。
しかし、最も大切なのは、費用だけで施設を決めないことです。
ご本人にとって最適なケアを受けられるか、安心して生活できる環境かを見極め、総合的に判断し、ご家族全員が「この施設でよかった」と心から思える選択をするようにしましょう。
情報収集や手続きで分からないことがあれば、ひとりで悩まずに地域包括支援センターなどの専門家に相談しましょう。
この記事が、あなたの費用に関する不安を解消し、納得のいく施設選びの一助となれば幸いです。
お近くの介護施設を探すこともできますので、ぜひご活用ください。