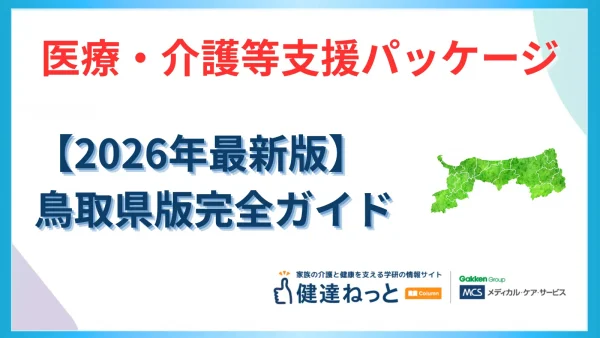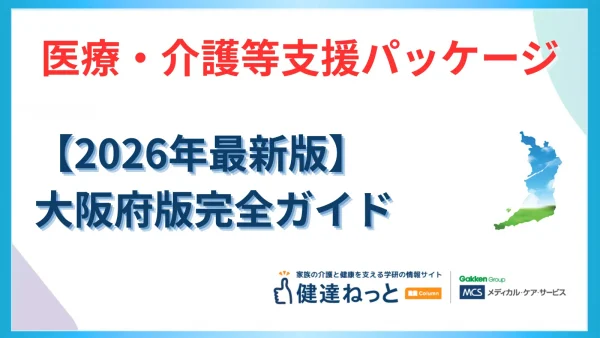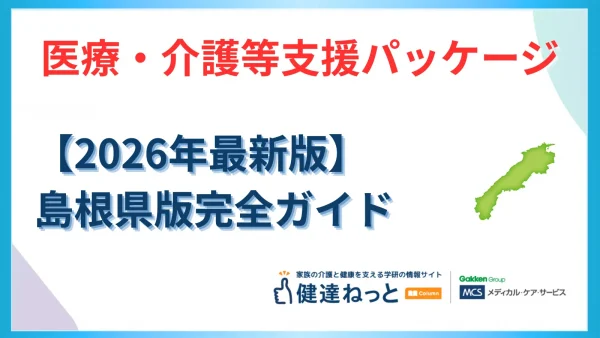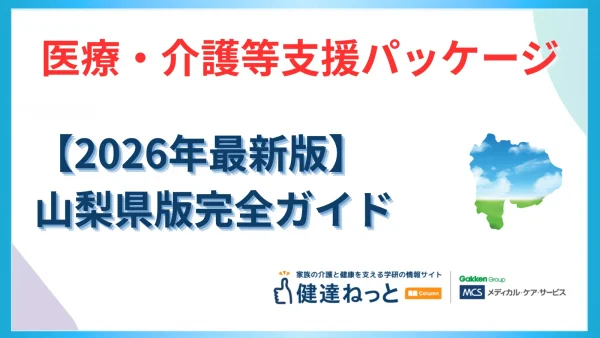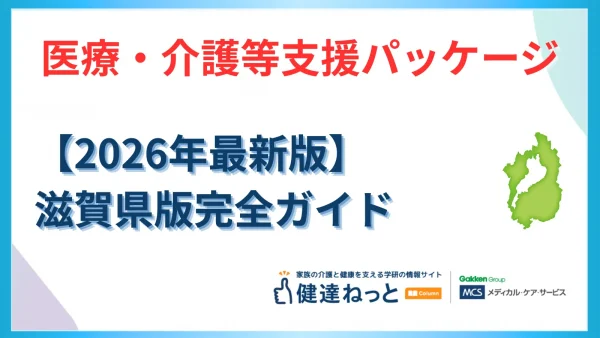介護予防サービスには大きく分けて、訪問介護と通所介護の2種類があります。
通所介護は在宅被介護者が寝たきりにならないためにも、近年特に重要視されています。
皆さんは通所介護が近年変化していることをご存知ですか?
この記事では通所介護サービスについて、下記のような内容を解説します。
- 介護予防の目的
- 通所介護の対象者と費用
- 多方面からサポートする介護予防サービス
介護予防について理解するための参考としていただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
最近同居中の祖父母が、体調不良を訴える頻度が多くて不安になりませんか?「要介護になる前に、予防する方法があるの?」と疑問を持つことがあると思いますが、実は高齢者の自立支援を補助する介護予防サービスがあります。本記事では、介護[…]
スポンサーリンク
介護予防とは
 介護予防とは、様々な訓練や活動を通じて要介護状態の予防に力を入れることを指します。
介護予防とは、様々な訓練や活動を通じて要介護状態の予防に力を入れることを指します。
高齢社会を迎えて増大する要介護者の数を抑え、長く健康に過ごすことを目的とします。
また、要介護者にも身体機能の回復と重症化の防止を図るため、介護予防サービスを提供します。
なお、介護予防サービスは平成29年度末に厚生労働省の予防給付サービスから各市町村の総合事業サービスへと移行されています。
高齢者の生活の質の向上を目指す
介護予防の取り組みにより、ご高齢の方々にとって生活の質が向上するよう目指します。
生活の質を高める観点から、介護予防では心身の自立に主眼を置いています。
具体的には、
- 全身の筋力を訓練で回復させる
- 生きがいを持つ
- 社会活動に参加する
以上の3点を中心にサービスを提供します。
運動機能の向上
介護予防の一環として、運動機能の向上を目標として活動しています。
具体的には、体操やレクリエーションなどの活動により、足腰や全身の筋力の回復を目指しています。
介護予防の対象となる高齢者は?
予防介護が必要な可能性のある高齢者の判断に役立てようと、厚生労働省にてチェックリストを作成しています。
以下にリストを表示しますので参考にしてみてください。
介護予防チェックリスト
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか |
| 2 | 日用品の買い物をしていますか |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか |
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか |
| 8 | 15分位続けて歩いていますか |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか |
| 11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか |
| 12 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか |
| 13 | お茶や汁物等でむせることがありますか |
| 14 | 口の渇きが気になりますか |
| 15 | 週に1回以上は外出していますか |
| 16 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか |
| 17 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか |
| 18 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか |
| 19 | 今日が何月何日かわからない時がありますか |
| 20 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない |
| 21 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった |
| 22 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる |
| 23 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない |
| 24 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |
日常生活はほぼ自立しているけれど自分で行うのに不安がある。しかし、なるべく施設に通わず今の暮らしを維持したい。「介護予防訪問看護のサービスを受ければ、良くなるの?」と疑問を持つことがあると思いますが、状態の悪化を防げる可能性がありま[…]
スポンサーリンク
介護予防の通所介護とは
 高齢者の増加に伴い、ニーズは年々多様化しています。
高齢者の増加に伴い、ニーズは年々多様化しています。
生活支援サービスの内容についても、より実際の生活に即したものが求められています。
そのため、厚生労働省が主体となる予防給付型の通所介護サービスは、平成29年に各市町村へと権限が移行され、総合事業の通所サービスとなりました。
地方自治体が主体となることで、より柔軟な運営が可能になりました。
利用者のニーズに沿えるようになり、従来の介護事業者だけではなく、
- NPO
- 協同組合
- 社会福祉法人
- ボランティア
なども参入して介護予防サービスや生活を支援しています。
近年、サルコペニアという疾患の認識が広まりつつあります。サルコペニアは老化現象の1種で、進行すると歩行困難や寝たきりに発展します。老化自体は避けられないものの、サルコペニアの予防で健康寿命を延ばすことは可能です。それではサル[…]
介護予防での通所介護(デイサービス)の利用について
 通所介護(デイサービス)は、平成29年に事業の主体が厚生労働省から地方自治体に変更されています。
通所介護(デイサービス)は、平成29年に事業の主体が厚生労働省から地方自治体に変更されています。
制度の変更により地域ごとのニーズに応えたサービスの提供が可能になり、利用しやすい環境が整いつつあります。
申請の仕方
介護予防(通所介護)サービスを利用する場合の申請手順を解説します。
通所介護の対象者は要介護1~5の認定を受けた方です。そのため、まずは要介護認定の申請を行う必要があります。
- 各市区町村の地域包括支援センターまたは、介護担当課と相談します。
- 担当職員の訪問調査を受けた後、コンピュータで一次判定を受けます。
- 一次判定の結果と主治医の意見書を基に「介護認定審査会」で要支援、又は要介護の必要度について最終的な判定がなされます。
- 地域包括支援センターで介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 介護予防(通所介護)サービス事業を開始します。
利用者の負担額
介護予防サービスの単価や利用負担額は、サービス内容に応じて各市区町村で決定します。
原則、月ごとにサービス利用料の1割を負担します。
また、所得に応じて2割または3割の負担になる場合もあります。
下の表は新潟市の例です。
介護予防通所介護相当サービス料金(新潟市の例)(自己負担は表示の1割/2割/3割)
| 総合事業対象者・要支援1・事業対象者 | 3,893円 | 1回:月3回まで |
| 16,954円 | 1月:月4回以上 | |
| 総合事業対象者・要支援2 | 4,005円 | 1回:月7回まで |
| 34,759円 | 1月:月8回以上 |
出典:新潟市2021年版介護保険サービスガイド『在宅で利用できるサービス』
出典:厚生労働省『介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要)』
超高齢化社会の現在では、ご家族の介護を在宅でされている方も増えています。そのような中でデイサービスは、在宅介護の負担を軽減し介護をされる方の社会参加の場にもなるなど大きな役割を担っています。しかし、デイサービスは具体的にどういっ[…]
介護予防の通所介護と通所リハビリの併用

通所リハビリテーションと通所介護の併用は、要介護1以上であれば利用可能です。
しかし、要支援1・2の場合は、予防給付の通所介護(デイサービス)が対象外になるため、基本的に介護保険の予防給付の範囲では併用できません。
要支援1・2で通所介護と通所リハビリの併用を希望する場合、通所介護(デイサービス)の費用を10割自己負担で申し込むことにより可能になる場合があります。
希望される方は各市区町村に相談することをおすすめします。
また、市区町村の通所サービスを利用することで、併用相当の介護予防が可能になるかもしれません。
多方面からサポートする介護予防サービス

介護予防サービスは、各自治体が主体となって事業に取り組むことで、地域に密着した地域包括ケアシステム・サービスとしての構築が進んでいます。
従来のリハビリテーションや介護者の生活支援に加え、
- 安否確認
- 配食サービス
- 外出支援
- 声かけ
- コミュニティカフェ
- 交流サロン
といった、より実際の生活に即したサービスが必要不可欠となり、事業内容は多岐にわたります。
ここで重要なのが、地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)の活動です。地域の介護予防・生活支援サービスのニーズと介護サービス事業者の資源をマッチングさせるのが生活支援コーディネーターの主な役割です。
近年、介護サービス事業者の例として
- 民間企業
- NPO
- 社会福祉法人
- ボランティア
が主に活動しています。
地域が一体となって高齢者を支援するためにも生活支援コーディネーターの位置づけは重要度を増してきています。
介護予防の通所介護についてのまとめ

ここまで介護予防の通所介護についてお伝えしてきました。
通所介護サービスの要点をまとめると以下の通りです。
- 介護予防は、何歳になっても元気で自立的な生活ができるよう支援するために行う
- 通所介護の対象者は要介護1~5の方で、要介護度は訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で決定する
- 自己負担は1~3割程度で所得に応じて変動する
- 介護予防サービスは市区町村の総合事業の位置づけとなったことで、民間企業、NPO、協同組合、社会福祉法人、ボランティアなどの多方面が協働して運営している
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。