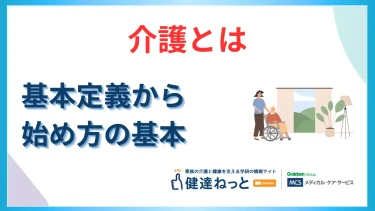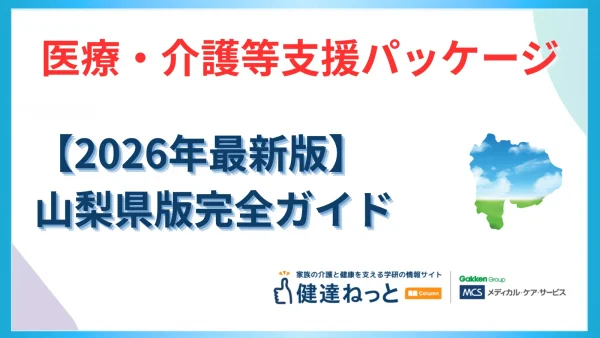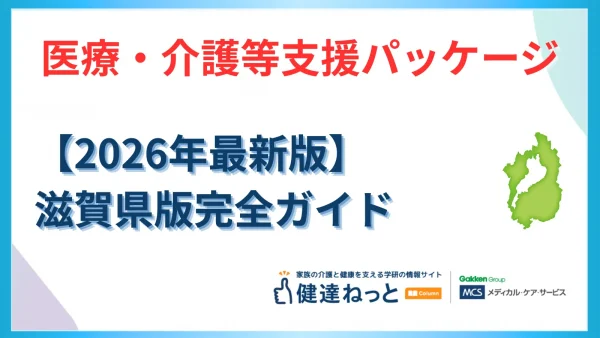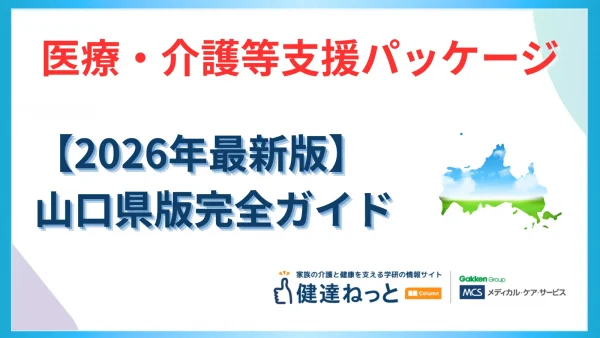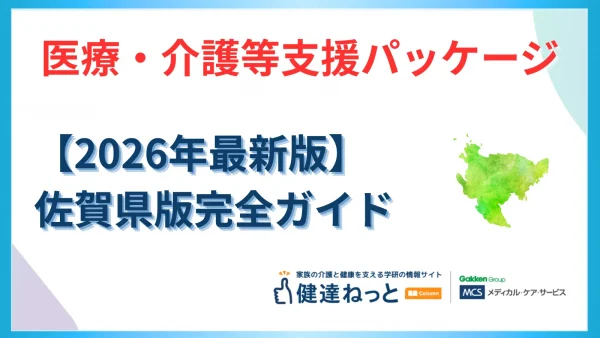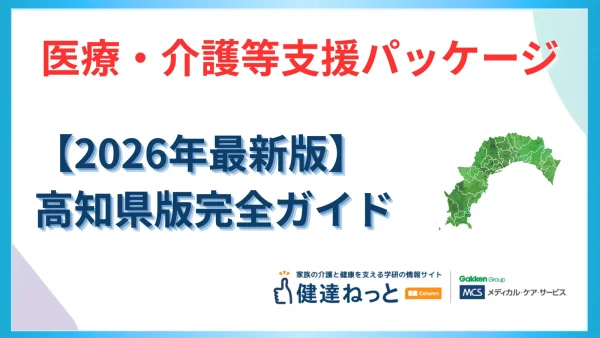親の介護をめぐる問題では、「なぜ親孝行しないのか?」と責めるような発言が出ることがあります。
しかし、その背景には、介護への考え方や価値観の違いがあることが多く、一方的な非難では対話がうまく進みません。
特に、自分の考えを変えにくい「頭の固さ」が強く出ていると、相手の立場を受け入れづらく、感情的な言動につながりがちです。
まずはこうした心理の背景を理解することが、冷静な話し合いの糸口になります。
スポンサーリンク
自己奉仕バイアスが引き起こす対立
「どいつもこいつも、親孝行しようと思わないのか!」と考える人の中には、「自分は正しい」と思い込みやすい傾向(自己奉仕バイアス)が強く働いていることがあります。
こうした人は、自分の価値観に自信があり、それを当然と信じて疑わない「視野の狭さ」を抱えていることもあります。
本来、介護の負担は話し合って分担するものですが、「自分と違う意見=間違っている」と決めつけると、対話はうまく進みません。
スポンサーリンク
価値観の違いが生む誤解
「親の世話をするのは家族の務め」と考える人にとって、協力しないように見える家族は無責任に映ることがあります。
しかし、実際には仕事や育児など、介護が難しい理由がある人も多く、関われる範囲は人それぞれです。
「親孝行=すべてをやること」という考えにとらわれず、「それぞれにできる関わり方がある」という柔軟な視点が求められます。
思い込みに気づき、思考の幅を広げることは、頭が固くなりがちな人の思考をほぐす一歩でもあります。
介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか? 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない… 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう? 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいい[…]
頭が固い人と穏やかに話すコツ
介護に関する話し合いでは、
「なんで手伝わないの?」
「親孝行する気がないのか」
といった強い言葉が飛び交い、かえって協力しづらくなることがあります。
しかし、相手の考えや状況を無視した押しつけは、対立を深めてしまいがちです。
そんなときに有効なのが、「ナッジ(Nudge)」と呼ばれるアプローチです。
ナッジとは、相手の自由を奪わずに、自然に望ましい行動を促す工夫のこと。
無理強いではなく、本人の意思を尊重しながら、前向きな選択を後押しする方法として注目されています。
ここでは、介護や親孝行の話し合いで使えるナッジの活用法をご紹介します。
頭が固い人にも届く、承認欲求を満たす声かけ
親孝行や介護への関わり方をめぐって感情的になっている人は、実は「自分の思いをわかってほしい」「努力を認めてほしい」という承認欲求が強く働いていることがあります。
そのような相手に対して、正面から反論するよりも、「あなたにしかできないことをお願いしたい」といった形で承認欲求を満たす声かけをすると、自然に協力を引き出しやすくなります。
例えば、次のような伝え方が効果的です。
- 「専門家に相談してみるのはどう?」
- 「あなたは顔が広いから、調整役をお願いできる?」
このように、相手の強みや経験を活かす提案をすることで、「それなら自分がやろうか」と前向きな気持ちになりやすくなります。
対立を避けつつ、自然な形で役割を担ってもらえるようになります。
頭の固さをほぐす役割分担の工夫
介護の負担をめぐる話し合いでは、「全部やるか、何もしないか」といった極端な考え方に陥りがちです。
しかし、役割は細かく分けて考えられます。
「調整だけ」「週1回の付き添い」「金銭的な支援」など、それぞれが無理なく担える範囲を提案することが、現実的で持続可能な解決につながります。
例えば、
- 「病院の付き添いは週1回ならできるよ」
- 「掃除や食事の準備はヘルパーを頼むのはどう?」
こうした具体的で現実的な提案は、極端な思考に偏りがちな人の視野を広げるナッジにもなります。
一人で抱え込まず、行政や外部サービスを活用することも、大切な選択肢です。
頭が固い人との対立を避けるために大切なこと
介護や親のサポートをめぐる話し合いでは、感情的になりやすく、対立が生じることもあります。
しかし、価値観や事情の違いを受け止め、相手の立場に立って考えることが、円滑な話し合いの第一歩です。
- 家族間でも価値観は異なる:介護や親孝行への考え方には個人差がある
- 自己奉仕バイアスに注意する:自分が正しいと思い込みすぎると対立が生まれやすい
- ナッジを活用して提案する:相手の承認欲求や特性に合った伝え方で協力を引き出す
頭が固く感じる相手にも、「変わるべき」と押しつけるのではなく、自然に視点を広げてもらう関わり方を心がけましょう。
ナッジの工夫を取り入れることで、家族の関係性も少しずつ前向きに変えていけるはずです。
介護のことになると親子はなぜすれ違うのか
親が高齢になり、「介護」を考えるとどんどん出てくる家族のお悩み――――
親子だから、家族だからこそのすれ違い――――
もう、悩まなくていいんです!
介護をラクにする相手に伝わるコミュニケーション術が親に効く!
行動経済学と福祉社会学、看護の専門家がそれぞれの家族介護経験と専門知識、
ノーベル経済学賞を受賞した「ナッジ(※1)」を用いてみなさまを解決へ導きます。
本書では、8家族の事例を紹介し、それぞれの親が持つ「わかってはいるけど、できない心理(高齢者によく見られる認知バイアス)」が親子のすれ違いに関係していると解説しています。
この「認知バイアス(※2)」に対して、著者3名が自らの家族介護経験と専門知識、そして「ナッジ」を用いて解説しています。
※1:直訳すると「そっと後押しをする」「ひじでつつく」という意味の英語。
2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー博士が提唱した理論で、
「ついそうしたくなる心理」をくすぐって、直感的に望ましい行動をしたくなる仕掛けを指す。
※2:人の脳が持つ、自分に都合よく、解釈を歪めてしまう習性。
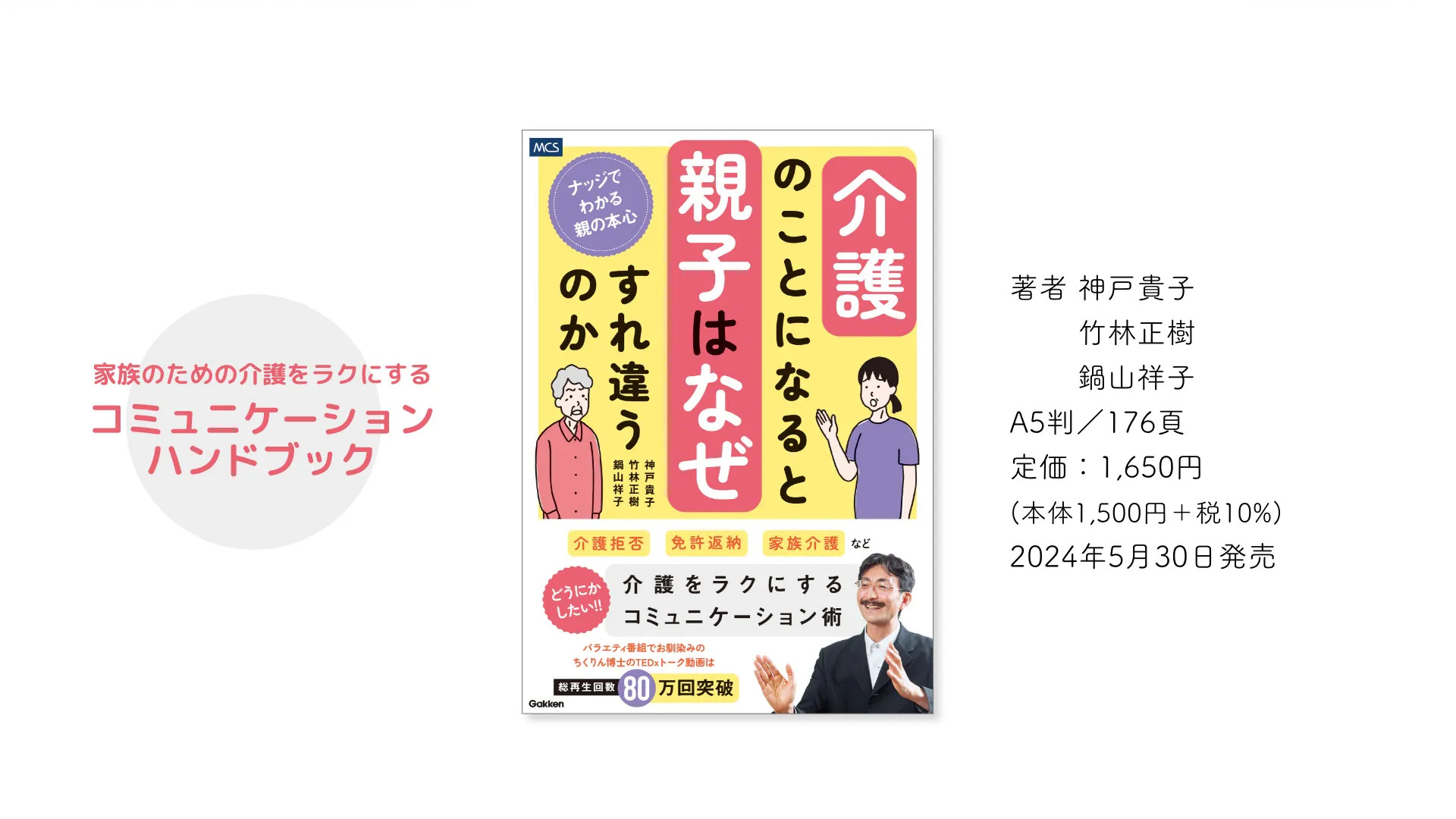
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります