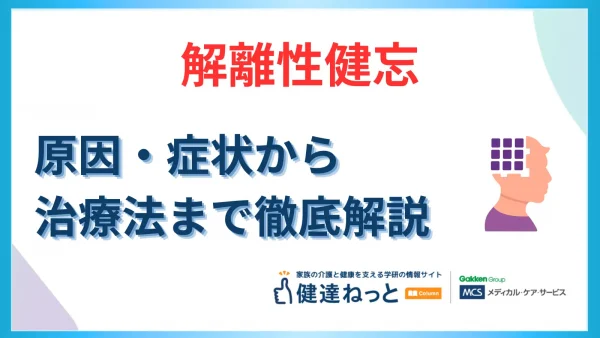解離性健忘とは、精神的なストレスや心的外傷(トラウマ)が原因で、重要な個人的な記憶を思い出せなくなる状態を指します。
ある日突然、大切な記憶の一部が抜け落ちてしまう。
もし、あなたやあなたの身近な人に、このようなことが起きたらどうしますか?
- 特定の出来事や期間を思い出せない
- 自分が誰なのか、どこにいるのか分からなくなる瞬間がある
- 単なるもの忘れとは違う、深刻な記憶の空白に悩んでいる
このような記憶に関する深刻な悩みは、計り知れない不安や恐怖、そして孤立感につながります。
自分が自分でなくなってしまうかのような感覚は、ご本人だけでなく、支えるご家族にとってもつらいものです。
この記事では、そのような悩みを抱える方々のために、ストレスや心の傷が引き起こす記憶障害「解離性健忘」について、専門的な知見を元に徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、以下のことが分かります。
- 解離性健忘の正しい知識と、もの忘れや認知症との違い
- 症状の具体的な種類と、その背景にある原因
- 専門的な治療法と、回復までの道のり
- ご家族や周りの人ができる、心に寄り添うサポート方法
解離性健忘は、決して珍しい病気ではありません。
正しい知識を身につけ、適切なサポートを得ることで、回復への道は開けます。
この記事が、あなたの不安を和らげ、未来への一歩を踏み出すための助けとなることを願っています。
スポンサーリンク
解離性健忘とは?まず知っておきたい基礎知識
解離性健忘とは何か、その基本的な概念から解説します。
これは、つらい体験から心を守るための、いわば防衛反応の一種といえます。
まずは、その定義や他の記憶障害との違いを正確に理解しましょう。
解離性健忘の定義とメカニズム
解離性健忘とは、精神的なストレスや心的外傷(トラウマ)が原因で、重要な個人的な記憶を思い出せなくなる状態を指します。
これは、脳の損傷など身体的な原因で起こる記憶障害とは区別されるのです。
私たちの心は、耐えがたいほどのつらい出来事に直面した時、その記憶や感情を意識から切り離して自分を守ろうとすることがあります。
この心の働きを「解離」と呼びます。
解離性健忘は、この解離という心の防衛機能が、記憶を司る部分に強く働いた結果、生じると考えられています。
つまり、記憶そのものが消えたわけではなく、一時的にアクセスできなくなっている状態といえるのです。
単なる「もの忘れ」と「認知症」との決定的な違い
解離性健忘による記憶の喪失は、日常的な「もの忘れ」や「認知症」とは性質が大きく異なります。
最も大きな違いは、失われる記憶の範囲と、新しいことを覚える能力(記銘力)です。
もの忘れは、体験の一部を忘れることはあっても、体験したこと自体は覚えている場合がほとんどです。
一方、解離性健忘では、特定の期間の記憶がすっぽりと抜け落ちてしまいます。
また、認知症、特にアルツハイマー型認知症では、新しい出来事を記憶する能力が徐々に低下していくのが特徴です。
しかし、解離性健忘の多くは、記憶を失っている期間以外は、新しいことを覚えたり、日常的なスキルをこなしたりする能力は保たれています。
| 記憶障害の種類 | 主な特徴 | 新しい記憶の能力 |
|---|---|---|
| 解離性健忘 | 特定の期間の重要な個人情報を思い出せない | 多くの場合、保たれる |
| 日常のもの忘れ | 体験の一部を忘れるが、体験自体は覚えている | 保たれる |
| 認知症 | 新しいことを覚えにくく、症状が徐々に進行する | 低下していく |
このように、記憶障害の背景にある原因や症状はさまざまです。
記憶障害の種類や受診すべき診療科について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
有病率(どのくらいの人が経験するか)
解離性健忘は、決してまれな疾患ではありません。
米国の精神医学会の診断基準「DSM-5」を用いたある調査では、12ヶ月間の有病率が1.8%であったと報告されています。
また、研究によっては、有病率は0.2%~7.3%と推定されており、これらの数値の幅は、診断基準や調査対象により異なることを示しています。
発症年齢はさまざまで、子どもから高齢者までどの年代でも起こる可能性があります。
特に、戦争や大規模な災害などを経験した集団では、有病率がさらに高まることが知られています。
若い世代でも、強いストレスやトラウマをきっかけに発症するケースは少なくありません。
若い世代でも発症する記憶障害について、健達ねっとでは詳しく解説しています。
この疾患は、誰の身にも起こりうるという認識を持つことが、ご本人やご家族の孤立を防ぐ第一歩となります。
スポンサーリンク
解離性健忘の主な症状と5つのタイプ
解離性健忘の症状は、単に「記憶がなくなる」というだけではありません。
記憶の失われ方にはいくつかのパターンが存在します。
ここでは、その中核となる症状と、代表的な5つのタイプについて詳しく見ていきましょう。
中核症状は「重要な個人的情報の想起不能」
解離性健忘の最も中心的な症状は、「重要な個人的情報を思い出せなくなる」ことです。
これは、単に人の名前を忘れたり、鍵をどこに置いたか忘れたりするレベルのものではありません。
通常では考えられないような、自分自身の人生に関わる大切な記憶が失われます。
具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 数時間から数日間、時には数年間の出来事を全く思い出せない
- 自分の名前や年齢、どこに住んでいるかなどが分からなくなる
- 家族や親しい友人のことを忘れてしまう
多くの場合、本人は記憶がないこと自体に気づいていなかったり、気づいていても平静を装ったりすることがあります。
この無自覚な状態が、周囲からの発見を遅らせる一因にもなります。
記憶の失われ方による5つの分類
解離性健忘は、記憶が失われる範囲やパターンによって、主に5つのタイプに分類されます。
どのタイプに当てはまるかによって、症状の現れ方や日常生活への影響も異なります。
限局性健忘
限局性健忘は、特定の期間の記憶が「すっぽり」と抜け落ちてしまう、最も一般的なタイプです。
なぜなら、心が耐えられないほどの強いストレスがかかった出来事を、その時間帯ごと丸ごと意識から切り離すことで、自己防衛を図るために起こるためです。
つらい記憶そのものだけでなく、その前後の時間を含めてブロックすることで、心へのダメージを最小限に抑えようとします。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 交通事故に遭った後、意識を失っていたわけではないのに事故発生から2時間分の記憶がない
- 激しい口論をした日の午後の出来事を、何があったか全く思い出せない
このように、ある出来事に関連する「時間」の記憶が、ある範囲に限定されて局所的に失われるのが、限局性健忘の大きな特徴です。
選択的健忘
選択的健忘は、特定の期間の出来事について、記憶が「まだらに」失われてしまうタイプです。
これは、一連の出来事全体を忘れるのではなく、その中で特につらく衝撃的だった部分だけを無意識に選び取って忘れることで、心の負担を部分的に軽減しようとするために生じます。
すべての記憶を失うと生活への支障が大きすぎるため、心が必要な部分とそうでない部分を取捨選択している状態といえます。
| 覚えていることの例 | 忘れていることの例 |
|---|---|
| 大規模な災害で避難所にいたこと | 自宅が崩れる瞬間を目撃したこと |
| 戦地で仲間と食事をしたこと | 目の前で仲間が負傷した場面 |
このように、ひとつの出来事の中で記憶している部分と喪失している部分が混在し、特定のつらい体験だけが選択的に思い出せなくなるのが選択的健忘です。
全般性健忘
全般性健忘は、「自分が誰か」という自己同一性を含め、人生全体の記憶を失ってしまう、非常にまれで深刻なタイプです。
これまでの人生で積み重ねてきた経験のすべてが、耐えがたいほどの苦痛と結びついてしまった場合に起こりえます。
もはや部分的な記憶の解離では対処しきれず、アイデンティティそのものを一時的に手放すことでしか、心が崩壊するのを防げない極限状態といえるでしょう。
失われる情報の範囲は、以下のように多岐にわたります。
- 自分の名前、年齢、どこで育ったか
- 家族、友人、職場の同僚のこと
- 学歴や職歴、身につけたスキルや知識
このように、自分の人生史そのものが失われるため、日常生活への影響が最も甚大になるのが全般性健忘です。
系統的健忘
系統的健忘は、特定の「カテゴリー」に関する記憶だけを、系統立ててまとめて失ってしまうタイプです。
これは、時間的な区切りではなく、特定の人物や場所、テーマといった「情報の種類」によって記憶がブロックされる場合に起こります。
例えば、ある特定の人物との関係性が極めて強いストレスの原因となっている場合、その人物に関連する情報だけを脳内で切り離そうとするのです。
具体例としては、以下のようなケースが考えられます。
- 虐待を受けていた父親に関する記憶(名前、顔、一緒に過ごした時間など)は一切ないが、母親や兄弟のことは鮮明に覚えている
- 過去に深刻なトラブルがあった特定の職場での出来事はすべて忘れたが、それ以外の職歴は覚えている
このように、時間軸ではなく「テーマ」で記憶が失われるという、特徴的なパターンを持つのが系統的健忘です。
持続性健忘
持続性健忘は、過去の記憶は保たれているものの、新しい出来事を「次から次へと」忘れてしまうタイプです。
これまでの4タイプが「過去の記憶を思い出せない」逆行性健忘であるのに対し、このタイプは「新しい記憶を作れない」前向性健忘の性質を持ちます。
過去のトラウマから防衛するというよりは、今この瞬間から未来にかけて、新しい情報を記憶として定着させる機能が、何らかの心理的な理由で停止してしまうために起こると考えられています。
| 記憶障害の方向性 | 該当する健忘タイプ |
|---|---|
| 過去の記憶を失う(逆行性) | 限局性、選択的、全般性、系統的健忘 |
| 新しい記憶を作れない(前向性) | 持続性健忘 |
過去の自分は覚えているのに、現在の自分の体験が積み重なっていかないという、非常にまれな状態が持続性健忘です。
特殊な病型の「解離性とん走」
解離性とん走は、解離性健忘の中でも特に特殊な病型です。
これは、突然、自分の家や職場から離れて予期せぬ放浪の旅に出てしまい、その間の自分の過去(名前や経歴など)を思い出せなくなる状態を指します。
とん走中は、以前の自分とは全く異なる新しい名前を名乗り、新しい生活を始めることがあります。
周りから見ると、特に混乱している様子はなく、ごく普通に行動しているように見えることが多いのが特徴です。
この状態は数時間から数ヶ月、時にはそれ以上続くこともあります。
回復すると、とん走中の記憶は失われ、以前の記憶は戻ります。
しかし、自分がなぜ見知らぬ場所にいるのか分からず、ひどく混乱することがあるのです。
解離性健忘が発生する原因
解離性健忘は、なぜ起こるのでしょうか。
その直接的な引き金となるのは、脳の物理的な損傷ではなく、心が耐えきれないほどの「圧倒的な体験」です。
なぜなら、人間の心には、処理能力を超えるほどの強烈な出来事に直面した際、その記憶を一時的に切り離して精神の崩壊を防ぐ「防衛機制」という仕組みが備わっているためです。
解離性健忘は、この防衛機制が極端な形で現れた状態といえます。
これから説明するさまざまな体験に共通するのは、個人の力ではどうすることもできない無力感や、生命の危機を感じるほどの恐怖です。
つまり、解離性健忘は、異常な状況に対する心の正常な反応であり、決して本人の弱さが原因ではないことを理解することが、ご本人と周囲の双方にとって重要になります。
圧倒的なストレスや心的外傷(トラウマ)体験
解離性健忘の直接的な原因は、心が耐えきれないほどの「圧倒的な体験」です。
人間の心は、処理能力を超える強烈な出来事に直面すると、その記憶を一時的に切り離して精神の崩壊を防ぐ「防衛機制」という仕組みを持っています。
解離性健忘は、この防衛機制が極端な形で現れた状態といえるでしょう。
これから説明する体験に共通するのは、個人の力ではどうすることもできない無力感や、生命の危機を感じるほどの恐怖です。
つまり、解離性健忘は異常な状況に対する心の正常な反応であり、本人の弱さが原因ではないことを理解することが重要です。
精神的・身体的虐待
逃げ場のない環境で繰り返し行われる虐待は、解離性健忘の最も深刻な原因のひとつです。
特に、安全であるべき家庭などが脅威の場となる幼少期において、子どもは「その場にいない」かのように心を切り離す(解離する)ことでしか生き延びられないことがあります。
この心の対処法が常態化することで、つらい記憶が断片化し、後の人生で記憶の欠落として現れるのです。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- 親からの日常的な暴力や暴言、ネグレクト(育児放棄)
- パートナーからのDV(ドメスティック・バイオレンス)
- 学校や職場での執拗ないじめやパワーハラスメント
このように、安全なはずの場所で繰り返し心身を傷つけられる体験は、自分を守るために記憶を断片化させる強力な引き金となります。
戦闘や自然災害
戦争や大規模な災害といった、生命が直接脅かされる非日常的な体験も、解離性健忘の典型的な原因です。
人間の脳は、日常とかけ離れた凄惨な光景や死の恐怖をスムーズに処理するようにできていません。
そのため、強烈すぎる体験を「現実のことではなかった」かのように記憶からシャットアウトし、精神的なショックを和らげようとするのです。
| 体験の例 | その体験がもたらす心理的影響 |
|---|---|
| 戦闘への参加、テロ事件への遭遇 | 極度の恐怖、仲間を失う悲しみ、罪悪感 |
| 地震、津波、大規模火災などの被災 | 生命の危機、無力感、大切なものを失う喪失感 |
災害対策として「地震・台風時に動けるガイド」のような物理的な備えも重要ですが、こうした体験後の心のケアがいかに大切かを示唆しています。
個人の尊厳が脅かされるほどの出来事は、記憶を封じ込める原因となりえるのです。
レイプなどの暴力的被害
性的暴行や強盗といった犯罪被害は、心と身体の境界線を暴力的に破壊され、深刻な解離を引き起こします。
これらの体験は、個人の尊厳と安全を根底から否定するものであり、被害者は強烈な恐怖、屈辱、無力感に苛まれます。
あまりにもおぞましい体験であるため、心はその記憶から自分を切り離し、まるで他人事であったかのように感じさせようと防衛機能が働くのです。
その結果、事件そのものやその前後の記憶が失われることがあります。
また、このような体験はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を併発することも少なくありません。
PTSDと記憶喪失の関係について正しく理解することも、適切なサポートには不可欠です。
このように、個人の尊厳が暴力によって踏みにじられる体験は、その記憶自体を耐えがたいものとし、解離性健忘の直接的な原因となります。
近親者の突然の死
大切な人との予期せぬ死別も、心が受け止めきれないほどの衝撃となり、記憶の欠落を引き起こすことがあります。
特に、事故や災害、自殺といった突然で理不尽な形で家族や親友を失った場合、その悲しみや衝撃は心の処理能力をはるかに超えてしまいます。
「信じたくない」という強い否認の気持ちが、死に関連する記憶へのアクセスを一時的に遮断してしまうのです。
具体的には、以下のような形で症状が現れることがあります。
- 警察から訃報の連絡を受けた時のことを思い出せない
- 葬儀に参列したはずなのに、その間の記憶がほとんどない
このように、愛する人を失ったという耐えがたい現実から心を守るために、一時的に記憶が失われることは、誰にでも起こりうる反応なのです。
耐えがたい内的な葛藤
外部からの衝撃的な出来事だけでなく、自分自身の内面で生じる激しい葛藤も、解離性健忘の原因となりえます。
これは、社会的に許されない行為をしてしまったという強烈な罪悪感や、誰にも打ち明けられない秘密を抱えたことによる精神的重圧などが限界に達した時に起こります。
自分の行いや感情と向き合うことから逃れるため、関連する記憶を無意識のうちに封じ込めてしまうのです。
考えられる状況としては、以下のようなものがあります。
- 自分の過失で重大な事故を起こしてしまったという自責の念
- 誰にも言えない関係や借金など、深刻な秘密を抱えるストレス
- 自身のアイデンティティに関する深い悩み
つまり、外的なトラウマだけでなく、内面で燃え盛る炎のような葛藤もまた、心を守るために記憶を解離させる原因となりうるのです。
発症の引き金となりやすい状況
上記のようなトラウマ体験に加えて、特定の状況が発症の引き金となりやすいことも分かっています。
- 極度の疲労
- 身体的な病気
- 睡眠不足
- アルコールの多量摂取
これらの要因は、心身の抵抗力を低下させ、トラウマ記憶のコントロールを難しくします。
その結果、心の防御壁が破れ、解離という形で症状が現れやすくなるのです。
ストレスによる記憶障害のメカニズムと対処法について詳しく解説した記事も、あわせてご参照ください。
専門家が解離性健忘と診断する基準
解離性健忘の診断は、専門家による慎重な評価を必要とします。
なぜなら、記憶障害を引き起こす原因はさまざまであり、他の身体疾患や精神疾患との鑑別が非常に重要になるためです。
ここでは、医師がどのような基準で診断を下すのかを解説します。
DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル)に基づく診断基準
精神科医は、診断の際に米国精神医学会が作成した「DSM-5-TR」という診断基準を参考にします。
これは、世界中の専門家が共通の認識で診断を行うためのガイドラインです。
DSM-5-TRにおける解離性健忘の診断基準の要点は、以下の通りです。
- 通常のもの忘れでは説明できない、重要な自伝的情報(特にトラウマ的またはストレスの強い性質のもの)を思い出せない
- その症状が、著しい苦痛、または社会的、職業的、その他の重要な領域における機能の低下を引き起こしている
- その症状が、物質(薬物やアルコールなど)や、他の神経疾患・医学的疾患(頭部外傷、てんかんなど)によるものではない
- その症状が、他の精神疾患(解離性同一性障害、PTSD、認知症など)ではうまく説明できない
医師はこれらの基準に照らし合わせ、患者さんの状態を総合的に判断します。
DSM-5を用いた精神的疾患の診断プロセスについては、他の疾患の例ですが参考になります。
問診や心理検査で確認されること
診断の中心となるのは、医師による詳細な問診(面接)です。
医師は、患者さん本人や、可能であれば家族からも話を聞き、記憶障害の具体的な内容や、発症前後の状況、ストレス要因の有無などを丁寧に確認します。
問診で確認される主なポイントは以下の通りです。
- いつから、どのような記憶が思い出せないか
- 記憶がなくなる直前に、何か特別な出来事はあったか
- 日常生活や社会生活にどのような支障が出ているか
- 過去の病歴や、現在服用中の薬、飲酒の習慣など
- 家族関係や生育歴について
また、必要に応じて心理検査が行われることもあります。
これにより、記憶障害の程度を客観的に評価したり、他の精神疾患が隠れていないかを確認したりします。
他の疾患との識別が重要
解離性健忘の診断で最も重要なことのひとつが、他の疾患との識別(鑑別診断)です。
記憶障害は、さまざまな原因で起こりうるため、その背景に身体的な問題が隠れていないかを慎重に見極める必要があります。
特に、以下の疾患との鑑別が重要になります。
| 鑑別が必要な主な疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 認知症 | 徐々に進行し、新しいことを覚えられなくなるのが主症状 |
| てんかん | 発作に伴って、一時的な記憶障害が起こることがある |
| 脳の疾患(脳腫瘍、脳炎など) | 画像検査(MRIやCT)で異常が見つかることがある |
| 頭部外傷 | 頭を打った直後から記憶障害が始まる |
| 薬物やアルコールの影響 | 物質の使用に関連して記憶障害が起こる |
これらの可能性を排除するために、血液検査や脳波検査、頭部のMRIやCTなどの画像検査が行われることもあります。
認知症の診断プロセスと必要な情報のように、正確な診断には多角的な検査が不可欠です。
解離性健忘の治療法
解離性健忘の治療は、失われた記憶を取り戻すことだけが目的ではありません。
最も大切なのは、患者さんが安心して過ごせる環境を整え、記憶を失う原因となった心の傷と向き合えるようにサポートすることです。
ここでは、主な治療法と回復までの道のりについて解説します。
治療の第一歩は安全で支持的な環境の確保
治療を始めるにあたり、何よりも優先されるのが「安全な環境」の確保です。
患者さんが身体的にも精神的にも脅かされることなく、安心できる場所で過ごすことが、回復の絶対的な基盤となります。
記憶を失う原因となったストレス要因(例えば、虐待的な家庭環境や過酷な職場など)から物理的に距離を置くことが必要な場合もあります。
周囲の人が、患者さんのつらい体験や症状を理解し、非難することなく受け入れる「支持的な環境」を作ることも、心の安定につながるのです。
基本となる精神療法
解離性健忘の治療の中心は、専門家による精神療法(カウンセリングや心理療法)です。
薬物療法が中心となる他の精神疾患とは異なり、対話を通じて心の回復を目指します。
精神療法の目的は、以下の通りです。
- 患者さんが自分の感情や体験を安全に話せる、信頼関係を築く
- 記憶を失う原因となったトラウマやストレスを、少しずつ整理していく
- ストレスへの対処法(コーピングスキル)を身につける
- 失われた記憶と再統合し、自己の連続性を取り戻す
精神科医で『「幕間」の心理学―人生の転機の乗り切り方―』の著者でもある保坂隆先生は、人生の転機における心理的サポートの重要性を説いています。
解離性健忘のように記憶が途切れた状態は、まさに人生の「幕間」といえます。
このような不安定な時期を乗り越えるには、専門家による丁寧な心理的アプローチが不可欠です。
精神療法の種類と効果についても参考に、自分に合った治療法を見つけることが大切です。
失われた記憶へのアプローチ(記憶想起法)
精神療法がある程度進み、患者さんの状態が安定してきたら、失われた記憶を取り戻すためのアプローチが試みられることがあります。
ただし、これは無理やり思い出させるものではなく、慎重に行われます。
代表的な方法は、以下の2つです。
- 催眠療法:専門家の誘導のもとでリラックスした状態(催眠状態)に入り、無意識下に抑圧されている記憶にアクセスしやすくする方法です
- 薬物補助下面接:鎮静作用のある薬を少量使い、不安や緊張を和らげることで、つらい記憶について話しやすくする方法です
これらの方法は、思い出した記憶によって患者さんが再び精神的に不安定になるリスクもあるため、経験豊富な専門家のもとで、十分な準備をしてから行われます。
薬物療法により不安やうつ症状を和らげる
解離性健忘自体に直接効く特効薬はありません。
しかし、解離性健忘を抱える方の多くは、強い不安や抑うつ、不眠、フラッシュバックといった症状を併発しています。
これらの併存する症状が日常生活に大きな支障をきたしている場合には、症状を和らげる目的で薬物療法が行われます。
主に、抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤などが用いられます。
薬物療法は、あくまで精神療法を円滑に進めるための補助的な役割であり、心の安定を図り、患者さんが治療に主体的に取り組める状態を作ることを目指します。
抗うつ薬や抗不安薬の使用については、医師の指示に従うことが重要です。
治療期間と予後
解離性健忘の予後(回復の見通し)は、一般的に良好とされています。
多くの場合、失われた記憶は数日から数週間で自然に、あるいは突然回復します。
特に、原因となったストレスフルな出来事が一度きりで、期間が短い場合は、回復が早い傾向にあるのです。
しかし、幼少期からの虐待など、慢性的・反復的なトラウマが原因である場合は、回復に時間がかかることもあります。
記憶が戻る過程で、つらい感情が再燃することもあるため、継続的な精神療法のサポートが重要です。
回復期における記憶機能のサポートに関心がある方は、科学的根拠に基づいた機能性表示食品もご参考ください。
※これらの商品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
医師の治療を受けている方は、ご使用前に必ず医師にご相談ください。
解離性健忘の方への周囲からの接し方とサポート
解離性健忘を抱える方の回復には、ご家族や友人など、身近な人々の理解とサポートが不可欠です。
しかし、どのように接すればよいのか分からず、戸惑う方も多いでしょう。
ここでは、ご本人を支えるために周囲ができる、具体的なサポートのポイントを解説します。
無理に記憶を思い出させようとしない
周囲の人が最もやってはいけないのが、失われた記憶を無理に思い出させようとすることです。
「なぜ忘れたの?」「よく思い出してみて」などと問い詰めたり、記憶がないことを責めたりするのは必ず避けるべきです。
解離性健忘は、心を守るための防衛反応です。
無理に記憶をこじ開けようとすると、ご本人はさらに強い苦痛を感じ、症状が悪化したり、回復が遅れたりする可能性があります。
記憶は、心の準備ができた時に自然に戻ってくるのを、辛抱強く待つ姿勢が大切です。
本人が安心できる環境作り
ご本人が「ここは安全だ」と感じられる環境を整えることが、回復への近道です。
これは、メディカル・ケア・サービスが開発した「MCSケアモデル」の考え方にも通じます。
このモデルは、認知症の方の「不確かさ」による「不安」を、「確か」で「安心」できる状況に変える科学的アプローチです。
解離性健忘の方もまた、記憶の欠落という「不確かさ」の中に生きており、強い不安を抱えています。
具体的には、以下の点を心がけるとよいでしょう。
- 穏やかで、予測可能な日常を保つ
- ご本人の話を否定せずに、静かに耳を傾ける
- 感情的にならず、冷静で一貫した態度で接する
ストレス環境の改善と対処法も参考に、ご本人が心穏やかに過ごせる空間作りを目指しましょう。
専門家への相談を促し、付き添う
ご本人が自身の状態に困惑し、医療機関への受診をためらっている場合、周囲の人が優しく背中を押してあげることが重要です。
「一緒に病院を探そうか」「よかったら付き添うよ」といった声かけは、ご本人の心強い支えになります。
実際に、記憶障害を抱える方への支援事例として、「愛の家グループホーム多賀城笠神」のケースがあります。
職員は、記憶障害による不安を抱える利用者様に対し、なぜここに入居しているのか、ご家族がどこで何をしているかを丁寧に伝え続けました。
この「安心できる言葉かけ」を職員全員で共有した結果、利用者様の落ち着きがない様子はすぐに見られなくなったといいます。
このように、専門家と連携し、一貫したサポートを提供することが、安心感につながります。
専門的な相談窓口の活用方法を知っておくことも役立ちます。
本人の感情やペースを尊重する
回復のペースは人それぞれです。
記憶が戻る過程で、ご本人は混乱したり、つらい感情に襲われたりすることがあります。
そのような時は、ご本人の感情に寄り添い、決して急かさないことが大切です。
「つらいね」「ゆっくりでいいんだよ」と、ありのままの感情を受け止める姿勢が、ご本人の孤立感を和らげます。
記憶が戻ること自体がゴールなのではなく、ご本人が自分のペースで人生を取り戻していくプロセス全体を支えるという視点を持つことが、真のサポートといえるでしょう。
解離性健忘について相談できる窓口と医療機関
「もしかして解離性健忘かもしれない…」と感じた時、あるいはご家族の様子が心配な時、どこに相談すればよいのでしょうか。
一人で抱え込まずに、適切な専門機関につながることが問題解決の第一歩です。
ここでは、相談できる主な窓口と医療機関を紹介します。
何科を受診すればよいか
記憶障害を主訴とする場合、まずは精神科または心療内科を受診するのが一般的です。
これらの診療科には、解離性障害を含む心の病気の専門家が在籍しています。
医師は、丁寧な問診や必要な検査を通じて、症状の原因を突き止め、適切な治療方針を立ててくれます。
記憶障害の受診方法と診療科の選び方について詳しく解説した記事も、受診の際の参考になるでしょう。
まずはかかりつけ医に相談し、専門医を紹介してもらうという方法もよいでしょう。
全国の精神保健福祉センター
各都道府県・指定都市に設置されている精神保健福祉センターは、こころの健康に関する専門の相談機関です。
本人や家族からの相談に応じており、無料で利用できます。
精神保健福祉センターで受けられるサポートは以下の通りです。
- 精神科医や臨床心理士などの専門家による相談
- 適切な医療機関や支援機関の情報提供
- 社会復帰に向けたサポート
どこに相談してよいか分からない場合の最初の窓口として、非常に頼りになる存在です。
お住まいの地域のセンターを調べて、気軽に電話してみましょう。
電話相談窓口(いのちの電話など)
今すぐ誰かに話を聞いてほしい、という切羽詰まった気持ちの時には、電話相談窓口を利用するのもひとつの方法です。
匿名で相談でき、専門の相談員があなたの気持ちに寄り添って話を聞いてくれます。
| 相談窓口の例 | 特徴 |
|---|---|
| よりそいホットライン | どのような悩みでも24時間無料で相談可能 |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 全国の精神保健福祉センターにつながる共通番号 |
| いのちの電話 | さまざまな困難や危機に追い込まれた人のための相談窓口 |
これらの窓口は、直接的な治療を行う場所ではありません。
しかし、つらい気持ちを吐き出し、専門機関につながるきっかけを得るための大切なステップとなりえます。
地域包括支援センターなど相談窓口の詳細情報も、高齢者のケースでは役立つ情報源です。
スポンサーリンク
解離性健忘についてよくある疑問
ここでは、解離性健忘に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
より深く疾患について理解するための一助となれば幸いです。
解離性健忘は繰り返すことあるか
はい、解離性健忘は繰り返す可能性があります。
特に、原因となったトラウマが慢性的であったり、新たな強いストレスにさらされたりした場合に、再発することがあります。
一度回復しても、根本的な原因である心の傷が癒えていなければ、ストレスへの対処能力が低い状態が続くためです。
再発を防ぐためには、症状がなくなった後も、継続的にカウンセリングを受け、ストレス管理の方法を学ぶことが重要です。
恋人や家族など特定の人に関する記憶だけを忘れることはあるか
はい、そのようなケースはありえます。
これは「系統的健忘」と呼ばれるタイプに該当する可能性があります。
特定の人との関係性に、耐えがたいほどの葛藤や罪悪感、あるいはトラウマ体験が関連している場合に、その人に関する記憶だけが選択的に失われることがあります。
これは、その人との関係から心を守るための、無意識的な防衛反応と考えることができます。
子どもでも発症することがあるか
はい、子どもでも解離性健忘を発症します。
むしろ、子どもの心は発達途上で非常に柔軟であると同時に、傷つきやすいため、解離を起こしやすいといわれています。
特に、家庭内での虐待やネグレクト(育児放棄)など、逃れられないトラウマ体験に継続的にさらされている子どもは、解離性障害を発症するリスクが高いとされています。
子どもの虐待と解離性健忘の関係について、社会全体で理解を深めていくことが大事です。
回復のきっかけはあるか
回復のきっかけは人それぞれですが、最も重要なのは「安全な環境」が確保されることです。
原因となっていたストレスフルな状況から離れることが、大きな転機となるケースは少なくありません。
具体的なきっかけとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 信頼できる治療者や支援者との出会い
- 家族や友人の温かいサポート
- 失われた記憶の断片を思い出す(写真や場所など)
- 日常生活の中で、ふとした瞬間に突然記憶が戻る
多くの場合、記憶は突然、まとまって回復する傾向があります。
その際、つらい感情も一緒に蘇ることがあるため、専門家のサポートのもとで、心の準備をしておくことが望ましいです。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、ストレスやトラウマが引き起こす記憶障害「解離性健忘」について、その症状、原因、診断、治療法から、周囲のサポート方法までを包括的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 解離性健忘は、つらい体験から心を守るための防衛反応であり、脳の病気ではありません
- 症状は、記憶の失われ方によって5つのタイプに分類され、もの忘れや認知症とは異なります
- 治療の中心は、安全な環境のもとで行われる精神療法(カウンセリング)です
- 周囲の人は、無理に思い出させようとせず、本人のペースを尊重し、安心できる環境を整えることが大切です
ある日突然、記憶を失うという体験は、ご本人にとってもご家族にとっても、計り知れない不安を伴います。
しかし、大切なのは、その不安を一人で抱え込まないことです。
解離性健忘は、適切な治療とサポートによって回復が期待できる疾患です。
もし、あなたやあなたの身近な人が記憶の問題で悩んでいるなら、どうか勇気を出して専門機関に相談するようにしましょう。
信頼できる専門家と共に、安心して回復への道を歩み始めることが、穏やかな日常を取り戻すための最も確実な一歩となるでしょう。
日頃の脳の健康維持に関心のある方向けに、記憶力や認知機能をサポートする機能性表示食品も取り扱っています。