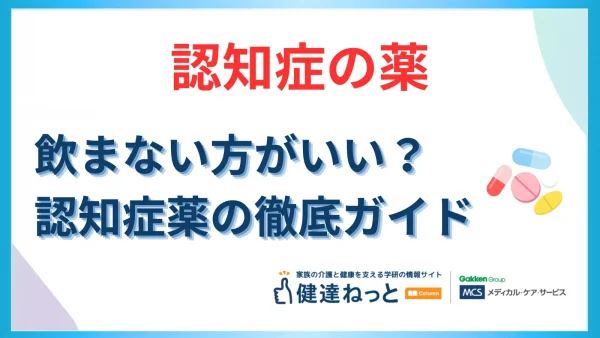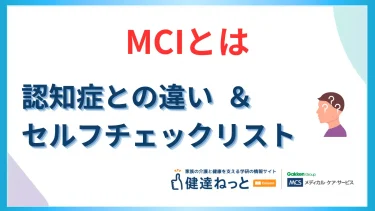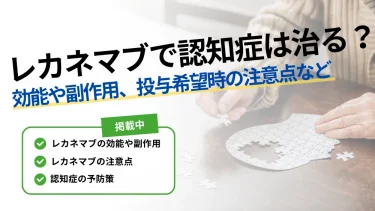- 「認知症の薬は、副作用が怖いから飲ませたくない…」
- 「もし薬をやめたら、症状は急に悪化してしまうの?」
- 「そもそも、この薬は本当に本人のためになっているのだろうか?」
ご家族やご自身の認知症治療を前に、薬に対してこのような強い不安や疑問を抱えていませんか。
インターネット上ではさまざまな情報が飛び交い、何が正しいのか分からず、混乱されている方も多いかもしれません。
そのお気持ち、非常によく分かります。
大切なご家族だからこそ、最善の選択をしたいと思うのは当然のことです。
この記事では、そのような薬への不安に真正面からお答えします。
認知症治療の専門的な知見と、多くの介護現場での実績を元に、薬との正しい付き合い方を徹底解説します。
- 認知症治療における薬の本当の役割
- 「薬を飲まない」という選択肢を検討すべき具体的な4つのケース
- 自己判断で薬をやめた場合のリスクと、安全な減薬の方法
- 薬に頼りすぎない、認知症ケアの新しいアプローチ
この記事を最後まで読めば、薬に対する漠然とした不安が解消されます。
そして、ご本人とご家族が心から納得できる治療法を選択するための、確かな一歩を踏み出せるはずです。
スポンサーリンク
認知症の薬を考える前に知っておきたい3つの大原則
認知症の薬について考える時、つい「どの薬が効くのか」という点に目が行きがちです。
しかし、その前に治療の全体像を正しく理解することが、後悔しない選択への第一歩となります。
ここでは、まず知っておくべき3つの大原則を解説します。
認知症は「症状」であり、原因となる「病気」はさまざま
まず理解すべき最も重要なことは、「認知症」とはひとつの病名ではなく、さまざまな原因によって記憶や判断力などの認知機能が低下し、生活に支障が出ている「状態」を指すことです。
原因となる代表的な病気には、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症などがあります。
どの病気が原因かによって、脳の変化や現れる症状、そして有効な治療法も根本的に異なります。
例えば、アルツハイマー病の薬が、他のタイプの認知症には効かない、あるいはかえって症状を悪化させるケースもあるのです。
- アルツハイマー病: 脳に特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が壊れて脳が萎縮する。
- 血管性認知症: 脳梗塞や脳出血など、脳の血管のトラブルによって神経細胞が壊れる。
- レビー小体型認知症: 「レビー小体」という特殊なたんぱく質が脳に現れる。
このように原因が異なるため、薬を考える以前に、専門医による正確な「診断」が全ての出発点となります。
診断が違えば、治療の方向性も全く変わってくるためです。
認知症の前段階であるMCIについて理解を深めたい方はこちらをご覧ください。
「最近、もの忘れがひどくなった気がする…」「親の言動に、以前とは違う変化を感じる…」「MCIという言葉を聞くけど、認知症とは違うの?」このような不安や疑問を感じていませんか。年齢を重ねるにつれて増える「もの忘れ」に対[…]
治療の目的は「完治」ではなく、「進行を穏やかにし、よりよく共に生きること」
認知症の薬について調べる時、多くの方が「薬で治るのか?」という期待を抱きます。
しかし、現在の医療では、一度壊れてしまった脳細胞を元に戻し、認知症を「完治」させる薬はまだありません。
認知症治療薬の主な目的は、病気の進行を完全に止めることではなく、そのスピードを「穏やかにする」ことです。
そして、症状を緩和することで、ご本人が少しでも長く自分らしい穏やかな生活、すなわち生活の質(QOL)を維持できるようサポートすることにあります。
治療のゴールを「完治」に設定してしまうと、「なぜ治らないんだ」という焦りや失望につながりかねません。
そうではなく、病気と「よりよく共に生きる」ために、薬をどう活用していくか、という視点を持つことが、ご本人とご家族の心の負担を軽くする上で非常に重要です。
この視点の転換が、穏やかな介護生活への第一歩となります。
治療の第一選択は「非薬物療法」で、薬はあくまで選択肢のひとつ
意外に思われるかもしれませんが、認知症のケアにおいて、国内外の主要なガイドラインで推奨されているのは、薬物療法よりも先に「非薬物療法」を試みることです。
日本神経学会による認知症診療ガイドライン2017年版でも、「認知症の行動・心理症状(BPSD)には非薬物療法を薬物療法より優先的に行うことを原則とする」と明記されています。
なぜなら、認知症の症状は、本人の不安や身体的な不快感、周囲の環境が引き金になっていることが多いためです。
メディカル・ケア・サービスが実践する「MCS版自立支援ケア」でも、薬は12の解決方法のひとつと位置づけられています。
まず水分・栄養・運動などの身体状態や、人との繋がりといった環境を整えることを優先し、薬に依存しない生活を目指すものです。
このアプローチにより、多くの方で症状が改善し、結果として減薬につながる事例が確認されています。
薬はあくまで強力な選択肢のひとつであり、万能ではないことを理解しておくことが大切です。
非薬物療法には具体的にどのような方法があるのか詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
認知症の治療方法は、薬物療法と非薬物療法に分けられます。非薬物療法では、認知症の方の能力を引き出すことができます。非薬物療法という言葉に聞き馴染みがないという人も多いのではないでしょうか?本記事では、非薬物療法について以下の点を[…]
スポンサーリンク
認知症の症状を和らげる4つの基本薬の効果と副作用
現在、認知症の中核症状(記憶障害など)の進行を穏やかにする目的で使われる基本薬は、作用の仕組みによって2種類に大別され、合計4つの成分があります。
ここでは、それぞれの薬の特徴と、知っておくべき副作用について詳しく見ていきましょう。
4つの基本薬の一覧比較
まずは、4つの薬がどのような特徴を持つのか、一覧で比較してみましょう。
これらの薬は、脳内の神経伝達物質に働きかけることで、認知機能の低下を緩やかにします。
薬の選択は、認知症のタイプや重症度、副作用の出やすさ、本人の生活スタイルなどを考慮して、医師が総合的に判断します。
| 一般名(主な製品名) | 作用のタイプ | 主な適応 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩(アリセプト®) | AChE阻害薬 | AD(軽度~高度)、DLB | 錠剤、口腔内崩壊錠、ゼリー、貼付剤 |
| リバスチグミン(イクセロン®パッチなど) | AChE阻害薬 | AD(軽度~中等度) | 貼付剤 |
| ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール®) | AChE阻害薬 | AD(軽度~中等度) | 錠剤、口腔内崩壊錠、内用液 |
| メマンチン塩酸塩(メマリー®) | NMDA受容体拮抗薬 | AD(中等度~高度) | 錠剤、口腔内崩壊錠 |
※AD:アルツハイマー型認知症、DLB:レビー小体型認知症
※AChE阻害薬:アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
ご本人にとってどの薬が最適か、また副作用が出た場合にどう対処するかは、専門医との密な連携が不可欠です。
ドネペジル塩酸塩(アリセプト®)
ドネペジルは、日本で最初に承認された認知症治療薬であり、最も広く使用され、豊富な実績を持つ薬です。
記憶や学習に関わる神経伝達物質「アセチルコリン」を増やすことで、認知機能の低下を穏やかにします。
アルツハイマー型認知症の軽度から高度まで、幅広いステージで使えるのが大きな特徴です。
また、レビー小体型認知症の認知機能障害にも適応が認められています。
錠剤や貼り薬などさまざまな剤形があり、患者さんの状態に合わせて選択できるのも利点といえるでしょう。
一方で、副作用として注意が必要なのは、吐き気や下痢、食欲不振といった消化器系の症状です。
これらは薬の作用で消化管の動きが活発になるために起こりますが、徐々に慣れていくことも多いです。
まれに脈が遅くなる(徐脈)などの心臓への影響や、かえってイライラや興奮といった症状が出る場合もあります。
服薬開始後は体調の変化を注意深く観察し、気になることがあればすぐに医師に相談することが大切です。
アリセプトがレビー小体型認知症にも使用されることについて詳しく知りたい方は下記もご覧ください。
レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症、血管性認知症と合わせて3大認知症の一つです。認知症の治療薬には、症状の進行を抑制する効果があります。レビー小体型認知症に効果的なアリセプトという薬をご存知ですか?本記事では、レビー小体[…]
リバスチグミン(イクセロン®/リバスタッチ®パッチ)
リバスチグミンは、1日1回、皮膚に貼るタイプの「パッチ剤」であることが最大の特徴です。
有効成分が皮膚からゆっくりと吸収されるため、血中濃度が安定しやすく、ドネペジルなどで見られる吐き気などの消化器系副作用が出にくいという大きなメリットがあります。
薬を飲むのが苦手な方や、ご家族が服薬管理をする上で、貼り替えの方が負担が少ないという点も、長く治療を続ける上で重要なポイントになります。
この特徴から、以下のような方に特に選択されやすい薬です。
- 内服薬で吐き気や食欲不振が強く出てしまう方
- 嚥下(飲み込み)機能が低下していて、錠剤を飲むのが難しい方
- 多くの薬を飲んでおり、管理を少しでも簡便にしたい方
ただし、貼り薬特有の副作用として、貼った場所の皮膚がかぶれたり、赤みやかゆみが出たりすることが高頻度で見られます。
これを防ぐためには、毎日同じ場所に貼らず、背中・上腕・胸など、貼る場所を少しずつずらしていく工夫が必要です。
もし皮膚の異常が続く場合は、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。
ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール®)
ガランタミンも、ドネペジルと同様にアセチルコリンを増やして認知機能の低下を穏やかにする薬です。
それに加え、神経伝達物質の受け皿である「ニコチン性アセチルコリン受容体」にも働きかけ、アセチルコリンの放出を促すという二重の作用を持つのが特徴とされています。
このユニークな作用機序により、他の同系統の薬とは少し違った効果が期待される場合があります。
使用されるのは、軽度から中等度のアルツハイマー型認知症です。
ドネペジルで効果が不十分な場合や、副作用で使えない場合の選択肢となることがあります。
錠剤のほかに、少量から調整しやすい液体タイプ(内用液)があるのも特徴のひとつです。
副作用は、他の同系統の薬と同じく吐き気、嘔吐、食欲不振などが報告されています。
注意すべき点として、脈が遅くなったり、まれに失神したりするリスクが指摘されており、心臓に持病がある方は特に慎重な使用が必要です。
服薬を開始する際は、少量から始め、体の状態を見ながらゆっくりと量を増やしていくのが一般的です。
メマンチン塩酸塩(メマリー®)
メマンチンは、これまで紹介した3つの薬とは全く異なる仕組みで作用する薬です。
脳内の神経伝達物質「グルタミン酸」が過剰に働くと、神経細胞が興奮しすぎて傷ついてしまいます。
メマンチンは、このグルタミン酸の過剰な働きを抑えることで、神経細胞を保護し、認知機能の低下を防ぎます。
この薬の最大の特徴は、中等度から高度のアルツハイマー型認知症に適応があることです。
また、攻撃的になったり、興奮しやすくなったりといった行動・心理症状(BPSD)を穏やかにする効果も期待できるため、そのような症状に悩む方に処方されることが多いです。
先に紹介したアセチルコリンエステラーゼ阻害薬と併用もできます。
主な副作用としては、めまいや眠気、頭痛、便秘などが報告されています。
消化器系の副作用は少ない一方、ふらつきによる転倒のリスクには注意が必要です。
特に高齢者は転倒から骨折につながり、寝たきりの原因となることもあるため、生活環境を整えるなどの配慮が大切になります。
メマリーの詳しい効果や使用上の注意点は下記で解説しています。
認知症治療の薬についてご存知でしょうか?代表的な認知症の治療薬は、「アリセプト」「レミニール」「メマリー」の3種類があります。この3種類の中でも、唯一NMDA受容体拮抗作用のある薬がメマリーです。今回は、認知症の治療薬メマリーに[…]
【結論】認知症の薬は飲まない方がいい?「飲まない」を検討すべき4つのケース
「副作用が怖いなら、やはり薬は飲まない方がよいのでは?」という疑問は、多くの方が抱くものです。
薬を飲むことは、必ずしも全ての患者さんにとって最善の選択とは限りません。
ここでは、どのような場合に「薬を飲まない」という選択肢を検討すべきか、具体的な4つのケースを解説します。
副作用が効果を上回っている
薬物治療の基本は、薬によって得られるメリット(効果)が、デメリット(副作用)を上回っていることです。
認知症の薬を服用し始めてから、ご本人にとって明らかに苦痛となる状態が続く場合は、薬のメリットよりもデメリットの方が大きい可能性があります。
- 吐き気や食欲不振で、好きなものも食べられなくなってしまった。
- 下痢が続いて体重が減り、日中の活動意欲が著しく落ちてしまった。
- 薬を飲んでから、かえってイライラしたり攻撃的になったりすることが増えた。
- めまいやふらつきがひどく、家の中を歩くのも危険な状態になっている。
このような状態は、ご本人の生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、脱水や低栄養、骨折といった新たな健康問題を引き起こすリスクも高めます。
ご家族から見て「薬のおかげで少しもの忘れが減ったかも」と感じても、ご本人がつらい思いをしているのであれば本末転倒です。
効果がはっきりと感じられない一方で、副作用による苦痛が大きい場合は、医師と相談の上で減薬や中止を検討すべき重要なサインといえるでしょう。
多剤併用(ポリファーマシー)で心身への負担が大きい
高齢者は認知症以外にも、高血圧や糖尿病、骨粗しょう症など、複数の持病を抱えていることが少なくありません。
その結果、多くの種類の薬を同時に服用する「多剤併用(ポリファーマシー)」の状態に陥りがちです。
服用する薬の種類が増えれば増えるほど、薬同士が互いに影響し合い、予期せぬ副作用が出やすくなります。
また、薬を分解・排泄する肝臓や腎臓への負担も大きくなります。
日本老年医学会の研究では、多剤併用によるリスクが指摘されており、多剤併用はその大きな原因のひとつです。
認知症の症状だと思っていた混乱やふらつきが、実は他の薬の副作用だったというケースも珍しくありません。
メディカル・ケア・サービスでは、医療機関と連携して処方薬の適正化を図ることで、ご入居者様の心身の状態が改善する事例を多数経験しています。
多くの薬を飲んでいて体調が優れない場合は、認知症の薬だけでなく、服用している全ての薬を見直すことが、症状改善のきっかけになることがあります。
基礎疾患が悪化している
認知症の薬の中には、心臓の病気や喘息、消化性潰瘍などの基礎疾患に影響を与える可能性があるものも含まれます。
例えば、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬は、脈を遅くする作用があるため、もともと不整脈(洞不全症候群など)がある方には慎重な投与が必要です。
また、胃酸の分泌を促進させるため、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の既往がある方も注意が求められます。
薬を服用し始めてから、息切れがひどくなった、胸が苦しいと訴える、胃の調子が悪いなど、持病の症状が悪化したり、検査の数値が不安定になったりした場合は、認知症の薬が影響している可能性を考えなくてはいけません。
このような場合、医師は認知症の治療と基礎疾患の治療の優先順位を判断し、薬の変更や中止を検討します。
持病のある方が認知症の薬を始める際は、必ず事前に医師にそのことを伝え、治療による影響について十分に説明を受けておくことが、ご本人の安全を守る上で非常に重要です。
終末期(ターミナルケア)で本人の負担軽減を優先したい
認知症が進行し、人生の最終段階である終末期(ターミナルケア)を迎えた時、治療の目的は「延命」から「苦痛の緩和」と「生活の質の維持」へとシフトします。
この段階になると、多くの方は寝たきりの状態となり、食事や薬を飲み込む力(嚥下機能)も低下してきます。
無理に薬を飲ませようとすると、誤嚥(食べ物や薬が気管に入ってしまうこと)を起こし、肺炎などの重篤な合併症を引き起こす危険性が高まります。
薬を飲むこと自体が、ご本人にとって大きな苦痛や負担となってしまうのです。
このような状況では、認知症の進行を穏やかにする薬のメリットよりも、誤嚥のリスクや服薬の負担というデメリットの方が大きくなることが少なくありません。
ご本人やご家族がどのような最期を迎えたいか、という意思を尊重し、穏やかな時間を過ごすことを最優先に考え、医師の判断のもとで薬を中止するという選択がなされることが多くあります。
これは治療の放棄ではなく、その人らしい最期を迎えるための、積極的なケアのひとつといえます。
認知症の薬を飲まないを選択する上での最重要事項
薬を飲まないという選択肢がある一方で、その判断は極めて慎重に行う必要があります。
自己判断で薬をやめてしまうことには、大きなリスクが伴います。
ここでは、減薬や中止を考える上で、絶対に守らなければならない最重要事項を解説します。
減薬・中止する際は必ず医師の管理のもとで行う
どのような理由があっても、認知症の薬を自己判断でやめることは絶対に避けてください。
薬の減量や中止は、ご本人の状態を最もよく知る医師が、専門的な知識と経験に基づいて判断すべき医療行為です。
医師は、薬の必要性、副作用のリスク、ご本人やご家族の意向などを総合的に評価し、中止が妥当かどうかを判断します。
中止すると決まった場合も、多くは急にやめるのではなく、数週間から数か月かけて少しずつ薬の量を減らしていく「漸減法」がとられます。
これは、次に述べる離脱症状などのリスクを最小限にするためです。
相談のポイント
- なぜ薬をやめたいのか(副作用、本人の負担など)を具体的に伝える。
- やめた場合にどのような変化が起こりうるか、医師に確認する。
- 中止後の体調変化にどう対応すればよいか、アドバイスをもらう。
ご家族だけで悩まず、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談することが、安全な治療への第一歩です。
離脱症状や症状の進行が起こる可能性がある
「薬をやめたら、どうなるの?」これは、多くの方が抱く最大の不安のひとつでしょう。
自己判断で急に薬の服用をやめた場合、いくつかの好ましくない変化が起こる可能性があります。
ひとつは、「離脱症状」です。
薬がある状態に慣れていた体が、急に薬がなくなることでバランスを崩し、一時的にイライラや不安感が強まったり、吐き気や頭痛などの身体症状が現れたりすることがあります。
これは薬への依存とは異なり、体が変化に適応する過程で起こる一時的な反応です。
もうひとつは、認知症の症状そのものが悪化するリスクです。
薬によって穏やかに抑えられていた症状が、服薬を中断することで、再び進行し始める可能性があります。
特に、落ち着いていた方が急に混乱し始めたり、攻撃的になったりすることもあります。
こうした変化は、ご本人の生活の質を損なうだけでなく、介護するご家族の負担を急激に増大させることにもつながりかねません。
だからこそ、薬の中止は医師の監督下で慎重に進める必要があるのです。
副作用が出ても自己判断でやめてはいけない理由
副作用がつらそうだから、という理由でご家族が薬を飲ませるのをやめてしまうケースは少なくありません。
しかし、その善意の行動が、かえってご本人を危険にさらす可能性があります。
副作用と思われる症状が、実は全く別の病気のサインである可能性も考えられます。
例えば、「食欲がない」という症状が、薬の副作用ではなく、胃腸の病気や感染症によるものかもしれません。
自己判断で薬をやめて様子を見ている間に、本来治療すべき病気が進行してしまう恐れがあるのです。
| 症状 | 薬の副作用の可能性 | 他の病気の可能性 |
|---|---|---|
| 食欲不振 | 消化器系の副作用 | 胃潰瘍、感染症、うつ状態 |
| ふらつき | めまい、眠気 | 脱水、脳梗塞、貧血 |
| イライラ | 興奮の副作用 | 身体的苦痛(痛み、便秘)、環境の変化 |
副作用が出た時こそ、医師に相談する絶好のタイミングです。
医師は症状の原因を正確に突き止め、薬の量を調整したり、副作用を抑える薬を追加したり、あるいは別の種類の薬に変更するなど、専門的な対応をとれます。
ご本人の安全を守るためにも、異変を感じたらすぐに専門家へつなぐことが重要です。
認知症の行動・心理症状(BPSD)を緩和する薬
認知症の方の介護において、ご家族を最も悩ませるのが、妄想・興奮・攻撃性・うつ状態といった「行動・心理症状(BPSD)」です。
これらの症状は、薬で緩和できる場合があります。
ただし、使用には専門的な判断と慎重な姿勢が求められます。
抑肝散などの漢方薬
BPSDに対して、まず選択肢として検討されることが多いのが「抑肝散(よくかんさん)」などの漢方薬です。
抑肝散は、もともと子どもの夜泣きやかんしゃくに使われてきた薬で、神経の高ぶりを鎮め、心身のバランスを整える働きがあります。
西洋医学的な視点だけでなく、東洋医学的な「気・血・水」のバランスを整えるという考え方に基づいています。
認知症においては、期待されている効果は特に以下の通りです。
- イライラして怒りっぽい
- 攻撃的な言動がある
- 不安や焦りが強い
- 夜、眠れずに騒いでしまう
西洋薬の抗精神病薬と比べて副作用が比較的少なく、高齢者にも使いやすいのが大きなメリットです。
ただし、複数の研究では抑肝散の有効性が確認されている一方で、科学的根拠が十分ではないとの指摘もあります。
「漢方だから安心」と安易に考えず、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談の上で、その方の体質(証)に合ったものを選んでもらうことが大切です。
抗精神病薬
幻覚や妄想、強い興奮や攻撃性など、漢方薬だけではコントロールが難しい激しいBPSDに対しては、「抗精神病薬」の使用が検討されます。
リスペリドンやクエチアピンといった薬が、少量で用いられることがあります。
これらの薬は、脳内のドパミンなどの神経伝達物質の働きを調整することで、精神症状を強力に鎮静させる効果があるのです。
ご本人や介護者が著しく消耗し、身の危険が及ぶような状況では、必要不可欠な治療選択肢となりえます。
しかし、その使用は極めて慎重に行われなければなりません。
高齢者が抗精神病薬を服用すると、転倒や誤嚥性肺炎のリスクが高まるほか、脳血管障害のリスクや死亡率が上昇するという報告もあります。
特にレビー小体型認知症の方は、抗精神病薬に対して非常に過敏に反応し、症状が急激に悪化することがあるため原則禁忌です。
使用する際は、医師から十分な説明を受け、最小限の量を短期間に留めるのが鉄則です。
抗精神病薬の種類と注意すべきデメリットについて詳しく解説しています。
認知症による幻覚、妄想、興奮、怒りっぽさといった症状は、介護する側の大きなストレスとなります。抗精神病薬はこうした症状の抑制に効果的であると聞いたことはありませんか?本記事では、認知症治療に用いられる抗精神病薬について以下の内容を中心に[…]
抗うつ薬
「気分が落ち込んでいる」「何事にもやる気が出ない」「不安で落ち着かない」といった、うつ状態や不安症状が強く見られる場合には、「抗うつ薬」が有効なことがあります。
認知症の方は、自身の能力の低下に気づき、将来への悲観からうつ状態に陥ることが少なくありません。
うつ症状は、単なる気分の落ち込みに留まらず、食欲不振や引きこもり、意欲の低下といったさらなる悪循環を招くこともあります。
抗うつ薬は、セロトニンなど脳内の気分に関わる神経伝達物質のバランスを整えることで、落ち込んだ気分を和らげ、前向きな気持ちを取り戻す手助けをします。
主に使われる抗うつ薬の種類
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬): 比較的副作用が少なく、高齢者にも使いやすい。
- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬): 意欲を高める効果も期待できる。
ただし、抗うつ薬にも吐き気や眠気などの副作用があり、効果が現れるまでに数週間かかることもあります。
BPSDの治療薬は、いずれも専門医による慎重な判断のもとで使用されるべきものです。
【最新治療】アルツハイマー病の新薬「レカネマブ(レケンビ®)」とは
2023年9月25日、アルツハイマー病治療は歴史的な転換点を迎えました。
病気の進行そのものを抑制する、全く新しいタイプの治療薬が厚生労働省により承認され、同年12月20日に保険収載されたのです。
ここでは、大きな注目を集める新薬「レカネマブ」について、その革新性と、知っておくべき現実を解説します。
従来の薬との根本的な違い
これまで紹介してきた4つの基本薬は、神経伝達物質を調整することで症状を緩和する「対症療法薬」でした。
一方、レカネマブは、アルツハイマー病の根本原因と考えられている脳内の異常なたんぱく質「アミロイドβ」を直接取り除くことで、病気の進行自体を遅らせる「疾患修飾薬」です。
これは、認知症治療のパラダイムを大きく変える画期的な進歩といえます。
対症療法が「火事で充満した煙を、窓を開けて一時的に換気する」ようなものだとすれば、疾患修飾薬は「火事の原因である火種そのものを消しに行く」ようなアプローチです。
煙を取り払っても火種が残っていればまた煙は出ますが、火種を消せば煙の発生は根本から抑えられます。
この根本的な違いを理解することが、新薬を正しく評価する上で非常に重要です。
レカネマブの投与を検討している方は、下記で詳しい情報をご確認ください。
「レカネマブは認知症に効果があるの?」「レカネマブの安全性やリスクが知りたい」レカネマブについて調べている方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。レカネマブは、2023年12月に発売され始めた新薬で、アルツ[…]
効果と厳しい投与条件
レカネマブは、臨床試験において、18か月間の投与でプラセボ(偽薬)群と比べて認知機能の悪化を27.1%抑制したと報告されています。
これは病気の進行を平均で数か月から2~3年遅らせる可能性を示すもので、大きな希望となります。
しかし、この薬は誰もが使えるわけではありません。
その効果を最大限に引き出し、安全性を確保するため、厚生労働省は非常に厳しい投与条件を定めています。
- 対象となる病期: アルツハイマー病による「軽度認知障害(MCI)」または「軽度の認知症」のみ。中等度以上に進行した方や、症状のない方は対象外です。
- 必須の検査: PET検査や脳脊髄液検査で、脳内にアミロイドβが溜まっていることを証明する必要があります。
- 専門の医療機関: 認知症専門医が在籍し、定期的なMRI検査などが行える体制が整った施設でのみ治療が可能です。
これらの厳しい条件は、薬の恩恵を最も受けられる可能性が高い人を慎重に見極め、同時に副作用のリスクを管理するために不可欠です。
費用と副作用
レカネマブの治療を考える上で、避けて通れないのが費用と副作用の問題です。
費用は非常に高額で、体重50kgの方の場合、薬剤費だけで年間約298万円にのぼります。
高額療養費制度などの公的助成を利用できますが、それでも一定の自己負担は発生します。
医療費については、病院の医療ソーシャルワーカーなどに相談すると、利用可能な制度について教えてもらうことが可能です。
また、最も注意すべき副作用が「アミロイド関連画像異常(ARIA)」です。
これは、脳の浮腫(ARIA-E)や微小な出血(ARIA-H)を指し、投与された方の約2割に認められます。
多くは無症状ですが、頭痛やめまい、錯乱などの症状が現れることもあり、重篤な脳出血に至るケースもまれに報告されています。
そのため、治療中は定期的なMRI検査による厳重なモニタリングが義務付けられているのです。
画期的な薬である一方、その恩恵を受けるためには、これらの現実も正しく理解し、医師と十分に話し合うことが求められます。
認知症の薬と上手に付き合うための家族としてできること
認知症の薬物治療は、処方された薬をただ飲むだけでは成功しません。
日々の生活の中で、ご家族がどのようにサポートするかが、治療効果を大きく左右します。
ここでは、ご家族だからこそできる、服薬を支えるための具体的な工夫について解説します。
飲み忘れ・飲み過ぎを防ぐ工夫
認知症の中核症状である記憶障害は、服薬管理を難しくする大きな要因です。
「飲んだことを忘れてもう一度飲んでしまう」「飲むこと自体を忘れてしまう」といった事態は、副作用のリスクを高め、治療効果を不安定にします。
以下のような工夫で、安全な服薬をサポートしましょう。
可能であれば、ご本人と一緒に管理方法を決めることで、自尊心を保ちながら治療に取り組めます。
- お薬カレンダー・お薬ボックスの活用:
曜日や朝昼夕ごとにポケットが分かれたカレンダーやボックスに薬をセットしておく方法です。「どこのポケットが空になっているか」で飲んだかどうかが一目で分かり、ご本人も確認しやすくなります。 - 薬局での「一包化」サービス:
複数の薬を服用時間ごとにひとつの袋にまとめてもらうサービスです。飲み間違いを防ぐ最も基本的な方法で、かかりつけの薬局で相談できます。 - 声かけと確認:
食事のついでなど、決まった時間に「お薬の時間ですよ」と声をかけ、実際に飲むところまで見届けると確実です。飲んだ後は、カレンダーなどにチェックを入れる習慣をつけると、二重服薬を防げます。
服薬拒否がある場合の対処法
「これは毒だ!」「もう飲んだ!」など、認知症の方が薬を飲むことを拒否するのは、よくある悩みのひとつです。
このような時、無理強いするのは逆効果。かえって不信感を強め、その後の介護全体が難しくなってしまうこともあります。
まずは、「なぜ飲みたくないのか」というご本人の気持ちに寄り添うことが大切です。
その上で、以下のようなアプローチを試してみましょう。
- 理由を探る:
「錠剤が大きくて飲みにくい」「薬の味が苦い」といった物理的な理由や、「薬を飲む=病人」と認めたくない心理的な理由が隠れている場合があります。 - 剤形を変更する:
医師や薬剤師に相談し、錠剤から口腔内崩壊錠、粉薬、ゼリー剤、貼り薬など、ご本人が受け入れやすい形に変更できないか検討します。 - 服薬補助ゼリーを使う:
薬をゼリーで包むことで、味やにおいを感じにくくし、つるんと飲み込みやすくなります。 - 信頼する人から勧めてもらう:
介護する家族のいうことは聞かなくても、訪問看護師やヘルパー、あるいは孫など、ご本人が信頼している第三者から勧められると、すんなり飲んでくれることがあります。
服薬拒否への具体的な対応策について詳しく知りたい方は下記も参考にしてみてください。
認知症の方に薬を飲んでもらおうと思っても、飲まない場合があります。では、認知症の方が薬を飲まないときは一体どうしたら良いのでしょうか。今回は認知症の方が薬を飲まないときの対応をご紹介した上で薬を飲むメリット・デメリットや飲まない[…]
スポンサーリンク
薬に頼らない「非薬物療法」という認知症ケアの重要な選択肢
薬物治療への不安がある方にとって、薬以外の方法で症状を穏やかにできる「非薬物療法」は、非常に重要な選択肢です。
これは、薬に頼りすぎず、その人らしさを尊重しながら生活の質を高めるための、認知症ケアの基本となるアプローチです。
運動療法
ウォーキングや軽い体操などの運動は、認知症の方に多くのよい影響をもたらすことが科学的に証明されています。
体を動かすことで、脳への血流が促進され、神経細胞の働きが活発になるのです。
また、気分の安定にもつながり、BPSDの軽減も期待できます。
期待できる効果は多岐にわたります。
- 認知機能の維持・向上: 記憶力や注意力の低下を緩やかにする。
- BPSDの軽減: 不安やうつ気分を和らげ、意欲を高める。夜間の良質な睡眠にもつながる。
- 身体機能の向上: 筋力やバランス能力を維持し、転倒を予防する。
- 生活リズムの確立: 日中に活動し、夜に休むというメリハリのある生活を作る。
メディカル・ケア・サービスでは、科学的根拠に基づいた個別運動プログラムを実践しており、BPSDや身体機能の改善事例を多数確認しています。
無理のない範囲で、散歩やラジオ体操、椅子に座ったままでの足踏みなど、ご本人が楽しめる運動を毎日の習慣に取り入れることが大切です。
認知症を発症したらどのような治療をするのか知っていますか?認知症の方の治療には運動療法というものがあり、今回はそんな運動療法について以下の項目を中心に解説していきます。認知症における運動療法の目的や効果[…]
>参考:MCSケアモデル
回想法・音楽療法
回想法や音楽療法は、脳の活性化と精神的な安定を促す、代表的な非薬物療法です。
これらは、ご本人の感情や記憶に働きかけることで、コミュニケーションを促し、生活の質を高めます。
事実の記憶は失われても、その時の感情は長く保たれるという「感情記憶」を活かしたアプローチです。
- 回想法:
昔の写真や使い慣れた道具などを見ながら、過去の楽しかった思い出を語り合ってもらう手法です。昔の記憶は比較的保たれていることが多く、自信や自尊心を取り戻すきっかけになります。また、他者との会話は脳によい刺激を与えます。 - 音楽療法:
若い頃に親しんだ歌を聴いたり、一緒に歌ったり、簡単な楽器を演奏したりする活動です。音楽は、言葉を介さずに感情を呼び覚まし、リラックス効果や不安を軽減する効果があります。
メディカル・ケア・サービスの施設では、こうした感情記憶を活かした関わりを続けることで、薬に頼らずとも穏やかな生活を送られている方が多くいらっしゃいます。
ご家庭でも気軽に行えるのが魅力です。
認知症の治療は薬物療法だけではなく、薬を使わず治療する「非薬物療法」があります。非薬物療法の代表的な療法に「回想療法」があるのを知っていますか?今回は認知症の回想法について、以下の点を中心にご紹介します。認知[…]
>参考:愛の家グループホーム帯広東12条
運動療法や音楽療法と併せて、栄養面からの認知機能サポートも重要な非薬物的アプローチのひとつです。
特に、脳の健康維持に重要とされる成分を含むサプリメントは、日常的な食事では不足しがちな栄養素を補う選択肢として注目されています。
リアリティ・オリエンテーション
リアリティ・オリエンテーション(現実見当識訓練)は、時間や場所・季節など、ご自身が置かれている状況を認識する手がかりを繰り返し提供することで、見当識障害の進行を和らげ、不安を軽減する手法です。
見当識障害があると、「今がいつで、ここがどこか分からない」という状態になり、ご本人は大きな不安と混乱の中に置かれます。
この不安が、BPSDの引き金になることも少なくありません。
リアリティ・オリエンテーションは、この不安を和らげることを目的とします。
具体的な実践例:
- 朝起きた時に「おはようございます。今日は8月8日、金曜日ですよ」と日付を伝える。
- カレンダーや時計を、見やすい場所に置く。
- 食事の際に「お昼ご飯ですよ。今日はカレーライスです」とメニューを説明する。
- 窓の外を見ながら「よいお天気ですね。セミが鳴いていますね」と季節について話しかける。
ここで大切なのは、決して本人を試したり、間違いを正したりしないことです。
問い詰めるように試すのではなく、あくまで日常会話の中で自然に情報を提供することがポイントです。
ご本人が安心できる環境を整えることが、薬に頼らないケアの基本となります。
スポンサーリンク
まとめ
今回は、認知症の薬について、「飲まない方がよいのか」という疑問を中心に、薬の種類や副作用、そして薬に頼らないケアについて解説しました。
この記事の重要なポイントを以下にまとめます。
- 認知症の薬物治療は、病気の完治ではなく、進行を穏やかにし、生活の質を維持することが目的です。
- 副作用が効果を上回る場合など、「薬を飲まない」という選択肢を検討すべきケースもありますが、自己判断での中止は絶対に避けるべきです。
- 薬の減量や中止は、離脱症状などのリスクを避けるため、必ず医師の管理のもとで行う必要があります。
- 運動療法や音楽療法などの「非薬物療法」は、薬物療法より優先されるべき重要なアプローチであり、ご家族が主体的に取り組めることも多くあります。
認知症の治療は、ひとつの正解があるわけではありません。
薬物治療・非薬物療法、そしてご家族の関わり方、これら全てを組み合わせ、ご本人にとって何が最善かを考え続けることが大切です。
また、認知症の薬について理解を深めた上で、ご本人とご家族にとって最適なケア方法を見つけることが大切です。
薬物治療、非薬物療法、そして日常的な認知機能サポートサプリメントなど、複数の選択肢を組み合わせながら、総合的なアプローチを検討しましょう。
▼認知機能サポートサプリメントの詳細はこちら
健達ねっと監修 機能性表示食品一覧
薬に対する不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、かかりつけの医師や薬剤師、地域包括支援センターなどの専門家にぜひ相談してみてください。
正しい知識を持つことが、あなたと大切なご家族を支える一番の力になります。